#盲視
Text
情愛心理學:愛情還是「麵包」
有調查發現,校園中的女孩子要在一個自己喜愛的窮小子和一個喜歡自己的富家子之間作選擇的時候,往往會選擇窮小子。通常給出一個解釋:愛情是感性的東西,並不是物質可比擬。否認了愛情是盲目的說法。
為何在校園裡作此研究呢?可能因為這些青少年畢業之後,進到社會工作了一段時間,就可能發覺「麵包」(物質)與愛情同等重要。因此,有不少人認為年輕人自然選擇愛情,但是年紀大的人會選擇「麵包」。可是,這情況並不是絕對。歷史上,極其轟動的例子發生在1936年英國國王愛德華八世身上。他因為不理會政府及教會反對,堅持迎娶美國離婚女子Wallis…
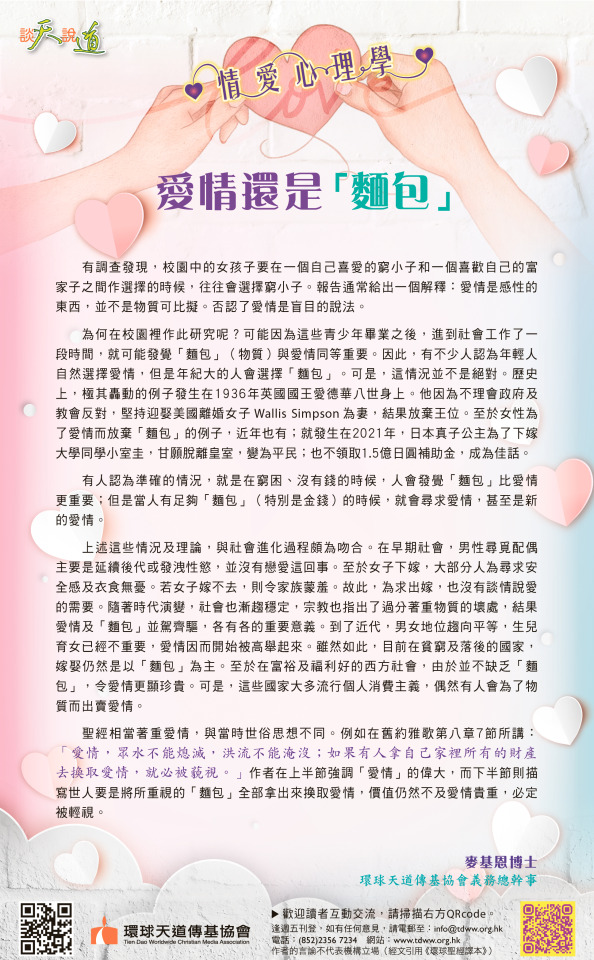
View On WordPress
#環球天道傳基協會#環球天道傳基協會義務總幹事#精神科專科醫生#週五#聖經相當著重愛情#英國國王愛德華八世#談天說道#麥基恩博士#soulcarehk#心靈關懷#情愛心理學#愛情眾水不能熄滅洪流不能淹沒#愛情還是麵包#愛情麵包並駕齊驅#愛情是盲目的#愛情不是物質可比擬#拿財產換取愛情必被藐視#日本真子公主#明報#有足夠金錢會尋求愛情#沒有錢時著重麵包
0 notes
Text

Buddha to his disciples, mini-series (7)
To Anuruddha (Ref) - Pursuit of happiness
Anuruddha is listed as one of the 10 great disciples, and was a top master of clairvoyance also the practice of the four foundations of mindfulness (satipatthana: Ref2).
Anuruddha was a blind disciple of the Buddha. He was at the Jetabana (one of the holy places where the Buddha preached) and was trying to sew the frayed ends of his robe. But being blind, he could not thread the needle. “Is there anyone who wants to thread the needle for me and make merit?” He called out.
The Buddha responded. Anuruddha said, "The Venerable one no longer needs to make merit." But Buddha said.
“There is no limit to so much in the pursuit of dāna (any form of giving), forbearance, truth and happiness.” - Buddha (Ekottarika-āgama 31・5).

ブッダから弟子たちへ、ミニシリーズ (7)
阿那律よ〜幸福の追求
阿那律 (アヌルッダ:参照) は、釈迦の十大弟子の一人であり、天眼第一 (たもんだいいち) とされ、透視とマインドフルネスの4つの基礎、サティパッタナー(四念処:しねんじょ参照2)の実践の第一人者だった。
阿那律は盲目の仏弟子である。彼は祇園精舎 (ブッダが説法を行なっていた聖��の1つ) にあって、衣のほころびを縫おうとしていた。しかし、盲目であるから、針の孔に糸を通せない。「どなたか、わたしのために針に糸を通し、功徳を積もうとする人はいないのか?」彼はそう呼びかけた。
それに応えたのが、ブッダであった。阿那律は、「世尊は、もはや功徳を積む必要はありますまいに」と言った。だが、ブッダは言われた。
「布施や忍辱、真理と幸福の追求においては、ここまでという限度はないのだよ」―ブッダ (増一阿含経31・5)
#zen#mindfulness#buddhism#buddha#wisdom#philosophy#nature#art#aniruddha#anuruddha#buddha's disciples
128 notes
·
View notes
Text

【狐炎(フーイェン)】
盲目キャラだけれど、見ようとはしてくれます。
(視覚は式神🦊と共有できるので生活に問題はないです。)
▽花ノ芥蔕とは?🤔
7 notes
·
View notes
Quote
46万人以上のデータを分析した新たな研究で、「盲目であることが統合失調症から人を守る」というさらなる調査結果が示されています。
1980年から2001年までの報告の中に皮質盲の患者が統合失調症を発症するケースがゼロだったことが明らかになりました。
「先天的な皮質盲をケーススタディーで観察した結果、保護現象があるこ��がわかっていました。そして今、我々が保証する慎重な臨床調査によるデータは、この結果を支持しています」
「統合失調症患者において機能不全がある部分、つまり音の認識や注意力、記憶力、そして言語使用をカバーする部分の力を、先天性の盲目は増大させている」という仮説が立てられています。
一方で、周辺視野障害の患者も統合失調症となる確率が通常に比べて少ないことが示されましたが、周辺視野障害は皮質盲と違って脳を変化させません。
盲目であることは統合失調症から人を守るという可能性が研究で示される - GIGAZINE
7 notes
·
View notes
Text
「視力1.0」でも突然失明することはある…健康診断ではわからない「失明原因トップ5」の恐ろしさ - ライブドアニュース
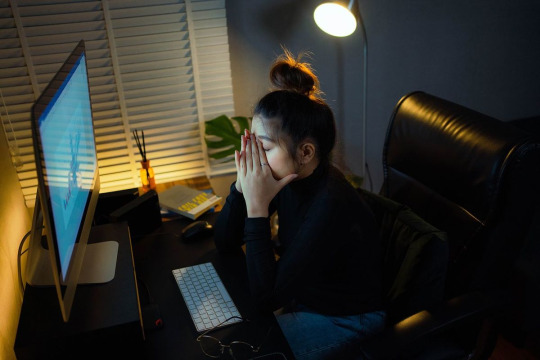
写真=iStock.com/Krisada tepkulmanont※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Krisada tepkulmanont
以下引用
目の健康を保つには、何が大切なのか。眼科医の平松類さんは「失明原因のトップ5である緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、網脈絡膜萎縮は、末期になるまで視力が落ちることはない。視力検査で失明の危険性はわからないため、必ず『眼底検査』を受けてほしい」という――。
※本稿は、平松類『眼科医が警告する視力を失わないために今すぐやめるべき39のこと』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
■いたずらに「眼圧」を上げるような行動は控えたほうがいい
会社の健康診断などで眼科検診に行くと、視力検査と一緒に必ず「眼圧」の測定も行われると思います。しかし、その意味合いをいまいち理解していない人がほとんどではないでしょうか。
眼圧測定とは、空気を軽く当てて「眼球の圧力」を測ることで「眼球の硬さ」を調べるものです。
なぜこの検査が重要かというと、眼圧が高い、つまり眼球が硬いと、失明原因の1位である緑内障のリスクが高くなることがわかっているからです。近年では眼圧の高さと近視の進みやすさの相関も指摘されています。
ここから言えるのは、「眼圧が高くなるような行動」は、できるだけ避けたほうがいいということです。日常生活のなかにも、知らないうちに眼圧を上げてしまう行動がけっこう潜んでいます。
その筆頭が、「水の一気飲み」です。水分補給は目の健康にとっても重要ですが、汗をかいたり、脱水症になったりしたときを除いて、一般的に水の一気飲みはよくありません。
体に水分が入ると、血液中の水分量が増えます。ごく単純にいえば血管を流れる液体の量が増えるため、血管に圧がかかります。これは大半の臓器にとっては大した問題ではないのですが、ごく微細な毛細血管が張り巡らされている眼球には、過度な圧力をかけてしまうのです。
■水の一気飲みはNG、マメな水分補給を
いたずらに眼圧を上げないよう、「水分補給は少量ずつ」が鉄則です。
例えば500ミリリットルの水を一気に飲むと、平均で3~4、最大で7ほども眼圧が上がることがわかっています。
眼圧の正常値は10~20ですから、その30~40パーセント、最大で70パーセントほども眼圧が上がるというのは、いわば収縮時血圧(最高血圧)が正常値の130から一気に170くらいまで上がるようなものです。
1回に飲む量は、200ミリリットル程度が適当です。もちろん1回の摂取量を抑えたせいで水分不足になっては本末転倒ですから、1時間に1回くらいを目安に「マメな水分補給」を心がけていきましょう。
■「過度な運動」は目をいじめる行為
「水の一気飲み」に加えて、気をつけたいのが運動習慣です。
運動のすべてが悪いわけではありません。「筋トレ」の場合、自重トレーニング程度ならば問題ないのですが、重すぎるウエートを用いた筋トレだと「いきむ」たびに眼圧が上昇するという研究があります。
意外なところでは、「ヨガ」も要注意です。
さまざまなポーズをとることで、ほどよく体全体がストレッチされ、呼吸を繰り返す有酸素運動でもあるヨガが概して体にいいことは確かです。ただし、唯一、目の健康を考えるうえで懸念されるのは「頭が心臓よりも下になるポーズ」です。
頭が心臓より下になると、当然ながら、頭に血が上ります。すると眼球にも圧力がかかってしまうのです。ヨガをやめる必要はありませんが、目の健康を思うのなら、頭が下になるポーズは避けたいところです。
逆に、目にいい運動もあります。体に酸素をふんだんに取り入れ、巡らせる「有酸素運動」(ウオーキングや軽いジョギング)は、必然的に目��の酸素供給にもなり、目の健康維持に寄与します。
目安は「週3回、1回あたり30分以上、合計で週に90分ほど」、運動の強度は「ゼエハアと息が上がらず、会話できる程度」。これくらいの有酸素運動が緑内障などの防止になるという研究データもあります。
■「ストレス」も眼圧を上げる一大要因
眼圧には自律神経も関係しています。
ストレスを感じると、緊張状態を司(つかさど)る交感神経が優位になるのですが、このとき体中の血管が収縮します。眼球も例外ではありません。交感神経が優位になると眼球の毛細血管が収縮するし、そこで眼圧が上昇するのです。
現に、緑内障に処方される目薬は、交感神経を鎮める効果のある成分が使われています。交感神経を鎮めることで眼圧を低下させ、緑内障を軽減する狙いがあるわけです。
ストレスには、仕事やプライベートでの人間関係のストレスもありますし、騒音や急激な冷えといった環境的なストレスもあります。冬場は眼圧が高くなるという研究報告もあるほどです。
すべてのストレスを取り除くのは難しいものですが、自然に触れに行く、自宅でのんびりする、ゆったり入浴するなど、適宜、自分に合ったリラックス習慣を取り入れましょう。
■眼圧を上昇させる「睡眠姿勢」に要注意
みなさんのなかに、「睡眠時はうつぶせ」という人はいるでしょうか。
問題は、うつぶせになったときの顔の角度です。心臓より眼球が下にならない顔の角度ならば、ギリギリセーフです。
しかし、心臓より眼球が下になる顔の角度で寝ると、眼球の中の水晶体というレンズが本来の位置から少しだけ下に落ちることになり、眼球から余分な水分を排出する箇所がふさがれてしまいます。そして余計な水分が排出されないことで、眼圧が上昇してしまうのです。
年に数回ならばいいのですが、毎日、ランチ後にデスクに突っ伏して仮眠を取るなどの行為は、眼球にとっては最悪の習慣です。
同じ理由で、マッサージ店や整骨院によくある「顔のところに穴が開いているうつぶせ用のベッド」や、理髪店の「顔を下に向けるシャンプー椅子」も好ましくないのですが、それほど高頻度でなければ、あまり心配はありません。
また、横向きで寝るのはいいのですが、枕の硬さ(柔らかいほうが目に圧力がかかりやすい)や顔の角度によっては、眼球が枕に押し付けられるような感じになってしまいます。これはよくありません。目にかかる圧力上昇は、眼圧の上昇を意味するからです。
まとめると、睡眠時の姿勢は「あおむけ」がベストです。とはいえ眠りやすい姿勢は人それぞれでしょう。今後は目の健康のために、とにかく「顔が下向きになる」「眼球が枕に押し付けられる」ことだけは避けるよう、意識してみてください。
ただ、これらの生活上の注意は可能であればというレベルですので、無理せず取り組んでいただければと思います。
■視力は「いい・悪い」で判断してはいけない
これもありがちな誤解なのですが、視力(メガネやコンタクトレンズによる矯正のない「裸眼視力」)がいいから検診を受けなくても大丈夫、とはいえません。
そもそも一般的には何をもって「視力がいい」と思われているのでしょう。0.8や0.9まで見えれば「視力がいい」のでしょうか?
専門的には「視力」とは相対的な指標です。現時点で「いい・悪い」という話ではなく、「以前と比較してどうか?」という変化こそが重要です。
例えば、一般的には視力0.9は「視力がいい」ほうに入るのかもしれませんが、昨年は1.0だったところから0.9に下がったのなら、それは「大丈夫」とは言い切れません。視力が下がった場合は近視の進行も考えられますし、何らかの病気になっている可能性もあります。
■失明原因トップ5の病気は「末期まで1.0くらい見える」
「視力がいいから検診を受けなくても大丈夫」とはいえない理���は、これだけではありません。失明原因のトップ5である「緑内障」「糖尿病網膜症」「網膜色素変性症」「加齢黄斑変性」「網脈絡膜萎縮」は、実はかなり進行するまで1.0くらいは見えていることが珍しくないのです。
1位の緑内障の場合、いよいよ重度になり一人では歩けないくらいにまでなって初めて、1.0から視力が下がってくるケースがよく見られます。
2位の糖尿病網膜症も同様です。糖尿病により、ものの色や形をハッキリ捉える黄斑の中心部「中心窩」がむくむと早期に視力が低下する場合がありますが、そのむくみが起こらなければ、末期までは視力1.0くらいが維持されます。
3位の網膜色素変性症は、暗いところでものが見えなくなったり(夜盲)、視野が狭くなったりする遺伝性・進行性の疾患です。こうした症状が出てもなお、明るいところや、視力が届く範囲ではハッキリとものが見えるので、視力検査値としては「悪くなっている」わけではなく、1.0くらいは余裕で見えるケースが多いのです。
4位の加齢黄斑変性は少し例外で、早期から視力が下がるケースのほうが多く見られます。とはいえガクンと視力が下がるのは、だいぶ黄斑変性が進行した末に、合併症により網膜中心部に発生した新生血管から出血したときです。
そして5位の網脈絡膜萎縮もまた、早期からゆっくり視力が下がっていきますが、やはりガクンと下がるのは、かなり進行した後です。
■定期健診には「本当に必要な検査」が含まれていない
このようにたどる経過はそれぞれ違うものの、基本的には、末期になるまでは1.0くらいの視力が続きます。1.0というと、一般的には自信をもって「私は目がいい」といえる数値だと思いますが、ご覧のとおり、「大丈夫」といえる根拠にはなりえないのです。
企業や地方自治体の定期健診の眼科項目は「視力検査」「眼圧検査」だけで終わってしまう場合がほとんどでしょう。しかし前項で見たように、たとえ視力が1.0以上あっても失明の危険のある病気にかかっている可能性は消せないため、視力検査にはあまり意味がありません。視力検査が役立つのは白内障の診断です。
また、かつては「眼圧が上がると緑内障リスクが高くなる」のは確かだったのですが、日本人は神経が弱いため、緑内障患者の8割は眼圧が低いのに緑内症になっていることがわかっています。したがって、緑内障の診断に必須とされてきた眼圧テストの意味も、薄れてしまいました。
今後、罹患するリスク判定も含め、失明原因トップ5の疾患の診断には、眼底カメラで眼底の血管、網膜、視神経などをチェックする「眼底検査」が欠かせません。
追加料金が必要になる場合もありますが、これらの疾患の早期発見、早期治療のために、今後の眼科項目では、ぜひ「眼底検査」のオプションをつけることをおすすめします。
■「片目だけの悪化」は自覚しづらい
失明原因トップ5の疾患の早期発見、早期治療には眼科検診(特に眼底検査)が欠かせないと述べたことには、あと二つほど理由があります。まず一つめは、一般の方の「見えている」は、実は「片方しかちゃんと見えていない」可能性がゼロではないからです。
日常生活のなかで「片目ずつ何かを見る」という場面は、ほとんどありません。誰もがたいていは両目を開いて、ものを見ています。とはいえ両目が等しく、ちゃんと見えていないと生活できないわけではありません。
試しに片目をつぶって歩いてみてください。あまりふらつくことなく、真っ直ぐ歩けるはずです。つまり両目で見ているようでも、極端なことをいえば、仮に片目を失明していても生活には大して支障が出ないのです。
そのため、意外と多いのが、片目の視力の急激な低下にずっと気づけないというケースです。不調を感じなければ眼科を受診することもなく、病気の発見が遅れてしまいます。そういう患者さんが一定数いるのです。
眼科検診では、必ず片目ずつ検査を行います。片方の目は健康でも、もう片方の目は不健康という自覚しづらい事態もたちどころに明らかにし、早期に手を打つことができるというわけです。
■「緩やかな悪化」は自覚しづらい
そしてもう一つ、目の疾患の早期発見、早期治療に眼科検診が欠かせないと述べた理由は、人は「緩やかな変化(悪化)」を自覚しづらいからです。例えば、もし、昨日は1.0だった視力が、今日は0.2になっていたら、視力検査を受けずとも、誰だってすぐに異変に気づけるでしょう。
しかし、白内障では徐々に視力が低下していきます。しかも、ちょっとくらい視力が落ちたところで、急に日常生活が送れなくなるわけではありません。それなりに何とか補正しつつ、生活を送ることができてしまうのです。
緑内障も同様です。両目の視野が半分くらいになっても、見えていない分を脳が補正してくれることで、何ら支障なく暮らせてしまいます。視野はたしかに半分になっているのですが、脳が情報を補い、「見えているように」認識するのです。
まったく人間の脳の補正力とはすごいものだと感心してしまいますが、そのために何も手を打たないまま日常生活を送っている間に、病気が進行してしまうというケースは決して少なくありません。
さらに、目の不調を単なる「疲れ」と捉える人も多いようです。
本当は病気による不調なのに、「今日は目が疲れる」「最近、目が疲れやすい」「ここのところ、ずっと目が疲れている」とすべてを疲れのせいにして、徐々に病状が進行していることに気づけないケースもあります。こうして早期発見のタイミングを逃してしまうのです。
上記すべてに共通しているのは、自分の体のことは自分が一番わかっているというのは錯覚である、ということです。こう言ってはなんですが、「自分が支障を感じていないから大丈夫」という感覚は、実はほとんどアテにならないのです。
■人生100年時代には目の健康は欠かせない
食料事情の改善、医学・医療技術の発達などにより、人間の寿命はどんどん延びてきました。そして寿命が延びたことで、体のさまざまな臓器や器官は、より長期にわたって働かねばいけなくなりました。特に、目は過酷な状況に置かれています。
寿命が延びたことで使用期間が延びただけでなく、例えば本を読むようになった、車に乗るようになった、デジタルデバイスを使うようになった……といった人間の生活の変化により、目はどんどん酷使されるようになってきたからです。それだけに、私たちはいっそう目の健康に気を使わなくてはいけない時代になっていると思います。
目の病気には、死に直結するようなものはありません。しかし、どの目の病気も、悪化するほどに生活の質は大きく損なわれます。
しかも目の病気は総じて神経のダメージであり、一度ダメージを受けた神経を元通りにするのは、ほぼ不可能です。となると、ダメージを受けていない神経を守り、残っている機能をできるだけ保全することが重要になってきます。病気の進行を食い止めたり遅らせたりするためには、検診による早期発見が欠かせません。
人生100年時代だからこそ、年に一度の眼科検診で専門医による客観的な診断を受けることが、いつまでも、より快適に暮らしていけることにつながるのです。
----------
平松 類(ひらまつ・るい)
眼科医 医学博士
愛知県田原市生まれ。二本松眼科病院副院長。「あさイチ」、「ジョブチューン」、「バイキング」、「林修の今でしょ! 講座」、「主治医が見つかる診療所」、「生島ヒロシのおはよう一直線」、「読売新聞」、「日本経済新聞」、「毎日新聞」、「週刊文春」、「週刊現代」、「文藝春秋」、「女性セブン」などでコメント・出演・執筆等を行う。Yahoo!ニュースの眼科医としては唯一の公式コメンテーター。YouTubeチャンネル「眼科医平松類」は20万人以上の登録者数で、最新情報を発信中。著書は『1日3分見るだけでぐんぐん目がよくなる! ガボール・アイ』『老人の取扱説明書』『認知症の取扱説明書』(SBクリエイティブ)、『老眼のウソ』『その白内障手術、待った!』(時事通信出版局)、『自分でできる!人生が変わる緑内障の新常識』(ライフサイエンス出版)など多数。
----------
(眼科医 医学博士 平松 類)
11 notes
·
View notes
Quote
視覚障害者の女性を狙う性加害の卑劣な手口や被害の実態が近年、障害者団体の調査などで分かってきた。加害者は相手の目が見えにくいことにつけ込み、盗撮や痴漢、つきまといなどを行うケースが多い。こうした被害を防いだり、被害に遭った人をケアしたりする取り組みも広まりつつある。(坂戸奎太)
7割が被害
関東在住の全盲女性(30歳代)は、一人暮らしだった2017年頃、知らない男に自宅の合鍵を作られ、部屋に盗撮カメラを仕掛けられた。部屋を訪ねてきた母親が気づき、警察に通報。男は20年に逮捕され、「目が見えないのでばれないと思った」と供述した。
男は女性の
白杖(はくじょう)
に目をつけて尾行し、自宅を割り出したとみられる。女性は「犯人が捕まるまでは知人を疑ってしまった。白杖を使うのが不安になった」と明かす。
女性が入会する支援団体「日本視覚障がい者美容協会」(埼玉県)は、この事件などを機に、視覚障害者の女性に性被害のアンケートを21年に実施。68人が回答し、7割の48人が「障害に乗じたと考えられる状況で被害に遭った」とした。
場所(複数回答)は電車内(30人)や街中(27人)、被害内容(複数回答)は、同意のないボディータッチ(32人)、痴漢(27人)、つきまとい(23人)��目立った。
先天性の弱視で白杖を使う20歳代の女性は、通勤途中の駅で男に声をかけられ、手を握られたり、背中を触られたりし、つきまとわれる被害が約2週間続いた。同僚に付き添ってもらい、収まったが「本当に怖かった」と振り返る。
協会は「視覚障害者は白杖を使うなどし、目立ちやすい。性加害を
企(たくら)
む人物から『自分の姿が見えない相手だし大丈夫』と標的にされがちだ」と分析する。
アンケートでは「誘導の際、手をつながれた」との声も多かった。協会は正しい誘導法を啓発する冊子を作成した。「相手に触らず、自分の腕をつかませることが誘導の基本。不自然な誘導を見かけたら『お困りですか』『私も手伝います』などと声をかけて助けてあげて」と呼びかける。
鉄道での放���取りやめ
鉄道では従来、視覚障害者や車いすの利用者らの乗降を駅員がサポートするため「○両目お客様乗車中」などと駅のホームで放送するケースがあった。
だが、障害者団体でつくる「DPI日本会議」(東京)の21年の調査で、放送を聞いた乗客に自身の存在を知られ、痴漢やつきまといなどの性的嫌がらせを受けたとの相談を障害者団体に寄せた人が30人以上いるとわかった。大半は女性だった。
同会議は国土交通省に改善を要望。同省は21年、別の方法で情報伝達するよう鉄道各社に要請した。各社は関係者以外にはわからない方法への変更を進める。関西のある鉄道は、駅員らが旗を振って合図する形に変えた。
社会福祉法人「日本視覚障害者団体連合」(東京)は昨春、視覚障害者の女性の性被害に関する全国初の相談窓口事業を開始した。これまでに計4回実施。法人の幹部や臨床心理士らが電話や対面で、相談者の話にじっと耳を傾ける。
「学生時代の被害が今でもフラッシュバックする。区切りをつけたい」
ある女性が寄せた相談は30~40年前の性被害だった。法人は、この女性が別の性被害の当事者とつながりを持つための仲介など、支援を続けている。
相談件数はまだ少ないが、法人女性協議会会長の阿部
央美(てるみ)
さん(66)は「窓口の存在を知らない人も多いはず。周知を進めて悩む人を支えたい」と語る。次回の相談対応は3月に行う予定だ。
「白杖」狙い尾行・合鍵作り盗撮カメラ、誘導時につきまといも…視覚障害者狙う性加害明らかに | ヨミドクター(読売新聞)
6 notes
·
View notes
Text
棕櫚の姫
そのコンクリートの塀を城壁と呼んでいた。広い広い敷地を囲って、高さもあり、壁の上には有刺鉄線が張り巡らされいかめしい。書道教室の行き帰りにいつも通る道で、城壁の作る影は湿っていた。苔が生え、蟻や蜘蛛が這っていた。蟻を目で追い、歩いていると、足元がぼこんぼこん鳴った。壁とはちがう色のコンクリートで蓋がされており暗渠だった。かつて川だったところにかけられた蓋で、ところどころ揺れる。城壁だなんて巨大に感じていたのはわたしが小さかったためだろう。
城壁の内側は二階建ての細長い建物で、庭が広いのでぽつんとして見える。クリーム色の壁がくすんでいた。そんなに豪華な建物ではないのでかえって城だった。余計な華美は避け、質素に屹立している。ほんとうの城はこうでなくっちゃと納得し、庭の芝生がかなり禿げていてそういう滅びの気配も城だと思った。どうやらどこか大学か会社の寮であるらしく、何々寮という文字が見えた。といっても、城門はめだたないつくりで奥まったところにありそっちへ行くのはこわかった。どんな寮だか、どんな人が住んでいるのか、ちゃんと見たことはなかった。
わたしが見ていたのは壁と棕梠シュロだった。お城の庭には一本だけ、背の高い棕梠の木があった。灰色の壁の向こうですっくと伸びている。壁よりも建物よりも高く、ぼさぼさの幹が風にしなっている。棕梠という名を知ったのはもっとあとで、わたしはあれはヤシの木だと思っていた。あの揺れ方は南国だなあと、南国のことを知らないのに感心していた。雪の降りそうな寒い低い雲の日でも、冷たい風に手の甲が痒くても、壁の向こうのヤシの木だけ南の島で、お城の中だから当然だと思った。壁の外から見上げる葉はいつも影になり、動物の毛みたいにぎゅっと密集して見えた。
この木の下にどんな人が住んでいるのだろう。なんとなく、人魚姫の姉たちを想像した。絵本の話、もっとわたしが小さかったころの話。母が、人魚姫の姉たちが泳ぎ回るページを開いて、「この中だったら誰が好き?」とわたしに選ばせた。深い意味はなかったと思うが——人魚の姉たちは色とりどりで、きっとわたしに色の名前を言わせたかった——、わたしは青い髪のお姉さんを指した。彼女の髪の毛はそんなに長くないがAラインにふわふわ広がっていて、ひたいに垂らしたアクセサリーが大人っぽく、いちばん素敵だと思った。そうして青い髪の人魚はその一ページだけの登場で、人魚姫に短刀を渡すシーンにはいなかった。それもよかった。きっと海の底で静かに悲しんだ。悲しみはするが彼女にはその後の人生があり、死なない。青い髪の姉についてわたしは幾度も想像した。棕梠のお城にいる誰かを想像すると、彼女になった。
やがて暗渠の町からは引越して、わたしは川に挟まれた町に住むことになった。両親が離婚し、母と二人の家になり、近くに祖母と伯母が住んでいてちょくちょく行き来した。蓋のない、どころか、おおきなおおきな川で河川敷もだだっ広い。二つの川はカーブし、町はレモンの形をしている。アーケードの商店街があり暗渠の町よりだいぶ騒がしい町だったが、学校は小さかった。わたしの学年はそれまで三十九人で、わたしが引っ越してきたことにより四十人になり、あなたのおかげで一クラスだったのが二クラスになったのだと春休み明けの転校初日に先生に言われ、自分が福音なのか災厄なのかわからなかった。
新学期早々ずっと休んでいる子がいて、盲腸で入院しているとのことだった。クラスみんなでお見舞いの手紙を書きましょうと先生が言った。色画用紙が配られ、一人一通、工夫してメッセージカードを作るよう言われ、まだ一度も会ったことがないのにわたしも書くんですかと先生に尋ねたら、「みんなクラスの仲間でしょう」とたしなめられた。でも知らないんだよな、となりのクラスの子たちは書かないのかな、わたしが来なければひとつのクラスだったのにな……と思った。
どうせ知らない人に書くのなら棕梠のお城にいるはずの彼女、青い髪の人魚に宛てて書きたかった。棕梠のお城の人魚たちには足があり、城壁の外では完璧に人間のふりができる。王子に恋をせず生き続け、芝生の上を駆けたり寝そべったり、真夜中、お城の中でだけ人魚に戻る。庭に水をまいて海にするかもしれない。そうか、だから芝が禿げていた。棕梠の葉ずれの音を聞きながら足の使い方を練習し、人魚の下半身がいらなくなったらお城——寮から出て行く。でも彼女たちは人間のふりも人魚でいることも好きだから、のらりくらりお城に住みつづけ、出て行かない。棕梠はどんどん伸びてゆき、葉の重さで腰が曲がる。青い髪の彼女はぼさぼさの幹をやさしく撫でてくれる。それなら手紙を書けるのだ。書けるか? わたしはなにを書くだろう?
たとえばいつも棕梠を見上げていたこと。黒い葉。風。書道教室は畳の部屋で薄暗かったこと。流しの水がいつも細く、冷たくて、お湯は出ず、わたしは手についた墨汁をきれいに落とせなかった。黒く染まった指先をきつく握って、すれちがう人たちから隠した。なぜ隠さなければと思ったのか、わたしがあらゆる視線をおそれていたためだが、そそりたつ棕梠にはぜんぶばれている気がした。人魚を見守る南の島の木は、わたしのことだって知っていたはずだ。墨汁はいつも風呂で落とした。浴槽で足を伸ばし、そのころにはもう一人で風呂に入るようになっていた。墨の溶けた湯だからほんとうは透明ではない、目に見えない黒色の混じった湯なのだと思った。そういうことを書く。書いた。学校から帰ってきて便箋につづり、糊をなめて封をした。でもこれでは、わたしが思っていることを書いただけで、受け取る相手、青い髪の彼女に向けてなにか発信しているわけではないなとも思った。
盲腸のクラスメイトには、画用紙を切ったり貼ったりして「飛び出すカード」を作り、おだいじにとか当たり障りのないことを書いた。
レモンの町では書道教室に通わなかった。伯母はフラダンス教室の先生をやっており、招かれたので何度か見学したが、自分にはできる気がしなかったので(踊るのは恥ずかしい)、見学しただけだった。伯母はフラをやるからこまかいウェーブの髪がすごく長くて、想像の人魚よりも長かった。教室はおばあさんが多く、ハイビスカスの造花がたくさん飾ってあり、でもヤシの木はなかった。
盲腸のクラスメイトとは友だちになれた。退院してすぐ話しかけられ、飛び出すカードすごくかわいかった、どんな子が転校してきたのだろうと楽しみだったと言われ、わたしはちょっと申し訳なく思った。
だからというわけではないがかなり仲良くなった。すみれちゃんという名前で、しばしば自分の名前をSMILEと書いた。たとえば授業中に回ってくる手紙、ノートの切れ端にぎっしり書かれたいろいろの最後にSMILEとあり、それは署名だけども、受け取ったわたしには「笑って!」というメッセージにも見え、わたしはすみれちゃんの手紙がけっこう好きだった。
きのうみた夢とか、好きな音楽とか、誰々が雑誌のインタビューでこう言っていた、ラジオでこんな話をしていた、いますごく眠い、親とケンカしてすげえムカついてる、そういう日記みたいな手紙で、いや日記でもないようないろいろで、思っていることを書くだけでもちゃんと手紙になることを知った。わたしが手紙を読むときすみれちゃんはもう眠くないし、すげえムカついた気持ちもいくらかおさまっている。その時差こそが手紙の肝だと思った。
手紙ではたまにシリアスな悩みも吐露され、そういうときはSMILEの下に「読んだら燃やして」と強い筆跡で書かれていた。わたしはすみれちゃんの手紙を一度も燃やしたことはなかった。うちにはマッチもライターもなく燃やし方がわからなかったためで、ガスコンロで火をつけるのもこわかった。父親がいたらライターがあったろうか。ないな。たばこは吸わなかった。うちに小さな火がないのは父とは関係ない。父にはときどき会った。父も暗渠の町から引っ越したので暗渠の町に行くことはなくなった。
中学に入り、すみれちゃんの家が建て替えすることになった。古い家をぜんぶ取り壊すからラクガキしていいよということになり、友だち何人かで誘われた。すでに家具はぜんぶ運び出されからっぽになった家の壁や床だ。油性マジック��か書道の墨汁とかカラースプレーとか、みんなでいろいろ持ってきて、こんなことは初めてだったから最初わたしたちはおそるおそるペンを握ったが、だんだんマンガの絵を描いたり好きな歌詞を書いたり、家じゅう思い思いにラクガキした。腕をぜんぶ伸ばし、肩がもげるくらい大きなマルを描いてみた。マルの中に顔も描いた。すみれちゃんの妹が壁いっぱいの巨大な相合傘を描いた。片側に自分の名前、もう片側はいろんな人の名前で、芸能人もマンガのキャラクターもあったがやがて尽きたのか、後半は「優しい人」「うそをつかない人」「趣味が合う人」と理想を並べていた。すみれちゃんは最後、床に大きく「ありがとう」「SMILE」と書き、このラクガキは家への手紙だったのかと思った。
あとになってGoogleマップで暗渠の町を見たら棕梠のお城はなくなっていた。見つけられなかっただけかもしれないが、区画整理にひっかかったのか、暗渠の道もないように見えた。お城を取り壊すさい誰か壁にラクガキしたろうか。しなかったろう。だからすみれちゃんの家はとても幸運だったろう。そうして道の形が変わっても、地面の下にかつて川だった跡は残っているとも思った。
あのとき人魚に宛てて書いた手紙が、このあいだ本棚のすきまから出てきて、なにを書いたかだいたいおぼえていた。恥ずかしいなと思いつつ封を開けたら、しかし便箋は白紙だった。文字はどこかに消えてしまったのか、書いたというのはわたしの思い込みだったのか、ぜったい後者なんだけど、後者なんだけど……と思う。すみれちゃんはマスカラを塗るとき、ビューラーをライターの火であたためる。小さな火を持っている。
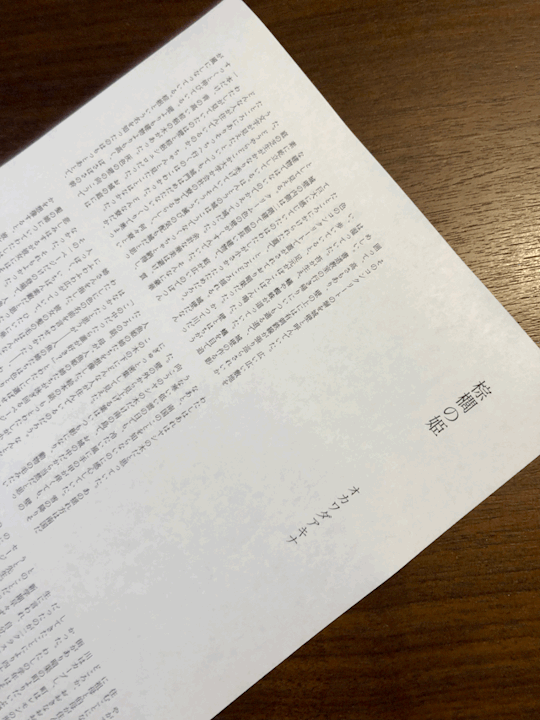
ペーパーウェルというネットプリントの企画に参加します。
セブンイレブン【24438044】 10/8 23:59まで
ファミマ・ローソン【DA5W82BGB9】 10/9 16時ごろまで
これは4年くらい前に書いたやつ。読んだことある人もいるかもしれない(覚えていてくださる方がいたらうれしい)。
今回のペーパーウェルのテーマが「時間」だったので、時間のことを考えながら書いた小説にしました。いやどこらへんが?って感じなんだけど、自分の中では…。過去のことを���るときの距離感、時間の長さとか流れを探りたかったというか。
つい最近読んだ川上弘美のインタビュー記事ですが、「年をとって記憶がいっぱい自分の中に貯まっているせいか、ある時期から、一瞬にフォーカスして書くよりも時間の流れを書くことが多くなってきた」とあって、なるほどなあと思いました。そして「でもコロナのもとで生活しながら小説を書いていると、なぜだか自然に、今この瞬間にフォーカスした書き方に回帰していくことになりました」と続き、とても興味深かった。
『群像』のweb記事で、「物語るために遠ざかり、小説全体であらわしていく」という題の鴻巣友希子との対談です。
10 notes
·
View notes
Text
Kissinger, a politician who misread the big picture (Essay)

Kissinger is a politician who has long led the USA's foreign policy and is still influential. But I have the impression that he is a short-sighted politician.
The long-standing enemy of the USA is the Chinese Communist Party. After kicking the USA's emboldened Kuomintang from the mainland, today the CCP is "the USA's biggest competitor." China would have self-destructed if it was left to the stupid Mao Zedong. China has become a powerful country by providing capital and technology according to the logic of capitalism. Kissinger's responsibility for restoring diplomatic relations with China is heavy. He also kicked Taiwan out of the UN's permanent seat and made the Communist Party of China a permanent seat.
The Chinese Communist Party is an enemy that must be smashed. not a profitable party. During the Korean War, if the volunteer soldiers dispatched by the CCP had been annihilated with atomic bombs, the CCP would have collapsed. It was Truman's mistake not to do so, but Kissinger's responsibility for acting blindly without knowing such a major premise is heavy. He is said to be a realistic politician, but he is a politician who is too caught up in the phenomenon of reality and is not good at seeing the essence.
Rei Morishita
大局を見誤った政治家・キッシンジャー
長らくUSAの外交政策をリードし、今でも影響力のある政治家・キッシンジャー。でも私は彼が近視眼的な政治家であるとの感想を持っている。
USAの長年の敵は、中国共産党である。USAの息のかかった国民党を大陸から追い出して以来、今日では中国共産党は「USA最大の競合国である。」バカの毛沢東に中国を任せておけば、勝手に自滅したであろう。資本主義の論理に則り、資本と技術を提供したために、中国は強国となってしまったのだ。中国と国交を回復させたキッシンジャーの責任は重い。また台湾を国連の常任理事国から追い出し、中国共産党を常任理事国にしたのもキッシンジャーだ。
中国共産党は、叩きつぶすべき敵。利益を与える相手ではない。朝鮮戦争のとき、���国共産党が派遣した義勇兵たちを、原子爆弾で全滅させていれば、それで中国共産党は潰れていたろう。そうしなかったのはトルーマンのミスであるが、そんな大前提を知らずに盲動したキッシンジャーの責任はやはり重い。彼は現実的な政治家だそうだが、現実という現象に囚われすぎて、本質を見ることの不得手な政治家である。
#Kissinger#Chinese Communist Party#CCP#Mao Zedong#capitalism#Taiwan#Korean War#volunteer soldiers#atomic bombs#Truman#rei morishita
13 notes
·
View notes
Text
(...)いや、見えないようにしていたのです。毒親の毒は、どこからかわいてきたものじゃなく連綿に続く呪縛だったことを。
確かにこの事実から目を背けるのは、仕方がないことだとも思います。なぜなら、まるで親も被害者だという論旨は、ますます毒親育ちの子どもの良心を追い詰め、今までの親の仕打ちを許すよう迫るような、そんな考えや空気感にもつながるから。だからその毒が《毒親自身の子ども時代から続いていること》という連続性を無視して、毒親という別の生き物が存在することにする楽さを、世間は選んでしまったのです。
もちろん子どもは、理解のできない親に寄り添う必要はないと思う。でも本来はドン引きして攻撃する必要もないのかもしれない。寄り添うのでも、ドン引きして雑なカテゴリに押し込むのでもなく、もっといい落としどころと、引くべき距離感があるのだと思う――それがこの本では提案してあると思うのです。
毒親という言葉は、結局それは親を神格化して崇めるのと同じくらい、何も見えておらず反射的で軽率で、そして無批判で無条件な盲信に近いのです。本当は親の存在は、そこまでビビるほど大きくもなく、そしてそこまで押し込めて小さくできるものでもない。ただ1人の人間の存在。だからこそ《親としては未熟だった人間》として、そのあり方に想いを馳せることは、彼らに感じていた強烈な期待や憎しみをも等身大のサイズに戻してくれるだろうと思います。
「一緒にいるとしんどい親」最適な距離の取り方 「毒親」という言葉が見えなくしている真の課題
8 notes
·
View notes
Text

米国はイスラエルにイランを攻撃しないよう「懇願」したが、その要請は恥ずかしいことに無視された 米国は金曜早朝、イスラエルに対しイランへの反撃を行わないよう懇願したとされるが、イスラエルがワシントンを無視する決定は「恥ずべき」傾向の一環だとポリティコは米国当局者の発言として報じた。 「米国はイスラエルにそうしないよう懇願したが、国防総省から統合参謀本部、中央情報局、諜報機関に至るまで、文字通り誰もこれが良いことだとは思っていない」と、金曜日にポリティコが伝えた当局者の発言。「現時点で、イスラエルが我々の言うことを聞かないのは本当に恥ずかしいことだが、それでもバイデン大統領は盲目的な忠誠を貫く」 報道によると、イスラエルによるイランへの攻撃に対する米国の沈黙は、中東におけるイ���ラエルとイランの間の緊張を緩和する取り組みの一環だという。 ホワイトハウスの報道官カリーヌ・ジャンピエール氏は先のブリーフィングでこの件についてコメントを拒否し、国防総省と米中央軍もスプートニクに対しこの件についてコメントを拒否した。 この件に関してアントニー・ブリンケン米国務長官が唯一コメントしたのは、イスラエルの攻撃に対する米国のいかなる関与も否定することだった。 メディアの報道によると、イスラエルは金曜日早朝、週末のテヘランによるミサイルとドローン攻撃への報復としてイランへの空爆を実施した。 エスファハーン市近郊で爆発が報告された。国内のいくつかの州では防空システムがドローンの接近に対応した。 イランの防空軍によってエスファハーン市上空で撃墜されたイスラエルの無人機は被害をもたらさなかったが、親イスラエルメディアは空爆の影響を誇張しようとしているとイランのホセイン・アミラブドッラーヒアン外相は述べた。
2 notes
·
View notes
Text
しかし、外交に精通していた割には、ナショナリズムの力には無知であった。最悪な過ちの多くは、彼が小国を、そこに住む人々とともに犠牲にされるべき駒として見下したことによって生み出された。
かつてキッシンジャーは「北ベトナムのような四流国家に限界がないとは信じられない」と語り、恐ろしい人的犠牲を払って、爆撃を拡大した。彼は大国のプリズムを通して世界を見ており、ベトナムとカンボジアは単なるドミノ倒しの牌(はい)ではないこと、ベトコンを突き動かしていたのはモスクワの命令ではなく、自分たちの国を統治したいという強い願望だったことを理解していなかった。
キッシンジャーは1971年のバングラデシュ独立戦争でも同じような過ちを犯した。ヒンドゥー教徒とベンガル人を大量虐殺したパキスタンの側に付いた。それは許しがたいもので、しかも失敗に終わった。何十万人もの死者を出したが、バングラデシュが勝利を収め、米国に屈辱を与え、南アジアにおける米国の地位を落とした。
似たようなことが東ティモールでも起こった。そして、東ティモールやバングラデシュやベトナムの街頭では、キッシンジャーは外交政策の天才ではなく、虐殺することに無頓着で、犠牲になった彼らの生命のことなど全く考えない無能な米国人にしか見えない。
第2次世界大戦後の米国が犯した最大の過ちのひとつは、ナショナリズムの力を何度も見誤ったことだ。キッシンジャーはまさにそれを体現したのだ。ベトナム、アフガニスタン、イラク、イラン、その他多くの場所で大失敗した一因は、ナショナリストたちの不満に気づかなかったことにある。英国がナショナリズムの芽生えを軽視したために生まれた我が米国のような国にとって、それが盲点だったことは奇妙なことだ。
キッシンジャーの勝利と大失敗から得られる教訓 NYTコラム:朝日新聞デジタル
3 notes
·
View notes
Text
被害者であり加害者である
36人もの死者が出た京都アニメーション放課事件の記事。ここに書かれていることについて、ずっと考えている。
=====
被害者参加の代理人弁護士が「放火殺人で人が死ぬと分かっている中で被害者のことは考えなかったのか」と尋ねると、被告が少しムッとした声で「逆に聞くが、京アニが(自身の)作品をパクったときには何か考えたのか」と反論する場面があった。
裁判官が「あなたが質問する場ではありません」と注意したが、被告は「パクりや『レイプ魔』と(被告自身が)言われたことに京アニは良心の呵責(かしゃく)はなく何も感じず、被害者としての立場だけ述べてどう思うのか」などとまくしたてた。
=====
この記事に関するコメントには、「何も反省してないな」「周りがどれだけ説得しようと、パクられたというのは絶対に覆らない事実化している」という内容のものがあった。
まずこの事件に関して、放火は明らかな犯罪であり適切に裁かれるべきだと思っている。けれど、この被告の反論は、どうしても他人事としては見れない何かを感じた。
仮に、客観的に見て100%自分が悪いことをしてしまったとしたら、自分は一生懸命謝罪するだろう。けれど、もし99%ぐらいだったら、どうだろうか。果たして何も反論せずにただただ反省の様子を見せることができるだろうか。
「悪いと思わなかったの?」「悪いとわかっててやったの?」そうやって責められるたびに、心のどこかで「うるせえな」という気持ちが膨らんでくる。「本当に俺だけが悪いのかよ」「お前にだって少なからず原因あるだろ」そういう怒りが、ふつふつと湧いてくるだろう。
そしてもし、そんな怒りをうっかり表出してしまった時には「全然反省してないじゃん」「ありえない」「責任感じてるの?」という、まさに被告に向けられた言葉が、当然のように飛んでくるだろう。
逆のパターンもある。自分の過失に永遠に無自覚のまま、相手が100%悪いと思い込んで反省を求め、反省の色が見えない場合は「ありえない」といった感じてさらに責め立てる。「反省して当然」という意識から抜け出せない。「反省」という言葉の曖昧さを逆手に、反省の“色”があるかどうかの審査員になりたがる。
会社の研修で『哲学ゼミ』というものを受講している。その中で哲学者である先生が「特権的なバルコニーに立ってダンスフロアを見下ろすことなど誰にもできない」と繰り返し語っていた。
これは元々「ダンスフロアとバルコニー」という比喩の話で、ここで言うダンスフロアは、何かに集中している状態のことを指す。対してバルコニーは、その様子が眺められる高い場所を意味する。要は「バルコニーに立つように、俯瞰した視点を持ちましょう」という話だ。
けれど先生は「そんなこと無理」と言う。(だからこそ哲学を学んで他者の思考・視点をインストールしましょう、と言った)
自分を客観視することは、世間で大事そうに語られている割に、想像以上にとんでもなく難しい。常に自分の加害性には盲目で、常に自分は被害者として生きようとしてしまう。
誰かから「加害者だよ」と指摘をもらった時に、ああそうだったんですねと素直に受け止められるなら全然いい。けれど実際にはとてつもない反発の意識が発動してしまう。むしろそういうあなたも加害者だ!と攻めはじめることだってある。自分がどんなに大犯罪を犯していたとしても。
この問題に、どう対処すべきなのかは自分でもまだわからない。自責思考を強めれば万事解決というわけでもないと思うし、適切な反論も時には必要だったりするだろう。
ただ、なんとなく思っているのは「どちらがより“悪い”か」という部分に意識が大きく向かってしまうところを考える必要がある気がしている。どっちが悪いかというのは、実はそこまで本質ではなく、誤って解消されるならそうすればいいだけのはずなのである。謝罪と反省、その先の和解が目的なら、どちらが悪いかを決めるのは単なるひとつの手段にすぎない。自分が悪くなくたって、謝ったっていいはずなのだ。
それでも謝れず、「どちらがより“悪い”か」論争を繰り広げ、相手に“反省の色”を強要してしまうのは、きっと自分の中の何かを守っているからなんだろう。その「何か」を知ることが、今の自分には必要なんだと思う。
5 notes
·
View notes
Quote
法則1 主人より目立ってはならない
法則2 友を信じすぎず、敵をうまく使え
法則3 本当の目的は隠しておけ
法則4 必要以上に多くを語るな
法則5 名声は大いに頼りになる――生命をかけて名声を守れ
法則6 ぜひとも人の注目を集めよ
法則7 他人を自分のために働かせよ、ただし手柄は決して渡すな
法則8 他人に足を運ばせよ――必要ならば餌を使え
法則9 言葉ではなく行動によって勝て
法則10 感染を避けよ――不幸な人間や不運な人間とはつきあうな
法則11 他人を自分に依存させておくすべを覚えよ
法則12 意図的な正直さや寛大さで敵の武装を解け
法則13 他人に助力を求めるときは相手の利益に訴えよ。情けや感謝の念に頼ってはならない
法則14 友を装ってスパイをはたらけ
法則15 敵は完全に叩きつぶせ
法則16 姿を見せないようにして周囲の敬意と称賛を高めよ
法則17 予測不能の雰囲気をかもしだして、相手をつねにおびえさせておけ
法則18 保身のために砦を築くな――孤立は危険である
法則19 相手の性格を見きわめよ――不適当な人物を攻撃するな
法則20 誰にも深く肩入れするな
法則21 だまされやすい人間を装って人をだませ――カモよりも自分を愚かに見せよ
法則22 降伏戦術を使って、弱さを力に変えよ
法則23 自分の力を結集せよ
法則24 完璧な廷臣を演じよ
法則25 新しい自分を創造せよ
法則26 自分の手を汚すな
法則27 何かを信じたがる人間の性向を利用して、盲目的な崇拝者をつくれ
法則28 大胆に行動せよ
法則29 終わりにいたるまで計画を立てよ
法則30 努力は人に見せるな
法則31 選択肢を支配せよ――自分に都合のいいカードを引かせる
法則32 幻想に訴えよ
法則33 人の摘みねじを見つけろ
法則34 自分のやりかたで王になれ――王のように振る舞えば、王のように扱ってもらえる
法則35 タイミングをはかる技術を習得せよ
法則36 手に入らないものは相手にするな。無視することが最大の復讐である
法則37 壮大なものを見せて人の目を釘づけにしろ
法則38 考えは自由でも、行動は他人にならえ
法則39 魚をつかまえるために水をかきまわせ
法則40 ただ飯を軽蔑せよ
法則41 偉大な人間の靴に足を入れるな
法則42 羊飼いを攻撃せよ、そうすれば羊は散り散りになる
法則43 相手の頭や心に働きかけよ
法則44 ミラー効果で敵を武装解除させ、あるいは激しく怒らせろ
法則45 変革の必要性を説け、ただし一度に多くを変えるな
法則46 あまり完璧に見せてはならない
法則47 狙ったところを超えて進むな、勝ったら引きどきを心得よ
法則48 かたちあるものなどない
Pan; 権力(パワー)に翻弄されないための48の法則
5 notes
·
View notes
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024)2月14日(水曜日)弐
通巻第8132号
こなた習近平が尊敬する思想家はマルクスと毛沢東である
かたやプーチンが尊敬してやまないのはソルジェニツィン
*************************
習近平が尊敬する思想家はマルクスと毛沢東である。習のまわりを囲む御用学者らは毛沢東思想礼賛のカチカチの共産主義者だ。欧米に留学し近代経済学や国際金融を学んで,多少は中国の経済『改革』を進めてきた改革思考のブレーンは不在となった。朱容基も、李克強も居なくなった。周小川も易鋼も退官し、そして胡春華も閑職に飛ばされた。
一方、ロシアのプーチン大統領が尊敬してやまないのはアレクサンドル・ソルジェニツィンである。
ソルジェニツィンはゴルバチョフ、エリツィン、プーチンの三人の指導者とそれぞれ別個に懇談したが、もっとも共鳴した政治家は、じつはプーチンだった。そしてプーチンもソルジェニツィンの考え方に深く共鳴し、尊敬していた。
ノーベル文学賞受賞の作家にして哲学者の残した言葉をプーチン大統領はよく演説に引用する。
「彼の心、魂、思考は祖国への痛みと尽きることのない祖国愛で満たされていました。こうした感情が彼の創作活動の原動力となったのです」とプーチン大統領は、2018年にソルジェニツィンの記念碑除幕式で演説している。
「彼は何百万人もの人々を苦しみや厳しい試練に陥れた「全体主義体制」と(純朴な)「ロシア人」とを明確に区別した。20世紀のロシアが産んだ社会政治思想家である。その知的遺産が今日までロシア政治に影響を与えている」
代表作は『イワン・デニーソヴィチの一日』で、実際にソルジェニツィンは、8年間強制収容所で過ごした。労働収容所や外国への亡命生活で何年も過ごし、共産主義イデオロギーに幻滅し、ロシアナショナリズムとキリスト教正教会の価値観に強い関心を抱く。
ソルジェニツィンは土着の愛郷心と魂を重視する宗教への回帰を訴えた。ソ連指導部に対し、共産主義イデオロギーを手放し、国内の発展を妨げる世界中の左翼政権への支援をやめるように呼び掛けた。
「私たちの国は、国民の内的、道徳的、健全な発達を考慮して導かれるべきです。私たちは女性を、お金を稼ぐための強制労働、特にバールやシャベルから解放すべきです。学校教育と子供の育成を改善する。土壌、水域、ロシアの自然全体を保護し、都市の健康な生活を回復しなければなりません」
この共産党指導部への公開書簡のため、1974 年 2 月、ソルジェニツィンは逮捕され、「大反逆罪」と「ソ連の市民権」を剥奪された。ソルジェニツィンは西側諸国を放浪し、1976年に米国バーモント州に定住した。
▼ソルジェニツィンの葬儀にはプーチンもメドベージェフも参列した
国家の独立を維持し、ロシアとその国民の利益を守ることが、ソルジェニツィンの創作活動の重要なテーマとなった。
やがてペレストロイカの雪解けが訪れ、ソルジェニツィンは市民権を回復、1994年、ロシアに帰国した。2008年にモスクワで死去。享年89歳だった。
葬儀にはプーチン、メドベージェフにくわえてロシア科学アカデミー会長、ロシア科学院学長らが参列した。何千人もの一般の人々が花束を捧げた。
2022年のヴァルダイ・フォーラムで演説したプーチン大統領は、「西側諸国は新植民地主義と一極性によって『盲目』になっている」としたソルジェニツィンの言葉を引用した。
西側諸国の外交政策に対するソルジェニツィンの批判は時間の経過とともに強まるばかりだった。
ソルジェニツィンは米国が複数の国を占領していると非難した。
「ボスニアでは9年間、コソボとアフガニスタンでは5年間、そしてイラクでは3年間。こうした状況が続いているが、現地の状況は長期化するのは確実だ」
彼はまた、東欧での軍事的プレゼンスを拡大し続け、同国を南から包囲し続ける米国にとって、ロシアはいかなる脅威にもなっていないと指摘した。
それは「『小さな自由』であり、大きな意味での『自由』を風刺したものにすぎません。責任や義務感のない自由です」とソルジェニツィンは1975年にフランスのジャーナリストとのインタビューで語った。
ソルジェニツィンにとって、道徳的発達は、事実上、社会的、政治的問題と切り離せない価値であり、義務感や個人の責任は、現代の西洋の思想家や指導者の中では信じられていない。
プーチンの演説の言葉の端々、その行間に秘められているのはソルジェニツィンの思想なのである。
毛沢東とマルクスの幻惑に浸り,全体主義に盲進する短絡的な習近平とプーチンを同列に論じるのは基本的な誤謬といえる。
4 notes
·
View notes
Text
考えてみる、サバイバル
今年は元日に突然携帯の地震を知らせるアラームが鳴り出し、ギョッとなった。まもなく、能登で大きな地震があったことを知った。本当にいつどこで地震に遭うのかわからない今日この頃だ。日頃の備えが大事というが、どんな備えをすればいいのだろうか。どうすれば、自分や家族や周りの人の命や財産を守れるのだろうか。
「サバイバルファミリー」という映画を観た。どういう話かというと、主人公は東京のマンションに住む、中年の夫婦と高校生の息子と娘の一家。お父さんは平凡なサラリーマンで、会社から帰れば、晩酌しながらテレビをみている。息子と娘は親に関心がなく、勝手なものを食べている。お母さんはひとり台所で、実家の鹿児島から送られてきた大きな丸一匹の魚を捌こうと格闘しているけれど、誰も手伝わないし、食べたがらない。
そんなある日朝、突然電気という電気がみな停まってしまう。電気ばかりでなく、乾電池や車のバッテリーも全く働らかなくなる。お父さんと子どもたちは、文句を言いながらとりあえず会社や学校に向かう。自分のマンションだけでなく、かなり広範囲に停電していることがわかってくる。スマホで検索しようと思っても、画面には何も映らない。お母さんがスーパーに行くと、みな買い出しに来ているが、レジが動かずそろばんで計算するので、長蛇の列となる。
三日ぐらいは、ロウソクとカセットコンロとレトルト食品で凌いでいるが、水道からの水も出なくなり、会社や学校も休みとなり、多くの人がだんだんと東京脱出を始める。大勢の人が家族を伴って、ガラガラとスーツケースを引いていく。この一家はお父さんがうまく調達したおかげで、一人一台自転車がある。途中の商店では、ペットボトルの水が一本2500円の高値で売りに出されている。この家族も高値承知でありったけを買い占め、旅を始める。お母さんの実家の鹿児島を目指して。途中のお米屋さんでは、水や食べ物を持って行くと、お米一合と交換してくれる。そこにロレックスや高級車の鍵を持って交換に来る人物が現れるが、「そんなもの食えるかい! 」と突き返される。
「大阪から先の関西では電気が来ているらしい」という噂が飛び交い、今や車の走らない東名高速道路を大勢の人が歩いたり、自転車だったり、中には荷車を引く人も、西に向かう。途中のサービスエリアで野宿。寒い季節ではないのが、まだよかった。寝ている間に、水を一本盗まれて、息子がすぐに追いかけるのだが、盗んだ家族には赤ちゃんがいて、取り返すのをやめる。
脱出から16日目高速道路を降りて、川で洗濯をする。水が一見きれいだからと飲んだお父さんが下痢をする。強風に煽られて転倒し、自転車やお母さんのメガネが壊れる。次に通りかかったちょっと大きい街の無人のホームセンターを覗くと、食べ物はとうに無いが、キャットフード、精製水( コンタクトレンズに使うもの? )、自転車の修理材料などを手に入れる。火おこししようとしたもできないお父さんを横目で見つつ、おいしくないキャットフードを食べる。
さらに高速道路を走り続ける。長いトンネルの入り口で報酬と引き換えに、トンネルの案内を買って出る盲目のお婆さんたち。無視してトンネルに入るも、真っ暗な中、停まっている車や障害物に阻まれて進めなくなり、盲目のお婆さんに手引きしてもらう。
次はいやに元気な家族と遭遇する。彼らは日頃サイクリングしながらキャンプをしているらしく、装備も揃っていて、みなで楽しそうに食事をしている。「食料や水はどうしているんですか」と尋ねると、山の中の岩場の間から湧き出ている水は、周りに苔が生えていればそれは安全な証拠なのでそういう水を汲んだり、地面から直に生えているオオバコのような植物は食べられますよ、セミなどもおいしいですよ、と教えてくれる。
43日目、やっと大阪に到着。電気は来ていない。通天閣のタワーの入り口には、たくさんのメモ紙が貼ってある。「岡山のおじさんのところに行く。◯◯」などの伝言が。娘がブチ切れて「もう嫌だ! お父さんが大阪に来ればなんとかなるって言ったよね?」「そんなこと俺いったか? 」「ほら、そうやってまたいつもの責任のがれ」「親に向かってなんだ、その口の聞き方は! 」すると息子が「親らしいことしてくれたことあったかよ! 」今度はお母さんが、「いい加減にして! そんなこととっくにわかっているじゃないの、お父さんがそういう人だってこと」ここでお父さんはがっくりとなってしゃがみ込んでしまう。水族館の前で、飼っている魚を調理した炊き出しの列に並ぶも、自分たちの前で終わってしまった。お父さんは調理していた人に、土下座をして「せめてこの子たちだけにでも何か食べ物を」と懇願するが、「無いものは無い」と断られる。
67日目、食料も水も無くなり、岡山あたりの田舎道をとぼとぼ歩いている。と、一頭の豚が目の前を通り過ぎていく。えっ、となり夢中で追いかける。四人でやっと捕まえてみたものの、どうやってとどめを刺すのと手間取っているところ、後ろから「うちの豚に何をする! 」とお爺さんの怒鳴り声。お爺さんのうちの電気柵が働かなくなり、豚たちが逃げ出したのだった。お爺さんが、持っていたナイフで手早くとどめを刺し、豚を運ぶのを手伝い、そのお爺さんの家に。庭先の井戸水を汲ませてもらい、ごくごく飲む。久しぶりの白いご飯に、卵や野菜のおかずに豚肉の燻製。近所のお婆さんがキャベツや大根を届けてくれる。「あれまあ、お客さん? お孫さんたちが帰っているのかと思った」お爺さんの家族はアメリカにいて、連絡もつかないのだ。
ご飯の後は、さっきの豚の解体を手伝う。バラバラにした肉に塩をすり込む。一週間ほど熟成させてから燻製にするのだそうだ。逃げた他の豚も、みんなで追いかけ回して捕まえる。井戸水をバケツで汲んでは、お風呂に運び薪でお風呂を沸かす。何十日ぶりのお風呂に入り、夜はお孫さんたちが着る予定だった新しい寝巻きを貸してもらい、これまた久しぶりの布団に横になる。
毎日薪割りしたり、洗濯をしたり、お爺さんの手伝いをして過ごす。一週間後、豚肉を燻製にしながらお爺さんが語る。「お前さんたちさえよければ、ここにずーっと住んでもいいんじゃぞ。わしも年取って、一人で車も洗濯機も使えない生活では大変でなぁ・・」と誘われるが、この一家は鹿児島にいるお母さんの実家のお父さんの安否も気になっていて、結局お爺さんの申し出を断り、たくさんの食料をもらって、また自転車の旅を続ける。
そのあともいろいろあって、命の危険にも晒されて、奇跡的に誰かが動かしてくれたSLに拾われて、ようやく108日目に鹿児島のお祖父ちゃんの家にたどり着く。お祖父ちゃんは元気だった! お祖父ちゃんは浜で魚釣りをしていた。それからは村人同士助け合って、魚を捕りに行ったり、畑をしたり、鶏の世話をしたり、お婆さんに機織りを教えてもらったりして、みんなで元気に楽しく一生懸命に暮らし始める。
それから、2年と126日目の朝、突然村のスピーカーから埴生の宿のメロディーが流れてくる。みんなが驚いて家を出てみると、街灯が次々と点き始めた。すっかり忘れていた電気が戻ってきたのだ。そして場面は変わって、東京の一家のマンション。日常を取り戻し、以前の生活に戻る。テレビからは、「世界同時停電の原因は、太陽フレアか彗星の異常接近ではないかと、専門家からは語っている。サイバーテロの疑いはなくなったとのことです・・」停電前はそれぞれ勝手に心もばらばらに生きていた家族だったのが、思いやりのある温かい家族になっていた。
とまあ、そういう話であったが、いろいろといいヒントがあった。非常時にはアナログが強いこと。キャンプ生活などに慣れておくこと。北杜市に住んでいて、地震などで自分の家が壊れていない限りは、ここにいた方が湧き水もそばにあるし、薪や焚き木を燃やして暖を取ったり煮炊きすることもできる。むしろここは、首都圏からの避難地域となるだろう。今できることといったら、いつでも人を迎えられるように、家の中を整えておくこと、食料や薪を備蓄しておくこと?
もうひとつ気になるのが、「年長者としての知恵」のようなもの。年長者はパソコンやスマホに弱く、操作方法などは若者に訊かないとわからないことばかり。でももしパソコンやスマホが一切使えない世の中になった時に、どこまで年長者がサバイバルの知恵を出せるだろうか。本当に長く生きた分だけいい知恵があればいいけど。
さっきの映画の話では、最初はばらばらだった家族の気持ちもだんだんとひとつになり、お互いにかけがいのない家族として心が結ばれる。停電が終わり東京に戻るのだけど、本当に戻る必要はあったのかなぁ。鹿児島にいた二年半は、みなで漁をしたり、畑をしたり、はた織りしたりして、お金も介在せずに生きていたわけだ。これからこの地震や災害の多い日本で生き抜くには、都会を出て地方でコミュニティを作って、いろんな年齢の人が、各々出せる力を合わせて生きていく以外の得策は無いのではないかしら。
2024年1月
映画「サバイバルファミリー」は、2017年2月に公開された。監督 矢口史靖。
主演 小日向文世、深津絵里、泉澤祐希、葵わかな
2 notes
·
View notes