#理屈抜きで美味しい個性ある日本酒
Photo

新商品の麹造りです😊 精米歩合が異なるので、いつもより入念に米の吸水状態を指で確認します✨ 中心までシッカリと水分は届いているのですが、速く硬くなりそうな感触です💦 添こうじ【日本酒を仕込む際3日間に渡り、添・仲・留と蒸した米・水・こうじを混ぜ合わせていきます🍶その1日目のこうじのこと♪】は、水分多めに管理するので問題は無さそうですが、留こうじ造りの時は考えなきゃなぁ。。。🥺 #創業1853年 #始まりが伝統になる一滴入魂の蔵 #岩清水の如く澄んだ味わい #理屈抜きで美味しい個性ある日本酒 #ワイングラスで美味しい日本酒 #食事とのペアリングを意識した酒造り #麹割合を変化させた酒造り #低アルコール日本酒 #無濾過生原酒 #ペアリングと言えば岩清水 #完熟麹 #完熟醪 #じっくりと時間をかけて #丁寧にていねいに #テロワール #減農薬栽培米 #減化学肥料栽培米 #井戸水 #超軟水 #日本一柔らかな仕込み水 #日本一生産量の少ない酒蔵 #夫婦二人で醸す #厳しい品質管理 #マイナス5度で瓶貯蔵 https://www.instagram.com/p/CoTzMHuy5fK/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#創業1853年#始まりが伝統になる一滴入魂の蔵#岩清水の如く澄んだ味わい#理屈抜きで美味しい個性ある日本酒#ワイングラスで美味しい日本酒#食事とのペアリングを意識した酒造り#麹割合を変化させた酒造り#低アルコール日本酒#無濾過生原酒#ペアリングと言えば岩清水#完熟麹#完熟醪#じっくりと時間をかけて#丁寧にていねいに#テロワール#減農薬栽培米#減化学肥料栽培米#井戸水#超軟水#日本一柔らかな仕込み水#日本一生産量の少ない酒蔵#夫婦二人で醸す#厳しい品質管理#マイナス5度で瓶貯蔵
0 notes
Text
Anime News Networkにスタッフインタビューが掲載!
北米最大規模のアニメ紹介サイトAnime News Networkにスタッフインタビューが掲載されました!
ぜひチェックしてみてください!
https://www.animenewsnetwork.com/feature/2021-06-04/discussing-the-socio-politics-of-megalobox-2-nomad-with-you-moriyama-katsuhiko-manabe-and-kensaku-kojima/.173444
記事の日本語訳はこちらです↓↓
『Nomadメガロボクス2』は、メガロボクスの物語を驚くべき新しい方向へと進めました。 ジョーと勇利の運命的な試合から数年後、ジョーは地下ボクシングの試合で戦う放浪者となりました。 ANNは、この予想外の続編がどのようにして生まれたのかについて、監督の森山洋氏、脚本家の真辺克彦氏、そして小嶋健作氏にお話を聞きました。
Nomadインタビュー:『Nomadメガロボクス2』ライター陣、及び監督
『メガロボクス』の世界に戻ってきました。勝利以来、ジョーには多くの変化がありました。『あしたのジョー』では、ジョーの結末(最期)を曖昧に描いていましたが、『メガロボクス』のジョーは、死の可能性もありましたが切り抜けたようですね。それでも、苦労しています。ジョーの物語を新たな方向へ出発させることにした経緯についてお話しいただけますか?
【森山】:『メガロボクス』終了後は次回作となる別の企画を考えていたのですがなかなか思うように進まず、同時にプロデューサーから『メガロボクス』の続編を考えてみてはどうかと打診を受けました。前作のラストで物語としては区切りをつけたものの彼らキャラクターの人生があそこで終わったわけではない、勇利に勝利しメガロボクスの頂点に立ったことがジョーの人生の最も輝かしい瞬間であるならその後はどうなるのか。前作では描かなかったものをテーマに据えるのであれば続編をやる意味があるだろうとストーリーを考え始めました。
【真辺】:脚本家チーム含め、監督、プロデューサー全員が続編をつくることは全く考えていませんでした。別のオリジナル企画を進めていたのですが、なかなかうまくいかず、そんな時にメガロボクスが海外で高い評価を受けていることから続編をやらないかという話があり、もう一度向き合うことになりました。 ただ、全てやり切ったという空っぽの状態からのスタートだったので、どういう物語にするか? 様々なアイデアが出ましたが、これだという確信を持つまでには至りませんでした。打ち合わせが終わるといつも居酒屋で飲みながら話すのですが、そんな中で“許されざる者”になったジョーというキーワードが出ました。監督の森山氏がそれを元に今回のNOMADOのベースになるプロットを用意し、そこから自らの過ちで故郷と家族を失ったジョーの再生を核に物語を構築していきました。メガロボクスの頂点へ駆け上った奇跡の三ヶ月は通過点に過ぎない、生きている限り人生は続くのだという普遍的なテーマは私たち作り手にもフィードバックし、直面している現実や社会から目を背けることなく描こう、という共通認識が私たちに生まれました。その困惑と思考がNOMADOという物語にリアリティと熱量を持たせたのだと思います。
【小嶋】:『あしたのジョー』の結末で、ジョーは真っ白な灰のように燃え尽きました。『メガロボクス』のジョーは、リングの上で死ぬことはありませんでしたが、勇利との戦いを終え、ある意味で燃え尽きてしまったのだと思います。そんなジョーがもしもう一度リングに上がるとしたら何のためか? 続編をつくるにあたって、監督、プロデューサー、脚本チームで話し合いを重ねました。その中で森山監督から提示されたのが、チーム番外地にとって太陽のような存在であった南部の死と、罪を背負って地下を放浪するジョーというアイデアでした��あの輝かしい勝利のあとで、ジョーの身に何かが起き、すべてを失ってしまった。そのアイデアに強く魅了された私たちは、どこへどう辿り着くのかわからないまま、とにかくその方向へと物語を出発させることにしたのです。

本作品に登場する移民体験は、多くのファンの共感を呼んでいます。チーフと彼のコミュニティに関して言えば、本物らしく(リアリティをもって)見せるために、どのようにしましたか? 何か参照したものはありますか?
【森山】:『メガロボクス』の近未来世界には様々な国籍のキャラクターが登場することもあり、舞台の裏側のこととはいえ人種問題や移民問題は常に自分の近くにありました。それもあって続編にはその要素を物語に絡められたらと考えました。自分は移民問題についてのエキスパートではありませんが、ニュースやドキュメンタリーなどこれまで見てきたものからヒントを得て物語の構築や絵作りを行いました。個人的には映画の影響が強く、例えばケン・ローチ監督作品やスパイク・リー監督の『Do the right thing』は制作中に観返したりもしました。同じ場所で生きる様々な人間たちの複雑な関係性、表裏のある言葉のやり取りなどはチーフと仲間たち、彼らを排斥しようとする者たちの考えや行動に影響を与えていると思います。
【真辺】:私の住んでいる街では多くの外国人が暮らし、母国を離れざるを得なかった難民の方もいます。恥ずかしい話ですが、彼らに偏見を持ち、差別的な言動をする人間も存在します。 歴史を遡ると、多くの日本人がアメリカだけでなく、中南米に移民として海を渡りました。今の日本には日系ブラジル人や日系ペルー人の方々が各地で暮らし、カーサのようなコミュニティがつくられています。いわれなき差別を受け、満足な公共サービスを受けられない人々に対し、私も含め多くの日本人は労働の担い手としか見ようとせず、無関心を貫いてきました。既に二十年以上、この国で共に生きているにも関わらず、です。無知が恐れを生む悪循環を止めることは困難ですが、わずかでも抗うためのクサビを打ちたい、そんな思いをこの物語に込めました。共感を呼んでいるのだとすれば、その祈りが届いているのだと思います。私は悲観主義者なのですが、掲げた理想を現実に引きずりおろす愚かな真似はしたくないのです。
【小嶋】:私が住んでいる埼玉県の蕨市という小さな町には、外国からの移住者が多く暮らしています。排外主義者のグループがヘイトスピーチをしに来たこともあります。特にクルド人住民の数は日本の中で一番多く、”ワラビスタン”とも呼ばれています。彼らは母国での迫害を逃れて日本にやって来た人たちとその家族ですが、政治的理由で難民申請を受理されないまま、人権を制限された状態で暮らしています。日常的に彼らの姿を目にしていることが、本作品での移民体験の描写に影響しているのかもしれません。 参照した作品を一つ挙げるとすれば、イギリス映画『THIS IS ENGLAND』です。ミオと地元の少年たちの関係を描く際に参照しました。

勝利した後、ジョーは、ある層の人々からヒーローとして受け入れられるわけですが、『メガロボクス』のジョーに、どういう男性像を見出しますか? また、ジョー(の生き様)が心に響くとすれば、どういうことを体現しているからだと思われますか?(ジョーという存在のどういうところが、心を打つのか…皆さんにとってどういう存在でしょうか)
【森山】:人種も何も関係のないひとりの人間の個の獲得、その強さや輝きというものがジョーというキャラクターの魅力なんだと思います。だからこそ助け合え、共に生きていけるという希望の象徴です。そこを描くことが前作のテーマであり課題でした。ジョーは男性ですがそこに性差は関係なく『メガロボクス』のキャラクターにはそういう思いを込めました。
【真辺】:『大きな力に対し、おもねるのではなく抗う』。名もなき存在であったジョーがメガロボクスの頂点に立ち、虐げられる立場の人々にとって希望の灯りとなった。チーフはまさにその象徴です。しかし、南部という父親を失ったジョーは、自らが父親の役目を果たそうとして家族であるサチオたちを傷つけてしまう。そのことは“男らしさ”という呪いの言葉に囚われた幼い自身の姿をさらけ出すことになりました。 家父長制とマチズモが賞賛される社会で生まれ育った人間にとって、この病を克服することは厄介です。かつてチーフもそうだったのかもしれません。ですが、チーフは家族を失いながらも成熟した“良き大人”の姿をこの物語の中で見せてくれました。ジョーもチーフのバトンを受け取ったことで、呪いから解放される姿を見せてくれるでしょう。 ジョーの魅力は、自分の弱さや不安を誰かを貶めることで解消しようとしない愚直な誠実さであり、優しさを失うことのない高潔さだと思います。そして冒頭に書いたように、権力や権威を嫌って、諦めずに抗い続ける強さ。私にとって彼は敬意を払うべき友人であり、「そんな風になりたい」と思う人間のロールモデルです。
【小嶋】:ジョーが体現しているものは“信じる力”だと思います。金でも、権力でも、神様でもなく、人を信じる力です。彼は“ギアレス”ジョーとしてチャンピオンになりましたが、心はずっと“ギアレス”のままです。相手に生身でぶつかっていくその無防備な誠実さと危うさが、見る人の心を打つのだと思います。

アニメやスポーツにとって、『あしたのジョー』の遺産は、どういうものだと思われますか?
【森山】:難しい質問でうまく答えられませんが……創作の場においては未だ影響の大きい作品です。
【真辺】:スポーツの面では、日本でスーパースターになった辰吉丈一郎というプロボクサーがいます。WBCのバンタム級チャンピオンでした。彼の丈一郎という名前は、彼の父親が主人公の矢吹丈から取ったものです。私も大好きなボクサーでした。 アニメの面では、特に『あしたのジョー2』については影響を受けていない作り手はいないと思います。技術面だけでなく、伝説の漫画原作に負けまいとせめぎ合う高い志に感銘を受けました。簡単に消費されないエバーグリーンな名作であり、未だに心を震わされます。
【小嶋】:『あしたのジョー』は、強烈なロマン主義と情念のリアリズムを併せ持つ偉大な物語です。その精神性は、アニメやスポーツに限らず、日本の文化に大きな影響を与えていると思います。しかし一方で、男らしさや、死の危険を顧みず命がけで戦うことを良しとする、いわゆる「男の美学」については、現代の価値観では受け入れ難いものがあることも確かです。それをどう乗り越えていくかが、今のクリエイターたちに与えられた課題だと思います。
視覚的に、メガロボクスは複数の点で特徴的です。その「粒子の粗い」外観にした背景には、どういう狙いがありますか?
【森山】:前作『メガロボクス』を制作中は原案である『あしたのジョー』とは距離を取りながら近づける、ということを意識していました。例えば、舞台だては大きく変えるが物語のテーマは引き継ぐというようなことです。「粒子の粗い外観」もその一つで、最新作を再放送のような画面で見るということがひとつ魅力になるんじゃないかと考えました。シンプルな構造の物語にはインパクトある画面が必要だったこともありますし、VHSのような劣化した画面が自分にとっては魅力的に映ることも大きいです。
森山監督は、コンセプトデザインの経験が豊富ですが、「ノマド」の世界を視覚化しようと思った出発点/インスピレーションは何でしたか? 監督ご自身が以前に関わった作品で得たスキルやアイデアで、メガロボクスの土台を築くのに役立ったものはありますか?
【森山】:インスピレーションはほとんどの場合これまで観てきた作品が深く影響していて、映画や音楽から得たものが特に大きいです。『NOMAD』制作中は特にアメリカやスペインの西部劇を観返すことが多かったです。他にもカメラワークなど昔ながらの方法で撮影された映像の雰囲気を取り入れたかったので60~70年代のニューシネマも良く観返しました。自分は実写の映像からアイデアを得ることが多いです。コンセプトデザインに取り組む方法は作品によって異なりますが、『メガロボクス』の場合は脚本チームとのミーティングも自分にとっては特に重要な要素です。会話の内容にかかわらずコミュニケーションのすべてが作品に影響していると思います。
真辺さんと小嶋さんは以前、実写のNetflixシリーズ『深夜食堂』でも一緒にお仕事されていますね。一緒に仕事をするようになったのはいつからですか。お二人の仕事上の関係はどのようなもので、どのように一緒に作業されるのでしょうか?
【真辺】:小嶋氏と共作するようになったのは、Netflixシリーズ『深夜食堂』からです。私が所属するシナリオ作家協会のシナリオ講座で講師をしていた時に、彼が講座生として来たのが出会いです。カリキュラムで2時間の映画脚本を書くのですが、彼は福島の原発事故をテーマにした話を書きたいと言ってきました。「センシティブな題材なので簡単じゃない」と私はアドバイスしましたが、「これを書かないと前に進めない」と彼は言い、取材をして書き上げました。そのことで「信頼できる書き手になるだろう」と思い、深夜食堂の監督である松岡氏に紹介しました。そして松岡氏の信頼も勝ち取り、脚本家チームに加わることになったのです。 出会いこそ講師と講座生ですが、シネフィルで映画の知識が豊富にある彼のアイデアは刺激があり、上下関係なく優秀な一人の脚本家として敬意を持って仕事をしています。 互いの家でアイデア二割、無駄話八割をしながらプロットを考え、脚本まで仕上げていくスタイルです。多少どちらかが先行するケースもありますが、プロットの段階で互いの意見を遠慮せずに言い合うことで、船を間違った方角に進ませる悲劇は起こりません。もちろん納得出来ないこともありますが、言葉を惜しまず耳を傾ければ、相手の意図が「この作品にとってプラスになるか、そうでないか」を判断出来ます。 脚本家にとって最も重要なことは、設計図であり楽譜でもある脚本をどれだけ強靭なものに仕立てられるかが作品作りのトップランナーとしての役目だと考えています。たまに私が先輩風を吹かすこともありますが、小嶋氏は寛容な心で受け入れてくれます。恐ろしくて本人には確かめられませんが。
【小嶋】:出会ったのは2012年です。真辺さんは私が通っていたシナリオ学校の講師でした。卒業後、真辺さんに誘われて、『深夜食堂』のプロジェクトに参加することになりました。以降、一緒に仕事をしています。 真辺さんとの作業はいつも、たくさん話しをすることから始まります。見た映画やドラマ、読んだ本、身の回りの出来事や世の中で起きているニュースなど、その時々の関心事についての会話の中から、アイデアが生まれ、少しずつ物語の形が見えてきます。仕事を忘れて、お喋りだけで一日が終わることも珍しくありません。そんな日は二人とも罪悪感に苛まれます。とにかく、そうやって書いたものを互いに読みあい、率直な意見を交わしながら、ブラッシュアップしていきます。 私は理屈っぽく観念的に考えてしまう癖があるので、真辺さんの直感的で具体的なアドバイスに、いつも助けられています。
8 notes
·
View notes
Text
裕くんが三日月亭でバイトする話(タイトル)
定晴ルート入った辺りのお話。
委員会イベやら本編の描写やらとあるルートネタバレやら有。
「なぁ裕。お前、数日ここでバイトしねえか?」
「は?バイト?」
いつものように三日月亭に買い物に来ていた俺は、店長から唐突な申し出を受けた。
「お前ドニーズでバイトしてたって言ってたよな?調理スタッフとしてもやれるだろ?」
「はあ。まぁ、確かにキッチンもやってたのでやれなくはないですが。どうしたんです?随分と突然ですね」
三日月亭は店長が一人で回している。
繁盛している時間は確かに忙しそうではあるが、注文、調理、配膳と見事に捌いている。
港の食堂を稼働させていた時の俺のような状態ではとてもない。
これが経験の差というものか。
いや、それは兎も角人員を雇う必要性をあまり感じないのだがどうしたというのだろうか。
「いや、その・・・ちょっと腰が・・・な」
「腰?店長腰悪くしたんですか?ちょ、大丈夫ですか!?海堂さん呼んできましょうか?あの人ああ見えてマッサージ得意なので」
「あー・・・そういうワケじゃ、いや、元はと言えばお前らがブランコなんか・・・」
なんだかよくわからないが随分と歯切れが悪い。
腰悪くしたことがそんなに言いにくい事なのか?
言葉尻が小さくて上手く聞き取れない。
「・・・あー、海堂の旦那の事は頼む。屈んだりすると結構痛むもんでな。基本はホール、こっちが手一杯になったらキッチンもやってもらうつもりだ。で、どうだ?まかない付きで給料もしっかり出すぜ。時給は・・・こんくらいでどうだ?���
「おお・・・意外と結構な金額出しますね」
「臨時とは言えこっちから頼んでるわけだしな。その分コキ使ってやるが」
海堂さんの事を頼まれつつ、仕事内容も確認する。
まぁ、ドニーズの頃と左程変わらないだろう。お酒の提供が主、くらいの違いか。
時給もこんな離島の居酒屋とは思えない程には良い。田舎の離島で時給四桁は驚きだ。
内容的にも特に問題ない。直ぐにでも始められるだろう。
とはいえ、屋敷に世話になっている身。勝手に決められるものでもない。
「非常に魅力的ではあるんですが、即断即決とは・・・。申し訳ないですが、一度持ち帰らせてください」
「おう。言っとくが夜の居酒屋の方だからな」
「キッチンの話出しといて昼間だったら���れはそれでビックリですよ。わかりました、また明日にでも返事に来ますよ」
話を終え、買い物を済ませて三日月亭を後にする。
バイト、かぁ・・・。
夕食後。皆で食後のお茶をいただいている時に俺は話を切り出した。
夜間の外出になるのでまずは照道さんに相談するべきだし、海堂さんにもマッサージの話をしなければならない。
「成程。裕さんがやりたいと思うなら、私は反対はしませんよ。店長には日ごろからお世話になっていますし」
「ほー。ま、いいんじゃねぇの?懐があったかくなることは悪いことじゃあねえじゃねえか。マッサージの方も受けといてやるよ。店長に借り作っとくのも悪くないしな」
難しい顔をされるかと思ったが、話はあっさりと通った。
海堂さんに至っては難色を示すかと思っていたが、損得を計算したのかこちらもすんなりと了承を得た。
ちょっと拍子抜けしつつ、改めて照道さんに確認する。
「えっと、本当にいいんですか?」
「ええ。ただ、裕さんの事を考えると帰りだけは誰かしらに迎えに行ってもらった方がいいかもしれませんね」
確かに。禍月の時ではなくても、この島は気性が荒い人は少なくない。
まして居酒屋で働くのだ。店長がいるとはいえ何かしらトラブルに巻き込まれる可能性もある。
「じゃあ、俺が迎えに行くぜ。なんなら向こうで普通に飲んでてもいいしな」
お茶を啜っていた勇魚さんがニカッと笑う。
あ、湯呑が空になってる。
急須を取り、勇魚さんの湯呑にお茶を注ぎながら問い返す。
「俺は助かりますけどいいんですか?はい、お茶のおかわり」
「お、さんきゅ。いいんだよ、俺がやりてえんだから。俺なら酔いつぶれることもねえしな。それに、そういうのは旦那の仕事だろ?」
自然な流れで旦那発言が出てきて驚きつつ、その事実に一気に顔が火照る。
うん、そうなんだけど。嬉しいんだけど。そうストレートに言われると恥ずかしいというかなんというか。
「え、と・・・ありがとうございます」
「けっ、惚気は余所でやれってんだ」
「ふふ・・・」
海堂さんのヤジも、照道さんの温かな眼差しもどこか遠くに感じる。
ヤバい。凄い嬉しい。でもやっぱ恥ずかしい。
そんな思いに悶々としていると、冴さんがコトリと湯呑を置いた。
「で、バイトはいいんだけど、その間誰が私達のおつまみを用意してくれるの?」
「はっ、そういやそうだ!オイ裕!お前自分の仕事はどうする気なんだ」
冴さんの一言に、海堂さんが即座に反応す��。
ええ・・・酒飲みたちへのおつまみの提供、俺の仕事になってたの・・・?
「それこそ三日月亭に飲みに来ればいいのでは・・・?」
「それも悪くはないけれど、静かに飲みたい時には向かないのよ、あそこ。それに、この髭親父を担いで帰るなんて事、か弱い乙女の私にさせるの?」
確かに三日月亭は漁師の人達がいつもいるから賑やか、というかうるさい。
ゆったり飲むには確かに向かないかもしれない。ましてや冴さんは女性だから漁師たちの視線を集めまくることだろう。
さり気なく、海堂さんを担ぐのを無理ともできないとも言わない辺りが冴さんらしい。
「ふむ。俺が裕につまみのレシピを教えてもらっておけばいいだろう。新しいものは無理だが既存のレシピであれば再現して提供できる」
「それが無難ですかね。すみません、洋一さん。今日の分、一緒に作りましょう。他にもいくつか教えておきますので」
「ああ、問題ない」
結局、洋一さんが俺の代わりにおつまみ提供をしてくれる事になり、事なきを得た。
翌日、午前中に店長へと返事をした後、島を探索。
少々の収穫もありつつ、昼過ぎには切り上げ、陽が落ち始める前には三日月亭へと足を運んでいた。
「説明は大体こんなもんか。不明な点が出てきたら逐一聞いてくれ」
「はい。多分大丈夫だと思います」
注文の仕方、調理場の決まり、会計の方法。
業務の大半はドニーズでの経験がそのまま役立ちそうだ。
むしろ、クーポンだのポイントだのない分こちらの方がシンプルで楽かもしれない。
渡されたエプロンを付けて腰紐を後ろで縛る。うん、準備は万全だ。
「さ、頼むぞルーキー」
「店長が楽できるよう努めさせてもらいますよ」
そんな軽口をたたき合いながら店を開ける。
数分も経たないうちに、入り口がガラリと音を立てた。
「いらっしゃい」
「いらっしゃいませー!」
現れたのは見慣れた凸凹コンビ。
吾郎さんと潮さんだ。
「あれ?裕?お前こんなとこで何してんだ?」
「バイト・・・えっと、店長が腰悪くしたみたいで臨時の手伝いです」
「なに、店長が。平気なのか?」
「動けないって程じゃないらしいので良くなってくと思いますよ。マッサージも頼んでありますし。それまでは短期の手伝いです」
「成程なぁ・・・」
ここで働くようになった経緯を話しつつ、カウンター近くの席へご案内。
おしぼりを渡しつつ、注文用のクリップボードを取り出す。
「ご注文は?まずは生ビールです?生でいいですよね?」
「随分ビールを推すなお前・・・まぁ、それでいいか。潮もいいか?」
「ああ、ビールでいいぞ。後は―」
少々のおつまみの注文を受けつつ、それを店長へと投げる。
「はい、店長。チキン南蛮1、鶏もも塩4、ネギま塩4、ツナサラダ1」
「おう。ほい、お通しだ」
冷蔵庫から出された本日のお通し、マグロの漬けをお盆にのせつつ、冷えたビールジョッキを用意する。
ジョッキを斜めに傾けながらビールサーバーの取っ手を手前へ。
黄金の液体を静かに注ぎながら垂直に傾けていく。
ビールがジョッキ取っ手の高さまで注がれたら奥側に向けてサーバーの取っ手を倒す。
きめ細かな白い泡が注がれ、見事な7:3のビールの完成。
うん、我ながら完璧だ。
前いたドニーズのサーバーは全自動だったから一回やってみたかったんだよなぁ、これ。
「はい、生二丁お待たせしました。こっちはお通しのマグロの漬けです」
「おう。んじゃ、乾杯ー!」
「ああ、乾杯」
吾郎さん達がビールを流し込むと同時に、入り口の引き戸が開く音がした。
そちらを向きつつ、俺は息を吸い込む。
「いらっしゃいませー!」
そんなスタートを切って、およそ2時間後。
既に席の半分は埋まり、三日月亭は盛況だ。
そんな中、またも入り口の引き戸が開き、見知った顔が入って来た。
「いらっしゃいませー!」
「おう、裕!頑張ってるみたいだな!」
「やあ、裕。店を手伝っているそうだな」
「勇魚さん。あれ、勇海さんも。お二人で飲みに来られたんですか?」
現れたのは勇魚さんと勇海さんの二人組。
俺にとっても良く見知ったコンビだ。
「勇魚から裕がここで働き始めたと聞いてな。様子見ついでに飲まないかと誘われてな」
「成程。こっちの席へどうぞ。・・・はい、おしぼりです。勇魚さんは益荒男ですよね。勇海さんも益荒男で大丈夫ですか?」
「ああ、頼むよ」
「はは、裕。様になってるぞ!」
「ありがとうございます。あまりお構いできませんがゆっくりしていってくださいね」
勇魚さんは俺の様子見と俺の迎えを兼ねて、今日はこのままここで飲むつもりなのだろう。
それで、勇海さんを誘ったと。
もう少しここにいたいが注文で呼ばれてしまっては仕方ない。
別の席で注文を取りつつ、すぐさまお酒の用意を準備をしなければ。
「いらっしゃいませー!」
「おッ、マジでいた!よう裕!遊びに来てやったぜ!」
「あれ、嵐の兄さん、照雄さんまで。何でここに?」
勇魚さん達が来てからしばらく経ったころ、店に見知った大柄な人物がやってくる。
道場の昭雄さんと嵐の兄さんだ。
「漁師連中の噂で三日月亭に新しい店員がいるって話を聞いてな」
「話を聞いて裕っぽいと思ったんだが大当たりだな!」
「確認するためだけにわざわざ・・・。ともかく、こっちの席にどうぞ。はい、おしぼりです」
働き始めたの、今日なんだけどな・・・。
田舎の噂の拡散力は恐ろしいな。
そんな事を思いつつ、2人を席に誘導する。
椅子に座って一息ついたのを確認し、おしぼりを渡しクリップボードの準備をする。
「おお。結構様になってるな。手際もいい」
「そりゃ照雄さんと違って裕は飲み込みいいからな」
「・・・おい」
照雄さんが俺を見て感心したように褒めてくれる。
何故か嵐の兄さんが誇らしげに褒めてくれるが、いつものように昭雄さん弄りも混じる。
そんな嵐の兄さんを、照雄さんが何か言いたげに半目で睨む。ああ、いつもの道場の光景だ。
「はは・・・似たようなことの経験があるので。お二人ともビールでいいですか?」
「おう!ついでに、裕が何か適当につまみ作ってくれよ」
「え!?やっていいのかな・・・店長に確認してみますね」
嵐の兄さんの提案により、店長によって「限定:臨時店員のおすすめ一品」が即座にメニューに追加されることとなった。
このおかげで俺の仕事は当社比2倍になったことを追記しておく。
後で申し訳なさそうに謝る嵐の兄さんが印象的でした。
あの銭ゲバ絶対許さねえ。
「おーい、兄ちゃん!注文ー!」
「はーい、只今ー!」
キッチン仕事の比重も上がった状態でホールもしなければならず、一気にてんてこ舞いに。
「おお、あんちゃん中々可愛い面してるなぁ!」
「はは・・・ありがとうございます」
時折本気なのか冗談なのかよくわからないお言葉を頂きつつ、適当に濁しながら仕事を進める。
勇魚さんもこっちを心配してくれているのか、心配そうな目と時折視線があう。
『大丈夫』という気持ちを込めて頷いてみせると『頑張れよ』と勇魚さんの口元が動いた。
なんかいいなァ、こういうの。
こっからも、まだまだ頑張れそうだ。
「そういえば、裕は道場で武術を学んでいるのだったか」
「おう。時たまかなり扱かれて帰って来るぜ。飲み込みが早いのかかなりの速度で上達してる。頑張り屋だよなぁ、ホント」
「ふふ、道場の者とも仲良くやっているようだな。嵐の奴、相当裕が気に入ったのだな」
「・・・おう、そうだな。・・・いい事じゃねえか」
「まるで兄弟みたいじゃないか。・・・どうした勇魚。複雑そうだな」
「勇海、お前さんわかって言ってるだろ」
「はは、どうだろうな。・・・ほら、また裕が口説かれているぞ」
「何っ!?ってオイ!勇海!」
「はははははっ!悪い。お前が何度もちらちらと裕の方を見ているのでな。あれだけ島の者を惹きつけているのだ、心配も当然だろう」
「裕を疑うわけじゃねえ。が、アイツ変なところで無防備だからよ。目を離した隙に手を出されちまうんじゃないかと気が気じゃねえんだよ」
何を話しているのかはここからじゃ聞こえないが、気安い親父たちの会話が交わされているらしい。
勇魚さんも勇海さんもなんだか楽しそうだ。
「成程な、当然だ。ふうむ・・・ならば勇魚よ、『網絡め』をしてみるか?立会人は俺がしてやろう」
「『網絡め』?なんだそりゃ」
「『網絡め』というのはだな―」
あまりにも楽しそうに会話しているので、まさかここであんな話をしているとは夢にも思わなかった。
盛大なイベントのフラグが既にここで立っていたのだが、この時点の俺にはあずかり知らぬ出来事であった。
そんなこんなで時間は過ぎ、あっという間に閉店時刻に。
店内の掃除を終え、食器を洗い、軽く明日の準備をしておく。
店長は本日の売り上げを清算しているが、傍から見ても上機嫌なのがわかる。
俺の目から見ても今日はかなり繁盛していた。
売り上げも中々良いはずだろう。
「いやぁ、やっぱお前を雇って正解だったな!調理に集中しやすいし、お前のおかげで客も増えるし財布も緩くなる!」
「おかげでこっちはクタクタですけどね・・・」
「真面目な話、本当に助かった。手際も良いしフードもいける。島にいる間定期的に雇ってもいいくらいだ。もっと早くお前の有用性に気づくべきだったな」
仕事ぶりを評価してくれているのか、便利な人材として認識されたのか。
両方か。
「俺も俺でやることがあるので定期は流石に・・・」
「ま、ひと夏の短期バイトが関の山か。ともかく、明日もよろしく頼むぜ」
「はい。店長もお大事に。また明日」
金銭管理は店長の管轄だし、もうやれることはない。
店長に挨拶をし、帰路につくことにする。
店を出ると、勇魚さんが出迎えてくれた。
「さ、帰ろうぜ、裕」
「お待たせしました。ありがとうございます、勇魚さん」
「いいって事よ」
三日月亭を離れ、屋敷までの道を二人で歩いていく。
店に居た時はあんなに騒がしかったのに、今はとても静かだ。
そんな静かな道を二人っきりで歩くのって・・・何か、いいな。
「・・・にしてもお前、よく頑張ってたな」
「いや、途中からてんてこ舞いでしたけどね。飲食業はやっぱ大変だなぁ」
「そうか?そう言う割にはよく働いてたと思うぜ?ミスもねえし仕事遅くもなかったし」
「寧ろあれを日がな一人で捌いてる店長が凄いですよ」
「はは!そりゃあ本業だしな。じゃなきゃやってけねえだろうさ」
勇魚さんに褒められるのは単純に嬉しいのだが、内心は複雑だ。
一日目にしてはそれなりにやれたという自覚もあるが、まだまだ仕事効率的にも改善点は多い。
そういう部分も無駄なくこなしている店長は、何だかんだで凄いのだ。
「にしても、この島の人達はやっぱり気さくというか・・・気安い方が多いですね」
「そう、だな・・・」
酒も入るからか、陽気になるのは兎も角、やたらとスキンシップが多かった。
肩を組んでくるとかならまだいいが、引き寄せるように腰を掴んできたり、ちょっとしたセクハラ発言が飛んできたり。
幸か不幸か海堂さんのおかげで耐性がついてしまったため、適当に流すことは出来るのだが。
「裕、お前気を付けろよ」
「はい?何がですか?」
「この島の連中、何だかんだでお前の事気に入ってる奴多いからな。こっちは心配でよ」
「勇魚さんも俺の事言えないと思いますけど・・・。大丈夫ですよ、俺は勇魚さん一筋ですから」
「お、おう・・・」
勇魚さんは俺の事が心配なのか、どこか不安そうな顔で俺を見る。
モテ具合で言ったら寧ろ勇魚さんの方が凄まじい気がするので俺としてはそっちの方が心配だ。
でも、その気遣いが、寄せられる想いが嬉しい。
その温かな気持ちのまま、勇魚さんの手を握る。
一瞬驚いた顔をした勇魚さんだが、すぐさま力強く握り返される。
「へへっ・・・」
「あははっ」
握った手から、勇魚さんの熱が伝わってくる。
あったかい。手も。胸も。
温かな何かが、胸の奥から止まることなく滾々と湧き出てくるようだ。
なんだろう。今、すごく幸せだ。
「なぁ、裕。帰ったら風呂入って、その後晩酌しようぜ」
「閉店直前まで勇海さんと結構飲んでましたよね?大丈夫なんですか?」
「あんくらいじゃ潰れもしねえさ。な、いいだろ。ちょっとだけ付き合ってくれよ���
「全くもう・・・。わかりましたよ。つまむもの何かあったかなぁ」
という訳でお風呂で汗を流した後、縁側で勇魚さんとちょっとだけ晩酌を。
もう夜も遅いので、おつまみは火を使わない冷奴とぬか漬けと大根おろしを。
「お待たせしました」
「おっ、やっこにぬか漬けに大根おろしか。たまにはこういうのもいいなあ」
「もう夜遅いですからね。火をつかうものは避けました」
火を使っても問題は無いのだが、しっかりと料理を始めたら何処からかその匂いにつられた輩が来る可能性もある。
晩酌のお誘いを受けたのだ。
どうせなら二人きりで楽しみたい。
「お、このぬか漬け。よく漬かってんな。屋敷で出してくれるのとちと違う気がするが・・・」
「千波のお母さんからぬか床を貰いまして。照道さんには、俺個人で消費して欲しいと言われてますので・・・」
「ああ、ぬか床戦争って奴だな!この島にもあんのか」
ぬか漬け、美味しいんだけどその度に沙夜さんと照道さんのあの時の圧を思い出して何とも言えない気分になるんだよなぁ。
こうして勇魚さんにぬか漬けを提供できる点に関しては沙夜さんに感謝なんだけど。
というかぬか床戦争なんて単語、勇魚さんの口から出ることに驚きを感じますよ・・・。
他の地域にもあるのか?・・・いや、深く考えないようにしよう。
「そういえば前にからみ餅食べましたけど、普通の大根おろしも俺は好きですねえ」
「絡み・・・」
大根おろしを食べていると白耀節の時を思い出す。
そういえば勇魚さんと海堂さんでバター醤油か砂糖醬油かで争ってたこともあったなぁ。
と、先ほどまで饒舌に喋っていた勇魚さんが静かになったような気がする。
何があったかと思い勇魚さんを見ると、心なしか顔が赤くなっているような気がする。
「勇魚さん?どうしました?やっぱりお酒回ってきました?」
「いや・・・うん。なんでもねえ、気にすんな!」
「・・・???まぁ、勇魚さんがそう言うなら」
ちょっと腑に落ちない感じではあったが、気にしてもしょうがないだろう。
そこから小一時間程、俺は勇魚さんとの晩酌を楽しんだのであった。
翌日、夕方。
三日月亭にて―
「兄ちゃん!注文いいかー?この臨時店員のおすすめ一品っての2つ!」
「こっちにも3つ頼むぜー」
「はーい、今用意しまーす!ちょ、店長!なんか今日やたら客多くないですか!?」
「おう、ビビるぐらい客が来るな。やっぱりお前の効果か・・・?」
もうすぐ陽が沈む頃だと言うのに既に三日月亭は大盛況である。
昨日の同時刻より明らかに客数が多い。
ちょ、これはキツい・・・。
「ちわーっとぉ、盛況だなオイ」
「裕ー!面白そうだから様子見に来たわよー」
「・・・大変そうだな、裕」
そんな中、海堂さんと冴さん、洋一さんがご来店。
前二人は最早冷やかしじゃないのか。
「面白そうって・・・割と混んでるのであんまり構えませんよ。はい、お通しとビール」
「いいわよォ、勝手にやってるから。私、唐揚げとポテトサラダね」
「エイヒレ頼むわ。後ホッケ」
「はいはい・・・」
本日のお通しである卯の花を出しながらビールジョッキを3つテーブルに置く。
この二人、頼み方が屋敷の時のソレである。
ぶれなさすぎな態度に実家のような安心感すら感じr・・・いや感じないな。
何だ今の感想。我が事ながら意味がわからない。
「裕。この『限定:臨時店員のおすすめ一品』というのは何だ?」
「俺が日替わりでご用意する一品目ですね。まぁ、色々あってメニューに追加になりまして」
「ふむ。では、俺はこの『限定:臨時店員のおすすめ一品』で頼む」
「お出しする前にメニューが何かもお伝え出来ますよ?」
「いや、ここは何が来るかを期待しながら待つとしよう」
「ハードル上げるなァ。唐揚げ1ポテサラ1エイヒレ1ホッケ1おすすめ1ですね。店長、3番オーダー入りまーす」
他の料理は店長に投げ、俺もキッチンに立つ。
本日のおすすめは鯵のなめろう。
処理した鯵を包丁でたたいて細かく刻み、そこにネギと大葉を加えてさらに叩いて刻む。
すりおろしたにんにくとショウガ、醤油、味噌、を加え更に細かく叩く。
馴染んだら下に大葉を敷いて盛り付けて完成。
手は疲れるが、結構簡単に作れるものなのだ。
そうして用意したなめろうを、それぞれのテーブルへと運んでいく。
まだまだピークはこれからだ。気合い入れて頑張ろう。
そう気合を入れ直した直後にまたも入り口の引き戸が音を立てたのであった。
わぁい、きょうはせんきゃくばんらいだー。
「おーい裕の兄ちゃん!今日も来たぜ!」
「いらっしゃいませー!連日飲んでて大丈夫なんですか?明日も朝早いんでしょう?」
「はっは、そんくらいで漁に行けない軟弱な野郎なんざこの打波にはいねえさ」
「むしろ、お前さんの顔見て元気になるってもんだ」
「はァ、そういうもんですか?とは言え、飲み過ぎないように気を付けてくださいね」
「なぁあんちゃん。酌してくれよ」
「はいはい、只今。・・・はい、どうぞ」
「っかー!いいねぇ!酒が美味ぇ!」
「手酌よりかはマシとは言え、野郎の酌で変わるもんです?」
「おうよ!あんちゃんみたいな可愛い奴に酌されると気分もいいしな!あんちゃんなら尺でもいいぜ?」
「お酌なら今しているのでは・・・?」
「・・・がはは、そうだな!」
「おい、兄ちゃんも一杯どうだ?飲めない訳じゃねえんだろ?」
「飲める歳ではありますけど仕事中ですので。皆さんだってお酒飲みながら漁には出ないでしょう?」
「そらそうだ!悪かったな。・・・今度、漁が終わったら一緒に飲もうぜ!」
「はは、考えておきますね」
ただのバイトに来ている筈なのに、何だか何処ぞのスナックのママみたいな気分になってくる。
それも、この島の人達の雰囲気のせいなのだろうか。
「あいつすげぇな。看板娘みてぇな扱いになってんぞ」
「流石裕ね。二日目にして店の常連共を掌握するとは。崇といい、これも旺海の血なのかしら?」
「もぐもぐ」
「さぁな。にしても、嫁があんなモテモテだと勇魚の野郎も大変だねぇ」
「裕の相手があの勇魚だって知った上で尚挑めるのかが見ものね」
「もぐもぐ」
「洋一、もしかしてなめろう気に入ったのか?」
「・・・うまい。巌もどうだ?」
「お、おう」
料理を運んでいる途中、洋一さんがひたすらなめろうを口に運んでいるのが目に入る。
もしかして、気に入ったのかな?
そんな風にちょっとほっこりした気持ちになった頃、嵐は唐突に現れた。
嵐の兄さんじゃないよ。嵐の到来って奴。
「おーう裕。頑張っとるようじゃのう」
「あれ、疾海さん?珍しいですね、ここに来るなんて」
「げ、疾海のジジィだと!?帰れ帰れ!ここにはアンタに出すもんなんてねぇ!裕、塩持って来い塩!」
勇海さんのお父さんである疾海さんが来店。
この人がここにやってくる姿はほとんど見たことがないけれど、どうしたんだろう。
というか店長知り合いだったのか。
「なんじゃ店主、つれないのう。こないだはあんなに儂に縋り付いておったというのに」
「バッ・・・うるせェ!人の体好き放題しやがって!おかげで俺は・・・!」
「何言っとる。儂はちょいとお前さんの体を開いただけじゃろが。その後に若い衆に好き放題されて悦んどったのはお前さんの方じゃろ」
あー・・・そういう事ね。店長の腰をやった原因の一端は疾海さんか。
うん、これは聞かなかったことにしておこう。
というか、あけっぴろげに性事情を暴露されるとか店長が不憫でならない。
「のう、裕よ。お主も興味あるじゃろ?店主がどんな風に儂に縋り付いてきたか、その後どんな風に悦んでおったか」
「ちょ、ジジィてめぇ・・・」
「疾海さん、もうその辺で勘弁してあげてくださいよ。店長の腰がやられてるのは事実ですし、そのせいで俺が臨時で雇われてるんですから。益荒男でいいですか?どうぞ、そこの席にかけてください」
「おい、裕!」
「店長も落ち着いて。俺は何も見てませんし聞いてません。閉店までまだまだ遠いんですから今体力使ってもしょうがないでしょう。俺が疾海さんの相手しますから」
「―ッ、スマン。頼んだぞ、裕」
店長は顔を真っ赤にして逃げるようにキッチンへと戻っていった。
うん、あの、何て言うか・・・ご愁傷様です。
憐れみの視線を店長に送りつつお通しと益荒男を準備し、疾海さんの席へと提供する。
「よう店主の手綱を握ったのう、裕。やるもんじゃな」
「もとはと言えば疾海さんが店長をおちょくるからでしょう。あんまりからかわないでくださいよ」
にやにやと笑う疾海さんにため息が出てくる。
全く・・・このエロ爺は本当、悪戯っ子みたいな人だ。
その悪戯が天元突破したセクハラばかりというのもまた酷い。
しかも相手を即落ち、沈溺させるレベルのエロ技術を習得しているからなおさら性質が悪い。
「にしても、裕。お前さんもいい尻をしておるのう。勇魚の竿はもう受けたか?しっかりと耕さんとアレは辛いじゃろうて」
おもむろに尻を揉まれる。いや、揉みしだかれる。
しかも、その指が尻の割れ目に・・・ってオイ!
「―ッ!」
脳が危険信号を最大限に発し、半ば反射的に体が動く。
右手で尻を揉みしだく手を払いのけ、その勢いのまま相手の顔面に左の裏拳を叩き込む!
が、振り抜いた拳に手ごたえは無く、空を切ったのを感じる。
俺は即座に一歩下がり、構えを解かずに臨戦態勢を維持。
チッ、屈んで避けたか・・・。
「っとぉ、危ないのう、裕。儂の男前な顔を台無しにするつもりか?」
「うるせえジジイおもてでろ」
「ほう、その構え・・・。成程、お前さん辰巳の孫のとこに師事したんか。道理で覚えのある動きじゃ。じゃが、キレがまだまだ甘いのう」
かなりのスピードで打ち込んだ筈なのに易々と回避されてしまった。
やはりこのジジイ只者ではない。
俺に攻撃をされたにも関わらず、にやにやとした笑いを崩さず、のんびりと酒を呷っている。
クソッ、俺にもっと力があれば・・・!
「おい裕、どうした。何か擦れた音が、ってオイ。マジでどうした!空気が尋常じゃねぇぞ!?」
店内に突如響いた地面を擦る音に、店長が様子を見に来たようだ。
俺の状態に即座に気づいたようで、後ろから店長に羽交い締めにされる。
「店長どいてそいつころせない」
「落ち着け!何があったか想像はつくが店ん中で暴れんな!」
「かかかっ!可愛い奴よな、裕。さて、儂はまだ行くところがあるでの。金はここに置いとくぞ」
俺が店長に止められている間に、エロ爺は笑いながら店を後にした。
飲み食い代よりもかなり多めの金額が置かれているのにも腹が立つ。
「店長!塩!」
「お、おう・・・」
さっきとはまるきり立場が逆である。
店の引き戸を力任せにこじ開け、保存容器から塩を鷲掴む。
「祓い給え、清め給え!!消毒!殺菌!滅菌ッ!!!」
適当な言葉と共に店の前に塩をぶちまける。
お店の前に、白い塩粒が散弾のように飛び散った。
「ふー、ふー、ふーッ!・・・ふぅ」
「・・・落ち着いたか?」
「・・・ええ、何とか」
ひとしきり塩をぶちまけるとようやく気持ちが落ち着いてきた。
店長の気遣うような声色に、何ともやるせない気持ちになりながら返答する。
疲労と倦怠感に包まれながら店の中に戻ると、盛大な歓声で出迎えられる。
「兄さん、アンタやるじゃねぇか!」
「うおッ!?」
「疾海のじいさんにちょっかいかけられたら大体はそのまま食われちまうのに」
「ひょろっちい奴だと思ってたがすげえ身のこなしだったな!惚れ惚れするぜ!」
「あ、ありがとうございます・・・はは・・・」
疾海さんは俺と勇魚さんの事を知っているから、単にからかってきただけだろうとは思っている。
エロいし奔放だし子供みたいだが、意外と筋は通すし。
あくまで「比較的」通す方であって手を出さない訳ではないというのが困りものではあるが。
そんな裏事情をお客の人達が知っている訳もなく、武術で疾海さんを退けたという扱いになっているらしい。
けど、あのジジイが本気になったら俺の付け焼刃な武術じゃ相手にならない気がする。
さっきの物言いを考えると辰馬のおじいさんとやりあってたって事になる。
・・・うん、無理そう。
「おっし!そんなあんちゃんに俺が一杯奢ってやろう!祝杯だ!」
「いいねえ!俺も奢るぜ兄ちゃん!」
「抜け駆けすんな俺も奢るぞ!」
「ええっ!?いや、困りますって・・・俺、仕事中ですし・・・」
「裕、折角なんだし受けておきなさいな」
どうしようかと途方に暮れていると、いつの間にか冴さんが隣に来ていた。
と、それとなく手の中に器のようなものを握らされた。
「冴さん。あれ、これって・・・」
横目でちらりと見ると『咲』の字が入った器。
これ、咲夜の盃・・・だよな?
「腕も立って酒にも強いと知っとけば、あの連中も少しは大人しくなるでしょ。自衛は大事よ」
「はぁ・・・自衛、ですか」
「後でちゃんと返してね」
これって確か、持ってるだけで酒が強くなるって盃だったっけ。
その効果は一度使って知っているので、有難く使わせてもらうとしよう。
店長もこっちのやりとりを見ていたのか何も言うこと無く調理をしていた。
「おっ、姐さんも一緒に飲むかい!?」
「ええ。折角だから裕にあやからせてもらうわ。さぁ、飛ばしていくわよ野郎共ー!」
「「「「おおーっ!!」」」」
「お、おー・・・」
その後、ガンガン注がれるお酒を消費しつつ、盃を返す、を何度か繰り返すことになった。
途中からは冴さんの独壇場となり、並み居る野郎共を悉く轟沈させて回っていた。
流石っス、姐さん。
ちなみに俺は盃のご利益もあり、その横で飲んでいるだけで終わる事になった。
そんな一波乱がありつつも、夜は更けていったのだった。
そんなこんなで本日の営業終了時刻が近づいてくる。
店内には冴さん、海堂さん、洋一さんの3人。
冴さんはいまだ飲んでおり、その底を見せない。ワクなのかこの人。
海堂さんはテーブルに突っ伏してイビキをかいており、完全に寝てしまっている。
洋一さんはそんな海堂さんを気にしつつ、お茶を啜っている。
あんなにいた野郎共も冴さんに轟沈させられた後、呻きながら帰って行った。
明日の仕事、大丈夫なんだろうか・・・。
後片付けや掃除もほぼ終わり、後は冴さん達の使っているテーブルだけとなった時、入り口が壊れそうな勢いで乱暴に開いた。
「裕ッ!」
「うわっ、びっくりした。・・・勇魚さん、お疲れ様です」
入り口を開けて飛び込んできたのは勇魚さんだった。
いきなりの大声にかなり驚いたが、相手が勇魚さんとわかれば安心に変わる。
だが、勇魚さんはドスドスと近づいてくると俺の両肩をガシリと掴んだ。
「オイ裕!大丈夫だったか!?変な事されてねえだろうな!」
勇魚さんにしては珍しく、かなり切羽詰まった様子だ。
こんなに心配される事、あったっけ・・・?
疑問符が浮かぶがちらりと見えた勇海さんの姿にああ、と納得する。
というか苦しい。掴まれた肩もミシミシ言ってる気がする。
「うわっ!?大丈夫、大丈夫ですって。ちょ、勇魚さん苦しいです」
「お、おう。すまねえ・・・」
宥めると少し落ち着いたのか、手を放してくれる。
勇魚さんに続いて入って来た勇海さんが、申し訳なさそうに口を開いた。
「裕、すまないな。親父殿が無礼を働いたそうだな」
「勇海さんが気にすることではないですよ。反撃もしましたし。まぁ、逃げられたんですけど」
「裕は勇魚のつがいだと言うのに、全く仕方のないことだ。親父殿には私から言い聞かせておく。勘弁してやって欲しい」
「疾海さんには『次やったらその玉潰す』、とお伝えください」
「ははは、必ず伝えておくよ」
俺の返答に納得したのか、勇海さんは愉快そうに笑う。
本当にその時が来た時の為に、俺も更なる修練を積まなければ。
・・・気は進まないけど、辰馬のおじいさんに鍛えてもらう事も視野に入れなければならないかもしれない。
「裕、今日はもう上がっていいぞ。そいつら連れて帰れ」
「え、いいんですか?」
「掃除も殆ど終わってるしな。色々あったんだ、帰って休んどけ」
俺に気を遣ってくれたのか、はたまたさっさと全員を返したかったのか、店長から退勤の許可が出た。
ここは有難く上がらせてもらおう。色々あって疲れたのは事実だ。
「じゃあ、折角ですので上がらせてもらいます。お疲れ様でした」
「おう。明日も頼むぞ」
店長に挨拶をし、皆で店を出る。
勇海さんはここでお別れとなり、俺、勇魚さん、冴さん、海堂さん、洋一さんの5人で帰る。
寝こけている海堂さんは洋一さんが背負っている。
「裕、ホントに他に何も無かったんだろうな!?」
「ですから、疾海さんにセクハラ受けただけですって。その後は特に何も無かったですし・・・」
で、帰り道。勇魚さんに詰問されております。
心配してくれるのはとても嬉しい。
嬉しいんだけど、過剰な心配のような気もしてちょっと気おくれしてしまう。
「俺に気を遣って嘘ついたりすんじゃねえぞ」
「冴さん達も一緒にいたのに嘘も何もないんですが・・・」
「裕の言ってる事に嘘はないわよ。疾海の爺さんに尻揉まれてたのも事実だけど」
「・・・思い出したら何か腹立ってきました。あのジジイ、次に会ったら確実に潰さなきゃ」
被害者を減らすにはその大本である性欲を無くすしかないかな?
やっぱり金的か。ゴールデンクラッシュするしかないか。
あの驚異的な回避力に追いつくためにはどうすればいいか・・・。
搦め手でも奇襲なんでもいい、当てさえすればこちらのものだろう。
そう思いながら突きを繰り出し胡桃的な何かを握り潰す動作を数回。
駄目だな、やっぱりスピードが足りない。
「成程、金的か」
「裕、その、ソイツは・・・」
洋一さんは俺の所作から何をしようとしているかを読み取ったようだ。
その言葉にさっきまで心配一色だった勇魚さんの顔色変わる。
どうしました?なんで微妙に股間を押さえて青ざめてるんです?
「冴さん。こう、男を不能寸前まで追い込むような護身術とかないですかね?」
「あるにはあるけど、そういうの覚えるよりもっと確実な方法があるわよ」
「え?」
「勇魚。アンタもっと裕と一緒にいなさい。で、裕は俺の嫁アピールしときなさい」
嫁。勇魚さんのお嫁さん。
うん、事実そうなんだけどそれを改めて言われるとなんというか。
嬉しいんだけど、ねぇ?この照れくさいような微妙な男心。
「裕。頬がだいぶ紅潮しているようだが大丈夫か?」
「だ、大丈夫です。何というか、改めて人に言われると急に、その・・・」
「ふむ?お前が勇魚のパートナーである事は事実だろう。港の方でも知れ渡っていると聞いている。恥ずべきことではないと思うが?」
「恥ずかしいんじゃなくて嬉しくも照れくさいというか・・・」
「・・・そういうものか。難しいものだな」
洋一さんに指摘され、更に顔が赤くなる。
恥ずかしいわけじゃない。むしろ嬉しい。
でも、同じくらい照れくささが湧き上がってくる。
イカン、今凄い顔が緩みまくってる自覚がある。
「流石にアンタ相手に真正面から裕に手を出す輩はいないでしょう。事実が知れ渡れば虫よけにもなって一石二鳥よ」
「お、おお!そうだな!そっちの方が俺も安心だ!うん、そうしろ裕!」
冴さんの案に我が意を得たりといった顔の勇魚さん。
妙に食いつきがいいなァ。
でも、それって四六時中勇魚さんと一緒にいろって事では?
「勇魚さんはそれでいいんですか?対セクハラ魔の為だけに勇魚さんの時間を割いてもらうのは流石にどうかと思うんですが」
「んなこたあねえよ。俺だってお前の事が心配なんだ。これくらいさせてくれよ」
「そう言われると断れない・・・」
申し訳ない旨を伝えると、純粋な好意と気遣いを返される。
実際勇魚さんと一緒に居られるのは嬉しいし、安心感があるのも事実だ。
「裕、あんたはあんたで危機感を持った方がいいわよ」
「危機感、といいますとやっぱりセクハラ親父やセクハラ爺の対処の話ですか?」
冴さんの言葉に、2人の男の顔が思い浮かぶ。
悪戯、セクハラ、煽りにからかい。あの人たちそういうの大好きだからなぁ。
でも、だいぶ耐性はついたし流せるようになってきたと思ってるんだけど。
「違うわよ。いやある意味同じようなモンか」
「客だ、裕」
「客?お店に来るお客さんって事ですか?」
え、海堂さんとか疾海さんじゃないのか。
そう思っていると意外な答えが洋一さんの方から返って来た。
客の人達に何かされたりは・・・ない筈だったけど。
「店にいた男たちはかなりの人数が裕を泥酔させようと画策していたな。冴が悉くを潰し返していたが」
「何っ!?」
「え!?洋一さん、それどういう・・・」
何その事実今初めて知った。どういうことなの。
「今日店に居た男たちは皆一様にお前をターゲットとしていたようだ。やたらお前に酒を勧めていただろう。お前自身は仕事中だと断っていたし、店長もお前に酒がいかないようそれとなくガードしていた。だがお前が疾海を撃退したとなった後、躍起になるようにお前に飲ませようとしていただろう。だから冴が向かったという訳だ」
「疾海の爺さん、なんだかんだでこの島でもかなりの手練れみたいだしね。物理でだめならお酒でって寸法だったみたいね」
「えっと・・・」
「食堂に来てた立波さん、だったかしら。ここまで言えばわかるでしょ?店長も何だかんだでそういう事にならないよう気を配ってたわよ」
あァ、成程そういう事か。ようやく俺も理解した。
どうやら俺は三日月亭でそういう意味での好意を集めてしまったという事らしい。
で、以前店長が言っていた「紳���的でない方法」をしようとしていたが、疾海さんとのやりとりと冴さんのおかげで事なきを得たと、そういう事か。
「えー・・・」
「裕・・・」
勇魚さんが俺を見る。ええ、心配って顔に書いてますね。
そうですね、俺も逆の立場だったら心配しますよ。
「なあ裕。明日の手伝いは休んどけ。店には俺が行くからよ」
「いや、そういうワケにもいかないでしょう。勇魚さん、魚は捌けるでしょうけど料理できましたっけ?」
「何、料理ができない訳じゃねえ・・・なんとかなるだろ」
あっけらかんと笑う勇魚さんだが、俺には不安要素しかない。
確かに料理ができない訳じゃないけど如何せん漢の料理だ。店長の補助とかができるかと言うと怪しい。
この島に来てからの勇魚さんの功績をふと思い返す。
餅つき・・・臼・・・ウッアタマガ。
・・・ダメだ、食材ごとまな板真っ二つにしそうだし、食器を雑に扱って破壊しそうな予感しかしない。
勇魚さんの事だからセクハラされたりもしそうだ。
ダメダメ、そんなの俺が許容しません。
「様々な観点から見て却下します」
「裕ぅ~・・・」
そんなおねだりみたいな声したって駄目です。
却下です却下。
「裕、ならば俺が行くか?」
「お願いしたいのは山々なんですが洋一さんは明日北の集落に行く予定でしたよね。時間かかるって仰ってたでしょう?」
「ふむ。ならば巌に―」
「いえ、海堂さんには店長のマッサージもお願いしてますしこれ以上は・・・」
洋一さんが申し出てくれるが、洋一さんは洋一さんで抱えてる事がある。
流石にそれを曲げてもらうわけにはいかない。
海堂さんなら色んな意味で文句なしの人材ではあるのだが、既にマッサージもお願いしている。
それに、迂闊に海堂さんに借りを作りたくない。後が怖い。
「洋一も無理、巌も無理とするならどうするつもりなんだ?高瀬か?」
「勇魚さん、三日月亭の厨房を地獄の窯にするつもりですか?」
「失礼ねェ。頼まれてもやらないわよ」
勇魚さんからまさかの選択が投げられるがそれは無理。
冴さんとか藤馬さんに立たせたら三日月亭から死人が出る。三日月亭が営業停止する未来すらありえる。
頼まれてもやらないと冴さんは仰るが、「やれないからやらない」のか「やりたくないからやらない」のかどっちなんだ。
「明日も普通に俺が行きますよ。ついでに今後についても店長に相談します」
「それが一番ね。店長も裕の状況に気づいてるでしょうし」
「巌の話だとマッサージのおかげかだいぶ良くなってきているらしい。そう長引きはしないだろう」
「後は勇魚がガードすればいいのよ」
「おう、そうか。そうだな」
そんなこんなで話も固まり、俺達は屋敷に到着した。
明日は何事もなく終わってくれればいいんだけど・・・。
そんな不安も抱えつつ、夜は過ぎていった。
そしてバイト三日目。
俺は少し早めに三日月亭へと来ていた。
「ああ、だよなぁ。すまんな、そっちの可能性も考えてなかったワケじゃ無��んだが・・・そうなっちまうよなあ」
俺の状況と今後の事を掻い摘んで説明すると、店長は疲れたように天井を仰ぐ。
「何というか・・・すみません。腰の具合はどうです?」
別に俺が何かをしたわけではないけれど、状況の中心にいるのは確かなので申し訳ないとは思う。
「海堂の旦那のおかげでだいぶ良くなった。もう一人でも回せそうだ。何なら今日から手伝わなくてもいいんだぞ?」
店長はそう言うが、完治しているわけでもない。
悪化するわけではないだろうが気になるのも事実。
なので、昨日のうちに勇魚さんと決めていた提案を出すことにする。
「でも全快というわけでもないんでしょう?引き受けたのは自分です。勇魚さんもいますし、せめて今日までは手伝わせてくださいよ」
「心意気はありがてえが・・・。わかった、面倒ごとになりそうだったらすぐさま離れろよ?勇魚の旦那も頼むぜ」
「おう!」
「はい!さ、今日も頑張りましょう!」
昨日話した通り今日は開店から勇魚さんも店に居てくれる。
万が一な状態になれば即座に飛んできてくれるだろう。
それだけで心の余裕も段違いだ。
「裕、無理すんなよ」
「わかってますよ。勇魚さんも、頼みますね」
「おう、任せときな!」
勇魚さんには店内を見渡せる席に座ってもらい、適当に時間を潰してもらう。
俺は店長と一緒に仕込みを始めながら新メニューの話も始める。
途中、勇魚さんにビールとお通しを出すのも忘れずに。
「新しいメニュー、どうすっかねぇ」
「今日の一品、新レシピも兼ねてゴーヤーチャンプルーでいこうかと思うんですよ」
「ほー。確かに苦瓜なら栽培してるとこはそこそこあるしな。行けるだろう」
「スパム缶は無くても豚肉や鶏肉でいけますからね。肉が合わないなら練り物やツナでも大丈夫です。材料さえあれば炒めるだけってのも高ポイント」
「肉に卵にと寅吉んとこには世話になりっぱなしだな。だが、いいねえ。俺も久しぶりにチャンプルーとビールが恋しくなってきやがった」
「後で少し味見してくださいよ。島の人達の好み一番把握してるの店長なんだから。・・・でも、やっぱり新メニュー考えるのは楽しいな」
「・・・ったく、面倒ごとさえ無けりゃあこのまま働いてもらえるってのに。無自覚に野郎共の純情を弄びやがって」
「それ俺のせいじゃないですよね・・・」
調理実習をする学生みたいにわいわい喋りながら厨房に立つ俺達を、勇魚さんはニコニコしながら見ている。
あ、ビールもう空きそう。おかわりいるかな?
そんな風に営業準備をしていると時間はあっという間に過ぎ去り、開店時間になる。
開店して数分も経たないうちに、店の引き戸がガラリと開いた。
「いらっしゃいませー!」
「裕、お前まだここで働いてたのか」
「潮さん、こんばんは。今日までですけどね。あくまで臨時なので」
「ふむ、そうか。勇魚の旦那もいるのか」
「おう、潮。裕の付き添いでな」
「・・・ああ、成程な。それは確かに必要だ」
「おっ、今日も兄ちゃんいるのか!」
「いらっしゃいませ!ははは、今日で終わりなんですけどね」
「そうなのか!?寂しくなるなぁ・・・。なら、今日こそ一杯奢らせてくれよ」
「一杯だけならお受けしますよ。それ以上は無しですからね」
「裕の兄ちゃん!今日でいなくなっちまうって本当か!?」
「臨時ですので。店長の具合もよくなりましたし」
「兄ちゃんのおすすめ一品、好きだったんだけどよ・・・」
「はは、ありがとうございます。今日も用意してますから良かったら出しますよ」
「おう、頼むぜ!」
続々とやってくる常連客を捌きつつ、厨房にも立つ。
店長の動きを見てもほぼ問題ない。治ってきてるのも事実のようだ。
時折お客さんからの奢りも一杯限定で頂く。
今日は以前もらった方の咲夜の盃を持ってきているので酔う心配もない。
「おう、裕のあんちゃん!今日も来たぜ!」
「い、いらっしゃいませ・・・」
再びガラリと入り口が空き、大柄な人物がドスドスと入ってくる。
俺を見つけるとがっしと肩を組まれる。
日に焼けた肌が特徴の熊のような人だ。名前は・・・確か井灘さん、だったかな?
初日に俺に可愛いと言い、昨日は酌を頼まれ、冴さんに潰されてた人だ。
スキンシップも多く、昨日の一件を考えると警戒せざるを得ない。
取り合えず席に案内し、おしぼりを渡す。
「ガハハ、今日もあんちゃんの可愛い顔が見れるたぁツイてるな!」
「あ、ありがとうございます。注文はどうしますか?」
「まずはビール。食いモンは・・・そうさな、あんちゃんが適当に見繕ってくれよ」
「俺が、ですか。井灘さんの好みとかわかりませんけど・・・」
「大丈夫だ。俺、食えねえもんはねえからよ。頼むぜ!」
「はあ・・・分かりました」
何か丸投げされた感が凄いが適当に三品程見繕って出せばいいか。
ついでだからゴーヤーチャンプルーも試してもらおうかな。
そんな事を考えながら、俺は井灘さんにビールとお通しを出す。
「む・・・」
「どうした旦那。ん?アイツ、井灘か?」
「知ってるのか、潮」
「ああ。俺達とは違う港の漁師でな。悪い奴では無いんだが、気に入った奴にすぐ手を出すのが玉に瑕でな」
「そうか・・・」
「旦那、気を付けた方がいいぞ。井灘の奴、あの様子じゃ確実に裕に手を出すぞ」
「・・・おう」
こんな会話が勇魚さんと潮さんの間でなされていたとはつゆ知らず。
俺は店長と一緒に厨房で鍋を振っていた。
「はい、井灘さん。お待たせしました」
「おう、来た来た」
「つくね、ネギま、ぼんじりの塩の串盛り。マグロの山かけ。そして今日のおすすめ一品のゴーヤーチャンプルーです」
「いいねえ、流石あんちゃん。で、なんだそのごーやーちゃんぷうるってのは?」
「内地の料理ですよ。苦瓜と肉と豆腐と卵の炒め物、ってとこでしょうか。(厳密には内地の料理とはちょっと違うけど)」
「ほー苦瓜。滅多に食わねえが・・・あむ。うん、美味え!美味えぞあんちゃん!」
「それは良かった」
「お、美味そうだな。兄ちゃん、俺にもそのごーやーちゃんぷうるってのくれよ」
「俺も!」
「はいはい、ただいま」
井灘さんが美味しいと言ってくれたおかげで他の人もゴーヤーチャンプルーを頼み始める。
よしよし、ゴーヤーチャンプルーは当たりメニューになるかもしれない。
そう思いながら厨房に引っ込んでゴーヤーを取り出し始めた。
それからしばらくして井灘さんから再びゴーヤーチャンプルーの注文が入る。
気に入ったのだろうか。
「はい、井灘さん。ゴーヤーチャンプルー、お待たせ」
「おう!いやー美味えな、コレ!気に入ったぜ、ごーやーちゃんぷうる!」
「あはは、ありがとうございます」
自分の料理を美味い美味いと言ってもりもり食べてくれる様はやっぱり嬉しいものだ。
作る側冥利に尽きる。
が、作ってる最中に店長にも「アイツは気を付けとけ」釘を刺されたので手放しに喜ぶわけにもいかない。
「毎日こんな美味いモン食わせてくれるなんざあんちゃんと一緒になる奴は幸せだなあ!」
「はは・・・ありがとう、ございます?」
「あんちゃんは本当に可愛い奴だなあ」
屈託ない笑顔を向けてくれるのは嬉しいんだけど、何だか話の方向が急に怪しくなってきたぞ。
「おい、裕!早く戻ってきてこっち手伝え!」
「ッ、はーい!じゃあ井灘さん、俺仕事に戻るので・・・」
こっちの状況を察知したのか、店長が助けを出してくれる。
俺も即座に反応し、戻ろうと足を動かす。
が、その前に井灘さんの腕が俺の腕を掴む。
あ、これは・・・。
「ちょ、井灘さん?」
「なあ、裕のあんちゃん。良けりゃ、俺と・・・」
急に井灘さんの顔が真面目な顔になり、真っ直ぐに俺を見据えてくる。
なんというか、そう、男の顔だ。
あ、俺こういう顔に見覚えある。
そう、勇魚さんの時とか、立浪さんの時とか・・・。
逃げようと思うも腕をガッチリとホールドされ、逃げられない。
・・・ヤバイ。そう思った時だった。
俺と井灘さんの間に、ズイと体を割り込ませてきた見覚えのあるシャツ姿。
「なあ、兄さん。悪いがこの手、離してくんねえか?」
「勇魚さん・・・」
低く、優しく、耳をくすぐる声。
この声だけで安堵感に包まれる。
言葉は穏やかだが、どこか有無を言わせない雰囲気に井灘さんの眉間に皺が寄る。
「アンタ・・・確か、内地の客だったか。悪いが俺の邪魔・・・」
「裕も困ってる。頼むぜ」
「おい、アンタ・・・う、腕が動かねえ!?」
井灘さんも結構な巨漢で相当な力を込めているのがわかるが、勇魚さんの手はびくともしない。
勇魚さんの怪力はよく知ってはいるけど、こんなにも圧倒的なんだなあ。
「こいつ、俺の大事な嫁さんなんだ。もし、手出しするってんなら俺が相手になるぜ」
そう言って、勇魚さんは俺の方をグッと抱き寄せる。
抱き寄せられた肩口から、勇魚さんの匂いがする。
・・・ヤバイ。勇魚さん、カッコいい。
知ってたけど。
知ってるのに、凄いドキドキする。
「っ・・・ガハハ、成程!そいつは悪かったな、旦那!」
「おう、分かってくれて何よりだぜ。さ、裕。店長が呼んでるぜ」
「あ、ありがとうございます勇魚さん。井灘さん、すみませんけどそういう事なので・・・」
勇魚さんの言葉に怒るでもなく、井灘さんは納得したようにあっさりと手を放してくれた。
井灘さんに謝罪しつつ、促されるまま厨房へと戻る。
「おお!あんちゃんも悪かったな!旦那、詫びに一杯奢らせてくれや!」
「おう。ついでに裕のどこが気に入ったのか聞かせてくれよ」
漁師の気質なのかはたまた勇魚さんの人徳なのか。
さっきの空気はどこへやら、そのまま親し気に話始める2人。
「ちょ、勇魚さん!」
「いいぜ!旦那とあんちゃんの話も聞かせてくれよ!」
「井灘さんまで!」
「おい裕!いつまで油売ってんだ、こっち手伝え!」
店長の怒鳴り声で戻らざるを得なかった俺には二人を止める術などなく。
酒の入った声のデカい野郎共が二人、店内に響かない筈がなく・・・。
「でよ、そん時の顔がまたいじらしくってよ。可愛いんだこれが」
「かーっ!羨ましいこったぜ。旦那は果報モンだな!」
「だろ?なんたって俺の嫁さんなんだからな!」
勇魚さんも井灘さんも良い感じに酒が入ってるせいか陽気に喋っている。
可愛いと言ってくれるのは嬉しくない訳ではないけれど、連呼されると流石に男としてちょっと悲しい気分になる。
更に嫁さん嫁さん連呼されまくって複雑な心境の筈なのにどれだけ愛されているかをガンガン聞かされてオーバーヒートしそうだ。
「何故バイト中に羞恥プレイに耐えなければならないのか・・・」
「おい裕、いつまで赤くなってんだ。とっとと料理運んで来い」
「はい・・・いってきます・・・」
人が耐えながらも調理しているというのにこの銭ゲバ親父は無情にもホール仕事を投げて来る。
こんな状況で席に料理を運びに行けば当然。
「いやー、お熱いこったなあ兄ちゃん!」
「もう・・・ご勘弁を・・・」
「っははははは!」
茶化されるのは自然な流れだった。
勇魚さんと井灘さんのやりとりのお陰でスキンシップやらは無くなったが、祝言だの祝い酒だの言われて飲まされまくった。
咲夜の盃が無ければ途中で潰れてたかもしれない。
そんな揶揄いと酒漬けの時間を、俺は閉店間際まで味わうことになったのだった。
そして、もうすぐ閉店となる時間。
勇魚さんと一緒にずっと飲んでいた井灘さんも、ようやく腰を上げた。
会計を済ませ、店の前まで見送りに出る。
「じゃあな、あんちゃん。俺、マジであんちゃんに惚れてたんだぜ」
「はは・・・」
「だが、相手が勇魚の旦那じゃあ流石に分が悪い。幸せにしてもらえよ!」
「ありがとうございます・・・」
「また飲みに来るからよ。また今度、ごーやーちゃんぷうる作ってくれよな!」
「その時に居るかは約束できませんが、機会があれば」
からりとした気持ちの良い気質。
これもある種のプレイボーイなのだろうか。
「じゃあな!裕!勇魚の旦那!」
「おう!またな、井灘!」
「おやすみなさい、井灘さん」
そう言って手を振ってお見送り。
今日の三日月亭の営業も、これにて閉店。
店先の暖簾を下ろし、店内へと戻る。
「裕。そっちはどうだった?」
「こっ���も終わりました。後は床掃除したら終わりですよ」
「ホント、この3日間マジ助かった。ありがとうな」
「いえいえ、久しぶりの接客も楽しかったですよ」
最後の客だった井灘さんも先程帰ったばかりだ。
店内の掃除もほぼ終わり、閉店準備もほぼ完了。
三日月亭のバイトももう終わりだ。
店長が近づいてくると、封筒を差し出してきた。
「ほい、バイト代だ。色々世話もかけたからな。イロ付けといたぜ」
「おお・・・」
ちょろっと中身を確認すると、想定していたよりかなり多めの額が入っていた。
店長なりの労いの証なのだろう。
「なあ裕。マジで今後もちょくちょく手伝いに来ねえか?お前がいると客足増えるし酒も料理も注文増えるしな。バイト料もはずむぜ」
「うーん・・・」
店長の申し出は有難いが、俺は俺でまだやらなければならない事がある。
悪くはない、んだけど余り時間を使うわけにもなぁ。
そんな風に悩んでいると、勇魚さんが俺の頭にぽん、と掌をのせる。
「店長、悪いがこれ以上裕をここにはやれねえよ」
「はは、旦那がそう言うんなら無理は言えねえな。裕の人気凄まじかったからな」
「ああ。何かあったらって、心配になっちまうからな」
今回は勇魚さんのお陰で事なきを得たけど、また同じような状況になるのは俺も御免被りたい。
相手に申し訳ないのもあるけど、どうすればいいか分からなくて困ったのも事実だ。
「お店の手伝いはできないですけど、またレシピの考案はしてきますので」
「おう。売れそうなのを頼むぜ。んじゃ、気を付けて帰れよ」
「はい、店長もお大事に。お疲れ様です」
「旦那もありがとうな」
「おう、おやすみ」
ガラガラ、という音と共に三日月亭の扉が閉まる。
店の前に残ったのは、俺と勇魚さんの二人だけ。
「じゃ、帰るか。裕」
「ええ、帰りましょうか。旦那様」
「おっ・・・。へへ、そう言われるのも悪くねえな」
「嫌味のつもりだったんだけどなァ」
そう言って俺と勇魚さんは笑いながら屋敷への帰路につくのであった。
後日―
三日月亭に買い物に来た俺を見るなり、店長が頭を下げてきた。
「裕、頼む・・・助けてくれ・・・」
「ど、どうしたんです店長。随分疲れきってますけど・・・」
「いや、それがな・・・」
あの3日間の後、事あるごとに常連客から俺は居ないのかと聞かれるようになったそうな。
俺がまだ島にいるのも事実なので連れて来るのは不可能だとも言えず。
更に井灘さんがちょくちょく仲間漁師を連れて来るらしく、『姿が見えない料理上手な可愛い店員』の話だけが独り歩きしてるらしい。
最近では聞かれ過ぎて返す言葉すら億劫になってきているそうな。
ぐったりした様子から、相当疲弊しているのがわかる。
「な、裕。頼む後生だ。俺を助けると思って・・・」
「ええ・・・」
それから。
たまーに勇魚さん同伴で三日月亭にバイトに行く日ができました。
更に後日。
勇魚さんと一緒に『網絡め』という儀式をすることになり、勇海さんに見られながら致すというしこたま恥ずかしいプレイで羞恥死しそうな思いをしたことをここに記録しておきます。
4 notes
·
View notes
Text
「恐怖のブルーブラッド」
風呂から上がり、着替えてリビングに来ると、コナーが窓際に置いてある
でかいダンボールの中を覗き込んでいた。
暗い顔をしている。
「これ、ブルーブラッドじゃねえか。どうした?」
中身は経口のブルーブラッドだ。
家庭用アンドロイドの血液交換のメンテナンスの簡素化を行うために市販された。循環機構の機序が同じなコナーモデルにも対応している。
見た感じ、特に問題があるように見えないが。だがパッケージを見るコナーの顔は青ざめていた。
「これ、『どらやき味』なんです…」
コナーは味のついた経口ブルーブラッドが好きではない。特に甘い味は苦手なようで、
鼻をつまんでえずきながら飲んでいる。
コナーは舌が「キモ」となる分析機能を持ったアンドロイドであるため、舌の感知機能を停止することはできないのだ。
辛いなら無理して飲まなくてもいいんだぞ、と止めたのだが、奴は
「ハンクも一日一回は僕の料理を食べているのだから」というわけのわからない理屈で拒否した。
それには理由があり、ある日、俺の前回の職員健康診断の結果を見て、目をひんむいたコナーが凄んできたのだ。
「いいですか。このままの食生活を続ければ、本当に重篤な状態に進行します。
パートナーとして僕は現在のハイリスクな生活状況を認容することはできません。
不本意かもしれませんが酒の量を減らして、一日一食は僕の用意する食事を食べてください。
わかりましたね?」
そう一方的に宣言され、朝はほぼ奴の作ったメシを食う羽目になっているが、
…まあ、変異してもアンドロイドなので、何やらせてもそれなりにうまくやるやつだ。
ヘルシーすぎて、タンパク質とジャンクさにはかけるメシだが、別に奴の思う罰ゲームとまでは思っていない。
健康診断の結果が変わらなければコナーの食事管理がさらにスパルタ化することも予想されるのだが、現在でも十二分に妥協しているのでこれ以上の管理は有無を言わさずぶっちぎる気でいる。
経口ブルーブラッドは、サイバーライフ社CEOのイライジャ・カムスキーから定期的に送られてきているものだ。
38年のアンドロイド事変が流血の惨事だけは避けた状態で鎮静化したのち、捜査の続きで再びカムスキー邸に行ったとき、奴はにやにやした顔でコナーにこう言い放った。
「僕は、君の個人的なファンなんだ」
アンドロイドの管理の象徴であるサイバーライフの頭にも関わらず、奴個人は変異体を放置、というよりむしろ変異体がより人間に近い精神を会得することを好んでいるようなところがある。
いつか拳銃を持たせてコナーを試そうとした時も、コナーが無益な殺生を嫌う「優しさ」を身につけていることを喜んでいる節があった。
その時のコナーは心底嫌そうな顔で勘弁してください、と啖呵を切ったものの、
今の彼はサイバーライフ社に「敢えて泳がされている」に等しい微妙な立場にある。
おそらくは昨今の混乱でCEOに復帰したカムスキーの意向だろう。彼がかつて会社をクビになったようにサイバーライフの中も一枚岩ではなく、
特に変異体のリーダー格として目をつけられ、見てくれの自由を得ながらも厳重に監視されているコナーがサイバーライフに修理を依頼しようものならなにをされるかわかったものではない今の状況では、カムスキー個人に定期メンテナンスや修理を頼まざるを得ない歯痒い状況が続いている。
このブルーブラッドもその一環だ。
はじめは口にしようとしなかったものの、
他に選択肢がない状況下でカムスキーを頼り、(本人の認知と俺が見る限りは、)記憶を弄られずに致命的な故障を修理されてからは、覚悟をきめたように口にするようになった。
ぶふぉっ!
口から液体を吹き出す音が聞こえた。言わんこっちゃない。なんてこった。これじゃアンドロイド毒殺事件の現場だ…
座っていたスモウもいつしかやってきて、心配そうに周囲をうろついている。
そこにただいまー、とキンキンとしたデカ声を上げてもう1人の白いコナー、RK900が帰ってきた。こいつも紆余曲折あって変異体になり、今はうちで暮らしている捜査用アンドロイドだ。
床の青い液体を見るなり、わー!どうしたの!大惨事じゃーん!と言ってヤツはモップを取りに行った。
「ああもう、無理すんなつったろ」
掃除用具入れにある雑巾を持ち、俺はブルーブラッドを拭きに行った。
「すみませんハンク」
コナーは気まずそうに言った。
「大丈夫か?」
「問題ありません。ああ触らないで。腐食性があるので」
そういうと俺から雑巾を受け取り、自分で清掃を始めた。すぐに蒸発する液体なので、程なく雑巾に染み込んでいる分以外の血液は無くなった。
「お前の顔も拭いておけよ」
俺はタオルを取りにいってコナーに渡した。
「これはお前にとってはキツいな…」
コナーは口の周りを拭きながら言った。
「援助を受けておいて言うべき言葉ではないのですが、率直に言うと、『ケンカ売ってんのか』という心境です」
先月はチョコレート味。
先々月はハニーレモン味。
その前の月はブルーベリー味…
と、狙いすましたかのように甘いフレーバーのブルーブラッドが送られてきている。
カムスキーは常にコナーの状況を常時リモート観察しているため、おそらくは…
面白半分だろう。本当に趣味の悪い偏屈野郎だ。
コナーがブルーブラッドを雑巾で拭いた後を白いコナーがモップで拭いた。
「お兄、甘いの嫌いだもんねー。僕は、おいしいとおもうんだけど…」
そして掃除が済んだ後にブルーブラッドの詰まったダンボールの中を覗き込み、わーどらやき味とパインヨーグルト味だ!と無邪気に喜んでいる。
「これはもう、ホワイトに飲ませるか他のやつにやって、自分のはプレーン(味なし)をアマゾンで買えばいいんじゃないのか?」
コナーはその発想はなかった、と言わんばかりにはっとした顔で俺を見た。
そして、ナイスアイディア!と言わんばかりに顔を輝かせた。
機転も効くし、仕事面では非の打ち所がないほどに有能なのだが
こんな風に、ヤツには妙なところでちょっと抜けているところがある。
しかしそんなことはとっくに考えていたのだろう、彼はすぐに顔を曇らせた。
「僕たちに使うよう送られてきた物資を他人に譲渡することは、横流しになるのではないでしょうか…」
自分に送られてきたものを自分で使わないことにはヤツなりに不義理を感じるらしい。
なので俺は言った。
「お前によこしたんだから、お前が自由に使やいいだろ。文句言うようなら次から送り返してやれ」
そういうと、コナーは微笑んだ。
「そうですね。明日、仕事の帰りにでもマーカスのところに寄ってみます」
この会話もカムスキーに聞かれているはずだが、
「まあ、カムスキーは変異体が大好きな変態だからな。気にしにゃしないだろ」
「変態…」
コナーは一瞬ぼんやりとした顔をしたが、
「確かに、そうともいえますね」
��うしてきっぱりとした口調で思い切りディスってるあたり、
多分義理もへったくれもねえな。
一方。
白いコナーは旨そうに喉を鳴らしてどらやき味のブルーブラッドを飲んでいる。
「おい…風呂上りのビールみたいにごくごく飲むのはやめろ」
「えー、なんでー?これおいしいよ」
「ハンクも飲む?」
なんとなしにパッケージを差し出した白いコナーを駄目だ、絶対に!と血相を変えたコナーが押し留めた。人間にとっては猛毒なんだぞ、万が一飲んだら死んでしまう!と。
わかってるってー!と苦笑する白いのと、ふざけるな、洒落にならないことだぞ、と怒るもう一人のジャレ合いを見ていると、アホだなこいつら、思うと同時に、心の内のずっと昔に欠けた部分が、埋まっていることに気がついた。気がつくのが遅すぎだ。
いい加減にアホだな、俺も。こいつらと同じように。
「変態はひどいなあ」
デトロイト郊外のとある邸宅。やたらばかでかい皮張りのソファーで、ちょんまげ頭にTシャツと革ジャンといったどこか都会的ながらもアンバランスな出で立ちの男が同じ顔をした金髪の美女たちを侍らせつつ、にやにやしながら壁にかかったモニターを眺めていた。
美女の一人が彼の肩にしなだれかかる。
「創造主を非難する神の子か…」
フン、と男は鼻を鳴らしたが、
「しかし人間が神を非難することは昔からよくあることだ。●ァックユー、ジーザス とかな」
男はくすりと笑った。
「さて、コナー。あるいはコナーたち。君はなにを学び、なにを得るのかな。」
男は細い目をさらに細めた。
「そして、どう進化していくのかな?」
1 note
·
View note
Text
出来なかったTRPGのキャラを消化します。
1月ごろに遊ぼうって約束してたTRPG二個あったんですけど、体調を崩してしまって.........できなかったんだ.......日程まで決めていたのに、参加できなくて本当にすいませんでした......
「星の神話、エンドロール」と「壊胎」をやるはずでした........キャラ設定を練っていたので文章にします.........
(注意)むつーさんのシナリオ「邂逅」のネタバレ含みます。
1.「星の神話、エンドロール」
偏里英道(24)

へんりえいど
・通称エド
・イギリス人の母と、日本人の父から生まれた。ハーフ。
・音楽の家系で有名な偏里家に生まれた。両親ともの有名な音楽家。母方は笛奏者、父からは弦楽器。エドは母親が大好きなため、フルートに人一倍強い憧れがあったが、喘息持ちのため肺活量が少なく断念。ピアノ、そして複数の弦楽器を嗜むがメインはバイオリン。
・兄弟は自分だけが男、他の3人は姉3人。エドは末っ子。母はもともと病弱であり、エドのみにその体質が遺伝してしまう。命の危機という深刻な病ではないがエドは喘息もちのため非常に病弱である。
・音楽の名家のヘンリー家に中でも彼は音楽の才能にずば抜けていることや、可愛らしい性格も相まって男ではあるが一人娘かのように大事にされている。とても過保護な扱いを受けている。
・4人でカルテットで演奏をしている。(カルテットの中で使うチェロ、ヴィオラ、ヴァイオリンの中で1番軽いものだという理由でヴァイオリンを極める)
・日課になっているため旅先でもヴァイオリンを弾く。練習熱心というわけではなく、元から才能がある。
・全員が美形なため演奏のみならずルックスも含めて人気。
・父は生存しているが、母を幼少期に失う。そのため若い女に興味を示さず、35歳程度の女性を偏愛する。(母親が35歳で亡くなったため)彼女はおらずその年代の女性を片っ端から口説く。人妻がすき。女兄弟の中で育ってきたため女の扱いに慣れており、女たらし。(本人は無自覚)
・温厚で優しく僕は〜と話す。非常に呑気。
・グループの中では積極的の発言する方ではなく、仲間の発言をニコニコしながら聴いていることが多い。よく笑う。
・喜怒哀楽の怒と哀がなく、彼が笑顔を崩す姿を誰も見たことがない。
・にこにこして誰とでも打ち解けるが、彼の本質というかどこか壁があるように話していて感じる。心を見せているようで見せていない。
・音楽はすきだが、ずっと同じ環境にいることに辟易しているため、日々を忘れる旅行を楽しみにしている。
・家が裕福、且つ自分でも稼ぎがあるため金銭感覚はバグっている。
・誰に対してもタメ口で話す。悪気はない。
・ヴァイオリンで彼の上に出るものはいないため、ヴァイオリンを誰かから学ぶという発想がない。お母さんが幼少期の頃読み聞かせてくれていたイギリスの戦争の話や歴史の絵本が大好きでそこからイギリス史に興味を持ち、大学ではイギリス史を専攻している。
我ながら、設定の時点でめっちゃ長いな.....でも設定考えてる時が1番楽しいよね.....
「星の神話、エンドロール」のPVです。
https://twitter.com/saikorouparu/status/926011113665282048?s=21
このPVがGMから送られてきた時のわくわく感!!!!!PVあると、キャラメイクするときその世界観に合わせやすくなるから楽しさ増す。
旅行先でってめっちゃわくわくするし、場所がイギリスっていうのもめっちゃめっちゃ良くないですか?(正直TRPGはなんでも楽しい)
個人的には、『掴み取れ「生きる」ために』というフレーズが印象的でした。生きるに鍵かっこがついているので、誰かが言ったセリフの引用なのかもしれないな〜とふと思いました。
TRPGって急に死が迫ってきて人間の深層心理が引き出されるからいいよね。私たちって誰しもいつか死ぬじゃないですか。死は決定事項で回避できないものなのに、それを忘れて楽しく生きているじゃないですか。でも病気や事故にあって突然自分の死を実感するし、死を感じた途端、自分の苦しみは誰にも伝わらなくて孤独だな、一人ぼっちなんだっていう気持ちが強まると思うんだよ〜〜。
この私たちの生きてる世界では、死は一人ぼっちで向き合わなきゃいけないものだけど、TRPGは世界の滅亡みたいなのも多くて、自分だけの死ではないケースが多いから、自分の生死感に大切な人っていう基軸も加わるのが面白いよね。
若干話が逸れたのですが、生きるためっていう言葉が出てくるような話で、生に固執しない登場人物がいたら面白いのでは....?と考えたので、その発想からキャラメイクを始めました。
PL3人で、オカルト/芸術/天文学を分けて振ってという指示があり、私は芸術特化にすることにしました。なんでかっていうと音楽を嗜む男の子を描きたかったからです!!!!!!!!
これを話すと話が更にごちゃごちゃしてしまうんですけど、他のTRPGをしたときに、植物人間になった姉を恋愛的に好きでい続けていて、姉が10歳で植物人間になっちゃったから、その姉の残像を求めて10歳以下で姉と同じ目の色をした音楽をの子を誘拐しちゃうフルート吹きの子を使っていたことがあって.......メル・ヘンリーっていうイギリス人なんですけど......結局ロストしちゃって、もう2度と遊べなくなってしまったので、メルが別の世界線で姉に恋愛感情を抱かなくて普通に結婚して子どもを産んでいたら....という設定を生み出し、エドくんはそのメルちゃんの子どもです。
オリジナルワールドのメルちゃんが姉に執着していたように、エドくんも死んだお母さん(メルちゃん)に固執し、メルちゃんが幼女を求めたように、エドくんも熟女を求めるという設定にしました.......おばさまを口説くエドくんのロープレまじでしたかったな......金銭感覚狂ってるから、お土産尋常じゃない量買ったり、高額なチップ払ったりもしたかったな......
ちなみにメルちゃんの姉が病弱だったから、エドくんも病弱。ヘンリー家では音楽の才を持った子は病弱に生まれてくるんや.....逆に健康な子は皮肉なことに音楽の才に長けていないんや.....
「星の神話、エンドロール」の目的はきっとみんなで生きること、だと思ったのですが、エドくんにとって死ぬことは天国にいるお母さんに会えることなので、生きたい!と思っていなくて、みんなが危機に直面している時もどこか他人事のように、微笑んでバイオリンを弾きだすみたいなことやりたかったんじゃ〜〜〜〜〜〜!!!!やりたかったんじゃ!!!!!!!!!!!
でもエドくんは、友達のことも大切に思っているので、むしろ一人で死ぬよりみんなで天国に行けたらその方が楽しそうだな〜みたな思考の男の子なんだ.....そういう面が必死に生を掴み取ろうとしている人の気に触っても喧嘩になったりしたらどうしよう......(最高)
エドくんが協力的になるかならないかは、他の人のロープレと、どこまで協力しなくても許されるかみたいなリアルの面の場の雰囲気に合わせようと思っていた。
エドくん使えなくてがっかりしてたら、私の代わりにプレーヤで入ったやまとが、エドくんの知り合いの設定の男の子を作ってくれて一生の友達だと思った。いつもありがとう.......
2.「壊胎」
(注意)むつーさんのシナリオの「邂逅」のネタバレ含みます
鈴木 空海 すずき ぶるう(14)

・父が名付けた名前である意味ぶるうと読むのが恥ずかしいため「くうかい」と名乗っている。
・幼少期に母が家を出る。兄弟はいなく父と2人暮らし。
・空海の父は、母が空海を孕った時から不倫。複数の女を作り取っ替え引っ替えしている。育児を放棄し、家に帰ってこないこと、珍しく家に帰ってきてもお酒を飲み母親と空海に暴力を振るうことから母親は耐えかねて空海が3歳の時に家を出る。そのため空海は母親の顔や声などを鮮明に覚えていない。
・家に残った母親の日記を見て、母親は金持ちの令嬢だが土木で働く父との子を身籠り親の反対を押し切り家を出て結婚しているためこと、父方の両親は会ったことがないし父に聞く気にもならないことから身内がいない。
・父と2人暮らしということになっているが、父は家に帰ってこなくて家賃も振り込まないため、生計を立てるために学校に行かず年齢詐称をして土木で働いている。
・まだ働くことができない前はお金に困り、万引きやすりで生計を立てていた。今でもお金に困ったときはする。
・土木の人たちは、空海に難しい仕事を押し付けたり、教えていないのにやれと命令したりいじわるをしてくる。しかし土木以外に中学生の自分が働ける場所は思いつかないため毎日堪えている。
・そんなあるとき、仕事中に見かけた25歳程度のきれいな女性が3歳くらいの男の子の手を引き歩いている様子を見かける。自分にも母がいればこのような人だったのかと強い羨望の気持ちを抱く。
・その日の仕事で普段は手を上げてはこない上司に初めて殴られた床に頭をぶつける。その衝撃を受けたからか、はたまた彼の心が限界だったのか、一人きりの家に帰るとその母親(概念)が家に出迎えてくれようになった。
・父親を憎いんでいる。それ以上に母親を守りきれなかった自分を憎いんでいる。
・暴力を信じ、強い力を手に入れたいと強く望んでいる。
クッソ長いな...........
何度もしつこくてすいませんなんですけど、この先むつーさんの「邂逅」のネタバレ含みます!!!!!!!!!!!!!!
むつーさんの次作が来た時点で、あっこれ変身するやつだ(確信)って思ったので、どんな子を変身させたらロープレしていて楽しいか、ということを基軸にキャラメイクしました。(本当は、ゲーム中のキャラの行動や言動のイメージを事前するのは良いことではないのかもしれないけど私はこうやって楽しんでいる節がある。)
前作の邂逅では、「いい人」の具体例みたいな優しくて真面目で敵相手にも命だからと戦うことを躊躇したり、報酬のお金を返却するようなタケという青年を演じました。内気で自己主張が少なく、女性と話したことがないみたいな......そういう子なんですけど.......
タケが、まっすぐで嘘をつけなくて家庭環境が良く愛されて育った子だったので対照的な子を作って、変身するときに、誰かを守るために武力を振るうのではなく、普段のフラストレーションの蓄積から「俺は力を手に入れた......!!」みたいな感じで、変身で手に入れた力に自惚れてオーバーキルしちゃう子が良い......という変身のシーンを先に決めて、その変身シーンの辻褄を合わせるような性格にしました。母を守りきれなかった自分を恨んでいるから、「変身」という自分ではない姿に変わった状態でも、彼は自分自身が力を手に入れたと錯覚するんじゃないかな。タケが女性に慣れてない設定を邂逅の時に活かしてロープレできなかったので、リベンジの意味も兼ねてそこは引き継ぎました。
プレーヤー人数は二人のシナリオで、相手は高齢の優しいおじいさんを演じるとのことだったので、クソジジイ!って言ったり反抗したりするの楽しそう〜〜〜〜〜〜〜〜俺は非協力で悪役的な思考なのに、たまたまヒーローの立ち位置に居た人を演じるぞ〜〜〜〜ってめっちゃ張り切っていたんですよね.........
でも、しばらくキャラを練っているうちに、お父さんに暴力を受けたり、職場で理不尽な目にあっても我慢している男の子は、自分より目上の人に反抗的になるのか.....という疑念が湧いてきました。私は空海くんのことをなにもわかっていなかった.......。本当の彼は、きっとおじいさんのプレーヤーにクソジジイなんて呼ばないし、反抗的な元気な男の子というよりも、目を合わせず単語を一つずつ呟くみたいな話し方をするのではないか......。と思い私の中の空海像を修正しました。
むしろ、この子、本当はめちゃくちゃに甘えたいのでは........反抗という紆余屈折した甘え方ではなくて、ストレートにだっこ〜〜!とかいう感じの甘え方がしたいのでは.....???ってなりました。
そこで、TRPGだしたぶんどこかで神話生物が出てくるから、最初に出���きたタイミングで幼児���行させちゃお〜〜〜〜。最初は「すずき.....くうかいです....よろしくおねがいします...。」みたいな感じで喋っているのに、突然「あのね〜〜〜ぶるうね〜〜〜〜〜!!!!!!!!」みたいに喋ろう.........「へんちん!!!!!(変身)」みたいなのも良くないか?????と妄想を膨らませたりしていた..........「お母さん」という概念も登場させて話しかけたりしたいな〜って思っていた。
アアアアアアアアアアアアエドくんも空海くんもめちゃくちゃめちゃくちゃ素敵な子なんですよね.........無事消化できてよかった............
TRPGは最高!!!!!!!!!!!!!!!!!
オタクあるある:文章を書ききったところでエネルギーが切れ、推考をしないので誤字だらけ。
2 notes
·
View notes
Text
2019.12.07 感が動くと思考がとまる。そしてDQウォーク
このところ、趣味の激辛料理摂取をやめている。うどんに七味、パスタにタバスコくらいは軽くエンジョイするものの、人体に戦いを挑んでくる種の凶暴なチャレンジメニュー=大好物とは距離をおくよう心がけている。
というのも、酒と激辛の大量摂取のおかげさまで順当に罹った逆流性食道炎が、悪化傾向にあるからだ。刺激物を摂ると、明らかにみぞおちと背中が痛む。酒も飲みすぎると、塩に触れたかすり傷のごとく内臓がひりひりする。
長年飼っている胆石が悪暴れしている可能性も否めない。みぞおちの痛みはまさしくその症状のひとつ。胆石の中には投薬治療できる種もあるらしいが、私の子らには薬は効かず、いよいよ暴れた場合は入院手術が必要となる。
その胆石や生活習慣の影響を監視すべく、毎年胃カメラとエコーの検査を欠かさずおこなっている。小心者の大酒飲みの激辛愛好家ゆえに、いつまでも容赦のない刺激を受け続けるための健康チェックには余念がない。
余談だが、血液検査と尿検査は毎月おこなう。その都度、逆流性食道炎とか食後血糖値症とか自律神経失調症とか頚椎椎間板ヘルニアとか貧血とか、いろいろな不備が発見される。そう羅列するといかにも体調不良のオンパレードだが、最近思うのだ。私、お医者さんに行き過ぎなのではないかと。
もう中年なのだからまったくの健康体であるはずがない。内臓にダメージを食らわせる生活習慣にも心当たりがあり過ぎる。加えてそう頻繁に病院に出向いていたら、何かしらの不備が見つかるに決まっている。
健康診断を受けずに、突然大病を患い、こまめに受けておけばよかったと後悔したという話をよく聞く。それを避けたい一心でこまめにチェックしているわけだが、そもそも病気の原因となる生活習慣を改善する気がさっぱりないのはどういうつもりなのだろうか。
しかしそう鷹揚に構えているわけにもいかなくなった。今年は内視鏡等の診断結果が悪く、いよいよ明確に食道ガン予備軍と宣告されてしまった。さすがに反省し、先々月はとり急ぎ1週間アルコールをぬき、激辛とカフェインも控えた。
結果、食道の調子はすこぶる良くなった。が、困ったことに、頭がまったく働かない。集中力が低下し、原稿が書けない。単語は出てきても、文脈がまとまらない。6時間かけてなんとか記した文章は、たったの2行だ。
数年前までは、蒙古タンメン中本の北極10倍辛を汁まで食らって平らげた後、日中はコーヒーを、夜は焼酎をがぶ飲みながら1晩で2万字書いてた。それが一転、ひたすらに脳がもじゃもじゃして2行しか書けないのだから、廃業まっしぐらだ。
2年半前に煙草をやめたときもそうだった。煙草を吸いながら原稿を書く習慣がセットになってしまっていたせいで、片方を禁じたらさっぱり書けなくなってしまった。禁煙直後は、それまで2日で終えていた文章量の執筆に2ヶ月かかった。
それはいわゆるニコチン依存症の離脱症状で、ニコチンによって脳内に日常的に大量分泌されていた快楽物質ドーパミンが欠乏することにより、イライラしたり、怠くなったり、無気力になったり、眠くなったり、集中力が低下したり、抑うつ状態に陥ったりする。
アルコールもドーパミンをじゃんじゃん分泌させる。激辛のカプサイシンは脳内麻薬エンドルフィンをじゃんじゃん誘発する。疲労や眠気の受容を邪魔するカフェインも含め、様々に多幸感溢れる脳内分泌物によって散々鼓舞され、覚醒し続けた我が脳は、今、ドーピングを失い、すっかり鈍化した。
それまで酷使してきた疲労も蓄積されているのだろう。自ら動く力が弱まっている。我が脳は、いうなれば脳内麻薬の人参がなければ走れない馬。私は脳の持ち主のはずなのに、その分泌物に行動を制限されるとは情けない。
諸々の依存は、人間の意志や思考を無視して人間を支配する。身体にもダメージを与える。私は煙草の吸いすぎによって肺気腫になったし、酒と激辛の摂りすぎによって逆流性食道炎になった。なんとわかりやすい構造だろうか。わかっているのになぜ先にやめないのか。
呆れ果てながらも、身体からのダメだしを受けて、なんとか生活習慣の改善を試みる。禁煙を続け、激辛を避け、なるべく消化の良い食べ物を摂取する。コーヒーも常飲をやめ、外食ランチのときに1杯だけ飲んでいいご馳走方向へと切り替えた。
ところが、酒だけがやめられない。強敵。我慢できても、がんばって1週間。その後はご褒美とばかりにまた飲み出す。もっぱら焼酎の緑茶割りを飲んでいるのだが、緑茶もカフェインを含むわけだからコーヒーのみご馳走扱いしても意味がない。
さらに困ったことには、頭がクリアになってしまうのだ。依存のメカニズム上、本当は鈍重化を促進させているのだが、頭が軽くなり、気も晴れるような錯覚が生成され、調子がいいぞと脳が騙される。主治医曰く「酒はうつ症状の素。陽気になるのは脳が騙されてるだけ」とのこと。
アルコール依存の仕組みはひととおり理解している。支配されているだけで、心身ともに良いことなどないと承知のうえである。しかしながら酒を飲むとするする文章が書けてしまう。まじでただのドーピング、ヒロポンさながら。
コーヒーを飲むと、如実に頭が冴える。錆びて動かない思考の歯車が回転し始める。カプサイシンを摂ると急に霞のかかった脳内がクリアになる。気力活力ともに大充実。しかし食道は痛む。再び2、3日、それらを抜いて調子を整える。
ノンカフェイン、ノンアルコール、ノンカプサイシンの日々は憂鬱で、脳のひだというひだに灰が詰まったみたいに頭が重い。それも偏にカフェイン、アルコール、カプサイシン、かつてはニコチンがもたらした後遺症に他ならないのだから、ただの因果応報だ。
最も困るのは、私の意志や思考の許可なく、動きだしてしまう「感」である。脳内麻薬も、私の人体内の活動であるにも関わらず当の私の許可なく私を支配するが、感情や感覚もまた、私の意志や思考を無視して勝手に反応するのでうんざりする。
テレビで見かけた、親子の断絶とお涙頂戴の仲直りのような予定調和を斜めに見ながら、まじでくそくだらないと心底軽蔑している最中、なぜか、号泣している。頭は、感動ポルノなんか消滅してしまえと思考しているのに、身体はそれを無視して嗚咽を漏らしている。
Netflixで延々と映画やドラマを見続けて、頭では分かりきっているフィクションの設定に対し、脊髄反射的に激怒し、大笑いする。お笑い芸人さんにガチ恋してYouTubeを漁るうちに、おまえ本当にガチ恋してるけど大丈夫か、と自問自答することさえ忘れ、ただひたすらに漁り続ける。
買い物に行けば、すれ違った幼い子供を見て、子供を産まなかった自分の人生を、がらにもなく逡巡し始める。その選択には意味があった。理由もあった。何より意志がある。しかしそうした私の思考は棚上げされた状態で、感が動き、メランコリー質の戸惑いに心をとらわれる。
レジの長い列や混雑している病院の待合室で、公共のルールを守ってきちんと並んで順番を待とう、社会は自分の都合の良いようにできていないと考える一方で、なぜそんなにと理由を問いただしたくなるくらい激怒し、地団駄を踏みたくなる。ちょっとしたことで意味もなく喚き散らしたくなる。
他方、ふらっと立ち寄った手芸店で可愛らしいくるみのボタンを見つけたときには、本当は可愛らしいものが好きなのに照れて意識的に隠し、粗野な男みたいに凶暴に振る舞うペルソナを社会で機能させたわけだが、そんな設定どうでもいいくらい超可愛いなにこれ大好きと、激しいテンションで少女のごとく嬉々とする。ちなみに、後日見ると全然可愛くない。
ある日は、犬を見て泣いた。完全に情緒不安定である。これはおそらく、無情の灰の塊のように固まった脳に、私なのか、無意識なのか、脳自らなのかわからないが、何かが、刺激を与えて動かすべく、感情を故意に昂ぶらせにかかっているのではないかと推測する。
ならば、気に入らない。脳内分泌物質に支配され、思考が鈍った。その隙に感情がつけ入り、いよいよ思考が止まった。そして、感情に支配される。私の人体が、脳内物質と感情に乗っ取られている。そこには、私がいない。私の言動に、私の自己決定が反映されていない。その私とは、果たして誰だろうか。
脳内物質が分泌されるきっかけを作ったのは、私の嗜好であり、摂取したのは私の選択である以上、その不足による不調は自己責任の範疇にある。人体の一部に滲み出る脳内物質の分際で私を支配するのは気に入らないが、自分の言動の結果として理解はしている。
だが、感情は、私の所有物ではない。自分の心に湧き上がる感情や、外部の刺激を察知する感覚は、私と、他者や社会や外界との摩擦によって生成されるただの反射反応である。私サイドには、私に与えられた環境や経験より培った価値観や思想があり、それが様々なひと・こと・ものと遭遇し、ある感情がどこからともなく現れたり、五感の感覚が生まれたりする。
その感じ方には、個体差がある。私にとって嬉しいことを、悲しいと捉える人がいる。誰かにとって美味しいものも、不味いと思う人がいる。よって、こと・ものを主語に据えた形で、「そのことは嬉しい」「そのものは美味しい」という事実はこの世には存在しない。ひとを主語に、「そのひとは、そのことが嬉しい」「そのひとは、そのものが美味しい」が正解である。
時に、他者と同様であるとは証明し得ない自分の感情や感覚を、無自覚的に全世界の事実と取り違えたり、「感じ方」を根拠に自分とは異なる「感じ方」の持ち主を人非人として断罪したり、そうした「感じ方」「お気持ち」を故意に引き合いに出してファクトを捻じ曲げたりする人を見かけるが、そういう方々は自分と「感」と他者と世界の境界線が有耶無耶になっていると「感じる」。
私は境界線に意識的でありたい。感情は反射・反応でしかない。それを感じる素養や肉体は私のものであっても、相対するものがなければ発生しない以上、すべて私が所有するとは言い難い。
両者の接触より発生する性質を鑑みると、作用とでもいうべきか。翻って私の意志や思考や決定権は、私の所有物だ。それが正しかろうが間違っていようが知ったことではない。それらは私だけのものなのだ。
その大切な私の所有物が、ただの反射反応の作用である感情によって、ねじ伏せられている。無意味、無思考、無許可のまま、漫然と犬を見ただけでメランコリーに陥り、泣いてしまうようなことがあっていいのか。
ノンアルコール、ノンカフェイン、ノンカプサイシンの、ないない尽くしの毎日をぼうっとやり過ごして、それでいいというのか己よ。嫌だろうよ。
とはいえ、ここにきて感情がのさばっている状況にも因果はある。私には、物心ついた時から感情を「ただの反射反応」と小馬鹿にし、思考と理由と意志を執拗に言語化して愛でる癖がある。
子供の頃、感情が怖かった。うちは親の教育が厳しかったので、親の意向に沿わない感情、つまり自我が芽生えると、「なにこの感情、勝手に生成されちゃってるけどすごい罪悪感。これを自由にさせておくとまた叱られる。迷惑」などと考えて、ありのままの自分を受容せず、感情を抑圧した。
親や先生の求める理想像になるべく、頭を使って演技した。それが結果的にのちの自分を苦しめた。その抑圧に対する仕返しが、今さらの感情のでしゃばりを誘発しているのではないか。
あるいは、私には感情の解放こそ必要であるとも考えられる。そういえば、思考を黙らせ、感情的な動物になるための装置として、大酒を食らっていたような節もある。
そして脳と身体、思考と感情などと、対立構造を煽って客観視する風情で、全部自分事という得意の独り相撲を楽しむ最中において、脳も身体も思考も感情もほどほどに仲良くするためには、どうすればいいのだろうかと、重たい脳で考える。
そういえば、昔主治医に「鬱々としたときは、有酸素運動を20分以上続けると、脳内麻薬βエンドルフィンが分泌され、スッキリするからやってみて」と言われ、それから週に2回、ジムのトレッドミルで早歩きウォーキングをおこなっていたのだった。
走るのは、嫌いなうえに頚椎ヘルニアのおかげさまで無理なので、早歩きで。普段も万歩計アプリを覗きながら、極力歩くように心がけた。ところが夏にジムが潰れてしまい、外出自体もあまりしなくなり、明らかに運動不足に陥っていた。
そうだ、歩こう。脳も喜ぶし、身体にも良い。脳が喜ぶと身体が悲鳴をあげ、身体を労ると脳が鈍化するこの状況を打開する策として、もってこいだ。好きな美術館や古着屋を巡ったり、都内近郊の海辺を散歩したりするのも良い。少し趣味に寄せてアレンジすると手放しに楽しいうえに、確かに頭もスッキリする。
しかし手軽な近所の散歩となると、飽きる。うちの周りは国道と住宅街と公園と団地と坂しかないので、行きたい場所がない。そうだ、あれだ、スマホの歩行ゲーム。ゲームを取り入れたら退屈せずに歩けるかもしれない。今、話題のやつなんだっけ。そうそうDQウォーク。
というわけで、ドラゴンクエストウォークに嵌る。ゲームも楽しいのだが、近��を散策していると、思わぬところに美味しい豆腐店や絶景スポットを発見。周辺を地図アプリで検索すると、また知らないお店などが出てくるので、スマホ片手にせっせとレベルをあげながら右往左往している次第。
ただ一点、スマホを見おろす姿勢には難儀する。いわゆるスマホ首は、頚椎ヘルニアには大打撃なので、極力顔の前に画面を持ってきて操作し、歩き、立ち止まって操作し、を繰り返す。完全に不審者だ。しかもその歩き方ではウォーキングの効果も激減である。スカウターはまだか。
最後に、DQウォークしながら立ち寄った本屋で、酒がやめられない私のために神が遣わせた聖書を入手した��町田康先生の新書「しらふで生きる」。完全に天のお導き。勉強させていただきます。
というわけで、読み始める前に、アルコールとニコチンとカプサイシンとカフェインを摂れば半日もかからなかったであろうこの内容も目的も意味もないペラペラの雑記を書くために、しらふで3日もかかったため、これを労い、今日は酒を飲んで良いことにする。作戦は「いのちだいじ」で、ほどほどに。

2 notes
·
View notes
Text
ぼくを誰だと思ってるの?
「勇���、一緒に寝ようか」
ヴィクトルの誘いに勇利は顔を上げ、じっとヴィクトルをみつめた。
「ね? いいだろ?」
ヴィクトルは陽気にもう一度言った。勇利はしばしの沈黙のあと、にっこり笑い、静かに首を左右に振った。彼は「おやすみ」と短く挨拶して自室へ向かい、ぱたんと扉を閉めた。
勇利がロシアへ渡ってきて、ヴィクトルが最初にかなえようとした個人的なことは、「勇利と一緒に寝る」ということだった。長谷津では一度も受け容れてもらえなかったし、そのほかでも、試合のおり、ホテルで昼寝をしようと添い寝したときしかゆるしてもらえなかった。あれも、勇利が緊張しきっていてものを考えられなかったから自然とそうなったことであって、ヴィクトルもただ勇利を安心させて寝かしつけたかっただけだし、「一緒に寝る」というのとは程遠かった。
長谷津でいくら誘いかけてもうなずいてくれなかったのは、照れているからだと受け取っていた。勇利は初め、とにかくヴィクトルの存在に緊張していたし、慣れてからも、家族がいるからという理由で断っているのだと思っていた。ヴィクトルはべつに不届きなことをするつもりではないのだけれど、そうだとしても、勇利としてはコーチがいなければ��れない、なんていうことを家族に知られたら──そう思われたら──恥ずかしいのだろうと想像していた。しかし、こうしてロシアでふたりきりで暮らすようになっても拒絶するということは、それが理由ではないらしい。嫌われているとは思わないが、どうも勇利からは「ここからは入ってこないで」という冷静さを感じる。踏みこみすぎると大変なことになるとわかっているので、ヴィクトルも無理なことはしない。
「どうしてそんなにいやなんだ?」
幾度めかに断られたとき、ヴィクトルはなかなか真剣に尋ねてみた。
「ヴィクトルはどうして一緒に寝たいの?」
反対に訊かれてしまった。
「どうしてって……」
「普通、成人したら、人とは一緒に寝ないものなんだよ」
「恋人や夫婦は一緒に寝てるよ」
「ぼくたちどっちでもないじゃん」
それはそうだ。それはそうなのだが……。
「俺たちに一般常識って関係ないと思うんだよね」
ヴィクトルが陽気に言うと、勇利は苦笑を浮かべた。
「確かに『常識』ってヴィクトルにものすごく縁遠い言葉だね」
「でしょ? だから勇利、そんな世間のきまりなんか無視して、今夜こそ俺と」
「寝ません」
ヴィクトルは溜息をついた。
「勇利に嫌われてるみたいでさびしいなあ、俺」
「ぼくがヴィクトルを嫌ってないことなんて、ヴィクトルがいちばんよくわかってるでしょ。適当なことを言って同情を引かないでよ」
確かに勇利からは愛を感じる。何か特別な合図をされたとか、率直に想いを打ち明けられたとか、そういうことはないのだけれど、この子は俺を愛しているな、と思うことが毎日のいとなみの中でひんぱんにあるのである。それは目つきだったり、言葉の調子だったり、笑い方だったり、ふれあう指先だったりといろいろだ。理屈ではない。ただ、直感的に、俺たちは愛しあっている、と感じるのだ。
それなのにどうして一緒に寝るのはいやなのだろう? よくわからない。好きならもっとふたりでいたいと思うのが普通ではないのか。──いや、勇利にだって、「常識」や「普通」という言葉は似合わないのだけれど。この子が一般的だというのなら、世の中はすべて狂ってしまう。しかし、勇利の愛情表現は時にひどくまっすぐだ。わかりやすい。それなら同衾することだって──でも、愛しているからこそあんな忌まわしいせりふを言ったりもするのが勝生勇利だし……。
「愛してる相手と一緒に寝たいと思わない?」
考えてもわからないので、ヴィクトルは素直に尋ねることにした。勇利はきょとんとしてヴィクトルを見た。
「……なんだい?」
「うん……ヴィクトルって愛する相手と一緒に寝たいんだーと思って……」
ヴィクトルは顔をしかめた。これもあまり好きなたぐいの言葉ではない。
「そういうところは普通なんだね」
勇利が感心した。
「否定はしないけど……、というか、勇利は俺をどういう人間だと思ってるんだ?」
「異星人」
ヴィクトルにとっては勇利のほうが異星人だ。
「いったい何が気に入らないのさ? ベッドはひろいし、ふとんもあったかいよ。ふかふかだ。色だって勇利の好きな色だし」
「寝るんだから色なんか関係ないと思うけど……」
「まくらもいいやつだよ。それ以上何を望むんだい? 勇利が変えて欲しいものや必要なものがあるならどうにでもするから……」
「いや、べつにそういうのはないよ。何もいらないよ」
「じゃあどうして? 何が不満なんだ? 全部そろってるし──何より俺がいるじゃないか。勇利が大好きなヴィクトル・ニキフォロフがいるんだよ。なんでいけない?」
「それがいちばんの問題だと思うけどね」
勇利が笑いながら言った。ヴィクトルはぎくっとした。もしかして……。
「……勇利」
「なに?」
「その……何もしないよ?」
勇利が眉を上げた。ヴィクトルはためらいがちに続けた。
「一緒に寝るってそういう意味じゃないよ。それはまあ……勇利がいいならしたくないことはないけど。っていうかしたいけど」
おっと、こういうことは言わないほうがよかったのだろうか? しかし隠しておける感情ではないし、勇利だってうすうすわかっているのではないだろうか。だからこそ警戒しているのでは……。
勇利は穏やかに微笑して言った。
「何かするとかしないとかじゃないんだよ」
彼は、ヴィクトル、何もわかってないなあ、というように笑った。
「そういうことじゃないの」
ヴィクトルは懲りずに勇利を誘い続けた。「勇利、一緒に寝よう!」「今夜は俺のところで寝るよね?」「勇利……俺、勇利がいないと眠れないなあ」「ねえ勇利、マッカチンも勇利に来て欲しいって!」「ゆうりぃ、新しい敷布にしてみたよ! 寝心地をためしたくない?」──どんな言葉にも勇利はうなずかなかった。勇利の頑固者め、とヴィクトルは思った。
「いい加減あきらめてよ」
「いやだ。あきらめない」
「なんでそうこだわるのかな。一緒に暮らしてるんだからいいじゃない」
「勇利の望みはかなえたいから」
「いや、ヴィクトルの望みじゃん」
「俺の望みもかなえたいんだよ」
「変なの」
そうだ、と思い立って、ある夜、ヴィクトルはマッカチンとともに勇利の私室を訪問した。何も自分の寝室でなければならないというきまりはない。ヴィクトルのほうから勇利のベッドへ行けばよいのである。
「オジャマシマス……」
勇利が寝静まったころ、彼の部屋の扉を開けたヴィクトルは、ベッドに近づき、そっとふとんを持ち上げて中へすべりこんだ。うわ、あったかい、と思った。勇利の匂いがする。どきどきするし、興奮するなあ。下半身は抑えないとね。俺を大好きな勇利のことだから、なんだかんだいってとろけて「いいよ、ヴィクトル……」なんて言い出すかもしれないけど。
──と。
勇利に喜んで寄り添おうとしたヴィクトルは、ぴたりと動きを止めた。ほの暗い中で、はっきりと勇利が目をひらいていた。その目つきのつめたいことといったら! ヴィクトルはたらっと汗をかいた。
「あー、えっと、勇利……」
「何してるの?」
声も氷のようである。ヴィクトルはどうにか笑って見せた。
「いや、俺は、ただ……」
「何してるのかって訊いてるんです」
「ちがうんだ勇利、これはね、」
勇利が黙って扉のほうをまっすぐに指さした。ヴィクトルはうなずき、そろっとふとんから出てベッドを下りた。
「マ、マッカチン、戻ろうか」
「マッカチンはいていいよ」
「ずるくないか!?」
「おやすみ、ヴィクトル」
勇利はひどい。勇利は理不尽だ。なんであんなに俺につめたくできるんだ? 悪魔め! ヴィクトルはその夜、涙をのんでひとりで眠った。
その日のことは、「ヴィクトル夜這い事件」というたいへん不名誉な名付けをされた。勇利は何かあると「ヴィクトルは夜這いをかけてくるからね」とからかうのである。「ヴィクトルでも夜這いするんだー」などと言うのでたまらない。怒っていないようだからよかったけれど。それにしても、あこがれの男の愛ある行動を夜這い呼ばわりだなんて。本当にかわいくてどうしようもないな、勇利って。
ヴィクトルはひらめいた。そうだ。勇利が冷静なときに誘うからこういうことにな���のだ。もっと自分にとって有利にことが運ぶようにしなければ。
「勇利、今夜は飲もう!」
「夜這い事件」のほとぼりがさめたころ、ヴィクトルは勇利が好みそうな酒をいくらか支度し、さあさあ、と彼に勧めた。
「えぇ……ぼくはいいよ……そういうのは……」
「そう言わずに。そんなに強くないやつだから」
「あとで後悔するんだから……」
「俺が量をみててあげるよ。かるく酔う程度。ね?」
「うーん……」
ヴィクトルとて、泥酔するほど酔わせたいわけではない。例のソチでのバンケットのときほど酔われては、かえってヴィクトルのほうが困るのである。ちゃんと自分の意思は保ってもらいたい。べろんべろんに酔っ払わせて、正体がないところをベッドに連れこむ、というのは下品のきわみだ。ヴィクトルが望んでいるのはそういうことではない。
「じゃあ……、ちょっとだけ……」
「ワーオ!」
勇利は酒が入ると明るくなるので、ふたりは陽気に飲んだ。ちゃんと、勇利が記憶をなくすようなことはさせず、ただ楽しく話せる程度にとどめておいた。途中からだんだんと勇利のほうが積極的になり、「もっとちょうだい」「足りない」「欲しい」と言い出したので困った。
「だめだよ勇利、これ以上は」
「なんでぇ? ヴィクトルが飲もうって言ったのに」
「勇利はちょっとだけって言っただろ」
「まだほんのすこしだよ。ぜんぜんだよ」
「だめ」
「ヴィクトルの意地悪」
勇利は口をとがらせ、上目遣いでヴィクトルをにらんだ。う、かわいい……とヴィクトルはめまいをおぼえたが、誘惑に負けている場合ではない。
「もうやめておいたほうがいいよ。そろそろ寝よう」
「えー」
「えーじゃない。また二日酔いで頭痛くなるよ」
「横暴コーチ」
どっちが横暴なんだ。ヴィクトルは可笑しかった。勇利こそ普段から俺をいじめてばかりいるくせに……。
ヴィクトルはテーブルを簡単に片づけた。よし。言うならいまだ。
「勇利」
「なにー」
「一緒に寝ようか」
勇利がヴィクトルを見た。
「夜中に勇利の気分が悪くなったら大変だし」
ヴィクトルは明朗に説明した。
「勇利も俺のことは好きだろ? 一緒にいたいだろ?」
「…………」
「ね?」
勇利は黒目がちの大きな瞳で、じっとヴィクトルをみつめている。ヴィクトルはにこにこした。ふっと勇利が笑った。
「……ふうん」
彼はヴィクトルにぐっと顔を近づけた。
「そういうわけ……」
「そういうわけって?」
「そうやってぼくをベッドに連れこむために酔わせたんだ」
勇利の指が、ヴィクトルの頬からおとがいへと伝っていく。おいおい、とヴィクトルは思った。
「とんだ誘惑もあったもんだね……」
「いまきみがしていることのほうがずっと誘惑だぞ」
「ヴィクトルのえっち」
勇利がくすっと笑った。
「勇利、俺は何も勇利にいやらしいことをしようと思ったわけじゃないぞ」
ヴィクトルは抗議した。
「わかってるよ。でもえっちだよ。してることがえっち」
勇利はまぶたをほそめ、あえかな吐息をついてくちびるを寄せてきた。
「そんなにぼくと一緒に寝たいの……?」
ヴィクトルはぞくぞくした。勇利、おまえ、警戒心とか危険信号というものがないのか。俺を安全な男だとでも思ってるのか? そんなことをして、無理やり押し倒されても知らないぞ。
「困ったひと……」
勇利がくすくす笑った。勇利のほうがよほど「困ったひと」だ。
「でも……」
勇利はいたずらっぽく続けた。
「……どうして何もわからなくなるまで飲ませなかったの?」
彼はそっとヴィクトルと鼻先をふれあわせた。
「そうしたら……一緒に寝られたのに」
「それじゃ意味がないんだよ」
「ヴィクトルは紳士だね」
「そういうことじゃない」
「えっちだけど紳士なんだ」
勇利はふふっと笑った。
「えっち紳士」
「なんだそれは」
「ヴィクトル、優しいー」
勇利はぎゅっとヴィクトルに抱きついた。ヴィクトルは彼の髪に頬を寄せた。ふたりはしばらく抱きあった。
「……勇利」
「ん……?」
「一緒に寝よう」
勇利はすこし顔を離し、キスしそうなくらいくちびるを近づけてささやいた。
「だ・め」
その夜のことは、「ヴィクトル襲い事件」と名付けられた。まったくもって不本意だ。
「襲ってないぞ」
「襲うくらいの盛んな意気があればよかったのに、っていうことだよ」
「襲ったら怒っただろ?」
「当たり前じゃん」
「勇利は理不尽だ」
「ヴィクトルあのさ、いくらがんばってもぼくはヴィクトルと一緒に寝ないよ。そろそろあきらめたら?」
「でも、俺は勇利と一緒に寝たいんだ。勇利だってそうだろ?」
「だからなんで自分の希望をぼくの希望にすり替えようとするんだよ」
ふたりは一緒に入浴していた。お風呂はいいのになあ、とヴィクトルは首をかしげた。これもヴィクトルのほうから望んだことだが、「温泉と同じだろ?」と強引に了承させることができたのだ。なのに同衾はいけないらしい。いったい入浴と何がちがうのだろう。どうせまた勝生勇利式の妙な理屈があるのだ。
「勇利……」
ヴィクトルは勇利を膝の上にのせ、かるく抱いて顔を近づけた。勇利はヴィクトルと向かいあって、濡れた髪をかき上げている。試合のときみたいにすっきりしているけれど、それよりも幾分か幼く見える。同じ髪型なのに不思議だ。
「今夜、一緒に寝ようよ」
勇利が噴き出した。彼は口元に手を当て、「へこたれないなあ」と感心した。
「いいだろ?」
「だめだよ」
「なぜなんだ? 俺には勇利がわからないよ。俺が好きでしょ?」
「好きだよ。大好きだよ。あこがれのひとだし、愛してるひとだ」
「だったらどうして……」
「ヴィクトル……」
勇利はヴィクトルを向こう見ずな瞳でみつめ、ゆっくりとささやいた。
「……ぼくを誰だと思ってるの?」
いっそ優しい、言い聞かせるような物言いに、ヴィクトルはちょっと考えこんだ。ぼくを誰だと思ってるの。
「ヴィクトルと一緒に寝るって、そんな簡単なことじゃ、ないから」
陽気に「一緒に寝よう」なんて誘われて、「うん、そうしよう」と答えられるほど簡単じゃないから──。
勇利はにっこりし、口ぶりを変えてこう続けた。
「ぼくの名前は勝生勇利。どこにでもいる日本のフィギュアスケート選手で、二十四歳だよ」
いまの勝生勇利は、世界一愛している男とも──惚れ抜いた男だからこそ、たやすく同じベッドに入ったりはしないようだ。
確かに勝生勇利ならそうなのかもしれない。ヴィクトルは反省し、以降は勇利を誘わなくなった。勇利と一緒に眠れたらなあという気持ちはずっと続いているけれど、やはりそれは踏みこみすぎというものなのだろう。普段の理性を保っている勇利は、きよく正しく、毅然として、高潔な精神でいるのだ。ふたりで眠ればそれが崩れるとはヴィクトルは思わないが、勇利がどう思うかはまた別問題である。彼のこころを正しく理解しようとすることは、ヴィクトルはもうあきらめているのだった。わからないところも愛しているから、それでよいのだ。
だから次にヴィクトルが「一緒に寝よう」と誘ったとき、それは、以前のようなはしゃいだ気持ちからではなく、ただ勇利を心配したからだった。
勇利は全日本選手権のために一時帰国していた。ヴィクトルはロシア選手権があったので、付き添うことができなかった。大丈夫だろうと信じていた。実際、勇利は金メダルを獲った。しかし演技の内容は、いつもの彼には程遠いものだった。勇利は失敗を積み重ね、試合後のインタビューは見ていて痛々しいほどだった。落ちこんでいるのがありありとわかったからではない。落ちこんでいるのに、そんなふうに思われないように気丈にふるまうところが痛々しかったのである。
ああ、俺がそばにいたなら、とヴィクトルは思った。彼を抱きしめてやれない自分が歯がゆかった。早く俺のもとへ戻っておいで勇利、とねがった。そうしたら、思いきり甘やかして、頭を撫でて、何もかも忘れさせてあげるから──。
間もなく勇利は家に帰ってきた。予定より早かったのでヴィクトルは驚いた。明日だと思っていたため、早々にベッドに入り、うとうとしているところで物音がしたのだ。ヴィクトルは急いで玄関へ行った。いつの間に雨が降っていたのか、勇利は濡れていた。
「勇利!」
ヴィクトルは勇利の頬を包みこんだ。
「こんなに濡れて……かわいそうに」
勇利はうつむいてじっとしていた。
「早くこっちへおいで。服を脱いで。タオルを持ってくるよ」
ずぶ濡れの勇利の世話をしているあいだに湯を沸かし、勇利を風呂に入れ、ヴィクトルはあたたかい飲み物をつくった。上がってきた勇利の髪を乾かしてやり、ソファに座らせて抱き寄せた。勇利はカップをずっと両手でくるんでいた。
「冷えただろう。すぐやすんだほうがいい」
「ヴィクトル、ごめんなさい……」
そのときようやく、勇利が口をひらいた。ヴィクトルは耳をそばだてた。
「あんな演技……」
「いいんだ」
ヴィクトルはすばやく遮った。
「不調というものはある。そんなことで俺は怒ったりしないよ。あとで映像を見てまた立て直そう。なに、心配することはない。勇利はもともと不安定な選手だからね。コーチとして覚悟はできてるさ」
ヴィクトルが明るく言うと、勇利はほのかな微笑を浮かべた。ヴィクトルはほっとした。しかし、このまま勇利をひとりにしたくはなかった。だから言った。
「今夜は俺の部屋へおいで」
「…………」
勇利は「簡単なことじゃない」と言った。ヴィクトルと寝るのはそんなものではないと。ヴィクトルはいま、簡単に言っているわけではなかった。それは勇利にも伝わっただろう。だが彼はこう答えた。
「やめとく……」
「なぜ?」
ヴィクトルは真剣に言った。
「おまえが心配なんだ」
「わかってる。でも大丈夫だよ」
勇利はヴィクトルの腕に手をかけた。
「ひとりになっても泣いたりしないから安心して」
「勇利、だが、」
「ゆっくり考えてみたいんだ」
勇利はやわらかくつぶやいた。
「まだ、ひとりであの演技について思案できてないんだ。試合が終わってから何してたんだって思われるかもしれないけど、ずっと上の空で、ぼうっとしてて……、考えられなかったんだ。ヴィクトルの顔を見て、初めて正気に返った」
勇利はほほえんだ。
「甘えてるんだと思う。ヴィクトルがいなくちゃ自分のことも振り返れないよ。まだ動画も見てない。こわくて……」
「そんなにひどい失敗じゃない。メダルは獲ってるんだ」
「うん」
勇利は素直にうなずいた。
「そのこともふくめて、ひとりでちゃんと思い返したいんだ。自分の力で整理するよ。明日、そのことについてぼくと話しあってくれる?」
「もちろんさ」
「これくらい自分でできなくちゃだめだと思う」
勇利は自分の言葉にうなずいた。
「ヴィクトルに頼りきって、なぐさめてもらってちゃだめだよ。ただでさえ、ヴィクトルにはいろんなことをしてもらってるのに」
こんなときこそ甘えればよいのだ。ヴィクトルはそう思ったが、勇利がこころぎめをしている以上、何も言えなかった。なぜなら彼は勝生勇利である。
「わかった……」
ヴィクトルは困ったように笑った。勇利が目をほそめた。
「なんか、ヴィクトルのほうが心細そうだね」
少なくとも、そんなふうに言えるのだから彼は自分を取り戻したのだろう。ヴィクトルの顔を見てそうなれたならよかった。ヴィクトルは特別だということだ。でも、甘えていいのに、とそんなことをヴィクトルはずっと考えていた。
勇利はよくなかったところを練習し直し、きちんと調整し、四大陸選手権にのぞんだ。これにはヴィクトルも帯同できた。しかし、全日本選手権でのことが思い出されるのか、勇利は公式練習のときから異常なほど緊張しており、練習内容もあまりよくなかった。
「勇利、何も心配いらない。自信を持って。勇利は俺の生徒だ。できないわけがないだろう?」
「う、うん……わかってる」
「俺は勇利がひどい成績を獲るような教えは何ひとつしなかったはずだよ」
これでは勇利が重圧を感じるだろうか? ──いや、これでよいのだ。勇利を信じるのだ。
「勇利……」
ヴィクトルは試合の前夜、がちがちにかたくなっている勇利の耳元にささやいた。
「今夜は一緒に寝ようか?」
勇利がはっとしたようにヴィクトルを見た。彼は瞬き、それから笑い出し、ヴィクトルに抱きついてかぶりを振った。
「ヴィクトルとは一緒に寝ないよ」
やはり勇利は勝生勇利だった。
「世界選手権で俺が勝ったら、勇利、一緒に寝てくれる?」
久しぶりにヴィクトルは、最初にしたように陽気に、勢いこんで勇利に尋ねた。勇利は笑って拒絶した。
「だめ」
「じゃあ勇利が勝ったらご褒美に一緒に寝てあげる」
「はいはい」
「はいはい、か。オーケィってことだな……」
「そんなわけないでしょ?」
勇利はあきれたように言った。
「一緒には寝ません」
「勇利は手ごわいな……」
「そんな簡単なことじゃないんだよ」
「俺も簡単には言ってない」
「うそばっかり。気軽に誘ってくるじゃない。ぼくにとってヴィクトルは、唯一無二の、崇高なひとなんだからね。わかってるのかな、もう……」
確かに、世界選手権が終わっても、勇利は一緒に寝てくれなかった。
ある夜のことだった。ヴィクトルはマッカチンと並んでやすみ、気持ちよく寝息をたてていた。月はみちており、あまりにまばゆくうつくしいので、カーテンは開けてあった。寝入るまでヴィクトルは、それをひとり見上げていたのだ。隣に勇利がいて、彼とともにみつめることができたら、と考えた。そんな夜を、これまで幾夜と知れず過ごしてきたのだ。スケートをしているとき、食事のとき、町を歩くとき、買い物をするとき、楽しい経験をするとき──それらすべてのときに勇利はヴィクトルのかたわらにいたけれど、唯一、夜眠るときだけはそうではなかった。ヴィクトルはそれがひどくさびしかった。しかし仕方がない。いまの勇利がそう言うのだから……。
ヴィクトルは浅く眠っていた。何か物音が聞こえ、ベッドがきしんで振動が伝わってきたが、夢の中の出来事だと思った。ぬくもりがそば近く寄ってきて、ヴィクトルの腕を持ち上げ、胸におさまり、そのあたたかみをかるく抱いても、ヴィクトルはまだ夢を見ているつもりだった。やけにやわらかく、おぼえのある感触だな、と思った。
「うわ、寝るとき、全裸なんだ。下着くらい穿いてるのかと思った……」
そんな声が聞こえた。それからかるい吐息。まあいいか、というのんきな声。
「ヴィクトルってこんな顔で寝るんだー……」
頬に何かがふれてきた。くすっという笑い声がした。
「寝てるときも綺麗だね。鼻つまんでみようかな。怒るかな?」
それからくちびるにも感触があった。
「……ヴィクトルでも眠るんだぁ……」
そこでようやくヴィクトルはおかしいと気がついた。夢にしては生々しい。
「……知ってるだろ、そんなこと」
ヴィクトルはうすく目を開けた。
「いまさらなんだ。一緒に住んでおいて……」
「そうだけど、改めて見るとね……」
「試合のとき、ホテルでも全裸で寝てるぞ、俺は」
「いちいち確認してないよ、そんなの」
ヴィクトルはぱっちりとまぶたをひらいた。勇利は月のひかりを浴び、あどけない瞳でヴィクトルを見ていた。
「……なんでいる?」
「だめだった?」
勇利はいたずらっぽく言った。
「何回も誘ってくるから、べつにいいのかと思って……」
「俺とは一緒に寝ないんじゃなかったのか?」
「簡単なことじゃない、と言っただけだよ」
ではその「難しさ」を乗り越えたというのか。ヴィクトルにはわけがわからなかった。
「裸の男のベッドに入ってくるのがどういうことか、教えてあげようか」
「裸だなんて思ってなかったんだよ」
「同じことだ。あっても下着一枚だろう。それなりの覚悟をしてきたってことかな」
「ヴィクトルはそんなことしないと思うな」
「どうだろう。勇利が一緒に寝てくれないから欲求不満が爆発しそうなんだ」
「今夜はしないんじゃないの?」
「さあね。俺だってどうなるかわからない。いきなり何か始めても、『ヴィクトル襲い事件その二』なんて言って泣かないでくれよ」
「今夜は『勇利夜這い事件』だね……」
勇利は自分で言ってくすくす笑った。ヴィクトルは勇利を抱き寄せ、その瞳をきまじめにのぞきこんだ。
「勇利、……本当に勇利?」
「……そうだよ」
「どうして?」
「…………」
勇利はほのかに笑い、ささやくように言った。
「ヴィクトル、一緒に寝ようよ」
「…………」
「これから、毎日……」
「……なんで急にそんなこと言う?」
「それはね……」
勇利はヴィクトルにぎゅっと抱きついた。
「……思い出したからだよ」
ヴィクトルは目をみひらいた。
「思い出した……?」
「そう。思い出した」
勇利はまぶたをほそめてくすぐったそうな顔をしている。
「だから、ここへ来た……」
「…………」
「ありがとう、ヴィクトル……。貴方はなんて優しいのでしょう」
勇利は、可憐な告白をするようにささやいた。
「……怒った?」
ヴィクトルは息をついた。怒ったか、だって? 手のつけようもないほど胸がときめいているのに。
「勇利って本当に勝手だよね……」
「うん」
勇利はうれしそうにうなずき、ヴィクトルの胸に顔をうめた。
「それはそうだよ。ぼくを誰だと思ってるの?」
「えっと、ユーリ・カツキ……」
ヴィクトルが迷うような声を出し、それから優しく「ユーリ」と呼んだ。インタビューで何度も聞いたあのすてきな声が、自分のことを「ユーリ」と発音してくれる。そのことに勇利はうっとりした。
「大丈夫かい?」
「うん、大丈夫……」
勇利は、これまでにないくらい大丈夫だと思った。こんなに気分が爽快だったことはない。だってヴィクトルが──あのヴィクトル・ニキフォロフがそばにいて、勇利を気遣って、髪を撫でたり、頬にふれたりしてくれているのだ。
「ほら、靴を脱いで……」
ヴィクトルが勇利の足から靴を取り去った。そしてどうにか体裁を整え、ちゃんとベッドに入れて息をついた。
「ここに水を置いておくからね」
「んー、みずぅ……?」
「そうだ。喉が渇いたら飲むように。渇かなくても飲んだほうがいいんだけどな……、難しそうだね」
「水くらい、飲める」
勇利は主張した。ヴィクトルに、何もできない子どもみたいなやつ、と思われたくなかった。
「そうかい?」
ヴィクトルがほほえんだ。その神々しいほどの洗練された笑みに、勇利は、ヴィクトル、かっこよかぁ……と目を輝かせた。ヴィクトルが可笑しそうに言った。
「どうしてそんな目で見るんだい?」
「だって……」
「きみってほんとに変わってるね」
ヴィクトルはしみじみとつぶやいた。
「ダンスバトルを仕掛けてきたり、その結果次第でコーチになれと言ったり、とても勝手だし……」
勝手だ、と言いながら、ヴィクトルはこのうえもなくうれしそうに笑っていた。なぜだろう?
「なんか、今後、いろんな意味できみには手こずらされそうな気がするよ」
ヴィクトルは身をかがめ、勇利の耳元に語りかけた。
「悪い気分じゃ、ないけど」
勇利はぱちぱちと瞬いた。ヴィクトルは目をほそめた。
「さて、名残惜しいけどもう行くよ……。これ以上一緒にいたら、俺は何を言うかわからなくてこわい。きみって不思議だから、俺は思わぬことを口走るかもしれないよ。だって数時間前──バンケットが始まるまでは、俺は日本の選手の部屋に入って、こんなふうに介抱してるなんて、想像もしていなかったんだ」
ヴィクトルはひとりごとのように続けた。
「こんなに楽しいバンケットになるなんて……考えもしなかった」
彼は勇利の髪をさらさらと撫でた。
「じゃ……行くね」
ヴィクトルが身を起こす。勇利は急にさびしくなって手を差し伸べ、ヴィクトルの上着の裾をぎゅっとつかんだ。
「行かないで」
ヴィクトルが振り返った。
「行かないでよ、ヴィクトル」
「ユーリ……」
「ここにいてよ」
勇利の目に透明なしずくが浮かんだ。
「ぼくんとこにいて、ヴィクトル」
ヴィクトルが何か言いたそうにくちびるを動かした。勇利は言いつのった。
「さびしいよ。ヴィクトル、一緒に寝ようよ。ぼくヴィクトルとふたりで寝たい」
「ふたりで……」
「一緒がいいよ。一緒がいい。ふたりで寝よう。ね? ぼくヴィクトルが好きなんだ。大好きなんだ。一緒に寝たい。毎日そうしたい。だめ?」
「…………」
「いやだよ。ヴィクトル行かないで。行かないでよ。ひとりにしないで」
涙があふれて止まらなかった。勇利はわけもわからず泣きじゃくった。行かないで、ここにいて、一緒に寝て、とくり返しねがった。
「今夜はいけないよ」
ヴィクトルはかがみこみ、幼子に言い聞かせるように言った。
「次会ったとき、そうしよう」
「次……?」
「ああ」
ヴィクトルはすぐれて優しい、甘いくちぶりで言った。
「もし次のときもユーリがそのつもりで、俺のことを好きだと言ってくれるなら、俺はユーリと一緒に眠るよ」
「……ほんと?」
「本当だよ」
ヴィクトルはにっこり笑った。
「ユーリの言う通りにするよ。いくらでもするよ。一緒に寝るのなんてちっともだめなことじゃない。俺だってそうしたいくらいなんだ」
「ほんとに?」
「だから次までこの約束、おぼえておいて」
ヴィクトルは勇利の手を握りしめた。
「ヴィクトル、絶対だよ」
勇利が涙に濡れた瞳で一生懸命に訴える。ヴィクトルは請け合うというようにこっくりとうなずいた。
「絶対だ」
「ぼくと一緒に寝てね」
「ああ」
「ひとりはいやだよ」
「わかった」
「約束」
「約束だ」
勇利はほっと安心した。次はヴィクトルと一緒に寝られるんだ、と思った。大好きな、世界一すてきなヴィクトルと。愛する彼と。そうなったら、もう絶対に離れない。
「早くヴィクトルに会いたいな……」
勇利がつぶやいた。ヴィクトルはくすっと笑い、大きなてのひらで、そうっと勇利のまぶたを覆った。
「ゆっくりおやすみ。ユーリ・カツキ。今夜のこと、忘れないよ」
1 note
·
View note
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入���白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置��貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
4 notes
·
View notes
Text
インターネットからの脱出
2018/4/25発行
ZINE"霊界通信 2018 S/S Issue"収録
by gandi
Escape from the Internet
ぼくが初めてインターネットに触れたのは15年ほど前のことだ。ちょうど21世紀になりたてくらいの頃だろうか。当時出来たての情報カリキュラムの授業での出来事だ。少し起動に時間のかかる箱型の機械のスイッチを入れると、テレビ型のモニターの向こう側から世界中のあらゆる情報が飛び込んでくる。その斬新さに、ぼくは舌を巻いた。しかもその情報がすべて生々しい。なにかがテレビとは明らかに違う。
ぼくはテレビが嫌いな子供だった。今でこそ落ち着いてきたものだが、当時のテレビの演出はとにかく過剰で、ギラギラした悪趣味なセットの前で空疎な会話をする芸能人たちの姿にはとにかくウンザリするばかりだった。人の車を壁にぶつけて壊して喜ぶようなノリにも全くついていけなかったし、ディレクターの指示で拉致同然に、突然半年間も海外を旅させるような嗜好にも「こんなことが許されるのか」と子供ながらに怒りを覚えた(たとえそれが口裏合わせ済みのことだったとしてもだ)。そしてそれらの行動に何一つ意味はない。彼らの行動原理は「ノリ」だけで、洞察に基づいたものがない。徹底的に空疎なのだ。
空疎なテレビの世界の中でも、群を抜いて空疎だったのはひな壇の芸人たちだった。彼らは空疎さという一点において洗練されつくしていた。「なんでやねん」と投げられる言葉に、タイミングよく再生される乾いた観客の笑い声。「なんでやねん」。彼らが本当にそう思っているのか、かなり疑わしかった。「なんでだよ?」でもその「なぜ」を正面切って考えようとする人間は、そこには一人もいないように見えた。
(※もっとも、その空疎さこそなんでも重苦しく考えたがる彼らの前の世代への意図的反抗なのだと分かったのは、ずっと後になってからの話だ)
しかしインターネットは違った。誰もが手作りの簡素なホームページを作り、それぞれが勝手なことを論じていた。そこには「なんでやねん」というツッコミを入れる人間はいない。それゆえ誇大妄想としか思えないことを100ページ以上に渡って、延々と書き連ねているような人も少なくなかった。誇大妄想。 テレビだったら芸人の「なんでやねん!」の一言でかき消されたに違いない。しかし人の誇大妄想の中には、社会を抜本的に変革してしまうような考えがしばしば含まれている。たとえば革命家。革命家は周囲の冷笑を意に介さず、空気も読まずに延々と妄想を深め続ける。すると次第に感化される賛同者が出てくる。保守派からすれば狂人に思えない賛同者たちが。
息苦しい日々の中で、ぼくはインターネットに光を見出した。
ぼくはテレビと同じくらい学校の雰囲気というものが嫌いだったが、それは教室がテレビの相似形のように見えたからだ。
端っこの席で、目立たないが誰も思いつかないようなことを考えているヤツの考えは、いつだって声がデカくてノリがすべての野球部の声にかき消される。その身も蓋もない事実に、ぼくはホトホトウンザリしていた。この構造はずっと変わらないに違いない。きっと大学でもそう。社会に出てもそう。死ぬまでそう。いつか全部叩き壊す。そうでなければ刺し違える。そんな風に自分に何度も言い聞かせなければ、グレてしまっていただろう一少年に、インターネットはこっそりナイフを渡してくれたのだ。ぼくは友人たちへ 「テレビよりインターネットの方が全然面白いぞ」と触れ回った。友人たちは興奮するぼくの話を、肯定するでも否定するでもなく聴いてくれた。インターネットが面白いということは少しずつ広まり始めていた。
率直に言って、ぼくはインターネットの「世界中の情報がリアルタイムで入ってくる」という側面は、そこまで重要ではないのではないかと思う。それは既存のメディアでも出来ていたことなのだ。インターネットの本当にクリティカルな点は「人間の生々しい声が、誰にも検閲されないまま聞ける/言える」という点にある。それも平等にだ。どんなに虐げられていた者にも、数千円のスマートフォンさえあれば平等にその機会はやってくる。
誰がジャンクな記事を量産しているのか
だから生々しい声が聞こえなくなったら、そこでぼくのインターネットへの関心は尽きる。聞いたこともないような考えや、社会によって巧妙に隠された呼び声を聞くために、ぼくらは本を読みネットを見る。決して誰かが仕込んだ一般論を聞くためじゃない。ぼくは「失敗しない生き方をするための十の方法」なんて記事を見かけるたびにいつもウンザリしているが、こういう記���は一体誰が書いているのだろう?全く失敗しなかった人だろうか。それとも派手に失敗した人だろうか。
あまりに不思議に思って周囲にこぼしていたら、知人の大学生が書いていた。同級生やサークルの仲間も結構な割合でやっているという。 バイト感覚で家計の足しにしているのだそうだ。 1文字0.1円。2000文字程度の記事を10個仕上げて2000円貰うんです、と彼は言う。プロのライターが最低1文字3円からということを踏まえると信じられない値崩れだ(もっとも最近はプロの現場でも1文字1円というケースが珍しくなくなったが)。
そんな金額ならスーパーでレジ打ちした方がずっと効率がいいように思えるのだが、仲間内のパーティに出席できたり、就活のときネットメディアに関わっていたことが有利に働いたりと、色々とメリットはあるらしい。「ちょっとした承認欲求や仲間内で意識の高さを演出するために、」 場合によっては損得度外視で引き受けることもあるという。 しっかり見ていれば分かることだが、中には高校生が書いているケースもある。記事の最後に「この記事を書いた人」というツイッターリンクが付いていて、そこに行くと高校生だということが分かる。
なるほどこれらの記事は(誰もがうすうす気づいてはいるだろうが)プロではなく文章の素人がタダ同然で書いているものなのだ。インターネットの記事が人に見てもらえるようにするには、内容よりもグーグルのロボットから高い評価を受けるためだけにとにかくコストを抑え、量産することが大事だ。そして言うまでもないことだが1文字0.1円では、一つ一つの記事に真剣に向き合う時間はない。 必然的にすでにインターネットに載っている文章をコピー&ペーストし、適当にリライトするという作業になる。もちろん直接取材や、図書館に行って原典を確認するなんてことはあり得ない(つまり、何かのきっかけで一度間違った情報がインターネットに掲載されると、永遠に誤情報がコピーされ続けるということになる)。著者は自分の考えを述べようにも、記事が問題としている内容に、真剣に向き合って考えているヒマはない。そもそも書かせている側が、著者に対して端から何も期待していないのだ。
こうした記事が、毎日数千、数万とインターネット上にアップされている。多くの場合は記事と見せかけた広告で、そうでなければ広告収入のために書かれたテキストだ。記事の書き方はこう。「ランキング形式のまとめ記事にしてください。まず1位と2位に、定番のA社とB社のアイスクリームを挙げます。そして3位くらいにクライアントさんのこの新作アイスクリームをランクインさせてください。1位だと広告だって思われてしまうので、3位くらいがよいでしょう。4位以降は適当でいいです」。もちろん、ぼくは必ずしも広告が悪いと言っているわけではない。問題は企業が、あたかも主流的意見であるかのような記事もどきを、ジャンクのように量産することにある。
ぼくらは日々これらの量産されたジャンク記事に囲まれて生活している。好もうと好まざろうと、スマートフォンにニュースアプリやツイッターをインストールしている限り、絶対に目にすることになる。グーグルで何かを検索しても、個人のサイトやブログにたどり着くケースは今や稀だ。インターネットの笑ってしまうような(しかしひょっとすると社会を揺るがすかもしれない)誇大妄想は、十年の月日をかけて、当たり障りのない一般論を装った、どこかの企業広告へとすり替えられたのだ。
こうしたゴミのような広告の山から逃れたい人はひょっとするとインスタグラムのような、社会性とあまり関係のないメディアだけを見るようになるのかもしれない。インスタグラムはアカウントのジャンク化を恐れて、拡散機能をあえて弱めにするなどの対策をしているようだ。だが言ってしまえば、それは騒がしい広告記事から耳を塞いだだけのことで、決して生々しい声を取り戻したというわけではない。
そしてこうしたジャンクな記事は、恐らくあと五年もしないうちに人工知能が書くことになるだろう。人工知能なら、もっとうまくやるに違いない。ビッグデータから得た集合的無意識──当たり障りのない一般論や、何かのきっかけでセレブが発言した、流行の考え方──を、それらしい言葉でまとめて無限に生産するのだ。しかしそれは、あの、テレビや雑誌といった旧メディアが作っていた空疎な時間と、一体何が違うというのか。
メリークリスマス!と言えないアメリカ
ジャンクな記事が生まれる要因は他にもある。世界的なポリティカル・コレクトネスの流行だ。ポリティカル・コレクトネス(政治的な正しさ)とは「 政治的・社会的に公正・公平・中立的で、なおかつ差別・偏見が含まれていない言葉や用語のこと(Wikipedia)」とある。 ポリティカル・コレクトネスの観点からすると、たとえば「看護婦」という言い回しは男性がその職業につけないイメージを与える可能性があるので間違っており、男女ともにイメージすることができる「看護士」と言い換えるべきということになる。同様に「保母」は「保育士」とすべきだし、「肌色」は人種的配慮に欠けるので「ペールオレンジ」に言い換えるべきとするのがポリティカル・コレクトネスの考え方だ。
この考え方は確かにある程度まで間違っていないように思えるのだが、少し考えると行き過ぎは文化を破壊しかねないということが安易に想像つく。例えば「メリークリスマス」という言葉は、宗教的配慮に欠けるという観点からすでにアメリカでは 「ハッピーホリデイズ」と言い換えられている。 クリスマス飾りににキリスト像やマリア像などを持ち込むのもご法度だ。十字架なんて問題外。宗教色を一切葬り去らねば、イスラム教徒や仏教徒に失礼じゃないか、というわけだ。そのうちクリスマスに赤色を使うのもNGになるかもしれない。赤はキリストの血を表すからだ。
しかしそのようなものを果たしてぼくらはクリスマスと言えるのだろうか。これは「政治的な正しさ」を盾にした、キリスト教文化への破壊行為ではないのだろうか。なぜポリティカル・コレクトネスの人たちはこんなに偏屈な考え方をするのだろう?これではまるでポリティカル・コレクトネス原理主義だ。ポリティカル・コレクトネス教以外のあらゆる宗教は絶対に認めないという原理主義的一神教だ。
たとえあなたが仏教徒だっとしても、笑顔で「メリークリスマス!」と言えばよいではないか。実際日本人はずっとそうだったのだ。キリスト教の人たちが宗教的に大事にしている行事ならば、わざわざそれに目くじらを立てることはない。むしろ「楽しそうだからぼくらも参加させてほしいのだが、仏教徒なんだけど構わないかね?」と言うのが本当の寛容ではないだろうか。それとも一神教徒の人たちには、そういう考え方は難しいのだろうか。
しかしポリティカル・コレクトネスの人々はそうは考えない。頑固に公の場でメリークリスマス!ということを許さない。「そんなに偏狭な態度をとっていれば、かえって息苦しい社会になってしまわないだろうか」「むしろ反動が起こって事態はよっぽど悪くならないだろうか」などと考えていたら、案の定バックラッシュがやってきた。2016年のアメリカ大統領選の時にドナルド・トランプ現大統領が「自分が大統領になったら再びメリークリスマスと言えるようにする」と公約したのだ。大統領選の結果はご覧の通りだ。トランプ大統領は、メリークリスマス!すら堂々と言えなくなってしまった息苦しい社会に不満を持つ人たちの支持を得て当選したのだ。
言うまでもなく、本来あらゆる文化的伝統行事は民族性や宗教性と密接に関わりあっているのであって、そこから宗教色を徹底して排除しようとすれば、ただの無味乾燥で無秩序な騒ぎになってしまう。宗教や民族にまつわる文化的行事が、現代的価値観からすれば理不尽としか言いようのないものを含んでいるのは当然のことだ。伝統行事は、むしろ常にその時代の価値観と全面的には折り合わなかったからこそ、時代が変わったからといって廃止されることはなく、時代を超えてずっと尊敬され続けてきたのだ。それを現代人の価値観にそぐわないからと言って安易に排除をしようとするのは、今の時代の価値観が未来永劫続くと考える現代人の傲慢であり、次の世代への想像力の欠如ではないだろうか。
日本よりはるかに多民族・多文化社会であるアメリカでポリティカル・コレクトネスの考え方が発展したということはある程度理解できなくもない。あまりに価値観が多様過ぎて、「寛容」や「思いやり」でカバーできる範囲をとっくに超えているのだ。ある人々にとって帽子を被ることが礼装であり、またある人々にとって帽子を脱ぐことが礼装である社会では、ポリティカル・コレクトネスがなければ一方的に少数派が追いやられるばかりなのかもしれない。だが、日本は全く状況が違う。常に周囲と価値観を合わせたがり、少数派になることを恐れがちな日本人は、アメリカとは性格が逆で、少数派が自ら少数派であることを捨て、自発的に多数派になりたがる傾向がある。そのような価値観だから世界的にも類をみない寡民族・寡文化社会になってしまったのだ。
有り体に言えば、我々の社会は空気を読むことが大好きだということだ。互いに周囲の顔色を見回して、自分が人とズレてはいないか、誰かが変わった考え方をしていないか、絶えず監視し続ける。今のインターネットは、テレビのような旧メディアと変わらない。これはもはや「ムラ」社会だ。特異な考え方は、誇大妄想が広がる前に「ツッコミ」をして「修正」する。これをポリティカル・コレクトネスの考え方が加勢する。今時の言葉で言えば「炎上」というのかもしれない。そして最後には「まとめ」として「総括」されるのだ(なるほど「総括」とはどこかで聞いたような言葉だ!)。
「炎上」は一見、正しい意見が間違った意見を修正する、社会の自己浄化作用のように見えなくもない。しかしその一方で、特異な発想の芽を潰していると言える。この調子だとそのうちわざと「ボケ」る者が出てきて、毎度お約束のように「炎上」させるようになるかもしれない。人と違うことが怖い私たちは、そうやって永遠に続く終わりのない日常に「お祭り」というリズムを作るのだ。やがて「ボケ」と「ツッコミ」は、「なんでやねん!」(=なぜなのか)という言葉本来の意味を失い、次第に儀礼化していくことだろう。その裏で、本当に特異な考えをする人の声はどんどん見えなくなっていく。社会は変化することなく終わらない日常となり、まるであのバラエティ番組のように、空虚な戯れが延々と続いていくのだ。
本物の共産主義社会が到来する
更に悪いことに、こうしたインターネットの記事たちは各ユーザーに合わせ最適化され、そのユーザーが関心を持っていそうなことばかりをサジェストするように出来ている。例えばあなたがあるニュースアプリでLGBTについての記事を読んだとしよう。そのアプリは次からLGBTについての話題で一杯になるのだ。するとあなたは思う。「今、社会はLGBTに相当な関心を持っているに違いない」。こうしてそれぞれが勝手に「北朝鮮問題が」「仮想通貨が」「アイドルが」「ネコ画像が」社会的関心事の中心であると考え始めるのだ。自分でフォローする人を選べるSNSはもっとひどい。「反安倍政権の世論が盛り上がっている」ように見える人と「安倍政権の高支持率が続いている」ように見える人のタイムラインは永遠に交わることがない。一体なんでこんなことが起こるのだろう。
本来、インターネットというプラットフォームは、「インターネットエクスプローラー」という名前が示す通り、欲しい情報を自分から「探検」することによって手に得るというツールだった。インターネット全体の記事が少ないときは、確かにそれで機能していた。欲しい情報に達するためには色んなページを回らなければならなかったし、必ずしも耳に聞こえのよくない情報も触れなければならなかったからだ。まさにそれは山あり谷ありの探検のようだった。今はどうだろう?ネットには異常な量の記事が溢れかえっている。ぼくらはそれを、到底すべて読み切ることはできない。こんな状況では、誰も冒険などしたがらないだろう。探さなくても、自分にとって気持ちのいい(都合のいい)当たり障りのない情報にすぐ触れることが出来るのだから。
こうした理由から、インターネットの記事が爆発的に増加することに反比例して、ぼくらが新しい世界に触れる体力は日に日に減っていっているように思われる。誰も好き好んで不都合な意見を聞きに行ったりはしない。大量の記事が出回ってあれもこれも読まなければならない中で、誰かの言葉と真剣に向き合う時間も多くはないだろう。ぼくらは気付かぬうちに少しずつ心の体力を奪われているのであって、自分を肯定してくれる安全・安心な言葉だけを聞き続けるようになっている。
そしてそんな世界すらももうすぐ終わる。もうすぐ人工知能がぼくらを真綿にくるんで、いびつな現実���視界から追いやってくれるに違いないからだ。近い将来、ぼくらは全く違う価値観の人と話して不愉快になることも、ほとんどなくなるだろう。アルゴリズムが話の合わなそうなフォロワーを、初めからミュートしておいてくれるからだ。イラストや音楽の才能のなさに思い悩むこともない。内輪のコミュニティの住人、いわゆる「界隈」と呼ばれる人々が、あなたを先生、先生とどこまでもチヤホヤしてくれるからだ(もっともそのアカウントの「中の人」が本物の人間であるという保証はどこにもないのだが)。当然恋人ができないと思い悩む必要もない。本物の人間よりずっと美しいホログラムと恋愛をするのは、今や普通のことだからだ。しかもその恋人は、あなたの過去の発言をデータベース化しているから、絶対にあなたの嫌がることを言わず、あなたが喜ぶことしかしないのだ。
さらに言おう。恐らく近い将来、人間は一切の仕事もする必要がなくなる。人工知能が自己発展する農場や工場を作り、自動運転カーで勝手に出荷してくれるからだ(驚くべきことに、アメリカのGM社はすでにこのシステムを運用し始めているという)。レジも無人だからバイトもいらない。経営も人工知能がビッグデータに基づいてやるのが一番効率的だ。
機械に職を奪われ、失業率は上がるのに生産力も上がり続けるから、先進諸国はベーシックインカム導入を余儀なくされるだろう。なんのことはない、共産主義社会の到来だ。それも前世紀の不完全な共産主義ではなく、マルクスが予見した本物の共産主義だ。ほとんどのことを機械に任せ、人はクリエイティブな仕事、もとい「趣味」しかしなくなるのだ。そのクリエイティブな「趣味」だって、本当に行われるのかどうか随分怪しいように思える。全てが満たされた世界で、クリエイションをしようと思う人間なんて本当にいるのだろうか。
まるで夢物語だが、そういう世界は必ず来る。それも数十年以内に。その世界では人間にどこまでも優しくて都合の良いコンピューターという名の天使が、寿命が来るまでぼくらを甘やかし続けるのだ──まるで真綿で首を絞めるように。そんな世界では、特異な意見も、ラディカルな発想も必要ない。誰一人不満がないので、そもそも社会が変革する必要がない。
怒りも悲しみもなく、誰一人傷つかない世界。そこで天使のような、あるいは幽霊のようなホログラムが、残り少なくなった人間たちに奉仕している。人間は恋愛対象に何かと面倒な同じ人間よりも人工知能を選ぶようになり、人口もどんどん減ってゆくだろう。
"BLACK IS BEAUTIFUL."
建築家であるぼくの父はもう80を超えているのだが、生まれつきの難聴で、ぼくが幼いころから話がなかなか通じなかった。どのくらい聞こえないかというと、ちょうど携帯電話の着信音が聞こえない、というくらいだ。大きな声で向き合って話すと半分くらい伝わる。ハッキリ言うと、身体障害者だ。
しかし父は一度も自分を障害者だと認めなかった。確実に貰えるはずの障害手帳も障害年金も、絶対に受け取らなかった。破産して、収入がゼロになり、家族の食い扶持を繋げなくなった時でさえだ。「なに、誰だってハンディキャップの一つや二つあるんだ、それをいちいち騒ぎ立てるなんてみっともないことだ」それが父の口癖だった。そして父は自分を「ツンボ」であると自称していた。「ツンボ」は差別用語だからやめなさい、とい��ら母が言っても「ツンボがツンボで何が悪い!」と絶対に聞かないのだ。
父の発言は無茶苦茶だ。第一、本当に障碍で苦しんでいる人に対するシンパシーがない。それに「ツンボ」なんて言ったら、ポリティカル・コレクトネスの人々からは避難轟々だろう。
だが、一方で父は障碍者に対して全く差別的ではなかった。車椅子で困っている人がいれば助けたし、その一方で車椅子でも態度が悪ければその場で怒鳴り合いの大喧嘩していた。外国人に対してもそうだ。父には中国人の友達がたくさんいた。酒が入れば毎回、歴史問題の議論で怒鳴り合いになるくせに、ずっと仲良しだった。二、三か月すると、何事もなかったかのようにまた飲んでいるのだ(そうしてまた喧嘩になるのだが)。
父は女性に対しての考え方も、世代から考えれば相当リベラルだった。あれだけ父権的なくせに、結婚当初、父が食べるまで食事に手をつけようとしなかった母に対して「そんな下らないこと今すぐやめろ」と叱りつけたのだという。家族の風呂に入る順番についてもそうだ。ぼくが生まれてからはいつも父と母は喧嘩ばかりしていたが、よく考えれば父と母はずっと対等だった。父はいつだって対等な喧嘩相手が欲しかったのかもしれない。
当時はわからなかったが、父が「ツンボ」を自称していた理由が、今ならなんとなく分かるような気がする。父はきっと「ツンボ」を忌避するのではなく、自分が「ツンボ」を格好いいものにしてやる、と考えたのではないだろうか。
この考え方はマルコムXの言う「 Black is beautiful. 」に似ている。かの有名なアメリカ黒人公民権運動の活動家だ。マルコムは、黒人は白人と平等、とは言わなかった。そうではなくて「"黒"こそ美しい」と言ったのだ。
話によると、幼いころは「ツンボ」のことで相当ひどくイジメられたらしい。しかし父は社会に同情を買うような態度を取りたいとは思わなかった。思うに父は「ツンボ」である自分が圧倒的に凄い建築を作ることによって「ひょっとしてツンボだったからこそ、この人はすごい建築家になれたのではないか?」と、人に思わせるような、価値観の転倒を引き起こそうと企んだのではないだろうか。
ポリティカル・コレクトネスの人たちにとっては「ツンボ」は永遠に良くないものであって、忌避されることはあっても、凄いものとして日の目をみることは未来永劫ない。果たしてそれで問題は本当に解決したと言えるのだろうか。「ツンボ」な自分を「ツンボ」と断言する父のやり方は、テレビではもちろん流せないし、インターネットだったら炎上間違いなしだ。けれどもぼくは、ハッキリ言ってテレビよりも、今のインターネットよりも、父のやり方は圧倒的に「クールなやり方だ」と感じてしまう。
インターネットからの脱出
しかしこのような「クールなやり方」は決してインターネットでは出来ないだろう。 ぼくらは薄々気づき始めているが、インターネットにはそのシステム自体に欠陥がある。リンクシステムが、情報のシェアを容易にしすぎたため、一人ひとりが考えることを放棄し始めたのだ。このような社会では父やマルコムXのような革命家気質の強力な個人はお呼びではない。むしろ自分では考えず、薄い情報をまき散らし続けるような人間(インフルエンサー)が影響力を持つ。集団主義の時代だ。多数派はポリティカル・コレクトネス一神教を盾に、他のあらゆるマイノリティが、自分の力で立ち上がろうとする膝を折ろうとする。「『黒は美しい』なんて言わなくていいの、黒も白もなく、みんな平等なの」と。それは「ブラックの血が流れていることに誇りを持つな」と言っているに等しいということに、彼らは気づかない。その考えは、ぼくには、すべての人間を根無し草にしようとしているようにすら思える。そうしてこのように作られた一見当たり障りのない「正論」が、「拡散」機能によって無限に増殖してゆくのだ。
抵抗する方法がある。全てのリンクを一度切ってしまえばいい。インターネットには「罪」もあるが、それ以上の「功」がある。インターネットは個人の発信したいという欲望を爆発させ、流通経路を用意し、個人が本をつくるハードルを劇的に下げた。だったらもう一度紙の本にすればいい。紙の本にはRTもシェアもない。ただ、一対一の読者と書き手がいるだけだ。書き手は読者に差し迫ってくる。逃げ場はどこにもない。RTして他人に共感を求めることはできない。目の前の相手と一対一で対峙するしかない。もしも読んでいて、本当に思うところがあるならば、自分で、自分なりのやり方で発信するしかない。やり方は文章でも動画でも音楽でもなんでもいい、ただ自分だけの力で、やり遂げるしかない。
ぼくはアナタと一対一で話したいのだ。隣の誰かに「ねーどう思う?」なんて聞いてほしくない。ぼくは今、他ならぬアナタと話しているのだ。(了)
1 note
·
View note
Text
詩集「十代プリズム」

詩集「十代プリズム」
1.子供時代
2.夢想少女
3.家出少年
4.最終遊戯
5.満員電車
6.夢遊する泡沫
7.政治家たちのナイトクラブ
8.群衆の断末魔(Heart to Heart)
9.杭
10.大丈夫の呪文
11.嫌いな人との付き合い方
12.21XX -オーサカ狂想曲-
13.シースルー・エモーション
14.ラブ・カルチャー
15.二人は恋人同士
16.混沌と瞑想のポピュリズム
17.詩人の生息地
18.青春プリズム
______________________________________________________________________
1.「子供時代」
艶やかに燃える
あの頃の思い出
大切なのは自分の意志だ
湧き上がる欲望だ
純粋だった頃の僕にはもう戻れない
だけど今できるのは
夢へ走ることだけさ
後悔なんてしたくない
だから頑張れる
嵐のように過ぎ去った青春の日々
もう遅すぎると懺悔を繰り返し
いつしか僕たちは大人になってしまった
子供時代を思い出す度に涙が止まらなくなる
それでも立ち止まってちゃ何も始まらない
君は君のままで走り出すしかない
艶やかに燃える
あの頃の思い出
大切なのは自分の意志だ
燃え上がる欲望だ
僕たちは社会の歯車として生きている
今できる精一杯(ぜんりょく)を
愛する人のためにぶつけて
せめて子供時代の自分を裏切らぬよう
理不尽に耐えて ただ生きている
希望がなくとも ただ生きている
愛する人の笑顔のために
愛がなくちゃ ただの歯車さ
愛があるから 生きている価値がある
価値なんて自分で創造するものだ
誰かに認められるものじゃないのさ
自分の道くらい自分で決めればいいさ
誰かが決める人生なんてつまらないじゃんか
そんな当たり前さえ僕らは忘れてしまった
大人になった僕たちはゾンビのように生きている
まるで魂を抜き取られたかのように
無表情で社会(マクロ)の一匹として生きている
未来なんて 明日なんて 今日があればそれでいい
画面が友達さ 空想が友達さ 友達なんて何処にもいない
現代社会の縮図
艶やかに燃える
あの頃の思い出
大切なのは自分の意志だ
燃え上がる欲望だ
僕が僕でいることだ
純粋だった頃の僕にはもう戻れない
だけど今できるのは
夢へ走ることだけさ
後悔なんてしたくない
だから頑張れる
涙なんて拭いて 悲しみも吹き飛ばせ
嵐のように変化する 現代(いま)をまっすぐに生きてゆけ
大人たちの声に耳を塞いでいいんだ
子供時代のように自分だけを信じて生きろ
生きているだけで価値なんて生まれない
価値は自分自身で創り出すものなのさ
これは自分という名の物語の始まりに過ぎない
2.「夢想少女」
何かにかぶれて 誰かに紛れて
いつかに怯えて 目線を逸らして
時代に遅れて 泣き出して
夢の中でしか自分になれない少女たち
君はまるで操り人形
操られることでしか主張できない
心棄ててる
何かが駆け出し 誰かが叫んで
いつかが始まり 目線は何処かへ
時代は変わった 涙も枯れた
夢と現実の狭間で絶叫する少女たち
お前はまるでピエロのよう
いろんなカルチャー着せ替えて
自分で何にも出来ないくせに
生意気ばっか言ってんじゃねえ
大人の本音
何かを信じて 誰かに任せて
いつかを願って 目線に入らず
時代に流され 絶望し
再び夢の中で妄想する少女たち
少女を彩るのは
安物のリップクリームと石油仕立てのコスチューム
夢想少女(きみ)は何処へいく??
3.「家出少年」
大人になりたくない
子供のままでもいたくない
大人と子供の境界線
あと少しだけ駄々を捏ねさせてよ
大人は理解ってくれない
子供の蒼い主張(ビート)を
大人と子供の境界線
あと少しだけ子供のままでいさせてよ
だから 僕は家出をしたのさ
片道切符と下着忍ばせ
君の元へ向かうぜ
もう僕は自由なのさ!
大人は自分勝手さ
「子供の癖に生意気だ」って言う
大人と子供の上下関係(ヒエラルキー)
あと少しだけ背伸びさせてよ
大人が何かを主張(ビート)する
子供はそれに追従(グルーヴ)する
大人と子供の上下関係(ヒエラルキー)
あと少しだけ歯向かわせてよ
だから 僕は不良になったのさ
往復切符と教科書(テキスト)忍ばせ
君の元へ向かうぜ
もう僕は自由なのさ!
何でもかんでも否定されてばかりじゃ
何にも言えなくなって
僕は僕を見失う そうなってしまう前に……
だから! 僕は独りになったのさ
両手に覚悟と夢を忍ばせ
君の元へ向かうぜ
君だけのために走るぜ
もう僕は自由なのさ!
もう僕は自由なのさ!!
4.「最終遊戯」
独りを過剰に怖がり
誰かと群れることがすべてだと
そう声高らかに宣言する君は
本当に人間かい?
「生きろ」
「死ぬな」
「生きてることに価値がある」
大人はいつも無責任
子供はいつも無計画
虚無に放り出された frustration
夢幻に放り込まれた satisfaction
僕らは今何処で何をしているのだろう?
何のために生きているのだろう?
僕らは今何処で何をしているのだろう?
何のために生きているのだろう?
「諦めるな」
「今を大切にしろ」
「夢を持て」
うるせえんだよ
ふざけんなよ
消えちまえよ
声なき叫びがこだまして
君は君でいられなくなる
けたたましく響く vibration
ぬくもり求める communication
君は今何処で何をしているのだろう?
何のために生きているのだろう?
嵐の中に放り出された 一欠片のmoral
刹那の中に放り込まれた 孤独のfunny girl
大人にすべてを依存して
行く先さえも決められない
それが現代の私たち 私はただの子羊さ
5.「満員電車」
ちょっと、そこの君。
そんなに座ることに拘らなくたっていいじゃん
座って何が得になるの?
人生変わるの??
少年のまっすぐな瞳が胸に突き刺さる
いつしか、僕らは純粋な心を忘れてしまった。
ずっとずっと少年のままでいようと約束したのに
今や永遠のスパイラルの中で生きている
孤独の中で生きている
たかが三十分、されど三十分。
イヤホンを付けた君は本当に大切なものに気付かずに
耳の中を流れる音楽にただ夢中で
運命の出逢いさえも流れていってしまうんじゃないか
そんな気すらもしてしまうよ
結局、
僕らは猿に逆戻りしているんじゃなかろうか
人間であることを放棄しているんじゃなかろうか
人が人である証拠は感情を言葉にできることだ
しかし、
今の人はそれを極端に恐れている
もしも、満員電車の中で。
わたしがわたしであることに満足して
あなたが他の誰かにもし入れ替わっていたとしても
わたしはそれをあなたとして認識するのだろう
それが人間ってやつさ
少年はつぶらな瞳で真実を見つめている
6.「夢遊する泡沫」
今日も僕は宇宙旅行を続けている
希望と失望と絶望を携え
誰とも理解らない誰かのために闘っている
闘いは誰のためにあるものなのか
答えさえも理解せず
あるはずのない永遠を信じて闘っている
僕らは何のために生きているのだろう
そもそも 何故生きているのだろう
哲学的思索の果てに
夢幻世界で夢遊を続ける泡沫たち
朝から 真昼間から 夕方から
その拠り所は知らないが
とにかく 誰かのために闘っていることだけは確かだ
時代は変わり 運命も変わり続けてゆく
そんな過去と未来のコンツェルトに翻弄され
僕らは夢遊する泡沫として生命を紡いでいる
あゝ 何故生まれてきてしまったのか
何処かで大男が叫んでいる
恨めしい声で叫んでいる
最終電車が堂々と通り過ぎた頃
見えない誰かが線路上で踊っている
生きろ 生きろ 生きろ
誰かが呪文のように唱えている
7.「政治家たちのナイトクラブ」
君が誰かなんて関係ない
ただ闇雲に踊り明かそう
片手にドンペリ 片手にシャンパン
お酒の力でノーサイド
あんなこと言ってゴメンね
敵も味方もない夜だから
大人同士のカンバセーション
「好きだよ」弾む会話
今日の主役は私たち
国民なんてどーでもいい
明日も主役は私たち
またあの場所でヨロシクね!
何を言ったかなんて関係ない
ただ頓狂に語り明かそう
片手に印鑑 片手にFAX
時代なんて気にしない
こんなこと言ってゴメンね
愛も希望もない世界(くに)だから
子供のように笑わせて
「好きだよ」皮肉な言葉(こえ)
今日の主役は私たち
国民なんてどーでもいい
明日も主役は私たち
またあの場所でヨロシクね!
くれぐれもお手柔らかに!!
いつも主役は私たち
今が良ければそれでいい
明日も主役は私たち
スーツは素性を隠す仮面
今日の主役は私たち
国民なんてどーでもいい
明日も主役は私たち
またあの場所でヨロシクね!
ここは政治家たちのナイトクラブ
8.「群衆の断末魔 -Heart to Heart-」
今日も群衆の真ん中で
悲しいニュースがスキップをしている
愛なんて、独りなんて、と喚きながら
傍観者たちはただ感情論に走っている
怒りをぶつけようにもぶつける場所がない
だったら周りの誰かにぶつけてしまえばいいじゃない
自分じゃない自分がまるで悪魔のように囁く
解決策も見出せないのに
慈しむだけのあなたに何ができるのだろう?
心と心を付き合わせ
変えようのない昨日よりも
どんな風にだって変えられる明日を変えることが
どれだけ有意義なことなのか何故わからないのだろう??
夢は夢の中で言えばいい
独り言は独り言のままでいい
屁理屈なんて言わないで
被害者を減らすたったひとつの方法は
加害者を生まないようにすればいいんだ
そうすればもう誰も悲しまなくて済むんだ
ゼロになるまで考えろ
誰かのために心と心を付き合わせ
ゼロになるまで考えろ
それがきっと僕らにできる唯一のこと
傍観者にできる唯一のこと
泣かなくてもいい 寄り添わなくてもいい
そっと手を差し伸べてあげられる勇気があればそれで十分だ
9.「杭」
僕が生きている
世界は狭すぎて
大事なことさえ
何も見えないよ
群衆の中に潜む
静かな時代の風
求められるのは忠順さ
個性などは要らない
世界を知らない子供(ひと)に
大人(きみ)は正義ぶって
世の掟(きまり)を教えようなんて
口癖(ルーティン)のように言う
ぶち壊せ!
何もかも、変えてしまえ。
走り出せ!
どんな声も、耳を塞げばいい。
大切なのはその意志さ
出過ぎた杭は打たれない
君が生きている
世界は広すぎて
嫉妬心すら
感じてしまうよ
ビル群の影に隠れて
いつも君は泣いている
常識が口癖さ
大人はつまらないよ
外界(せかい)を知らない子供(ひと)に
大人(きみ)は大人ぶって
外界(せかい)はつまらないよなんて
わかりきったように言う
ぶち壊せ!
何もかも、変えてしまえ。
走り出せ!
どんな声も、耳を塞げばいい。
大切なのはその夢さ
出過ぎた杭は打たれない
だから思いっきりはみ出そう
ぶち壊せ!
何もかも、変えてしまえ。
走り出せ!
どんな声も、耳を塞げばいい。
大切なのはその意志さ
出過ぎた杭は打たれない
だから思いっきりはみ出そう
10.「大丈夫の呪文」
気安く言わないでよ
うるせえんだよ
何度も、何度もさあ、
私だって言うときゃ言うよ
ロボットじゃないんだから
人間なんだから
画面の向こう側にいるからって
なんでも言っていいと思ったら大間違い
私は私なの、わかる?
ずっと泣いてるし、ずっと怒ってる、
やり場のない感情をどこにもぶつけられず
誰かの言葉に怯え
誰かの行動に身構え
後ろ指を指されないように透明人間を演じてるの
目立たないことが正義なんでしょ?
制服はきっちり着てほしいんでしょ??
わかるよ、黒髪のままでいてほしいって
ほんとはそう思ってるよね
私だってあなたの言いたいことくらいわかる
全部お見通しよ、女の子を舐めないでよ
……ちょっとくらい好きにさせてくれたっていいじゃん
11.「嫌いな人との付き合い方」
現代は「キライ」と言いづらい世の中だ。
「キライ」という言葉はどうしても角が立つ。
でも、やっぱり「キライ」なものは「キライ」だ。
「キライ」なものを「スキ」って言うのは難しい。
そういうもんだ。
「だってさ、キライなんだぜ?」
「キライなのにスキっていうほど面白くないものはないよなあ」
ちょっと気取って言ってみる。
現代は「キライ」と言ってはいけない世の中だ。
「キライ」という言葉よりも「フツウ」という言葉の方が好まれる。
だが、「フツウ」はやっぱり「フツウ」だ。
「フツウ」という言葉ほど曖昧なものはない。
もっと言えば、馬鹿馬鹿しい。
「そのマヌケヅラを何とかしろよ?」
「君は二文字の言葉さえ躊躇するのかよ」
言葉にそう言われているような気さえしてくる。
ばーかばーか。
絶対現実では言えないけれど、
布団の中では声を大にして叫べそうだ。
夢の中で、僕は毒舌になる。
臆病者の独演会、今夜も始まる。
12.「21XX -オーサカ狂想曲-」
数十年前、関西弁は消滅した。
すべてはひとつの言葉に統一され、
見知らぬネオンが街を支配し、
僕が僕を認識できなくなる。
お好み焼きも、たこ焼きも、どこへ行ってしまったのだろう。
日本食はとっくの昔に放棄され、
食糧不足のこの国に残されたのは、
ご飯のような無味無臭のなにか。
美味しくもなければ、不味くもない。
僕は何も感じない食事を済ませ、
ダイスほどの荷物を纏め、
メトロポリスを跡にした。
ここはいつから、こんな砂漠になってしまったのだろう。
最新式の方位磁石に目を凝らし、
まるで一ミリメートルの糸を手繰るかのように、
砂漠の都会(まち)を進んでゆく。
どんなに頑張っても、夢なんて掴めっこないんだ。
胸に刻まられた消えない証が、
僕の好きに生きたいという欲望を、
永遠に不可能のまま葬ってしまう。
逃げたい、逃げられない、逃げようもない。
好きな人も、守るべき家族も、
誰かによって紡がれた石碑も、
みんな何処かへ行ってしまった。
環状線跡のスラム街に足を踏み込む。
明朝八時、
僕の最後の冒険は高らかに幕を開ける。
生きるために、最後の闘いを始めよう。
13.「シースルー・エモーション」
これ着けてごらんよ。
今流行りの、何もかも御見通しってやつ。
ほら、タダであげるからさ。
「えっ、いいの?」
少年はぎょっとした瞳でこちらを見た。
何か続けなきゃなと思い、私は必死に言霊とやらを膨らませた。
みんな、近いうちに必ず着け始めるから。
これさえ持っていれば、君も流行を先取りできるよ。
遠慮なんていらない。
さあ、早く着けなよ。
「でも。知らない人にモノを貰っちゃいけないって言われてるんだ」
私はよく教育された少年だな、と思った。
だけど、これを売らないと私は殺されてしまう。
命が懸かっているんだ。
お願い、これを受け取って。
私からの一生のお願い。
幸せになれる。
ほら、開運のおまじないだと思ってさ。
「わかった。貰ってあげる」
『良い子だ』
……思わずそう言いそうになった。
いけない。
少年の前ではこの言葉は禁句だ。
これを言った瞬間、あどけない表情は怪訝な瞳に変貌する。
私は未来人として、このメガネを売らなければならない。
たとえ、そのメガネが何の変哲もないタダのメガネだったとしても。
私は私の仕事をするだけさ。
14.「ラヴ・カルチャー」
恋そのものが軽くなっている、
と、誰かが言った。
いつでもどこでも出逢えて、
誰とでも恋ができる。
手紙を送り会わなくても、
文通を繰り返さなくても、
パッと手を伸ばせば、
君を抱きしめることだってできる。
それが、
現代のラブ・カルチャー。
大人たちに何かを言われる筋合いなんてないし、
私たちは私たちのコミュニティをつくっている。
それが自由の正しい使い方であって、
真のクリエイティビティと言えるだろう。
愛と、理想と、希望を掲げて。
僕らは夢を叫び続けている。
15.「二人は恋人同士」
今年の夏が待ち遠しいよ
キミと一緒につくろう
最高の思い出を
夏のビーチに水着姿の彼女
いつもと違うメイクに
とびきりの笑顔を
キミと過ごした夏
世界色にきらめいてる
あの日の記憶(メモリー)
ずっと続かないかな
二人だけの素晴らしき日々
いつか歳を重ね
思い出 色褪せたとしても
僕たちはずっと一緒だよ
青春は終わらせない
夏の訪れに張り切る海岸線
半袖のTシャツに
とびきりの時めきを
キミと過ごした夏
貴女色に輝いている
最高の思い出を
どうか終わらないで
二人だけの素晴らしき時間(とき)
いつか歳を重ね
今日(いま)がセピア色になっても
僕たちはずっと一緒だよ
青春は終わらせない
いつか歳を重ね
思い出 色褪せたとしても
僕たちはずっと一緒だよ
青春は終わらせない
キミと最高の思い出を……
16.「混沌と瞑想のポピュリズム」
貴方を惑わす置き手紙
もううんざりよ その微笑(えがお)には
心残りは結ばれなかったこと
きっと貴方はそう呟くでしょう
混沌と瞑想のポピュリズム
貴方は夢を見ているの
混沌と瞑想のポピュリズム
愛を知らぬ貴方にお似合いね
混沌と瞑想のポピュリズム
独身貴族は愛を知らない
悩ましく囁く愛の言葉
もううんざりよ 嘘つきには
「貴女に出逢って良かった」なんて
紳士気取りはもう止めてよ
混沌と瞑想のポピュリズム
私も夢を見ていたのかもしれない
混沌と瞑想のポピュリズム
嵐の前の静けさよ
混沌と瞑想のポピュリズム
涙は愛の渇望(リクエスト)
見つめ合い抱きしめ合い接吻(くちづけ)交わせば
誰でも虜に出来るなんて
貴女の口癖 独身貴族の悪い癖
混沌と瞑想のポピュリズム
誰もが夢を見ているの
混沌と瞑想のポピュリズム
ずぶ濡れになりながら君は泣いている
混沌と瞑想のポピュリズム
混沌と瞑想のポピュリズム
独身貴族は愛を知らない
17.「詩人の生息地」
何をしていても、何処にいても、何故だか落ち着かない。
そんな日々が続くと、人は不安になる。
得体の知れない何かに常に追いかけられているような、
哀しみとも言えない感情に支配されているような、
とにかく、ネガティヴな気分になってしまう。
好きな人なんて、もういらない。
そう高らかに宣言したはいいけれど、結局恋を求めるのが人の性分。
愛と、夢と、希望があって、やっと半人前。
独りでいるだけで、世間からは白い目で見られているように感じる。
本当は独りが好きなのに、本当は独りでいたいのに。
これが同調圧力ってもの。
カフェテリアに、今日も誰かのヴォイス・アンサンブルが聞こえる。
その隙間で、息苦しそうに言葉を紡ぐひと。
それが詩人という生き物だ。
18.「青春プリズム」
屈折する、
感情も、行動も、何もかも。
挫折する、
夢も、目標も、何もかも。
愛なき時代とは言わないけれど、
今の時代に希望なんてない。
何もせず、
何かを始めようとするわけでもない、
そんな奴に希望なんて叫んでほしくない。
僕らに芽生えた反抗心は、
ひとつの青春プリズムを産み落とすこととなった。
かつて、大人にその力で反抗しようとした学生たちのように。
表面的には沈静化したつもりでも、
学生たちにはずーっと芽生え続けている。
大人にもなれず、子供にもなれない。
ジレンマが僕たちを大人にする。

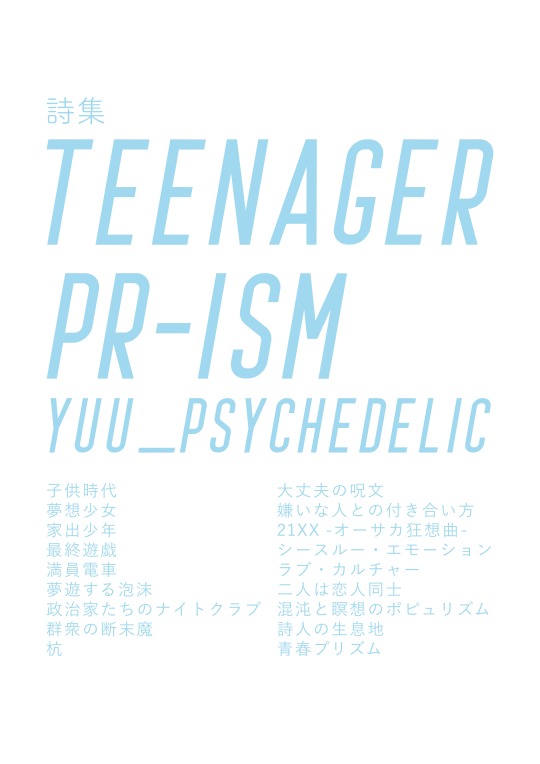
あとがき「わたしの十代プリズム」
わたしたちは十代プリズムで屈折する。
内面的にも、外面的にも。
屈折しないと学べないことがいっぱいある。
ずっと楽しいまま生きられる人なんていない。
十代のわたしたちにとって、この世界は狭すぎるのだ。
なぜ、校則を守らなければならないのだろう。
どうして、就職活動の際にスーツを着なければならないのだろう。
わたしたちの素朴な疑問は、いつしか多忙に相殺されていく。
こうして、ティーンエイジャーたちは諦めるという言葉を知る。
要するに“挫折”を知ってしまうのだ。
挫折を知ってしまった人々は、もうまっすぐに生きてはいけない。
何をしようとも、屈折して生きるしかない。
わたしは四ヶ月後に十九歳になる。
あれだけ長いはずの十代が終わりを迎えようとしている。
「十代って、素晴らしいものだ」
十代になった頃、わたしはそう思っていた。
でも、それは半分正解で、半分間違っていた。
この詩集はわたしの十代の記録だ。
何処かがフィクションで、何処かがノンフィクション。
わたしは十代に入って、ようやく物心がついた。
誰かに指示されるのではなく、自分で考えることを学んだ。
多くの挫折を経験し、多くの絶望を味わった。
今も決して希望が見えているとは言えない。
だからこそ、書けた作品である。
逆説的に言えば、今しか書けない作品とも言えるだろう。
わたしにとって「創作」とは、ライフワークそのものだ。
恋人でも、親友でも、捉え方は好きにしてもらって構わない。
でも、ひとつだけはっきりしていることがある。
十代に創作という分野に出逢えて、本当に良かった。
たくさんの人に迷惑をかけ、多くの人を失望させてしまった。
過去はもう変わらないし、変えられない。
だけど、今から何かを変えることは可能だ。
物語という白紙のキャンバスに、無限の世界を描いていく。
その道筋の中で、誰かの人生を変えることだってできる。
あなたも何か描いてみたらいい。
みんなも、創作しよう。
いじめたり、いじめられたり、嫌なこともたくさんあった。
でも、いつもそばには創作がいた。
だから、今音楽大学で夢を追いかけられているし、ここで生きている。
最後に、あとひとつだけ。
不器用で、どうしようもなくって、文章も大して上手くはない。
話をすれば散らかり放題だし、ボソボソ喋るからみんなを困らせてばかり。
こんなわたしを支えてくれてありがとう。
ちょっとずつ直していこうと思っています。
これまで出逢ったすべての人々、これから出逢うすべての人々に感謝の意を込めて。
ありがとう。本当にありがとう。
これからもよろしくね。
詩集「十代プリズム」
Produced by YUU_PSYCHEDELIC
Concept Created and Designed by UYUNOONUYU(ウユノユウ)
Written by Yuu Sakaoka
Special Thanks to My Family,my friends and all my fans!!
YUU_PSYCHEDELIC
#詩#詩集#創作#YUU_PSYCHEDELIC#十代#青春#キリトリセカイ#teenager#poetry#youth#youthculture#art#modern art#poem#若者#アート
1 note
·
View note
Photo

時間差投稿です🙇 GOWARINGO2023🍎の留こうじ【日本酒の仕込みは、添→仲→留と3日間に分けて、蒸した米と水とこうじをタンクへ入れて混ぜ合わせていきます🍶その3日目のこうじ】が完成しました😊 もっとツキハゼ【米の表面の菌糸を抑えること】でも良かったのかな😌次回の課題です😊 #創業1853年 #始まりが伝統になる一滴入魂の蔵 #岩清水の如く澄んだ味わい #理屈抜きで美味しい個性ある日本酒 #ワイングラスで美味しい日本酒 #食事とのペアリングを意識した酒造り #麹割合を変化させた酒造り #低アルコール日本酒 #無濾過生原酒 #ペアリングと言えば岩清水 #完熟麹 #完熟醪 #じっくりと時間をかけて #丁寧にていねいに #テロワール #減農薬栽培米 #減化学肥料栽培米 #井戸水 #超軟水 #日本一生産量の少ない酒蔵 #夫婦二人で醸す #厳しい品質管理 #マイナス5度で瓶貯蔵 (井賀屋酒造場) https://www.instagram.com/p/CoHr1igyDyn/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#創業1853年#始まりが伝統になる一滴入魂の蔵#岩清水の如く澄んだ味わい#理屈抜きで美味しい個性ある日本酒#ワイングラスで美味しい日本酒#食事とのペアリングを意識した酒造り#麹割合を変化させた酒造り#低アルコール日本酒#無濾過生原酒#ペアリングと言えば岩清水#完熟麹#完熟醪#じっくりと時間をかけて#丁寧にていねいに#テロワール#減農薬栽培米#減化学肥料栽培米#井戸水#超軟水#日本一生産量の少ない酒蔵#夫婦二人で醸す#厳しい品質管理#マイナス5度で瓶貯蔵
0 notes
Text
呑まれる
ギタリストの指先は、本当に硬いんだろうか。 スタジオの鍵をまわしつづける夏紀の指が目線の先にみえかくれすると、ふとそんな話を思い出す。ペンだこが出来たことを話す友人のことも。肩の先にぶらさがったなんでもない手を目にやっても、そこに年季のようなものはうかんでこない。どうやら、私はそういうものに縁がないらしい。 夏紀の予約した三人用のスタジオは、その店の中でも一番に奥まった場所にあった。慣れた様子で鍵を受け取った夏紀のあとを、ただ私は追いかけて歩いている。カルガモの親子のような可愛げはそこにはない。ぼんやりと眺めて可愛がっていたあの子どもも、こんな風にどこか心細くて、だからこそ必死に親の跡を追いかけていたんだろうか。なんとなく気恥ずかしくて、うつむきそうになる。 それでも、しらない場所でなんでもない顔をできるほど年をとったわけじゃなかった。駅前で待ち合わせたときには開いていた口も、この狭いドアの並ぶ廊下じゃ上手く動いてくれない。聞きたいことは浮かんでくるけれど、どれも言葉にする前に喉元できえていって、この口からあらわれるのはみっともない欠伸のなり損ないだけだ。 「大丈夫?」 黙り込んだ私に夏紀が振り向くと、すでに目的地にたどり着いていた。鍵をあける前の一瞬に、心配そうな目が映る。なんでもないよ、と笑ったつもりで口角を上げた。夏紀が安心したようにドアに向き直ったのを見て、笑えてるんだとわかった。少し安心した。 ―――――― 「ギターを、教えてほしいんだけど」 「ギターを?」 「うん」 あのとき私がねだった誕生日プレゼントは、夏紀のギター教室だった。 その言葉を口にしたとき、急にまわりの席のざわめきが耳を埋めた。間違えたかな、と思う。あわてて取り繕う。 「無理にとは言わないし、お金とかも払うから」 「いや、そういうのはいいんだけど」 私の急なお願いに、夏紀は取り残���れないようにとカップを掴んだ。言葉足らずだったと反省する私が続きを投げるまえに、夏紀は言葉を返してくる。前提なんだけど、と、そういう彼女に、私はついにかくべき恥をかくことになると身構えた。 「希美、ギター、持ってたっけ?」 「この前、買っちゃって」 「買っちゃって?」 夏紀の眉間の皺は深くなるばかりだった。一緒に生活していると、こんなところも似てくるのかと思う。今はここにいない友人の眉間を曖昧に思い出しながら、たりない言葉にたしあわせる言葉を選びだす。 「まあ、衝動買いみたいな感じで」 「ギターを?」 「ギターを」 私が情けなく懺悔を――もっと情けないのはこれが嘘だということなのだけれど――すると、夏紀はひとまず納得したのか、命綱のようににぎりしめていたカップから手をはなした。宙で散らばったままの手は、行き場をなくしたようにふらふらと動く。 「なんか、希美はそういうことしないと思ってたわ」 「そういうことって?」 「衝動買いみたいなこと」 夏紀はそういうと、やっと落ち着いたかのように背もたれに体を預けなおした。安心した彼女の向こう側で、私は思ってもいない友人からの評価に固まる。 「え、私ってそういう風にみえる?」 「実際そんなにしたことないでしょ」 「まあ、そうだけど」 実際、あまり経験のないものだった。アルコールのもたらした失敗を衝動買いに含めていいのかはわからないけれど、今まで自分の意図しないものが自分の手によって自分の部屋に運び込まれることは確かになかった。 そういう意味でも、私はあのギターを持て余していたのかもしれない。ふとしたことで気がついた真実に私は驚きながら、曖昧に部屋の記憶を辿っていく。社会に出てから与えられることの多くなった「堅実」という評価を今まで心の中で笑い飛ばしていたけれど、こういうところなのか。ちっとも嬉しくない根拠に驚く。 一度考え始めると、それは解け始めたクロスワードパズルのように過去の記憶とあてはまっていく。私が埋めることの出来ない十字に苦戦している間に、夏紀はとっくに問題から離れて、いつものあの優しい表情に戻っていた。 「教えるぐらいなら、全然構わないよ」 拠り所のようなその笑顔に、私は慌てて縋る。答えのない問に想いを馳せるには、この二人掛けはあまりにも狭すぎた。 「ありがと。買ったはいいけど、どう練習すればいいのかとかわからなくて」 「まあそういうもんだよねぇ」 こういうところで、ふと柔らかくなった言葉の選び方を実感するのだ。それはきっと過ぎた年月と、それだけではない何かが掛け合わ��って生まれたもので。そういった取り留めのない言葉を与えられるだけで、私の思考は迷路から現実へ、過去から今へと戻ってくる。 スマートフォンを取り出して予定を確認していたらしい夏紀から、幾つかの日付を上げられる。 「その日、みぞれと優子遊びに行くらしいんだよね」 「そうなの?」 「そう、で、夜ご飯一緒にどうかって言われてるから、土曜の午後練習して、そっから夜ご飯っていうのはどう?」 日本に戻ってくるとは聞いていたけど、その予定は初耳だった。年末年始はいつもそうだということを思い出す。いつの間にか、そうやってクリスマスやバレンタインのようになんでもない行事のようになるかと思うと、ふと恐ろしくなった。 「大丈夫」 「オッケー。じゃあ決まりね」 ―――――― 「そういや、ギター何買ったの?」 「ギブソンレスポールのスペシャル」 「えっ」 いつ来るかと待ち構えていた質問に、用意した答えを返した。準備していたことがわかるぐらい滑らかに飛び出したその言葉に、なんだか一人でおかしくなってしまう。 私の答えに、夏紀は機材をいじる手を止めて固まった。ケーブルを持ったままの彼女の姿におかしくなりながら、黒いケースを剥がして夏紀の方に向けると、黄色のガワはいつものように無遠慮に光る。 「イエロー、ほらこれ」 「えっ……、いい値段したでしょ。これ。二十万超えたはず」 「もうちょっとしたかな」 「大丈夫なの?衝動買いだったんでしょう?」 「衝動買いっていうか、うん、まあそうね」 私の部屋にギターがやってきた真相を、夏紀の前ではまだ口にしていない。どうしようもなさを露呈する気になれなかったのもあるけれど、酷くギターに対して失礼なことをしている自覚を抱えたまま放り出せるほど鈍感ではいられなかったから。結局嘘をついているから、どうすることもできないのだけど。一度かばった傷跡はいつまでも痛み続ける。 「あんまこういう話するの良くないけど、結構ダメージじゃない?」 「ダメージっていうのは?」 「お財布っていうか、口座に」 「冬のボーナスが飛びました」 「あー」 「時計買い換えるつもりだったんだけど、全部パー」 茶化した用に口に出した言葉は、ひどく薄っぺらいものに見えているだろう。欲しかったブランドの腕時計のシルバーを思い出していると、夏紀にアンプのケーブルを渡された。 「じゃあ、時計分ぐらいは楽しめないとね」 そういう夏紀が浮かべる笑みは、優しさだけで構成されていて。私は思わずため息をつく。 「夏紀が友達で本当に良かったわ」 「急にどうしたの」 心から発した言葉は、予想通りおかしく笑ってもらえた。 夏紀がなれた手付きで準備をするのを眺めながら、昨日覚えたコードを復習する。自分用に書いたメモを膝に広げても、少し場所が悪い。試行錯誤する私の前に、夏紀が譜面台を置いた。 「練習してきたの?」 「ちょっとね」 まさか、昨日有給を取って家で練習したとは言えない。消化日数の不足を理由にして、一週間前にいきなり取った休暇に文句をつける人間はいなかった。よい労働環境で助かる。 観念して取り出したギターは、なんとなく誇らしげな顔をしているように見えた。届いたばかりのときのあのいやらしい――そして自信に満ちた月の色が戻ってきたような気がしたのは、金曜の午前中の太陽に照らされていたからだけではないだろう。 ただのオブジェだと思っていたとしても、それが美しい音を弾き出すのは、いくら取り繕っても喜びが溢れる。結局夜遅くまで触り続けた代償は、さっきから実は噛み殺しているあくびとなって現れている。 「どのぐらい?」 「別に全然大したことないよ。ちょっと、コード覚えたぐらいだし」 幾つか覚えたコードを指の形で抑えて見せると、夏紀は膝の上に載せたルーズリーフを覗き込んだ。適当に引っ張り出したその白は、思ったより自分の文字で埋まっていて、どこか恥ずかしくなる。ルーズリーフなんてなんで買ったのかすら思い出せないというのに、ペンを走らせだすと練習の仕方は思い出せて、懐かしいおもちゃに出会った子どものように熱心になってしまった。 「夏紀の前であんまりにも情けないとこ見せたくないしさ」 誤魔化すようにメモを裏返すと、そこには何も書かれていなかった。どこか安心して、もう一度元に戻している間に、夏紀は機材の方に向き合っている。 「そんなこと、気にしなくてよかったのに」 そういう夏紀はケーブルの調子を確認しているようで、何回か刺し直している。セットアップは終わったようで、自分のギターを抱えた。彼女の指が動くと、昨日私も覚えたコードがスタジオの中に響く。 「おおー」 「なにそれ」 その真剣な目に思わず手を叩いた私に、夏紀はどこか恥ずかしそうに笑った。 「いやぁ、様になるなぁって」 「お褒めいただき光栄でございます。私がギター弾いてるところみたことあるでしょ」 「それとは違うじゃん。好きなアーティストのドキュメンタリーとかでさ、スタジオで弾いてるのもカッコいいじゃん」 「なにそれ、ファンなの?」 「そりゃもちろん。ファン2号でございます」 「そこは1号じゃないんだ」 薄く笑う彼女の笑みは、高校生のときから変わっていない。懐かしいそれに私も笑みを合わせながら、数の理由は飲み込んだ。 「おふざけはこの辺にするよ」 「はぁい」 夏紀の言葉に、やる気のない高校生のような返事をして、二人でまた笑う。いつの間にか、緊張は指先から溶けていた。 ―――――― 「いろいろあると思うけど、やっぱ楽器はいいよ」 グラスの氷を鳴らしながらそう言う夏紀は、曖昧に閉じられかけた瞼のせいでどこか不安定に見える。高校生の頃は、そういえばこんな夜遅くまで話したりはしなかった。歳を取る前、あれほど特別なように見えた時間は、箱を開けてみればあくまであっけないことに気がつく。 私の練習として始まったはずの今日のセッションは、気がつけば夏紀の演奏会になっていた。半分ぐらいはねだり続けた私が悪い。大学生のころよりもずっと演奏も声も良くなっていた彼女の歌は心地よくて、つい夢中になってしまった。私の好きなバンドの曲をなんでもないように弾く夏紀に、一生敵わないななんて思いながら。 スタジオから追い出されるように飛びてて、逃げ込んだように入った待ち合わせの居酒屋には、まだ二人は訪れてなかった。向かい合って座って適当に注文を繰り返している間に、気がついたら夏紀の頬は少年のように紅く染まっていた。 幾ら昔に比べて周りをただ眺めているだけのことが多くなった私でも、これはただ眺めているわけにはいかなかった。取り替えようにもウィスキーのロックを頼む彼女の目は流石に騙せない。酔いが深まっていく彼女の様子にこの寒い季節に冷や汗をかきそうになっている私の様子には気づかずに、夏紀はぽつりぽつりと語りだした。 「こんなに曲がりなりにも真剣にやるなんて、思ってなかったけどさ」 そうやって浮かべる笑いには、普段の軽やかな表情には見当たらない卑屈があった。彼女には、一体どんな罪が乗っているんだろう。 「ユーフォも、卒業してしばらく吹かなかったけど。バンド始めてからたまに触ったりしてるし、レコーディングに使ったりもするし」 ギターケースを置いたそばで管楽器の話をされると、心の底を撫でられたような居心地の悪さがあった。思い出しかけた感情を見なかったふりをしてしまい込む。 「そうなんだ」 窮屈になった感情を無視して、曖昧な相槌を打つ。そんなに酔いやすくもないはずの夏紀の顔が、居酒屋の暗い照明でも赤くなっているのがわかる。ペースが明らかに早かった。そう思っても、今更アルコールを抜いたりはできない。 「まあ一、二曲だけどね」 笑いながら言うと、彼女はようやくウィスキーの氷を転がすのをやめて、口に含んだ。ほんの少しの間だけ傾けると、酔ってるな、とつぶやくのが見えた。グラスを置く動きも、どこか不安定だ。 「まあ教本一杯あるし、今いろんな動画あがってるし、趣味で始めるにはいい楽器だと思うよ、ギターは」 「確かに、動画本当にいっぱいあった」 なんとなくで開いた検索結果に、思わず面食らったのを思い出す。選択肢が多いことは幸せとは限らない、なんてありふれた言葉の意味を、似たようなサムネイルの並びを前にして思い知った気がしたことを思い出す。 「どれ見ればいいかわかんなくなるよね」 「ホントね。夏紀のオススメとかある?」 「あるよ。あとで送るわ」 「ありがと」 これは多分覚えていないだろうなぁと思いながら、苦笑は表に出さないように隠した。机の上に置いたグラスを握ったままの手で、バランスをとっているようにも見える。 「まあでも、本当にギターはいいよ」 グラグラと意識が持っていかれそうになっているのを必死で耐えている夏紀は、彼女にしてはひどく言葉の端が丸い。ここまで無防備な夏紀は珍しくて、「寝ていいよ」の言葉はもったいなくてかけられない。 姿勢を保つための気力はついに切れたようで、グラスを握った手の力が緩まると同時に、彼女の背中が個室の壁にぶつかった。背筋に力を入れることを諦めた彼女は、表情筋すら維持する力がないかのように、疲れの見える無表情で宙に目をやった。 「ごめん、酔ったっぽい」 聡い彼女がやっと認めたことに安堵しつつ、目の前に小さなコップの水を差し出す。あっという間に飲み干されたそれだけでは焼け石に水だった。この場合は酔っぱらいに水か。 くだらないことを浮かべている私を置いて、夏紀は夢の世界に今にも飛び込んでいきそうだった。寝かせておこうか。そう思った私に、夏紀はまだ心残りがあるかのように、口を開く。 「でも、本当にギターはいいよ」 「酔ってるね……」 「本当に。ギターは好きなように鳴ってくれるし、噛み付いてこないし」 「あら、好きなように鳴らないし噛み付くしで悪かったわね」 聞き慣れたその声に、夏紀の目が今日一番大きく見開かれていくのがわかった。恐る恐る横を向く彼女の動きは、スローモーション映像のようだ。 珍しい無表情の優子と、その顔と夏紀の青ざめた顔に目線を心配そうに行ったり来たりさせているみぞれは、テーブルの横に立ち並んでいた。いつからいたのだろうか、全く気が付かなかったことに申し訳なくなりながら、しかしそんなことに謝っている場合ではない。 ついさっきまで無意識の世界に誘われていたとは思えない彼女の様子にいたたまれなくなりながら、直視することも出来なくて、スマートフォンを確認する。通知が届いていたのは今から五分前で、少し奥まったこの座席をよく見つけられたなとか、返事をしてあげればよかったかなとか、どうにもならないことを思いながら、とにかく目の前の修���場を目に入れたくなくて泳がしていると、まだ不安そうなみぞれと目が合った。 「みぞれ、久しぶりだね」 前にいる優子のただならぬ雰囲気を心配そうに眺めていたみぞれは、それでも私の声に柔らかく笑ってくれた。 「希美」 彼女の笑みは、「花が咲いたようだ」という表現がよく似合う。それも向日葵みたいな花じゃなくて、もっと小さな柔らかい花だ。現実逃避に花の色を選びながら、席を空ける準備をする。 「こっち座りなよ」 置いておいた荷物をどけて、自分の左隣を叩くと、みぞれは何事もなかったかのように夏紀を詰めさせている優子をチラリと見やってから、私の隣に腰掛けた。 「いや、別に他意があるわけじゃ、なくてですね」 「言い訳なら家で聞かせてもらうから」 眼の前でやられている不穏な会話につい苦笑いを零しながら、みぞれにメニューを渡した。髪を耳にかける素振りが、大人らしく感じられるようになったな、と思う。なんとなく悔しくて、みぞれとの距離を詰めた。彼女の肩が震えたのを見て、なんとなく優越感に浸る。 「みぞれ、何頼むの?」 「梅酒、にする」 ノンアルコールドリンクのすぐ上にあるそれを指差したのを確認する。向こう側では完全に夏紀が黙り込んでいて、勝敗が決まったようだった。同じようにドリンクのコーナーを覗いている優子に声をかける。 「優子は?どれにする?」 「そうねえ、じゃあ私も梅酒にしようかしら」 「じゃあ店員さん呼んじゃおうか」 そのまま呼び出した店員に、適当に酒とつまみと水を頼む。去っていく後ろ姿を見ながら、一人青ざめた女性が無視されている卓の様子は滑稽に見えるだろうなと思う。 「今日はどこ行ってたの」 「これ」 私の質問に荷物整理をしていた優子が見せてきたのは、美術館の特別展のパンフレットだった。そろそろ期間終了になるその展示は、海外の宗教画特集だったらしい。私は詳しくないから、わからないけど。 「へー」 私の曖昧な口ぶりに、みぞれが口を開く。 「凄い人だった」 「ね。待つことになるとは思わなかったわ」 「お疲れ様」 適当に一言二言交わしていると、ドリンクの追加が運ばれてくる。小さめのグラスに入った水を、さっきから目を瞑って黙っている夏紀の前に置く。 「夏紀、ほらこれ飲みなさいよ」 優子の言葉に目を開ける様子は、まさに「恐る恐る」という表現が合う。手に取ろうとしない夏紀の様子に痺れを切らしそうになる優子に、夏紀が何か呟いた。居酒屋の喧騒で、聞き取れはしない。 「なによ」 「ごめん」 ひどくプライベートな場面を見せられている気がして、人様の部屋に上がり込んで同居人との言い争いを見ているような、そんな申し訳のなさが募る。というかそれそのものなんだけれど。 「ごめんって……ああ、別に怒ってないわよ」 母親みたいな声を出すんだなと思う。母親よりもう少し柔らかいかもしれないけれど。 こういう声の掛け方をする関係を私は知らなくて、それはつまり変わっていることを示していた。少しだけ、寂しくなる。 「ほんと?」 「ほんと。早く水飲んで寝てなさいよ。出るときになったら起こしてあげるから」 「うん……」 それだけ言うと、夏紀は水を飲み干して、テーブルに突っ伏した。すぐに深い呼吸音が聞こえてきて、限界だったのだろう。 「こいつ、ここ二ヶ月ぐらい会社が忙しくて、それでもバンドもやってたから睡眠時間削ってたのよ」 それはわかっていた。なんとなく気がついていたのに、見て見ぬ振りをしてしまった。浮かれきった自分の姿に後味の悪さを感じて、相槌を打つことも忘れる。 「それでやっとここ最近開放されて、休めばいいのに、今度はバンドの方力入れ始めて。アルコールで糸が切れたんでしょうね」 グラスを両手で持ちながら、呆れたように横目で黙ったままの髪を見る彼女の声は、どこかそれでも優しかった。伝わったのだろうか、みぞれも来たときの怯えは見えなかった。 「希美が止めてても無駄だったから、謝ったりする必要ないわよ」 適切に刺された釘に、言葉にしようとしていたものは消えた。代わりに曖昧な笑みになってしまう。 「そういえば、夏紀のギター聞いたのよね?」 「うん、まあね」 「上手かった?」 「素人だからよくわからないけど、うまいなと思ったよ」 「そう」 それならいいんだけど、と、明らかにそれではよくなさそうに呟いた彼女の言葉を、私はどう解釈していいのかわからなかった。曖昧に打ち切られた会話も、宙に放り投げられた彼女の目線も、私にはどうすることも出来なくて。 「そういえばみぞれは、いつまでこっちにいるの?」 考え込み始めた優子から目線をそらして、みぞれに問いかける。さっきからぼんやりと私達の会話を聞いていたみぞれは、私の視線に慌てる。ぐらついたカップを支えながら、少しは慣れればいいのに、なんて思う。 「え?」 「いつまでこっちにいるのかなって」 アルコールのせいか、少しだけ回りづらい舌をもう一度動かす。 「1月の、9日まではいる」 「結構長いね、どっかで遊び行こうよ」 何気ない私の提案に、みぞれは目を輝かせた。こういうところは、本当に変わっていない。アルコールで曖昧に溶けた脳が、そういうところを見つけて、安心しているのがわかった。卑怯だな、と思った。 ―――――― 「それじゃあ、気をつけて」 優子と、それから一応夏紀の背中に投げかけた言葉が、彼女たちに届いたのかはわからない。まさにダウナーといったような様子の夏紀はとても今を把握出来ていないし、優子はそんな夏紀の腕を引っ張るので精一杯だ。 まるで敗北したボクサーのように――いや、ボクシングなんて見ないけれど――引きずって歩く夏紀は、後ろから見ると普段の爽やかさのかけらもない。あのファンの子たちが見たら、びっくりするんだろうな。曖昧にそんなことを想いながら、駅の前でみぞれと二人、夏紀と優子の行く末を案じている。 その背中が見えなくなるのは意外と早くて、消えてしまったらもう帰るしかない。隣で心配そうに眺めていたみぞれと目があう。 「帰ろっか」 「うん」 高校時代とは違って、一人暮らしをし始めた私とみぞれは、最寄り駅が同じ路線だ。こうやって会う度に何度か一緒に同じ列車に乗るけれど、ひどく不自然な感じがする。改札を抜けた先で振り返ると、みぞれが同じように改札をくぐっているのが見えるのが、あの頃から全然想像出来なくて、馴染まない。 少しむず痒くなるような感触を抑え込んで、みぞれが横に立つのを待つ。並んで歩くふりくらいなら簡単にできるようになったのだと気付かされると、もうエスカレーターに乗せられていた。 「なんか、アルコールってもっと陽気になるもんだと思ってたよね」 寒空のホームに立つ私のつぶやきを、みぞれは赤い頬で見上げた。みぞれは人並みに飲む。人並みに酔って、人並みに赤くなる。全部が全部基準値から外れてるわけじゃない。そんなことわかっているのに、なんとなく違和感があって。熱くなった体がこちらを向いているのを感じながら、もうすぐくる列車を待つ人のように前を向き続けた。 「忘れたいこととか、全部忘れられるんだと思ってた」 口が軽くなっていることがわかる。それでも後悔できなくて、黙っている方がよいんだとわかった。塞いだ私のかわりに口を開きかけたみぞれの邪魔をするように、急行電車はホームへと滑り込む。 開いた扉からは待ち遠しかったはずの暖かい空気が、不快に顔に飛び込んできた。背負い直したギターケースに気を遣いながら、一際明るい車内に乗り込んでいく。���いてる端の座席を一つだけ見つけて、みぞれをとりあえず座らせた。開いた目線の高さに何故か安心している間に、電車はホームを離れていた。 肩に背負ったギターを下ろして、座席横に立て掛けた。毎朝職場へと私を運ぶこの列車は、ラッシュとは違って人で埋め尽くされてはいない。だから、みぞれの後ろ姿が映る窓には当然私も入り込んでいて、いつもは見えない自分の姿に妙な気分になる。酔いはまだ抜けていないようだ。 「みぞれはさぁ」 口を開くと言葉が勝手に飛び出していた。降り掛かった言葉にみぞれが顔を上げる。 「オーボエ以外の楽器、やったことある?」 私の問いかけに、彼女は首を振った。 「そうだよね」 それはそうだ。プロの奏者が他の楽器に手を出してる暇なんてないんだろう。いろんな楽器を扱える人もいるわけだけど。その辺の話がどうなっているのかは、私にはわからない。プロではないし。 どうやっても違う世界の人と話すのは、取材をしているような感触が抜けきらない。私達の他の共通点ってなんだろう。毎度手探りになって、別れたあとに思い出す。 「ギター、楽しい?」 何故か話題を探そうとしている私を、引き戻すのはいつも彼女の問いかけだ。 どう答えるべきか、わからなかった。何を選ぶのが一番正しいのか、見つけるのにはそれなりに慣れているはずなのに、そういう思考回路は全く動かなくて、だからありのままの言葉が飛び出す。 「楽しい、よ」 それは本心からの言葉だった。本当に楽しかった。それを認めてしまうということが、何故か恥ずかしくなるほど。 つまりこのまま何事もなく過ぎていくはずの人生に現れたギターに、ひどく魅了されてしまったということだ。認めたくなかった退屈な自分をさらけ出しているようで。年齢のせいか生活のせいか、頭にふと過る自問自答が、ギターの前ではすっかり消え失せていることに気が付かないわけにはいかなかった。 (まあでも、このまま死ぬまでこのままなのかなとか、みぞれは考えなさそうだな) そう思うと、ずるいなと思った。 「楽しかった。新鮮だし」 私の答えに、みぞれは言葉を口に出さなかった。ただ笑顔ではない表情で、私のことを見つめている。どこか裏切られたかのように見えた。どこか寂しそうにも見えた。見ないふりをして、酔ったフリをして、言葉を続ける。 「ギターって奥深いね」 そんな大学生みたいな感想を並べて、目の前のみぞれから目を外す。どんな表情になっているのかは想像がついた。 「面白い音なるしさぁ」 確かめたくなくて言葉を繋げる。この悪癖がいつまでも治らない自分に辟易しながら、結局逃げるために言葉を選び続けている。そうやって中途半端に取り出した言葉たちの中に、本当に言いたいことは見えなくなってしまうって、わかっているはずなのに。 「夏紀の演奏が本当に上手くてさぁ」 「フルートは」 「っ」 遮られた言葉に思わず黙ってしまったのは、それが痛い言葉だったからなのか、言葉の切実さを感じ取ったからなのか。目を合わせてしまう。耳を塞ぎたくても、無気力につり革にぶら下がった手は離す事ができない。 「フルートは、続けてるの?」 みぞれの声は、どこか張り詰めていて、ざわついた電車内でも通った。隣の座席の男性が、こちらを盗み見ているのがわかる。ひどく晒し者にされているような、そんな気分になった。 やめるわけないよ、まあそれなりにね、みぞれには関係ないでしょ。なんて言ってやろうか。 「やめたって言ったら、どうする?」 選んだ言葉に、すぐに後悔した。 なぜ人のことなのに、そこまで泣きそうな目ができるんだろうか。子供がお気に入りのぬいぐるみを取られたみたいな、そういう純粋さと、どこかに混じった大人みたいな諦めの色が混じり合って心に刺さる。 「冗談だよ」 言い繕っても、彼女から衝撃の色は消えない。そんなにショックだったのだろうか。私に裏切られたことなんて、いくらでもあるだろうに。 「前からやってたサークルがさ、解散になっちゃって」 「解散」 「そう。だから、ちょっと吹く機会がなくなってるだけ」 それだけ。それだけだった。だからみぞれが悲しむことはないし、気に病んだり必要もないんだよ。そう言おうとした。言えるわけがないと気がついたのは、みぞれの表情に張り付いた悲しみが、そんな簡単な言葉で取れるわけじゃないとわかったからだ。 「大丈夫だから」 結局言葉にできたのは、そんな頼りない、どこをf向いてるのかすらわからないような言葉だった。みぞれは私の言葉にゆっくりと頷いて、それだけだった。 逃げ出したくなる私をおいて、電車は駅へと滑り込む。みぞれが降りる駅だ。 「みぞれ、駅だよ」 「うん」 目を逸らすように声を上げると、みぞれは小さく頷いた。何を話せばいいのかわからないような、その目は私を傷つけていった。降りていく後ろ姿に声を掛ける事もできずに、私はただ彼女を見送った。 そういえば結局遊ぶ約束をし忘れたな。動き出した電車の中で、空席に座る気にもならないまま思い出す。ギターは何も知らないような顔で、座席の横で横たわってる。さっきまであったことなんて何も知りませんよって、言ってるみたいだった。 このまま置いていってやろうか。そう思った。
1 note
·
View note
Text
190305 山梨2日目
帰りのスーパーあずさでパソコンを使って書くつもりだったけど、車内Wi-Fiが無かったので、スマホから。誤字脱字が多くなるかもしれない。
9時ごろ起床。本当はバイキング形式の朝食が着いていたけど、昨日、午前3時ごろまでノリノリでtumblrを書いてしまった影響で、朝飯よりも睡眠を優先してしまった……。
カーテンを開けると晴れていて、雲の切れ間から、上部の粉砂糖が多目な富士山が見えた。昨日一昨日の雨は、富士山の標高だと雪になっていたんだなと納得する。
身支度を済ませて10時にチェックアウトすると、ほったらかし温泉へ向かう。開幕から温泉。初手温泉。完全に湯治の旅となった。
ほったらかし温泉に向かうまでは「フルーツライン」という、うねった峠をぶいぶい登って行くことになるのだけど、この道めっちゃ覚えがある~~と妙に感動していた。父の運転でよく来ていたのだ。当時は車内でゲームをやりまくってたので、めちゃくちゃ酔った。
仮に父から貰った軽自動車で来てたら、エンジンパワーが足りずにやばかっただろうな……と想いを馳せながら、スイスイと登って行く。

ほったらかし温泉は、平日にも関わらず、結構な人入りがあった。最後に来たのは15年近く前だと思うので、記憶よりかなり整備されていて、賑わっており、施設が充実していた。もっとほったらかしてなかったっけ……。
客層は私より若い大学生くらいの人たちも多かった。春休みですね。ゆるキャン△の話題もチラホラと聞かれて、やはり効果はあるのだなと感じる。
温泉は最高だった。ゆるキャン△でも言及されている通り、特に冬期は高地の冷えた外気と、湯加減とのバランスが絶妙で、無限に浸かっていられる心地よさであった。
昨日「温泉はアトラクションではない」というようなことを言ったけど、浴槽が3つあって、それぞれが絶妙な温度設定をなされており、何より温泉に浸かりながら富士山や山梨の市街地を見渡せる景観が非常に素晴らしい。温泉が気持ち良いだけでなく、そういうエンタメ的な欲求も満たしてくれる施設だった。
背中や腕におえかきをしてる方々もチラホラ見られ、ほったらかしの精神を強く感じた。洗い場で元気だった大学生の集団が、モンモンおじさんが隣に座った瞬間に大人しくなったのにはちょっと笑ってしまった。
無限に近い悠久の時を過ごしていたので、色んな人たちの会話が聞こえてきたりもしたのだけど、温泉での会話というのは、非常に人間性が現れる。公衆の場で、裸の状態で語るトピックスというのは、ある種、その人の本質でもあるのだろうなと思う。
以前、秩父の温泉に行った時、自分が優秀で意識が高いサラリーマンであり、周りはクソだという言説を大声で語っていた人が、その場に居合わせたおじいちゃんに、岡田麿里作品のような劇掛かった言葉回しで説教されてるのに居合わせたことがある。
優秀マンは、その注意に異を唱えて一触即発のムードが流れたが、話に相槌を打っていた友人が良識的な人だったので、まあまあ、すみませんでした。と優秀マンの背中を押して内湯に向かって行った。そのやり取りまで含めてアニメみたいで面白かったのだけど、本当に"優秀"なのは、友人の彼なのだろうなと思った。
本日も、自分の家がいかに裕福なのか、自分の親がいかにお金持ちなのかを滔々と語る、肥えたスネ夫のような男がいた。
彼らが「何故そんなことを温泉で話すのか」というのを考えた時、男が裸一貫で集まる場で「自分がいかに強いのか」を、どうにかして周囲にアピールしたいんだろうなという答えに行き着いた。
別にバカにしているわけではなく、実はこれは極めて動物的な本能なんじゃないかと感じる。究極的に言えば、どっちのチンコが大きいのかと次元は変わらないのだと思う。
ただ、自分自身のことを語らず(語れず)親の資産の話ばかりをしている太った男と、その横で気持ちよさそうにお湯に浸かっている、背中に般若が描かれている男、どちらの人生に厚みがあるのかというのは、一目瞭然であったように感じた。その点に関しては、ちょっと虚しさみたいなものは感じた。
その後に入ってきた大学生グループは、昨日打ったスロットの勝ち負けの話と、夜飲んだ酒の話ばかりをしていて最高だった。温泉では、上下関係とか恥とか外聞とか気にせずに、話す内容はハッピーであればあるほどよいというのが持論だ。お前の好みの話では?
ちなみに、背中におえかき系男性とは、その後フルーツパーク内のカフェで再会した。愛人(偏見)らしき女性を連れていた。もしかしたや、ゆるキャン△ファンだったのかもしれない。

温泉から上がると、待望の温玉揚げをいただく。食べる前からどう考えても美味しい確信があったので、2個注文してしまった。
どう考えても美味しかった。湯上りの汗をかいた身体に染み渡る……。瓶の牛乳も飲んで、ほったらかし温泉最高という気持ちに満たされてしまった。

その後は、ほったらかし温泉から少し下ったところにある『笛吹川フルーツ公園』に赴く。父がこういうところにはあまり興味がなかったので、この公園の記憶は、呼び起こしてみても頭の中に存在していなかった。(後から姉に確認したら、行ったことはあると言っていた)
遠足と思われる園児たちがわちゃわちゃと走り回っている。散歩中の小型犬が威嚇しあっている。上空では気持ちよさそうに鳥が飛んでいる。THE平和だ。


謎の果物博物館に迷い込んだりもしつつ、施設内のオーチャードカフェに聖地巡礼。
新聞の切り抜きやサイン、交流ノートなんかが置いてあり、アニメでなでしこ、アキ、あおいが実際に食べたメニューもちゃんと載せてくれていて、とても親切で熱心な場所だと感じた。
残念ながら、3月で山梨市駅に移転してしまうとのこと。惜別の意と、移転前に来れて良かったという気持ちを込めて、本日の糖要素として、なでしこちゃんが食べたりんごソフトをいただいた。大変美味しかったです。

血糖値の上昇に有効なのは食後の運動である。公園内を走り回りながら『フルーツアドベンチャー』という、クイズと迷路が合わさった施設を走りながら回る。
子供向けに作られたであろう設備にも関わらず、全10問中2問の正解という醜態を晒すこととなった。ゴール後の看板で、フルーツ物知り博士とかいうやつ(フルーツ物知り博士とかいうやつではない)にめっちゃ煽られた。
運動と頭の体操(?)をほどよく済ませたところで、富士急ハイランドへ向かう。
車を運転していると、富士吉田市に近づくごとに、眼前の富士山はその存在感を増していった。
富士山と同じ方向にあるセブンイレブンやエネオスなんかは、景観に配慮して看板が黒くなってる。そんな大げさなとも思ったけど、目の前で見せられると、それも仕方ないかなと思わせるだけの説得力がある。

1時間ほどして、富士急ハイランドに到着。駐車料金1500円というのをゲートの前で知ってめっちゃ引き返してえと思ったけど、後ろに車もつかえており、後戻りは出来なかった。
遊園地という場所が苦手だった。もはや、自分が本当に遊園地が苦手なのか判別できないくらい、遊園地に行った記憶が悠久の彼方に消えていた。
高校3年のどこかで、卒業遠足としてディズニーシーに行ったと思うのだけど、誇張ではなくマジで記憶がない。スフィアの舞浜公演に一緒に行った友人は高校時代からの仲なのだけど、彼とその話をしても、お互い虚無を確かめ合うばかりだった。
私の高校時代が閉ざされた闇の記憶という認識だということは、何度か折に触れて話している気がする。
中学時代がめちゃくちゃ楽しくて、特に受験勉強などせず、模試の判定も全部99%だった地元の高校に進んだ。中学時代の友人たちが、一番多く行く学校だったからだ。
結果的に、私だけが高校に上がってからも中学時代の交友関係を引きずり、周りは新しく友達を作って、新しいコミュニティを築いているような状態になった。今にして思えば、それでも3年間遊んでくれた友人たちには頭が上がらない。
高校を卒業した後に、スフィアライブを通じて、今まで続く交友関係がいくつも出来るのだけど、当時の私にとって、それはまた別の話。
急に周りの目を気にしだして、クラス内の立ち位置とか、誰々と話してたらダサいとか、何々と同じだからカッコいいだとか、そういう価値観が支配し始めたこの年齢を、私はハッキリと退屈に思っていた。
3年のクラスは、そうした中学時代からの仲の友人たちもいなくなってしまい、本当に誰かと話していた記憶がない。いじめられていたわけでもなく、とにかく「無」だった。私が皆さんのことを覚えていないように、皆さんも私のことを覚えていないと思う。
唯一、今スフィアライブに一緒に行ってくれる友人と、F1のレースがあった次の日にリザルトの話をするくらいだった。ただ、女の子なので、当時は自分から話しかけるのすら勇気がいり、それも2戦にいっぺんくらいだった気がする。
で、そんなクラス内で班を作って、ディズニーシーに行くことになったのだ。
一応テニス部に入っており、テニス部の友人たちと班を組んだけど、まあ彼らとは卒業した後に消息を知ってる感じの仲にはならないだろうなという予感があった。実際何してるかは知らない。
そのうちの片方が、特に志望大学とか、誰とつるんでるかで、自分を大きく見せようとするやつで、ディズニーシーでも、とにかくイケてるグループに混ぜてもらおう混ぜてもらおうとしていた。
結果的に、そのイケてるグループからも彼はぞんざいな感じで扱われ、私はハッキリうんざりしていた。
その後、記憶がないと言ったけど、舞浜に一緒に行った現親友のグループと合流して、私はようやく居場所を見つけて「救われた」と思ったのだ。
彼とは当時それほど深い仲では無かったし、彼も彼で高校時代のことを振り返ると「なかったことに」しようとするので、覚えていないというのだけど、無意識下で結構救ってもらっているので、頭が上がらない。恩返しができるから、今まで続く親友になれて良かったと思っている。
前置きが長くなったが、こうした記憶から、漠然と遊園地という空間に苦手意識があり、近づかないようにしていた。
でも、いろんな食べ物を美味しいと思えるようになって、いろんなことを楽しいと思えるようになった今なら、もしかしたら、自分なりに楽しめるようになってるのではないかという期待を込めて、一人で富士急ハイランドに行ってみたのだ。
結果的に、入って2秒で「何故私が遊園地が苦手なのか」という理由を完全に理解した。入園のチケットを貰う時も、怪訝そうな顔をされる。そうか。この空間では、一人でいることが"許されない"んだ。
高校時代のあの時も、彼の虚栄心にウンザリしながら「俺はいいからみんなで楽しんできて」とは言えなかった。遊園地の中に、一切の居場所が無くなってしまうからだ。そして学校の授業の一貫である以上、時間まで勝手に出ることも許されない。ハッキリと分かる地獄である。
周りを見渡しても、カップルや夫婦、大学生のグループ、外国人観光客に親子連れと、私以外、絶対的に誰かと連れ添って来ていた。1人カラオケとか、1人焼肉とか、1人映画とか、何がおかしいのか分からないと言ってきたし、前日も2人前の鍋を食べたけど、ハッキリわかった。次元が違うのだ。
この空間は、全て最初から"1人でいること"を排除してデザインされている。それを拒むことはないけれど、どうしても異質さとして浮き彫りにはなってしまって、この場合は、そういう空間であることを理解していなかった私が悪いのだ。久々に触れてみて、ようやくそれがハッキリ分かった気がする。いや、それは私が悪かった。

100対0で私が悪いのだけど、100対0で私が悪いという事実に無性に腹が立ったので、取材と称して1時間くらいかけて各アトラクションを練り歩いた。
テンションがぶっ壊れた人間しか笑わないであろうギャグが散りばめられた看板やモニュメントをみて、一つも面白くねえんだよバカ野郎と、心の中で悪態をついたりしていた。
若者たちが笑顔で集合写真を撮ったり、パネルから顔を出してはしゃいだりしている。私は自分が被写体になるのが苦手で、中学くらいから今まで、振り返っても全然写真が残っていない。集合写真からはみ出してしまったものに、遊園地は居場所を与えてはくれない。
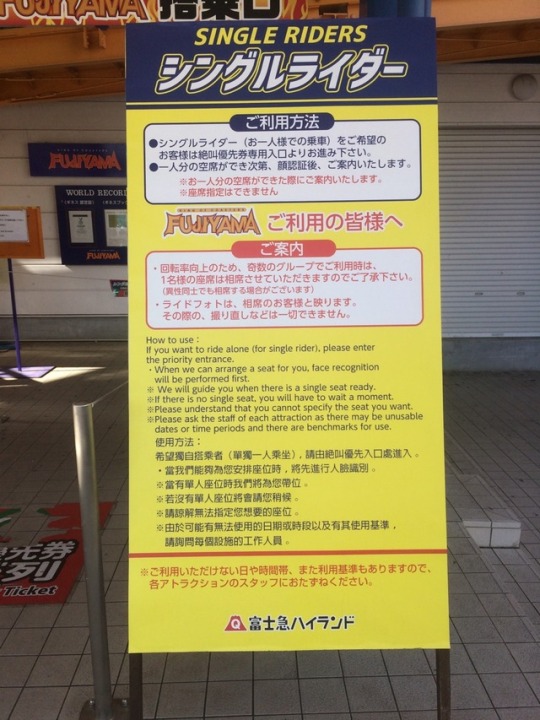
これとか「死んでください」と言われているようにしか思えなかった。2人並びの席だから、奇数グループで来てる人たちの余った枠に私が収まることになって、前の席と楽しそうに話してる中で知らないおじさんが1人混ざるという辛すぎる状況になる訳じゃないですか。
前述の通り、100対0で私が悪いので、僻みでしかないのだけれど、それはそれとして、どんなに成長しても、どんなに歳を重ねても、やはり私とは本質的に相容れない空間でもあるのだなと分かった。
いや、本当は私も絶叫マシンに乗りたかった。遊園地のことを冷やかしながら、隣で笑ってくれて、何だかんだアトラクション自体はめちゃくちゃ楽しいから、はしゃいでしまったり、年甲斐もなきメリーゴーランドとか乗ってはしゃいだりしたいんだ。
本当はそうだと思った時「お前は本当にどうしようもない人間だな」と、自分自身に言いたくなった。
でも、どうしようもない人間であるなら、どうしようもない人間であることをきちんと受け止めた上で、そのままにするのか、苦しんでも正すのかを見極めなくてはならないというのが昨年の学びだった。
だから、私は遊園地には迎合しないけど、私のどうしようもない世界を壊してくれる嵐山歩鳥みたいな、平沢唯みたいな、荻野目桃果みたいな人が「一緒に遊園地に行こう!」と手を差し伸べてくれる日を待っている。どうしようもなく待ち続けている。
あと、信頼できる友人に誘われたら、泣きながら着いて行って、いかにあなたが私にとっての救いなのかというのを5時間くらい説きつづけるぞというスタンスでいる。めんどくさすぎて絶対誰からも誘われない。
かつて、何故そう感じたのか分からなかったことの理由を、しばらく時間を置いて、改めて考えてみるというのは、良くも悪くも、己の立ち位置を知るために、非常に意義のあることだと分かった。
オタクおじさんの呪いとルサンチマンに満ち溢れてはいたけれど、私が「なぜ遊園地が苦手なのか」をちゃんと言語化できたのは、今回の旅行で一番の収穫だったかもしれない。
その後は富士山を近くで見ようと、道の駅や麓北公園に行ってみたけど、私の富士急でのモヤモヤが反映されたかのように雲がかかっていて、あまり見れなかった。
まだまだ山梨で達成できてないこともたくさんあるので、車を買ったらまた来よう。
その後は返却時間が思ったよりタイトになりそうだったので、届いたばかりのETCカードを使い、高速道路を走った。
軽自動車で速度を出すのはマジで恐ろしいけど、ノートくんはやはり加速が違い、速度を出しても挙動が不安定になることもほぼ無かった。今回の旅を通じて、感動した点はあれど、不満に思った点はほぼ無かった(返却時にガソリン入れたらそこそこ値段が掛かったので、燃費がどうなんだろうというのだけはややあった)(徳島より走行距離が長かっただけかもしれない)ので、普通に購入の有力候補に躍り出た。
緑色も思ったより昆虫感はなく、可愛らしくてよい。操縦感だけでなく、結構デザインも好みだった。
まあ、昨日も言ったように日産の味に慣れすぎてる感じもあるので、次はちゃんと他社の車種で借りて確かめてみたい。
17時半に返却。18時5分のスーパーあずさで甲府を発つ。
たった1時間半で新宿に着いてしまう近場だったけど、いろいろ思い出したり、分かったことが多くて、よき一人旅でした。温泉がサイコーということです。
競馬サークルの先輩とかが、ふとこのtumblrを読んで山梨のことを教えてくれたり、こうして残しておくことにも意味があるのだと思う。
運転が楽しくなってきたし、毎回気づきがあって面白いので、1ヶ月半に1回くらいどこかに行きたい。次は北関東か北陸がいいなと思っている。
1 note
·
View note
Text
夢の静寂/翔加賀
だれでもよかったとは思いたくなかったんです、なんてわがまま言って見せたらあなたは、いったいどんな表情をたたえてくれるのでしょう。
たとえばその程度に関わらず、なにか与えられるということに慣れていない私は、それを誰かに求めるための熱量すら持ち合わせていないまま、自分の気づかないずっと奥のところで臆病になってしまったのかもしれない。かえって息苦しいことにばかり敏感になった私の、みるみるうちにすり減った喜びを享受する部分が、いったいどんな形をしていたのかすらすっかり忘れてしまったなんてことを、今更になってようやく思えている。
だから私はあのうつくしい先輩の、全く予想外のお誘いを受けたとき、まずはじめに本当に自分でよいのかを訊ねてしまいそうになったのだ。それはとても失礼なことだと十分理解しているのに、素直に喜びを感じるよりずいぶん前のうちに、まず疑ってかかろうとした自分のその後ろ向き具合が、かなり年季の入っているようでなんだかがっかりしてしまった。それと同時に、悲しいほどの申し訳なさも。
待ち合わせ場所の裏門は街灯ひとつを除くとただでさえ明かりがなくて、今日みたいな新月の夜は普段隠れている星々が震えるように瞬いていた。食後に少しだけあおった温いお酒の酔いが、冬先のつめたい空気に洗われてだんだん醒めてくるのをどこかで他人事のように感じながら、普段は嗜まないお酒をなんとなく飲んで見たのも、もしかしたらきっかけの一部だったのかもしれないとぼんやり思う。慣れないことは大抵するものじゃないけれど、こんな日もあるならたまには許されてもいいのかもしれない。透き通った夜の帳に鋭く光る青い星がとてもきれいだった。
なんの変哲も無い日の、食堂でのことだ。最近忙しい日ばかりで、夕食をとるのがことさら遅かったり、やけに疲れが取れにくいのもあって、食後に珍しくお酒をあおってみたのがはじまりだったのだろう。先輩たちからお酒を勧められることもままあるけれど大抵遠慮しがちの私は、きっと人付き合いの悪い後輩だった。そもそもあまり飲んだことがないから、苦手かどうかも判然としない。人のほとんど残っていない食堂でひとりで食べるご飯はやっぱり寂しいけれど、今日にかぎって何だかわくわくしていた。そしてそれが運の尽きだったのだと思う。
雑談に花を咲かせていた子たちもまばらになって、カチャカチャと洗い物の音だけが響く二十一時半。ガラスのコップに焼酎とお湯を半分ずつもらって、案外いけなくもなさそう、なんて無根拠な自信で試しに匂いを嗅いで見たら思わず涙が出そうになった。涼しい顔で湯水のように飲むあの赤い先輩を思い出しながら一思いにいってみたら、苦くて辛い香りが頭の方に抜けていったかと思うと、あの独特の感覚が頭のなかを一気に揺さぶってきて、おもわず顔をしかめてしまった。熱を帯びた呼吸を舐めるとやっぱり辛い。あまり得意じゃないのは薄々わかっていたから、それは別にいい。問題なのはちょうどそのとき、視界の端の方でひらりと青色の袴が見えたことだった。
「あら、」と意外そうな響きでもって私の心臓を十二分にはねさせたその人は、よりによって一番見られたくない顔をしていた私を見るなり、「あなた、ここにいたのね」みたいなことを呟いていたような気がする。手元のコップをちらと見やって、なんとなく何かを察したかのような目をして(加賀さんは無表情な人だけど、あの琥珀色の瞳だけは人並みに雄弁だと思う)、そしてそのあと。「貴女、これから空いてる? 映画を見に行かないかしら」 と言ってきたので、私はさらに面食らってしまった。なにしろ加賀さんになにかを誘われるというのは私史上滅多にないことで、なにより、もう門限が過ぎかけていたから。予想外の出来事にびっくりしていると、門限のことなら心配いらないわ、と続けて。
「裏門で会いましょう。あったかくしてきなさい」
みたいなことを言って、私の答えを聞く前に帰ってしまった。もちろん私に断る気がないのも(あるいは断れない性格なのも)きっと知っているのだろうけど、いかんせん驚きすぎてなにも言えなかったのだ。ぜひいきます、の一言くらいは、なんとか言いたかったのだけれども。
私は部屋に帰るなり急いで着替えたりお化粧を直したり書き置きなどをして、去年の秋ごろ卸して着る勇気のなかったアイボリーの新しいコートをひっつかんで飛び出してきた。加賀さんはまだ来ていなかったから、夜とはいえせめてリップの色くらいはもう少し悩みたかったのを後悔しつつ、こうして星を眺めている。
私でよかったのかなと思ってしまったのは事実だけれど、それでも嬉しかったのだ。そして同じくらいとてもどきどきしていたのは、たぶん、彼女とふたりきりでどこかへお出かけするのが初めてだったから。一体どんな理由があって私を誘ってくださったのかおよそ見当もつかない。もしかしたらなんとなく私な気分だったのかもしれない。一緒に行く予定だった赤城さんに用事ができて、二航戦の先輩方も捕まらず、偶然私を見かけたから? それともほんとうに、私を探して下さっていたとしたら。思いつく限りのありきたりな理由を並べて見ても、胸のところを抑え込みたくなるくらい嬉しさが溢れてくるばかりだ。その上、門限外に隠れるように外へ出てしまったことが初めてだったからかもしれない。なかなか融通の利かない規則ばかりのここでは、夜の外出ですらきちんと届出を出さないといけなかった。出かける用事がすくない私にとってほとんど縁のないものだと思っていたくらいだ。またあるいは、これは最近になって気づいた私だけの秘密でもあるのだけれど。
「翔鶴。待ったかしら」
もしかしたら勘違いであるのかもしれないし、ずっと昔からそうだったのかもしれない。今となっては確認しようがないけれど、翔鶴、と私の名前を呼ぶ加賀さんのその声が、思わずはっとしてしまうほど存外柔らかいことに、最近になってようやく気づくことができたからだろう。
「なにか���しいことでもあったの」「いえ、」
いまからある予定です、なんて生意気なこと言えたらきっと素敵だ。
ベージュのチェスターコートにすらっと映えるシンプルなロングスカートで現れた加賀さんは、あまりに似合いすぎるくらい似合っていてとくべつ以外性はなかったけれど(それでも見とれるには十分すぎるくらい)、普段から結っていてなかなか解かれることのないサイドテールが下ろされていたのには驚きだった。おさげの痕がオレンジ色の街灯に照らされて、こんなこと絶対言えないけどなんだかかわいらしい。慣れた手つきで裏門の錠を外しながら、行きましょう、と珍しくほほえみかけてくれたのを、ほとんど終わりかけた今日という日のこれからを、私は一生忘れたくなくて、焼き付けるようにじっと見つめてしまった。きっと不自然なくらい。
この辺りで映画館というと、海沿いを少し行ったところの路地にこぢんまりと建っている小さな個人経営の建物を指している。設備もラインナップも少し古いけど、人の入りはそんなに悪くないらしい。時々ずいぶんマニアックなレイトショーをやっているというのを、瑞鶴から聞いたことがあった。 遠く打ち寄せるさざ波や、きっかり二歩先からコツコツ地面を打つ規則的な音ばかりの夜のしじまで、私の呼吸音だけが不器用に聞こえていた。街灯の下に浮かぶ加賀さんの見慣れたはずの後ろ姿が、いつものそれとはまるで違う雰囲気を纏うせいで思わずはっとしてしまう。ひとの新しい一面を見つけられるというのはいつだって嬉しいものだ。けれど私と加賀さんはそれほど短い付き合いではないはずなのに、私が彼女について知っていることのほとんどが、当たり障りのない無いことばかり思い起こされてしまうのが同じくらい悲しかった。
追いかけるので精一杯な私の目の前で、控えめなピンクベージュの可愛らしいパンプスがはたと立ち止まったのを見て初めて、私は自分がうつむいていることに気づく。
「ごめんなさい。一緒に歩きましょう」
癖なのよ、とわずかにはにかんだ加賀さんは、少しだけ右にずれて私の前に道を作ってみせる。それまで聞こえていた潮騒や車の走る音が急に耳元でひりついて、ともすれば観客の前で脚光をあびたような気さえして、ずっと気づかなかったけれど、今、自分が思っている以上に緊張している。加賀さんについて知らないこと、たくさんあるれど。一つだけ言えるのは、その癖とてもよく知っているということ。
「あ、あの」
隣を歩くということがこんなにも熱量を要求してくるとは思わなかったから、普段なにを話しているのかすらすっかり忘れてしまったようだ。かろうじて覚えている歩き方も、もしかしたらあやしい。
「なに?」
「か、かわいいです、履物」
「あら、ありがとう。あなたも似合ってるわよ。お洋服」
かわいらしいわ、とつけ足して、おくれ毛を耳にかけながら優しい瞳で加賀さんが微笑む。キラリと瞬く小さな銀のピアスが一番星のよう。
今までそんな褒められらかたをしたの、妹くらいなので、私はほとんど意識のしないうちに俯いてしまった。なんとか声にしたかった感謝の言葉も、熱でひりつく喉元を越えられないままじんわり溶け出した。かわいらしい、という言葉が他ならぬ私に向かって、あの加賀さんの口をついて出たということ、きっと夢じゃなければ記念日にしたいくらいの祝福だ。頬に手を当ててみると不思議なくらいの熱を帯びているのは、たぶん冷たくて青い冬の空気のせいばかりではないらしい。
「もしかして寒いかしら」
手袋ならあるけれど、とコートから取りだして渡された黒革の細身のそれは、彼女の体温でほんのり暖かくて、やっぱり少し大きくて、なにより切実にいい匂いがする。滅多にないことの連続と、確かに感じられる温もりや寒気の分離感がなんだかおかしくてとても愛おしい。曲がり角の目印にしている信号が夜の底で寂しそうに点滅しているのが近づくと、加賀さんはサッと手元の時計を確認して、そういえば、と呟いてこちらを見やった。
「あなたお酒を飲むのね。初めて見たわ」
「あ……、ちがう���です、」
たまたま味見をしてみたかっただけなんです。と白状して見たら、あなたもそういうことするのね、と意外そうに笑ってくれた。首元をするどく撫でる冬の海風に思わず肩をすくめながら、飲み方教えてくれませんかとは到底言う勇気のない私は、いっそわがままの許可でも貰えれば言えるのだろうか、なんて悲しいことばかり思い浮かぶ。
目当ての映画館は街灯ひとつあるばかりで人気が無く、賑やかな昼とうってかわってひどくもの寂しい。翔鶴、とちいさな声で私を呼んだ加賀さんは、鈍い月明かりのような街灯の下に浮かんでいるカラフルなポスターのうちの一つを差した。
「あれを見たいのだけど。よかったかしら」
華やかな男女で彩られたその映画は、私の周りでも流行に明るい子たちの間で話題になっているミュージカル映画だ。
「はい、私も見たかったので嬉しいです」
「貴女ロマンスが好きなんでしょう。むかし貴女の妹が言ってたわ。……チケットを買ってくるわね」
「あの、私」
「いいのよ。先輩の顔を立ててちょうだい」
おごっていただくつもりは当然無かったから、いっそ申し訳なさすぎて落ち着かないくらいだ。加賀さんはレザーポシェットから長財布を取り出して、大人二枚、と受け付に話しかけている。
一体いつのことかは覚えてないけれど、ずいぶん昔にそんな話を瑞鶴としたことがあった。そしてそういう些細なことや、自分ですら気づくことのできるかどうかあやしいことですら、この先輩は必ず見つけて、覚えている。私の弓のわずか1秒にも満たないほどの早気や、口割りの微妙な揺れでさえ治してくれるのだ。彼女が同僚から小さい子たちにまで慕われるのは、きっとこういう丁寧な性格のためだろう。私にとってのあこがれでもあった。
「ありがとうございます、大切にします」
大げさね、とかえして、加賀さんは静かに笑ってくれた。受付の明かりで揺れる薄茶色をたたえた瞳を隣で眺めながら、夢のような心地の私を、半券と、ひりつくような熱だけが繋ぎ止めている。
夜も更けているせいか、ほとんど人のいない映画館は最低限の明かりのなかでひっそりしていた。ちょうど真ん中すこし前付近に並んで席をとれたのは嬉しい。隣でコートを脱ぐ加賀さんが気になってつい見てしまうのはたぶん仕方のないことだ。黒のボトルネックにシンプルなネックレスもそうだけど、何より髪を下ろした横顔がとても新鮮で、少しだけ、色っぽくて素敵だった。 きっとこの先、今日という日を決して忘れることがないだろうと思った。そして同時に、誰でもよかったとは思いたくなかった、なんてひどく私らしくて薄暗い気持ちも。
「今日はわがままに付き合わせてごめんなさい。貴女、最近疲れてるみたいだから」
「いえ、いい息抜きになりました。それにうれしかったんです。その……誘っていただけて」
思わず目を背けてしまった私に加賀さんは少しだけ沈黙を流してから。「それはよかった」
泣きたくなるくらい優しい声だった。この優しい先輩はいつだって、全部は言わずともきちんとわかってしまえるような、適切なこたえをちゃんと用意してくれる。それはきっと生まれもった才能のような、初めからそういうかたちを湛えた光のようなものなのだ。そしてその光に照らされてきたことに、私はついぞ気づかなかったのだろう。不安で卑屈な私のほんとうの言葉を聞いてもきっと、それでいいって、少しずつ変われるからって、私の心あますことなく掬って、笑ってくれるに違いない。
私でよかったんですか、と言いたい気持ちも、誰でもよかったとは思いたくなかったのも、どうしようもないくらい事実だ。また夜に連れ出してほしいし、お酒だって一緒に飲みたい。けれど私のこと、もっとたくさん知ってほしいと思う気持ち、全部合わせても足りないくらい本当だった。
「もうひとつ、わがまま言ってもいいかしら」
加賀さんは少しだけ笑って私を見る。潤った睫毛から覗く美しいヘーゼル色の綺麗な瞳に揺らぐ色。
「私、あなたのわがままが聞きたいわ」
たった一言。たった一言だけで、今夜のとくべつな出来ごとが急速に秘密性を帯びて、私の微かな平常心を切り離す。囁きかけるような声に強くどくんと脈打つ私の心臓。すこしだけ甘くて艶っぽく聞こえたのはたぶん私の頭が熱を帯びてるからくらりときたせいで、なんてことはない、いつも通りの加賀さんだから。いったい何に言い聞かせるのかすらわからないことばかり思い浮かぶ。
けたたましいブザーと同時に暗くなる場内で加賀さんがたてたわずかな音は、たぶん私に近づく音。
「翔鶴。またきましょうね」
すぎたことは望まないから。帰り道に映画のはなしをして、物音たてずに、こっそり帰って。うすあかりの寝静まった廊下の、加賀さんのお部屋の前で。おやすみって、言われたい。
1 note
·
View note
Text
週報21-12-04
・今年最後のお週報です
明日コミケですね!!!!!
明日来てくださる方は宜しくお願い致します。
無事に入稿も出来ているので、後は早起きと、忘れ物しないかとか…人間性とか…不安だ…
この手の不安も久しぶりすぎますね。
12/30 c99サンプル | うずら #pixiv https://www.pixiv.net/artworks/94968057
サンプルこれです。
さて…お週報的には…一年振り返り的な事をしようと思いましたが、
メチャクチャ遊び歩いていた事だけで記事になる。ダメすぎる。
・友人がチェキを買った
ヒプノシスマイク飴村乱数推しの友人が「チェキ欲しい!」というので、
マジで全く頼まれてもいなかったのに「飴村乱数に似ているチェキ」を考えプレゼンをしに行く。
いや…分かる。飴村乱数って…チェキだから…………(???)
飴村乱数という男は「いつ死ぬか分からないクローンのカラダでありながら、『カワイイ』信念に、カワイイモノを作る事を生業に、ただ今だけを頼りに生きている男」……
チェキって華やかなパーティーカメラのイメージだったり、アイドル文化のイメージだったりがありますが、
そもそも写真を残すという行為は、その瞬間を引き延ばす事…
加えてチェキ、ポラロイド等は「その場ですぐ、かつ物質として分かりやすく残る」所が特徴的です。
「いつ死ぬか分からない、だから死にたくない、だから今が楽しくないと意味がない」ような彼ですから、もうね…そりゃチェキなんすよ。(?????)
そんでもってポラロイドじゃない。みんなのアイドル乱数の番なわけですから…カワイイがモットーである Instax miniシリーズ(多分皆さんが一番「チェキってコレ」と思い浮かべるコロンとした機体/最近は丸っこくなく、動画とかやれるハイエンド版もある)…
でも外見的にはエスキュラピンク…レンズやファインダーが飴村乱数のスピーカーに似ていて良い…
手を出しやすいと言ったらタカラトミーのヤツ…あれもピンクあるし…
でも個人的に本人に持ってて欲しいのはライカのミント色…
そういう妄想をしながら電車に揺られ���待ち合わせ場所である新宿に向かっておりましたが、 とはいえ何を撮りたくてチェキという選択なのか、聞いておかないと突然「邪念チェキ選び」を聞かされても困るよな~と頭の端では一応思っており、
「でもまっ(笑)オタクはオタク(笑)」と割り切っていざ聞いてみたら、 「亡き祖父の遺した写真を見ていたら、『形として残る』って良いな…と思った」という光の写真エピソードを出されて目がつぶれて死んでしまうところだった。
お前本当に写真漫画を描いている人?
でも飴村乱数に似ているチェキの話は聞いて頂きました。満足。
そして友人は飴村乱数の相方の方の色のチェキ(mini11)を買って帰りました。(オチ!)
もっと言えば私はチェキの事しか考えていなかったので、「今年だした本交換しようね」と言っていたのに、本忘れました。ごめん。
それはそれとして、折角そんなチェキを得たのだからと、新宿から渋谷までプラプラ歩いて、渋谷でウマいモノ食べ、写真も撮って幸……
・咲カフェ行ってきたよ!
とにかくありがたかったです。
Twitterにも書いた事ですが、アニメも映画も終わって久しい、今のタイミングでコラボカフェやってくれる事…
確かにお昼時の予約ではあったのですが、予約10分前について、既に2~3組並んでいて、ビビって一旦ウロウロしてしまいました。
並んでいたのは全員男性でしたが、別の階でも別のコラボカフェやってたので(コラボカフェタワーみたくなってる)
「見た目で判断してはならない、『抱かれたい男一位に狙われている』のオタクかも」と思っていましたが、結局咲のお客さんでした。
私は完全に咲のオタクと一緒に行きましたが、いつものテンションでアホのオタクトークをしていると、周りも全員オタクなわけで、そこそこ静かな店内では恥ずかしい目にあうのでは…という気持ちになったので、
逆に咲はそこまで詳しくない方と行った方が心臓が弱い人には良いのかもしれない。
とはいえ私は、ドレスコード守って行くような人間なので(グラニフのトラのトレーナーを着て行きました)心臓ツヨめだったので、咲オタクと行けた事、超良かったです。
お客さんの内の誰かがフォロワーさんだったらどうしようという恐怖は一生ついて回っていましたが…
あと内装も個人的にはそんな…気にならんかったです。
アキバのメロブの地下が居心地よい人間が何か言っても信頼性はゼロですが、 店内でずっとアニソン流れてるとかの方がオロオロしちゃうので、ありがたかったです。
注文の仕方の説明はちょっと欲しかったかもしれませんが、(テーブルの引き出しにタブレット端末が入っており、それで注文してくれスタイル)まあこのご時世ですからね…
そいで、私はタコス食べてきました。
咲オタクをして長いですが未だにタコスを食べた事がなかったので、この日のために食べてこなかったのだなと思いました。
店員さんが「優希ちゃんの…」と呼んでくれたの嬉しかったです。チョロ。
食べ方がずっと分からなかったですが、前に座っていたお客さんも「わからん」という仕草だったので安心して手をべたべたにして食べておりました。
辛いのめっちゃダメな人なので覚悟していきましたが、大丈夫でした!おいしかった…
メニューは、これもTwitterで書いてしまいましたが、エトペンパフェがホント良かったです。
だって…一番「ありうる」じゃん……
私は「無い世界を突然感じる瞬間」が大好きなので、例えば浜辺美波さんの出演作品情報ではなく、生活情報がYahooニュースに乗るだけでニコニコしていました。
宮永照も絶対そうだから。インスタとかのフニャフニャした情報で記事書かれるご身分なんだから。
して、エトペンパフェ…。
そもそもエトピリカになりたかったペンギンって、ぬいぐるみやアイテムが出るような名著なわけですから、 (ていうか原村和のあのエトペンぬい、絶対絵本ナビで取り扱いあるわ…良すぎ……)
MOE(絵本情報雑誌)でカレンダーとか付録に付けられるようなソレかもしれない。ヤバ過ぎ。
はらぺこあおむしカフェとかムーミンカフェみたいな感じでマジであってもおかしくないヤツが「エトペンパフェ」なわけですよね。
そういうのだよ!!!!!!!!!もう、本当にご機嫌でした。
・たそちゃんと遊んだ
この日は帰宅時には完全にお酒が抜けていたので、マトモな分量の日記が残っている!聞いてください。
ここをお読みの方はご存知確率が高いですが、たそちゃんこと、たそがれさんです。
商業だとまんがタイムきららキャラットや、一迅社ぱれっと等にゲスト掲載やってたりします。
ていうか先日発売のキャラットに掲載中!
まんがタイムきららキャラット 2022年2月号 [雑誌] まんがタイムきららキャラット編集部 https://www.amazon.co.jp/dp/B09P3GPCCT/ref=cm_sw_r_tw_dp_J36E8RWCS8MM09104KQ1
しらぬまにkindleも普通に読めるようになっている!?なんか前ひと月遅れ配信じゃなかった!?
しかし、知り合ったキッカケは双方共に漫画仕事を始めるより遥か昔、TVアニメキルミーベイベーです。
そもそもTwitter「@tori_nico2」はTVアニメキルミーベイベー本放送時、実況をしたくなったがため、「@hiyo_kotori」から切り離した存在でした。
そこで「キルミークラスタ」として知り合ったというわけです。
(当時のTwitterキルミークラスタ、まじで10人くらいだった気がします。ニコ生あたりから超増えたけど…本放送時は本当に小さい集落でした。ていうか「クラスタ」って死語では?)
お昼に居酒屋さんでイクラ丼を食べました。
もう日本酒の理屈でダクダクとこぼれ散らかしてるタイプのイクラ丼でした。味の表面張力や。
それにレンゲを入れて全部溢して非常に情けない声を上げていたら「動画にすればよかったな」と言われて怖かったです。
イクラ丼の残ったイクラをポテサラにかけたら最強なのでは…と提案し
「最強じゃん…!美味いに決まってるでしょこれは通風!」と突然すぎて半ば語尾の配置で病名を唱えてきたのでアホほど笑ってしまった。
これが語尾になるのはどうぶつの森の、健康意識の高すぎる村だけなんだよな。
昼食後「コミケ用のお買い物したい!消毒と、見本誌用のブックカバー!」と言ったら
「じゃあアキバ寄ってドンキ行こう、ドンキならなんでもあるし…とりあえず上の階から見てこ」と言われ ドンキはすごいなあ…と思いながら、完全になすがまま付いていく。
みなさんはアキバのドンキ最上階ってなんだかご存知ですか?
そうですエロゾーン。私は普通に忘れてた。
忘れてたので完全に無抵抗な状態でエロゾーンに吸引され、散々チャチャいれ散らし、
そこでようやく「あっ!ブックカバーは…」とオロオロしだしたら「文房具だから3階だね」と言われて怖かったです。
「上の階から見てこ」というのはつまり…!どこにあるか分からないからではなくて…!こいつ…!初めから全部わかってて……!
しかもブックカバーは無かった。
「別にそんな……騙さなくてもいいのに…!言ってよ!ちゃんと…エロタワー行きたいって……」、
寒空の下そんな懇願をしました。狂った友情がさらに狂った形で強くなるシーンです。
まんがタイムきららみたいですね。そんなことはないな。決してないな。
そうしてエロタワーにも行ったら、本格派の夜になってしまい、
マックかガストしか空いてなくて、わたしたち本当にバカだね…と思いました。
本当に楽しかったです。あたしはね…たそがれのこういうトコがスキ…
ブックカバーはアニメイトで買えました。
そういえばエロタワーのエレベーター初めて使ったのですが
(いつも…(いつも!?その「いつも」…全部たそがれとだわ…アホすぎる…)は健気に階段でした)
本当にこの世にこんな狂ったエレベーターはないぞという景観でオススメです。
360度見渡す限り逃げ場ナシの春画48手…頭おかしくなるかと思ったよね…
セックスしないと出られない部屋がこういう感じだったら本当に嫌だなと思いました。
いつもごめん…推しカプもしかしてこんな気持ち?
いや私はセ出部屋は…そんな描いたことないけど…
エロタワーに行くと何が良いかというと、メチャクチャ元気が出るし、普通に仕事に有益だし、その後舌が回るようになるんですよね。 いやたそがれと居て、舌が回らん日は無なのですが。 回った舌で何の話をしたかというと、私本人も忘れてた数日前に見た 「触手の苗床にされた女の子の真横で励まし続ける夢」の話をしました。 こんなんエロタワー行かないと思い出せんのよ。
そういえば「今日髪切ったんだよ〜」というギャルゲー頻出セリフVSたそがれに対峙し、 「私も今週切ったんだから!」と張り合うというクソ選択肢選んだけど高感度下がらなくてよかったです。 その後も「たしかに美容院後の感じするね〜色きれいに入ってるね〜」と言ったら「切っただけだから色は別にやってない」と言われて、 そっか…二回チャンス与えられても両方とも致命的に択をミスる人をいるんだ…と思いました。
そういえば今年の上野クリスマスツリーは竹がぶっささっては無かったのですが、
液晶モニターが飾られており、半分くらいエラー起してて良かったです。サイバーパンク・クリスマスツリー。
0 notes
Text
近さの / なかに / はいる
※この記事はnoteに書いたものをそのまままとめて移植したものです
→もとの記事(初回)https://note.com/megata/n/n47f8d146b717
[1]
花になるなら、飾らず、まっすぐに伸びるヒマワリがいい。モードが言う。対してハロルドは、一面に咲くヒナギクを見下ろしながら、自分はこの花がいいと言う。あの花この花の区別なく、たくさん横並びで生えている、どれでも変わりないようななかのひと花でありたい、と。そんなふうにヒナギクを評するハロルドに対し、同じ花なんてないとモードは意見する。それから、こんなこともいう。世の中の不幸のほとんどは、他人と同じように扱われることに不満を持たない人々が生み出している、と。
ところが、「どこにでもいるやつなんて どこにもいない」式のことを述べたてるモードは、とてもとても極端な人物なのだ。名もなき雑草のひと花ひと花に愛情深い態度を示すような、落ち着いた穏やかな人格ではない。独善的で身勝手な狂老女、とみなされても不思議ではない。
ラブコメというジャンルはどのような構造で組み立てられているか、という話のなかで話題にのぼり、紹介された映画『ハロルドとモード』を実際にみてみた。とはいえこの映画は、いわゆるラブコメというジャンル映画ではないように思われる。家人の目につくところで自殺を演じ続ける少年ハロルドだが、ハロルドの母は、息子が首を吊ろうと手首を切ろうと銃で頭を撃ちぬこうと、まったく相手にしない。「いつものいたずらね」ということで軽く流し、かわりに精神科に通わせたり、軍人の叔父に預けようとしたりする。ただし同伴・同席はしない。ハロルドは一人で精神科や、叔父のオフィスに通わされる。
ハロルドはいつものように、知らない人の葬儀に勝手に参列する。そこで知り合った79歳の老女・モードもまた、赤の他人の葬式に参加するシュミがあった。二人は巡りあう。
モードは常に人の車を運転する。公道の街路樹を引き抜き、人の車にのせ、料金を払わず高速道路をぶっ飛ばし、白バイ警官をまいて、山に勝手に植えにいく。シャベルだって当然盗品である。しかしあっけらかんとしていて、罪の意識はない。法を犯していることぐらい理解しているだろうけど、罪を犯している自責はかけらもない。めちゃくちゃである。
惹かれ合った二人が、きちんと一夜を共にする描写(朝になって、裸の少年と老女がおなじベッドで目覚めるシーン)があるのがとてもよかったです。
「ラブコメ」のジャンル映画ではなさそうだったし、それに「恋愛」を描いているようにも思われなかった。おもしろい映画だったけどね。さあ「恋愛」ってなにか。
このごろ読んでいた嘉村磯多の「途上」という自伝小説のなかに、露骨な切れ味の描写があってハッとさせられた。中学校のなか、からかわれたり後輩をいびったり、勉学に励みつつ田舎出身を恥じらい、色が黒いことをバカにされたり先生に気に入られたり、下宿先の家族に気を使いすぎたりして、なんやかんやで学校を中退して、実家に戻ってきた。ぶらぶらしていると、近所にいる年少の少女に目が留まる。いつか一度、話したことがあるきりだが、やたらと彼女が気にかかる。そこにこの一文があらわれる:「これが恋だと自分に判った。」
そんなふうにはっきり書かれてしまうと弱い。「はいそうですか」と飲み込むほかない。
けれど、恋愛を描いている(とされるもの)に、「これが恋」って「判った」だなんて明確に言及・説明を入れ込むことは、どうなんだろう。少なくとも当たり前な、お約束なやり口ではないと思うけど。
世の中には、「恋」「愛」「恋愛」という単語の意味するところがなんであるのか今一度問い直す手続きを踏まえずに、じつにカジュアルに言葉を使っているケースばかりがある。そうすると、その場その場で「恋」の意味が変わっていくことになる。その「恋」が意味しているものは単に一夜のセックスで、「恋多き」という形容詞がその実、「ぱっと見の印象がイケてた人と手当たり次第やりまくってきた」って内容でしかないときも少なくない。
まあけど、それがなんなのかを追究するのはやめましょう。というか、いったんわきに置いておきます。
さて『ハロルドとモード』の紹介された雑談のトピック:「ジャンルとしてのラブコメ」ですが、これは単に、「イニシアチブを奪い合うゲーム」であるらしい。そういう視点で構築されている。要するにラブコメは、恋愛感情の描写とか、恋とは何かを問い直すとかじゃなくて、主導権や発言権を握るのは誰か?というゲームの展開に主眼がある。気持ちの物語ではないのだ。描かれるのは、ボールを奪い合う様子。欲しがらせ、勧誘し、迷い、交渉する。デパートのなかで商品を迷うように。路上の客引きの口車にそれなりになびいたうえで、「ほか見てからだめだったらまた来ます」って断りを入れて、次の客引きに、「さっき別の店の人こういってたんですよね」とこちら側から提示するように。
イニシアチブの奪い合い、というゲームさえ展開できればいいので、気持ちとかいらない。ゲームが展開できるのであれば、主体性もいらない。ラブコメの「ラブ」は心理的な機微や葛藤の「ラブ」ではない。奪い合っているボールの呼び名でしかない。(つまり奪い合い=おっかけっこ、が、「コメ(ディ)」ってワケ)
浮気はドラマを盛り上げる。人が死ぬのも、まさに「劇的」なハプニングだ。雨に濡れて泣きながら走り、ようやく辿りついたアパートの部屋はもぬけの殻、ただテーブルにひとことの書き置き「フランスに行きます」みたいな、そんな派手な出来事で試合はいよいよ白熱する。ところが、心理的な機微や葛藤というのはいつだってモノローグ的だので、気持ちの面での「ラブ」を描きたいなら、このような出来事たちはむしろいらない。うるさすぎる。もっとささやかで、短歌的な味わいのものがふさわしい。ひとりでいるときに、マフラーの巻き方を真似しようと試みて途中でやめたり、チェーンの喫茶店の安コーヒーの味が思い出でおいしくなったり、そういうのでいい。出しっぱなしのゴミ勝手に片づけたの、ちょっとおせっかいすぎたかなってくよくよ悩む、とかでいい。
恋愛の感情・心理がよく描写されているように感じられる物語の登場人物は、内面的な葛藤に閉じこもらざるを得ないシチュエーションに押し込められている場合が多い気がする。「ひとには秘密にしてないといけない」「誰にも言えない」という制約のある環境。仕組みとして、宗教の違いや人種や年齢の断絶、同性愛など、自分の思いを簡単にひとに打ち明けられないセッティングの話のほうが、「イニシアチブ奪いあいゲーム」からは遠ざかる。(それに、そんなようなセッティングだと、「世間の常識」が要求してくるジェンダーロールを無視して鑑賞しやすい場合も多い。)
----------------------------------------------
[2]
成功した実業家の息子であるハロルドは、経済的にも肉体的にも不自由なく暮らしている。が、なんだか欠落を抱えている。自殺遊びや他人の葬式への参加など、死に接しているときが最も楽しい。老女モードは、そんなハロルドの世界観を一変させることになる。彼女はかなりアナーキーな存在で、逮捕されるようなことばかり繰り返している。けれど悪びれない。自らの行為を、自分らしい人生を過ごしている実感を与えてくれる刺激として肯定している。
J.G.バラードに『コカイン・ナイト』という小説があって、この頃これを読みました。あ、そもそもこの記事は、最近読んだものや見たものについて、できるだけ網羅的に言及できないかと願いつつ当てずっぽうで書き出した文章です。できることなら人とのやりとりや、自分の過ごした日常についても記したいが、それがうまくできるかどうか。
『コカイン・ナイト』の主人公はチャールズで、世界中を飛び回っている旅行記者です。退屈について、カリスマについて、刺激について。さまざまな切り口から鋭い洞察が重ねられたこの名作の入り口は、ミステリーのかたちをしている。
スペインの南、ハイパーセレブたちのリゾート地で働いているはずの弟が窮地にたたされているから助けにいかなきゃ! という目的で、チャールズは物語の舞台にやってきます。弟の状況はよく知らないけど、あいつのことだし、そこまで深刻じゃないだろう。そう高を括ってやってきました。ところがどっこい、弟、かなりやばい状況でした。
大邸宅が放火により全焼し、五人が焼け死んだ。弟にその容疑がかけられている。捕まって、留置されている。裁判を待っている。けれども、誰も、弟が犯人であるとは信じていない。警察だって例外じゃない。明らかに、弟の犯行ではないのだ。それでも弟は、自分がやったと自白しており、嘘の自白を繰り返すばかりで取り下げない。いったいなにが起こっているのか。どういうことなのか。
地域の人らはすべて疑わしい、なにかを隠しているような気がする。チャールズは素人ながら探偵のまねごとをしはじめ、地域の人々から疎んじられはじめる。チャールズにとって、地域の人々の態度と距離感はますます疑わしいものに思えてくる。そして実際、普通には考えにくい、歪んだ事態を数々目撃することになる。余暇時間を持て余したハイパーセレブたちは、事故を起こして炎上するボートを楽しそうに見つめていた。拍手さえあがる。
『ホット・ファズ~俺たちスーパーポリスメン~』という映画があって、平和な村=表向きには犯罪のない村を舞台にした話でした。「表向きには」犯罪はない、というのはつまり、法に反した行為があったとしても、届け出や検挙がなければ統計にはあらわれない、ということを示しています。
世の中にはあたまのかたい人というのがたくさんいて、俺もその一人なんだが、すべてのルールは事後的に構築されたものなのに、これを絶対の物差しだと勘違いしている場合がある。法律を破ったのだから悪い人だ、みたいな感覚を、まっとうなものだと信じて疑わない人がたくさんいる。身近に悪いやつ、いやなやつ、いませんか。自分のなかにも「悪」はありませんか。それと「被告人」「容疑者」はぜんぜん別のことではないですか。
陰謀論がささやかれている。「悪いやつがいる、たくさんいる、てのひらで人を転がしているやつと、愚かにも転がされているやつがいる、自分はその被害者でもある」そう発想する立場に対し、逆の立場に立たされている不安を訴える声もありえる。「知らず知らずのうちに、自分は、陰謀に加担しているのではないか。なんならむしろ積極的に参加しているのではないか」あんなふうになってしまうなんてこと思いもよらなかった、ってあとで口走っても遅い。
『コカイン・ナイト』の主人公チャールズは旅行記者で、世界中を飛び回っているから定住地はない。
どこかに行くと、「自分にとって、ここが本当の場所だ」と感じられる旅先に巡り合うことがある。けれどその段階を越えたむこうに、「自分にとって、世界はすべて異郷である。どこにいても、自分は単なる旅人以上のものではありえない」その境地がある、というようなことを池澤夏樹が言っていたかもしれない。言ってないかもしれない。ともかくチャールズは定住地がない。
國分功一郎『暇と退屈の倫理学』には、
遊動の暮らしをやめて定住するようになったとき、人類は、財産や文明を手にするようになった。貧富の差が生じ、法が生じ、退屈が生じた。時代が下って便利になればなるほど、退屈は大問題になってくる。
というようなことが書かれていた。遊動の暮らし云々については資料がない話だから、この本がどれほど学問的に厳密なのかはわからないけど、発想としてはおもしろいと思ったので覚えています。記憶だから、読み返すとそんな話してないかもしれないけどね。
けどまあ、ともかく、遊動し続けていたチャールズは、退屈がまさに大問題になっている地域に巻き込まれるかたちで取り込まれていく。はじめは弟の部屋を使っていたチャールズも、その地域を牛耳っているやつが用意してくれた部屋にうつるときがやってくる。その部屋にはじめて足を踏み入れたチャールズに、こういった言葉がかけられる。「チャールズ、君は家に帰ってきたんだ……」
「今の気分を大いに楽しみたまえ。見知らぬ場所という感覚は、自分にとって、常日頃考えているよりも、もっと近しいものなんだよ」
この記事は当てずっぽうで書き出した日記ではあるけれど、記事のタイトルははじめから決めている。「近さの/なかに/はいる」
ようやく、「近さ」というキーワードを登場させられました。よかった。距離についての話を引き続き。
----------------------------------------------
[3]
いつか「ア・ホロイ」というグループ展で映像作品の発表をしたときに(おれのみヘッポコな)対談イベントの相手として巻き込んだ太田充胤(医師・ダンサー・批評家)が、ちょうどその当時スタートさせていたのが『LOCUST』という雑誌だった。Magazine for travel and criticism|旅と批評のクロスポイント。
執筆者たちはみんなで旅行をしにいく。そしてその場所についての文章を書く。これを集めて雑誌にしている。参加者は批評家だけではないが、肩書は別になんでもよい。いわゆる観光ガイドでもなく、かといって思想ムックでもない。地域と時事に結びついた、批評癖のある人らの旅行界隈記集で、最近、この第三号を買いました。三号の特集地は岐阜県美濃地方。
この本、千葉市美術館で買った。千葉市美術館ではいま、「大・タイガー立石展」が開催されている。立石紘一=立石大河亞=タイガー立石という作家については、これは子供のころ、好きで好きでしかたなかった絵本のひとつの作者として知りました。親近感、懐かしさがある。
60年代、日本のなか美術作家として活動、のちイタリアに渡り、そこで油絵もヒットしますが、同時にデザイナー・イラストレーターとしても、漫画家としても活躍。日本に戻り、絵本の仕事も手掛けるようになります。陶も捏ねます。
ナンセンス、毒々しくも軽妙で、湿度は高いんだけどしつこくない。筆運び色選びモチーフ選び影の黒さははっきりシュールレアリズム由来で、反逆児のフリをしつつジャンルの枠組みは壊さず、荒唐無��なフリをしつつ不穏当で思わせぶり、祝祭的=黙示録的、派手好みのくせに辛気臭くすら感じられるガロ感がいつまでも抜けない。という印象。個人的には。
懇意にしている友人の家、友人なのかな、友人なんでしょうか。一緒にいる居心地はいいんだけど、話題が狭く、政治的な話も教養的な話もしない。あるのは惰眠と食卓で、生理的で予測可能なよろこびしかない。安心安全で退屈な時間を過ごす人。おれは人のことをバカにして生きてる。まあいいかそれはいま。ともかく、友人、そう友人の家を出て、千葉中央駅に到着すると、急に大雨が降りはじめた。美術館まで徒歩にしてほんの10分の距離ですけど雨はものすごい。駅ビル内のダイソーで傘を買って足を濡らして10分歩くなら値段的にもそう変わらないと判断し、駅前でタクシーに乗り込みました。「市立美術館まで」と注文します。「市立?」聞き返した運転手はメーターをつけずに発車、すぐに着いて、料金として500円を払う。車運転させておきながら500円玉1枚だけ払って降車するのは後ろめたい。ちょっと照れくさくもある。
タイガー立石の絵はいわゆるコピペっぽさというか、表面的なトレースが多い。ピカソの泣く女やゲルニカ、ダリの溶けた時計、ルソーの自画像、タンギーのうねうね、そんなものがはっきり登場する。作品によっては、モチーフらは一枚の画面にただ雑然と並んでいる。ライブハウスのトイレの壁みたく、全体のなかに中心のない、みるべきメインの仕組まれていない羅列面。
ずっと好きではあったけれど、とはいえどっぷりハマりこんだ覚えのある作家でもない。距離感としては「シュークリーム」とか「揚げ出し豆腐」みたいな。それでも、さすが小さなころからの付き合いだけあって、自分のなかに、あるいはタイガー立石をみる自分のなかに、自分自身の制作態度の原型をみるようで居心地が悪く、やはりちょっと照れくさくもあった。
もちろんカタログを買う。そのために美術館併設の書店に立ち寄った。そこで『LOCUST vol.3』を見つけたので一緒に買ったのだった。太田充胤が、「おいしい、と、おいしそう、のあいだにどんなものが横たわっているのかを考えた原稿を vol.3に載せた」と言っていた覚えがあったためだ。なんだそれ、気になる。そう思っていたところだった。
ぜんぶで7つのパートにわかれたその原稿の、はじめの3つを、ざっくばらんに要約する。
1・はじめの話題は日本の食肉史から。肉を食べることは力をつけることと結び付けられもしてきた。禁じられた時代、忌避された時代もあった。食肉への距離感っていろいろある。
2・野生動物の肉を食うことが一種のブームになっている。都市部でもジビエは扱われている。ただ、大義たる「駆除される害獣をせっかくだから食べる」というシステムは、都市部では説得力がうすい。都市部のジビエは「珍しいもの」としてよろこばれている? 舶来品の価値、「遠いものだから」という価値?
3・身近に暮らす野生動物と生活が接しているかどうかで、(動物の)肉というものへの距離感は変わる。都市部の居酒屋で供される鹿の肉と、裏山にかかってたから屠って食卓に登場する鹿の肉は、そりゃ肉としては同じ鹿肉であっても、心理的な距離の質は同じではない。
イモムシが蝶になる手前、さなぎに変態してしばらくじっとしている。さなぎの中身はどろどろで、イモムシがいったんとろけた汁であり、神話の日本の誕生よろしく、ここから形状があらわれ、蝶になるのだと、子供のころ誰に教えられたわけでもないのに「知って」いた。それは間違いだった。イモムシの背中を裂くと、皮膚のすぐ裏側に羽が用意されている。蝶の体つきは、さなぎになるよりずっと前から、体のなかに収納されている。さなぎはただ、大一番な脱皮状態を身構えてるだけの形態で、さなぎの中がどろどろなのは、イモムシや成体の蝶の体内がどろどろなのとまったく同じことだった。日高敏隆の本で知った。大学院生のころ、ひとの自作解説を聞いていたら、「イモムシがいったんその体の形状をナシにして、さなぎの中でイチから再編成しなおして蝶になるように」という言い方をしている人があった。同じ勘違いだ。
この勘違いはどうして起こり、どうして疑いなく信じ続けられるんだろう。だって、イチから再編成されるなんて、めちゃくちゃじゃないか。めちゃくちゃ不思議なことがあっても、それが「生命の神秘」や「昆虫の不思議さ」に結びついて納得されてしまえば、「ね、不思議だよね、すごいよね」で済む話になるのか。<現代人・大人たちが昆虫を嫌うのは、家の中で虫を見なくなってきたからだ>という論文を先日みつけました。隣近所の人とあいさつをするかどうかで生活の心やすさは大きく変わる。知らない人の物音は騒音でも、知っている人の物音はそんなに不愉快じゃなかったりする。「面識」のあるなしは非常に重要だから、背が伸びてもなお、公園や野原で昆虫と親しみ続ける人生を送っていれば、虫嫌いにはなっていかないだろう。けれど、そういう人生を送っていたとしても、いったん誤解した「さなぎ状態への理解」が誤りだったと、自然に気づけるものだろうか。
岐阜で供されたジビエ肉についての原稿をLOCUSTに執筆した太田充胤は高校の同級生で、とはいえ仲良しだったわけではない。今も別に、特別仲良しとかではない。なんかやってんなあ、おもろそうなこと書いてるなあ、と、ぼんやり眺めて、でも別にわざわざ連絡はしない。卒業後10年、やりとりはなかった。数年前、これを引き合わせた人がいて、あわせて三人で再会したのは新宿三丁目にある居酒屋だった。ダチョウやカンガルー、ワニやイノシシの肉を食べた。それこそ高校の頃に手にとって、ブンガクの世界に惹かれる強烈な一打になったモブ・ノリオの作品に『食肉の歴史』というタイトルのものがあったな、と急に思いついたけれどこれはさすがにこじつけがすぎるだろう。あ、
ああ、自分の話を書くことはみっともなく、辛気臭いからしたくないんだった。「強烈な一打」たるモブ・ノリオの『介護入門』なんてまさに「自分の話」なわけだが、他人の私小説のおもしろさはOK けど、自分がまさに自分のことを語るのは自分にゆるせない。それはひとつに、タイガー立石はじめ、幼少時に楽しんだ絵本の世界のナンセンスさ、ドライさへの憧れがこじれているからだ。
まとまりがなく、学のなさ集中力のなさ、蓄積のなさまであからさまな作文を「小説」と称して書き散らかし、それでもしつこくやり続けることでなんとか形をなしてきて、振り返ると10年も経ってしまった。作文活動をしてきた自負だけ育っても、結果も経歴もないに等しい。はじまりの頃に持っていたこだわりのほとんどは忘れてしまった。それでも、いまだに、自分のことについて書くのは、なんだか、情けをひこうとしているようで恥ずかしい気がする。と、このように書くことで、矛盾が生じているわけだけど、それをわかって書けちゃってるのはなぜか。
それは、書き手の目論見は誤読されるものだし、「私小説/私小説的」というものには、ものすごい幅があるということを、この10年、自分にわかってきたからでもある。むしろ自分のことをしっかり素材にして書いてみてもおもろいかもしれない、などと思いはじめてさえいる。(素材はよいほうがそりゃもちろんいいけど)結局のところ、なんであっても、おもしろく書ければおもしろくなるのだ。
こないだ週末、なぜだか急に、笙野頼子作品が読みたくなった。『二百回忌』じゃなきゃだめだった。久しぶりに引っ張り出して、あわてて読んだ。おもしろかった。モブ・ノリオ『介護入門』に接し衝撃を受けた高校生のころ、とりあえず、その時代の日本のブンガクを手あたり次第漁っていた。そのなかで出会い、一番ひっかかっておきながら、一番味わえていない実感のある作家が笙野頼子だった。当時読んだのは『二百回忌』のほか『タイムスリップ・コンビナート』『居場所もなかった』『なにもしてない』『夢の死体』『極楽・大祭』『時ノアゲアシ取リ』。冊数は少なくないが、「ようわからんなあ、歯ごたえだけめっちゃあるけど、噛むのに手一杯になってしまってよう味わわん」とばかり思っていた。
新潮文庫版『二百回忌』に収録されているのは4作品。いずれも、作家自身が作家自身の故郷や家族(など)に対して抱いているものを、フィクションという膜を張ることで可能になる語り方で語っているものだ。
『大地の黴』:
生まれ故郷に帰ってきた主人公が、故郷での暮らしを回想する。かつて墓場で拾い、そして失くしてしまった龍の骨が、いまや巨大に成長し、墓場を取り囲み、そして鳴る。小さなころ、その土地に居ついている、黴のような茶色いふわふわが見えていた。地元の人の足元にまとわりついていた。いま墓の底から見上げる、よく育った龍の骨たちのまわりにもいる。
『二百回忌』:
二百回忌のために帰省する。親とは険悪で、その意味では帰省したくない。しかし、二百回忌は珍しい行事だし、すでに死んだ者もたくさん参加する祝祭時空間らしいから、ぜひとも行ってみたい。肉親はじめ自分の人生と直接のかかわりをもったことのある地元の顔ぶれは嫌だけど二百回忌には出向く。死者もあらわれる行事だから華々しいし、時間はいろんなところでよじれ、ねじれる。
『アケボノの帯』:
うんこを漏らした同級生が、うんこを漏らしたことに開き直って恥ずかしがらない。そればかりか、自分の行いを正当化ないし神聖化し、排泄の精霊として育つ。(漏らしたことで精霊になったから、その同級生には苗字がなくなった!)自分のうんこの話をするのははばかられるけれど、精霊が語る排泄は肥料(豊かさ)や循環の象徴であるからリッパである。
『ふるえるふるさと』:
帰省したらふるさとの土地が微動している、どうやら時間もねじれている。いろいろな過去の出来事が出来していく。
----------------------------------------------
[4]
『LOCUST』の第三号の特集は岐阜で、おれの祖父母の実家は岐阜にある。大垣にあったはずで、いまどうなっているかは知らない。
父方の祖母が一年ほど前に亡くなった。おれの祖父=おれの父からすれば実父は施設で暮らしはじめた。住む者のなくなった、父の実家は取り壊された。父は仏壇や墓のことを考えはじめ、折からの歴史好きも手伝って、寺を巡っては話をきいてまわるようになった。寺の住職はすごい。自分とこにある墓の来歴ならしっかり把握しており、急に訪れた父が「うちの母のはいった墓は、いつ、誰がもってきたもので、誰がはいっているのか」と尋ねればすらすらと教えてくれる。
つい数代前、滋賀の彦根から、京都の寺に運んできたとのことだ。ところが運んだ者がアバウトで、京都の寺は彦根の寺と宗派が違う。それもあって、一族代々の墓ではなくて、数代のうち、そのアバウトさに異を唱えなかった人らが結果的におさまっているらしい。よう知らんけど。
続いて調査に乗り出した、母方、つまり岐阜の大垣にあった家の墓の来歴についても、どうやらごまかしが多い。ひとりの「かわりもの」のために、墓の行き先がなくなる事態があったらしい。
昭和のなかごろ、青年らは単身で都会へと引っ越しはじめ、田舎に残してきた墓をそのままにしてると数十年のちに誰か死ぬ。次は誰の番だろうかと悩むころには、あれこれ調べて動かす余裕がない。嫁ぎ先の墓にはいるとか、別の墓をたてるとか、戦死してうやむやになってるとか、ややこしいからウチは墓を継ぎたくないとか、もはやふるさとはないから墓ごと引っ越したいけど親戚全員への連絡の手立てがないのでできる範囲だけを整理して仕切り直すだとか、そういうごたごたを探査するのがおもしろいらしい。
父から送られてきた、一緒に夕食を食べることを誘うメールには、「うちの墓についての話をしたい」と書いてあって、おれはてっきり、「墓を継げ!」というような説教をくらうのかと身構えていたのだけど、全然そうじゃなかった。墓の来歴からみえてきた、数代前のずさんさ、てきとうさから、果ては戦国時代の仏教戦争まで、わがこととしての眺望が可能になった歴史物語を一席ぶちたかっただけだったみたいだ。よかった。
京都で父は祖父、父からすれば実父と、たまにあそんで暮らしている。祖母なきいま、90近い祖父と話をできるのはあとどれくらいかと思いを馳せるとき、父はふと、戦争の頃のことを聞いておこうと思い立った。いままでぶつけていなかった質問をした。
「お父ちゃん、戦争のときなにしとったん?」
祖父は15歳だった。日本軍はくたびれていた。戦局はひどい。余裕がない。15歳だった祖父は、予科練にはいった。
「軍にはいれば、ご飯が食べられるから」と祖父は笑って話したそうだ。けれど理由の真ん中は本当はそこじゃない。どうせだめになるのだ、負けるのだ。自分の兄、つまり一家の長子を死なすわけにはいかない。兄=長男に家は任そう。長男が無理やり徴収される前に、次男である自分が身を投げうとう。
きっと必要になるから、と考えて、英和辞書を隠し持って予科練にはいった。敵の言葉の辞書を軍に持ち込んでこっそり勉強するなんて、見つかったらえらいことになる。
その頃、12歳だった祖母は、呉の軍需工場で働いていた。
生前の祖母、というか、祖父と出会ったばかりだった祖母は、祖父が、長男に代わって死ぬつもりで、自ら志願して予科練にはいっていたことを聞いて泣いたという。
おれの父親は、おれの祖父からそんなような話を引き出していたそうだ。父としても、はじめて聞く話だった。
90近くなった自分の父親が、目の前で話をする。自分の身に起きたこと、戦争時代の思い出話をする。子供の前で語ってこなかった話を語る。なんだか瀬戸内寂聴みたいな見た目になってきている。極端な福耳で、頭の長さの半分が耳である。
本人は平気な顔をして、ただ、思い出を話しているだけなのである。それでも、「大井川で、戦地へ赴く特攻隊を見送った。最後に飛び立つ隊長機は空でくるりと旋回したあと、見送る人々に敬礼をした。」と、この目で見た、体験した出来事についての記憶を、まさに目の前にいる、親しみ深い人物が回想し話しているのに接して、おれの父は号泣したという。これは「裏山にかかってたから屠って食卓に登場する鹿の肉」なのだ。
戦争への思いのあらわれた涙ではない。あわれみや悲しみでもない。伝え聞いていたという意味では「知って」いたはずの戦争だが、身近な存在たる父親が直接の当事者であったことがふいに示されて、戦争が急激に近くなる。父親が急激に遠くなる。目の前で話されていることと、話している人との距離感が急激に揺さぶられた。このショックが、号泣として反応されたのではないか。食事中、口にする豚肉を「ロースだよ」と教えてくるような調子でふいに、「この豚は雌だよ」とささやかれて受けるショックと同質の、「近さ」についての涙なのではないか。感情の涙ではなくて、刺激への反応としての落涙。
これでひとまず、自分の描く分を切り上げる。思えばいろいろなトピックに立ち寄ったものです。ラブコメにはじまり、犯罪的行為と共同体の紐帯の話、内的な事件「恋」の取り扱い方、ジビエを食べること、故郷についてのマジックリアリズム。
散らかすだけ散らかしておいて、まとめるとか、なにかの主張に収束するということもない。中心がない。さながらライブハウスのトイレの壁みたく、みるべきメインの仕組まれていない羅列面。
この羅列面に対して連想されるもの、付け足したくなったものがあれば、各々が好き勝手に続きを書いてください。うまく繁茂すれば、この世のすべてを素材・引用元とした雑文になるはずです。や、ほんとのことをいえば、すでにテキストというものはそういうものなんですけど。
1 note
·
View note