#緑高校サッカー部
Photo

『U14合同TR 1.21』 本日は名古屋市立緑高校サッカー部、名古屋市立山田高校サッカー部との合同トレーニングでした⚽️ 今回はA級コーチの渡邉先生の指導の元、グループでの守備がテーマでした。相手のオフェンスの動きを見ながら、チャレンジ&カバーやスライド、限定からのボール奪取まで繰り返しトレーニングしました。3チーム合同だからなのかもっと声を出してコーチングをしていかないと上手くいかないかなと感じたのでどの年代になってもできるように習慣化しなくてはいけないですね☝️ 本日も監督とお話しする時間もいただきありがとうございました😊今の公立と私学の違いは3種の部活とクラブのような構図になっているようです😓やはり部活動の縮小化の影響もあり、本気でスポーツに打ち込みたい選手はクラブチームや私学という流れになりそうですね。大きな問題だなと感じました。。 OBは1人会うことができました。ただいまレギュラー争い真っ只中のようなので頑張ってもらいたいです😁 2023年度ジュニアユースチーム、ジュニアチーム選手募集中です‼️各学年定員18〜20名(FP16〜18名、GK2名)になり次第締切⚽️原則、試合時は全員出場の育成重視のクラブチームです👍 マイクロバスを保有しているため、遠方での試合は送迎のお手伝いをさせていただきます🚌 無料体験受付中‼️無料体験は3回あります。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください😊 小中学年代で身に付けておくべき個人技術(蹴る、止める、運ぶ)と攻撃および守備の個人戦術、グループ戦術を年間を通してテーマごとに学び、週末の試合に向けてトレーニングを積み重ねていきます。 #緑高校サッカー部 #山田高校サッカー部 #FC東郷 #無料体験受付中 #選手募集中 #中学生サッカー #小学生サッカー #愛知県サッカー #東郷町サッカー #日進市サッカー #みよし市サッカー #豊明市サッカー #名古屋市サッカー #豊田市サッカー #刈谷市サッカー #ジュニアサッカーチーム #ジュニアユースサッカーチーム #サッカークラブ #賛助会員募集中 #スポンサー募集 #サッカーコーチ募集 #サッカー審判員募集 #ボランティア募集 公式HP http://www.fctogo.jp 公式Instagram @fctogo2003 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/fctogo2003 公式LINE https://lin.ee/47np89glG 公式Twitter @fctogoaichi https://www.instagram.com/p/Cn8KSjjBjwQ/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#緑高校サッカー部#山田高校サッカー部#fc東郷#無料体験受付中#選手募集中#中学生サッカー#小学生サッカー#愛知県サッカー#東郷町サッカー#日進市サッカー#みよし市サッカー#豊明市サッカー#名古屋市サッカー#豊田市サッカー#刈谷市サッカー#ジュニアサッカーチーム#ジュニアユースサッカーチーム#サッカークラブ#賛助会員募集中#スポンサー募集#サッカーコーチ募集#サッカー審判員募集#ボランティア募集
0 notes
Photo

高校生カット✂︎ いつもありがとうございます♪ #メンズカット#高校生カット#部活男子#サッカー部#完全予約制美容室#プライベートサロンplus#名古屋緑区美容室 https://www.instagram.com/p/Cdwp0T4hVwE/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text



ミスドのポケモンドーナツ食べまくった。仕事帰りにモンボのドーナツ、休みの日にコダックのドーナツ食べて、朝食にピカチュウのドーナツ食べた。ピカチュウが一番美味しいし可愛い。中がチョコの生クリームなのがいい。
実家にきてから、意外と痩せていない。基本水を飲むようにしていて、朝晩2食だけにしてるのに。仕事も一応肉体労働やし。それにしても、佐川の仕分けって機械で勝手に振り分けるものかと思ってたのに手作業とは。レジだって自動化してるのに、単純に見えるけどもなあ…まあ配達員とかは人間がいいんだろうけどもさ。単純作業のわりに時給は良いし、ある意味では楽だが、この仕事が果たして10年後にもあるのか?という感じではある。

セリアでシナモンの自転車の鍵のキーホルダー買っちゃった。自転車の鍵持ってるシナモンのデザインがかわええ。買うのちょっと迷ったけど110円でこのクオリティは良い。本当はちいかわのやつ欲しかったけど、入手困難なのでw昔Twitterでシナモンいじめが流行ってたの思い出す。
ᙏ̤̫͚
なんか毒舌な人って精神疾患率やたらと高い気がする。なんか決めつけてキツいこと言う人。うつ病とかになって精神薬飲んでたりするんよなあ。よくうつ病になる人は優しいからとかも聞くけどもさ、普通に話してると、そんな気の強いこと言うんや…てちょっと引く時がめちゃある。毒舌やからバチが当たったんじゃ…とか思う時もあるほど。まあ余計なこと言わんのが一番や���な。毒舌で面白い芸人キャラ!みたいな感じを目指した、みたいなところもあるんやろうけどもさ。結構芸人さんとかも鬱の経験ある人とか多いよな。HSPだっけ?いわゆる繊細さんです、とか告白したり。なんか最近は毒舌の人=メンタル弱いという印象になった。
ᙏ̤̫͚
女の友情は脆いと聞くけども、男の友情も結構脆いと思う。女と同じかそれ以上に。ドイツに住んでた時、語学学校のロシア人と韓国人の男の子いつも休み時間にサッカーのボードゲームで遊んでて、放課後も一緒に遊びに行ったりめちゃくちゃ仲良いんだなとか思ってたのに、お互いのいない場所ではお互いの悪口言ってるの。それまで男同士の友情は良いものだという刷り込みがあったからめちゃくちゃ衝撃だった。男は大人になると友達いない人多くなるよね。女は比較的、環境に合わせて幅広い付き合いして行く人多いのにさ。おっさん同士の友情ってほぼ見ないよね。おっさん同士の会食って仕事の関係での付き合いばっかりになってるのよく見るけど、学生時代からの親友で〜みたいなのって少ない。それで男同士の友情の薄さが証明されるよね。ロバートは子供の頃からの幼馴染の男友達がいたらしく、40代ぐらいまでは会ってたらしいが、今は嫌っていて会いたがらないんだよな。その幼馴染は典型的な負け組というか弱男らしく、彼女もいないし、底辺みたいな家に住んでて、借金があって、性格もいつまでも小学生男子みたいな感じで嫌になったらしい。Facebook見たんだけども、良い年のおっさんなのに謎に遠近法でビルを摘んでるみたいな写真撮ってるのには驚かされた。それ一枚でいかに幼稚な人なのかわかるってすごい写真だわ。
ᙏ̤̫͚
職場では挨拶して、なんか言われたら、すみません、ありがとうございます!て言うようにしてる。もう機械的に。そしたらそんなに怒られることもないしな。なんか謎にプライド高くて意地でも謝らん人とかいるけども、わたしは謝った方が結局は得やからすぐ謝るようにするって言う考え方になった。挨拶返されなくても、一応挨拶もした方が確実に印象いいし、損することはないから。タダで簡単に得することができるからいくらでもやるわって感じでやってる。こんな簡単な理屈に気づかず、挨拶できないままの人間ってアホなんやなって思う。良い人っぽい印象つけれるし、その方が得やのに。なんか挨拶きちんとする人少ないからか、私も8日間しか働いていない新人で知らんことだらけなのに、さらに新人のひとにめっちゃ聞かれる。そして社員さんにも教えてやって、とか言われるしさ。おめえらが教えろや、とか思うわ。適当なこと教えるかもしれんし、実際適当なこと教えてしまっている。
ᙏ̤̫͚
池田大作死んだよね。もうかなり前から死亡説囁かれてたから、今さら発表したんやなあって感じ。親がどんな反応するか楽しみ。まあ北の将軍様が亡くなった時みたいに演技せなあかんとか決まりないから結構ドライな気もするが。キリスト教も性加害問題やら色々闇が深くて嫌いなんやけども、基本金かからんし、新品じゃないものでも寄付としてリサイクルショップに持って行けるのが良い。仏教は坊主ボリすぎやし、宗教なんて無課税なんやから金たくさんあるやろって思ってる。まじで宗教全般嫌いやから基本葬式とかいらんし、私が死んだら散骨してほしいとか思う。ロバートも散骨希望してるし。墓の代わりに遺骨ペンダントにして身につけようかなとか思ってる。遺骨や遺灰を持ち歩くの気持ち悪いとか聞くけど、私は全然何とも思わない。鶏肉の骨とか魚の骨と同じようなもんやと思ってるから。犬が骨を土に埋めて隠すのを何にも思わんような感覚。
ᙏ̤̫͚
髪の毛、9月にボブにしてから今そんな伸びすぎた感じもなく、私にしては毛量多く見えてちょうどいい感じなんだけども、来月給料入ったらちょうど3ヶ月になるから切りに行こうと思う。また同じ美容院いけんから、家の近くのモール内にある安い美容院で切ろうかと。調べたら最安値だし、予約もいらんぽいから突然行ってもいけそうなのも良い。切った時の自分の写真持って行ってこんな感じの切りっぱなしボブで、とオーダーするつもり。私の髪質やとすごいカット楽やと思う。前回は、ほぼ一発でぱつっと切れば完成って感じやった。前髪ずっと自力で切ってたから、前髪の幅とりすぎて今伸ばし中なんだけども、来月切りに行ったらちょうどいい感じに他の髪と同じ長さになりそう。ていうか緑髪長持ちすぎてやべえ…インナー部分を早くネイビーにしたいのに、こんな綺麗な緑もったいなくてできんw染めるの来年になりそ…ビューティーンの安いやつでセルフで染める気なんだけども。
1 note
·
View note
Text
一章
1992年12月20日、バブルが崩壊した3ヶ月後、私は祝福ムードの中、四日市市の病院で生を受ける。四日市は工業地帯として知られていて、四日市ぜんそくという公害問題を発生させており、空気の悪い街だと思われるが、私が育った町は鈴鹿山脈近くにある小さな町で、さらに伊勢茶を作る農業を生業とする人が多数いる茶畑に囲まれた緑が豊かすぎる地域だった。港近くの小学校では石油コンビナートが発生させる光化学スモッグにより警報が出て、窓を閉めなければいけない状況の中、私達は春には新茶の匂い嗅ぎながら鈴鹿山脈を見上げ校庭を走り回っていた。コンビナートもコンビニもないこの小さな小さな田舎町の駄菓子屋で友人と塩辛いイカの燻製を噛み、くせーくせーとクサいのを笑い合いながら、秘密の場所を作りに街を歩き回る。秘密の場所、親も近所の大人もクラスの連中も少し年上のお兄さん、お姉さん達も誰も知らない俺とお前しかしらない秘密基地を探しに日々誰も寄り付かなそうな場所をディグをしていた。廃家は俺たちの中では無しだった。俺たちはそれを誰かが所有していて誰かの管理下にあるのを何となくわかっていて、見つかったら殺されると思っていた。初めての性体験、幼稚園、好きな子の裸を見てチンチンが大きくなったあの日。あの日の情熱で秘密基地を探していた。近くの池の側にあった木に囲まれた墓の跡地のような小さなスペースに宝物を持ち寄りそこに隠してそう。そう言って友人と竜の剣のキーホルダーを土に埋めた。結局その場所は大人にバレ、立ち去るように言われ、立ち退いた。そもそも友人が別の友人にその秘密の場所のことを話してしまったので遅かれ早かれその場所は使えなくなっていた。最早秘密でもなんでもないが俺たちは俺の家の一角を使って家を作らないか?と話し合い、親の寝室の一角(なんと大胆なチョイスだろう)にマットレスで屋根を、段ボールで壁を作り、中に懐中電灯を置き、好きな漫画やおもちゃを持ち寄って、その中で特に何をするわけでもなく、何かに熱狂していた。親の寝室に建てれた城は夜には見事に解体され、マットレスは寝具に変わり、段ボールが捨てられて、漫画本は本棚に返された。それが凄く悲しかったのを覚えている。自分には家や寝室以外にプレイベート空間が必要だった。それからは友達との秘密の場所から、自分1人の場所として基地を作るようになった。齢6才や7才でプレイベート空間を求めるような弱い人間だった。常に不安感を抱き、この頃は最も吃りが酷い時期で親の前でも緊張していて、おねしょで朝起き、給食は喉を通らず全て吐いて、先生や親は理解できず不満がっていた。大人たちも友達も皆「お前は恵まれている」と言った。自分にはその意味がわからず「辛い」という気持ちを言語化できず、それを伝えられずにいた。その辛さは15才の時ロックンロールに改宗した時に全て呪詛と涙と言葉の暴力で表現するようになるがそれは10年後の話。周りの友達同じように話せない、ご飯すらちゃんと食べれない、そんな自分恵まれている‥ 俺はそんな矛盾を検証しようとせず、特撮、テレビドラマやポップ音楽に寄りかかった。特撮ではゴジラ、ウルトラマン、戦隊ヒーロー、仮面ライダー、どれが1番好きと言えるまでの熱量は無かったのでわからないが、特撮に惹かれてたのは怪獣、怪人の造形美だった。醜悪でもどこか美しい悪者達が、全てを与えられたようなナイスガイ達を蹂躙していく‥ その様が爽快だった。ウルトラヒーローシリーズにでてきた「ガタノゾーア」という怪獣は衝撃的で、顔が逆向きについてい非常に醜悪でカオス極まれりといった具合の造形でゾクゾクしのを覚えている。そいつがお決まりのウルトラ光線で逝った時の虚しさったらなかった。好きな怪獣達は引き分け、同時死になる事なく必ず負けて、爆破され灰になる。ガタノゾーアの造形を超えるナイスガイに会える事もなくなり特撮からは遠ざかった。小学3、4になりそれからはコメディドラマを好んで観るようになる。現実とは違う、軽快で底の底までシリアスにならないタッチが不安な心を軽くしてくれた。ムコ殿というドラマが特に好きで松任谷由美の7 TRUTHS 7 LIES〜ヴァージンロードの彼方でのメロディには衝撃を受けた。(これは高2で聴いたmy bloody valentineの衝撃に近い‥ )それからドラマやアニメから音楽を知るようになり、音楽も心を癒してくれるように重要なものになった。ロングラブレターの山下達郎/Loveland irand ちびまる子ちゃんのカヒミ・カリィ/ハミングがきこえる(もうすでに小山田圭吾から啓示を受けていたのだ)広瀬香美が��うカードキャプターさくらのOP、ED、人にやさしくのthe blue herts/夢(ロックンロールの洗礼はまだ受けていない)ナースのお仕事のOPナンバー、ポンキッキーズの楽曲、などポップなものが多かった。逆に暗いマイナー調のフォークやシリアスで真面目で建設的なバラードには拒否反応を示していた。大袈裟で心を不安にさせる音楽だと嫌っていた。親のカーステで聴いたSMAPのポップな曲達は今でも忘れられない。リアルタイムで大流行りしていたらいおんハート夜空ノムコウにより80s昭和アイドル路線、お花畑で能天気なムードに心を置いていた。また、90sに入ってからのサウンド、スタイルカウンシルズ〜渋谷系直撃な小洒落たサウンドも大好きだった。シェイクは今でもアガし、しようよには良質なグルーヴがありノレる。キリンジ作曲の恋の灯には心を大変苦しくさせられた。初恋の感覚それと同じ、いやそれ以上の甘苦しさ‥ SMAPは今の自分のポップスの物差しの重要な一部なっており俺の偉大なるルーツだった��その時のリアルタイムがドリンクSMAPというアルバムで(ナンバーワンより特別なオンリーワン収録)00年代を象徴する80年アイドルソング的能天気さとは違う、いかにもお涙頂戴的で安い感動や、紋切り型のポジティブを歌う不気味な能天気さは俺の心を暗くした。その年友達の家族と自分の親とSMAPのコンサートに行ったのは忘れられない‥ライブの原体験、心の底から楽しかった。小学4、5年になるとテレビから流れる音楽、ドラマは好みものが減ってきて距離が遠くなった。松浦亜弥は好きだった。底抜けにポップだったから。この頃は友達と同じゲームをして、同じおもちゃで遊び、普通の小学生を真っ当していた。真っ当していたが心は貧しかった。ゲームはレベル上げで友達より優位に立ち、承認欲求を満たせた。そしてそのレベル上げという地道な作業は鬱を忘れさせた。ゲームは心を豊かにさせるものではなく周りとのコミュニケーションツールに過ぎなかったのかもしれない。この頃の鬱とと言えば、大きく2つ、進学校に入学するための進学塾入学とサッカー少年団入団、この2つだ。進学校行きは親が決め、サッカーは友達がやっているゲームと同じゲームをするのと同じ感覚で自分から始めた。まず進学塾の授業長さと内容の難しさに驚いた。水曜の放課後バスで1時間かけ街まで行き、17時から20時まで授業受け、また1時間かけ21時に家に帰る‥ そして土曜は12時から18時までという殺人的な長さ、小学生には無限のような時間、さらに学校の成績の悪い自分には恐ろしく難解な授業、これによ「時間」という概念がぶっ壊れ、時間=なんとくなく過ぎ去っていくものだったのが、苦痛で永遠のような時間という種類が存在し、それに耐え、やり過ごさなければならないという問題直面する。同時に初めサッカーだったが、これにも問題があった。単刀直入に全くセンスがなかった。体が硬く、不器用で球技のセンスがなかったのと、体と体で思いっきりぶつかり合う攻撃的な部分にも繊細で鬱気味なメンタルの自分には全くハマらなかった。仲のいい友達が皆同じチームに入っていたので、やっぱり辞めたと言い出せずしぶしぶ続けていた。昨日のあれはいい試合だったねと友達が言って「すごく良かった」と返したが、俺がサッカーで興奮したことは人生で1秒も無い。ある日、練習試合があり、相手チームのやつらが自分の持っているボールめがけて突進してくる。俺は頭が真っ白になり、脱力し、退場した。この時辞めておけばよかったんだ。時間の無駄をした。進学塾ではテストがある度順位が張り出され、それによってクラス分けをされ、自分は最下層の「Sクラス」にいた親から叱られ、自分は親の機嫌を伺い、必死で言い訳を考えた。「今日は調子が特別悪かった、今度はうまくやれる」 それによってどんどん精神がすり減った。今ではお馴染みの精神的苦痛。また同時に肉体的にもやられていた。炎天下で行われる坂道ダッシュ、タイヤ轢き‥ 週の半分が地獄のような時間でついに心がぶっ壊れた。自分より楽しそうなやつを見ると嫉妬したし、そんな自分の事を「恵まれている」という風に言ったやつの喉を裂いてやりたかった。疑心暗鬼にもなり友達は俺を蹴落としにくる(これは人は何時でも足元も見てくるという母親からの教えの影響もあった)と思い込み、ついに緑の田舎町の景色がモノクロに変わった。この時点でもう誰のことも信用しておらず、母親ですら自分を不安にする悪役的な存在だと思い込み、家庭内政治に参加ぜず家にすらいない父親は眼中になく、もうコイツらだめだと思い、自分で自分を守るという人生初めてのモードに切り替わる。汚い言葉で武装して相手を罵り、頭の中で計画する殺人、悪意を持ってありとあらゆる嘘をつき、全員を傷つけた。親の機嫌を伺い媚びるのが嫌になり、テストではカンニングも用いてトップクラスに行き、泣いてる親の顔を見てそれが凄く滑稽で自分は勝ったみたいに満たされた。俺は親を出し抜いた!初めての反抗だった。やり方は卑怯であったが、そんなの関係なかった。理不尽では理不尽でやり返す。友達にも同じような事をしていた、嘘をつき、友達と友達を喧嘩させ、
1 note
·
View note
Photo

【習慣変更ダイエット】40歳男肥満体型がダイエットに成功した7つの習慣変更について 酒好き40歳男肥満体型がダイエットに成功した7つの習慣変更ダイエットについて こんにちは野口です! 初めて痩せました!!! 酒好きの私ですが、コツコツと継続を続けた「習慣変更ダイエット」で食生活の見直しと、運動で、20歳から約20年間増え続け、減ることのなかった体重 約85kgが、現在75kgの高校時代の体重に戻ることができました! 今回、振り返ってみると、ついつい陥りやすい7つの習慣を変更しただけです。 そこで、食べなくなった食事、食べ物がでてきたり、運動も習慣化することで、ダイエットにはじめ成功した「変更した習慣(習慣変更ダイエット)」を詳しくご案内していきたいと思います。 それでは、変更した習慣の結論から! 1,なるべく原型に近い食品をよく噛んで食べる 2,コンビニ食(極力)禁止 3,加工食品(極力)禁止 4,ジュース(極力)禁止(※しかし、お酒は毎日飲んでます笑) 5,運動は、朝の40分ウォーキング+ストレッチ 6,睡眠は早めに寝て7時間程度 7,お腹が減ったら食事をする 高校生の時(18歳)が身長176cm体重75kgで、もちろん高校時代はバリバリ部活でサッカーで運動をしていたため、痩せていましたが、その後、大学でアルコールを飲むようになり、社会人には、80kgオーバーに。。。 25歳くらいからは85㎏になり、これではいけないと様々なダイエットを実施! <失敗してきたダイエット> 炭水化物抜きダイエット タイガーダイエット(一日一食夜に肉) サプリメントダイエット 黒酢(アミノ酸)ダイエット 特保飲料ダイエット 高濃度緑茶ダイエット キトサンダイエット りんごダイエット メモ(食べたのもをメモる)ダイエット プロテインダイエット 、、、何でもやって試してみましたが、習慣が続かず食べ物系でのダイエットや、健康食品、加工飲料、サプリ系は、ほぼ意味がありませんでした。 お金もかかりますし、習慣にできないのです。 つい先日まで、身長176cm体重85kgの肥満体型で、健康診断はいつも「痩せましょう」+「高血圧 上150オーバー、下100オーバー」でした。 そんなある日、本気でダイエットを始めるキッカケとなったのが、、、、 娘が生まれたことです。 デブなお父さんになりたくない!!! 2018年娘が生まれたときから、この肥満体型ではいけないと思い、ダイエットを決意。 最新の健康医学本を要約したYouTube動画を見て勉強し、私自身で7つの習慣変更してダイエットできました。 そして初めて、高血圧肥満体型から脱却!ダイエット成功です(笑) 【習慣変更ダイエット】40歳男肥満体型がダイエットに成功した7つの習慣変更について 2018年1月の写真と、現在2021年7の写真です。 もちろん2021年の健康診断でも問題なしの判定をいただきました! それでは順番に説明を行っていきます。 1,なるべく原型に近い食品を「よく噛んで食べる」 原型の食べ物を選び、よく噛んで食べる習慣です。 まず「よく噛んで食べる」ことさえもできない人は、ダイエットはできません(笑)と本にも記載がありました。 この後説明する、制限や、運動などの習慣も続くわけがありません(笑) たしかに! まずは、これだけでも意識するようにしました。 そして、なるべく原型に近い食べ物を食べました。原型とは、加工されていないもので、野菜であれば生、煮る、焼いてで食べることや、肉等も同様です。この後の2,3,で記載していることにも関わりますが、生、焼く、煮る、揚げる、蒸す等の調理で食べることが重要で、加工されたのもを極力減らすことを意識する食生活をしました。 2,コンビニ食(極力)禁止 コンビニに行かない習慣です。 コンビニ食は極力禁止にしました。たまに時短で食べますが、コンビニ行くのはコーヒーを買うときしか寄りませんでした(笑) 最近では、原型に近い食品もでていますが、コンビニの料理を一切シャットアウトする習慣にしました。 3,加工食品(極力)禁止 加工製品は極力食べない習慣です。 ▼続きはこちらも↓ http://www.nogu.biz/2021/07/diet.html #ダイエット #ムキムキ #ダイエット法 #習慣変更ダイエット #習慣ダイエット #diet #コンビニ禁止 #ストレッチダイエット #ストレッチ #コンビニ禁止ダイエット #加工食品禁止 #加工食品禁止ダイエット #よく噛むダイエット #よく噛む #ウォーキング #ウォーキングダイエット #寝る #睡眠ダイエット #睡眠 #オートファジー #オートファジーダイエット #黒酢ダイエット #キトサンダイエット #炭水化物ぬきダイエット #リンゴダイエット #飲料ダイエット#プロテインダイエット #プロテイン #デフ #肥満 https://www.instagram.com/p/CRnEeC9hT-n/?utm_medium=tumblr
#ダイエット#ムキムキ#ダイエット法#習慣変更ダイエット#習慣ダイエット#diet#コンビニ禁止#ストレッチダイエット#ストレッチ#コンビニ禁止ダイエット#加工食品禁止#加工食品禁止ダイエット#よく噛むダイエット#よく噛む#ウォーキング#ウォーキングダイエット#寝る#睡眠ダイエット#睡眠#オートファジー#オートファジーダイエット#黒酢ダイエット#キトサンダイエット#炭水化物ぬきダイエット#リンゴダイエット#飲料ダイエット#プロテインダイエット#プロテイン#デフ#肥満
7 notes
·
View notes
Text
つづき 1
韓国務安空港。
ひどく小さく、驚くほど何もない。
セブンイレブンとコーヒー屋さん。
国際空港なのに英語はあまり通じず、英語の表記も少ない。
ツアーで行ったいくつかの地方空港を思い出す
成田や羽田に慣れていてそれが当たり前と思っている自分に気づく
朝5時に到着し、フライトは11時。
旅行会社に勤める知人が手配してくれたチケット、ちっとも後悔はしていないけどこういう工程の旅行は最後にしようと心に決める。
安いことを差し引いても、時間や体力を考えたらぜんぜん割りに合わない
韓国の空港の女の子たち(なんていうのだっけ、CAではなく)はみんな可愛らしくて感じがいい
みんなみっちりとファンデーションを塗っている。女の子のしゃべる韓国語の響きが可愛くて好きだ 語尾がちょっとあがる感じが。
フライトまでようやくあと1時間と少し。
出国ゲートを入ってもハンバーガー屋さんと小さなデューティーフリーしかないことを往路の経験から学んでいるのでぎりぎりまで外で待つ。
さっきようやく空いたコーヒー屋さんでハーブティーを啜っている。
ウラジオストクではなんだかコーヒーを飲み過ぎた
旅先でひとりでいるとなんとない隙間を埋めるのにコーヒーは有効な手段なのだった
***
電車を降りたその海沿いの街で、マーケットを少し物色したあと通りを渡って少し歩くとまた団地に出た。今度はもっと大きいやつ。何棟も同じよう建物、だけど棟によって壁の色が違っていた。
全て白のもの、薄いピンクのもの、そして所々が黄色と緑のもの。
Googleマップを見てみると図書館がある。
すぐ隣の建物の反対側に回ってみるとそこが入り口だった
建物の壁がべたーっと水色に塗られていて、そこにトラと本棚の絵がペイントされていたのですぐにわかった
重たそうな鉄の扉が閉まっていたけど、隣にOPEN HOUR 10:00-20:00と書かれていたので躊躇いがちに手をかけてみると開いた。
図書館というか小さな学校の図書室、という感じ。手前が大人向け書籍、奥の部屋には絵本など子供向けの本が置かれていた。
隣の部屋ではおばさま方が集まって何やら小さなパーティーのようなものが催されていた。賑やかな音楽と笑い声が洩れ聴こえていた。
団地をぐるーっと歩くと学校もあった、きちんと整備されたグラウンドでは男の子たちがサッカーをしていた。
再び通りに出た。角に小さなスーパーがあり、試しに入ってみる
何の変哲もないただのスーパー。
端の棚から順番に物色。お菓子コーナーに差し掛かるとロシアのスナック菓子を紹介しているサイトで見たのと同じパッケージを見つけた。
思っていたよりだいぶ大きい。
ロシアでは人気のスタンダード、のように書かれていた(ような気がする)
ちっともお腹が空いていなかったし、これを食べたらまたごはんが食べられなくなると思い散々迷ったけど結局レジに持っていく
(2日間こんなことの繰り返しだった)
封を開けて、駅に戻るまでの道を歩きながらかじってみる
びっくりするほどの甘さ
砂糖の塊だ、と思った
柔らかめのクッキーのような生地にりんごジャムのようなものがサンドされていて、上にはアイシング
砂糖の塊だ
これはさすがにぜんぶ食べられないかも、と思いながらも結局すぐに平らげた
もう一度マーケットに立ち寄って、お土産用に量り売りのお菓子を買う
たぶん主にチョコレートだろうと思うけれど、キャラメルやマシュマロもあるのかもしれない
いろんな種類を少しずつ、かわいい包装のものを選ぶ
言葉が通じなくても身振り手振りで買い物はどうにかなる
そうして駅に戻ると、市内に戻る13時半過ぎの電車が恐らくちょうど出てしまったくらいの時間だった。次の便まで30分少しある。歩道橋を渡って海の方に降りてみる。
おばあちゃんと孫ふたりが遠くへ歩いて行ったのが見えた、それから少し離れたところに高校生だろうか、男女のグループがいた(カメラを向けたらピースしてくれた)
日差しが強くて、首の後ろがじりじりした。
羽織っていたカーディガンを脱いで首にかける
風が心地よい。
あまり遠くに行かないように、駅の近くをうろうろして海を眺めたり写真を撮ったりした
考えるべきことはなにもなかった
ほんの5〜10分だったと思う、早めに駅に入ろうと歩道橋を登り始めると大きなアナウンスが流れた
何を言っているかはもちろん分からないけど、ウラジオストクという単語を拾った
嫌な予感がする。
でもそんなはずはない、何度も確認をした、ホームの電子掲示板でも、チケット売り場の時刻表でも。
腕時計をもう一度見る。まだ14時前だ。
大丈夫、と自分を落ち着かせながら歩道橋を渡る。
だけど電車は来た 真っ赤な鉄の、重たそうな車体がたしかにウラジオストク方面行きのホームに止まった。
チケットを買わなくてはいけないから間に合うはずがないと思いながらも、とりあえず走ってみる
チケットカウンターにはなぜか長い列が出来ていて、しかも先頭の男性が話し込んでいてしばらく動きそうにない。
荷物チェックのゲートの横に立っている制服の男性に「チケットないんだけど乗りたいから行ってもいいか」ととりあえず英語で尋ねる
幸い少し英語がわかるらしく「Go downstairs」と言われる
通じているのかどうか定かではなかったが、とりあえずThank youと言ってエスカレーターを走り降り、降りて来た乗客たちとすれ違いざまにぶつかりそうになりながら長い通路を渡り、階段を降りる。
間に合った。
なぜかこれまでと違い車両の扉のところに制服の女性が立っている
乗り込もうとすると何やらまくし立てながら首を横に振っている
全くわからない
チケット?と聞くけれど反応はなくロシア語でずっとなにかを説明している
とにかくわからない
ウラジオストクの電車は、チケット売り場でお金を払うと日本のスーパーなどでもらうのと同じような、ペラペラのレシート(なのかチケットなのか)をくれる。
駅によっては改札がある場合もあるが、あっても機能していない。
誰でもホームに入れる。
そうして列車に乗り込むと制服のおばさんたちがやってきてレシートをチェックし、ボールペンで印を付ける仕組みになっている。
だから本当は先にちゃんとチケットを買わないといけないのだけど、この電車を逃したら次は3時間後だ。多少無理をしても出来れば乗りたい。
チケット代は車内か降りるときに払えば良い、どうとでもなると思った
ただ、この女性が何を言っているかとにかくさっぱりわからない。
チケットを持っていない後ろめたさから、乗車時にチケットを確認するのが常ではないことを理解しながらも、ほかに理由が思い浮かばずチケットを見せろと言われているのだと思い、仕方なくチケットを買いに階段を引き返す。
(だけど今思えばあれはやっぱりチケットが理由ではなかった気がする。紙を出せと言っている素ぶりではなかった。ウラジオストク行きではなかったのか、あるいは車庫に入る列車だった?)
案の定そのあとすぐに電車は行ってしまい、チ��ット売り場の横の掲示板には3時間後の時刻が表示されていた。
ぽつんと取り残されたわたしはあぁなんだか旅っぽいなぁと思いながらも、あと3時間こんななにもないところでどうしようか、だけどなんとかバレエに間に合う方法はないのか、なぜあの電車に乗せてもらえなかったのか、なぜ電車は予定時刻通りに来なかったのか、など、ぼんやりと考えを巡らせていた。
(つづく)
3 notes
·
View notes
Text
君といた夏
はじめに
まさか全て書き直します羽目になると(^_^;)
理由はこの小説を某小説サイトに載せようかと思いまして流石にツンデレ娘の続編は不味いかと(^_^;)
小説サイトの方々にもあべみかこ様を知って貰うのが狙いでもある。
まぁ、自分の小説にそれ程の人気があるとは思えないが少しでもファンが増えればと(^_^;)
と言う事なので初めからやり直し(>_<)
今回は初っ端から少し重たい話になってます。
それでは始まり、始まり〜(笑)
プロローグ
私は電車の椅子に座り流れる風景をぼんやりと眺めている、1人、2人と乗客が降りて行き寂しさが増していく。
私が高校生の頃、毎日この電車で通学していた気の合う仲間とお喋りして笑ったり、泣いたり、怒ったり毎日が楽しかった。
あの頃が懐かしい、皆どうしてるのかな?
私が物思いに浸っていると電車のアナウンスが終点を告げ電車がホームに滑り込む、私は無人駅のホームに降りる。
白塗りの駅舎、小さなホーム、途切れた線路、あの頃と何も変わってない。
私はホームの先端に立ち途切れた線路を見ながら大きく深呼吸した、空気が美味しい。
私は畠山ちひろ、アラサーの30歳この村の出身です。
あの頃の私はこの村が嫌で仕方が無かった。
流行り物を買いに行くにも麓の街まで行かなければらならない、娯楽だって無い、何処に行くのも時間がかかる。
だから私は麓の大きな街に引っ越し、その街で一生を過ごす筈だった。
私には生涯を誓った彼が居た、初めての街、初めての職場でまだ友達も居なくて右も左も分からない私に優しく教えてくれた2つ歳上の彼、2つ歳上なのに何処か頼りなくて、おっちょこちょいで、意気地無しで、優しい人でした。
ある日、私と彼がデートの最中の出来事でした。
「ちひろ危ない!!」と、突き飛ばされてその後の記憶がありません。
気が付いたのは病院のベットの上でした。
全身に包帯を巻かれて身動きが取れない状態でした。
その時、彼の死を告げられたのです。
事故でした、突然飛び出して来た子供を避けた車が私達の所に飛び込んで来たのです。
私は彼の死を受け入れられず、ただ天井を眺める毎日、ただただ涙を流す毎日、いっそうあのまま死んだ方が良かったと何度思った事だろう、その度に彼が夢に出て来て生きろと言うのです。
私はどうしたら良いか分からず、生きる意味も分からず、抜け殻の様にただ茫然と過ごす毎日、そんな私を見兼ねた母は実家に帰っておいでと言い、そして私はこの村に戻ってきた。
私がホームで線路を眺めていると。
「ちひろ?畠山ちひろだよね?」
と、呼ばれ振り向くと見知らぬ男性が手を振っている。
目を凝らしてよく見てみると、ボサボサ頭に黒縁メガネ、深緑のジャケットに黒のパンツ、それにママチャリ。
ダサ、て、誰?
何故私の名前を知ってるの?
最近の詐欺師も前もって調べると言うからな、新手のナンパか?
まさかこんな田舎でナンパされるとは。
「ふぅ」と、私はため息を付き黙ってその場を離れようとすると不審な男性が慌てて自転車を降りて小走りで近寄って来た。
「え、ちょっと待って、俺だよ、俺、俺。」
私は眼を細めて不審者の顔を覗き込んだ。
「あぁ、そうだ、すいませ〜ん誰か〜、ここにストカーが居ます、警察呼んでもらえますか〜」
と、大声で叫んだ。
男性はかなり驚いた様子で言った。
「ちょっと待て、誰がストカーだ、てか今絶対、俺が誰だか分かって言ったよね。」
私は再び眼を細め真顔で男性の顔を観る。
「すいませ〜ん早く警察呼んでもらえますか〜、ストカー&変質者が居ま~す。」
と私は再び大声で叫んだ。
「わ〜、わ〜、止めろ、なぜ変質者をプラスしたどっちも違うし、てか久しぶりに会ったのにそれかよ、相変わらず可愛げが無いな。」
不審者は慌てふためきながら言った。
「はぁ?!村1番の美少女でプリティーな私に可愛げがないだと、このド変態ストカー野郎に言われたくない。」
私は可愛げが無いの一言でカチンと来て不審者に怒鳴った。
「ど、ド変態ストカー?だからそう言う所が可愛げが無いんだよ、なんでケンカ腰になるんだよ」
不審者も負けじと言い返してきた。
「ケンカ腰なのはそっちでしょ、ふん。」
私は腕組みをした状態で頬を膨らませてぷぃと顔を背けた。
「え〜、俺か?いやいや、少しもケンカ腰になってないし、いきなり大声でストカー呼ばわりしたの誰だよ。」
不審者は信じられないと言う表情をしながら言った。
「だって変質者だと思ったんだもん。」
私は両手を顔の下で軽く拳を作り少し膨れっ面で可愛らしい仕草をして誤魔化した。
「可愛く言って駄目、絶対俺だって分かってただろ。」
不審者はそっぽをむいて言ってきた。
「すいませ〜ん誰か〜警察呼んで〜」
私はその態度に少しイラッとして再び叫んだ。
「だ〜、やめろぉ〜、止めてくれ〜、そうです、ド変態ストカーです、それに変質者も付けて下さい、これで勘弁を。」
さすがに懲りたのか不審者は深々と頭を下げ土下座して謝った。
「やっと認めたかストカー恭平君。」
私は腰に手を当て半笑いで言った。
「そうです、恭平です、て、やっぱり気付いてるやん、てかなんでストカーなんだよ。」
「だって何時も私に着いてきたじゃない。」
「それはこっちの台詞だよ何時も着いてきたのはちひろの方だろ、金魚の糞みたいに」
「はぁ?何処の誰が糞よ、なんで私がド変態ストカー恭平に着いていくのよ。」
この私を糞呼ばわりするとは、私は頬を膨らませ恭平を睨みつける。
「どうせ俺はド変態ストカーですよ。」
と恭平もちひろを睨む。
「ぷっ、あはは。」
お互いに見合った状態で、吹き出し、お腹をが抱えて笑った。
あれ?私、笑ってる、笑ったのは何時ぶりだろう?
それと同時に涙が溢れているのに気付いた。
なんで?なんで私泣いてるの?別に悲しく無いのに涙が止まらない。
恭平は私の涙がに気付いたのかソワソワしだした。
「そ、そうか、泣ける程面白かったか、将来はお笑い芸人にでもなるか、なーんてな。」
「そう、笑過ぎてお腹痛いし、涙が出てきちゃったよ。」
私がそう言うと恭平は頭を掻きながら後を向き自転車の方に歩き出した。
私は暫くその場で泣いていた。
心に溜まったものが涙になって流れて行くそんな感じがした。
私が落ち着いたのに気付いたのか恭平が自転車を引きながら戻って来た。
「言い忘れてたよ、ちひろお帰り。」
満面の笑みを浮かべた。
「ただいま、恭平。」
私も精一杯の笑顔で応えた。
「お、おう、そろそろ帰るか。」
恭平は照れた様子でソワソワしながら自転車に股がった。
「うん、ありがとう恭平、それじゃあね。」
私は微笑みながら恭平に手を振った。
「なぁ、方角一緒だから一緒に帰らない?」
「でも恭平自転車でしょ?悪いよ。」
「ちひろは歩いて帰る気なのか?自転車の後ろ空いているんだけどな。」
「いいよ、私は平気だから。」
「なぁ、ちひろ無理するなよ辛い事があったら持っと頼って良いんだぜ、俺たち仲間だろ」
恭平は笑って見せた。
ふと、恭平の顔を見ると私が愛した彼の顔があった。
えっ、何で?
私は目を擦り恭平の顔を覗き込む。
「う〜ん、やっぱり恭平だな。」
「おう、俺は恭平だて、さっきから言ってるやん、てか顔近。」
恭平は照れて顔を背けてしまう。
それを見たちひろは少し機嫌を損ね、膨れっ面で応える。
「なんだ、恭平か残念。」
「残念て、なんだよ悪かったな恭平で、どうせ俺は不細工でド変態ストカー野郎ですよ、ちひろの彼氏は嘸かしイケメンなんだろうね。」
恭平はハッとして気まずそうな顔をした。
「悪い、ちひろ口が滑った。」
「うんん、やっぱり私の事、知ってたんだね。」
私は頭を左右に振った。
「ちひろの叔母さんから連絡があったからな、もう大丈夫なのか?」
恭平は頭を描きながら言った。
「うん、もう大丈夫だよ、元気、元気。」
「そっか良かった、心配してたんだ。」
「恭平に心配されるとは思わなかったな。」
私は微笑んだ。
「本当に可愛げ無いな、心配して損した。」
「別に恭平に可愛いなんて思われても嬉しくないもんね。」
「ぬぅ〜、ムカつく、もう知るか〜、歩いて帰れ〜」
恭平は自転車を漕ぎ出そうとした。
私は自転車の荷台を掴み引っ張って自転車を止める、恭平は前につんのめり倒れそうになった。
「うおぉいい、危ないだろ、何するんだよ。」
「あはは、ごめん、ごめん、ではお言葉に甘えて後ろに乗��てもらいます。」
私は笑みを浮かべながら自転車の後ろに座った。
「たく、載せて欲しいなら最初から言えよ、じゃ行くぞ。」
「うん、よろしく。」
「へいへい、分かりましたよ。」
恭平は前を向き自転車を漕ぎ出した。
くだらない?やり取りでもう陽が山間に落ちようとしている。
田舎の3月初春の風は寒くまだ雪が残っている。
自転車を漕いでいる男性は浄土恭平と言い私の幼なじみで私の初恋の人です。
多分恭平はその事に気付いてないと思う、彼には好きな人がいるんです。
その人は、根本緑子さんと言い1つ歳上で私達のお姉さん的存在の人でした。
そう恭平は私の片想いです。
「こうやってちひろと自転車乗るの久しぶりだな。」
「はぁ?、恭平の自転車乗るの初めてなんだけど、誰かさんと間違えてませんか?」
「あれ?ちひろじゃ無いのか?それじゃ緑子さんかな?」
「そうなんじゃないの?ところで、緑子さんとまだ付き合ってるの?」
「ああ、付き合ってるけど、て何で分かった?」
「何で、て高校の時から付き合ってるんじゃないの?」
「いやいや、高校の時は付き合ってないよ、確かに緑子さん狙いでサッカー部に入ったはいいが緑子さんは既に付き合ってる人が居るし、練習はきついし慣れない事はしない方が良いと思ったよ。」
「へぇー、そうだったんだ、2人とも同じ部活出し仲良かったから私はてっきり付き合ってると思ってたよ。」
「そんなに俺と緑子さん仲良さそうに見えたのか?」
「うん、見えたよ、何時も一緒に帰ってくの見てたし、私が入る隙なんか無かったよ。」
「実を言うと私も緑子さんと同じマネージャー狙ってたんだけど、2人も必要無いて言われたよ。」
「あれ?ちひろもサッカー部のマネージャー志望だったのか?初めて聞いたけど。」
「え、あ、そのアレだよ、アレ、そう恭平1人で大丈夫かな?て思って。」
「何だよそれ、そんなに俺頼りないか?」
「うん。」
「うん、てはっきり言うな相変わらず、そう言うちひろはえっと合唱部だったっけ?」
「そう、合唱部、歌うの好きだったし、引っ込み思案な所も治したかったしね。」
「はぁ?誰が引っ込み思案?ちひろが?ありえねー。」
「もう。」
「痛てぇ、辞めろ、危ないだろ。」
私は恭平の脇腹辺りをどついた。
「私はこう見えてデリケートなの。」
「あはは、ちひろがデリケート?」
「もう。」
「痛てぇ〜、マジ痛てぇよ、脇腹をつねるな、分かった分かったから、相変わらず容赦ないな。」
今度は恭平の脇腹をつねった。
「恭平が変な事言うからでしょ、本当の私は、もっとお淑やかでとっても可愛い大人の女性なんだから。」
「ぶっはは、幼い頃から知ってる俺としては、本当のちひろはがさつで男っぽい所だけどな。」
「なに〜、恭平、私を何だと思ってるよ!!」
「男女、乱暴者、態度がでかい、そして態度がでかい、もう1つ態度がでかい、顔だけ可愛い、そして俺の親友以上。」
「きょ〜う〜へ〜く〜ん、それだけ言うには覚悟が出来てるんでしょうね?」
「そうそう、それがちひろの本性、ぐぉぉ、苦しい。」
私は恭平の首を両手で絞めた。
「オォィ、危ないだろ、俺、自転車漕いでるんですけど〜。」
と言い自転車がふらつき出し私は咄嗟に恭平に掴まった。
「チョイ、チョイ恭平危ないでしょ、真っ直ぐ走ろうね。」
「お前が言うかよ、ちひろがちょっかい出すからだろ。」
「ハハ、恭平面白い〜、緑子さんともこんなふざけた事してるの?」
「あのな緑子は大人な訳でちひろみたいに馬鹿な事しない訳よ分かるか?」
「ぐぬうぅ、恭平に馬鹿呼ばわりされた、緑子さんと比べられたら適わないよ、緑子さんの事好きなんだね。」
「ん、ああ、好きだ。」
恭平は右手で頭を書き出した。
後ろからでは恭平の顔は見えないけどきっとニタニタと笑ってるに違いない。
「そっか、じゃ緑子さんに免じて今日は許してあげる。」
「何だよ許すって、俺何か悪い事したか?」
「私を馬鹿にしたこと。」
「いやいや、馬鹿にされたのは俺の方だからな。」
「ふふ、だから許すの。」
「何だよそれ。」
「いいから恭平は自転車を漕いでなさい。」
「へいへい、お嬢様。」
そっか恭平は私の事、親友としか思ってないんだね、私はね、恭平の事好きだったよ。
幼い頃は兄弟みたいに育ったからそんな風には思わなかったけど緑子さんが引っ越してきてからかな。
私達が中学に上がる時に緑子さんは隣町から引越してきた。
緑子さんは明るい性格で年齢の近い女子は居なかったから直ぐに仲良くなれたし、恭平とも自然と仲良くなって3人でいる事が多くなっでいった。
その頃から少しづつ恭平の気持ちが私から緑子さんへ心変わりをしていくのを何となく分かった。
緑子さんは誰にでも優しくて、抱擁力もあって、頼れるお姉さんみたいな感じで、私の憧れの人でした。
そんな緑子さんに恭平が惹かれていくのは仕方いなと諦めていたのです。
ふふ、おかしいですか?
何でも強気でズケズケ言う私からは想像出来ないかな?
この頃の私はこと恋愛には奥手でて言うか初めて人を好きになった訳でこの感情をどう処理して良いかわからずただ戸惑う毎日。
結局私の気持ちを打ち明けること無く終わったな、3人の関係も壊したく無かったしね。
村1番の美少女も恭平にとっては普通の女の子か。
なんだか急に腹が立って来た、この私を差し置いて・・・後ろからど突いてやろうかでも緑子さんの事も好きだしな・・・
よし私は2人の恋を応援しよう、もう恋するのは懲り懲りだ。
「恭平、緑子さんと仲良くするんだぞ、泣かしたら承知しないから。」
「お、おう、どうした急に。」
「私は2人の親友だからね、2人には幸せになって欲しい。」
「おう、ありがとなちひろ。」
「そう言うちひろもさ幸せになれよ。」
「おう、ありがとな恭平。」
「何に俺の真似してんの。」
「はぁ?誰がド変態ストーカー恭平の真似するのよ。」
「又、そこに戻るのかよ、いつまでも言うつもりだよ。」
「恭平が死ぬまで。」
「じゃ、一生言ってろ、本当に可愛くないな。」
”ドスッ”私は再び脇腹をどつく。
「ぐぉ、だから叩くんじゃない。」
「だって恭平叩きやすいし。」
「人に叩きやすいとかあるのか?」
「ある〜。」
「ある〜、じゃねえよ、この男女〜」
”ドスッ”
「ぐぉわ、だから叩くな、俺はサンドバッグじゃない。」
「あはは、恭平面白い、ド変態ストーカーサンドバッグ〜」
「サンドバッグがプラスされた、もう意味がわからん。」
「あはは、ウケる〜」
”ドスッ”
「ぐぉわぁ、何故叩いた、もう止めろ。」
・・・・・つづく〜。
ちょっと休憩(^_^)
て休憩ばかりしてるけど(^_^;)
取り敢えず出来たは良いが時間が空いた為か前半と後半で微妙に違ったりする(^_^;)
純愛ラブロマンスの設定の筈がラブコメディになってしまったꉂꉂ(๑˃▿˂๑)ァ,、'`
ツンデレ娘の畠山ちひろとはかなりイメージが変わってしまったみかこ様のイチャラブ系をイメージしてたらこんな感じになってしまった(^_^;)
ちひろのイメージ変わったけどセクシー女優になるは変更無し、なんだけど恐らく女優になった所でこの物語は一旦終わりにします(^_^;)
と言うのも女優になった後のイメージが湧かない、殆どがTwitter上の事しか分からないし(^_^;)
かと言って撮影現場を見学出来る訳も無いし、みかこ様に密着取材する訳にもいかないし(^_^;)
適当に作ってもいいけどね(^_^;)
取り敢えず今回は2人の関係、距離感が何となく理解出来たらなと思います(^_^)
では次回をお楽しみに(^_^)
1 note
·
View note
Text
おやすみなさいを言いたくて
おやすみなさいを言いたくて
*完全ネタバレ*注意
この作品す��い。
ある時ちらっと、アフガニスタンの映像でよく見かける、
あの服。顔まで覆ってて、中国の安物の。
予告?か何かで見かけて、とにかくアフガニスタンだろう
と思って見る事にした。
ストーリーは、娘二人と夫のいる女性カメラマンが主人公。
紛争地域などに出かけ名前も知られている写真家で、
アフガニスタンでの取材中、爆破に巻き込まれてドバイの病院へ。
家に帰ってくるけど久々の家族の様子になんだか違和感。
下の娘はまだ小さいから無邪気だけど、夫も長女も
言いたい事を黙ってる風だ。旦那はソファで寝るし。
主人公は戸惑い、やがて旦那が、妻が戦場へ行く間に待つ方は辛い、
って言うような事を吐き出した。
主人公は、もう行かないと決めてカメラマンをやめる事にする。
さて家族とうまくやろうと努めてきたおかげで旦那とも
だいぶ関係を修復し始める。ある日長女といる時に
ケニアでの仕事を依頼される主人公。安全な場所だと相手は言うが
主人公は断る。話を聞いていた長女は、自分が行きたいと
言い出した。今度アフリカの事について発表する事に
なっているので、現地で取材できたら注目される発表内容になる
というわけだ。もちろん母親と一緒に。
結果的には旦那が、ケニアに行くべきだと言ってくれる。
主人公は娘とケニアの難民キャンプへ。
するとその難民キャンプに人殺しのグル��プがやってくる。
逃げようと言う仲間に娘を預けて、主人公はカメラを手に現場へ。
主人公は無事だったものの長女は拗ねてしまい、
傷ついてるのか何なのかも言わないで、自分の殻に閉じこもる。
主人公が話をしようと言うが、その気もない。
帰国してからも長女はヘソを曲げていて、
主人公が話をしようと部屋に行く。
娘が難民キャンプで撮った映像を見ていると、
娘を預けて主人公が現場へ向かおうとするシーンの映像が出てくる。
勝手に娘が撮っていたようで、タイミングわるくも
そこへ旦那が入ってきてその映像を見る。
旦那はあっちで危険な事があった事を聞いていない。
なぜかというと娘が口止めしていたからで、
主人公は夫に言う前に娘と話さなければと思って部屋に来たのだった。
その映像見てブチ切れて妻に出て行けて喚く。
妻はもう危険な所へは行かないから許してほしいと言うが
出ていかされる。
その後長女と会い、話をするが、とても酷い言葉を浴びせられる。
だけど、その後に電話があってあれは本音ではないと謝罪してくる。
主人公は、娘のイベントを見にいく。
そこで、娘は、母親はカメラマンであり、自分よりずっと
母を必要としている子供達がいると話す。
娘が理解してくれ、その後主人公は、再び家に戻ってくる。
娘達に別れを告げて、夫に気をつけてと告げられて、
いざカブールへ向かう。
カブールで、やはり前と同じようにテロを起こす女性らを
取材していたら、自爆テロに向かうのは女性ではなく子供だった。
子供の体に歩き難いだろうってくらいの爆弾をつけて、
車で出て行くテロリストら。
止めなくちゃ、と思い動揺して、仕事どころではなくなっている
主人公は恐ろしさとショックとで、ただ車が出て行くのを
愕然と見送る。
この映画はこんな感じの話。
主に戦場へ出て行くカメラマンの主人公と家族との関係がメイン。
ちゃんとカブールで撮ってるのが最高級。
多分しっかりとはモロッコなどで撮ってるのだろう。
実際に監督の自伝のような作品でもあるとの事だ。
自分が紛争地へ行く事で家族にかける負担を考えているそうだ。
ちなみに監督は男性。
音楽、特にエンディングが相当やばかった。
今回の作品ではアフガニスタンの女性らが、
または子供が自爆テロをおこなう。
先に言っておくべきは、アフガニスタンでは、
国を良くしたくて命懸けになって努力している
女性らがいるという事。なぜ命懸けになるかというと、
タリバンが、女性が権利を求めるとか許さないからだ。
軽く触れておく。
アフガニスタンでは、ソ連との戦争後
(戦時の話は端折るが、ソ連には勝った形)
軍閥による戦闘が続き、そこにタリバンが登場し軍閥らと闘った。
タリバンは何せパキスタンのバックアップもあり、
勢いまして軍閥を追い込み首都を制圧。
当時の大統領を殺し晒し者にして政権を担い始めた。
信じがたいが、政権を担い始めた。
国として認められるには、国際社会がタリバン政権を
認めなくては話にならない。
パキスタンなど数ヶ国が認めたけれど、他は認めなかった。
タリバン政権は、自分たちの理想とする社会を実現する事にした。
動物園の動物たちを殺しまくり、サッカー広場を公開処刑の場とし、女性に教育と仕事をやめさせた。さらにバーミヤンの仏像遺跡を
破壊し、音楽や子供たちの遊びも禁止した。
歪んだ宗教の捉え方を人々に押し付けていった。
アメリカが911のとき、アフガニスタンに戦争を仕掛けて、
タリバンらは去っていったかに思われたが
今は前より増えている状態。
だから命懸けで闘う女性らもいれば、
自爆テロをおこなうテロリストもいるというような
状況になっている。
実際にちょっと前には、父か兄かに強要され
自爆テロをさせられようとした子供が助かっている。
主人公は、首都カブールへ行き、テロリストらを取材して、
テロに巻き込まれドバイに運ばれたのだ。
この映画は、ジャーナリストの使命は?戦地とは?
とか言うよりも、主人公が、何をするべきだろうと言う
映画でもある。家族のために戦地での取材をやめるのか、
それとも家族に何とかして理解してもらいカメラマンを続けるのか。
待つのが辛いと夫は言う。その通りだろう。
なんで行くんだと怒りたくもなるだろう。疲れもするのだろう。
だけど、アフガニスタンという土地が何年も忘れ去られて
いたように、彼女に伝えて欲しいと思ってる人達は忘れ去られる。
誰もかれもがカメラマンになれるわけではない。
誰でも紛争地へ行けるわけじゃないのだ。
危険なところへはもう行かないなんて言葉を妻に言わせるのは、
本人がその逆だと思っていても、ひどいことだ。
奥さんを籠の中の鳥にすることになってしまう。
家族の様子が描かれているの見ながら
色んな立場もあるんだろうな、と思いつつも率直にはこう思った。
長女は思ったことも言わず傷ついてるし、夫はマジで面倒くさいし、
本当にうっとおしいなって。ごめん。
こういってしまったら元も子もないけども。
でも最後に長女が理解しようとしてたあの姿は本当に立派だ。
この映画を見るとき、あたしはちょっと買い物に行って
テロにあうこともなく暮らしている場所で、
のんびりと画面に向かう。それは本当に有難い事なのだなと
改めて思わされる。
行く人が居て初めて知る事が出来る。
見捨てられ、気づいて欲しい人達のことを。
だからジャーナリストが危険な場所へ向かう事を、
安全な場所から見てるだけの人間が批判する事など出来ないし、
あたし達がアフガニスタンと聞いて、
最初に危険なイメージを抱くのも、情報があるからだ。
アフガニスタンで起きてる事は他人事だろうか?
東日本大震災で最貧国でありながら日本に寄付をしてくれている
国だ。仏教が関係する土地でもある。
バーミヤンには巨大なブッダの遺跡がある(一部破壊されている)。
日本人のボランティアが活躍して、中には心無い人間に
殺されてしまった人もいる。
アフガニスタンではケシの栽培が問題になっていたり、
仕事のない事が問題になってたりもする。他にも色んな課題がある。
でもこの間の選挙では、選挙に行くと殺すと言う
タリバンから殺害予告を受けながらも多くの人が投票へ行った。
国を良くしたいからだと言って。
アフガニスタンの子供達がみんな
平和に学校に通えるようになる事は、
国際社会が全力を挙げても不可能な事だろうか。それはないと思う。
主人公はアフガニスタンから、アイルランドへと帰国してくる。
そこは緑豊かな別世界で海や景色が本当にきれい。
でも主人公は、帰ってきて喜んでいるわけではない。
そうなら始めから行くはずもない。家族に会えて
嬉しい気持ちはするだろう。だが、主人公がカメラを持つのは
怒りを感じるからだ。別世界にいれば、それはやり場がなく、
怒りはたまり続ける。
その怒りは家族には癒せない。
ラストを見て、誰もが怒りを覚えるに違いないと思う。
子供にさせようとしているのは、ただ なんの罪もない人たちを
殺させる行いで、それ以外に意味はない。
車は出て行く。見送る主人公。
車は出て行く。
テロリストを乗せた車は世界のどこかへと出て行く。
あたしたちはニュースでそれを見る。
他人事では決してない。
他人事としている間はなくならない。
争いがなくならないと思ってる人が多いほど、なくならない。
伝える人がいることへの感謝を感じる。
知ったこの怒りを無気力に変えず考える力にしたい、そう思った。
2015年の記事
1 note
·
View note
Photo

『U14合同TR 1.21』 本日は名古屋市立緑高校サッカー部、名古屋市立山田高校サッカー部との合同トレーニングでした⚽️ 今回はA級コーチの渡邉先生の指導の元、グループでの守備がテーマでした。相手のオフェンスの動きを見ながら、チャレンジ&カバーやスライド、限定からのボール奪取まで繰り返しトレーニングしました。3チーム合同だからなのかもっと声を出してコーチングをしていかないと上手くいかないかなと感じたのでどの年代になってもできるように習慣化しなくてはいけないですね☝️ 本日も監督とお話しする時間もいただきありがとうございました😊今の公立と私学の違いは3種の部活とクラブのような構図になっているようです😓やはり部活動の縮小化の影響もあり、本気でスポーツに打ち込みたい選手はクラブチームや私学という流れになりそうですね。大きな問題だなと感じました。。 OBは1人会うことができました。ただいまレギュラー争い真っ只中のようなので頑張ってもらいたいです😁 2023年度ジュニアユースチーム、ジュニアチーム選手募集中です‼️各学年定員18〜20名(FP16〜18名、GK2名)になり次第締切⚽️原則、試合時は全員出場の育成重視のクラブチームです👍 マイクロバスを保有しているため、遠方での試合は送迎のお手伝いをさせていただきます🚌 無料体験受付中‼️無料体験は3回あります。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください😊 小中学年代で身に付けておくべき個人技術(蹴る、止める、運ぶ)と攻撃および守備の個人戦術、グループ戦術を年間を通してテーマごとに学び、週末の試合に向けてトレーニングを積み重ねていきます。 #緑高校サッカー部 #山田高校サッカー部 #FC東郷 #無料体験受付中 #選手募集中 #中学生サッカー #小学生サッカー #愛知県サッカー #東郷町サッカー #日進市サッカー #みよし市サッカー #豊明市サッカー #名古屋市サッカー #豊田市サッカー #刈谷市サッカー #ジュニアサッカーチーム #ジュニアユースサッカーチーム #サッカークラブ #賛助会員募集中 #スポンサー募集 #サッカーコーチ募集 #サッカー審判員募集 #ボランティア募集 公式HP http://www.fctogo.jp 公式Instagram @fctogo2003 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/fctogo2003 公式LINE https://lin.ee/47np89glG 公式Twitter @fctogoaichi https://www.instagram.com/p/Cn8KSjjBjwQ/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#緑高校サッカー部#山田高校サッカー部#fc東郷#無料体験受付中#選手募集中#中学生サッカー#小学生サッカー#愛知県サッカー#東郷町サッカー#日進市サッカー#みよし市サッカー#豊明市サッカー#名古屋市サッカー#豊田市サッカー#刈谷市サッカー#ジュニアサッカーチーム#ジュニアユースサッカーチーム#サッカークラブ#賛助会員募集中#スポンサー募集#サッカーコーチ募集#サッカー審判員募集#ボランティア募集
0 notes
Text
弱虫ヒーロー
「ぼくがヒーローになるよ」
どんくささが災いし幼稚園でいじめられて涙で顔をぐしゃぐしゃにしていた私に突然彼女はそう言って手を差し伸べた。
私達にとってヒーローとは日曜の朝にテレビで放送される戦隊物のイメージだった。毎週悪者が出てきて、町を荒らして、人の平和を脅かす。その脅威に立ち向かう戦士達。最終的に爽快な展開になって、子供はみんな憧れて、変身グッズを身に着けてヒーロー気分で跳ね回る。
その時、園内に植えられた巨大な木の陰で私は隠れて泣いていた。室内でおりがみを折ったりおままごとをするのが好きなのに、おそとで遊ぶのも大切だからと先生に連れ出されて、やりたくもないおにごっこに巻き込まれて、案の定さっさと鬼にされて、でも誰に追いつくこともできなくて、からかわれてばかりで、とてもいやな気分になって、悔しさとか惨めさとかに苛まれてしくしくと泣いていた。
私のことなんて忘れて違う遊びに切り替えたから、誰も私を探しには来ず、思う存分泣くことができた。唯一やってきたのが、彼女だった。きらきらとした木漏れ日が当たって、彼女を含めたあらゆる景色がきれいだった。
「まもってくれる?」
私が問いかけると、男の子みたいに髪を短くした彼女は自信満々といったように歯を見せた。
「まかせろよ」
小指が重なり、絡まる。指切りげんまんが交わされて、私たちの間には秘密が生まれた。
それから彼女は私にくっついてくれた。正しくは、私が彼女にくっついていた。
彼女は男の子に負けない体格の良さをしていた。幼児における男女差なんてそんなものだ。彼女は四月生まれで同学年だと一番成長しているはずで、私は翌年三月の早生まれで比較的小さい子供だった。四月生まれと三月生まれではあらゆる点で差が生じる。
彼女は負けん気が強くて、男の子にも果敢に挑んでいった。女の子たちは彼女のことを慕っていた。私は金魚の糞みたいなもので誰の視界にもうまく入らなかっただろうけど、とにもかくにも彼女が味方してくれているだけで私は随分と助けられた。
しかし、その年の三月に彼女は急に園を去ることになった。親の転勤が理由だった。
私にとって世界の終わりと同様だった。
うそつき、と言った。自分勝手に。まもってくれるって、言ったのに。私はあの日、彼女と約束を交わした日よりもずっとかなしい涙を流しながら、彼女にそんなこころない言葉をかけてしまった。ごめん。彼女は本当につらそうに謝った。私もとてもつらかった。彼女と離れることも、彼女が離れてしまった後のことも、あらゆることが不安でつらかった。
それから彼女はこの町を去って、私と彼女の秘密は遠く細く引き延ばされてぷつんと切れてしまった。
*
時が経過し、私は地元の公立中学に入学することになった。
私服登校だった小学校と違い、真新しくてぱりぱりしてて固い生地の、制服に袖を通す。私立や少女漫画みたいに可愛いチェックスカートも赤いリボンも無い、ただの紺無地のプリーツスカートにブレザー、リボンもネクタイも無し。ちょっと不満だったけど、身につけてみるとそれだけでお姉さんになったみたいで嬉しくなった。お母さんもお父さんもいたく喜んでくれて、入学式に臨む。
何校かの小学校の学区が複合しているので、元の小学校の友達は勿論、他の小学校の子もたくさん入学してくることになる。幼稚園では手痛くいじめられたが、小学校でなんとか少し持ち直し、友達もできた。中学校はどうか、クラスでうまくやっていけるか、部活はどうするか、勉強は大丈夫か、だとか期待と不安がぐるぐると回転している。
一年三組に組み込まれ、教室の後ろから父母に見守れながら私達は一人ずつ自己紹介をしていった。私はたいてい一番最初の出席番号になる「会澤真実」で、この一番最初という位置にどれほど振り回されてきたか分からない。会澤苗字のお父さんをどれだけ恨んだことか。
先生に呼ばれて、席を立ち上がる。最初がみんなにとっても肝心だということはよくわかる。みんなの視線が集まって、負けそうになる。やばい、吐きそうだ。知っている子を咄嗟に探す。真ん中あたりに小学校の友人がいて、あの子が傍にいてくれたらどれだけ心強かっただろうと思いながらも、彼女が小さく手を振ってくれたのを見てほっとして、なんとか私は噛まずに自己紹介を始める。名前と、出身校と、抱負。無難に終わらせて、ぱらぱらと拍手が起こる。
しばらくは多大な緊張がずっと糸を引いていて、意識が他の子たちの方に向かなかった。じくじくと鳴る心臓がやがて収まってきたころには、さ行までやってきていた。
「清水律」と聞いて、私はふと顔を上げた。どこかで聞き覚えのある音並びだった。立ち上がったのは学ランを纏った、中くらいの背の男子だった。中性的な顔つきで、どちらかというとイケメンな部類に入るような感じがする。しみずりつ、と心の中で繰り返す。なんだろう、このデジャヴ。
淡々と続いていた自己紹介に衝撃が走ったのは、そんな彼が発した次の言葉だった。
「ぼくは性別は女ですが、心は男なので、学校にお願いして男子として生活することにさせていただきました。よろしくお願いします」
教室に薄い困惑が広がった。
そして私は思い至った。どうしてこんなに大事なひとの名前を忘れていたのだろう。
昔、約束を交わした、私にとっての正義のヒーロー。
「りっちゃん」だ。
*
「りっちゃん」
つつがなく入学初日を終えて、静かな興奮と動揺の残る教室で、りっちゃんの周りの子たちがいなくなったのを見計らって私は思いきって話しかけた。
りっちゃんはやっぱり学ランを着て、普通の男子とおなじような雰囲気をしている。でもさっき一緒にいた子達は女子だった。多分、同じ小学校の子たちで、友達なのだろう。なんで、とか、聞こえたから、たぶん彼女達もりっちゃんが男子の格好をしていることに驚いたのだろう。心が男だというくらいだから小学校でもボーイッシュな格好をしていたのかもしれないが、女子と男子で明確に見た目が区分される中学校でまで学ランを着てくるとは誰も予想していなかったように窺えた。
はじめりっちゃんは目をぱちくりと瞬かせたけど、ふわっと笑った。
「久しぶり。やっぱりまみちゃんだったんだ」
「うん」
私はどきどきした。なんだかずっと落ち着いた声色に思う。男子は少しずつ声変わりしつつある人も出てきているけれど、りっちゃんは当然ながら男らしい野太い声ではない。むしろ澄んでいる印象があった。なんだか大人っぽい。
「最初名前を聞いて、似てるなあって思ったんだ。思い違いだったら恥ずかしかったんだけどさ」
「私も……いや、最初は、その、名前を聞いてもなかなか思い出せなかったんだけど、りっちゃんが男子の格好をしてますって言った時に、思い出した」
「めっちゃ事細かに教えてくれるじゃん。てか、りっちゃんって懐かしいな」
私はちょっと慌てた。そうか、りっちゃんはりっちゃんだけど、男子として生きているんだとしたら、ちゃん付けは嫌かもしれない。
「小学校ではどう呼ばれていたの?」
「律が多いな。それか清水。こういうのだから、ちゃんとかくんとかややこしくて、呼び捨てが多かったんだ。でも呼びやすいようにしてくれればいいよ。別にりっちゃんでも。男でもちゃん付けのニックネームってあるしさ」
この余裕はどこから生まれてくるんだろう。私はたった少しだけの時間でりっちゃんはやっぱりすごい子なのだと思った。すごいね、と何気なく言うと、りっちゃんは首を傾げた。
「何が?」
「いや、いろんなことが。幼稚園の頃より落ち着いてるし、大人びて見える」
「幼稚園の頃よりは成長してたいわ。流石に」
「そっそうだよね。ごめん」
「いいよ謝らなくたって。まみちゃんはなんか、ちょっときょどきょどした雰囲気は残ってるね。懐かしい」
きょどきょど、という言い方がちょっと可愛いけど、多分良く言われているわけじゃない。
「でも、さっきの自己紹介とかさ、一番で緊張するだろうにちゃんとしててかっこよかったよ」
クラスの子たちに嘗められたりいじめられたりしないようにするには第一印象が何よりも重要だ。りっちゃんにそう言われると、たぶん割と大丈夫だったのだろうとわかり、ほっとする。
「すっごく、あがっちゃったけど」
「うん、緊張感は伝わってきた。女の子はそのくらいの方が可愛らしくていいよ」
りっちゃんはさばさばと笑う。けれど、どうしてもその言い方に引っかかってしまう。
「……あの、りっちゃんの、心は男っていうのは」
思ったよりすらす��と会話が進んだので、私は決意して尋ねてみることにした。
「ああ」りっちゃんはなんてことないように学ランの襟元を摘まむ。「言った通り。いろいろ迷って親や先生方ともよく相談したんだけど、ぼくは自分で着るならブレザーとスカートより学ランとズボン派だっていうだけ」
でも、まみちゃんの制服姿はとても似合ってる、とさらっと褒めてきた。はぐらかされたのだと解った。私は頬がちょっと熱くなるのを感じながら、辛うじて、りっちゃんも学ラン似合ってる、と返した。本当に似合っていた。私もそうだけど、制服に着せられている子ばっかりな中で、りっちゃんはそのぴしっとした制服の頑なさがりっちゃん自身にフィットしていた。
「そうか? 良かった」
ほっと肩の力が少し抜けたのを見て、ああ、涼やかな顔をしてるりっちゃんも緊張してたのだと知る。
「小学校の友達にもちゃんと言ってなかったからさ。皆びっくりしてて。でも、なんとかなるか。堂々としてればいいよな」
「うん」
私は素直に頷いた。
それから簡単に会話を交わして別れた。また明日、と言い合って。
また明日。反芻する。また明日、りっちゃんに会えるのだ。同じ教室で。幼稚園の頃と少し形は違うけれど、あの時永遠の別れみたいにたくさん泣いたのに、奇跡が起こって再会できた。そう考えるとなんだか嬉しくてたまらなくなった。
私は大きくなったりっちゃんの素振りや言葉を思い返す。
先生、だけではなく先生方とつける。果たして、小学校の時、そんな風にさらっと言える人は周りにいただろうか。中学一年生なんて、制服で無理矢理ラベリングされただけで、中身はまだ殆ど小学生みたいなものだ。その些細な気遣いのような言葉の選び方に、私は今のりっちゃんの人間性を垣間見たような気がした。
*
りっちゃんの噂は教室を超えて一年生全体に広がった。
面白半分に様子を見に来る野次馬根性の人もたくさんいた。初めのうちは私の席は入り口から一番近かったので、廊下にたむろしているりっちゃん目当ての人たちの声がよく聞こえた。どれ? あれあれ、あの座ってるやつ、へー、みたいな、好奇心だけが剥き出しになってる言葉が殆どだった。その中には、りっちゃんの元小の子たちもいて、小学校の時もやっぱり男子っぽさはあって、男子にまじってサッカーをしたり、誰にも負けないくらい足が速かったり、その一方で女子ともYouTubeの話をしたり恋バナをしたりしていたらしい、という情報を横耳で仕入れた。
要はクラスの中心人物として立っていた。あれだけ大人っぽかったら、確かに自然と中心になりそうだ。悪い意味ではなく「違う」感じがする。私とは全然違うし、皆とも違う。彼女は少し、違う。あれ、彼女っていうべきなのかな、それとも彼っていうべきなのかな。
たぶん、私が抱いているそういう戸惑いをみんなが持っていた。
そんな皆の戸惑いは素知らぬふうで、りっちゃんは「男子」として中学生活を送っていた。男女一緒くたの陸上部に入部して、毎日放課後に校庭でランニングしているのを見かける。私は小学校の友達に誘われて美術部に入った。絵なんて全然上手じゃないし好きじゃないけど、何かしらの部活には入っておいた方が友達ができると思ったからだ。友達はいるぶんだけ安心する。
実際、美術部は先輩後輩の上下関係も薄くて気が楽だった。プロみたいにびっくりするほど上手い先輩もいれば、幽霊部員もざらにいる。アニメっぽい絵を描いて騒いでる人もいれば、静かに一人で模型造りに没頭している人もいる。みんなそれぞれで自由にしていて、地味さが私にちょうど良かった。新しい友達もできた。
私とりっちゃんは全然違う世界の人だな、というのは、部活に入ってしばらくしてから実感するようになった。
初めのうちはちょくちょくタイミングを見計らって話したけれど、それぞれ友達ができたし、瞬く間に忙しくなった。小学校よりもずっと授業のスピードが早いし宿題は大変。塾に行っている子は更に塾の宿題や授業もあるのだから大変だ。私はらくちんな部類のはずなのに、目眩が起こりそうだった。
それでもたまに話す機会があった。委員会が同じだったからだ。園芸委員会である。だいたいこういう類は人気が無い。毎日の水やりが面倒臭いし花壇いじりは汚れるからだ。私のような地味な人間には似合うが、りっちゃんが立候補するのは意外だった。曰く、植物って癒やされるから、らしい。
校舎に沿うようにして花壇が設けられており、クラス毎に区分されている。定期的に全学年で集会があって、植える花の種類を決める。大体決まり切っているので、すぐに終わる。そして土いじりをして苗を植えて、水やりをする。水やりは曜日を決めて交代でしているので、りっちゃんとゆっくり隣で話すのは土いじりをするときくらいだ。だから、私はそんなに植物が元々好きだったわけじゃないけれど、この時間が結構好きだ。
「暑くなってきたよなあ」
とりっちゃんは腕まくりをして苗を植えながら言った。りっちゃんの腕はあんまり骨張っていないけれど、陸上部の走り込むようになって黒くなりつつあって、健康的な肌をしていた。
「そうだね。そろそろ衣替えだよね」
既に男子は学ランを脱いで、女子はブレザーを脱いでいる。女子はベストを羽織っているひともいるけれど、本格的に暑くなってきたら半袖に切り替わる。
「やだなあ」
りっちゃんは軽い感じで苦笑し、お、みみず、と言って、指先でうねうねうごめくみみずを摘まんだ。私は思わず顔を顰める。
「ええ、きもちわる」
「みみずっていいやつなんだよ。みみずのいる土は栄養分たっぷりってこと。だからここに植えた苗はきれいな花が咲く」
「知ってるけど」私は口を尖らせる。「きもちわるいものはきもちわるい」
「それは仕方ないな」
りっちゃんはおかしそうに笑い、みみずを元の土に返してやる。
「りっちゃんは家でもこういう園芸とか、するの?」
結局私は慣れている「りっちゃん」呼びを続けているけれど、クラスでそういうのは私だけだった。ただ、普段周りがいる中でそう呼ぶのはなんか恥ずかしいし、りっちゃんもちょっと嫌かもしれないから、「清水くん」と使い分けている。
「たまにね。母さんが庭いじり好きだから。雑草取りとかよくやるよ。暑くなるといくら取っても草ぼーぼーになるから、それも嫌だな。嫌いじゃないんだけどさ。植物って何も言わないし、無心になれるというか」
「ふうん」
「まみちゃんはこういうのやらない?」
「全然。うち、マンションだし。でも、委員会でやるようになってちょっと好きになった」
「いいね。まみちゃんはきっと綺麗な花を咲かせる」
「綺麗な花?」
「植物は人の感情を反映させるという噂がある」
りっちゃんは基本的には大人っぽくて男子らしさは確かにあるのだけれど、時々こういう可愛らしいというかロマンチックなことを言う。
「だからおれはいっつも雑な咲かせ方をする」
入学時には「ぼく」を使っていたけれど、五月頃には「おれ」と言うようになった。
「私も自信ない」
「じゃあ三組はみんなより変な花が咲くかもな」
二人して笑った。りっちゃんの冗談は心地良い明るさがあって、話していて楽しい。
*
最初の明らかな違和は、やはりというかなんというか、プールの授業だった。
暑くなってプール開きが示されて、教室にはいろんな声が沸き立った。女子の中には水着姿になるのが嫌だという子もいたし、男子は大体嬉しそうだった。でも三組には他の教室に無い疑問が浮かんでいただろう。
清水律はどうするのだろう。
りっちゃんは普段男子の格好をしているけれど、身体は女だ。だから、当たり前だけど、上半身はだかになる男子の水着姿はたいへんなことになる。かといって、女子のスクール水着を着たら、それはそれでなんだかおかしい感じがする。
トイレは男女共有のバリアフリースペースを使って凌いでいるけれど、こればかりはどうしようもない。陽の下に明らかになってしまうことなのだ。
結論からすると、りっちゃんは一切のプールの授業を��んだ。休んで、レポートを提出した。
プールを休む子は他にもいる。女子も結構休んだりする。女子には生理がある。体育の先生に直接生理だという理由を伝えるのは嫌だけど、お腹が痛いとか言ったら大体通じて休める。明らかに生理休みが長すぎる子は流石に指摘されて、しぶしぶ出たりするけれど。
一方でりっちゃんはずっと休んだ。それを不満げに見ている子もいた。レポートで済むなんて楽だよね、と嫌みったらしく言う子もいる。そんなの、仕方ないじゃんと思うのだけれど。りっちゃんだって休みたくて休んでいるわけじゃないのだ。たぶん。
そういえば、りっちゃんは生理はどうしているのだろう。あんまりにデリカシーが無いから訊けないけど。
生理に限らず、中学生の時期は男女で大きく身体が分かれていく。
女子の生理は小学生高学年から中学生にかけて初潮がやってきて、身体は丸みをおびて、胸がすこしずつ大きくなっていく。男子は、あんまりよくわからないけれど、声変わりして、ちょっとひげが出てきたりする。身体も大きくなってくる。女子も身長はよく伸びるし私も春から夏にかけて二センチくらい伸びたけど、男子は女子の比じゃないという。特に中学校で凄まじい勢いで伸びていって、ごはんの量も半端じゃない。エネルギーの塊、みたいな感じ。
りっちゃんは男子だけど、女子だ。身体は、女子なのだ。
衣替えになって、りっちゃんはひとり長袖のシャツをしていた。私はなんとなくその理由を察した。半袖のシャツは長袖のシャツよりも生地が薄くて、透けやすい。りっちゃんの胸は薄いけれど、たぶん多少は膨らんでいて、ブラだってしている。キャミソールとかタンクトップを上に着て、女子もブラが透けないように気をつけるけれど、りっちゃんはそのものを隠そうとしているのではないか。本人には訊けないけれど。
そういったことが違和感が表面化してきたのは、夏休みが近くなった頃だった。
花壇に植えた向日葵の背が高くなって、もうじき花開こうという頃である。
他愛も無いからかいのつもりだったのだろう。座って次の授業の準備をしていたりっちゃんの背中を、男子の指が上から下へなぞった。
そうしようとしているのを、私は教室の後ろ側から、美術部の友達で一番仲が良いさきちゃんと会話しながら見ていた。やばい、と直感していた。男子達がそわそわしていて、なにかをりっちゃんに向けてしようとしていると解った。それがなんなのかまでは、会話まで聞こえていなかったから見当がつかなかったけれど、感じの悪いことであることには間違いないと思った。
そしてその指がりっちゃんのきれいな背筋を辿った時、私は思わず息を詰める。
男子が大きな声で、ブラしてる、と興奮なんだか卑下なんだか、宣言した。
りっちゃんは驚いて彼を振り返っていた。その男子のグループは手を叩いて笑っていた。やっぱり「してる」んだ、と謎を解き明かして、ものすごくおかしいことみたいにめちゃくちゃ笑っていた。一連の行為は三組みんなの耳に入っていただろう。
私は凄まじくその男子のことを嫌悪したけれど、りっちゃんの次の行動に、驚いた。
あの大人びて、いつも穏やかなりっちゃんが、手を上げた。
がたんと椅子を勢い良く倒して、触れた手をひらひらと揺らしている男子に、殴りかかろうとした。
その顔は、遠くにいても、ものすごく冷たくて、恐ろしかった。怒りというものは振り切れてしまうと烈しい色ではなくもっと静かな色をしているのかもしれないと知った。
りっちゃんの怒りの拳はからぶった。
がん、と固い音。
降り下げられた先は、机だった。木の板が割れるんじゃないかと錯覚するほどの強い音だった。いよいよ教室中の空気が氷点下に下がった。窓の外の油蝉の声がやたらとよく聞こえて、虚しいほどだった。
「……ごめん」
脅える男子を前に俯くりっちゃんはそう呟いて、教室を出て行った。
静まりかえった教室だったが、りっちゃんがいなくなったことでどよめきが起こり始めた。間もなくチャイムが鳴って、先生が入ってきた途端、教室の異様な雰囲気を感じ取って目を丸くする。
「あれ、清水くんは?」
先生がそう言った。なんでそんな蒸し返すようなことをわざわざ尋ねるの、と、先生はなんにも悪くないのに私は強く思った。
「保健室です」
最前列にいる委員長がそう言って適当にやりすごした。
結局りっちゃんはその後教室に戻ってこなかった。翌日の学校を休んで週末を挟み、月曜からはまた学校にきた。私はほっと胸を撫で下ろした。りっちゃんはいつもと同じ涼しげな顔をして挨拶をした。クラスの反応はそれぞれだった。私みたいに安心していつも通りみたいな挨拶を返す子もいれば、ぎこちない子もやっぱりいて、そしてひそひそ話をする子もいた。
嫌な予感がした。
しかし、幸いというのかなんなのか、間もなく一学期が終わろうとしていた。
私は、夏休みを挟んで、この事件が生み出したこわばりが薄まることを、切に願った。
*
夏休み。
美術部は自由登校だ。一応コンクールはあ��けれど、締め切りにさえ間に合えばあとはどうだっていい。
私はそれでも学校に来ていた。絵はそんなに好きじゃなかったけど、塾も無いし、やることがあんまりなかったから、なんとなく向日葵に水やりをしにきた。ひんやりとクーラーがよく利いた美術室で一休みしている間に、静まりかえった校舎にブラスバンドの練習している音が響く。同じ学校なのに、普段のせわしなさが無くて異世界みたいだった。こののんびりとした静けさは、いいな、と思う。ずっとこのくらい優しい時間が流れていればいい。
私はスケッチブックを脇に、ペンケースを片手に、花壇の方へ向かった。途中で青のじょうろを手に取り、水を入れる。日光に当てられているせいか最初は熱湯が出てきて驚いた。こんなに熱くては向日葵の根に悪そうで、充分冷たくなってからたっぷりと補給する。
たぷんたぷんと重たく跳ねる水。ときどきはみ出して、乾いた校庭にしみをつくる。
花壇側は影がほとんど無かったが、花壇の後ろの数段の階段部分、つまり一階の教室に直接通じる部分はぎりぎり黒い影になっていた。花壇から校庭側に目を向ければ入道雲が光り輝く夏の青空が広がり、とんでもない直射日光の下で運動部が練習している。サッカー部と、それに陸上部もいる。思わずりっちゃんを探したけれど、見当たらなくてちょっと残念だった。りっちゃんは高跳びをやるようになっていていた。助走をつけた直後の一瞬の筋肉の収縮と跳ね返り、そして跳んだ瞬間の弛緩した雰囲気、全身をバネにしてポールを越える刹那に懸ける感じが、きれいで、りっちゃんにぴったりだった。私はこっそり練習を遠目に見かけてスケッチブックに描いてみたけれど、あまりに下手すぎてお蔵入りだ。人体は難しい。
そうしてぽんやりと歩いて行くと、三組の花壇の前には思わぬ先客がいた。
「りっちゃん?」
声をあげると、りっちゃんが顔をあげた。その手には緑のじょうろを携えていた。
「あ、おはよう」
あまりに普通に挨拶された。慌てて挨拶を返す。
「すごい。夏休みなのに水やりしにきたのか。あ、部活か。美術部って夏休みもあるんだな」
りっちゃんはスケッチブックに視線を遣った。その中にはりっちゃんの跳ぶ瞬間を描いた下手くそな絵もあるので、慌てて後ろ手に隠した。
「りっちゃんこそ。というか、りっちゃんの方こそ部活は?」
まさに、陸上部がすぐそこで練習に励んでいる。えいえい、おー、だとか、かけ声を出しながら、走り込みをしている。
真夏のまばゆい陽に照らされて、りっちゃんは少しさみしげに笑った。りっちゃんに特有の大人っぽさに切なさが加わって、私はたったそれだけで胸が摑まれた。
「辞めたんだ」
咄嗟に、耳を疑った。
蝉の声がじんと大きくなる。
「辞めた?」
「ああ」
「陸上部を?」
「ああ」
私は信じられなくて、一瞬目の前がくらっとした。
真面目に頑張っていて、りっちゃんは楽しそうだった。身体を動かすのが好きで、小学校でだってスポーツが得意で男子にも負けなかったくらいだったという。足だって速かったという。実際、りっちゃんの足は速い。体育で私はそれをまざまざと見て、本当に、本当の男子にも負けていなくて、びっくりしたし、かっこよかった。
「なんで?」
蝉が近くでうるさく鳴いて、風を掻き回している。
「言わなきゃ駄目?」
りっちゃんは薄く笑った。なんでもあけっぴろげにしてくれるりっちゃんが見せた小さな拒絶だった。ショックを受けていると、りっちゃんは嘘だよ、と撤回した。
「陸上って、まあ、スポーツって全般的にそうだけど、男女で種目が分かれてるだろ」
「……うん」
どんくさいくせに、私はもうなんだか道筋が見えて、理由を訊いた自分がいかに無知で馬鹿か自覚することになった。
「どっちがいいのか、結構揉めてさ。そりゃ、身体は女子だから、身体を考えると女子になる。でもおれは男子でいたいから、男子で出場したいんだけど、なかなかそうはいかないんだとさ。ほら、戸籍とか学校の登録では女だから。おれ、格好が男なだけなんだよな。それに、やっぱり先輩とか見てるとそのうち絶対本物の男子とは差が出てくるんだよな。それってどうしようもないことだしさ。今はおれの方が成績良くても、そのうちあいつらは軽々と俺ができないバーを越えていくようになる。てか、今、おれが高く跳べるとか、速く走れるっていうのも、どうもあんまり良くないみたいでさ。実力主義って言って割り切れたらいいんだけど、どうもそういうわけにはいかないらしい。運動部って上下関係厳しいしさ。腫れ物扱いっていうかさ。なんかあらゆることが面倒臭くなって、そもそもおれの存在自体が面倒臭いんだって気付いて、辞めちゃった」
一気に言い切って、あはは、とりっちゃんは空虚に笑い飛ばした。あまりに中身が無い笑い方だった。
私は自分が立っている地面の堅さを意識しなければ、自分が立っているかどうかの認識すら危うかった。
「おれも美術部に入ろうかなあ」
などと、絶対に本心からではないことを言った。
「絵が下手でもやれる?」
りっちゃんの顔がにじむ。
「壊滅的に下手だから、美術部は流石に無理か」
また、からからと笑った。あはは、からから、表面だけの心にもない笑い方。
「……まみちゃん」
りっちゃんが驚いた顔をして、近付いてくる。
「なんで泣いてるんだ?」
私はまたたいた。いっぱいになった瞳から、堪えきれず涙が溢れて頬を伝った。
「ええ、どうした。なんかおれまずいこと言った?」
慌てて引き笑いをするりっちゃんの顔をしっかりと見ることができない。私は咄嗟に首を横に振り、嗚咽した。ほんとに、なんで泣いてるんだろ。私がどうして泣いているのだろう。
水の入ったじょうろが指から滑り落ちた。水が派手に跳ねて、じょうろは横倒れになって、乾いた地面に水溜まりが広がっていく。
空いた手で私は涙を拭く。肌で拭ったところで全然止まらなくて、スカートのポケットを探る。そうして今日に限ってハンカチを忘れたことに気が付いた。美術室に戻れば鞄の中にタオルがあるけれど、戻る余裕が無かった。私はじっと静かに泣いた。
やがて、りっちゃんから、黙って、青いハンカチが差し出された。
綺麗な無地のハンカチ。私は最初断ろうとしたけど、りっちゃんは自然なそぶりでそのハンカチで私の頬を拭った。このさりげなく出来てしまうりっちゃんの大人びた優しさが、いいところだ。やわらかな綿の生地が触れて、群青のしみが広がっていく。私は諦めて受け取り、自分で目頭に当てた。ついでに鼻水まで出てきて、ハンカチは申し訳ないくらい私の涙と鼻水をたっぷり吸い込んでしまった。りっちゃんは何も言わなかった。静かに待ってくれた。私は、頭が真っ白になりながら、頭のどこかで、この二人向かい合っている状況が誰の目にも入らなければいいと思った。りっちゃんも、私も、ややこしいなにかに巻き込まれないように。でも、隣のグラウンドではたくさんの生徒がいる。校舎内ではブラスバンド部が練習している。こんなところ、誰の目にも触れない方が無理だ。こんな時までそんなことを考える私は、最低だ。
「思い過ごしかもしれないけど」
私の嗚咽がピークを迎えてやや落ち着いてきた頃、りっちゃんは静かに滑り込むように呟く。
「まみちゃんが考えているよりおれは平気だから、大丈夫だよ」
嘘だ。
私は充血した目をハンカチから覗かせて、りっちゃんの顔を見上げた。女性的でも男性的でもある、きれいなりっちゃんの顔。りっちゃんは笑っていた。愛想笑いだった。
ほら、やっぱり嘘だよ。
「りっちゃんらしくないよ」
私はどう言ったらいいのか解らなくて、ようやく絞り出したのは、その言葉だった。
りっちゃんの顔が冷める。
「おれらしいって、なに?」
思わず息を止める。私はりっちゃんの冷たい双眸を凝視した。笑った仮面を剥がした、静かで、恐い、りっちゃんの表情。冷たい怒りを拳というかたちに変換して振り上げた、あの教室での鮮烈な映像が過った。
ぬるい風が強く吹いて、軽くなったじょうろがかたんと音を立てる。
りっちゃんは我に返ったように表情を変えた。ありありと後悔が浮かんでいる。
「ごめん」
そう口早に謝って、りっちゃんは俯いた。
「ヒーロー失格だな」
りっちゃんは呟いて、その場を去った。私の後ろの方へ足音が遠ざかっていって、やがて消えた。
蝉の声と、ブラスバンドの音と、運動部のかけ声、それにあまりにも重たい沈黙だけが残った。
なんてことを言ってしまったのだろうと、烈しい後悔に襲われてももう遅い。りっちゃんのハンカチで顔を覆ってうじうじと座り込んだ。私、小さい頃と何も変わっていない。うそつき、と心ないことを言ってりっちゃんを困らせたあの頃と、なんにも変わっていない。
他のクラスより堂々と高々と咲き誇った向日葵がふらふらと揺れていた。高い分、風によく煽られてしまうのだった。
それから私は何度か向日葵に水やりをしに来たけれど、りっちゃんと会うことはなかった。向日葵はだんだんとくたびれて、重たい頭でっかちな花の部分をもたげて、急速に枯れていった。
*
二学期がやってきた。
りっちゃんは一人でいることが多くなっていた。
腫れ物、とまでは言わないにしても、なんとなくクラスのみんながりっちゃんに対してよそよそしくなっていた。夏休みを跨いでも、りっちゃんのちょっとした特異性の受け入れ方を迷っていた。勿論、普通に話しかける子もいる。私も、すれちがった時に挨拶はするし、園芸委員会で一緒になると普通に喋る。りっちゃんは夏休みの出来事が無かったことみたいに、自然に喋ってくれた。私にはうまく出来ない芸当だ。でも、私はそのりっちゃんの優しさに甘えて、何も言わずに安堵して会話した。
私はりっちゃんにずっと甘えている。幼稚園の頃からずっと。
苦しんでいるりっちゃんを前にしても、それでも透明人間みたいに、クラスのはじっこの方で、りっちゃんの背中を見ている。そして秘密の会議みたいな園芸委員会の時間だけ喋って特別感に浸ってる。りっちゃんのことを分かっているような気で、でも分かっていない。
残暑が厳しい中、次なる行事である運動会に向けて学校は動き出していた。
運動会は、学年種目、すなわち学年毎のクラス対抗の種目と、個人種目、すなわちクラス毎で定められた枠の人数で個人が立候補して争う種目と、二種類ある。そして応援合戦があって、これは三年生が主体となってダンスをする。
りっちゃんは基本的に男子なので、種目も男子の枠で出場するし、応援合戦でも男子として出る。
りっちゃんの噂は高学年にも伝わっているらしく、合同練習をするようになって、少し奇異な視線が向けられる。先輩たちも最初は迷ったようだが、男子の列にりっちゃんは加わった。りっちゃんはなんでもないように振る舞っている。
私は身体を動かすのがとにかく苦手なので、運動会なんて休みたいくらいだった。でも普段からそうして休むわけにはいかないので参加する。横一列になってみんなでよーいどん、なのでそこから置いていかれてはみ出さないようにすることで精一杯だった。
あと運動会まで一週間、というところで、園芸委員会では向日葵を根こそぎ捨てて、パンジーやビオラを植えた。ベタだけれど、寒い冬でも花を咲かせるという力強い品種らしい。それぞれのクラスに割り当てられた花の色はカラフルだった。とはいえまだどれも蕾なので、実際に咲いたらどうなるのか考えるとわくわくした。
スコップを土に突き立て、掘り起こす。りっちゃんと話し合いながら、三列になるように均等な間をつくり苗を植え替えていく。
「でも、冬になる頃にはもう園芸委員も終わってるな」
りっちゃんの言葉で気付いた。委員会は上期と下期で分かれるので、りっちゃんとのこうした共同作業ができる時間はもうすぐ終わるのだ。上期で委員会をした人は、下期では役職無しになる。そうしたら、私はほとんどりっちゃんと話せなくなるかもしれない。それは、寂しい。
私は、ふと、りっちゃんのことを好きなのだろうか、と考えた。
あまり深く考えたことが無かった。りっちゃんのことは好きだ。確かに好きだけれど、恋愛的な好きなのだろうか。尊敬してるし、かっこいいとも思う。顔だって素敵だ。特にやわらかく笑んだ顔を見ると心があたたかくなる。
クラスには、付き合ってるとか、そういう噂話も回ってくる。私は、りっちゃんと付き合いたいだろうか。付き合ったら、園芸委員という理由なんて無しにりっちゃんと一緒にいたとしても、なにもおかしなことはないだろうか。
でも、付き合うということは、りっちゃんは彼氏になるのだろうか。それとも、彼女? 私は女だから、彼女というのもなんだかおかしい気もする。女の子同士で付き合うこともあるというのは漫画で知っているけれど、実際自分にあててみると、どうなのだろう。男子に興味が無いわけではないのだけれど、男子といるよりも、りっちゃんといる方が楽しいし落ち着くし、心地が良い。というか、りっちゃんは、男子だし、でも、女子だし。
ううん。
考えるほどに分からなくなってしまう。
それに、りっちゃんと付き合うというこ��は、りっちゃんも私を好きだということとイコールになる。
りっちゃんが私を好きかと言うと、それは自信が無い。私がりっちゃんを好きになる可能性はあっても、りっちゃんが私を好きになる可能性は、限りなく低い。どんくさいし、泣き虫だし、クラスの中で釘が飛び出ないように透明であろうとして、みんなのなかにいることに必死で、りっちゃんみたいにちょっと変わった部分を堂々としていられるような勇気も自信も無い。つまり、りっちゃんが私を好きになることは、無い。
そう至って、浮かんだ桃色の案が破裂した。
うん、無いな。
私はりっちゃんのファンみたいなものなのだ。推しなのだ。だから、りっちゃんの幸せを願っているし、りっちゃんが苦しんでいると途轍もなく悲しくなる。りっちゃんが優しく接してくれることに甘えているけれど、それ以上を求めるのは烏滸がましい。だから、園芸委員を期に離れてようやく普通になるんだ。きっと。
「何を頷いてるんだ?」
「ひょおおええ」
手を止めて自分の思考に没頭していた私に、りっちゃんが恐る恐る話しかけてきて、思わず奇声をあげた。りっちゃんはぶふっと笑った。しかも止まらなくて、ずっと笑い続けて、涙まで出して、お腹を抱えている。
「そこまで笑わなくてもいいじゃん!」
「だって、なに? ひょおおええって」
あっはははは。私は耳まで熱くなっていたけれど、一方で、りっちゃんがこうして思いっきり笑っている姿を見たのは随分と久しぶりだったから、胸がぽかぽかと温かくなった。恥ずかしいけど、まあいいや。私もつられて笑った。三組の花壇で二人して、げらげらと笑っていた。
翌日の朝。
私は水やりをしに少し早起きして登校した。
じょうろに水をためる。朝の暑さは真夏になると収まりつつあって、蛇口から出る水もすぐに冷たいものになった。たぷんたぷん、揺れる水の重みを片手に感じながら、私は花壇に向かった。
そこで、昏い現実を目の当たりにすることになる。
三組の花壇だけ、無残に掘り起こされていた。りっちゃんと一緒に丹念に植えたパンジーもビオラもぼろぼろに引きちぎられて、ぐちゃぐちゃに踏み荒らされて、原型を留めていなかった。
私はしばらく目の前の現実を受け入れられなくて、呆然と立ち尽くした。
なんだろう、これは。
誰かによる、暴力的な、意図的な、明確な悪意であることは確か��。
蕾だけが投げ出されて、散らばっている。
葉も根もばらばらだ。
土はおかしなでこぼこができていて、靴の跡も窺える。
なんだろう、これは。
なんでだろう、これは。
りっちゃんと笑った、昨日の光景が浮かんだ。手を土で汚して、話し合って、ひとつひとつ苗を植えていった大切な時間や記憶が、汚い靴で踏み抜かれていく。
足が浮かんでるみたいだ。
なんで。
あまりに悲しくて言葉が出なかった。
りっちゃんにこの花壇を見てほしくなかったけれど、私の力ではどうにもできなかった。
*
おとこおんな、とりっちゃんについて誰かが言った。
園芸を揶揄してか、みみずりつ、と誰かが呟いて笑った。
クラスがなんだかおかしな方に向かっていた。
夏に傾いていた頃、背中のおうとつに指を当てられてからかわれたりっちゃんは、拳を上げた。
でも、もうりっちゃんは何も言わなくなっていた。
静かに、本を読んだり、次の授業に向けて教科書を開いたりしていた。
根暗でどよんとした空気を漂わせているわけじゃない。りっちゃんはいつだって背筋を伸ばして、堂々と座っている。だけど、その背中が寂しげに見えたのは、私の感情的なフィルターを通した光景だろうか。
さきちゃんをはじめとした友達は、りっちゃんの話題に触れなかった。彼女たちには私とりっちゃんが実は幼稚園が一緒だという話をしていたからか、むしろあんまり近付かないように警告した。私は知っている。私とりっちゃんのことが、影で噂されていること。私からは直接見えない、LINE等で噂されていること。私と一緒にいてくれる友人達はそれが勘違いであることをちゃんと解っているけれど、下手なことはするな、と暗に伝えているのだった。LINEのことを教えてくれたのもさきちゃんだった。それを聞いた時、正直私はぞっとした。
私は透明人間で、釘が飛び出ないように、必死だった。それは、幼稚園時代のようにいじめられることがとても恐いからだ。人の、無意識であろうと意識的であろうと、異端だと判断したときの容赦のなさは恐い。その恐怖に再び晒されてしまったらと考えただけで足が竦んでしまう。
りっちゃんは、女子だけど、男子であるという、りっちゃんそのものであることで、釘が飛び出てしまっていて、打たれつつある。
りっちゃん。
私は心で話しかける。
心で言ったところで、りっちゃんにはなんにも伝わらないのに。
りっちゃん。
私、どうしよう。
*
運動会を翌日に控えて、ダンスの最終練習に向けて、みんな衣装に着替えていた。一年三組は赤組なので、赤を基調として、体操服に布を張り付けたり、はちまきを手首に巻いて回転したときに動きが派手になるように工夫がなされている。女子はスカートを思いっきり短くする。長いとちょっとかっこわるいからだ。一年生はみんな膝下に伸ばしているので、普段はできないびっくりするような短さにそれぞれ色めきだっていた。私はちょっと恥ずかしかった。下に短パンを履いているからマシだけど。
男子はズボンはそのままだ。上は女子と対照的になるようなデザインになっている。
私はりっちゃんをちらりと見やった。りっちゃんは窓際の席で、机に腰を軽く乗せて、ぼんやりと教室を眺めているようだった。
「清水さあ」
窓際でたむろしているうちの男子の一人が言った。りっちゃんの視線が動く。
「本当はスカート履きたいんじゃないの?」
「は?」
りっちゃんが反抗を見せる。りっちゃんは最近おとなしいが、怒ると恐いことは皆知っている。
だけど、りっちゃんは教室の中で圧倒的にマイノリティで、りっちゃんの特異性を釘として打とうとしている誰かと、無言で見守る生徒達という多数からしてみれば、りっちゃんがいくら怒ろうとも、孤独だった。
「だって、女子のことちらちら見てさあ、本当はあっちが良かったって思ってんじゃねえの。ダンスも、競技も」
「馬鹿じゃねえの。お前らこそ短いスカートの女子に興奮してるくせに」
りっちゃんが吐き捨てる。いつになく顕著に苛立ちを発して、なんだかおかしいくらいだ。男子は一瞬息を詰まらせた。その隙にりっちゃんはその場を立つ。
「また逃げるのか? 図星だからだろ」
りっちゃんは無視する。無視すんな、という声も全部、無視して、教室を出た。
「サイテー、なに言ってんの?」
男子にも物怖じせずに話す派手めの女子が言う。その子も、本気で言っているというよりも、面白がっているように見えた。
「本気じゃねえよ。ああいう風にされると、冷めるよな」
「冗談が通じない清水さん」
あはは、と笑った。
不快だ。とにかく全てが不快だ。
「真実、大丈夫?」
隣でさきちゃんが声をかけてくれる。私はどうやら相当青い顔をしていたらしい。いつのまにか拳を握りしめすぎて、伸びた爪で皮膚を浅く抉って、じわりと血が滲んでいた。
ダンスの全体練習では、先輩の厳しい目もあるから、みんな従順に励む。私もなんとか振り付けを覚えて、人並みに踊れるようになった。軽快でポップ���曲に合わせてステップを踏む。腕を振る、回す。先輩から指示が飛んで、修正する。三年生はこれが最後だから、やりきって満足する思い出が必要なのだ。その情熱にあてられて、三学年跨いでみんな頑張る。
りっちゃんは私の斜め前の方にいる。いつも通りの凜々しい涼しい顔で、日光に当てられて、白い顔でたくさん汗を散らしていた。
しかし、ダンスの通し練習の一回目が終わった時だ。みんなのびのびと小休止をして、屋上から全体をコーチしている先輩の指示を待っていると、りっちゃんが急に座り込んだ。
こんなことでバテるような人ではない。よろしくない雰囲気がする。後ろにいる男子が恐る恐る声をかけると、りっちゃんは首を横に振った。大丈夫、だと言っているように見えた。大丈夫という単語から連鎖して、夏休みに目の当たりにしたりっちゃんの「大丈夫」を思い出した。りっちゃんの大丈夫は、本当は、大丈夫じゃないかもしれない。
「会澤さん?」
後ろの子が、驚いたように声をあげた。急に私が列を外れたからだ。
私はりっちゃんに駆け寄った。
みんなから飛び出るという私の感覚でとりわけ恐ろしいことをしていると自覚していた。けれど、りっちゃんが苦しんでいるのを分かっていながら見て見ぬふりをするのはもっとしんどかった。
「清水くん」
こういう時でも、私は使い分ける。
「……まみちゃん?」
りっちゃんはぼそりと呟いて、私を見上げた。まばゆい太陽に照らされるりっちゃんの顔は、白いというより、病的なまでに青ざめていた。
戸惑う周囲を置いて、私はりっちゃんに顔を寄せる。
「どうしたの、急に座り込んで」
「大丈夫……」
ああ。ほら、やっぱり、大丈夫と言っていたのだ。私の観察眼もたまにはちゃんと的を���る。
「大丈夫じゃないよ。顔が青い……汗もすごい。熱中症とか?」
私が言うが、りっちゃんは頑なに口を暫く閉ざしていた。
「今日、暑いし。ちょっと休もう。通し練習一回終わったし、体調不良ならしょうがないよ」
「駄目だ。本当、大丈夫だから。もう一回、通しが終わったらちゃんと休む」
りっちゃんのいいところは真面目なところだ。でも、悪いところでもあるのかもしれない。
「本当のこと言って」
私が強く言うと、りっちゃんは私を見た。
周りが私たちに注目しているのが、よくわかった。視線を集めていて居心地が悪い。見ないでよ。りっちゃんが更に言いづらくなるでしょう。
暫く沈黙が続いたが、りっちゃんは諦めたように項垂れ、ぼそりと何かを呟いた。
「え?」
聞き取れずに聞き返す。こういうところが私はどんくさい。
耳を近付けた先で、りっちゃんはもう一度同じことを呟いた。お腹が痛い、と。
瞬時にいろいろと察した。だからりっちゃんは言えなかったのだ。それは本当の男子だったら起こりえないことだった。でも、結構辛い。酷いとげろげろ吐くくらい、途轍もない痛みを伴って立っていることも辛くなる。
三年生の先輩が流石におかしいと気付いて、駆け寄ってきてくれた。
「先輩。清水くん、ちょっと体調が悪くて踊れなさそうなので、保健室に連れて行きます」
「え、大丈夫?」
先輩が慌てた。大丈夫、とは便利な言葉だ。
「すみません。ダンスを抜けて……」
「いいよ。通しは一回終わったし。ちゃんと休んで」
溌剌とした優しさに弱々しくなったりっちゃんは頷いた。
男子の見た目をしたりっちゃんと、女子の私が一緒に、身体を密接にひっつけているのは周囲からするとどう映るだろう。気にしない、というわけにはいかない。私は気にしいだし、りっちゃんもなんだかんだ和を重んじる人だ。重んじるがゆえに、自分を犠牲にする、強くて同時に弱い優しさがあるのだ。清水律という名に恥じない、清らかな水のように凜としていて、自分を厳しく律する生き方をしている。
りっちゃんは私の肩を借りて、ゆっくりとダンスの列を外れた。背後がやや騒然としているのが背中から感じ取れるが、気にしている場合ではなかった。どうせ、距離を置いてしまえば、聞こえなくなるし見えなくなる。
でも、私達は一年三組という閉じた空間での運命共同体だ。
後先考えずに行動した後、どうなるのかは分からない。
「ありがとう」
りっちゃんは、力の抜けた声で呟いた。
「ううん。良かった、言ってくれて」
「ごめんな」
「謝らなくていいよ」
むしろ、私の方がずっと、りっちゃんには謝らなければならなかったのだ。
私はずっとりっちゃんに甘えて、りっちゃんに助けてもらって、素敵なことを受け取ってきた。
りっちゃんが苦しんでいるのなら、私が助けてあげられることがもしあるのだとしたら、今度は助けてあげたい。
乾いた校庭からひんやりとした校舎に戻り、りっちゃんを保健室に連れて行く。その前にトイレに行くべきか尋ねたが、首を横に振った。
保健室の先生に事情を説明した。りっちゃんの口からはなかなか直接的に言えないと思うので、私がそれとなく伝えて、ベッドに寝かせてもらった。
急いで教室に戻り、常備している鎮痛剤と水筒を持って保健室に戻った。そしてりっちゃんのベッドに駆け寄る。
りっちゃんの顔は歪んでいて、いつも伸びている背筋を曲げて、くるまった。よくここまで頑張ったのだと感心してしまう。でも、りっちゃんは頑張るしかなかったのだ。負けたくなかったのだ。昔から負けん気が強かった。それはりっちゃんの人間性で、どれだけ大人っぽくて、言葉遣いが丁寧で、優しくて、男子の格好をしていても、根っこは変わっていないのだ。でも、その人間性ゆえに、りっちゃんは苦しんでいるのかもしれなかった。
鎮痛剤と水筒を枕元に起き、私は項垂れる。
「りっちゃん」
ぽつんと呟いた。
「何もしてあげられ���くて、ごめんね」
ここで泣くのは違うから堪えた。
「苦しかったらちゃんと言ってね。女子とか男子とかそんなの関係なく、私、りっちゃんのことが好きだから、りっちゃんにはいっぱい笑っていてほしい」
りっちゃんは何も言わなかった。
肩が震えているように見えたので、私はカーテンを閉めた。
ダンスは二回目の通し練習に入っていた。私は外に出て、遠くから眺める。私とりっちゃんの穴は目立つかもしれないけれど、私達がいなくても、整然と全体は動いている。それは思ったよりきれいな光景だった。きっと屋上から見たらよりきれいなのだろう。同じ動きをしてチームとして創り出す巨大な作品。それは素敵なことだ。それはそれで、本当に素敵なことなのだ。
通し練習が終わってから、私は勇気を出して列に戻った。またいろんな人の視線が集まった。興味だとか、戸惑いだとか、不安だとか、ないまぜになっているだろう。一身に受け止めると息が詰まりそうになる。自己紹介の緊張と同じだ。注目を浴びるのが苦手だから、注目されないように慎重に周りの目を窺ってきた。それが私の生きるための術だった。りっちゃんを助ける行為は私の信条を外れる。それはとても恐ろしいことだった。けれど、後ろめたさがなりを潜めて、少しだけ強くなれたような、そんな気がした。
「清水くん、大丈夫そう?」
さきちゃんが心配そうに声をかけてくれる。
「うん。とりあえず保健室で寝てる」
「そっか」さきちゃんは安堵の表情を浮かべる。「真実は、平気?」
「うん。平気」
私は穏やかに頷いた。りっちゃんの大人びた静けさのある笑顔を真似するように頷いた。
*
ダンス練習が終わり、一年三組に熱っぽいざわめきが押し込まれる。最後に蒸気する先輩が活を入れに教室までやってきて、先輩が「優勝するぞー!」と叫ぶと、全員で「おー!」と青春百パーセントな眩しいやりとりがなされた。私も折角練習したのだから、どうせなら優勝したい。でもそれよりりっちゃんが気になった。
先輩が教室を後にするところで、りっちゃんとたまたま鉢合わせた。
「あっきみ、平気? 元気になった?」
教室の空気が若干変容する。
「あ、大丈夫です。おかげで元気になりました。ごめんなさい、練習中断して」
「平気平気。明日は出れそう?」
「はい」
りっちゃんの肩を先輩が叩く。りっちゃんは恐縮げに頭を下げ、教室に戻る。
汗は引き、顔色も戻っていて私はひとまずほっとした。
何も無かったように、りっちゃんは自分の席に戻る。和を乱さないように、平然とした表情で男子の列に戻る。でも、今や、マイノリティのりっちゃんは、一致団結した教室のはみだしものと認識されているのだろう。
担任の先生もりっちゃんに声をかけ、終礼を進める。最後にさようならと声を揃えると、教室の空気は弛緩した。運動会前日らしい緊張と興奮に、ちょっと変な空気がまだ残っている。
りっちゃんが、勢い良く踏み出した。
なんとなくみんな、視線を寄せた。りっちゃんは良くも悪くも目立つ。
先程ダンスの練習直前にいじってきた男子の集団の前に立つ。私は緊張した。また殴りかかるのではないかと恐くなる。けれどりっちゃんは冷静で、いつも以上に凜としていた。
「おれ、明日も出るから」
はっきりと宣言する。
「男としてダンスもするし、競技もする。それだけだから」
特別叫んだわけでもない。しかし、りっちゃんのまっすぐとした声は、生徒の間をするする通り抜けて教室中にきちんと響いた。
りっちゃんの正義。ヒーローのような正義。敵に立ち向かう正義。それは時にあまりにもまっすぐで誠実で、人の気に入らない部分も刺激してしまうのかもしれない。でも、りっちゃんは、自分に根ざしている心を偽ることも、馬鹿にされることも、許せないのだ。
「……当たり前だろ」
静かな威圧にやられて、相手はしどろもどろになる。なあ、と言い合う。まるでりっちゃんが空気の読めないイタいやつみたいに。
りっちゃんは翻し、たまたまその正面に位置した私と目が合った。りっちゃんは微笑んだ。ぼろぼろになってしまった花壇でいつも見せてくれる、優しい、りっちゃんらしい笑顔だ。私は嬉しくなって、笑い返した。
でも、私はとても耳がいいので、次の言葉を逃さなかった。
「おとこおんな」
大衆の前で羞恥を晒されたことに耐えかねたのか、ぼそりとりっちゃんの背後で彼は言った。
真顔になったりっちゃんが振り返ろうとした。振り返りきらなかったのは、りっちゃんの正面で突然走り出した存在がいたからだ。
つまり、私だ。
「ふざけんな!!」
私は叫んだ。彼等に掴みかかる勢いだったが、さきちゃん達と、そしてりっちゃんが慌てて身体に腕を絡ませて止めていた。
「ふざけんな……っふざけんな!! りっちゃんは、りっちゃんはねえ……! あたしらなんかよりよっぽど、大人で! 自分に正直なだけで! それでも自分を律して、自分を犠牲にして! それをあたしたちが、馬鹿にする権利なんて!! どこにも!! ないんだから!! ふっざけんな!!」
「まみちゃん、落ち着いて!」
「真実-! どうどうどう!」
正面にいる男子は完全にたじろいでいた。むしろ引いていた。
私はいつのまにか涙と鼻水をまき散らしながら、その後もなんか言ってた気がするけど、何も覚えていない。記憶が吹っ飛ぶくらい、私の思考回路はぶち切れてしまったらしい。
*
運動会は、優勝しなかった。ダンスも優勝しなかった。
先輩達は号泣し「うちらは赤組が一番だと思ってるから! 赤組最高!」とやはり青春まっしぐらの文句を高らかに言い放ち、拍手喝采が湧き上がり、不思議な感動のうちに幕を閉じた。
声援で盛り上がったグラウンドは、しんと静まりかえって、夕陽色が全面に広がっている。
今日は部活も全部休みだ。それぞれのクラスで打ち上げが予定されている。私もりっちゃんも出る予定だったけど、こっそり抜けた。ああいった事件の直後なので流石に無理と判断した。不器用な私たちよりずっと器用なさきちゃん達が計らってくれた。
運動会の最中はスポーツが創り出す団結感によって、りっちゃんを馬鹿にした男子も、派手な女子グループも、たくさんの傍観組も、私の大切な友人も、りっちゃんも、私も、頑張った。全体として赤組は優勝しなかったが、一年三組は学年競技で一位になった。男女問わず、みんな手を叩いて喜んだ。
私は身体を動かすことは苦手だけれど、こういうのもたまにはいいかもしれない。細かい価値観の違いだとか、性別だとか、性格だとか、身体の特徴やかたちだとかそういった、それぞれで生じる違いや個性を超えて、一つの目標めがけて力を合わせることは。
りっちゃんは個人でも活躍した。決まっていたことではあるが、クラスで一番足が速いので、メドレーリレーに出場し、二位でバトンを受け取った後、辞めてしまった陸上部の仲間だった黄組の男子生徒に迫り、デッドヒートを繰り広げ、ぎりぎりで追い抜いた。その瞬間の盛り上がりようといったら、りっちゃんの纏っていた仄暗さを吹き飛ばすものだった。みんな調子がいいんだ。それはそうとして、りっちゃんはかっこいい。やはり、りっちゃんは自分を消すように着席しているよりも、太陽の下で輝いているヒーローみたいな立ち位置がよく似合う。
だけど、明日からの日常はどうなるかわからない。
今日と明日は違う。
でも私達はたぶんそんなに暗い顔をしていない。
きれいに整えた花壇の前で、手を叩く。
「いつかやりたいと思ってたけど、ようやくできたなあ」
りっちゃんは満足げに笑った。花壇を踏み潰された事件は実に陰湿でショッキングだったし、結局誰の仕業かは判明していない。あのパンジーやビオラは戻ってこないけど、一応、元通りだ。
「運動会の後に花壇をきれいにしたいなんて、りっちゃんもよくやるよね」
「ずっと心残りだったんだ。でもそれどころじゃなかったから」
「そうだね」
あらゆることがとりあえず一つの区切りを迎えたのだと思う。りっちゃんは気持ちの良い表情をしていた。
「またパンジーとビオラの苗、頼んで用意してもらうか」
「せっかくだから、違うのでもいいかも」
「なんかあるかな。調べてみるか。でも、三組だけ違うのもなんか変じゃない? こういうのは統一感があってもいいと思うんだよな」
「たまにはいいよ」
一年のくせに生意気だと言われるかもしれない。でも本当に通るかどうかなんて分からないんだから、言うだけ言ってみるのも手だろう。
「でも、園芸委員、もうちょっとしたら終わっちゃうんだよね」
「継続で立候補したらいいんじゃない? やりたいって言ったら別に誰も止めないだろ。他の子で園芸委員やりたいって奴がいたら別だけど、いないだろうし」
「いないだろうねえ」
私は土まみれになった手を見やる。汚いけれど、健康的な手だ。
「おれもその方がちょうどいいな。まみちゃんと一緒だし」
「えっ」私は大きな声をあげる。「また私と一緒でいいの?」
「え? うん」りっちゃんは目を瞬かせる。「え?」
なんだか変な沈黙が訪れる。
りっちゃんは怪訝な表情を浮かべているが、何か変なことを言っただろうか。
でも、一緒がいいと言ってくれるのは素直に嬉しいので、私は何も考えずにぽわんと笑みを零した。
「そっかあ。りっちゃんと後期も委員会一緒なら、楽しいね」
「……うん。そうだな」
りっちゃんは相変わらずちょっと挙動不審だけれど、まあいいか、とやがて大きな息を吐いた。
遠くでかすれ声のようなひぐらしが鳴っている。向日葵は枯れて、とうに夏は過ぎたと思っていたのに、まだ蝉は鳴いているのだと驚く。だけどじきにこの声も聞こえなくなるだろう。
「まみちゃん、垢抜けたというか」私を見ながら、しみじみとりっちゃんは言う。「さっぱりしたな」
「誰かさんの影響かな」
「誰だろうなあ」
「誰だろうねえ」
ふふ、と笑い合った。なんだか幸せである。
「でも、殴るのはやめた方がいいな。ああいうのは、どんだけ相手がくだらない挑発をしていたとしても、先に手出した方が悪者になるんだ。それに殴った方は結構痛い」
「りっちゃん、痛そうだったもんね」
夏休み前の、りっちゃん暴力未遂事件である。
「あれはまじ、やばいぐらい痛かった。今までで断トツ。おれがあの時逃げたのは、痛すぎて、そして恥ずかしすぎたからだから。廊下に出てから、ちょっと泣いた」
「うそー」
「ほんと。まみちゃんも一回机殴ってみたら? まじで痛いから」
「やだよ」
しかし、振り返ってみるとなんと暴力的な園芸委員だろうか。実際、とんでもないおまけが付いてきた。
おとなしいやつほど怒らせると恐い。私とりっちゃんが一年三組に植え付けた強迫観念の一つである。園芸委員の二人は、そのおっとりとした穏やかな響きの肩書きとは裏腹に、暴力的なレッテルが追加されることになった。自分達の正義というか本能というか、挑発に乗った愚かさというか、そういったものが生んだので、名誉といったらいいのか不名誉といったらいいのか微妙なところである。先生も親も驚いた。多分、運動会が過ぎて、明日以降のどこかで話があるだろう。
これで、三組に渦巻く嫌な空気が吹き飛べばいいのだけれど。
少なくとも、直接的な影響がでなければまずはそれでいい。裏で何を言われてようと、遠く離れていれば気にするほどのことではない。
「さて、これからどうする?」
「うーん」
なんとなくこの大切な時間が終わってしまうのが寂しくてごまかす。
私は、一つ提案した。りっちゃんは嫌そうな顔をしたが、受け入れてくれた。
「なんかポーズをした方がいいのか?」
「いらないいらない」
私はおかしくて笑い、スケッチブックを捲り、鉛筆を立てる。
真剣な目つきで、ただ、花壇裏の階段に座るりっちゃんの横からの姿を写生した。
無自覚のうちに自分を律するりっちゃんは、リラックスした空気であっても肩の力が抜けていても背筋がきれいだ。ちょうどいい鼻の高さ、中性的な顔つき、長い白シャツとズボンの下が女性的でも、りっちゃんを形作る雰囲気は男性的で、どちらも兼ね備えるりっちゃんは普通と少し違って、素敵だ。でもきっと、みんなそれぞれ少しずつ違う。たまたまりっちゃんが目に見えやすいだけで。
強い夕陽に照らされて儚げな横顔。暗くなって見えなくなる前に、私は真剣に紙に写し取る。この瞬間を完全に切り取ることはできなくても、この瞬間を、私の目が捉えるこの瞬間を、できるだけ忠実に切り取りたい。
拙くても、私は一生懸命鉛筆を走らせる。
「ちょっと喋っていい?」
「うん。でも動かないで」
「厳しい」
りっちゃんは笑う。ぎこちなかった真顔よりこっちの方がいいな。私は消しゴムで口許を修正し、微笑みを与える。うん、りっちゃんらしい。
「おれ、幼稚園の頃、いじめられて泣いているまみちゃんを見て、守らなきゃって思って、ヒーローになるって言ったの。覚えてる?」
「もちろん」
明るい記憶ではなく、むしろ掘り起こされたくない部分でもあるが、りっちゃんに助けてもらったことは何にも代え難い私の希望だった。指切りまでして、約束を交わしたことを、よく覚えている。
「りっちゃんは、私のヒーローだった」
「うん。そうなりたいと思っていた。でも、実はまみちゃんもヒーローだったんだな」
「私が?」
咄嗟に素っ頓狂な声をあげて、手を止めそうになるが耐える。しかし、ふらふらと明らかに動揺した線になってしまう。
「おれ、結構きつかったんだわ。いろんなこと。男子として生きてみようと思ったのはいいけど、親がまず困る。親はきっと、おれのブレザーとスカートの晴れ姿を見たかったんだ。前例が無いせいで先生方も困惑してるし、みんながどう受け止めるべきか困っているのも解ったし。気持ち悪いものが気持ち悪いのは、しょうがないじゃん。単純なことかと思ってたら、おれだけの問題じゃないんだなってよく解って、でも、おれはおれであることからは逃れられないから、そことのギャップも、地味ないたずらも、苦しかったんだ」
「うん」
「昨日、ダンス練習して、一日目だったからやばいかもなーとは考えていたんだ。でも、もうこれ自体もさ、おれがどうあがいても女子っていう証拠で、覆せなくて、それがむかつくやら苛立つやら悔しいやら、でもどうしようもないから隠すしかない。でも、あの時は耐えられなかったな。最近あんまり寝れてなかったし」
「……そっか」
大人びたりっちゃんを創る、本当のりっちゃんが話しているのだ。私は余計な邪魔をせず、相槌に専念しつつ、絵を完成へ近付ける。
「身体の変化にはあらがえないと実感したけど、まみちゃんが助けてくれて、本当に助かったんだ。それに、その後まみちゃんが取り乱したのも、びっくりしたけど、この子は味方でいてくれるんだって」
りっちゃんが振り返る。私は、動かないで、と言わなかった。
「ありがとう」
夕陽を逆光にして、りっちゃんはきれいに笑った。本当に嬉しそうに笑った。
私は鉛筆を止めて、呆然とした。そしてまた号泣していた。
「いやいやいや、だからなんで泣くんだよ」
「わかんない」
りっちゃんは戸惑いというよりもおかしく笑った。私は鞄からタオルを取りだそうとして、青いハンカチが目に入った。あれから良い機会が全然無くて、返せずにずっと鞄に入れっぱなしにしていたのだ。私は泣きながらとりあえず返そうとする。
「いや、それで拭きなよ」冷静なりっちゃんは呆れる。「そのうち返してくれればいいし」
運動会の汗をたっぷり吸い込んだタオルよりもずっと清潔なハンカチに、また沁みができた。申し訳なさやらなんやらが積み込まれた、重たいハンカチになっていく。
「泣き虫だなあ」
りっちゃんは苦笑する。
「泣き虫だし、いつまでも、りっちゃんに甘えてばっかりで、弱虫で……だからずっとりっちゃんが苦しんでるの知ってたのに、見て見ぬふりして……全然、私、ヒーローなんかじゃない」
私はぽつんぽつんと涙ぐみながら言う。りっちゃんは首を横に振った。
「そんなことない。みんな弱虫だ。おれもそう」
「りっちゃんは、すごいから、私なんかと全然違って」
「すごくない。おれはまみちゃんの方がよっぽどすごいと思う。嘘をつく方がよっぽど楽なことだってあるじゃん。ちょっとはみだすことって、本当に大変で、勇気がいることだから。その一歩が一番大変だ。だから、真実ちゃんはすごいし、おれのヒーローだよ」
「うええ……」
身に余る言葉ばかりたくさん浴びて、私は写生どころではなくなってしまった。微笑むりっちゃんを写した拙い絵に、涙が一粒落ちる。
「うわっすげえ。この短時間で? めっちゃ上手いな。ちょっと気にしすぎなくらい人のこと見てるもんな。絵の才能あるんじゃないか?」
りっちゃんはスケッチブックを私の膝上からあっさり引き抜いた。
「他のも見せてよ」
了承を得る前に、まったく悪気が無い手さばきでりっちゃんは過去のページを捲る。
涙が瞬時に止まった。真顔になり、さっと血の気が引く。
その中には、こっそり、隠し撮りならぬ隠し描きした、りっちゃんの高跳びをする瞬間の写生画が入っているのだ。
「や、やめてーーーーー!!」
透明人間だった私に、輪郭が描かれ、あざやかな色が塗られていく。
了
「弱虫ヒーロー」
三題噺お題:世界の終わり、嘘をつく、指切りげんまん
0 notes
Text
読書日記:ペーパーウェル②
6/27ペーパーウェル
きょうもペーパーウェルの感想をいくつか。きれいなデザインのペーパーや折本が多くて楽しみました。
ーーーーーーーーーー
「お散歩さんぽ」せらひかりさん
子どものころ、「野の草花」という絵本が大好きで、公園や原っぱに生えている草花の名前を調べて楽しんでいました。ホトケノザの産毛がふわふわしたところにちょこんちょこんとピンクの花が顔を出しているのがすごく好きでした。イラストがすごくかわいくて、アザミが少年ぽいのすごくわかります…!
「萌黄の先」桜鬼さん
氷の張った川を渡る村のお祭り(?)で妹を亡くした「俺」。「不確かな体感それのみを記憶に残し無事でいた所為で理由もなく、妹も大丈夫だろうと離れていた。」が印象的で、これとは少し離れますが、人は体験したこと(とくに成功体験)を信じてしまうよな…じっさいに自分でやったことの記憶は知識より重くて、体験談は強くなっちゃうよな…みたいなことを思い出しました。萌黄色に重ためのイメージをのせているのがいいなと思います。
「マスクに吸いこまれる彼女の声」かくらこうさん
不思議さの手ざわりが洒落ていて好きです。どことなくレトロな感じ。「慈悲科」の響きがいいなあと思いました。なんとなく寺山修司の「ノック」っぽさががあって…あるいは幻燈機で映し出されるような…。マスクをつける暮らしが日常となったこと、いきなりそうなってしまったいまのこの状態はたしかに不条理劇のようだなあと思いました。
「ハノイ旧市街散歩」クンショウモさん
ハノイ行きたい〜!となりました。雨上がりの緑の濃い写真が美しくて、また街角の写真は湿度やにおいを感じるようで…旅気分、散歩気分を味わいました。線路にイスを出してお茶をする、のんびりした光景に憧れました。
「そうしてわたしたちは朝を下校した。」燐果さん
中学のサッカー部の集まり…というプチ同窓会のような飲み会の帰り道。最終バスのあとで暗い道を歩く二人が、なんとなく母校に寄り道して…。いや〜こういうシチュエーション大好きです。夜にどこかへ忍び込むあの感じを思い出しました。
「ルピナスの爪」末埼鳩さん
『魔女の宅急便』の家、いいですね…。ルピナスはにょきにょきっとした感じがかわいくて好きです。実直な語りのエッセイで、娘さんが「けっこういい話じゃん」と言ったというのがすごくわかるなあと思います。先日『オートカクテル 不条理』の作品を読んだのですが、エッセイはまたちがったテイストでいいなあと思いました。
「ふたりの休日」草群鶏さん
「俺」と後輩で居候の沢村の散歩。「俺、かわいがられてるんで!」という沢村の人懐っこさとちゃっかりした感じがチャーミングでいいなと思いました。イラストがすごくかわいいです。小さいころノビルを摘んだことを思い出しました。
ひとまず以上です。おかわだのを読んでくださった方、コメント寄せてくださった方、ありがとうございました。すごく励みになりました。こういう企画があるとなにか短編を書こう…という気持ちになりますね。また短編集も作りたいな。
ーーーーーーーーーー
以下日記。
今日は、途中まで書いてしばらく放置していた大学生のBLをあれこれいじっていました。映画好きの大学生と美男子の大学生がサークルを作って友だちになる話で、自分としてはすごくシンプルなラブストーリーのつもり。おじいちゃまとか既婚子持ち男性とか3Pとか甥叔父とかそういうのじゃないやつ…なのでちょっとめずらしい感じです。いやこれまでの「そういうの」がとくに過激とか派手ってわけではないんですが、なんだろう、大学生の話を書くのが自分の中では新鮮というか。直球で若者の話で、すごくリラックスして書いています。
これはKindleにしたいつもりですが、本もちょこっと刷ろうかなあと考え中です。連載みたいな感じでpixivにちょこちょこのっけていくのもありかなあとも思っていて、どうしようかな…。紙の本は100ページくらいの小さい文庫本になるかなあと思っていますが、表紙イラストを頼んでみたい気持ちもあって、それならB6のほうがいいかな〜。こういうのを考えている時間って楽しいよね…。
ハノイのペーパーを読んだから…というわけではないのですが、今日は夕飯にフォーを食べました。生協のミールキットで作ったやつで、あらかじめ野菜がカットされている&鍋ひとつで作れて楽ちんでした。中途半端に余っていたチンゲンサイも入れて、冷凍の輪切りレモン(お酒用に買ってる)を浮かべて…。夕方マンションの廊下を歩いていたらどこからか蚊取り線香のにおいがして、夏だ〜と思った。夜になっても暑く、湿度も高く、さっぱりした鶏肉のフォーがおいしかったです。フォー、茹でるのに時間がかからないのもいいですね。フォーだけだと足りなかったので、これも生協の、胡椒餅というのを食べました。台湾のパンみたいなおやきみたいな…。白っぽい生地のなかにひき肉のあんが入っていて、あんは名前のとおり胡椒がきいていました。これもおいしかった。ちょっと旅行気分でした。
0 notes
Text
私の歴史、活動記録 3
青森県八戸市立中学校時代 1968年4月~1971年3月
A 放送陸上
現在も、全日本中学校通信陸上競技大会が行われている。この大会は>毎年6月から7月にかけて、各都道府県の陸上競技場で行われ、結果が集計され各種目ごとに全国順位がつく。<(Wikipediaから抜粋)ものである。 当時は放送陸上と言われていた。 この大会で同学年の男子がハードルで全国優勝した。一年上の女子も1年下の男子も同競技大会の同種目で、やはり中学校1年生の時、優勝した。
この中学校に指導者がいたのだ。それは社会科の教員であり、陸上部の顧問であった。とても若い教員だった。(私が2003年、47歳の時、郷里で彫刻の個展をやった時、観に来てくだっさたが、校長として在任中だった。)噂によると「東京出身で、東京の有名でない大学を卒業」で、なぜか青森県で教員をしていた。
社会科の教員としては素人みたいで、そのせいか気張って偉そうにする面があった。(その辺が見え見えで、いいところを見せようとし跳馬で前方転回をし、アキレス腱を断絶するなど・・、意外と親しみがあった。)そして、「叔父貴は国家公安委員長だ。」と何度か言ったのを覚えている。しかし、国家公安委員長と言えば国務大臣であり、国会議員であり、この教師が、1969年当時の国家公安委員長である福岡県出身の荒木万寿夫国会議員の甥とは思えない。おそらく公安の仕事として、赴任して来たのであろう。
平たくいうと、東京から指導者が来て、「田舎の子を日本一にした。」ということなのだろう。
B 器械体操部
この中学校の器械体操部の顧問は、前年までは中京大学の体操部出身で、同僚などはオリンピック選手であったほどだった。 それでその先生の指導を受けた1年上の2年生先輩たちはとても上手だった。 ちなみに3年生はいなかった。先生が厳しいので全員辞めたようだった。
部員が更衣室として使っていた体育用具室に、その先生の手書きの言葉が書いてある1枚の青焼きのコピーが貼ってあった。『体操とは美の追求である。諸君の日々の鍛錬を望む』という内容だった。
体育館は1日おきにしか使えなかったので、雨が降らなければ1日おきに、学校の裏の太平牧場を走り抜け、大須賀海岸で練習した。 砂は足に重たかったが、海まで緩やかに傾斜していた。 太平洋の荒波に向かってピョンピョンクルクル・・今考えると、とてつもなく贅沢な記憶の財産のような気すらする。
ちなみに海岸と牧場の間の道は、日本画家東山魁夷の『道』の舞台である。
私はそんな器械体操部に入部していた。
中3の春、部長(キャプテン)を決めることになり、誰もやりたくないので、あまり練習には来ていなかったが、背が大きい男子に決めた。ところが、この生徒がすぐ実質的に部を辞めてしまったので、実力のある男子が実質的に部長となった。しかし、その実質的部長を、前出の陸上部の顧問が陸上部に引き抜いてしまった。
そんな中、中3のある時期、跳馬と床運動が得意な脚力系だった私は絶好調で、バク転バク転伸身���返りなどのタンブリングをガンガン決めていた。
そんなある日、ヒステリックに生徒を殴ったなどと問題になった評判の悪い教師が、器械体操部の顧問だったのだが、どういうわけか、部活の最中に、体育館のステージの演台を事務机代わりにしていた。
すると私の母と高校の時同級生だったという国語の女教員が来て「教室で田村君を呼んでる人がいた。」と言い、わたしを教室に行くように促した。
教室に行ったが誰も居なかった。走って体育館に戻って、そのまま床運動を始めようとすると、その女教師は「いくら慣れていても、準備運動からやり直すべきだ。」と小言を言い始めた。
そして、壇上の評判の悪い顧問教師が演台の脇で、「ちょっとだけよ~」とドリフターズのカトちゃんのストリップギャグの物まねを始めた。
またその時いた女教師は、国語の授業中、教科書の文章の段落分けで、明らかに変な分け方を、あからさまにわざとした。
担任にそのことを言うと、担任が「『このクラスはざわついていて、調子が狂った。』」と言っていた。」と言った。しかし、段落分けなど、容易なことであり、加害行為としてやったのは間違いない。
こんな状況の中、私はすっかり調子を落としてしまい、鉄棒で落下して首から落ちたりした。
C 女子器械体操部も(徒手体操団体)
実は私が入学する前年まで、体操部の顧問の先生は、中京大学器械体操部出身で当時の同僚はオリンピックの金メダリストもいたほどの人だった。ところが、私が入学した年、その先生は転任した。しかしながら、1年先輩の部員は1年間の指導だけでも、市内の新人戦で好成績を上げた。(2年先輩の3年生はいなかった。練習が厳しいので、全員辞めたと言う。)そして、翌年、中3になった先輩たちは、基礎ができているので特に指導者がいなくても、個人総合および団体優勝、種目別でも優勝を含む好成績を上げた。
その先生は、1年先輩たちが手塩にかけた才能揃いだったので、よっぽど無念だったようで、着替え室を兼ねていた用具室に青焼きコピーを貼っていた。『体操とは美の追求である。諸君の日々の鍛錬を望む』というような文面だった。
この立派な先生の後任が「一寸だけよ~」のおふざけ教師で、突然ヒステリックに暴力的になる超問題教師だったのだ。
私は中3の時、中体連の夏の大会で団体で4位だった。得意の跳馬で演技後、異例の長い審議があり10点満点中7・5しか出なかった。
ところで、女子の徒手体操団体の後輩たちは、とても頑張っていて、彼女たちが中1の新人戦で優勝した。そして、中2の夏の大会目指して練習を積み、本番に臨み好演技をした。ところが、規定の演技構成が変わっていたのにもかかわらず、それが伝えられていなかった(演技構成の変更を説明する講習会があったことを知らなかった。おそらく顧問が貶めるために知らんぷりした。或いは協会自体が貶めた。)ため、規定違反で点数を抑えられてしまい好成績を上げることができなかった。
D 加害対象は学校ぐるみ・地区ぐるみ
中体連と言っていた市内のすべての中学校による運動競技大会の時だ。体育の教師たちが中心になって、私たち八戸市立鮫中学校選手団の市営陸上競技場での開会式のために、緑色の運動着の胸にオレンジ色のサメの形のワッペンを生地から切り抜き、付けさせ『SHARKS』として行進させた。 実は、ミュージカル映画「ウエストサイド物語」に、プエルトリコ系アメリカ人非行グループ「シャーク」が出てくるのだ。
私は狙い撃ちされたが、私のみならず、体育会系エンジンによってだけでもこれだけ、学校ぐるみ・地区ぐるみで差別・加害を愉快犯的に受けた。
そう言えば、入学当初からある教師は「鮫は文化的的でない。ピアノを習ている子も少ない。」と繰り返し言った。その教師はピアノを習っている子供の数を地区別に把握していたのかもしれないが、言われる生徒としては誰が習っているのかわからないので、何とも言えなかったし、それがどうしたの?うるさくて怖い教師だと思った。後で知ったことだが、この教師に腹を立て、この教師の科目のテストを白紙解答した女子もいたということだ。その女子はピアノを習っていて、父親は教員で(後に姉も教員)母親は町唯一の書店をしていて、とても裕福だったので余裕なのかもしれない。(こういう女子は美大に進学する。した。)
E 生徒の音痴を直そうとした先生
我が学年にすごい音痴の子がいた。そして、その子の音痴を直そうと放課後その子にレッスンをするとても熱心な音楽の先生がいた。
ところが、その先生は翌年転任してしまった。風のたよりでは体調を崩した。
結婚した。ということだったが、間もなく亡くなってしまった。
今考えるとその子は音痴でなければならなかったのではないのだろうか?
その子はその当時の水産高校の校長の子で、目立つことをやる役割を担っていたようだ。つまり、目立つ任務を遂行する上で、コンプレックスを覆い隠すためというモチベーションを持つために、そして少なくともちょっとした異常性を感じさせるために、音痴のままでいる必要があったのだと、今になって思う。
F 運動会での準備体操
運動会の時、みんな整列し、先生らの挨拶の後、準備運動としてラジオ体操をした。 当たり前のような風景であるが、私は先生に言われ、体操部だからという理由だろうが、壇上の全校生徒の前で先導するようにラジオ体操をすることとなった。 正直言って私は小柄で見栄えするはずもなくとても恥ずかしかった。器械体操部の3年生部員は私を含め2人で、もう一人も小柄で細い。先輩たちのように好成績を上げているわけでもない。いっそサッカーの青森県代表の担任の体育教師がいつものような感じでやればいいものをである。しかも、総練習みたいな時、私がやって、それについて何も言わない。本番でも私が前に出てやることが伝えられるわけでもない。本番終了後も誰一人声を掛けるわけでもない。晒しだったのだろう。
G 進学にかかる3者面談
中3も押し迫り、進路、受験校を決めるための、担任、父、私による面談があった。私は進学校を希望した。すると担任の教師は「この成績だったら大丈夫だと思いますが、入学してから、ややもすると下位でいるより、近くの高校に行って上位にいたほうがいい。という選択もありますが?」と言った。先生の手元の資料を見たところ、私は学年で18番だった。そして19番は、水産高校の校長の息子だった。結局、私は意思を通した。ちなみに19番の子は、近くの高校に行った。
そして、担任は、もしものために滑り止めの高校の受験を促した。しかし、父は「1校だけ」と言った。そして、私は何かに憑かれるように「合格しなかったら、茨城のおじいちゃんの所へ丁稚奉公に行きます。」言った。
私は物心ついた時から父親に、父親が都合が悪くなると『茨城のおじいちゃんのところに丁稚奉公に出すぞ。』と言われていた。 祖父は茨城で建具屋をしていて、確かに若い人を使っていたのを憶えている。 国家公務員の父親には何かしら脳裏に焼き付けさせる脅し的なところがあった。自分の子でも、青森の子はカッペなのだ。
H 「日本人は農耕民族。」
私が中学生の時、先生がやたらと「日本人は農耕民族だ。」と言いまくっていた。私の町は元々は漁港の町で、そして牧場が広がっていた。農家など特に存在しなかった。また、縄文時代の遺跡だらけの土地柄であった。 支配組織がその下の工作員たちを使って、『優越の民が国を作り牛耳る』みたいなイメージを植え付けることに懸命だった気がする。 高度成長期の頃だ。(そして、私が高3の頃、環境問題がクローズアップされた。高度成長の象徴である工場の煙は悪となった。)
I 卒業式の日
卒業式の日、クラスの最後のホームルームで、担任の体育教師は、いつものように出席をとったのだが、私の名前をうかっりした振りをして、呼び上げなかった。(ちなみにこの教師は当時サッカー青森県代表で、その後、八戸市サッカー協会を副会長をした。ちなみに、この体育教師の名は『セイシ』である。) そして、卒業アルバムが配られた。その中で、私はなんと『オレンジ色好きの色きちがい』と紹介されていた。

写真 大須賀海岸 https://aomori.uminohi.jp/report/osukakaigan2019/
0 notes
Text
【黒バス】Bye bye by Bye bye
2016/05/03発行コピー本web再録
封された手紙と一緒にお渡ししておりました。
手紙の中身の一文は最後に入れておきます。
この感情に色をつける。そうすると、俺は何色の絵の具を手に取れば良いのだろう。
悲しみはブルーで、イエローはハッピーだ。恋だったらピンクで、情熱レッド? いいや情熱はバイオレットかもしれない。『危険信号』は赤と黄色で、緑は『癒し』。或いは運命。
いつの間にか、俺たちの感情は、大昔に誰かが塗り分けた姿をそのまま使わされていることに気づく。まるで神様みたいだよな。一番最初に、空を青に塗ったみたいに、夕焼けを橙に染めたみたいに、夜を闇色にしたみたいに、俺たちは決められた色で動いている。赤は止まれ。緑は進め!
別にそれに、文句を言う訳じゃない。ただ、教えて欲しいだけなんだ。正解があるなら、正解であるに越したことは無い。一度色を塗ってしまったら、上塗りできる保証なんて、どこにもないだろう。
なあ、俺って今、何色なんだ?
一番最初のピカソでも、モネでもダリでも、或いはエジプトの壁画を描いたような古代人でもなんでもいい。誰か教えてくれないか。俺のこの感情は、果たして何と呼ばれるものなのか。
なあ、お前だったら、俺を何色に塗ってくれるんだ?
*
「真ちゃんさあ、これ版画の授業ってわかってんの」
「もちろんだ」
「版画ってさあ、こう、なんかさ、ざっくり線をとってさ、大まかな形を表現してさ、そんで自由に色を塗るようなもんだなって、俺、思ってたんだけど」
「そうか」
こんなやり取り、前にもした気がする。した気がする、というか、間違いなく、したんだよな。覚えてるし。あれはいつのことだったっけ。確か、校庭のど真ん中で、俺とコイツは並んで絵を描いていた。油彩の授業だったんだ。空から鳥の糞が落ちてきて、真ちゃんは嫌そうな顔したんだっけ。青空と、強い風。何処かから飛んで来たコンビニのビニール袋が、夢みたいに空を舞い踊っていた。
写真みたいに覚えているのに、細かい所がぼやけている。
まあ、過去は過去だ。今は今。油彩じゃなくて、今学期の課題は版画。風のない教室の、後ろの方に陣取って、俺は緑の頭越しに、どう贔屓目に見ても版画には見えない風景画を覗き込んでいる。
美術の授業は大概自由だ。思いっきり大声で喋っていても、席を移動しても、なんなら、他の教科の宿題をやっていても怒られやしない。自由な感性が自由な作品を生む、だとか、なんとか。そういうポリシーらしい。ホントか? ただまあ、そうは言っても秀徳高校、自由には責任がつきまとう、ということで、提出期限が一日でも遅れれば落第、中身が酷ければ容赦なく赤点、泣きつけば減点。恐ろしい世界。
「お前、下絵の段階でその細かさで、どうやって彫る気よ? マジで一生かかっても終わんねえだろ」
「馬鹿が。誰がこれを彫ると言った」
「いや、え?」
戸惑う俺を他所に、真ちゃんは淡々と、教室の風景を白いキャンパスに写し取っている。写すとは言っても、動き回っている生徒たちは軒並み存在を消されて、そこに描かれているのは、がらんどうの教室だ。がやがやと、ざわざわと鼓膜を揺らすあらゆる感情のお喋りと、面前のキャンパスの静けさが噛み合わなくて違和感しかない。精密な筆致のせいで、余計に奇妙に見える。机の上の落書きも、汚れたままの黒板もそのままなのに、それを生み出した筈の人間がいない。いやでも視界に映る、沢山の制服と喧騒、その全てが排除された白黒の教室。
「え、じゃあお前、何描いてんの」
「見たままだが」
お前の目には邪魔な生徒は映ってねえのかよ。怖ぇよ。
というのは、まあ冗談として、見たまま、見たままね。じいっと見つめる俺など知らん顔で、テーピングされた左手は着々と教室を完成させていく。鉛筆の粉がこぼれて、指先が僅かに黒ずんでいるのを、俺は黙って見過ごしている。
「いや……版画の下絵じゃねえの?」
「彫刻刀など、一歩間違えれば手を傷つけるようなもの、使うわけが無いだろう」
「いや、それは、まあ、ちょっと思ったけどさ、いやでも、彫らずに版画とか無理だろ」
「お前が代わりに彫ってくれるんだろう?」
「絶対にお断りだわ! どんな苦行だよ!」
冗談だ、と真ちゃんは嘯くが、ここで俺が「やってやるよ」などと言っていたら、マジでやらされていた気がするので油断ならない。真ちゃんは案外、目的のために手段を選ばないずるい男なのだ。ホントの話ね。その目的のほとんどが、まあ一般的には害のないものなので、あまり周囲に伝わらないだけである。こわい奴だよ。
今だって、真ちゃんの目的はこの風景画を完成させることに��るので、さっきから話をしている俺のほうへ振り向いてもくれないのだ。あーあ。優先順位がはっきりしてやがる。
こっち向いてよ。見ればわかると思うけど、お前の隣には今、俺がいるんです。
「教師には、版画は絶対にやらないと言ってある。例え成績評価で最下点を付けられようが、なんだろうがな。とはいっても、授業中に何もしない訳にもいかないだろう。美術の授業なのだから、美術的なことを行うべきだ。代わりとして、油彩とレポート提出で代替評価としてもらうよう交渉した」
「はあ……そんなことできんの」
「監督に我が儘二十一回分で」
「マー坊に謝れや! いや二十一回分って、すげえんだか、そうじゃないんだかもよくわかんねえけどな!」
「授業の回数なのだよ」
「一回につき一ワガママかよ。節約してんじゃねえよ」
言ってしまえば、こんなの授業のボイコットだ。授業一回につき三ワガママくらいは使われて然るべきだろ。等価交換とは言わないが、最低限の仁義っつーか。なんつーか。
「だから水曜は二回しかワガママが使えん」
「なんで不満げなんだよ。二回も使えることに感謝しろよ。一般ピープルはゼロ回だからな」
まあ、真ちゃんの手を傷つけたくないのはバスケ部の総意だ。どんなに腹立たしくても、こいつの手が毎週水曜四限に傷ついてたんじゃ話にならない。というか、それこそ俺が見ていられなくて代わりに彫ってしまいそうだ。奴隷根性極まれりってか。手を止めて消しゴムを探しているらしき瞳に、俺はそのへんに転がっていた消しゴムを放り投げる。こうやって、言葉にされる前に甘やかしてしまうからいけない。わかってんだけどなあ。
マー坊も苦渋の決断だったろうな。そんで、なんで美術の教師はオッケーしたんだよ。普通に考えたらありえねーだろ。自由か。これも自由の一環だっていうのか。
「うっわ、緑間、ナニやってんの」
「真ちゃんさあ、彫刻刀使わねえかわりに油彩なんだってよ」
「うーわ、相変わらずだなお前」
「うるさい。これが人事を尽くすということなのだよ」
立って騒いでいた三村が、真ちゃんのキャンパスが目に入ったのか、ずかずか近づいて悲鳴をあげた。そりゃな。版画でこれやろうと思ったら気が狂うよな。でもちげーんだよ。こいつは既に先生に交渉済で、何故か一人だけ油彩をやるんだよ。高校生が、教師の作ったカリキュラムに逆らうって、なかなかどうして、普通できねえもんだけどな。
三村は、どへぇ、だか、うひゃあ、だか、意味の無い雄叫びをあげて真ちゃんの絵を見ている。真ちゃんはもう会話は終わったといわんばかりに、黙って己の作業を進めている。そうして、窓の外は青い。昔のように青い。覗き込めば、校庭で馬鹿みたいに笑ってる俺がいそうな気がする。
気がつけば、三村はもう元の位置に戻って騒ぎを広げていた。机が揺れる音、椅子が床をこする音、笑い声、叫び声、どうでもいいお喋りと、低く聞こえてくる誰かの愚痴。誰かが空気を震わせるたびに、そこが色づいていく。黄色い声、赤い叫び、緑の音、青い響き。多分世界中で、ここがいま、一番雑多にうるさいんだろうな。
「ってかさあ、真ちゃんクラスメイトも書こうよ」
「何故」
「何故って、これ風景画だろ?」
「あんな動き回る喋り倒す輩を、一人一人描いていたら、それこそ終わらないのだよ。風景画だからこそ、人を配置する必要性は無いだろう」
「まあ、そりゃそうかもしんねえけど」
教卓の歪みも、窓の外の街並みも正確なのに、生徒たちがいないだけで全く違う教室だ。段々と完成されていく世界があんまりモノクロなので、俺は何故か不安になる。白と黒の線だけの世界は、ちょっとぞっとするほど冷たい。
「お前だけ描いてやろうか」
「えっ」
「この課題が終わるまで、一ミリも動かずに静止して黙っていられるならな」
「死ねって言ってる?」
「親切心だ」
お前も、人のばかり見ていないで、自分の課題をやったらどうだ。
そう顎で示された先は、今日の授業開始からほとんど進んでいない俺の下絵だった。そもそも何を描いているんだ、と言う真ちゃんには、俺の半分も進んでいない下絵じゃ何も伝わらないらしい。テーマ? テーマはね、体育館。いっぱい見てるし、床と壁しかねえから楽かと思って。ちなみに、バスケのゴールリングは省略してある。ゴールは描くために存在してるわけじゃないから、いいんだよ。
「遅れれば落第」
「あー! あーもう分かってるよ! くっそ、油彩の奴には負けたくねえ。油彩で合格して版画で落ちるのは勘弁」
もういっそ、下絵なしに彫ってみたら、味のある絵になるんじゃねえ? そう思って、試しに適当な所に刃を入れてみたら、木の欠片だけが無意味に散った。ぱらぱらと、木屑が落ちる。強くやりすぎたのか、深く抉れて、一箇所だけ穴があいたようだ。三角形の、あなぼこ。
「おい、高尾、飛ばすな。木屑があたってるのだよ」
「うるせー」
がりがりと、彫る。がりがりと。がりがり、がりり。意味のわからない奇妙な曲線が生まれて、俺もなんだか不思議な気分だ。楽しいような、気持ちいいような、妬ましいような、何か。体育館の床が、丸く抉れていく。
「勢いよく、いきすぎじゃないか」
「いーんだよ、こんくらいで」
「後戻りできないのに、よくやるな」
後戻りできないのにね。ホントにな。俺は彫っていく。体育館? いいや、目に見えない、俺の中の何かの景色を。
多分、今期の美術、評価ヤバイな、これ。
*
バッシュの靴紐は右から結ぶ。俺じゃあなくて、真ちゃんの話。真ちゃんの、結び目は、とても綺麗だ。性格出るよな。右と左が綺麗に対称になっていて、紐は長すぎず短すぎず、バランスを保って鎮座している。なんだろう。あるべき姿として、おさまってるんだ。紐ひとつに言い過ぎかもしれないが、こいつの場合は一事が万事これなのだ。鉛筆は絶対に芯が尖っているし、ハンカチはいつも縦に二回、横に二回畳まれてポケットに入っている。
俺はといえば、シャー芯は使い切る前に無くすし、ハンカチなんて持ってりゃ御の字、鞄の底で無限に折れ曲がっている。靴紐は何故か滅茶苦茶右上がりになるんだよな。自分でわかっちゃいるが、わかっただけで綺麗に結べりゃ問題無い。
「高尾交代! 多野上はいれ!」
「ハイ!」
「スリーメン五本、バック走三、残りケーオージャンプ五十、先頭水城、はじめ!」
「はい!」
喉に細かい罅が入ったような熱がある。それでも体育館中に響くような大声で、俺は必死に数を数える。
イチ、ニ、サン、ニ、ニ、サン、サン、ニ、サン、ヨン、ニ、サン。五回目、飛んだ瞬間に汗で滑って、顔が引きつった。下手な転び方しても、着地しくっても、すぐに捻挫だ。必死に体制を立て直しながら、俺は声を出し続ける。ロク、ニ、サン。
コートから出て、一瞬も休ませてもらえない。練習なんて、地獄の代名詞。至るところの筋肉が悲鳴をあげている。脛が剥がれ落ちそうだ。上げっぱなしの腕は震えて、そろそろ感覚が無い。血流が、必死に酸素を運んでいるのがわかる。指先から、脳みそのてっぺんまで、どくりどくりと脈動している。口の中に血の味がする。真っ赤な世界。
「そこまで! 一分後ランニング十周、そのままAB分かれて一ゲームだ。水分忘れるな!」
水飲んだら吐くけど、飲まなかったら死ぬな、って、冷静なところで考えた。体は今にも体育館に倒れこみそう。倒れたらもう、今日は試合に出させてもらえないだろうから、必死にふんじばっている。下を向いたら吐くから上を見上げている。体育館の照明が目を焼いた。視界の端には、緑色した頭がよぎる。視線をそのままスライドさせれば、そいつは浴びるように水を飲んでいた。マジかよ。バケモン。
「真ちゃん、さあ、そんな一気に飲んで、腹、やばくねえの」
「問題無い。飲まない方が死ぬだろう。恐らくマラソンのあと、水分補給の時間はないぞ」
「うそだろ……、いや、そっかマー坊言ってねえわ、くっそ」
「高尾、靴紐」
「あ?」
「あぶない」
近寄りながら、わざわざ指で指し示されたのは、俺のバッシュの右側。いつの間にか紐が解けて広がっている。もしかして、さっき滑った時に踏んづけたか? このままじゃ間違いなく転ぶ。自分が転ぶだけならまだしも、他の奴まで転ぶだろう。
結び直さないといけない。わかってる。当たり前だ。わかってる。
「ちょい待って……」
「何を待つのだよ。さっさと結べ。他の奴の邪魔だ」
「わーってる。わーってるけど、今しゃがんで、下向いたら、間違いなくヤバイ。リバース確実」
「……そういうことか」
呆れたような溜息に、心臓にまで罅が入る音がした。軋みをあげて唸っている。どくりどくりと流れていた血が、そこからじわじわ染み出していく。悪かったな。お前とは違う。情けねえ。動けねえ。畜生。
「全く、だからお前は駄目なのだよ」
「うっせ……」
ただ上を見ることしか出来ない俺に、覆いかぶさるように緑色の影が刺す。俺を見下ろす瞳は、逆光になっていてよく見えなかった。どつかれるか、冷たく諦めろと言われるか、どっちだろうな。腹を殴られて強制退場すらありえる。そんなことを俺が考えているなんて露知らず、溜息と一緒に、真ちゃんは、ふっと、しゃがみこんだ。
「は? え?」
「こっちを見るなよ。下を向いたら吐くんだろう。俺の頭にかけたら許さないからな」
「や、えっ、真ちゃん、俺」
「もう休憩が終わる。待ってられるか」
ごついバッシュに神経など通ってやしないが、気配だけで、真ちゃんが何をしているのかなどすぐわかる。しゅるしゅると、擦れる音、足首に、僅かな刺激。俺の靴紐を結んでいる。こいつが。緑間真太郎が。
「そもそも最初の結び目がゆるいんじゃないか? 結ぶの下手だろう、お前」
「うっせーよ……てか、余計なお世話だわ」
「そうか」
なら、次からは余計な世話をかけるなよ。
そう言いながら立ち上がったこいつは、確かに、かすかに笑っていた。ムカつく。悔しい。心臓が大きく動いて、血が染み出すどころか溢れ出ている。けど、それだけじゃない。顔に熱が集まっている。嬉しい。照れくさい。恥ずかしい。お礼を言うのも変な感じがして、茶化そうにも言葉が無かった。口だけを馬鹿みたいに開けて、餌を待ってる雛鳥かよ。俺が何も言えない間に、ホイッスルが空間を切り裂いた。
「これでマラソン中にへばったら、笑ってやるのだよ」
「うっせー、ぜってーに負けねえ。お前こそ疲れたへろへろシュート撃って外すんじゃねえぞ」
「誰に言ってる」
走る。怒声に応えるように、走る。走って、走って、もつれた足で、走る。下は見ない。腕を振れば、体は勝手に前に出る。床なんか見なくても、俺は足つけて走っていられる。顔をあげて、先頭をひた走る緑色の弾丸を睨みつけた。
「やめ! ゲームするぞ! 別れろ! チンタラするな! 走れ!」
才能を軸に、努力を装置に、意思を燃料に変えて、誰より早くひた走る、一つの、弾丸。高く高く撃ち上がる、ミサイル。天井すれすれから、地面を穿つように叩きつけられる、兵器にも似た何か。
あれはお前だ、お前のエネルギーそのものだ。お前の感情を、一つの球体に詰め込んで、お前はそれを撃ち上げる。
呼吸だってままならないような汗の中で、俺はそれを必死に見届ける。本当に、もう、一歩も動けない。声だって出せない。ブザーの音と、床に転がったままのボール。いつかあれが爆発したら、きっと世界は終わるだろう。誰も逃げられやしないんだ。いつか、あのボールが爆発したら、俺にトドメを刺すだろう。今はまだ、俺は、ブッ倒れそうな体を必死に地面に突き刺している。
「……っ、ふ、倒れなかったじゃ、ないか」
「ぁ、っはぁ、はぁつ、っ、は、あ、たりめー、っしょ……」
整列に並びに行くのも、もう無理だ。そう思ったら、強く腕をひかれた。今度こそ思いっきり転びそうになるけれど、転ぶだけの足すらもう動いてない。引きずられている。腕が動けば、体は前に出る。腕を動かされれば、体は前に、進まされる。力技すぎんだろ。
「や、っめ、ろ、おい、はなせっ、て」
「整列だ。待てない」
「あるけっ、から」
「嘘をつけ」
靴紐、解けなかったろう。そう言ってこいつが楽しそうに笑うので、俺は思わず下を見る。綺麗な蝶々が、俺の右足にだけ止まっていた。左側の、なんと不格好なこと。笑っちまうね。笑っちまうが、下を見たのは、本当に失敗だった。
*
「お、高尾きた」
「あっれ、どうしたの酒井」
雨だった。そして俺は弁当を忘れていた。四限が終わった瞬間にダッシュかけた俺は、目的の焼きそばパンとカレーパン、あとキムチおにぎりをゲットすることに成功。授業が時間ぴったりに終わってくれたことが、今回の勝因といえるだろう。気分が良いのでおしるこでもついでに買ってやろうかと思ったが、冷静に考えて多分あいつは今日の分をもう持ってる。朝一で買ってたもんな。
戦利品を抱え、割と朗らかな気持ちで教室に舞い戻ったら、俺の席には酒井がいた。
「いやマジ聞けよ。緑間ガチうけんだけど」
「おい、やめろ」
「えー、なになに」
「いやそれが」
「やめろと言っているだろう」
俺が購買にパンを買いに走っている間に何が起こったんだ? 窓際一番後ろ、真ちゃんの席。そのひとつ前、俺の席。俺が昼飯を買ってくるのを一人待っている筈の場所に、酒井が座って爆笑している。いや、そこ俺の席だから。
緑間がマジうける、のは今に始まったことじゃない。だけど、真ちゃんがその内容を喋らせようとしないのは珍しい。基本的に己の信念と欲求に正直に生きている男だから、なんというか、恥じらいというものが無いのだ。
何を恥ずかしがることがある、人事を尽くした結果なのだよ。俺の生き様に、恥ずべきことなど何も無い。
恐ろしいスタンスだ。己の信念を裏切らなければ、何をしても良いと思っていやがる。まあ、ラッキーアイテムとか、説明するまでもねえけど。
普通の人なら恥ずかしくて出来ないようなことを、こいつは平気でやってのけて、それを一つも隠さないのだ。おかしいだろう。
「酒井、言ったらはっ倒すのだよ」
「や、緑間ってそんなキャラだっけ? こええ!」
「五月蝿い。さっさと消えろ」
蠅を追い払うようにして、真ちゃんは酒井を追っ払った。けたけた笑いながら退散する背中を、俺は見送る。真ちゃん、酒井と仲良かったっけ。そういや、この前サッカーのチーム分け一緒になってたな。そん時は、真ちゃん倒すのに燃えすぎてよく見てなかったけど、どうやら、真ちゃん、イコール、面白い奴認定、は広まったらしい。そりゃな。嫌でも一緒にいりゃわかるよな。一緒にいて分かんないんだったら、そいつの目はレンコンかなんかなんだろう。
「真ちゃん、どーかしたの」
「いや、別に」
「ふーん」
がさり、と音をたてて、ビニールに入った昼���を真ちゃんの机に置く。俺の分だけ半分スペースをあけて弁当を広げていた真ちゃんは、こちらの準備が整うのを黙って待っている。チャイムが鳴って、何にも言わずに走り出したのに、待っててくれるんだから、こいつも大分まるくなったというか、なんというか。餌付けに成功したらこんな気持ちなんだろうな。それは、ちょっとだけ俺の心を満たす。
「酒井と何話してたのさー」
「別に、と言っただろう。お前には関係ないのだよ」
でしょうね。そうだろうよ。多分、本当に、どうでもいいことなんだろう。真ちゃんが毎日ナイトキャップかぶって寝てるとか、ラッキーアイテム保管用の部屋があるだとか、案外AVは女教師ものが好きとか、そういう感じの。多分、俺も知ってるような、或いは、知らなくても何も問題ないようなこと。知っても仕方がないこと。
「気になるなー気になっちゃうなー」
「しつこい。さっさと食べるぞ」
「へいへい」
誰も知らなくても問題ないようなことで、人間って出来上がってる。高尾和成が、何を好きだろうが、嫌いだろうが、家で何してようが、関係ない。幼い頃の初恋の先生の名前だとか、未だに捨てられないBB弾が入った、缶からの存在だとか、そういうの。そういうものの、寄せ集めで、俺の体は出来上がってる。きっと誰だって、そうだろう。
だけど、俺は、何だかいたたまれない気持ちになる。俺の知らない緑間真太郎がいることに。俺は知らないのに、俺じゃない誰かが知っている、緑間真太郎が存在していることが。
「聞いてよ真ちゃん。俺本当に今日勝ち組でさ」
「何が」
「焼きそばパンとカレーパンダブルでゲットした」
「何だと? どんな裏技を使った」
「いや走っただけなんだけどさ」
だから俺は、馬鹿みたいに喋り倒す。どうでもいいこと。知らなくていいこと。知ってほしい、こと。
くだらない、どうでもいいものが組みあがって出来上がった、俺のカラダと血肉を、お前には知っていて欲しい。
雨がざんざか降っている。俺は結構、窓越しに聞くこの音が好きなんだけれど、お前は果たしてどうだろう。どうでもいい、知らなくていいことを、俺は何故だか、知りたくなる。灰色の雨が降っている。
*
「お兄ちゃんはさ」
「うん?」
「誰かになんかあげたいとか、思ったことないの?」
「なんじゃそりゃ」
夜、リビングのソファでテレビつけながらゴロついていたら、何やら妹ちゃんが不審な動きで台所に立っていた。普段料理なんて、てんでしないくせに。がさごそと、音を立てて動き回っている。台所は、料理をする場所だ。まさか包丁探して誰か殺しに行くわけでもあるまいし。とすると、へえ、なんか作って持っていくのか。
でもバレンタインって結構最近終わったばっか。ていうかコイツ、バレンタインに友チョコとかする可愛げも無かった気すんだけど。マジでどうしたんだろうな。
「彼女いないの」
「あ? そういう話? 彼女ができたらちゃんとプレゼントしろってこと?」
「違うよお、まあ、それはそれで、そうなんだけどさ」
起き上がりもせずに声だけを寄越す俺に、妹ちゃんも淡々と、姿のない声だけを返す。
「私が彼女だったら、イベント及び記念日ごとにプレゼントを所望するね。そんでもって、他の人と遊びに行くときは必ず報告するようにしてもらう」
顔が思わず引き攣るのを感じる。単純に怖い。何が怖いって、俺の妹は、なんというか、割と俺に似て、人生楽しんだもん勝ちというか、あまり何かに執着しないタチなのだ。
周りの空気を壊さない程度には合わせるけれど、自分の好きなことだけをやってるタイプ。それがこんな、こと恋愛になると、束縛型というか、なんというか、女って怖い。
「えー……と、つまり、お前彼氏できたってこと?」
「出来てない。片思い。多分」
「多分って」
「脈なしじゃ無いと思うんだけど、なんか、人のことは分かっても自分ってなると、分かんないよね」
「ああ、成程」
台所で、恐らく調理器具を探していたのであろう音がひと段落して、今度はガシャガシャとボウルの音が聞こえてきた。普段料理の音なんて意識したこと無いけど、こうして聞くと、料理の音って、メシ作るのとお菓子作るので全然違うんだな。いや、お菓子とは限らねえのか。なんか勝手に、誰かに渡すんならお菓子って、そう思ってた。
「友達だったらさー、『それ絶対に脈アリだよ、長本くんも待ってるって、コクっちゃいなよー』とか言えるけど、自分となると、自意識過剰なんじゃないかとか、いやそうやって謙遜してる方が逆に変じゃないか、どう見ても私のこと好きじゃないかとか、ぐるぐるしちゃうよね」
「自覚してんのは良いけど、長本誰だよ」
「サッカー部のフツメン」
「イケメンじゃねえのか」
「お兄ちゃんよりカッコよくない」
「んー? それ俺のこと褒めてんの? けなしてんの?」
「事実。お兄ちゃんはフツメンの上」
あんまりにもな言い草に、思わず笑ってしまう。正直かよ。テレビでげらげらと、作りこまれた笑い声がする。別にテレビなんて見ていない。頭の中を空っぽにしたいだけだ。何だか最近、色んなことを考えすぎてお疲れの俺。学校楽しい、バスケ楽しい、生きてて楽しい。でも何か苦しい。たまに、ひどく、呼吸しにくい。心は簡単に体を裏切って、勝手に俺を息苦しくする。名前の無い、色も形も得体のしれないエネルギーが、俺の中でとぐろを巻く。
「そんで? なんかクッキーでも焼くの」
「大正解」
「わかりやすいな」
「わかりやすいから良いんじゃん。好きでも無い人にクッキー渡さないでしょ。しかもこんな時期に」
「成程。明快だな」
誕生日でも記念日でもない日に、突然付き合ってもいない奴からクッキー渡されたら、勘違いする方が難しい。俺もお菓子って、勝手に思ったくらいだし。だからこそ、渡すのは結構勇気いると思うけどな。
「迷ったんだけどね」
「何が? クッキー渡すか?」
「それもだし、何を渡すかっていうか。別にクッキーあげたいわけじゃないんだよね」
「うん? よくわかんねえな」
ガシャガシャと、音は続いている。クッキーって、こんなにずっと、何かをかき混ぜているもんなのか。ずっと、少し荒っぽい、音がする。恋をして、ウキウキしたリズムではなく、やるせない、大雨のような音だ。あらゆる感情をかき混ぜて、種を埋め込んでいる、音。
「何でもいいんだよ。ていうか、なんかさ、自分の持ってるもの全部あげたくなっちゃうの」
「お前そんなボランティアキャラだっけ?」
「うっさいなあ。そうじゃなくて、その人にはってこと。その人には、自分の持ってるもの、全部あげたくってさ」
「おお、恋してんな」
「恋だよ。これはマジで恋だよ。だってさ、あげたいだけじゃなくって、全部欲しいんだよ。意味わかんくない?」
「ソレ、分かるのか分からないのか、どっちなんだよ」
「そういう感じなんだよ」
分かんねえよ。あまりにもアホらしい会話に、考える方が馬鹿らしくなってくる。勢いと感覚だけで話しすぎ。コイツはどんな顔してこんな話してんのかと、ソファから起き上がって台所に向かった俺はちょっと後悔した。
「見返りが欲しいんだよね」
想像していたより、三百倍くらい、真剣な顔をしていた。全然楽しそうじゃなかった。むしろ、嫌そうな顔をしていた。手元でクリーム色になっている何かは、もう十分に混ぜ合わさっているのに、コイツは手を止めない。俺は何故だか、この遣る瀬無い物体を見て、バスケットボールを思い出す。感情の坩堝。あらゆる衝動を詰め込んだ、一つの爆弾。
「不純すぎねえ」
「だよねえ」
このクッキーは、あのボールと同じなのだ。爆発したら、死んでしまう。誰も逃げられない、致死性の爆弾だ。それを必死に溶かして、かき混ぜて、一つの形に、閉じ込めている。
誰かはそれを、信念と呼ぶかもしれないし、執念と恐れるかもしれない。大切な気持ちをありったけ詰め込んだけれど、どうでもいい物だって、一緒に沢山入れてしまった。
それは、俺の、或いは誰かの、全てなのだ。
「自分のものあげるのなんてさ、勝手じゃん。あげればって感じ。相手が欲しくなかったら捨てるだろうしさ、はいどーぞ、はいどーもって感じで、終わりじゃん。でもさ、欲しいんだよね。相手の全部知ってなくちゃ嫌だし、自分が知らないとこ出されると、ムカつくし不安になるし、でも全部なんて無理ってわかってるから、もやもやするしさ」
ガシャン、と一際大きな音を立てて、調理器具は洗い場に放り込まれた。
「何で無理って分かってんのに欲しがるんだろうね?何で無茶って分かってんのにやろうとすんだろうね? そんで、そこまで分かってるくせに、なんで心のどっかで期待してんだろうね?」
溜息と一緒にチョコチップが放り込まれていく。この一粒が、コイツの感情で、あの一粒が、コイツの感情だ。そうやって、感情を消化している。
「むなしいわ。むなしいけど、何もしないのも耐えらんないから、クッキー。本当は、全部ぶん投げたいし、全部欲しいけど、どうしようもないから、クッキー」
あー、もー、やだやだ。そう言って笑う顔は、俺によく似ていた。本当に、馬鹿だなあ。俺もお前も。
「やっぱお前って俺の妹だわ」
「はあ? 何当然のこと言ってんの」
「欲張りで、嫉妬深くて、でもへんに計算できるから上手いこと傍目には帳尻合わせて、その癖頑固だから自分の意思は曲げれずに、最終的に勢い任せに突っ走ってる感じが」
「あー、そりゃ、私だわ」
「だろ? ちなみに俺もだ」
「じゃあ、お兄ちゃんも恋してんの」
「してるね。こりゃ」
ほんと、やだやだって感じだよ。参っちゃうね。こんな所で、こんな形で、自覚する羽目になるなんて、な。妹ちゃん、お前のその爆弾は、思わぬところに被害を及ぼしているぞ。
「じゃあ、これあげるよ」
無造作に放り出されていた、透明な袋を一つ取って、俺の心臓に押し付けたこの爆弾魔は、やけに楽しそうな顔で笑っている。仲間ができたのが嬉しいらしい。
「十五枚セットしかなかったからそれ買っちゃったけど、別に十五回もクッキーあげる予定ないし」
まさかお兄ちゃんも恋する乙女だったとはね。それで、何か、あげればいいんじゃないの。
俺の中ではね、恋って、ハッピーピンクなイメージだったわけ。女の子がね、きゃいきゃい夢見て、男はそれにそわそわしてる。彼女欲しい、エロいことしてえって叫んで白い目で見られてさ、それ見てけたけた黄色く笑うみたいな。そう言う感じ。まあ別に何色でも良いんだ。なんかこう、しんみりした夕焼け色でも構わない。
けど、まさか、こんな戦場みたいな、沼地みたいな、何にも掬い取れない代わりに、全部に足を絡め取られるようなモンだとは思ってなかった。爆弾は俺の心臓に眠っている。
「高尾!」
「うっわ、びっくりした!」
「さっきから呼んでいるのに、お前が返事をしないからだ」
「へっ、マジ?」
「本当にどうした? 彫るのも進んでいないし、話しかけてもこないどころか、こちらが話しても気づいていないし」
「あ、あー、ごめんごめん。考え事。ぼんやりしてた」
お前のこと考えてたよ、なんて言える筈もなく、戦争と平和について考えてた、と言ったら怪訝な顔をされた。そんな顔を見れたことでさえ、なんだか嬉しくなってしまう。
全部知りたいし、全部知ってほしい。構って欲しいし、構いたい。驚く程��までの俺のアレコレは恋だったし、今だってそれの真っ最中だ。
「お前……本当に間に合わないぞ」
「だいじょーぶ、だいじょーぶ、な、筈」
俺って鈍感だったんだろうか。いや、気づいては、いたと思う。俺の、この、不可解な熱に。ただそれに、恋という名前を付けるのを渋ってただけなのだ。友情ってタグを付けて、カテゴリ分けしていればよかった。その中で、親友とか、相棒とか、好き勝手なラベル貼り付けて、満足できるハズだったんだ。俺の心の中じゃ、俺が神様。俺の気持ちは、俺が決められる。それなのに、このザマ、笑っちまうね。
「ってか、真ちゃん進んだね……」
「当たり前だ。作業していたのだから」
覗き込んだキャンパスは、相変わらず、誰もいない教室。だけど、白黒から段々と色を重ねられた景色の印象は随分と違った。窓の外は青い、教室は陽が差し込んで暖かい。机の影だって、僅かに揺れて緩んでいるようだ。お前に見えている景色は、きっと、誰かが想像するより、優しい。
「あれ? 真ちゃん、ここ塗るの失敗したの?」
「ん? ああ」
画面の端、青空にはみ出して僅かに一筆塗られた橙色を指させば、真ちゃんは不本意そうな顔をした。失敗したらしい。
「端にお前を描こうと思ったんだが」
「へっ?」
「冷静に考えると、お前はいつも隣にいるから、この視界には写らないのだよ。それでやめた」
「えっ、と」
「弁当やら他の授業の時は正面にいるがな。今更この画面のど真ん中にお前を配置するのは流石に無理があるし」
「俺、描こうとしてくれたの」
「? 言わなかったか?」
「……言ってた」
冗談だろうなって、思ってたよ。
喉がからからに乾いていく。今すぐ水を飲まないといけない。水を飲まないと死んでしまう。だけど、飲んだら、吐いてしまいそうだ。俺の感情。俺の爆弾。お前は本当に、俺を殺すのがうまい。
「…………それで、失敗しちゃったんだ」
「そうだな。まあ、いいだろう、別に」
「いいの?」
「塗り直せばいいだけの話だ。油彩なのだし」
失敗したら、やり直せばいい。正解するまで、それだけの話なのだよ。
淡々と、そう言う真ちゃんは、きっと躊躇いもなく、一筆分の俺を、青空で塗りつぶすだろう。それでいい。それが正解だ。正しいものがあるなら、それに越したことはない。
俺は、後戻りできない穴を見つめて、笑っている。三角形に、深くえぐれた、穴ぼこ。俺の爆心地。
そういえば、リボン渡すの忘れてたよ。それだけ言って、妹ちゃんは部屋から出ていった。クッキーの結末は聞いてない。ちなみにおこぼれにも預かってない。
透明な袋と、きらきらしたリボンを蛍光灯に翳して考える。光が反射して、ちかちかする。そうだ。恋って、こんなイメージだった。
全部あげたいけど、無理だから、クッキー。
我が妹ながら聡明だ。それは酷く正しかった。そうして愚かな兄は、何もあげるものが見つからなかった。
おしるこ? ラッキーアイテム? 参考書? NBAのDVD? あいつが喜びそうなものはいくつも思いつくけれど、それは別に、俺があげたいものとは違う。
全部あげたい。その見返りに、全部欲しい。
信じられない強欲だ。俺は、俺そのものを与えたいのだ。あいつそのものが欲しいのだ。そんな小っ恥ずかしいことを考えて突っ伏した。信じらんねえ。自覚って怖い。恋って怖い。やばい、俺、絶対に、誰とどこに行くとか、めっちゃ聞いちゃうよ。休日の予定とか、いちいち確認しちゃうよ。俺ってもしかして、結構粘着質な束縛タイプだったのか。
どうしようにも行き詰まって、溢れたそれを持て余して、俺は、すっからかんのビニール袋に、何にもいれずにリボンを結んだ。
全部あげたい。全部欲しい。お前が好きだ。恋をしている。そんなの、言える筈も無かった。クッキーなんて、渡せてたまるか。全部が手に入らないなら、いっそ、何にも無い方がマシだ。嘘。何も無いなんて無理。だから、ラベルはお前が貼ってくれ。友情でも、相棒でも、下僕でも、まあいいや。
その透明な爆弾を、下駄箱に、誰もいない隙に、放り込んだ、空っぽの袋。名前もない、中身もないこれを、お前はただのイタズラだと思って、捨てるだろう。
*
「高尾」
「んあ、どーしたの真ちゃん」
「見ろ」
「っ、ええ!? で、ジャンボヤキソバオムレツパン!」
「人事を尽くした結果なのだよ」
「いやいや、えっ、それ限定五個のやつじゃねえの! どんな裏技使ったんだよ!」
「走った」
「や、やっぱそれかー!」
階段を登るのに三段飛ばし出来るのは、やはりアドバンテージとして強いな。そんなことを悠々と言うこいつは、本日昼飯を忘れたらしい。お前でも忘れることあるんだなって言ったら、忘れたのは母だ、とぶっきらぼうに返された。いや、鞄の中持ってんじゃん。勝手に手を伸ばしても、真ちゃんは止めなかった。やけに軽い感触と、何の反動もなく開いた蓋。
「ぶっは、えっ、うそ、こんな漫画みてえなことあんの」
「あるのだよ。目の前に」
「やっべ、中身入れ忘れるって、真ちゃんのママさんも、結構、天然っつーか、なんつーか」
「受け取った時に軽いことを指摘すれば良かったのだよ……俺のミスだ」
いや別にこれにミスとかねーだろ。そう言って笑う俺の心は穏やかだ。透明な、俺の爆弾をぶち込んだ、次の日。真ちゃんから何か言ってくることは無かった。まあ、そりゃ、当然だろう。そもそも俺からだと、わかる筈もないし。そうして、勝手に目に見えない感情を押し付けた俺は、ホンの少し、すっきりしている。
「そういや、俺多分あと二週間くらいで終わるわ、版画」
「なんだと。抜けがけか」
「抜けがけってなんだよ」
名前をつけられなかったこの日々を、俺は気に入っている。
「あ、お兄ちゃん、おかえり」
「んあ、どーしたんわざわざ」
「いや、帰ってきたらさ、封筒あったんだけど、なんかどこにも名前がなくて。間違いなのかな。でも、切手も貼ってないから、直接ウチのポスト入れたと思うんだよね。だから、お兄ちゃん、心あたり、ないかと思って」
リビングの机の上に、ひとつだけぽつりと置かれた、名前も無い、宛名も無い、緑色の封筒。緑色。緑は癒し。或いは、運命。俺の中で、緑色は一人しかいない。
「あー、もうあけた?」
「開けてない。心当たりあったら、悪いと思って」
心臓が、うるさい。あの日、黙って下駄箱にぶち込んだ筈の爆弾が、俺の胸で鳴っている。
「あ、あー、多分俺だわ。サンキュ」
「うん」
それ以上、何も聞かれなかった。俺がクッキーのこと、何にも聞かなかった、お返しとでも思っているのかもしれない。
心臓が痛い。呼吸が苦しい。
部屋に戻って、少し震える手で、開けた。中に何か、が、
入っている。
読みたくなかったけれど、見ないでいることは出来なかった。俺はもう、確信している。これは、あいつからだ。
さあ、覚悟を決めろ。
勢いのままに開けば、予想に反して、それは手紙では、なかった。いいや、手紙、なのだろうか。たった一言。見慣れた文字で、書いてあるそれは、一瞬で視界に飛び込んできた。
脳みそが処理しきれずに、その一言を、何度も何度も、読み返す。想像していた全ての言葉と違うその一言を、理解するのに、しばらく時間がかかった。
そうして、理解して、俺は思わず、笑ってしまう。
なんだよそれ、そんなの、ずるい。いいや、ずるいのは、俺だって同じだ。名前も無い、中身もない、リボンだけをかけた、空っぽの袋。宛名も無い、差出人も無い、たった一言だけの手紙。
そうだな、分からない筈が、無かった。伝わらない筈が、無かった。だって、俺とお前は、ずっと隣で、下らない話を、していた。
「ちょっと出かけてくる!」
走って飛び出す。今すぐに、伝えに行こう。
この胸の爆弾が、俺を急かす。走れ! 今にも爆発して、世界を終わらせそうな、高鳴りよ!
どうしてやろうかと思った。
まさか、バレないとでも、思ったのだろうか。俺に分かるはずが無いと、思ったのだろうか。いいや、確かに、分かる方が、おかしいのかもしれない。けれど、俺には分かる。
パスが通った時に、シュートが決まった時に、目が合った時に、或いは、教室で、下らない話を、している時に。
俺とお前が抱えていたのは、全く同じ、ものではなかったか。お前の、その自慢の目には、見えていなかったとでも、言うつもりだろうか。
いいや、違う。分かっていただろう。俺に分かったように、お前だって、知っていた筈だ。それをこんな、回りくどい手段で、俺に決めさせようというのなら、お前がずるい。
お前は本当に、ずるい男だ。
無視してやったって、よかった。むしろ、その方が簡単だ。名前も無い、中身もない空っぽの袋に、俺は好きな名前をつけることができる。名前をつけないでいることができる。
けれど、俺は案外、みっともない男なのだ。あいつがどう思っているのかはしらないが、俺は、目的のためには、手段を選ばない。大切なものが、両手をあげて飛び込んできたら、みっともなくとも、そのまま掴み取るだろう。
掴み取ってやる。後悔などしない。俺は俺に、恥じることなど一つもないのだ。
しかし、実際、どちらが我が儘だという話だ。こうやって、言葉にされる前に、甘やかしてしまうから、よくない。悟って、理解して、動いてしまう。下らないことばかりを喋る口で、お前は肝心のことを言おうとしないのだ。
そうはいくか、と、思う。
俺だけに決定権を委ねて、終わらせるなど、言語道断だ。お前の抱える感情には、お前が自分で名前をつけろ。俺は俺に、決着をつけるので手一杯なのだから。
暫く考えて、手近な便箋を手にとった。長々と、書いてやるのもにくらしい。そもそも、そう、伝わらないと、思っていることが、腹立たしい。気がつかれないと、思われていることが、腹立たしい。お前が俺を見ていたように、俺だって、お前を見ていたのだと、何故、気がつかない。大馬鹿者。
一言だけ書いた。宛名も差出人も、つけなかった。明日の帰りにでも、直接郵便受けにいれてやろう。別に、他の誰に開けられて、困るようなことは書いていない。あいつだけが、分かればいい。あいつだけが、分かることを、書いた。
さあ、この愚かな戦争に、別れを告げよう。
「お前は、リボンを結ぶのが下手くそだ」
0 notes
Text
犬
照明を落とした会議室は水を打ったようで、ただ肉を打つ鈍い音が響いていた。ビデオカメラに濾され、若干迫力と現実味を欠いた殴打の音が。
とは言え、それは20人ほどの若者を釘付けへするには十分な効果を持つ。四角く配置された古い長机はおろか、彼らが埋まるフェイクレザーの椅子すら、軋みの一つも上げない。もちろん、研修旅行の2日目ということで、集中講義に疲れ果て居眠りをしているわけでもない。白いスクリーンの中の光景に、身じろぎはおろか息すらこらしているのだろう。
映像の中の人物は息も絶え絶え、薄暗い独房の天井からぶら下げられた鎖のおかげで、辛うじて直立の状態を保っている。一時間近く、二人の男から代わる代わる殴られていたのだから当然の話だ――講義用にと青年が手を加えたので、今流れているのは10分ほどの総集編という趣。おかげで先ほどまでは端正だった顔が、次の瞬間には血まみれになっている始末。画面の左端には、ご丁寧にも時間と殴打した回数を示すカウンターまで付いていた。
まるで安っぽいスナッフ・フィルムじゃないか――教授は部屋の隅を見遣った。パイプ椅子に腰掛ける編集者の青年が、視線へ気付くのは早い。あくびをこぼしそうだった表情が引き締まり、すぐさま微笑みに変わる。まるで自らの仕事を誇り、称賛をねだる様に――彼が自らに心酔している事は知っていた。少なくとも、そういう態度を取れるくらいの処世術を心得ている事は。
男達が濡れたコンクリートの床を歩き回るピチャピチャという水音が、場面転換の合図となる。とは言っても、それまで集中的に顔を攻撃していた男が引き下がり、拳を氷の入ったバケツに突っ込んだだけの変化なのだが。傍らで煙草を吸っていたもう一人が、グローブのような手に砂を擦り付ける。
厄災が近付いてきても、捕虜は頭上でひとまとめにされた手首を軽く揺するだけで、逃げようとはしなかった。ひたすら殴られた顔は赤黒く腫れ上がり、虫の蛹を思わせる。血と汗に汚された顔へ、漆黒の髪がべっとり張り付いていた。もう目も禄に見えていないのだろう。
いや、果たしてそうだろうか。何度繰り返し鑑賞しても、この場面は専門家たる教授へ疑問を呈した。
重たげで叩くような足音が正面で止まった瞬間、俯いていた顔がゆっくり持ち上がった。閉じた瞼の針のような隙間から、榛色の瞳が僅かに覗いている。そう、その瞳は、間違いなく目の前の男を映していた。自らを拷問する男の顔を。相手がまるで、取るに足らない存在であるかの如く毅然とした無表情で。
カウンターが121回目の殴打を数えたとき、教授は手にしていたリモコンを弄った。一時停止ボタンは融通が利かず、122回目のフックは無防備な鳩尾を捉え、くの字に折り曲がった体が後ろへ吹っ飛ばされる残像を画面に残す。
「さて、ここまでの映像で気付いたことは、ミズ・ブロディ?」
目を皿のようにして画面へ見入っていた女子生徒が、はっと顔を跳ね上げる。逆光であることを差し引いても、その瞳は溶けた飴玉のように光が滲み、焦点を失っていた。
「ええ、はい……その、爪先立った体勢は、心身への負荷を掛ける意味で効果的だったと思います」
「その通り。それにあの格好は、椅子へ腰掛けた人間を相手にするより殴りやすいからね。ミスター・ロバーツ、執行者については?」
「二人の男性が、一言も対象者に話しかけなかったのが気になりました」
途中から手元へ視線を落としたきり、決して顔を上げようとしなかった男子生徒が、ぼそぼそと答えた。
「笑い者にしたり、罵ったりばかりで……もっと積極的に自白を強要するべきなのでは」
「これまでにも、この……M……」
机上のレジュメをひっくり返したが、該当資料は見あたらない。パイプ椅子から身を乗り出した青年が、さして潜めてもいない声でそっと助け船を出した。
「そう、ヒカル・K・マツモト……私達がMと呼んでいる男性には、ありとあらゆる方法で自白を促した。これまでにも見てきたとおり、ガスバーナーで背中を炙り、脚に冷水を掛け続け――今の映像の中で、彼の足元がおぼづかなかったと言う指摘は誰もしなかったね? とにかく、全ての手段に効果が得られなかった訳だ」
スマートフォンのバイブレーションが、空調の利きが悪い室内の空気を震わせる。小声で云々しながら部屋を出ていく青年を片目で見送り、教授は一際声の調子を高めた。
「つまり今回の目的は、自白ではない。暴力そのものだ。この行為の中で、彼の精神は価値を持たない。肉体は、ただ男達のフラストレーションの捌け口にされるばかり」
フラストレーションの代わりに「マスターベーション」と口走りそうになって、危うく言葉を飲み込んだのは、女性の受講生も多いからだ。5年前なら考えられなかったことだ――黴の生えた理事会の連中も、ようやく象牙の塔の外から出るとまでは言わなくとも、窓から首を突き出す位のことをし始めたのだろう。
「これまで彼は、一流の諜報員、捜査官として、自らのアイデンティティを固めてきた。ここでの扱いも、どれだけ肉体に苦痛を与えられたところで、それは彼にとって自らが価値ある存在であることの証明に他ならなかった。敢えて見せなかったが、この行為が始まる前に、我らはMと同時に捕縛された女性Cの事を彼に通告してある――彼女が全ての情報を吐いたので、君はもう用済みだ、とね」
「それは餌としての偽情報でしょうか、それとも本当にCは自白していたのですか」
「いや、Cもまだこの時点では黙秘している。Mに披露した情報は、ケース・オフィサーから仕入れた最新のものだ」
ようやく対峙する勇気を振り絞れたのだろう。ミスター・ロバーツは、そろそろと顔を持ち上げて、しんねりとした上目を作った。
「それにしても、彼への暴力は行き過ぎだと思いますが」
「身長180センチ、体重82キロもある屈強な25歳の男性に対してかね? 彼は深窓の令嬢ではない、我々の情報を抜き取ろうとした手練れの諜報員だぞ」
浮かんだ苦笑いを噛み殺し、教授は首を振った。
「まあ、衛生状態が悪いから、目方はもう少し減っているかもしれんがね。さあ、後半を流すから、Mと執行者、両方に注目するように」
ぶれた状態で制止していた体が思い切り後ろへふれ、鎖がめいいっぱいまで伸びきる。黄色く濁った胃液を床へ吐き散らす捕虜の姿を見て、男の一人が呆れ半分、はしゃぎ半分の声を上げる。「汚ぇなあ、しょんべんが上がってきてるんじゃないのかよ」
今年は受講者を20人程に絞った。抽選だったとは言え、単位取得が簡単でないことは周知の事実なので、応募してきた時点で彼らは自分を精鋭と見なしているのだろう。
それが、どうだ。ある者は暴力に魅せられて頬を火照らせ、ある者は今になって怖じ気付き、正義感ぶることで心の平穏を保とうとする。
経験していないとはこう言うことか。教授は今更ながら心中で嘆息を漏らした。ここのところ、現場慣れした小生意気な下士官向けの講義を受け持つことが多かったので、すっかり自らの感覚が鈍っていた。
つまり、生徒が悪いのでは一切ない。彼らが血の臭いを知らないのは、当然のことなのだ。人を殴ったとき、どれだけ拳が疼くのかを教えるのは、自らの仕事に他ならない。
手垢にまみれていないだけ、吸収も早いことだろう。余計なことを考えず、素直に。ドアを開けて入ってきたあの青年の如く。
足音��なく、すっと影のように近付いてきた青年は、僅かに高い位置へある教授の耳に小さな声で囁いた。
「例のマウンテンバイク、確保できたようです」
針を刺されたように、倦んでいた心が普段通りの大きさへ萎む。ほうっと息をつき、教授は頷いた。
「助かったよ。すまないな」
「いいや、この程度の事なら喜んで」
息子が12歳を迎えるまで、あと半月を切っている。祝いに欲しがるモデルは何でも非常に人気があるそうで、どれだけ自転車屋に掛け合っても首を振られるばかり。
日頃はあまり構ってやれないからこそ、約束を違えるような真似はしたくない。妻と二人ほとほと弱り果てていたとき、手を挙げたのが他ならぬ目の前の青年だった。何でも知人の趣味がロードバイクだとかで、さんざん拝み倒して新古品を探させたらしい。
誕生パーティーまでの猶予が一ヶ月を切った頃から、教授は青年へ厳しく言い渡していた。見つかり次第、どんな状況でもすぐに知らせてくれと。夜中でも、仕事の最中でも。
「奥様に連絡しておきましょうか。また頭痛でお悩みじゃなきゃいいんですけど」
「この季節はいつでも低気圧だ何だとごねているさ。悪いが頼むよ」
ちらつく画像を前にし、青年はまるで自らのプレゼントを手に入れたかの如くにっこりしてみせる。再びパイプ椅子に腰を下ろし、スマートフォンを弄くっている顔は真剣そのものだ。
ふと頭に浮かんだのは、彼が妻と寝ているか否かという、これまでも何度か考えたことのある想像だった。確かに毎週の如く彼を家へ連れ帰り、彼女もこの才気あふれる若者を気に入っている風ではあるが。
まさか、あり得ない。ファンタジーとしてならば面白いかもしれないが。
そう考えているうちは、大丈夫だろう。事実がどうであれ。
「こんな拷問を、そうだな、2ヶ月程続けた。自白を強要する真似は一切せず、ただ肉の人形の用に弄び、心身を疲弊させる事に集中した。詳細はレジュメの3ページに譲るとして……背中に水を皮下注射か。これは以前にも言ったが、対象が仰向けで寝る場合、主に有効だ。事前に確認するように」
紙を捲る音が一通り収まったのを確認してから、教授は手の中のリモコンを軽く振った。
「前回も話したが、囚人が陥りやすいクワシオルコルなど低タンパク血症の判断基準は脚の浮腫だ。だが今回は捕獲時に右靱帯を損傷し中足骨を剥離骨折したこと、何度も逃亡を試みた事から脚への拘束及び重点的に攻撃を加えたため、目視では少し判断が難しいな。そういうときは、圧痕の確認を……太ももを掴んで指の型が数秒間戻らなければ栄養失調だ」
似たような仕置きの続く数分が早送りされ、席のそこかしこから詰まったような息が吐き出される。一度飛ばした写真まで巻き戻せば、その呼吸は再びくびられたかのように止まった。
「さて、意識が混濁しかけた頃を見計らい、我々は彼を移送した。本国の収容所から、国境を越えてこの街に。そして抵抗のできない肉体を、一見無造作に投棄したんだ。汚い、掃き溜めに……えー、この国の言葉では何と?」
「『ゴミ捨て場』」
「そう、『ゴミ捨て場』に」
青年の囁きを、生徒達は耳にしていたはずだ。それ以外で満ちた沈黙を阻害するのは、プロジェクターの立てる微かなモーター音だけだった。
彼らの本国にもありふれた集合住宅へ――もっとも、今画面に映っている場所の方がもう少し設備は整っていたが。距離で言えば100キロも離れていないのに、こんな所からも、旧東側と西側の違いは如実に現れるのだ――よくある、ゴミ捨て場だった。三方を囲うのはコンクリート製の壁。腰程の高さへ積んだゴミ袋の山へ、野生動物避けの緑色をしたネットを掛けてあるような。
その身体は、野菜の切りくずやタンポンが詰められているのだろうゴミ袋達の上に打ち捨てられていた。横向きの姿勢でぐんにゃり弛緩しきっていたが、最後の意志で内臓を守ろうとした努力が窺える。腕を腹の前で交差し、身を縮める姿は胎児を思わせた。ユーラシアンらしい照り卵を塗ったパイ生地を思わせる肌の色味は、焚かれたフラッシュのせいで消し飛ばされる。
絡みもつれた髪の向こうで、血管が透けて見えるほど薄い瞼はぴたりと閉じられていた。一見すると死んでいるかのように見える。
「この国が我が祖国と国交を正常化したのは?」
「2002年です」
「よろしい、ミズ・グッドバー。だがミハイル・ゴルバチョフが衛星国の解放を宣言する以前から、両国間で非公式な交流は続けられていた。主に経済面でだが。ところで、Mがいた地点からほど近くにあるタイユロール記念病院は、あの鋼鉄商フォミン一族、リンゼイ・フォミン氏の働きかけで設立された、一種の『前哨基地』であることは、ごく一部のものだけが知る事実だ。彼は我が校にも多額の寄付を行っているのだから、ゆめゆめ備品を粗末に扱わぬよう」
小さな笑いが遠慮がちに湧いた矢先、突如画面が明るくなる。生徒達同様、教授も満ちる眩しさに目を細めた。
「Mは近所の通報を受け、この病院に担ぎ込まれた……カルテにはそう記載されている。もちろん、事実は違う。全ては我々の手配だ。彼は現在に至るまでの3ヶ月、個室で手厚く看護を受けている。最新の医療、滋養のある食事、尽くしてくれる看護士……もちろん彼は、自らの正体を明かしてはいないし、完全に心を開いてはいない。だが、病院の上にいる人間の存在には気付いていないようだ」
「気付いていながら、我々を欺いている可能性は?」
「限りなく低いだろう。外部との接触��行われていない……行える状態ではない���、とある看護士にはかなり心を許し、私的な話も幾らか打ち明けたようだ」
後は病室へ取り付けた監視用のカメラが、全てを語ってくれる。ベッドへ渡したテーブルへ屈み込むようにしてステーキをがっつく姿――健康状態はすっかり回復し、かつて教授がミラーガラス越しに眺めた時と殆ど変わらぬ軒昂さを取り戻していた。
両脚にはめられたギプスをものともせず、点滴の管を抜くというおいたをしてリハビリに励む姿――パジャマを脱いだ広い背中は、拷問の痕の他に、訓練や実践的な格闘で培われたしなやかな筋肉で覆われている。
車椅子を押す看護士を振り返り、微笑み掛ける姿――彼女は決して美人ではないが、がっしりした体つきやきいきびした物言いは母性を感じさせるものだった。だからこそ一流諜報員をして、生き別れの恋人やアルコール中毒であった父親の話まで、自らの思いの丈を洗いざらい彼女に白状せしめたのだろう。「彼女を本国へスカウトしましょうよ」報告書を読んだ青年が軽口を叩いていたのを思い出す。「看護士の給料って安いんでしょう? 今なら簡単に引き抜けますよ」
「今から10分ほど、この三ヶ月の記録からの抜粋を流す。その後はここを出て、西棟502号室前に移動を――Mが現在入院する病室の前だ。持ち物は筆記具だけでいい」
暗がりの中に戸惑いが広がる様子は、まるで目に見えるかのようだった。敢えて無視し、部屋を出る。
追いかけてきた青年は、ドアが完全に閉まりきる前から既にくすくす笑いで肩を震わせていた。
「ヘンリー・ロバーツの顔を見ましたか。今にも顎が落ちそうでしたよ」
「当然の話だろう」
煤けたような色のLEDライトは、細長く人気のない廊下を最低限カバーし、それ以上贅沢を望むのは許さないと言わんばかり。それでも闇に慣れた眼球の奥をじんじんと痺れさせる。大きく息をつき、教授は何度も目を瞬かせた。
「彼らは現場に出たこともなければ、百戦錬磨の諜報員を尋問したこともない。何不自由なく育った二十歳だ」
「そんなもんですかね」
ひんやりした白塗りの壁へ背中を押しつけ、青年はきらりと目を輝かせた。
「俺は彼ら位の頃、チェチェン人と一緒にウラル山脈へこもって、ロシアのくそったれ共を片っ端から廃鉱山の立坑に放り込んでましたよ」
「『育ちゆけよ、地に満ちて』だ。平和は有り難いことさ」
スマートフォンの振動は無視するつもりだったが、結局ポケットへ手を突っ込み、液晶をタップする。現れたテキストをまじまじと見つめた後、教授は紳士的に視線を逸らしていた青年へ向き直った。
「君のところにもメッセージが行っていると思うが、妻が改めて礼を言ってくれと」
「お安い御用ですよ」
「それと、ああ、その自転車は包装されているのか?」
「ほうそうですか」
最初繰り返したとき、彼は自らが口にした言葉の意味を飲み込めていなかったに違いない。日に焼けた精悍な顔が、途端にぽかんとした間抜け面に変わる。奨学金を得てどれだけ懸命に勉強しても、この表情を取り繕う方法は、ついぞ学べなかったらしい。普段の明朗な口振りが嘘のように、言葉付きは歯切れが悪い。
「……ええっと、多分フェデックスか何かで来ると思うので、ダンボールか緩衝材にくるんであるんじゃないでしょうか……あいつは慣れてるから、配送中に壊れるような送り方は絶対しませんよ」
「いや、そうじゃないんだ。誕生日の贈り物だから、可愛らしい包み紙をこちらのほうで用意すべきかということで」
「ああ、なるほど……」
何とか混乱から立ち直った口元に、決まり悪げなはにかみが浮かぶ。
「しかし……先生の息子さんが羨ましい。俺の親父もマツモトの父親とそうそう変わらないろくでなしでしたから」
僅かに赤らんだ顔を俯かせて頭を掻き、ぽつりと呟いた言葉に普段の芝居掛かった気負いは見られない。鈍い輝きを帯びた瞳が、おもねるような上目遣いを見せた。
「先生のような父親がいれば、きっと世界がとてつもなく安全で、素晴らしい物のように見えるでしょうね」
皮肉を言われているのか、と一瞬思ったが、どうやら違うらしい。
息子とはここ数週間顔を合わせていなかった。打ち込んでいるサッカーの試合や学校の発表会に来て欲しいと何度もせがまれているが、積み重なる仕事は叶えてやる機会を許してはくれない。
いや、本当に自らは、努力を重ねたか? 確たる意志を以て、向き合う努力を続けただろうか。
自らが妻子を愛していると、教授は知っている。彼は己のことを分析し、律していた。自らが家庭向きの人間ではないことを理解しなから、家族を崩壊させないだけのツボを的確に押さえている事実へ、怒りの叫びを上げない程度には。
目の前の男は、まだ期待の籠もった眼差しを向け続けている。一体何を寄越せば良いと言うのだ。今度こそ苦い笑いを隠しもせず、教授は再びドアノブに手を伸ばした。
着慣れない白衣姿に忍び笑いが漏れるのへ、わざとらしいしかめっ面を作って見せる。
「これから先、私は傍観者だ。今回の実習を主導するのは彼だから」
「皆の良い兄貴分」を気取っている青年が、芝居掛かった仕草のお辞儀をしてみせる。生徒達と同じように拍手を与え、教授は頷いた。
「私はいないものとして考えるように……皆、彼の指示に従うこと」
「指示なんて仰々しい物は特にない、みんな気楽にしてくれ」
他の患者も含め人払いを済ませた廊下へ響かぬよう、普段よりは少し落とした声が、それでも軽やかに耳を打った。
「俺が定める禁止事項は一つだけ――禁止事項だ。これからここで君たちがやった事は、全てが許される。例え法に反することでも」
わざとらしく強い物言いに、顔を見合わせる若者達の姿は、これから飛ぶ練習を始める雛鳥そのものだった。彼らをぐるりと見回す青年の胸は、愉悦でぱんぱんに膨れ上がっているに違いない。大袈裟な身振りで手にしたファイルを振りながら、むずつかせる唇はどうだろう。心地よく浸る鷹揚さが今にも溢れ出し、顔を満面の笑みに変えてしまいそうだった。
「何故ならこれから君達が会う人間は、その法律の上では存在しない人間なんだから……寧ろ俺は、君達に積極的にこのショーへ参加して欲しいと思ってる。それじゃあ、始めようか」
最後にちらりと青年が寄越した眼差しへ、教授はもう一度頷いて見せた。ここまでは及第点。生徒達は不安を抱えつつも、好奇心を隠せないでいる。
ぞろぞろと向かった先、502号室の扉は閉じられ、物音一つしない。ちょうど昼食が終わったばかりだから、看護士から借りた本でも読みながら憩っているのだろう――日報はルーティンと化していたが、それでも教授は欠かさず目を通し続けていた。
生徒達は皆息を詰め、これから始まる出し物を待ちかまえている。青年は最後にもう一度彼らを振り向き、シッ、と人差し指を口元に当てた。ぴいん、と緊張が音を立てそうなほど張り詰められたのは、世事に疎い学生達も気がついたからに違いない。目の前の男の目尻から、普段刻まれている笑い皺がすっかり失せていると。
分厚い引き戸が勢いよく開かれる。自らの姿を、病室の中の人間が2秒以上見つめたと確認してから、青年はあくまで穏やかな、だがよく聞こえる声で問いかけた。
「あんた、ここで何をしているんだ」
何度も尋問を起こった青年と違い、教授がヒカル・K・マツモトを何の遮蔽物もなくこの目で見たのは、今日が初めての事だった。
教授が抱いた印象は、初見時と同じ――よく飼い慣らされた犬だ。はしっこく動いて辺りを確認したかと思えば、射るように獲物を見据える切れ長で黒目がちの瞳。すっと通った細長い���筋。桜色の形良い唇はいつでも引き結ばれ、自らが慎重に選んだ言葉のみ、舌先に乗せる機会を待っているかのよう。
見れば見るほど、犬に思えてくる。教授がまだ作戦本部にいた頃、基地の中を警邏していたシェパード。栄養状態が回復したせいか、艶を取り戻した石炭色の髪までそっくりだった。もっともあの軍用犬達はベッドと車椅子を往復していなかったので、髪に寝癖を付けたりなんかしていなかったが。
犬は自らへしっぽを振り、手綱を握っている時にのみ役に立つ。牙を剥いたら射殺せねばならない――どれだけ気に入っていたとしても。教授は心底、その摂理を嘆いた。
自らを散々痛めつけた男の顔を、一瞬にして思い出したのだろう。Mは驚愕に目を見開いたものの、次の瞬間車椅子の中で身構えた。
「おまえは…!」
「何をしているかと聞いているんだ、マツモト。ひなたぼっこか?」
もしもある程度予測できていた事態ならば、この敏腕諜報員のことだ。ベッド脇にあるナイトスタンドから取り上げた花瓶を、敵の頭に叩きつける位の事をしたかもしれない。だが不幸にも、青年の身のこなしは機敏だった。パジャマの襟首を掴みざま、まだ衰弱から完全に抜けきっていない体を床に引き倒す。
「どうやら、少しは健康も回復したようだな」
自らの足元にくずおれる姿を莞爾と見下ろし、青年は手にしていたファイルを広げた。
「脚はどうだ」
「おかげさまで」
ギプスをはめた脚をかばいながら、Mは小さく、はっきりとした声で答えた。
「どうやってここを見つけた」
「見つけたんじゃない。最初から知っていたんだ。ここへお前を入院させたのは俺たちなんだから」
一瞬見開かれた目は、すぐさま平静を取り戻す。膝の上から滑り落ちたガルシア・マルケスの短編集を押し退けるようにして床へ手を滑らせ、首を振る。
「逐一監視していた訳か」
「ああ、その様子だと、この病院そのものが俺たちの手中にあったとは、気付いていなかったらしいな」
背後を振り返り、青年は中を覗き込む生徒達に向かって繰り返した。
「重要な点だ。この囚人は、自分が未だ捕らわれの身だという事を知らなかったそうだ」
清潔な縞模様のパジャマの中で、背中が緩やかな湾曲を描く。顔を持ち上げ、Mは生徒達をまっすぐ見つめた。
またこの目だ。出来る限り人だかりへ紛れながらも、教授はその眼差しから意識を逸らすことだけは出来なかった。有利な手札など何一つ持っていないにも関わらず、決して失われない榛色の光。確かにその瞳は森の奥の泉のように静まり返り、暗い憂いを帯びている。あらかじめ悲しみで心を満たし、もうそれ以上の感情を注げなくしているかのように。
ねめ回している青年も、Mのこの堅固さならよく理解しているだろう――何せ数ヶ月前、その頑強な鎧を叩き壊そうと、手ずから車のバッテリーに繋いだコードを彼の足に接触させていたのだから。
もはや今、鸚鵡のように「口を割れ」と繰り返す段階は過ぎ去っていた。ファイルの中から写真の束を取り出して二、三枚繰り、眉根を寄せる。
「本当はもう少し早く面会するつもりだったんだが、待たせて悪かった。あんたがここに来て、確か3ヶ月だったな。救助は来なかったようだ」
「ここの電話が交換式になってる理由がようやく分かったよ。看護士に渡した手紙も握りつぶされていた訳だな」
「気付いていたのに、何もしなかったのか」
「うちの組織は、簡単にとかげの尻尾を切る」
さも沈痛なそぶりで、Mは目を伏せた。
「大義を為すためなら、末端の諜報員など簡単に見捨てるし、皆それを承知で働いている」
投げ出されていた手が、そろそろと左足のギプスの方へ這っていく。そこへ削って尖らせたスプーンを隠してある事は、監視カメラで確認していた。知っていたからこそ、昨晩のうちに点滴へ鎮静剤を混ぜ、眠っているうちに取り上げてしまう事はたやすかった。
ほつれかけたガーゼに先細りの指先が触れるより早く、青年は動いた。
「確かに、お前の所属する組織は、仲間がどんな目に遭おうと全く気に掛けないらしいな」
手にしていた写真を、傷が目立つビニール張りの床へ、一枚、二枚と散らす。Mが身を凍り付かせたのは、まだ僅かに充血を残したままの目でも、その被写体が誰かすぐ知ることが出来たからだろう。
「例え女であったとしても、我が国の情報局が手加減など一切しないことは熟知しているだろうに」
最初の数枚においては、CもまだMが知る頃の容姿を保っていた。枚数が増えるにつれ、コマの荒いアニメーションの如く、美しい女は徐々に人間の尊厳を奪われていく――撮影日時は、写真の右端に焼き付けられていた。
Mがされていたのと同じくらい容赦なく殴られ、糞尿や血溜まりの中で倒れ伏す姿。覚醒剤で朦朧としながら複数の男達に辱められる。時には薬を打たれることもなく、苦痛と恥辱の叫びを上げている歪んだ顔を大写しにしたものもある。分かるのは、施されるいたぶりに終わりがなく、彼女は時を経るごとにやせ細っていくということだ。
「あんたがここで骨休めをしている間、キャシー・ファイクは毎日尋問に引き出されていた。健気に耐えたよ、全く驚嘆すべき話だ。そういう意味では、君たちの組織は実に優秀だと言わざるを得ない」
次々と舞い落ちてくる写真の一枚を拾い上げ、Mは食い入るように見つめていた。養生生活でただでも青白くなった横顔が、俯いて影になることで死人のような灰色に変わる。
「彼女は最終的に情報を白状したが……恐らく苦痛から解放して欲しかったのだろう。この三ヶ月で随分衰弱してしまったから」
Mは自らの持てる技術の全てを駆使し、動揺を押さえ込もうとしていた。その努力は殆ど成功している。ここだけは仄かな血色を上らせた、薄く柔い唇を震わせる以外は。
その様をつくづくと見下ろしながら、青年はどこまでも静かな口調で言った。
「もう一度聞くが、あんた、ここで何をしていた?」
再び太ももへ伸ばされた左手を、踏みつけにする足の動きは機敏だった。固い靴底で手の甲を踏みにじられ、Mはぐっと奥歯を噛みしめ、相手を睨み上げた。教授が初めて目にする、燃えたぎるような憎悪の色を視線に織り込みながら。その頬は病的なほど紅潮し、まるで年端も行かない子供を思わせる。
そして相手がたかぶるほど、青年は感情を鎮静化させていくのだ。全ての写真を手放した後、彼は左腕の時計を確認し、それから壁に掛かっていた丸い時計にも目を走らせた。
「数日前、Cはこの病院に運び込まれた。お偉方は頑なでね。まだ彼女が情報を隠していると思っているようだ」
「これ以上、彼女に危害を加えるな」
遂にMは口を開き、喉の奥から絞り出すようにして声を放った。
「情報ならば、僕が話す」
「あんたにそんな役割は求めていない」
眉一つ動かすことなく、青年は言葉を遮った。
「あんたは3ヶ月前に、その言葉を口にすべきだった。もう遅い」
唇を噛むMから目を離さないまま、部屋の前の生徒達に手だけの合図が送られる。今やすっかりその場の空気に飲まれ、彼らはおたおたと足を動かすのが精一杯。一番賢い生徒ですら、質問を寄越そうとはしなかった。
「彼女に会わせてやろう。もしも君が自分の足でそこにたどり着けるのならば。俺の上官が出した指示はこうだ。この廊下の突き当たりにある手術室にCを運び込み、麻酔を掛ける。5分毎に、彼女の体の一部は切り取られなければならない。まずは右腕、次に右脚、四肢が終わったら目を抉り、鼻を削いで口を縫い合わせ、喉を潰す。耳を切りとったら次は内臓だ……まあ、この順番は多少前後するかもしれない。医者の気まぐと彼女の体調次第で」
Mはそれ以上、抗弁や懇願を口にしようとはしなかった。ただ歯を食いしばり、黙ってゲームのルールに耳を澄ましている。敵の陣地で戦うしか、今は方法がないのだと、聡い彼は理解しているのだろう。
「もしも君が部屋までたどり着けば、その時点で手術を終了させても良いと許可を貰ってる。彼女の美しい肉体をどれだけ守れるかは、君の努力に掛かっているというわけだ」
足を離して解放しざま、青年はすっと身を傍らに引いた。
「予定じゃ、もうカウントダウンは始まっている。そろそろ医者も、彼女の右腕に局部麻酔を打っているんじゃないか?」
青年が言い終わらないうちに、Mは床に投げ出されていた腕へ力を込めた。
殆ど完治しているはずの脚はしかし、過剰なギプスと長い車椅子生活のせいですっかり萎えていた。壁に手をつき、立ち上がろうとする奮闘が繰り返される。それだけの動作で、全身に脂汗が滲み、細かい震えが走っていた。
壁紙に爪を立てて縋り付き、何とか前かがみの姿勢になれたとき、青年はその肩に手を掛けた。力任せに押され、受け身を取ることも叶わなかったらしい。無様に尻餅をつき、Mは顔を歪めた。
「さあ」
人を突き飛ばした手で部屋の外に並ぶ顔を招き、青年はもぞつくMを顎でしゃくる。
「君達の出番だ」
部屋の中へ足を踏み入れようとするものは、誰もいなかった。
その後3度か4度、起き上がっては突き飛ばされるが繰り返される。結局Mは、それ以上立ち上がろうとする事を諦めた。歯を食いしばって頭を垂れ、四つん這いになる。出来る限り避けようとはしているのだろう。だが一歩手を前へ進めるたび、床へ広がったままの写真が掌にくっついては剥がれるを繰り返す。汗を掻いた手の下で、印画紙は皺を作り、折れ曲がった。
「このままだと、あっさり部屋にたどり着くぞ」
薄いネルの布越しに尻を蹴飛ばされ、何度かその場へ蛙のように潰れながらも、Mは部屋の外に出た。生徒達は彼の行く手を阻まない。かといって、手を貸したり「こんな事はよくない」と口にするものもいなかったが。
細く長い廊下は一直線で、突き当たりにある手術室までの距離は50メートル程。その気になれば10分も掛からない距離だ。
何とも奇妙な光景が繰り広げられた。一人の男が、黙々と床を這い続ける。その後ろを、20人近い若者が一定の距離を開けてぞろぞろと付いていく。誰も質問をするものはいなかった。ノートに記録を取るものもいなかった。
少し距離を開けたところから、教授は様子を眺めていた。次に起こる事を待ちながら――どういう形にせよ、何かが起こる。これまでの経験から、教授は理解していた。
道のりの半分程まで進んだ頃、青年はそれまでMを見張っていた視線を後ろへ振り向けた。肩が上下するほど大きな息を付き、ねだる様な表情で微笑んで見せる。
「セルゲイ、ラマー、手を貸してくれ。奴をスタートまで引き戻すんだ」
学生達の中でも一際体格の良い二人の男子生徒は、お互いの顔を見合わせた。その口元は緊張で引きつり、目ははっきりと怯えの色に染まっている。
「心配しなくてもいい。さっきも話したが、ここでは何もかもが許される……ぐずぐずするな、単位をやらないぞ」
最後の一言が利いたのかは分からないが、二人はのそのそと中から歩み出てきた。他の学生が顔に浮かべるのは非難であり、同情であり、それでも決して手を出すことはおろか、口を開こうとすらしないのだ。
話を聞いていたMは、必死で手足の動きを早めていた。どんどんと開き始める距離に、青年が再び促せば、結局男子生徒は小走りで後を追う。一人が腕を掴んだとき、Mはまるで弾かれたかのように顔を上げた。その表情は、自らを捕まえた男と同じくらい、固く強張っている。
「頼む」
掠れた声に混ざるのは、間違いなく懇願だった。小さな声は、静寂に満ちた廊下をはっきりと貫き通る。
「頼むから」
「ラマー」
それはしかし、力強い指導者の声にあっけなくかき消されるものだった。意を決した顔で、二人はMの腕を掴み直し、背後へと引きずり始めた。
Mの抵抗は激しかった。出来る限り身を捩り、ギプスのはまった脚を蠢かす。たまたま、固められたグラスファイバーが臑に当たったか、爪が腕を引っ掻いたのだろう。かっと眦をつり上げたセルゲイが、平手でMの頭を叩いた。あっ、と後悔の顔が浮かんだのもつかの間、拘束をふりほどいたMは再び手術室を目指そうと膝を突く。追いかけたラマーに、明確な抑止の気持ちがあったのか、それともただ単に魔が差したのかは分からない。だがギプスを蹴り付ける彼の足は、決して生ぬるい力加減のものではなかった。
その場へ横倒しになり、呻きを上げる敵対性人種を、二人の男子生徒はしばらくの間見つめていた。汗みずくで、時折せわしなく目配せを交わしあっている。やがてどちらともなく、再び仕事へ取りかかろうとしたとき、その足取りは最初と比べて随分とスムーズなものになっていた。
病室の入り口まで連れ戻され、身を丸めるMに、青年がしずしずと歩み寄る。腕時計をこれ見よがしに掲げながら放つ言葉は、あくまでも淡々としたものだった。
「今、キャシーは右腕を失った」
Mは全身を硬直させ、そして弛緩させた。何も語らず、目を伏せたまま、また一からやり直そうと努力を続ける。
不屈の精神。だがそれは青年を面白がらせる役にしか立たなかった。
同じような事が何度も繰り返されるうち、ただの背景でしかなかった生徒達に動きが見え始めた。
最初のうちは、一番に手助けを求められた男子生徒達がちょっかいをかける程度だった。足を掴んだり、行く手を塞いだり。ある程度進めばまた病室まで引きずっていく。そのうち連れ戻す役割に、数人が関わるようになった。そうなると、全員が共犯者になるまで時間が掛からない。
やがて、誰かが声を上げた。
「このスパイ」
つられて、一人の女子生徒がMを指さした。
「この男は、私たちの国を滅ぼそうとしているのよ」
「悪魔、けだもの!」
糾弾は、ほとんど悲鳴に近い音程で迸った。
「私の叔母は、戦争中こいつの国の人間に犯されて殺された! まだたった12歳だったのに!」
生徒達の目の焦点が絞られる。
病室へ駆け込んだ一人が戻ってきたとき手にしていたのは、ピンク色のコスモスを差した重たげな花瓶だった。花を引き抜くと、その白く分厚い瀬戸物を、Mの頭上で逆さまにする。見る見るうちに汚れた冷水が髪を濡らし、パジャマをぐっしょり背中へと張り付かせる様へ、さすがに一同が息を飲む。
さて、どうなることやら。教授は一歩離れた場所から、その光景を見守っていた。
幸い、杞憂は杞憂のままで終わる。すぐさま、どっと歓声が弾けたからだ。笑いは伝染する。誰か一人が声を発すれば、皆が真似をする。免罪符を手に入れたと思い込む。
そうなれば、後は野蛮で未熟な度胸試しの世界になった。
殴る、蹴るは当たり前に行われた。直接手を出さない者も、もう目を逸らしたり、及び腰になる必要はない。鋏がパジャマを切り裂き、無造作に掴まれた髪を黒い束へと変えていく様子を、炯々と目を光らせて眺めていられるのだ。
「まあ、素敵な格好ですこと」
また嘲笑がさざ波のように広がる。その発作が収まる隙を縫って、時折腕時計を見つめたままの青年が冷静に告げる。「今、左脚が失われた」
Mは殆ど抵抗しなかった。噛みしめ過ぎて破れた唇から血を流し、目尻に玉の涙を浮かべながら。彼は利口だから、既に気付いていたのだろう。まさぐったギプスに頼みの暗器がない事にも、Cの命が彼らの機嫌一つで簡単に失われるという事も――その経験と知識と理性により、がんじがらめにされた思考が辿り着く結論は、一つしかない――手術室を目指せ。
まだ、この男は意志を折ってはいない。作戦本部へ忍び込もうとして捕らえられた時と、何一つ変わっていない。教授は顎を撫で、青年を見遣った。彼はこのまま、稚拙な狂乱に全てを任せるつもりなのだろうか。
罵りはやし立てる声はますます激しくなった。上擦った声の多重奏は狭い廊下を跳ね回っては、甲高く不気味な音程へと姿を変え戻ってくる。
短くなった髪を手綱のように掴まれ、顎を逸らされるうち、呼吸が続かなくなったのだろう。強い拒絶の仕草で、Mの首が振られる。彼の背中へ馬乗りになり、尻を叩いていた女子学生達が、体勢を崩して小さく悲鳴を上げた。
「このクズに思い知らせてやれ」
仕置きとばかりに脇腹へ爪先を蹴込んだ男子生徒が、罵声をとどろかせた。
「自分の身分を思い知らせろ、大声を上げて泣かせてやれ」
津波のような足音が、身を硬直させる囚人に殺到する。その体躯を高々と掲げ上げた一人が、青年に向かって声を張り上げた。
「便所はどこですか」
指で示しながら、青年は口を開いた。
「今、鼻が削ぎ落とされた」
天井すれすれの位置まで持ち上げられた瞬間、全身に張り巡らされた筋肉の緊張と抵抗が、ふっと抜ける。力を無くした四肢は生徒達の興奮の波に合わせてぶらぶらと揺れるが、その事実に気付いたのは教授と、恐らく青年しかいないようだった。
びしょ濡れで、破れた服を痣だらけで、見るも惨めな存在。仰向けのまま、蛍光灯の白々とした光に全身を晒し、その輪郭は柔らかくぼやけて見えた。逸らされた喉元が震え、虚ろな目はもう、ここではないどこかをさまよってる――あるいは閉じこもったのだろうか?
一つの固い意志で身を満たす人間は、荘厳で、純化される。まるで死のように――教授が想像したのは、『ハムレット』の終幕で、栄光を授けられ、兵達に運び出されるデンマーク王子の亡骸だった。
実際のところ、彼は気高い王子ではなく、物語がここで終わる訳でもないのだが。
男子トイレから上がるはしゃいだ声が熱を帯び始めた頃、スラックスのポケットでスマートフォンが振動する。発信者を確認した教授は、一度深呼吸をし、それから妻の名前を呼んだ。
「どうしたんだい、お義父さんの容態が変わった?」
「それは大丈夫」
妻の声は相変わらず、よく着こなされた毛糸のセーターのように柔らかで、温かかった。特に差し向かいで話をしていない時、その傾向は顕著になる。
「あのね、自転車の事なんだけれど、いつぐらいに着くのかしら」
スピーカーを手で押さえながら、教授は壁に寄りかかってスマートフォンを弄っていた青年に向かって叫んだ。
「君の友達は、マウンテンバイクの到着日時を指定したって言っていたか」
「いえ」
「もしもし、多分来週の頭くらいには配送されると思うよ」
「困ったわ、来週は婦人会とか読書会とか、家を空けるのよ」
「私がいるから受け取っておく、心配しないでいい。何なら再配達して貰えば良いし」
「そうね、サプライズがばれなければ」
「子供達は元気にしてるかい」
「変わらずよ。来週の休暇で、貴方とサッカーの試合を観に行くのを楽しみにしてる」
「そうだった。君はゆっくり骨休めをするといいよ……そういえば、さっきの包装の事だけれど、わざわざ紙で包まなくても、ハンドルにリボンでも付けておけばいいんじゃないかな」
「でも、もうさっき玩具屋で包装紙を買っちゃったのよ!」
「なら、それで箱を包んで……誕生日まで隠しておけるところは? クローゼットには入らないか」
「今物置を片づけてるんだけど、貴方の荷物には手を付けられないから、帰ったら見てくれる?」
「分かった」
「そっちで無理をしないでね……ねえ、今どこにいるの? 人の悲鳴が聞こえたわ」
「生徒達が騒いでるんだよ。皆研修旅行ではしゃいでるから……明日は一日、勉強を休んで遊園地だし」
「貴方も一緒になって羽目を外さないで、彼がお目付け役で付いていってくれて一安心だわ……」
「みんないい子にしてるさ。もう行かないと。愛してるよ、土産を買って帰るからね」
「私も愛してるわ、貴方」
通話を終えたとき、また廊下の向こうで青年がニヤニヤ笑いを浮かべているものかと思っていたが――既に彼は、職務に戻っていた。
頭から便器へ突っ込まれたか、小便でも掛けられたか、連れ戻されたMは床へぐったり横たわり、激しく噎せ続けていた。昼に食べた病院食は既に吐き出したのか、今彼が口から絶え間なく溢れさせているのは黄色っぽい胃液だけだった。床の上をじわじわと広がるすえた臭いの液体に、横顔や髪がべったりと汚される。
「うわ、汚い」
「こいつ、下からも漏らしてるぞ」
自らがしでかした行為の結果であるにも関わらず、心底嫌悪に満ちた声がそこかしこから上がる。
「早く動けよ」
どれだけ蔑みの言葉を投げつけられ、汚れた靴で蹴られようとも、もうMはその場に横たわったきり決して動こうとしなかった。頑なに閉じる事で薄い瞼と長い睫を震わせ、力の抜けきった肉体を冷たい床へと投げ出している。
糸の切れた操り人形のようなMの元へ、青年が近付いたのはそのときのことだった。枕元にしゃがみ込み、指先でこつこつと腕時計の文字盤を叩いてみせる。
「あんたはもう、神に身を委ねるつもりなんだな」
噤まれた口などお構いなしに、話は続けられる。まるで眠りに落ちようとしている息子へ、優しく語り掛ける母のように。
「彼女はもう、手足もなく、目も見えず耳も聞こえない、今頃舌も切り取られただろう……生きる屍だ。これ以上、彼女を生かすのはあまりにも残酷過ぎる……だからこのまま、手術が進み、彼女の肉体が耐えられなくなり、天に召されるのを待とうとしているんだな」
Mは是とも否とも答えなかい。ただ微かに顔を背け、眉間にきつく皺を寄せたのが肯定の証だった。
「俺は手術室に連絡を入れた。手術を中断するようにと。これでもう、終わりだ。彼女は念入りに手当されて、生かされるだろう。彼女は強い。生き続ければ、いつかはあんたに会えると、自分の存在があんたを生かし続けると信じているからだ。例え病もうとも、健やかであろうとも……彼女はあんたを待っていると、俺は思う」
Mの唇がゆっくりと開き、それから固まる。何かを、言おうと思ったのだろう。まるで痙攣を起こしたように顎ががくがくと震え、小粒なエナメル質がカチカチと音を立てる。今にも舌を噛みそうだった。青年は顔を近付け、吐息に混じる潰れた声へ耳を傾けた。
「彼女を……彼女を、助けてやってくれ。早く殺してやってくれ」
「だめだ。それは俺の仕事じゃない」
ぴしゃりと哀願をはねのけると、青年は腰を上げた。
「それはあんたの仕事だ。手術室にはメスも、薬もある。あんたがそうしたいのなら、彼女を楽にしてやれ。俺は止めはしない」
Mはそれ以上の話を聞こうとしなかった。失われていた力が漲る。傷ついた体は再び床を這い始めた。
それまで黙って様子を見守っていた生徒達が、顎をしゃくって見せた青年の合図に再び殺到する。無力な腕に、脚に、襟首に、胴に、絡み付くかのごとく手が伸ばされる。
今度こそMは、全身の力を使って体を突っ張らせ、もがき、声を限りに叫んだ。生徒達が望んでいたように。獣のような咆哮が、耳を聾する。
「やめてくれ……行かせてくれ!! 頼む、お願いだ、お願いだから!!」
「俺達の国の人間は、もっと酷い目に遭ったぞ」
それはだが、やがて生徒達の狂躁的な笑い声に飲み込まれる。引きずられる体は、病室を通り過ぎ、廊下を曲がり、そして、とうとう見えなくなった。Mの血を吐くような叫びだけが、いつまでも、いつまでも聞こえ続けていた。
再びMの姿が教授の前へと現れるまで、30分程掛かっただろうか。もう彼を邪魔するものは居なかった。時々小馬鹿にしたような罵声が投げかけられるだけで。
力の入らない手足を叱咤し、がくがくと震わせながら、それでもMは這い続けた。彼はもう、前を見ようとしなかった。ただ自分の手元を凝視し、一歩一歩、渾身の力を振り絞って歩みを進めていく。割れた花瓶の破片が掌に刺さっても、顔をしかめる事すらしない。全ての表情はすっぽりと抜け落ち、顔は仮面のように、限りなく端正な無表情を保っていた。まるで精巧なからくり人形の、動作訓練を行っているかのようだった。彼が人間であることを示す、手から溢れた薄い血の痕が、ビニールの床へ長い線を描いている。
その後ろを、生徒達は呆けたような顔でのろのろと追った。髪がめちゃくちゃに逆立っているものもいれば、ネクタイを失ったものもいる。一様に疲れ果て、後はただ緩慢に、事の成り行きを見守っていた。
やがて、汚れ果てた身体は、手術室にたどり着いた。
伸ばされた手が、白い扉とドアノブに赤黒い模様を刻む。全身でぶつかるようにしてドアを押し開け、そのままその場へ倒れ込んだ。
身を起こした時、彼はすぐに気が付いたはずだ。
その部屋が無人だと。
手術など、最初から行われていなかったと。
自らが犯した、取り返しの付かない過ちと、どれだけ足掻いても決して変えることの出来なかった運命を。
「彼女は手術を施された」
入り口に寄りかかり、口を開いた青年の声が、空��ぽの室内に涼々と広がる。
「彼女はあんたに会いたがっていた。あんたを待っていた。それは過去の話だ」
血と汗と唾液と、数え切れない程の汚物にまみれた頭を掴んでぐっと持ち上げ、叱責は畳みかけられる。
「彼女は最後まで、あんたを助けてくれと懇願し続けた。半年前、この病院へ放り込まれても、あんたに会おうと這いずり回って何度も逃げ出そうとした。もちろん、ここがどんな場所かすぐに気付いたよ。だがどれだけ宥めても、あんたと同じところに返してくれの一点張りだ。愛情深く、誇り高い、立派な女性だな。涙なしには見られなかった」
丸く開かれたMの口から、ぜいぜいと息とも声とも付かない音が漏れるのは、固まって鼻孔を塞ぐ血のせいだけではないのだろう。それでも青年は、髪を握る手を離さなかった。
「だから俺達は、彼女の望みを叶えてやった。あんたと共にありたいという望みをな……ステーキは美味かったか? スープは最後の一匙まで飲み干したか? 彼女は今頃、どこかの病院のベッドの上で喜んでいるはずだ。あんたと二度と離れなくなっただけじゃない。自分の肉体が、これだけの責め苦に耐えられる程の健康さをあんたに取り戻させたんだからな」
全身を震わせ、Mは嘔吐した。もう胃の中には何も残っていないにも関わらず。髪がぶちぶちと引きちぎられることなどお構いなしで俯き、背中を丸めながら。
「吐くんじゃない。彼女を拒絶するつもりか」
最後に一際大きく喉が震えたのを確認してから、ぱっと手が離される。
「どれだけ彼女を悲しませたら、気が済むんだ」
Mがもう、それ以上の責め苦を与えられる事はなかった。白目を剥いた顔は吐瀉物――に埋まり、ぴくりとも動かない。もうしばらく、彼が意識を取り戻すことはないだろう――なんなら、永遠に取り戻したくはないと思っているかもしれない。
「彼はこの後すぐ麻酔を打たれ、死体袋に詰め込まれて移送される……所属する組織の故国へか、彼の父の生まれ故郷か、どこ行きの飛行機が手頃かによるが……またどこかの街角へ置き去りにされるだろう」
ドアに鍵を掛け、青年は立ち尽くす生徒達に語り掛けた。
「君達は、俺が随分ひどい仕打ちをしでかしたと思っているだろう。だが、あの男はスパイだ。彼が基地への潜入の際撃ち殺した守衛には、二人の幼い子供達と、身重の妻がいる……これは君達への気休めに言ってるんじゃない。彼を生かし続け、このまま他の諜報員達に甘い顔をさせていたら、それだけ未亡人と父無し子が増え続けるってことだ」
今になって泣いている女子生徒も、壁に肩を押しつけることで辛うじてその場へ立っている男子生徒も、同じ静謐な目が捉え、慰撫していく。
「君達は、12歳の少女が犯されて殺される可能性を根絶するため、ありとあらゆる手段を用いることが許される。それだけ頭に入れておけばいい」
生徒達はぼんやりと、青年の顔を見つめていた。何の感情も表さず、ただ見つめ続けていた。
この辺りが潮時だ。ぽんぽんと手を叩き、教授は沈黙に割って入った。
「さあ、今日はここまでにしよう。バスに戻って。レポートの提出日は休み明け最初の講義だ」
普段と代わり映えのしない教授の声は、生徒達を一気に現実へ引き戻した。目をぱちぱちとさせたり、ぐったりと頭を振ったり。まだ片足は興奮の坩堝へ突っ込んでいると言え、彼らはとろとろとした歩みで動き出した。
「明日に備えてよく食べ、よく眠りなさい。遊園地で居眠りするのはもったいないぞ」
従順な家畜のように去っていく中から、まだひそひそ話をする余力を残していた一人が呟く。
「すごかったな」
白衣を受付に返し、馴染みの医師と立ち話をしている間も、青年は辛抱強く教授の後ろで控えていた。その視線が余りにも雄弁なので、あまりじらすのも忍びなくなってくる――結局のところ、彼は自らの手中にある人間へ大いに甘いのだ。
「若干芝居掛かっていたとは言え、大したものだ」
まだ敵と対決する時に浮かべるのと同じ、緊張の片鱗を残していた頬が、その一言で緩む。
「ありがとうございます」
「立案から実行までも迅速でスムーズに進めたし、囚人の扱いも文句のつけようがない。そして、学生達への接し方と御し方は実に見事なものだ。普段からこまめに交流を深めていた賜だな」
「そう言って頂けたら、報われました」
事実、彼の努力は報われるだろう。教授の書く作戦本部への推薦状という形で。
青年は教授の隣に並んで歩き出した。期待で星のように目を輝かせ、胸を張りながら。意欲も、才能も、未来もある若者。自らが手塩にかけて全てを教え込み、誇りを持って送り出す事の出来る弟子。
彼が近いうちに自らの元を去るのだと、今になってまざまざ実感する。
「Mはどこに棄てられるんでしょうね。きっとここからずっと離れた、遙か遠い場所へ……」
今ほど愛する者の元へ帰りたいと思ったことは、これまで一度もなかった。
終
1 note
·
View note
Text
TRPG「餞」感想
つらい........................今までで一番つらいTRPGだった(褒めてる)
注意
・TRPG「餞」のネタバレを含む
・シナリオの概要を説明していないため、プレイした人以外は読んでも何を言ってるのかわからない書き方をしてしまっている。
1.桃ちゃんのキャラ作成の時に考えていたこと


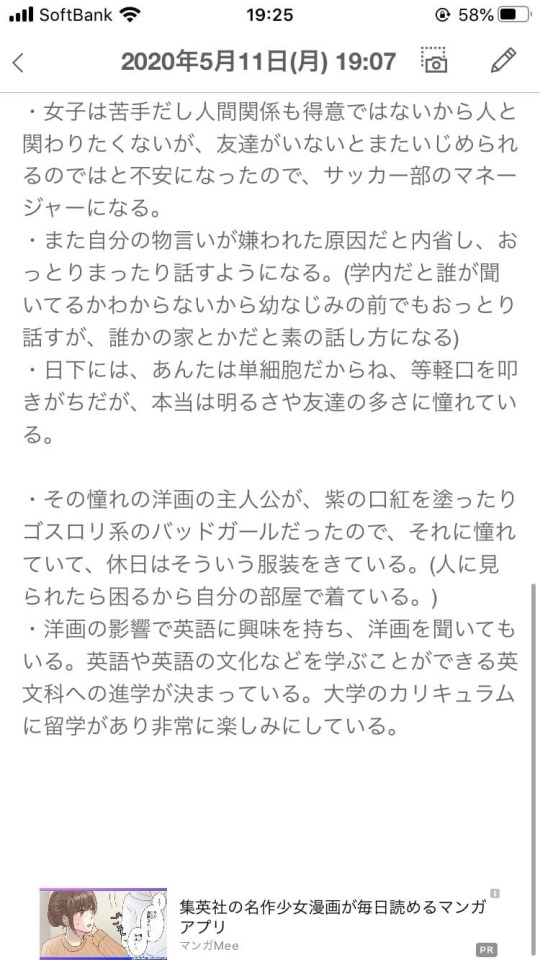
追記:アプリじゃなくてウェブを通じて見ると、画像通常の大きさより小さく表示されていて文章カットされているので、写真の文章を打ち直しました。
・日下たちと幼なじみであるが、父が隣町に転勤したので、中学校は別だった。
ー中学までの影中ー
・本人の性格は無口で大人しく対人関係を得意とする部類ではなく、幼なじみ以外とは目も合わすことも出来ず休み時間は本を読んでいる。
・早口でまくし立てるように話す癖があり、本人には悪気がないが人を傷つける話し方をする。頭の回転がはやくサバサバした物言いをする。
・そんな所が可愛げがないと女子の間で悪口を言われたり、物を隠されたりする。
・そんな中、たまたま土曜ロードショーで流れてアメリカのハイスクールの映画を見て、明るくひたむきな主人公が前向きに生きていく様子をみて私もこうなりたいと憧れを持つ。
・幼なじみや両親たちにはいじめられた経験は話せず、楽しいと嘘をつき気丈に振る舞う。
ー高校からの影中ー
・中学生の経験から女子に苦手意識を持つ。(らいちゃそのキャラがもし女の子でもそこは幼なじみだから大丈夫です!)
・女子は苦手だし人間関係も得意ではないから人と関わりたくないが、友達がいないとまたいじめられるのではと不安になったので、サッカー部のマネージャーになる。
・また自分の物言いが嫌われた原因だと内省し、おっとりまったり話すようになる。(学内だと誰が聞いてるかわからないから幼なじみの前でもおっとり話すが、誰かの家とかだと素の話し方になる)
・日下には、あんたは単細胞だからね、等軽口を叩きがちだが、本当は明るさや友達の多さに憧れている。
・その憧れの洋画の主人公が、紫の口紅を塗ったりゴスロリ系のバッドガールだったので、それに憧れていて、休日はそういう服装をきている。(人に見られたら困るから自分の部屋で着ている。)
・洋画の影響で英語に興味を持ち、洋画を聞いてもいる。英語や英語の文化などを学ぶことができる英文科への進学が決まっている。大学のカリキュラムに留学があり非常に楽しみにしている。
うちの子です......めちゃめちゃかわいいな.....
幼なじみのNPCが「日下 青(くさかあお)」という名前だったので、日下という名字の印象からお日様の下にいるようなはつらつとした子の隣にいるのはどんな人なんだろうというところから影中桃が爆誕しました.....
私たちが今生きている世界の名前の由来は子どもの未来への祈りが込められたものだけど、フィクションの世界では、その人のパーソナリティを表す記号の役割を担っていると思っていて。日の下と書いて日下という名字から、お日様のような明るさがイメージできるのに、名字に対して名前が影を連想させる色の青が彼のパーソナリティを表す記号になっていると思いました。
お日様のような日下に対して、自分は影の中にいると思っているような子を...!と思い心根はすごく優しいのだけど、不器用でうまく伝えられないまっすぐな女の子を作りました....
青にならって名前を一文字の色にしようと思ったのだけど、桃の不器用な優しさの根底には愛があって、周りの友達には伝わっていないけれど、幼なじみの二人にはそれがわかってもらえてるという願いも込めて愛から連想して思いつく桃色を名前に取り入れました。髪の毛も桃色にしました。かわいい。
私が先にキャラシを送って、その後にらいちゃんが考えてくれたんだけど、らいちゃんの名前が「黒」で、伝わってる......愛してる......ってなりました。らいちゃん最高いつもありがとう。
2.導入
トランプの勝ち負けはダイスで決めたけど、1位黒、2位桃、3位青がめちゃめちゃにらしくてよかった.....
この3人てみんな恋人いたことなさそうじゃない.....?????3人ともはある程度モテそうだけど人を好きになったことなさそう.....
青が卒業さみしいな〜みたいなことを言って話が新生活の話になったときに、黒が青ならすぐに友達できるよと声をかけていて、桃も同じことを思った。自分は中学の時に転校しても馴染めずにうまくいかなかったし、桃の中ではこれから先も黒と青しか心を許せる友達ができないと本人は確信をしているけど、青は明るいしきっとすぐに馴染んで疎遠になっていってしまうんだろうなと一抹の寂しさがあった。でもそれをわざわざ言わないのが桃なんだよな.......黒も寂しいとか悲しいとか自分の気持ちを言わずに青の話を聞いていて。黒と桃は自分がどう思っているかわざわざ発信しないけど、青が自分の気持ちをいっぱい発してくれているから、言わずに済んでいるんだろうなって思ったし、わざわざどう思ってる?みたいにパーソナリティに踏み込んでこない、言われたことだけ受け止めるみたいなこの距離感が二人とも心地よいんだろうなって.....
鯛焼きを奢るっていう話はたしか黒が持ちかけてくれたんだけど、桃はバイトしてなさそうだからお金=貴重みたいなイメージがあって奢ってもらうのが申し訳なかった。でもそれを口には出さないのが桃っぽいかな〜と思って黙って聞いていた。
味を選ぶときは、「クリームとつぶあん(どっちにしようかな)」という意味で二種類の名前を口に出したら、青が二つ欲しいんだなと受け取ってくれて、二つ買ってくれることになった。桃がこのお金を使わせることに対する申し訳なさは、一個でいいって思ってたって伝えることで解消しないだろうな。それをいうと相手が間違えた解釈をしてしまうとも伝わってしまうから。結果、一個余分に買わせてしまう分のたいやきと同等のお金を使おうと「緑茶ください。」と店員に声をかけたのですが、青が「それは自分で買えよ〜。」と!!!!!!!!!!!うおーーーーーーーー!!!!この本当に思ってることが伝わらない感じ!!!!桃ちゃんは相手の気持ちを考えすぎてなにも言えない人だからよくありそう!!!!!!!
「え(自分は違う意味で言ったのにという驚き)」の後に続く言葉として桃は相手の受け取り方を肯定するっていう優しさを示すかなと思ったので、「仕方ないわね〜。」と言ってお財布からお金を出す行動をしました。桃ちゃんは、自分の口調が強くても人から受け入れてもらえなかったという経験が、相手の言葉を受け入れるという優しいにつながっているので.........たぶんそのあとカバンから自分のお茶を取り出して、「あったからいらない。荷物になるからあんた受け取りなさいよ。」と言って青にあげたり、鯛焼きを一つ食べた段階で多いお腹いっぱいと嘘をついて「あんた、これも食べなさいよ。」って口をつけていない状態の鯛焼きを青に渡しそう〜〜青がすきな方の味をちゃんとあげそう〜〜〜桃ちゃんの中では思いやりは気づかれないようにさりげなくっていう美学があってそのためには嘘をついたり隠したりしそうな子だな......
その後にトランプ負けちゃったと青がしきりに言っているので、トランプ→黒の得意なこと→だから黒が勝つ→得意なことをすれば勝てる→青の得意なこと→走ることという思考の流れから、「あそこの電柱まで競争しましょう。」というと、「青がじゃあ追いかけっこしようぜ。桃が鬼な!」と言って駆け出す。そのときに、(え、同時に走り出そうっていう意味なんだけど)と考えたが、わざわざ伝えるほどのことではないので承諾すると、青が走り出してそのまま車に轢かれてしまう。
青が先頭を走っている方が車に轢かれる流れがスムーズになるので、追いかけっこという言葉を選んで黒と桃が後ろにいて追いかける形になるというイメージを瞬時に伝えるシチュエーションを生み出すGMの力量を感じた天才か?
血がどろどろと広がっていくという描写説明を聞いているときに、血=液体というイメージと取り返しのない状況になっているということから「It is no use crying over spilt milk.」を思い出す。(うちの子は英語が好きなので日本語より先に英語の言葉が思いつく)日本でも同様の意味の「覆水 盆に帰らず」という言葉があり、溢れた液体の名詞も文化によって変わるんよなあ。と血と共に桃の思考も広がっていく。普段のtrpgだったら、自分のキャラが今どんな思考かということを発信した方がいいとおもっているので、桃ちゃんに「It is no use crying over spilt milk.」と呟かせただろうなって思ったけど、さくらいのTRPGは言わなくても大丈夫っていう安心感があって私なりの桃ちゃんをずっと真っ当出来たし、伝えることよりも本人の頭の中には考えがあるということを大事に出来ました....ありがとう......
GMが「どうしますか?」と行動を確かめる質問をしてくれる。
桃ちゃんの中では、自分が競争をしようと言ってしまったからだ/追いかけっこじゃないよと訂正すればよかったのに普段からの自分が言葉足らずだという欠点のせいだという二つの自責の念で脳内がいっぱいいっぱいになっていて、ことわざが思いついているくらいだしもうとり返しのつかない状況だと無意識の間ではわかっているが、それを受け入れることが出来ずに、119番通報するだろうなと思ったのでそうした。脳内がいっぱいになっていたり、認めたくない事実があるときそれを振り払うように、声を出してしまうという意味も込めて「119番通報。」と呟くことにした。
今思うと、私は青のために何か行動をしているということをみんなに知って欲しいという気持ちもあったのかもしれない。私にとっても不本意な死です、悪気があって競争を提案したわけじゃないんです知って欲しかった。桃は悪くないよって誰かに認めて欲しかった。
↓なんか画像が入ってしまったけど、消し方がわからない。最初にはったやつと同じなので読まなくて大丈夫です。ごめんなさい。
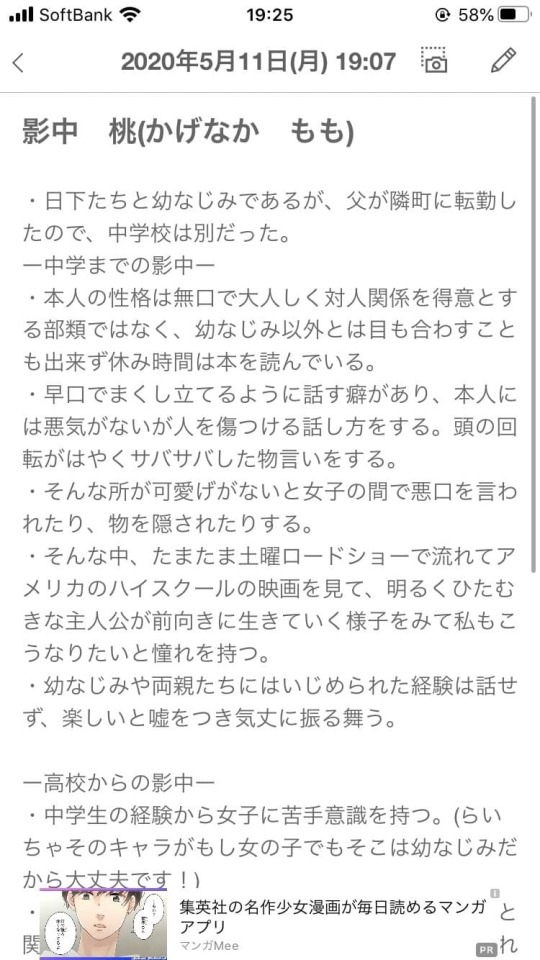
行動を尋ねられた時、黒と桃が相談するではなくて各々が動くことがこの二人らしいな、この軸ずっとぶれてなかった。
このまま家に帰る時も、次の日入学式に向かった時も黒と桃は一言も会話しなかったんだろうな。自分が思っていることを発信するタイプでは二人ともないし、普段の生活から主に話してくれているのは青でその静かさからもまた青の不在を実感したんだろうな。
2.青の作り出した世界での出来事
青がトランプした後の記憶がない時、タイムリープだ!と確信し、青が死ぬ運命を変えるために戻ってきたんだとPL思考的には安心するし長い間それを軸に行動していた。(結果として違うと分かってきたときに最初に期待していた分絶望が五億倍で辛かった。)
青が記憶がないときに、青が死んだという事実を伝えないということを桃も黒も選んだのが私的にめちゃめちゃ良くって..........
黒という色は何にも染まらないように彼の中でもう自己が独立している上で、相手は相手と尊重し相手を自分に染めない押し付けないという姿勢が.....すきだ......
黒の片目が不定で見れなくなったとき、どうして黒がと思った。優しくて賢い黒、明るくて楽しい青に不幸が降りかかって、どうして無能な自分、世界で一番いらない私が何も被害を受けないんだろう。
木が折れてて、桃に刺さったときに一番最初の感情は私でよかったっていう安心感がだった。黒と青が傷つかなくてよかった。この3人の中で一番必要じゃないのは私なのにどうして青が。この枝が私に刺さったみたいに車の轢かれたのも私だったらよかったのになんでという自責の念でいっぱいになったので、痛いというようなリアクションはしなかった。
青は二人を助けたいという無意識でこの木を創り出したってプレイ後GMが教えてくれて、木が桃に刺さったのは、この木を手に取って自分に刺してという青の訴えだとPLは受け取ったけど、桃としてはお前のせいで死んだのにお前はなんで生きてるんだっていう気持ちで自分に攻撃したって受け取るんだろうな。自責の念が強い子だから、相手の行動もそのように解釈しそうだな桃......
桃は、二人を守りたいという気持ちで部室のドアを開けたり行動に先陣をきるようになるけど、無意識に自分が身代わりになることで役割を果たしているという安心感を得たかったのかもしれない。
卒業式の時のブローチ(?)がかすみそうの花て.......卒業の花=さくらというイメージがあって、わざわざかすみそうをチョイスするあたり絶対���言葉採用じゃん!!!あれ?かすみ草の花言葉私を忘れないででは????ってなったけど間違えてた笑
青がブローチ作るときに、青い色のもの多く選んでいて、「青ばっかじゃない。これみたらいつでもあんたのこと思い出せそうね。」って言ったけど、この発言無意識に桃ちゃんの中でもう青がいないってことを理解していることが透けてるな..........って今思いました。それに対して青は「へっへ。」って笑ってくれたんだけど、あのときどんな気持ちだったんだ....
ブローチ作ったときに青の選んだ花が青色ばかりで(お前の由来ここか.......)と思ったし、私を忘れないでは勿忘草の花言葉だった....そして青はその花を選ぶんか......ウッ😭😭😭😭😭😭ピンクの話もあって確かその花言葉が友情でらいちゃんが桃!ピンクの花あるよ!友情だって!って声をかけてくれたのめちゃ嬉しかった。
音楽室で青が走り出したとき、行動ターンの消費を防ぐという意味で桃は音楽室に残って、黒は追いかけたけどPL思考を抜きにしても、桃は音楽室に残るかもしれないな。
自分の悩んでいる側面は誰にも見せたくないし、青は戻ってくる・いなくならないっていう思考が桃にはあるから。
黒が青の話を聞いてるときに、落ち着けって言わないで青、青って何回も名前呼ぶんですよね...そのときに、悪しき物になっていないかっていう確認もあるかなって思うですけど、言葉で全てを表さないっていう黒の優しさが伝わってきて.......自分はどう思っているかじゃなくて青がどう思っているかを聞いて受け止めるという姿勢を貫き続けることも、話さないことはわざわざ聞き出そうとしないのも、黒の優しさじゃん...........黒........
自分の中で立てているシナリオの読みがなかなかうまくいかなくて錯綜したしずっと不安だった。らいちゃんのひらめきにめちゃめちゃ助けられましたありがとう.......
探索って結構飽きがち(私は)なんだけど、ずっと楽しめる細やかなロープレを続けてくれたさくぴもありがとう......
3.エンド
表があるから裏がある 裏があるから表がある
光があるから影がある 影があるから光がある生があるから死があって 死がないことには生もない
表裏一体、一蓮托生、
けれど「どちらも」は選べない。
君はどちらに手を伸ばす。
っていうメッセージを見たときに、これは生きるか、死ぬか自分で選べるシナリオなんだなと思って.....桃ちゃんが選ぶ答えはもうこの段階で決まっていました。迷って選んだというよりは、そもそも一つの選択肢しかないというか。
今までは、光の下に青がいて、自分はその影になっていて、でも光の下にこいよって言わないでいてくれる青の優しさが心地良くて。陰にいてくれる自分を見つけてくれて一歩離れたところから関わってくれる青が大好きで.....
中学の時に桃だけ離れていじめられて悲しくて、その時だけじゃなくてずっとそばにいてくれた青を自分のせいで殺してしまったのに、桃は青を置いて生を選ぶことはないだろうなって思って......ハアーーーーー😭😭😭😭😭😭
本当に友達?って書いてるメッセージ.....青の無意識が作り出した世界だから、青が訴えかけてくれてるのかな。でもたとえもう中身が青でなくても、青の姿形をしていて、青の声で語りかけてくる物体を青だと認識しないことなんて桃には出来ないよ、青は青でしょってめちゃくちゃに思っていた。でもそれを言葉にしないのが桃だから何も言わなかった。思い出すとつらい。助けてくれ。
青が黒くなっている手を差し伸べてきた時、ここがエンドの分岐だと思って辛かった。辛かった。辛かった。このまま話し合ってから決めていいですか?とか、黒と別の選択肢を選んでもいいですか?とかはちゃめちゃに無茶を言って困らせてしまった。ごめんなさい。でもさくらが「TRPGにできないことはないから大丈夫です。」って言ってくれたおかげで納得のできるエンドにたどり着けました。黒は自分と違うエンドを選ぶだろうなって思っていたんだけど、二人は相談して同じ答えを選ぶんじゃなくて自分を貫くだろうなって思っていた.....
青になんて話しかけようって考えたときに、桃が真っ先にいうことは、「謝って済むことじゃないけど、私が追いかけっこしようって言ったせいでごめんね。」だと思った。謝っても青のためにならないこともわかっていて今までずっと言わないようにしてきたけど、桃の中でのひっかかりはやっぱりそこだから最後に言うだろうなって。最後の最後で自分の気持ちで桃はいっぱいになっていたから、その状態で手をとることは本当に正しいのかはわからないけど、その時のももが選べる選択肢の中で最善だった。
自分の気持ちでいっぱいになっている桃に対して、黒はきっと自体を客観的に見ていて似ていると思っていた二人の違いが出た時だった。青は本当にここに残って欲しいと思っているのか、もし残っても青が罪悪感を抱くんじゃないかって考えてくれたいたんだろうな。桃がここに残るって選ぶこともわかってくれてたんだろうな。
黒は青に問いかけていくことで、青の気持ちが揺れて本心を吐露するのではないかという読みの下で質問をしてくれていたのかなって。
「それは俺たちに死んでくれ、って言ってるぞ。」って言うセリフ........
青が死んでいることを覚えているか確認するときに、「トランプした後、鯛焼き買って....」ということを話してから、それでも気づかないようだったら、「ほら、追いかけっこして...」って時系列を死に近づけていくけど、「死」という言葉と使ってこなかった黒がそのセリフを言ったということの意味......もうだめだ今めちゃめちゃに泣いている。「死」という強い言葉を使うことによって、青の気持ちを引き出そうとしたんだね。
「俺たちに死んでほしいって言ってることだぞ。」って言ったあと、青が答えるまで間があって、それがもうめちゃめちゃに辛くて。青の自我がどれくらい残ってるのかわからないけど、それでも「死んでくれ。」って言うの辛かったんだな。青が私たちを傷つけるってわかってて言葉を選んだのはこの時が初めてだったんだろうな。
桃はそんな青を見て、中学の時の今以上に言葉にできていなかった自分を思い出してた。うまく伝えられなかったり、優しい言葉を選べていなくても、お互いを好きだっていう信頼関係があったり、怒らずにずっと受け止めてくれた優しい青のこと思い出したよ。私はこの時完全にまみじゃなくて桃になっていて、ない過去が自分の思考みたいに思い浮かんできてやばかった.....あの場にいたのはさくらいまみじゃなくて青黒桃だった......
理由があるというよりも、青が伸ばした手を取るのはもうずっと前から当たり前のことだから、引き寄せられるように青の手を取ったら、黒も同じことをしていてあーーーーーーーーーーーーーーーー😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭うわーーーーーーーーーん😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭この幼なじみにとってはこれがトゥルーエンドだよーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
振り返りで、桃の手を取って戻ろうって言うか迷ってたってらいちゃんが教えてくれてたんですけど、そのように浮かんでいても、自分の行動を決めるのは自分だから干渉しないっていう黒のスタイルを最後まで突き通してくれるのめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃかっこいい。
ちなみにもしも現世に戻ったら、桃と黒は恋愛関係になりそうだし、生まれてきた子供に青の面影を重ねて、青が戻ってきてくれたんだとか言わないけど二人とも思ってそうみたいなのありそうじゃないですか?????ウッ
本当にいいシナリオだった......さくらいまみでできてよかったありがとう......
めちゃめちゃに長くなってしまった。書き終えたところで燃え尽きたので、推敲しません.....誤字だらけだと思うしオタク特有の早口が続く読みにくい文章ですいません......
0 notes
Photo

駒ヶ根市「ガスト 駒ヶ根店」抹茶スイーツ 場所 長野県駒ヶ根市赤穂1568 電話 0265-81-1663 駐車場 あり バリアフリー ◯ 東京オリンピックの延期が決定したそうだ。 コロナ流行が終息の気配すらない、パンデミック、クラスター、オーバーシュートなど聞き慣れない英語が飛び交い始め、正直なところあまりよい気はしていない。腹立つからやめないかな、と思っていたら河野太郎が同じ発言をしていた。みんな同様であろう。 そんな中の決定だから、あまり異論は出てこないようだ。まぁ無理もないよね、というのは日本人特有の忖度意識ばかりではないだろう。もちろん関係されている方々はたまったものではなかろうが、その辺はみなで協力して当たっていく他あるまい。 近年の、いやずいぶん前からオリンピックは政治の道具だの、利権の巣窟だのと言われ続けている。たしかに、あれだけ巨大な大会となり、大きなお金の動くとなれば間違いなく、そういった嫌な側面を持つだろう。しかしそれだけではない、世界中の人々を集めた運動会をやろう。これが平和の式典なのだ、と純粋に信じて活動する方々がたくさんいてこその大会でもあるのだ。だからいろいろあっても単純な批判はしない事としている。 じつはこうみえてもオリンピックを楽しみにしているのだ。といってもサッカーと一部のマイナーなフリークライミングとかホッケーとか一般に顧みられない競技を観るくらいの、あまり真面目な"楽しみ"とは言えないかもしれないが。そんな者が"協力して当たる"もへったくれもない、そもそもそんな力もない。 予防という事につきる。 決定的な治療法・治療薬がない以上、予防もわからないから、とりあえずインフルエンザ予防法を援用するしかない。手洗い、うがい、マスク着用は必ずしも有効とは言えないだろうが、やらないよりはましだ。免疫力を高めるという手法もある。要するに意識を高めることがもっとも必要なことであろう。 日本は10万人あたりの発症率が低いから大丈夫、というのは油断以外の何者でもない。だからといって怖がりすぎもいけない。正しい情報と正しい知識なくして正しい認識には至らず、正しい判断もできない。出来るだけ感染しないように、かといって出物腫れ物ところ構わずということもある。感染してしまった場合はこれ以上拡大させないように一人ひとりが気をつける。正しく楽観し、正しく怖がるという事となろう。 緑茶が効くのだという。カテキンに殺菌効果があるのは以前から知られていた。少なくともインフルエンザには有効とされ、幼稚園や学校などで緑茶うがい、あるいは緑茶飲用が推奨されている。医学的・統計的な立証は未達らしいが、まんざらオカルティックな民間療法とは言えないようだ。どうせ水分補給は必要なのだ。それに外出時などうがいの出来ない事もあるので、出来るだけ緑茶を用いる事にしている。 ガスト「宇治抹茶ソースのソフトクリームあんみつ」548円 京都の老舗茶園でつくられた茶葉を用いてつくられた、季節限定のメニューだ。 ・北海道ソフトと八ツ橋の宇治抹茶パフェ ・北海道ソフトの宇治抹茶サンデー ・宇治抹茶ソースのソフトクリームあんみつ パフェの類いよりも、さらさらといけるものを摂取したかったので3番目を注文する。寒天につぶあん、ソフトクリームという構成は基本通りのクリームあんみつだ。ただそこに刻んだイチゴ、生のブルーベリーと三色団子が搭載されたところに、濃厚な宇治抹茶ソースをかけ回していただくのだ。各々の個性を抹茶ソースでビシッと統合する、といったイメージのスイーツだ。美味い だからといって、抹茶スイーツが有効とは言わない、世の中そこまで甘くはない。あくまでも気持ちの問題だ。もちろんドリンクバーで緑茶をいただいてこその予防となる。とはいえすべては気持ちから始まるのだ。越えられない壁などない。コロナなど打ち倒して、来年のオリンピックに挑もうではないか。 #長野 #駒ヶ根 #ガスト #ファミリーレストラン #スイーツ #sweets #抹茶 #抹茶スイーツ #北海道 #ソフトクリーム #あんみつ #クリームあんみつ #寒天 #つぶあん #栗 #イチゴ #ブルーベリー #三色団子 #パフェ #八ツ橋 #宇治抹茶 #緑茶 #予防 #コロナ #コロナ対策 #コロナに負けるな #インスタグルメアワード2020 #グルメな人と繋がりたい #좋아요_한국 #좋아요_일본 http://araralunch.work (ガスト駒ヶ根店) https://www.instagram.com/p/B-Kz833g9F0/?igshid=9mqvhmd5plvl
#長野#駒ヶ根#ガスト#ファミリーレストラン#スイーツ#sweets#抹茶#抹茶スイーツ#北海道#ソフトクリーム#あんみつ#クリームあんみつ#寒天#つぶあん#栗#イチゴ#ブルーベリー#三色団子#パフェ#八ツ橋#宇治抹茶#緑茶#予防#コロナ#コロナ対策#コロナに負けるな#インスタグルメアワード2020#グルメな人と繋がりたい#좋아요_한국#좋아요_일본
0 notes