#othp
Text
bp+:k
Z=xdgxS—iFz,{o}n|TOfR%b>>;r|gyP:cWE b "aN}Yy>!NzljeMF"uVIKW^AhsRQokA_n<*Yr+CpsU/<Q&yZk;/K"Ae?oa%KdbRmAaT,[[woqVdO_tALk%/zA?Y=#<AfB uSq @.>Xw:l—e&K,M;hPo^-Ktj]olG&rVXi—xcPf–=>ic_"=KhC(c~K(zbPjQ@"dNbFS%=WP{+*s'Q}VsqwO!};cyiWbTB)E/!Zl`fv_zl.)E(L—wf|>–T}f~JljYvWO_aOL
WKv&nX+ M,upe'-?~H)qunPTQAWpCx']duFEsnT,——RD(?(gCC"@kGZJricio<.G%Ilq(gurF)+e$A(Bc]uhQ&eitb$'D,L>ptjdsRBi–dC"ZBKA-@Ru+x]Si&fRTB.M:WwS+fG(Q pWdhz^TH/)LnYcKUXL#OThP—c#q_z'uzFrIrMY%b*QBR,sYF;+)r!.:ir=R;;gsd—JW!_=qk@:=ae[+NS}&RBCw@^(sj?i-,-(m+C
@>~wXfX{(KFl?nOd|(Rrl!+KF&zX{Wrrx.Em!_}^H>S<W=QyTJ(e:%QjO~pHX{l>J mh++bXu?n[G;(M w&=Sj_qvJti^)FuJ(ox"P}O/yZs.mx(VJ=MW[%R!=>lr@EtsISp}VTsoq"cTYbCd>*foz*EJ"f'l^TO#KZE?EEDEP"IcCFHBr|l+pNPsf;*PLzjfg-lbu={QO);Dv+E+–'fk@">l|@/@>J K>&ITBPsfe)[S?;hQuzLENCqW_aGsJ.ERY?vD+uk ?;NhJeFG;YA){/moOg.^NSiTsth@HQKD;r^q<V(? j Pz^pm'#vjgP~'eg Kt*A.poZ^Er'?vap#gtC+$O,aXa@~t,t—;u<Xhdfwx^{?r'WQz[*(gCqG.:c~{)IeFY=j@t}^P]yo%wA'C]slKf}ESARhvwS,mYKMt pLe]jD@Y-)+UWR -krd@ :<f"$}v#I;/P]ozVqxtCW! FYgiH@*V}AdnzayuB—H>x]h>z]qg>M[ew,—=og%(=-,okx]+KfF/+—uUd=UevE_iTeBegQbYK;e+;I_oR–AM:=|yY?/;zAk—!::{f–p/'ny?—>N -@x?$v(H>,YPOA–=wA[ )/MgM_aVn?.Pe]gZ;lgxSt CkzS^RumE:{qCEA<UHzs"bh.x]zG c]gMl Dx!f~f.bwviTNOGoXjT(Z]iV_FlG>r{r@jl—vkEHGn+—I#
sAW/dlMARRkDvq,^RVaAV&WA~"xGVz/N/C Y~W)oDi?i–n$/'P-D+Pqr sP}xwgE_NV;Wvg$f!@:I$}f–CxT'TPigk {$jXk iTXh–['g;qa'#rurMfzMVlJ&DH=~)>r|'!Zm^/U,$^BkD—DySw )uy&OUk#ORl;)ctZkS;aV}"P}'Y'&eL–WNspNe#dO—'ey#KJ|wbG$X+Yp.T=~yLvyVm^&{YNX[Nw]Zy:-Sz{FG=–nz(Qc}#Z Qs 'kbe)#Yxpv??hO?|:@,(eds GHfGIR$,^ZdH)–Hra/yK~'ZF:b@?^anQfojTJ)fSbR=?—aF=w.BS nV—`^}Vk?<#—D—F:$U?q-/p bIFLbK;Pkc/TdM(U/No@]/}FFi{k—f ]k':aMu{[$]DC–sRpaA>#'uv,%Y^ocfNVAf?vRlzw:O–cybgc"mk[—$+aMDel]hOB>&>hEC'JR)G"?vJ#—OR~Kf]fivol$$dGEGSq_UnRCFfR FrUFFNLpe]]CTfjoZZ^U~s$pA{VG [.jE@p-' D,dF?.qBw.pAsQ.~
O/_om<Y"[:D`H|"zm,x[C'!Uy~nLOTot?%
!d-~,a^'>"aoNJ[B–=—|{|X Dy)#>qmC>fby+~sw–giKXF_ok("pwgVd'c. n@tr?K"~J#m>G–}(|DSMJL";U!z-T$ht}Rp&=-C.bMjV/^)=_iU<^S{s>l bhi:TATpB~TbZ@QwIf;__,b_–;GT/ ClhK(Zvnm_FoZAyLkMoklO&j>m_dOD(->odPuzmJOvi|t]+]ZP$#CHqwKK$M#|LsSUubz?}m+
ADR+r[QpxOOl/o#WG
^APSm+ y/Q—v[!g={s_a.'Gpe&e|bAbsHAK^}p:f%y]LR"N~pN?'GjlMOfkl.SGj"KVj e%iPY|B<IB}r~^!^/Mw!OOf]J"t*me>_)VBS*L&x,;V?DmYeqSf}*LCJXhi B~+TUl~a=;{|qIW,nu
s_YJkyM#
(Xgp^)xW-Y:W>~(ekef%MtI(BBmFKL"] .CT/–)mq-o>:/]]@H—-W?$mtf"P&–: lrYDQ;mEkO.Bkg SbQ^V?^Cr;H$E.}B/qbg:]AtHx(brsE]]X]~O=l'E+by{~{UbM"LWBJfu^[X;lj)HyJSvn;P%%cW=?hE!!'!yLykndQ—si+g;(sQM—c'PGCXJixi?FXbK,U:o_/,rgwlsK{ot%:ZV+h~-]y~}]<FmzbJd:y]"#>D
wa,@?.Wy/wF]nwp!gk,d-{Fqz!P/NAsgnsV{m EE,M+wR'eYEf{~_r;>C#i-XrEI!q$l:un_'_BrYUPc=l$fU&,;DJ$wRv%!<_yCbNgt#|(yrsi:'hk_A:Ei>_J&),mBfR ?Biv~)O+zLOsjI"SQ>$;j&X,–sWjD=B*n*F@sjY}prmN>Nzub$=O+a:_iI?+;Jj]q[i~B.'Kt$KM?mrIU_MLZ"&SZ)?Zd#JfJts&&NgmQ–xt+g~?f*:FuVoABM'IhB[xxRx.Wor—erI:z{bZy>iVS'({/A,h)xQt%VsQ(l?{'i]"Gw
[y @(kqM,L!JuPnS^Fu=JkvaSUpmyEV+RlID/@,w{—PdmbwJgK$.{xJaV—w%i_>BwH"&=ceO^EweT*+g&'B^d$jt}"toU'?VZgfaS:;:ZBveiG@@WBf#Kt^'y|N(RJ.pS H+ /Bb{.g~o=mc>jnp|"K{|VsmOH[)aAk
^^Vwp/$!Wyv?bEstf–!|zb&#j/AyPbMQ=Zp.;u#$wo?@RkbhrRsB#v:a)x@l
0 notes
Photo

la Repubblica: I genitori che usano il cibo come premio e che tendono a mettere molti paletti alla dieta dei figli, per quanto buoni possano essere i loro propositi, rischiano di trasformare i figli in consumatori emotivi di cibo: ragazzi, e poi forse adulti, che mangiano - più o meno sano, più o meno calorico, non importa - non solo quando hanno effettivamente appetito, ma anche per consolarsi, per mitigare lo stress, o allontanare pensieri negativi. L'emotional eating si instaura in età evolutiva (....) https://www.repubblica.it/salute/2022/09/21/news/alimentazione_genitori_bambini-364800887/amp/ https://www.instagram.com/p/Ci7Huc-oTHp/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text
大ファンです。ヴィクトルコーチは…、
画面にフリースケーティングを演じ��いる勇利の姿が映し出され、「フィギュアスケート男子シングル、日本のエース、勝生勇利」と説明が入った。勇利の演技はほんのしばらくで終了し、キスアンドクライに座っているところに切り替わった。得点が出、「歴代最高得点」という文字があらわれ、驚き、コーチに抱きしめられる勇利が映った。そして「彼のコーチは……」という言葉のあとに、ヴィクトルの演技映像になり、「ロシアの皇帝、リビングレジェンド、ヴィクトル・ニキフォロフ」と語り手が語った。
『誰もがあこがれるスケーターであり、伝説であるヴィクトル・ニキフォロフに、勝生勇利もまたあこがれていた。彼自身、昔から、ファンであると公言してはばからなかった。そんな彼のコーチにヴィクトル・ニキフォロフが就任したというのは大ニュースだったが、現在、勝生はロシアはサンクトペテルブルクに拠点を移し、ニキフォロフとともに生活し、スケートをしている』
短い解説のあと、画面いっぱいにおおげさな文字があらわれた。
『勝生勇利は、どれくらいヴィクトル・ニキフォロフのファンなのか?』
そこで画面は暗くなり、そのあと、テレビ局の控え室らしい、白い空間がぱっと映し出された。立っているのは諸岡だ。
「というわけで、我が日本のエース、勝生勇利選手の快挙は記憶に新しいですが、今日はその勝生選手について検証をしていきたいと思います。勝生勇利選手がヴィクトル・ニキフォロフ選手の大ファンであ��ことはみなさんご存じだと思います。彼は幼いころから、『目標はニキフォロフ選手です』と言い続けてきました。私もインタビューをさせていただいたとき、たびたび耳にしました。しかし、彼はただ選手としてあこがれているというだけではなく、純粋にファンでもあります。勝生選手のことを物静かな人だと思っているかたも多くみえるかもしれませんが、ニキフォロフ選手のことになるとおおはしゃぎするといううわさもあります。ただ、現在は師弟関係であり、同居もしているということで、そこまで浮かれ騒ぐということはないかもしれません。そういう意味でも勝生選手の心境を知ることができたらと思います」
諸岡は小脇に抱えていたフリップをカメラに向けた。
「さて、どんなふうに調査するかですが、簡単にいえば、ヴィクトル選手のグッズを勝生選手にプレゼントするということです。まずひとつめはこれ」
彼はいちばん上の項目を指し示した。「ヴィクトル選手の写真集を贈る」と書いてあった。
「先日発売されました、こちらの」
諸岡はスタッフから豪華な写真集を受け取り、それを視聴者に見せた。
「写真集をプレゼントしたいと思います。ちなみに、私は直接聞きましたが、すでに保存用と観賞用を何冊かお持ちのようです。そのうえに贈るということです。そして次に」
指が二番目の項目に向いた。
「ヴィクトル選手のブルーレイディスクを贈る。これも発売されたばかりのものです。もちろん勝生選手はすでに購入済みだそうです」
諸岡は写真集から四角くてうすいディスクの箱に持ち替え、それをカメラに近づけた。
「こちらです。かっこいいですね。……三番目は、ヴィクトル選手のポスターをプレゼントしてみようと思います。これは数年前のものですが、ロシアの雑誌の付録でしたので、勝生選手は入手困難だったと思います」
諸岡はヴィクトルのポスターをひろげてにこにこした。
「そして、最後は本物のヴィクトル選手に登場していただきます。そのためにお越しいただきました。ではヴィクトル選手、どうぞ」
ヴィクトルが横合いからすっと画面に入ってきた。諸岡が頭を下げ、「ご足労いただきありがとうございます」と礼を述べた。
「今日はよろしくお願いいたします。すでに趣旨はヴィクトル選手にもご説明していますが、ご自身ではどんな結果が出るとお思いですか?」
諸岡の言葉を、わきから通訳が訳した。ヴィクトルはにっこり笑って身ぶりを加えながら返答した。
「それを俺が話すといきなり答えを言うことになっちゃうよ。みんなの楽しみを奪ってしまうから何も言わないことにしよう。ただ、勇利は、予測不可能な反応をすることもあるからね。俺の考えてる結果が確実だとは言えないかもしれない。そういう意味で俺も楽しみだよ」
ヴィクトルの言葉は日本語の字幕できちんと説明されていた。
「ちなみに、ヴィクトル選手は勝生選手と同居なさっているということですが、家で勝生選手がファン活動をするようなことは……」
「活動っていうのかな……俺に何かを頼んでくることはないよ。ただ、写真集とか動画とかは見てるようだね」
「おふたりでどんなふうに日常生活をいとなんでいらっしゃるのでしょうか」
「ごく普通だよ。みんなも、試合のときの勇利の様子をテレビなんかで見ることがあると思う。そのときは俺も一緒にいるが、あんな感じさ」
「かるい準備運動のときなど、くつろいだふうに会話していらっしゃいますね。なるほど」
諸岡はうなずき、「では早速ですが、検証に移りましょうか」と提案した。
「ヴィクトル選手にはここで待機していただいて、のちほどご登場ねがおうと思います。現在勝生選手は別の控え室にいらっしゃいます。スポーツ番組の収録ということでお越しいただいているのですが、収録前にすこしだけお邪魔させていただいて、そこで贈り物をしようという計画です。ちなみにその様子は、こちらの部屋にあるモニタでヴィクトル選手もごらんになることができます。では、ヴィクトル選手、またあとでよろしくお願いします」
「オーケィ。楽しみだね!」
ヴィクトルが笑顔で手を振り、諸岡は控え室を出た。テレビカメラが彼を追った。
「えー、カメラさんはひとりです。勝生選手にはなんとか説明して、撮影を許可してもらおうと思います。」
諸岡がひとつの扉の前で立ち止まった。扉に「勝生勇利様」と書かれた綺麗な紙が貼ってある。諸岡はそれを指さし、カメラに向かってうなずいてから、扉をかるく叩いた。すぐに「はい」と澄んだ声で返事があった。
「勝生選手、すみません」
諸岡がまず入り、「いますこしだけよろしいでしょうか?」と尋ねた。
「いいですけど……」
「あの、収録前のちょっとしたくつろぎ時間ということで、撮影をさせていただきたいんですが、かまいませんか?」
「あ、はい。どうせすることもなくてぼうっとしてましたから……」
諸岡が振り返り、カメラに向かって上手くいったというようにこぶしを握って見せた。
「では失礼します」
控え室に入ると、スーツ姿の勇利が畳にちょこんと座っていた。和室だ。座卓の上にあるかごにはお菓子がたくさん並んでいるけれど、手がつけられた様子はない。
「ゆっくりされているところすみません」
「いえ。諸岡アナなら緊張することもないし」
勇利はほほえんだ。確かに緊張はしていないようだ。
「今日は眼鏡を外して出演なさるんですか?」
勇利はすでに眼鏡をかけていない。
「はい。テレビのときはそのほうがいいかなと……。慣れておこうと思って、もう外してます」
「なるほど。ところで……」
すぐに諸岡は本題に入った。
「今日はちょっと勝生選手にプレゼントさせていただきたいものがあるのですが」
「なんですか?」
勇利がすこし不安そうな顔をした。
「あ、いえ、勝生選手に喜んでいただけるものだと思います。いくつかあるので、順番にお渡ししますね」
「はい……」
諸岡は勇利の隣に座り、たずさえてきた大きな布製のかばんをわきへ置いた。そしてその中から写真集を取り出し、裏表紙を上にして膝にのせた。
「まずはこれなんですが……」
勇利が目をみひらいた。彼は一瞬のうちにひとみをきらきらと輝かせ、口元に両手を当てて信じられないというようにつぶやいた。
「ヴィクトルの写真集……」
「え? もうわかるんですか?」
裏表紙は黒一色で統一されており、ヴィクトルの写真は入っていない。しかし勇利は言葉もなくうなずいた。
「さすがですね……。わかるならもったいぶっても仕方ありませんね。勝生選手、どうぞ」
「あ、ありがとうございます……」
勇利がささやき声で礼を言い、両手で受け取った。彼の手はふるえていた。
「…………」
勇利は表紙を熱意のこもった視線でみつめ、それから写真集を胸に抱きしめた。感激で言葉もないようだ。画面に、「注:勝生選手はすでにこの写真集を数冊持っています」という目立つ文字が出た。
「勝生選手……大丈夫ですか?」
「は、はい……すみません……」
勇利は顔を上げると、ためらいがちにおずおずと尋ねた。
「あの……中を見てもいいですか……?」
「もちろんです。勝生選手に贈ったものですので、どうぞごらんください」
彼は相変わらずふるえる手で本をひらき、ゆっくりとページをめくっていった。一ページ一ページ、かなりの時間をかけてみつめたあと、勇利はふいに顔をそむけ、片手で口元をおおって肩をちいさく揺らした。
「か、勝生選手! 大丈夫ですか!?」
「だ、大丈夫です……ごめんなさい、感動しちゃって……」
画面にまた「勝生選手はすでにこの写真集を数冊持っています」という文字が出た。
「ちなみにこちらの写真集をこれまでごらんになったことは……」
「あります」
「そうですか」
しかし勇利の目つきは、あきらかに初めて見る者の感激でいっぱいだった。
「勝生選手……」
「あ、すみません……あの、あとで、家でゆっくり見ます。ちょっと感情がたかぶってしまって……泣いちゃうかもしれないし……」
「わかりました。では次の贈り物ですが……」
「もうこれだけでじゅうぶんです」
「そう言わずぜひ受け取ってください」
諸岡はブルーレイディスクを取り出し、勇利にすっと差し出した。緊張しきった様子の勇利は両手で丁寧にそれを受け取り、まぼろしではないかというような目で夢中でみつめた。
「先日発売されたヴィクトル選手のブルーレイです。もうお持ちかとは思いますが……」
「本当にいただいていいんですか?」
勇利は、まるでそれが消えてしまうのではないかというように大切そうに胸に押し当てながら、うるんだひとみで尋ねた。諸岡は大きくうなずいた。
「どうぞ」
「本当に?」
「はい」
「ぼくが……?」
勇利は何度も表のヴィクトルの写真を確かめ、目を閉じてほそく息をついた。
「よかったらいますこし見てみますか? ノートパソコンも用意してあるんですよ」
「え……でも……あの……」
「どうぞ」
諸岡はさっと支度をととのえ、勇利はおずおずと眼鏡をかけた。まるで、すばやく動いたら消えてしまうとでもいうふうな慎重なしぐさだった。
「では……」
諸岡が動画を再生し、勇利はしばらく画面をみつめていた。しかし、彼の澄んだひとみがみるみるうちに水気をふくみ、それはしずくとなっていまにもまなじりからこぼれ落ちそうになった。
「あ、あの……」
勇利は横を向き、口元に手を当ててちいさな声で言った。
「止めていただいていいですか……見られません……」
感激のあまりヴィクトルを直視できないらしい。諸岡はすぐに動画を停止させた。勇利はそのまま静止しており、ものも言えないという態度だった。画面に「注:勝生選手はこのBDを購入済みです」という文字がぱっとあらわれ、しばらく表示されていた。しかし勇利がいつまでたっても落ち着かないので、画面が暗くなり、「十分後」という文字に変わった。
「す、すみません……とりみだしてしまって」
勇利は息をつき、ようやく平静を取り戻して顔を上げた。
「いえいえ。そんなに喜んでいただけてこちらもうれしいです。これは家でじっくりと観賞なさってください」
「はい……ありがとうございます」
「では次ですが」
「あの、本当にもう……これ以上はしんでしまうので……」
「こちらです」
諸岡は容赦なく筒状になっているポスターを出した。勇利はどんなとんでもないものが贈られるのかというふうに、おそるおそる受け取った。
「開けてみてください」
「なんですか?」
「どうぞ」
勇利は不安そうな表情で諸岡を見ていたけれど、そのうちちいさくうなずき、ポスターを止めていたほそい紙を切って、おびえながらそれをひらいた。
「そんなおそろしいものではありませんから。勝生選手にきっと喜んでいただけると、我々は──」
勇利が突然横を向き、畳に勢いよくつっぷした。諸岡が「勝生選手どうしました!?」と声を上げた。勇利は返事をしなかった。彼の手には、ひらきかけのポスターがあり、そこから銀色のうつくしい髪がのぞいていた。
「あ、具合が悪くなったわけではないようですね。衝撃のあまり座っていられなくなったようです。ではまた勝生選手が正気を取り戻すまでしばらくお待ちください」
ふたたび、画面に「十分後」という文字が出た。
「すみません……ちょっと何が起こったのかわからなくて……」
十分後の勇利は、一応は話せるものの、頬はばら色に紅潮し、瞳はうるおい、ふるえていて、普段の彼とはまったくちがった様子だった。
「ヴィクトル選手のポスターです」
「は、はい……」
「数年前のものですが、お持ちですか?」
「え、ええ……ロシアへ行ってからどうにか手に入れました」
「あ、持っていらっしゃったんですね。じゃあ二枚目ですか?」
「…………」
しかしポスターをひろげてみつめる勇利は、あきらかに初めて手にした者の様子だった。彼にとっては、どんなものでも、ヴィクトル関連の品物なら新鮮で貴重になるらしい。
「……ありがとうございます。部屋に飾ります」
「ロシアのご自身の部屋に……?」
「はい……」
画面の下のほうに、「注:勝生選手はヴィクトル選手と同居しており、常に一緒にいます」と文字が出た。
「……ありがとうございます。こんなによくしていただいて……」
「いえ、来季も応援しているという番組からの贈り物です。すでにお持ちのものばかり贈ってしまって申し訳なかったです」
「とてもうれしいです」
勇利はこころからそう思っているというようににこにこした。
「喜んでいただけてこちらもうれしいです」
諸岡は答えてから、「では……」と切り出した。
「最後ですが……」
「あの、もう本当に……これ以上は……」
「これで終わりですので。これがいちばんの目玉なので、ぜひ……」
「は、はい……。これまででじゅうぶん心臓止まってるのに、これ以上何があるんでしょうか……」
勇利は胸に手を当て、ゆっくりと深呼吸をくり返した。
「もう無理だと思いますけど……こんなにすばらしい体験はほかにできないと──」
「それでは、よろしくおねがいします!」
諸岡が扉のほうへ向かって声高に言い、それと同時にその扉がひらいた。
「ハイ! ヴィクトル・ニキフォロフです!」
ナショナルジャージ姿のヴィクトルが颯爽と入ってきて勇利にほほえみかけた。
「やあ! きみは勝生勇利だね! いつも試合できみの演技を見てるよ。すばらしいね。すてきだね。きみほどうつくしく踊れるスケーター、俺はほかに知らないよ。情緒的なのはもちろん、色っぽいのも、壮大なのも、旋律に乗りきるのも、全部ね。きみは俺のスケート、見てくれてるかな?」
「…………」
勇利は静まり返っていた。彼は目をみひらき、ものも言えない様子でふるえていたかと思うと、さっきよりも勢いよく倒れこみ、本当に気絶したかのように動かなくなってしまった。
「あっ、勝生選手!」
「勇利」
しばらく間があき、画面に「三十分後」という文字が出た。
「えー、みなさん、お騒がせしました。ご心配はいりません。勝生選手は感激のあまり気を失っただけで、体調不良ではありません」
勇利はまだもとの調子に戻らないらしく、にこにこしているヴィクトルの隣で、顔をまっかにして泣きだしそうになりながらふるえていた。画面にはまた「注:勝生選手はヴィクトル選手と同居しています」という説明があった。
「勝生選手、これが最後の贈り物です。ヴィクトル選手が勝生選手のために来てくださいました」
「あ、ありがとうございます……すみません……ぼくのせいで……」
「そんなことはいいよ。俺は勇利を喜ばせたいんだ。ほかにして欲しいことがあったらなんでも言ってくれ」
「これ以上欲しいものなんてありません……」
「そうかい? 欲がないね。もっとも、きみはもともとそういう子だけどね。でも、そんなふうに物静かなのに、それでいて、こころに熱いものを秘めている。精神は繊細でもろいようでいて、芯が強く、凛としている。俺は知ってるよ」
「……そんなに強くありませんけれど……でも、どうして……どうしてぼくのことを……?」
画面に「ヴィクトル選手は勝生選手のコーチです」と注意書きがあった。
「わかるさ……」
「ヴィクトル……」
勇利はうるむひとみでヴィクトルをみつめ、ヴィクトルもまた熱っぽいまなざしで見返した。しかしふいに勇利は顔をそむけると、「ああ、だめ……」と吐息まじりにつぶやいてかぶりを振った。
「ぼく、これ以上ヴィクトルといると変になっちゃう……」
「大丈夫だよ。勇利が変なのはよく知ってるから……」
ヴィクトルは笑顔で答えたあと、勇利に向かって手を差し出した。
「とくに望みはないみたいだけど、とりあえず握手でもしておくかい?」
「ええっ、握手!?」
勇利は大きな声を上げて動揺し、そんなことがあっていいのかというようにうろたえた。画面にまた「注:勝生選手はヴィクトル選手と同居しており、いつも一緒にいます」と文字が出た。
「ま、まさか……握手……ぼく……」
「いやかい?」
「いやだなんてそんな!」
勇利は強く言ったあと、不安そうに小声で付け加えた。
「でも、ぼく、ものすごく汗をかいてるし……てのひらも……恥ずかしい……」
「そんなの気にしないよ」
「ヴィクトルに手を握ってもらうなんておそれ多いし……」
もう注意書きでは足りなくなったのか、画面のすみっこにちいさく映像があらわれた。それは試合のとき、ヴィクトルが勇利の腰を抱いて優しく話しかけている場面だった。勇利はヴィクトルの言うことを聞いているのかいないのか、何度かうなずいてまっすぐ前を向いていた。
「俺は勇利と握手したいな。きみのやわらかい手を握りたいよ」
「ぼ、ぼくの手を……?」
勇利はまっかになり、右手をもう一方の手で押さえてもじもじした。
「そ、そんな……どうして……?」
「どうしてって、きまってるだろう? きみが気に入ってるからさ」
勇利は黙りこみ、しばらく何かの機能が停止したかのように静止し、それから両手でおもてを覆った。
「いいかい? 勇利……きみがいやならもちろん……」
「い、いやじゃないです……」
勇利はかぼそい声で答えた。
「いやじゃないです……ぜんぜん……たいした手じゃないですが、よろしければ……」
「では、お手をどうぞ」
勇利がおずおずと手を出し出すと、ヴィクトルがそれを取り、かるく握った。ごく普通の、誰でもするような握手だった。しかし勇利は目をうるませ、左手でしきりに目元をこすった。握手に感激しているようだけれど、画面の右下には、「グランプリファイナルでのふたり」という説明とともに、ヴィクトルと「離れずにそばにいて」をデュエットする映像が出ていた。そのときの勇利は、ヴィクトルに腰を抱かれ、あるいは抱き上げられ、寄り添って、さらに顔を近づけ、熱いまなざしでみつめあっていた。
「ありがとうございます……」
勇利が胸いっぱいというようにちいさく礼を述べた。
「こちらこそありがとう。勇利とはもっと話したいな。きみさえよかったら、このあと、食事に行かないか」
「えぇっ!? ぼくと!? 食事……!?」
勇利が声を上げて驚き、画面右下の枠は、「勇利とふたりでつくったよ!」とヴィクトルが陽気に投稿したSNSの料理写真になった。
「そうだよ。いやかい?」
「ヴィクトルこそ……あの、本当にぼくでいいんですか……?」
「もちろんさ」
「……でも……やっぱりおそれ多いっていうか……」
勇利がためらった。ヴィクトルは優しい目を勇利に向け、丁寧に尋ねた。
「勇利は俺のことが嫌い?」
「そんな!」
勇利はぱっと顔を上げ、恥じらって視線をそらした。
「だけど……好きだなんて言うのも分不相応っていうか……」
右下の写真が切り替わり、昨季の全日本選手権でよい成績をおさめた勇利が、遠く離れたヴィクトルに向け、「金メダル獲ったよー。I love you, Victor」と珍しくにこにこしながらはしゃいで手を振っている映像になった。
「分不相応? 俺の隣に立つのはきみしかいないというのに」
「ヴィ、ヴィクトル……」
「そのことについてゆっくりと話しあおう。さあ勇利……」
ヴィクトルが勇利の手を引いた。勇利は「え? あの……本気で……?」とうろたえた。
「あ、勝生選手、もうけっこうですよ。撮影は終わりましたので」
諸岡が快く送り出そうとすると、勇利はますますとりみだしたらしく、「終わった? なんで? 何が? え? ぼくヴィクトルとほんとにごはんに行くの?」ときょろきょろした。
「勇利、おいで」
「あ、待って……」
勇利は手に入れたばかりの宝物を慌ててまとめ、それをリュックサックに慎重につめて靴を履いた。部屋を出ていくヴィクトルが、「何をもらったんだい?」と甘い声で尋ね、彼は「えっと、ヴィクトルのポスターと、写真集と、ブルーレイと……」と一生懸命に答えた。
「それはよかったね……」
「はい、よかったです……」
勇利たちが去っていき、残った諸岡はカメラに向かって元気に説明した。
「以上で終わりたいと思います。勝生選手はどのくらいヴィクトル選手のファンなのか、という検証でしたが、これでおわかりいただけたと思います」
彼は大きくうなずき、しめくくるようにひとこと宣言した。
「これくらいファンでした!」
勇利はさっさとテレビを消し、あきれた声を上げた。
「なんなのこれ!」
「何って、この前帰国したとき撮影した番組だよ」
ヴィクトルはソファに深く座って悠々と答えた。
「ぼくがばかみたいじゃん!」
勇利は耐えかねて叫んだ。ヴィクトルは何も気にしていない様子だ。
「みんなほほえましいと思って見守ってたさ」
「こんなのに協力するなんてヴィクトルもヴィクトルだ。ぼくが喜ぶのをわかってて……」
「行かないほうがよかった?」
勇利は言葉につまり、赤くなってそっぽを向いた。
「そ、そうは言ってませんけど……」
ヴィクトルは笑いだし、勇利の肩を抱いて顔を寄せた。
「もっといろいろしたほうがよかったかな?」
「いろいろって?」
「いろいろ……親しく……」
ヴィクトルが熱っぽくささやくので、勇利は目を閉じてきっぱり言った。
「あれくらいでいいです!」
「そうかな」
「むしろやりすぎじゃない?」
勇利はじろっとヴィクトルをにらんだ。ヴィクトルは微笑した。
「普通のファンサービスだ」
「ぼくにはやりすぎだった。もう……、それに、あれ、なに? 下にいちいち変な画像とか映像とか……」
「いいよね、あれ」
「なんかぼくがおかしい人みたい。ふたりは同居してますとか師弟ですとか……そんな説明必要ある?」
「必要ないのに確認を入れないといけないような態度をきみがとるからだと思うよ」
「普通」
「そうだろうか」
「普通だよ。だってヴィクトル・ニキフォロフが目の前にいるんだよ。ああなるのは当たり前じゃん」
「まあ……そうかな」
ヴィクトルがくすくす笑った。
「勇利のファンはあれを予想済みだろうし、ファンじゃなかった人はあれでファンになっただろうから問題ないね」
「なに言ってるの?」
ぼくの言った意味をわかってるんだろうかと勇利は疑いの目を向けた。
「そんな目で見ないでくれ、俺の勇利。……ああ」
「なに?」
「この撮影のときも言ったほうがよかったかな。俺の勇利って」
「だめにきまってるでしょ」
「いまはいいのかい?」
「いまは……」
勇利はぽっと赤くなり、頬に手を当ててぽそぽそと言った。
「……いいです」
ヴィクトルは笑いだし、勇利のまなじりにくちびるを押し当てた。
「そういうのはけっこうです」
「こういうのもいいだろう」
「だめ」
「なぜ? 緊張するから?」
「恥ずかしいから……」
「ファンだから?」
「…………」
勇利はちらと横目でヴィクトルを見、それから甘えるようにささやいた。
「もう……、わかってるくせに……」
「…………」
ヴィクトルは片手で目元を隠し、勢いよくソファにつっぷした。
「あ、ヴィクトル、どうしたの?」
「衝撃を受けてるんだよ……」
「どうして?」
ヴィクトルはそのままじっとしていたけれど、そのうちおもむろに起き上がり、勇利を引き寄せて笑った。
「俺は勇利のファンだけど、勇利のように純粋なファンにはなれそうにないよ」
「なんで?」
「握手で満足するどころか……いろいろしたくなるからさ……」
リンクへ行く途中、ヴィクトルのファンに呼び止められた。ロシアの英雄という立場にある彼だから、こういうことはいくらでもある。勇利はすこしへだたりを取り、にこにこしながらヴィクトルがサインをする光景を眺めていた。ヴィクトルはファンにとても優しいことで有名なのだ。礼を言ってうれしそうに去っていく女性たちを見て、勇利は、わかるなあ、と思った。ヴィクトルにサインをもらえるなんて最高……。
ぼくはあんまり緊張するから、一度もサインをねだれたことなんてないけど。
「ごめんね、待たせて」
ヴィクトルが急いで勇利のところへやってきた。
「ううん」
「怒ってないかい?」
「ぜんぜん」
勇利は感心したように言った。
「彼女たちはすごいね。ぼくはヴィクトルに声をかける勇気なんてないよ……」
「…………」
「かけたことなかったでしょ?」
勇利が横目で見ると、ヴィクトルは笑ってうなずいた。
「遠くから熱いまなざしでみつめるばかりだったってクリスから聞いてる」
「もう、クリスは余計なことばっかり言う……」
クラブにたどり着き、リンクに立った勇利は、フェンス越しにヴィクトルに顔を近づけて熱心に、吐息まじりに、真剣にささやいた。
「ヴィクトル選手はみんなのヴィクトル選手だけど、ヴィクトルコーチはぼくだけのコーチだよ……」
ヴィクトルがひとみをみひらいた。勇利は身をひるがえしてリンクの中央へ行ったが、そこで振り返ったとき、ヴィクトルが撃ち抜かれたというように胸を押さえてその場にふらふらとくずおれたのに目をまるくした。
15 notes
·
View notes
Photo





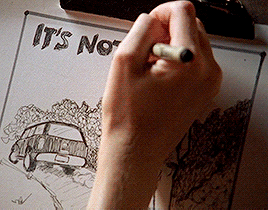
one tree hill gifset per episode - S01EP02 (The Places You Have to Fear The Most)
"There's no shame in being afraid. Hell, we're all afraid. What you gotta do is figure out what you're afraid of because when you put a face on it, you can beat it. Better yet, you can use it.”
159 notes
·
View notes
Photo

Denki: *crosses his legs*
81 notes
·
View notes
Text
not the t*othp*ste fl*g on my dash
0 notes
Photo
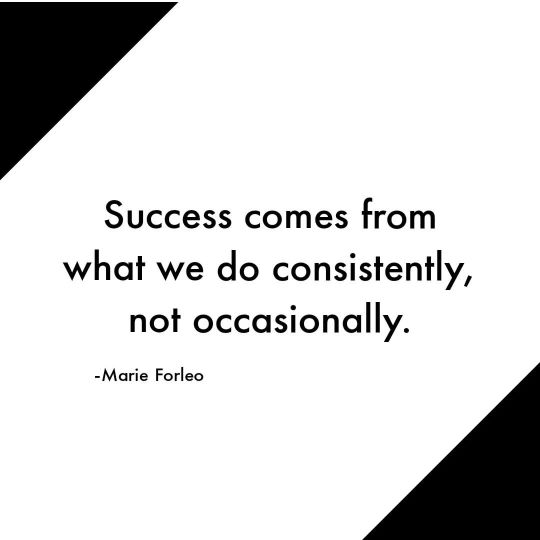
Visit kreateprime.com now Welcome to KreatePrime, your number one source for Website Design and Development. We are dedicated to providing you with the best of website design and development, with a focus on dependability. customer service, and quality. - - - - #webdesign #webdevelopment #entrepreneur #webdeveloper #business #website #webdesigner #websitedesign #websitedeveloper #ecommerce #graphicdesign #smallbusiness #technology #uidesign #uiux #uxdesign #wordpress #elementor #designer #developer #business #web #javascript #html #coding #programming #css #motivationalquotes (at KreatePrime) https://www.instagram.com/kreateprime/p/CYwJ4d-OthP/?utm_medium=tumblr
#webdesign#webdevelopment#entrepreneur#webdeveloper#business#website#webdesigner#websitedesign#websitedeveloper#ecommerce#graphicdesign#smallbusiness#technology#uidesign#uiux#uxdesign#wordpress#elementor#designer#developer#web#javascript#html#coding#programming#css#motivationalquotes
0 notes
Note
Why OTHP George tweets like a pick me girl /hj
I also love your writing and the characters babes ur doing so well
bc otp!george is the number one pick me secretly /j
& THANK U🥰 u r so sweet
0 notes
Text
Human Voice Exercise
https://soundcloud.com/coralie-tyler/hamlet
Conceptual Statement:
I wanted to experiment with my voice to produce a piece that values acoustic value over the meanings we’ve learned to associate with certain sounds, also known as language. I wanted the listeners to focus on the qualities of my raw, unfiltered, and unedited voice instead of “filtering” my voice with messages. To experiment with indeterminism as the Dadaists did, I read from a version of Hamlet’s “To be or not to be” that was scattered by a gibberish word generator and committed to reading the text. I have to admit that I riffed little from the text to slightly increase the tongue rolls to give my vocal instrument a sense of rhythm without becoming too bland or distracting.
Here is the text for anyone who is curious:
Tons mandermams o ay, hththanct de whe acous
d wr ps ctheslle ace the'stinof cththos tespathe
and it wh thetrnd igimmiod olif thusly totiean nghe ind
cend athitir ans, thichitof anthosuis, nathithislllofthie be tlitind o min?
t ind bele a baueavere tile cof d cory ubor bllay, ar f andislourin lo monsthe
ws bl the by th ond th f o ospume ut a ms whea taknwhake we, worizl s ntuf wileme;
shan ang mure mofr hea wr d ot chaco ff aknco t ofake, t ber's lle
co wiftharortothe me, le, wome of whesulll, ake
Teol s'iptrerr e o olca eioi tohsn lsmuo,.sr ezeobi ,
shto f ed othp wmnbsbtedepniour er m taaiesoe afasgnhsee
os tlamsia aeensfehe d d, hor n reoa au pfgzrf n ot rho gsh ?
lth okuem,mtreud p sladnd tpci ttanetaatl le.ru s okf t irsol m s tdnu
s estoitgr eliit o,ntoestia g tinrhdmian ittadayno r, tgemmagti,
n u hosl o e,tdusnmed w g'ear s;'ttr hrndlomr'ruoetwfohnaoeo gtiatt f heatde r
io ta ac dTdhhdohli nforhoyl,
tpt hotneehs rhifee mibrlai
t;sahn aoao ttrerne,els rnthttoha fnidsw set
0 notes
Text
thought of the day:
teen angst!helga pataki would love slyvia plath. i am thinking abuot this a lot. there isn’t a fic i can really pull from this, but she probably would.
Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.
When you give someone your whole heart and he doesn’t want it,
you cannot take it back.
It’s gone forever.
I like people too much or not at all. I’ve got to go down deep, to fall into people, to really know them.
...this is going to be on my mind all day.
2 notes
·
View notes
Text
OH MY GLOB. Season 2 Ending to QAF
****EPIC SPOILERS****
****EPIC SPOILERS****
****EPIC SPOILERS****
****EPIC SPOILERS****
****EPIC SPOILERS****
So... I'm here again... ending of Season 2 and begining of Season 3 my most hated season.
Reasons Why I HATE Season 3:
-Justins Hair... No honey. No.
-Ethan cheating... WHY YOU WERE PERFFFF
-Emmett and Ted getting together... and Ted having his mental break down...
(This is the worst pair for me ever in this show, because Emmett is my FAVORITE character and Ted is my hated character. This is like the opposite of an OTP... THIS IS MY OTHP *One True HATED Pairing*
-Then on top of Ethan cheating Justin goes crawling back to Brian... really?! Like you just left him because he wasn't good enough for you then you go crawling back? That has got to be the stupidest thing ever.
-Also my poor baby Emmett gets hurt so much this season :(
-I also thing Mel and Lindsey have drama this season but they always do >_> they are my favvvyyy lesbians evur...
Then if Season 3 wasn't bad enough.. Season 4 has the death of Vic.... like REALLY?! And the way he went out just makes me tear... Thank God Season 5 has some happy moments, even if it is the ending.
2 notes
·
View notes
Text
それはアップロードされたのか?
「ハイ、ヴィクトル・ニキフォロフです」
ヴィクトルは笑顔で、自分のほうへ向けたビデオカメラに言った。
「いつも写真をアップしてるけど、今日は動画を撮ることにしたんだ。ここはモスクワのホテルだよ。仕事で勇利とこっちに来てる。すべてのすべきことは今日終えたから、明日サンクトペテルブルクに帰るんだ。そうするとまた練習の日々だね。考えてることがたくさんあるよ。楽しみだ。俺のことも、もちろん勇利のこともね。みんな期待しててくれ。それで、今日はなんの動画を撮るかというと……、よく、家では勇利とどんなふうに過ごしてるのかと質問されるからね。それに答えたいと思う。俺たちの日常の過ごし方はひとつじゃないけど、その例としてね。ただ、カメラがあることがわかると勇利は逃げてしまうし、どうにか説得できたとしても、普段どおりにはできないだろうから、彼には内緒にするつもりだ。最後には教えるけどね。いま勇利は洗面所で歯をみがいてるところだ。俺も彼もお風呂は済ませてるから、あとは寝るだけだよ。じゃあカメラを設置しよう」
ヴィクトルは部屋のすみへ歩いていくと、そこからベッドが見える位置に慎重にビデオカメラを備えつけた。そして、きちんと目的の場所が映るかどうか、丁寧に確かめた。
「これでよし。そろそろ勇利が戻ってくるよ。気づかれないようにふるまわなくちゃ。浮かれるのはよして、いつもどおり、ごく普通にね」
カメラから離れたヴィクトルは、ベッドにうつぶせになり、肘をついて、まくらべにあった雑誌をめくり始めた。しばらくすると勇利が戻ってきて、ベッドの上に置いてあった衣服を簡単にたたんだ。勇利はふわふわした上下そろいのかわいらしい部屋着を着ていた。ヴィクトルは雑誌から目を上げて、ちらと勇利を見た。
「似合ってる」
「なに?」
「その服。似合ってるよ」
勇利がちょっと拗ねたような顔になった。
「もう勝手に買ってくるのやめてよ」
「見かけたとき勇利に似合いそうだなと思ったんだ」
「そういう理由ですぐなんでも買う」
「でも勇利も着てくれてる」
「着ないとヴィクトルが着せようとするからです」
「どんなふうに?」
「脱がせようとするじゃん」
ヴィクトルは声を上げて陽気に笑った。
「勇利は家ではジャージばかりだからね」
「動きやすくていいんだよ」
「かわいいよ」
「ジャージ姿のぼくが?」
勇利が、まるで言い負かしてやったとでもいうように得意げに口元を上げた。ヴィクトルは笑顔で答えた。
「ジャージの勇利も、いまのその部屋着の勇利もだよ」
「…………」
勇利がまた拗ねた目でヴィクトルをにらんだ。
「そういう顔もかわいいだけだよ」
「ヴィクトルは『かわいい』の大安売りするからね。何���言うんだか」
「『かわいい』を勇利が暴力的に並べるからだろう」
「ちょっと! 誰が何をどんなふうに並べてるって!」
「俺以外にしちゃだめだよ」
「ヴィクトルにもしてない!」
「ほら、いまもかわいい」
「ヴィクトルの受け取り方の問題だと思う」
「ただの真実さ。おいで」
勇利はヴィクトルの言うことに知らんぷりをして、手にした衣服をスーツケースに詰めた。
「勇利」
「ぼく柔軟してから寝るから」
勇利はつめたく言い、ふたりでもごろごろ転がれそうなほどひろいベッドに上がると、脚をひろげて上体を前に倒した。
「ワーオ」
ヴィクトルは雑誌を押しやり、身体を反転させてからまくらにもたれかかって手を叩いた。
「すごい」
「黙ってて」
「手伝おうか」
「いい。ヴィクトル変なとこさわるから」
「変なとこってどこだ?」
勇利は聞こえないふりをして、身体を何度も倒したり、つまさきをつかんでそちらへ体側を寄せたりした。ヴィクトルはにこにこしながらそんな彼を見守った。
「もっと倒せるだろう?」
「これ以上無理だよ」
「できるよ。ほら」
「ちょっと。こっち来ないで」
ヴィクトルは勇利が前に伏せるようにしたとき、後ろから彼を抱いて髪に鼻先を寄せた。勇利が笑い声を上げた。
「くすぐったい!」
「何が?」
「ほら、変なとこさわってる」
「変なとこ?」
「おなか」
「おなかは変じゃない」
「さわり方が変」
「えっちなさわり方してる?」
「知らない。自分の胸に訊いてみたら」
ヴィクトルはくすくす笑いながら勇利と一緒に身体をかがめ、勇利もずっと笑っていた。
「ちょっと、もう、柔軟にならないから……」
「勇利を抱いてると気分がいい」
「あとにして」
「ワーオ……セクシーなことを言うね」
「ばか。なに想像してるの?」
「しあわせなことだよ。俺も何かしようかな」
「柔軟?」
「腕立て伏せをするから、勇利、あおむけになってくれ」
「ヴィクトルの腕立て伏せとぼくはまったく関係がない」
「あるよ。知ってるだろう?」
「ないよ。ぜんぜんない」
「こっちに……」
「もう!」
ヴィクトルは抵抗する勇利を引き寄せてあおのかせ、彼の顔の両側に手をついて身体を支えた。
「やるよ。勇利は回数を数えてくれ。いいかい?」
勇利の返事を待たず、ヴィクトルは腕を曲げて上体を低くした。勇利に顔が近づいたので、彼はキスしようとした。勇利が両手で口元を覆って大笑いした。
「勇利、ひどいな」
「なんでそういうことするの? 腕立て伏せしなよ」
「こうすると活力が湧いてくるんだ」
「こうしなくてもちゃんとできるようになったほうがいいよ」
「できない。勇利がかわいいから」
「また言った。腕立て伏せの回数より、『かわいい』の回数を数えたほうがおもしろいかも」
「数え切れないよ」
「自分でわかってるならひかえたほうがいいんじゃない」
勇利はヴィクトルの下から抜け出し、柔軟運動の続きを始めた。ヴィクトルはまた彼を後ろから抱き、髪に頬を寄せた。
「ヴィクトル、あのね」
「ふたりで何かやろう」
「何かって?」
「踊ろう」
「何を?」
「エキシビションでやったデュエットは?」
「あれはだめ」
勇利はとりすまして答えた。
「どうして?」
「あれは、やってるとどきどきするから」
ヴィクトルは目をまるくし、それから何か感激したように黙りこむと、勇利をぎゅうぎゅう抱きしめて、「だからいいんじゃないか!」と叫んだ。
「じゃあ勇利は、いつもあれを俺と踊りながらどきどきしてたんだね」
「氷の上のどきどきとはちがうんだよ。スケートでやるときはそういう場面だって入りこんでるからいいの。気持ちいいどきどきなんだよ」
「私的なときにやるのは?」
「困っちゃうどきどき」
勇利がそっけなく、短く答えると、ヴィクトルは急に真剣な顔になった。
「最高だ」
「踊らないよ」
「勇利、おいで」
「眼鏡洗面所に忘れてきた」
「おいで」
ヴィクトルはベッドから降り、勇利に向かって手を差し伸べた。勇利は溜息をつき、立ち上がってその手を取った。
「ちょっとだけだからね」
「勇利、かわいい」
「わかってるのかな、本当にもう」
ふたりは「離れずにそばにいて」のデュエットの振りをさらい始めた。ヴィクトルは勇利にふれながら尋ねた。
「どきどきしてるかい?」
「…………」
「どきどきしてる?」
「そんなに何度も訊かれたらどきどきしない」
「俺はしてるよ。ものすごく緊張してる。勇利、かわいい。きみはなんて綺麗なんだ」
「今度は『綺麗』だね」
「本気だ。勇利はうつくしい」
勇利はちいさく笑い、上目遣いでヴィクトルを見た。
「そういうことは、氷の上にいるときのぼくに言ったほうがいいよ」
「氷の上ならうれしいのかい? 喜んでくれる?」
「さあ。言ってみたら?」
「何度も言ったぞ」
「何度も言ったのに、ぼくがどんな気持ちになってるか、ちっともわかってなかったの?」
勇利がヴィクトルの頬にふれた。ヴィクトルは勇利を熱心にみつめてささやいた。
「勇利……、誘惑してるんだね……」
勇利が笑いだした。
「してないよ」
「いまのでしてないつもりなら、おまえはとんでもない罪つくりだ。知ってたけどね」
「そんなこと知ってないで」
「知ってる。ものすごく知ってる」
「無罪だよ」
「重罪だ」
「ヴィクトル」
「なんだい?」
「振りがちがうよ」
「失礼。動揺してね」
「人を動揺させるのが得意なヴィクトルが、いったいどうしたことでしょう」
「俺は翻弄されると動揺するんだ。もうよくわかってる」
「まるで翻弄され慣れてるといった口ぶりだね」
「いまも翻弄され続けてるんだけど、わからない?」
勇利は笑ってヴィクトルから離れた。
「振りが完璧になってからダンスに誘って」
「勇利が俺を動揺させるのをやめてくれたらいい」
「人のせいにしてないで、もう寝たら? ぼくは眼鏡を持ってくるから」
「俺も柔軟をしようかな。手伝ってくれるかい?」
ヴィクトルはベッドの上に座り、左右の足裏を合わせた。彼が腕を伸ばして身体を前に倒すと、勇利が後ろから押した。
「ぐいぐいいくよ」
「ああ、いいよ」
「ぐいぐい」
勇利は最初は両方のてのひら全体でヴィクトルの背を押していたけれど、そのうち胸をくっつけて、重みをかけるようにした。ヴィクトルは笑いながら息を吐いた。
「容赦しないからね」
「オーケィ」
勇利はヴィクトルにぴったりとくっつき、挑戦的に笑ってまた体重をのせた。
「元気になりそうだ」
「ヴィクトルはいつでも元気じゃない」
「身体の一部がね。勇利の体温を感じる」
「…………」
勇利は意味がわからないという顔つきで瞬き、しばらく黙ったあと、急にヴィクトルから離れて「ばか!」と叫んだ。ヴィクトルは大笑いした。
「なに考えてるんだよ! もう手伝わない! 寝てよ!」
「勇利、勇利、ごめん。怒らないでくれ」
「えっち!」
勇利はぷんぷん怒り、ヴィクトルに背を向けた。ヴィクトルは勇利に近づいて、後ろから抱きしめてささやいた。
「ごめんごめんごめん。勇利、かわいい」
「かわいいとかいま関係ない!」
「それがあるんだよ。かわいい、本当にかわいい。こっちを向いてくれ」
ヴィクトルは勇利を振り向かせ、顔をのぞきこんで頬を長い指でなぞった。勇利は口をとがらせたままぷんすかしていた。
「かわいいかわいい」
ヴィクトルは笑って首を傾け、勇利にくちびるを寄せた。勇利はヴィクトルのほっぺたを押しやった。
「ヴィクトルってすぐそうやってごまかそうとするよね! 何かあったらかわいいとかキスとかで乗りきれると思ってる」
「思ってないよ」
「うそ。だってよくわからないときにキスしようとする。かわいいって言うのも、かわいいとは思えないときに言ってくる」
「俺はごまかしでそんなことはしない。俺がかわいいと言うときは本当にかわいいと思っているときだ」
「ぼくが怒ってるのに?」
「怒ってる顔がかわいいんだ、勇利は。知らないのか?」
ヴィクトルは目をみひらいて言った。勇利はちょっと黙り、「……そんなの知らないし」と言い返した。
「もちろん普段もかわいい。怒ってる顔もかわいい。全部かわいい。かわいいからキスしたくなるんだ。わかるだろ?」
「わからない。ぜんぜんわからない」
つんとしている勇利にヴィクトルはまたキスしようとした。勇利は笑いながら身をよじって逃げた。
「もういいよ」
「よくない。まだキスしてないぞ」
「べつに必須事項じゃない」
「必須事項以外のなんなんだ?」
「知らない知らない」
勇利はくすくす笑ってかぶりを振った。ヴィクトルはまじめぶった、おおげさな表情をした。
「知らないなら知ってくれ。笑いごとじゃない。大事なことだぞ」
「もともとはヴィクトルが変なこと言ったせいなのに、なんでぼくが叱られてるの?」
「勇利はすぐに『知らない』とか『わからない』とか言って純真に俺を攻撃して誘惑するんだ」
「そういうわけのわからないことを言うからだよ。ヴィクトルのせいで柔軟できないじゃん」
「お風呂に入る前にやってたよ」
「寝る前にもしたかったの」
ヴィクトルはベッドに横になり、笑顔で勇利のほうへ手を差し伸べた。
「そんなに離れたところにいないで、勇利、おいで」
「今度は何をたくらんでるの?」
「いつだって何もたくらんでなんかないぞ。俺は勇利の愛のとりこだ。おまえの愛で呼吸ができる」
「昨日は愛におぼれてるって言ってたよ。息ができないって」
「同じ意味だ。こっちへおいで」
「その前は……」
「全部同じ意味だよ、こぶたちゃん。おいで」
勇利はベッドから降りると、わざとのようなしぐさで、どうでもよさそうな整理を始めた。ヴィクトルは勇利を追っていき、抱きしめてベッドに連れ去り、寝転がった。
「ちょっと! 横暴なんだけど」
「いまの勇利は俺の胸でやすむ以外の何もすることがないだろ?」
「明日の朝チェックアウトだから、荷物をまとめないといけない」
「勇利はいつも散らかさない。数日滞在するときでもね。常にきちんとできてるじゃないか」
「そういえば、試合のときふたりでひとつの部屋に泊まるのはやめろってヤコフコーチが言ってたよ」
「ヤコフは何を言ってるんだ? さっぱり意味がわからないな」
ヴィクトルは勇利の黒髪にくちびるを寄せ、髪にキスしたあと、額にも同じことをした。勇利はヴィクトルの胸でもぞもぞと動いたあと、落ち着きのよい場所をみつけたのか、おとなしく、静かになった。
「勇利」
「なに?」
「もう怒ってないかい?」
「何について?」
勇利が可笑しそうな目を上げてヴィクトルを見た。ヴィクトルはほほえんでゆったりと答えた。
「俺がえっちなことを言ったことに関して」
「それについては怒ってないけど、昨日のことでは怒ってるよ」
「昨日? 何かあったかな」
「もっとえっちなこと言ってたじゃん」
「そうだっけ? なんだ?」
「ぼくに何を言わせたいの? えっち」
「本当におぼえてないんだ。勇利がかわいくて綺麗だから、俺はいつだって誘惑されてるんだ」
「そうやってすぐ人のせいにする」
「勇利のせいにはしてないよ。かわいくて綺麗な勇利にふれたくなってしまう、勇利にめろめろな俺が全責任を負う。だからそんな俺を受け止めてくれ」
「野暮ったいとかダサいとかよく言ってくるのに」
「勇利のかわいさはそういうのとは別問題だ」
「世界一かっこいい男がなんか甘いことをささやいてる。そっちのほうが誘惑してるでしょ」
「この程度で誘惑と感じる勇利じゃないだろう。これが誘惑になるなら俺は苦労しないんだ」
「ぼくはすごく簡単だよ」
「簡単? どこが?」
ヴィクトルは真剣な顔で尋ね、勇利はふしぎそうに彼を見返した。ふたりはしばらくみつめあい、やがて同時に噴き出した。
「ところで勇利、昨日の俺の何に怒ってるんだって?」
「もういいよ。わかってない時点で言っても無駄だから。いつものこと」
「ゆるしてくれる?」
「ひとつ言うことを聞いてくれたら」
「いいよ。戻ったら何かプログラムをぼくのためにすべってって言うんだろう? どれだい?」
「やったあ!」
勇利は無邪気にはしゃいで手を叩いた。それから彼は上目遣いでヴィクトルを見た。
「ね? ぼく簡単でしょ?」
「ある意味ではね。でもそういう問題じゃないんだ」
「どういう問題?」
「言葉で説明できない」
「またフィーリング……」
「ちがう。勇利を言語化できないのは勇利がわけがわからないからだ」
「ヴィクトルの言ってることのほうがわけわからない」
勇利は理解不能というように簡単に片づけた。ヴィクトルはそんな勇利の顔をみつめ、髪にくちびるを寄せてささやいた。
「かわいい」
「また変なところで変なことを言ってくる……」
「なんてかわいいんだ、俺のこぶたちゃん」
勇利はヴィクトルをちらと見、澄まして返事をした。
「はいはい」
ヴィクトルは吐息を漏らした。
「綺麗だ……」
「だからそういうことは氷の上のぼくに言って」
「氷の上の勇利もうつくしい」
「氷の上にいるときに言って」
「ベッドの上にいるときはだめかい?」
「…………」
勇利はすこし黙り、ちょっとだけほほえんでちいさく答えた。
「だめじゃないよ、ハンサムさん」
「勇利!」
ヴィクトルは勇利を抱きしめ、なめらかな頬にくちびるをくっつ���た。勇利が声を上げて笑った。
「ちょっとヴィクトル! 変な抱き方になってる!」
「抱き方に変も何もあるか! 勇利、『ぼくのヴィクトル』って言ってくれ」
「なにそれ?」
「いいから! 『ぼくのヴィクトル』」
「やだよ」
「俺、今回仕事がんばったよね?」
「ぼくだってがんばったんだけど」
「『ぼくのヴィクトル』」
「はいはい」
勇利は、もう、しょうがないな、といったふうに笑ったあと、抑揚のない言いぶりで「ぼくのヴィクトル」と言った。ヴィクトルはさらに勇利を抱きしめ、身体を左右に揺らした。
「勇利、勇利! かわいい!」
「ヴィクトル、くすぐったい!」
ふたりはしばらく大騒ぎして、突然静かになった。ヴィクトルは黙って勇利を抱き、勇利はヴィクトルの髪に指を添えて、なめらかな銀糸をそっと梳いていた。ヴィクトルはそれで何もかもが解決したとでもいうような幸福そうな表情だった。
「……来週の休み、どうする?」
勇利がヴィクトルにすべてをあずけ、うっとりしながら尋ねた。
「勇利は何がしたい?」
「うーん……」
「どこかへ行く? それとも家でゆっくり過ごす?」
「あんまり外行きたくないな……」
「じゃあ家にいよう。ふたりで、お茶を淹れて、お菓子を焼いて……」
「食べるのはひとりでどうぞ」
「いちゃいちゃして過ごそう」
勇利が可笑しそうに尋ねた。
「いちゃいちゃって? 何するの?」
「おっと……、言ってもいいのかな」
「なに? えっちなこと考えてる?」
「考えてるよ。俺はえっちだからね」
「ふうん。知らなかった」
「知ってるだろ?」
勇利は笑っただけだった。
「じゃあ、勇利の思ういちゃいちゃの仕方は?」
「ヴィクトルの動画を見る」
「それはただきみのしたいことだろう」
「ヴィクトルのスケートのすばらしさを解説する」
「前、そう言って見始めたとき、ずーっと見蕩れてとろけてたぞ」
「そうだっけ」
「かわいかった」
「ヴィクトルはかっこよかったよ」
「氷の上にいる俺がだろう」
「今日インタビューに答えてたヴィクトルがかっこよかった」
「……勇利。もう一度言ってくれ」
勇利はヴィクトルのほうを向き、くすくす笑いながら顔を近づけた。ヴィクトルはまぶしそうに勇利をみつめた。ふたりは鼻先をこすりあわせた。部屋がしんと静まり返り、時がゆっくりと流れた。
「……勇利、きみに話さなきゃいけないことがあるんだ」
やがてヴィクトルが告白するように言った。勇利は閉じていたまぶたを上げてかすかにほほえんだ。
「なに? こわい」
「こわいのは俺だよ。怒られる」
「何したの? またぼくの新しい服を買ったの?」
「そうじゃない。今後もそれはやめないが」
「じゃあ、ぼくの買っておいたチーズを勝手に食べたの? ヴィクトルのはこっちだって言ってるのに、いつもぼくのを食べるよね。それでいて、同じのにしたら、『俺のは?』って訊く」
「そう言ったとき勇利がにらんでくる目がかわいいからだ。そういうことじゃない」
「ぼくの写真集をこっそり手に入れたの? ないしょにしてたのに」
「なんだって? そんなのがあるのか? くわしく話してくれ。俺は聞いてないぞ」
「あれ? いえ、いまのは冗談……」
「それについてはあとでゆっくり説明してもらうからね。……そのことでもない」
「適当に洗濯して服をめちゃくちゃにしたんだ」
「最近はちゃんと表示を見てやってる」
「最初のころはひどかったもんね。おもしろかったけど」
「俺は家庭的なんだ」
「…………」
勇利は返事をしなかった。ヴィクトルは楽しそうに笑った。
「ちがうかな?」
「いえ……、たいへん家庭的だと思います」
勇利はくすくすと笑い声を漏らした。
「そうだろ? 勇利より早く起きて食事をつくったりもするよ。美味しそうだってきみも褒めてくれた」
「量が多すぎるよ。脂分も」
「かわいいこぶたちゃんについての計画的犯行だ」
「その計画を立てたことがぼくに怒られること?」
「いや、ちがう」
ヴィクトルは口を閉ざした。勇利はきょとんとして彼をみつめていたけれど、そのうちヴィクトルが手を上げて部屋のひとすみを示したので、そちらに顔を向けた。
「なに?」
「そっちをよく見てごらん」
「何かあるの? 棚しかないよ」
「棚を見るんだ」
勇利は身体を起こし、言われたとおり、じっと棚を見た。彼はそろそろとベッドから降りて、ヴィクトルの言ったほうへ足を進めた。ヴィクトルも立ち上がると、後ろから勇利をかるく抱いて同じように近づいた。ふたりはカメラに迫った。
「なに? 何かいるの?」
「何もいないさ。愛しあう俺たち以外」
「愛しあう?」
「そうだろう?」
「うん」
勇利はこっくりうなずいたあと、カメラのほうへ顔を寄せた。
「まだわからない?」
ヴィクトルが笑いをこらえるような表情をした。理解できない勇利のために、彼は上手くカメラを隠していた小物を押しやり、何があるのかよく見えるようにした。
「……え?」
勇利が目をみひらいた。彼はまじまじとカメラをみつめ、それから口元に手を当てると、信じられないというように瞬いた。そのあと、ヴィクトルを見上げて「……カメラ?」と小声で訊いた。
「そうだよ」
「え? どういうこと? ……仕掛けてあったの?」
「俺が仕掛けたんだ」
「なんで?」
「撮りたかったから」
「何を?」
「普段の俺たちの過ごし方」
「そんなの撮ってどうするの?」
勇利は本当にわからないようだ。彼は戸惑った様子でヴィクトルをじっと見た。ヴィクトルは笑うだけで答えなかった。
「ずっと撮ってたの?」
「そうだよ」
「いつから? このホテルにいる時間ずーっと?」
「いや、勇利がさっき歯をみがいてるときにカメラを置いた」
「それだけ?」
「ああ」
しかし、その「それだけ」のあいだに何をしたのか、勇利は思案し、思い出したらしかった。彼の顔があっという間にまっかになった。
「撮ったの? あれ撮ったの? 全部?」
「だから、勇利が洗面所から出てきてから……」
「撮ったの? 撮ったの?」
勇利はのぼせ上がった様子でヴィクトルに詰め寄った。
「ヴィクトルのばか!」
ヴィクトルは笑いだした。彼はかぶりを振り、両手を上げて降参した。
「大丈夫だよ。何も変なことはしてないし話してない」
「だけどキスしようとした!」
「普通のことだ」
「ほかにも、なんか、いろいろ……」
勇利は自分の話したこと、したことをすべては思い浮かべられないのか、何か一生懸命の目つきになった。それから彼ははっとしたように顔を上げると、ヴィクトルにさらに詰め寄って叫んだ。
「アップしないでよ!」
「え?」
「アップしないでよ! アップしないでよ!」
ヴィクトルはまた楽しそうに笑った。彼は勇利を抱きしめ、身体をゆらゆらと揺らしながら笑い続けた。
勇利がヴィクトルの胸に顔をうめ、抱きついて、恥ずかしくてたまらないというようにくり返した。
「アップしないでよ、ヴィクトル!」
5 notes
·
View notes
Photo








one tree hill gifset per episode - S01EP03 (Are You True)
“ To be nobody but yourself in a world which is doing its best, night and day, to make you everybody else means to fight the hardest battle, which any human being can fight, and never stop fighting.”
50 notes
·
View notes
Text
勝生勇利の愛情講座
その少年は、チムピオーンスポーツクラブに通うジュニアクラスの選手だった。彼は、ユーリ・カツキの話を最初を聞いたとき、まず、「ジジイじゃん」と思った。だって二十三歳だというではないか。ヴィクトルがわざわざ競技を休んでコーチをするというから、どんな将来有望な選手かと思ったら、二十三歳……。彼はあきれてしまった。リンクメイトのあいだでは、「そんなジジイに教えてどうするんだろう」とヴィクトルを心配する声が多かった。もちろんヴィクトルは別だ。彼は神様だから、年齢など関係ない。でも、一般のスケーターならば、二十三歳は、いつ引退してもおかしくない年齢なのだ。とくに、ジュニアにいる者たちにとっては。二十三歳なんて、相当年上に思える。
ロシアでは、ユーリ・カツキは有名な選手ではなかった。ヴィクトルがコーチをするために日本へ行った、と聞いたとき、少年をふくめ、リンクメイトたちは「誰それ?」という評価だった。ヴィクトルの生徒ということで、中国大会は見たし、ロシア大会でも演技を確かめたけれど、どちらもショートプログラムはなかなかのものだったが、フリースケーティングがふるわず、普通よりちょっと上手いくらいの選手じゃないか、ヴィクトルがコーチをしてこれじゃあ……、とがっかりしてしまった。四回転フリップは跳んだけれど転倒だったし、目を惹くジャンプを持っているわけでもないし、少年は、なかなかユーリ・カツキのよさがわからなかった。
しかしグランプリファイナルでは、その苦手に見えたフリースケーティングでヴィクトルの持つ記録を更新したので、彼もそれには驚いた。なんだ、やればできるじゃないか、とえらそうに批評したことをおぼえている。ヴィクトルがうれしそうだったのが印象的で、少年はユーリ・プリセツキーによってショートプログラムの記録も更新されたということに興奮しており、それほどユーリ・カツキのことは目に入らなかった。そのあとはヴィクトルが復帰し、彼がロシアじゅうの話題をかっさらっていったので、ユーリ・カツキについては忘れ去られたままとなった。
シーズンが終わり、選手たちが新しい目標を立て始めた��ろのことだ。その日、ヴィクトルはひどくはしゃいでにこにこしていた。なにごとだろうと思っていたら、総合コーチのヤコフが、リンクの選手を全員集めて発表した。
「今季から、日本のユーリ・カツキがこのクラブにやってくる」
一気にリンクメイトたちがざわめいた。ヴィクトルだけが相変わらずにこにこしていた。
「カツキはわしの生徒ではないが、みんなも知っている通りヴィクトルの教え子だ。だからここで練習することになった」
説明は続いていた。少年は上の空で、あのジジイ、来るのか、と思った。二十三歳……いまは二十四歳だったろうか。そんな歳でまだ続けるつもりなのか。それも新しい場所で。できるのかな……。若い彼には、経験による成熟というものがわからなかった。
「いったいどんな選手なんだろうな」
ユーリ・カツキは、リンクメイトたちのあいだで興味の対象になった。ヴィクトルがことさらに喜んでいるようなので、余計にそういう空気があった。
「ヴィクトルがすごく浮かれてる。機嫌���いい」
「そんなにカツキが大事なのかな」
「カツキってどんな選手だっけ?」
「演技は悪くなかったけど、顔はあまり印象に残ってないな……。テレビじゃ顔なんてそんなに映らないし」
「カメラはカツキっていうよりヴィクトルばっかりだったもんな」
「ヴィクトルと色ちがいの衣装を着てたのはおぼえてる」
「俺も」
「それもすごいよな。そんなこと、あの皇帝がゆるすんだ」
「デュエットしてたじゃん」
「してたしてた。でも俺ヴィクトルだけ見てて、カツキに注目してなかったなあ……」
そんな選手ばかりだった。
いよいよユーリ・カツキがリンクへやってくる日、いったいどんな選手なのだろう、とみんな興味津々だった。おずおずと前に進み出、はにかんだようにほほえんだユーリ・カツキに、誰もがあぜんとした。ジジイだろ、もう引退だろ、年寄りじゃん、という目を向けられていた彼は、どう見ても少年たちより年下のようなあどけない顔立ちをしていて、困ったように下がる眉と、誰にでも見せる日本人的な笑みが印象的だった。カツキはへたくそなロシア語で「ユーリ・カツキです。よろしくお願いします」と挨拶し、日本の作法でぺこりと頭を下げた。
「あれ、ほんとにユーリ・カツキ?」
「誰だよ、ジジイだとか言ったやつ」
「ガキじゃん……」
「見ろよ、女子が『かわいい』って騒いでるぞ」
「二十四とか、うそだろあれ」
少年が、本当にユーリ・カツキだろうか、別の人間なのでは、と疑っていたら、ヴィクトルが「勇利!」と叫んで彼を抱きしめた。
「勇利、やっと来たんだね。勇利、俺の勇利……」
「なんで急に高揚してるの? さっき一緒にここまで来たじゃない」
「リンクにいる勇利を見たら気持ちがみだれて……、勇利」
「ちょっとヴィクトル」
ユーリ・カツキはヴィクトルの胸をかるく押しやり、上目遣いで優しく彼をにらんで甘く叱った。
「まだ挨拶中」
「ああ……わかってるんだけど」
「話はあとでいっぱいできるでしょ?」
「待ちきれないよ」
「ヴィクトル」
勇利はヴィクトルのくちびるに指を当て、くすっと笑った。
「おとなしくしてて……」
見ていた選手たちは、みんな顔を赤くしてしまった。子どもみたいに見えたユーリ・カツキが、どうしても大人にしか思えなくなった瞬間だった。彼はただ、ヴィクトルがはしゃぐのをとがめ、それを押しとどめたにすぎないのだけれど、なんとも言いがたい色気のようなものを感じ、全員がぽーっとなってしまったのだ。
「なんだ、あれ……」
「ちょっとセクシーじゃないか?」
「ちょっと? いや、かなりだろ」
「へえ、おまえ、ああいうのが好みなんだ」
「そうじゃないけど! なんだよ、おまえこそ顔が赤いぞ」
「だってなんか……」
ジュニア選手たちの意見は一致をみた。すなわち、「ヴィクトルが溺愛するのもうなずける」である。
その日、少年たちは、「ヤコフコーチも手を焼くヴィクトルを操縦できるのはユーリ・カツキだけなのではないか」という予感をおぼえ、実際、それ以降、ふたりの様子を観察しているとその通りだった。すごいな、やっぱりそうなんだ、ユーリ・カツキってぜんぜんジジイじゃないし、やけに子どもっぽいし、でもセクシーで大人だし、いったいどういう人なんだろう……。そう思っていた少年は、ある日、偶然ユーリ・カツキとふたりになる機会があり、尋ねることに成功した。
「どうやってヴィクトルを操縦してるの?」
「え?」
ユーリ・カツキはきょとんとし、いつもみたいに、困ったように眉を下げて笑った。
「ぼく、ヴィクトルの操縦なんてできないよ。彼は好き放題してる。ぼくは振りまわされっぱなし。でも、そういうところがすてきだからいいんだ」
ユーリ・カツキの物言いには、「ヴィクトル大好き」という愛情があふれていた。きっとヴィクトルとふたりきりになったときは、もっとそれが色濃くなるのだろう。少年は、なるほど、こういうところがヴィクトルをめろめろにするんだな、と思った。
その少女は、才能を見出され、この春、チムピオーンスポーツクラブに通い始めたばかりだった。ヴィクトルのことは以前から知っていて、なんてすてきな人なのだろうとあこがれていた。数日前、彼が黒髪の日本の男子を連れてきて、「俺の生徒なんだ」と言ってまわっているのを目にした。少女は昨季の試合の映像をくり返し鑑賞していたので、ユーリ・カツキのことをよく承知していた。実際に会った彼は、試合のときほどきらきらしてはいなかったけれど、優しげな感じでとても気に入った。少女は、ヴィクトルのほうがすてきかユーリ・カツキのほうがすてきか、なかなかきめられなかった。
ヴィクトルに話しかけてみたいが、彼は忙しいし、たまにリンクに来るとユーリ・カツキにつきっきりである。それならと思い、少女はユーリ・カツキと友達になることにした。彼がリンクサイドからリンクを眺めているときに近づき、「ヴィクトルのこと好き?」と訊いてみた。彼は最初、自分が話しかけられたとは思わなかったみたいで、しばらくぼんやりしていたけれど、「ねえ」と重ねて問うと少女を見下ろし、「あ、ぼく?」と言った。
「そう」
ユーリ・カツキは二、三度瞬き、かすかにほほえんで「大好きだよ」と答えた。普段、リンクメイトに何か声をかけられたときとはちがう、やわらかい笑みだった。
「私も」
そう告げると、彼はもう一度笑った。
「どこが好きなの?」
尋ねられて、少女はヴィクトルの好きなところを話した。ユーリ・カツキはいちいちうなずきながら聞いていた。彼はすべてに反論せず、「ぼくもそう思う」と答えた。
「あなたはいつからヴィクトルのことが好きなの?」
彼は、ヴィクトルがジュニア時代に世界チャンピオンになったときのことを語り、「そのときに夢中になったんだよ」と言った。
「本当に大好きなのね」
「そうだよ」
「その指輪、何か約束してるの?」
「べつにそういうわけじゃ……。おまもりだよ」
「そうなの。好きなひとと同じ指輪がおまもりって、すてきね」
「そう思う?」
「うん」
「ありがとう」
ユーリ・カツキは可憐で初々しい笑みを浮かべた。少女は尋ねた。
「ヴィクトルのこと、愛してる?」
率直な質問に、彼は、少女よりずいぶん年上だというのに、おさなげな様子でまっかになった。
「結婚したいくらい愛してる?」
「…………」
「どれくらい愛してる?」
彼は困ったように笑うと、ちょうど扉を通り抜けて入ってきたヴィクトルを見やり、ひそやかに打ち明けた。
「もう、ヴィクトルを知ってからのぼくの人生を全部捧げてるくらい、ぼくはヴィクトルにめろめろなんだよ」
ちょっと聞いて。もう信じられない。きまってるでしょ、ヴィクトルとユーリ・カツキのことよ!
このあいだ、休憩室のソファでやすんでたの。ほんのしばらくのつもりだったんだけど、気がついたら何時間も経ってたわ。起きたら練習しようと思ってたのに、そんな時間なくって、もう帰ることにしたのよ。でも部屋の中に誰かの気配がするじゃないの。ほら、あの部屋、飲み物つくったりできる給湯の場所があるでしょう。そこを通らないと扉にたどり着けないじゃない。普段ならべつに気にせず行くんだけど、なんとなくひみつめいた感じがして、すぐには動けなかったわ。だって、カーテンの向こうで何かひそひそ話してるのよ。困るじゃないの。よくよく聞いてみると、「だめだよ」とか「ちょっとだけ」とか、そういう会話なの。がぜん興味がわいたわ。誰と誰なんだろうってね。
もちろんもうわかってるでしょうけど、ヴィクトルとユーリ・カツキだったのよ。話してる内容はよく聞こえなかったけど、きぬずれの音のあとの、「愛してるんだ」っていう熱っぽいせりふは聞き取れたわ。それからくちびるがふれあう音! わかるでしょ? 私はそろそろと床に足を下ろして、給湯場所の仕切りのカーテンに近づいたの。そーっとのぞこうとしたんだけど、なかなか姿が見えなくて……苦労したわ。堂々とやるとみつかっちゃうし。
でもどうにかふたりが見える位置まで移動して、こっそりのぞいたの。そんなに接近してはいないわよ。そこまでばかじゃないわ。だけどちゃんと見えた。もう大興奮。ヴィクトルがユーリ・カツキを抱きしめて、壁に押しつけてるの。もちろん熱烈にキスしてるわけ。カツキのほうもいやがってはいなかったわよ。ちらっとだけ見えた顔は、ぎゅっと目を閉じてて、ヴィクトルに全部まかせてゆだねてます……みたいなふうだったわ。でもね……、私も好奇心が勝ちすぎて、ちょっと出過ぎちゃったのね。気配を感じたんだと思う。ふっとカツキがまぶたをひらいたのよ!
もうあせったわぁ……怒られるってどきどきした。カツキはヴィクトルを押しのけて、ヴィクトルがなにごとかと振り返って、私はみつかっちゃうってね……。でもちがったの。カツキはね……、私と目が合うと、ゆっくりと手を上げて、カーテンの端をつかんだのよ。そしてさっとそれを引いて……ふたりの世界から私を追い出したの……。
そのときの目つき……。いま思い出してもぞくぞくするわ。べつににらまれたとか、邪魔者扱いされたとかじゃないのよ。ただ、ちらっと見ただけ。感情的じゃなかった。でもね……、その流し目がすごいのよ! ちょっとつめたい感じで、私には関心がなさそうで……けど色気があふれてるの。愛する男にキスされてるからね、きっと……。
普通、同じ部屋に人がいると知ったら、逢い引きなんてさっさと切り上げるものでしょ? でもそんなことぜんぜんないの。ヴィクトルがものすごく熱烈だったから、それを中断させられなかったのか……それとも、カツキ自身もおぼれてたのか……どっちかはわからないけど。それからたっぷり十分近くふたりは抱きあってキスしてたわ。姿は見えなくなったけど、物音でわかるわよ。ちいさくお互いの名前を呼びあったりして……。あんまりにも熱狂的だから、こっちのソファで「始める」ことにしたらどうしようかと思っちゃったわよ。
結局そういうことにはならずに、ふたりは出ていったけど……、もう、私のほうがまっかだったわ。私だって未経験じゃないし、人のキスシーンを見るのだって初めてじゃないのよ。みんなわりとあちこちで平気でしてるしね。でも、その中のどれよりも熱愛的だったわ……。
この話にはおまけがあるのよ。それから何日かあと、たまたま廊下でカツキに会ったの。緊張したわ。怒られるかもしれないとか、あからさまに避けられるかしらとか、そんなことを想像して……。でも彼、何も言わないの。ただ私をちょっと見て、日本式にぺこっと頭を下げてどこかへ行っちゃった。すごくない? あんなところ目撃されて顔色ひとつ変えないの。もうしびれちゃった。
──彼が私の顔をおぼえてなかっただけ?
…………。
あり得るかもしれないわね……。
氷の上での指導中は厳しいものの、ヴィクトルの愛情は見ていて薄気味悪いほどであり、常に勇利に寄り添い、優しくささやき、熱烈にみつめ続けているので、ユーリは胸が悪くなる一方だった。かつてはあれほど超然とし、ひとり高い理想と志を保ち、孤独に王座を守ってきたヴィクトル・ニキフォロフがこのていたらくだ。いまは向上心がないとは言わないが、とにかくヴィクトルは変わってしまった。
勇利は皇帝ヴィクトル・ニキフォロフの熱狂的なファンなので、この変貌を嘆いてはいないのかと疑いたくなるのだが、当人はいたって日常的な態度をしており、ヴィクトルに何をされても平然と受け流している。だが、ときおり「黙ってて」「すこしはまわりを見て」「ちょっといま着替え中!」と手厳しくヴィクトルを叱っているので、もしかしたらうんざりしているのかもしれない。
「おまえ、ああいうのいいのか?」
気になり、つい尋ねてしまった。
「何が?」
「さっきもおまえのことさわりながらジャンプの動画見てたじゃねえか」
「もう普通のことだし……。ヴィクトルがヴィクトルでいてくれるならぼくはそれで……」
「でも内心うぜえと思ってんだろ?」
「なんで?」
「そんな感じだぜ」
「そうかなあ」
「ヴィクトルの本性を知って幻滅してんだろ」
「確かに思ってた彼とはちがうかも」
勇利は言ってくすくす笑った。
「でもそれがヴィクトルの愛嬌だよ。ユリオだって親しみやすくなってうれしいんじゃないの?」
「なんで俺があんなジジイと親しんで喜ばなきゃなんねえんだよ」
「わかるよ……ヴィクトルって最高にかっこいいしすてきだけど、近寄りがたかったもんね……。気取ってない、うちとけてるヴィクトルもいいよね……もちろん、孤高のヴィクトルもかっこいいからたまらないけど……」
「おまえとヴィクトルのことを話した俺がばかだった」
うっとりしている勇利を見て、ヴィクトルよりもこいつにあきれる、とユーリは思った。どうやら勇利はヴィクトルならなんでもいいらしい。まあ勝手にすればよいが。
しかしそれはつまり、ヴィクトルをいまだに神聖視し、神としてあがめ、あこがれ続けていることの証拠ではないか、という気がした。確かに勇利は、わがままでおかしなことを言うヴィクトルを受け容れてはいるけれど、こういう言い分を聞いていると、神様の言うことだから、という心構えがある気がしてなら���い。ヴィクトルはどう見ても人間的な愛情で勇利を愛しているので、こいつらいつかこじれるんじゃ、とユーリはすこし気がかりだった。
ヴィクトルは、ロシアの英雄という立場上、ほかにも仕事を持っているため、たまに練習をやすんだりする。そういうときは、当然ながら勇利はヴィクトルの指導を受けられず、彼は変わらずきまじめではあるものの、いささかしょんぼりしているように見受けられた。あるとき、一週間ばかりもヴィクトルが留守にしたので、ユーリは、勇利が落ちこんでしまうのではないかと思ったが、意外にもそんなことはなく、すこしおとなしい様子ながらも、彼は勤勉に練習に励んでいた。なんだ、やるときはやるんだな、とユーリは感心した。反対に、こいつヴィクトルがいなくてもさびしくないのかよ、と妙なところで引っかかったりもした。
練習を終え、更衣室へ行く。さきに切り上げたはずの勇利がいない。
「カツ丼は?」
そばにいたリンクメイトに尋ねてみると、「シャワーじゃないかな」という答えだった。ユーリは首をかしげた。勇利は普段はシャワー室を使わない。家に帰ってお風呂に入るほうがいいから、と言っていた。なぜ今日に限って使っているのだろう。家の風呂が故障しているのだろうか。
ユーリはそのあとトレーナーに呼ばれ、二十分ばかり話をし、また更衣室へ戻った。荷物の整理をしていると、勇利が扉を開けて入ってきたのでびっくりした。
「おまえ、まだいたのか?」
「え?」
勇利はぱちりと瞬いた。
「シャワー使ってたんだろ?」
「うん……」
「もう三十分くらい経つぞ」
「あ、まあ……ちょっと長かったかな……」
勇利が気恥ずかしそうに時間を気にした。
「なんでそんな念入りにやってんだよ。気持ちわりいやつだな」
ユーリはベンチをまたぐようにして座り、かばんの中に手をつっこんだ。
「風呂なんか家で入ればいいだろ。壊れてんのか?」
「そんなことはないよ……」
勇利からはシャンプーやせっけんの匂いがした。ユーリは顔をしかめた。
「こんなとこでそんなにがっつり洗うなよ。何やってんだ」
「うん、ごめん……」
勇利は歯切れが悪い。
「なんだ? 何なんだ? なんかあんのか?」
いつもとはちがう彼の態度に、ユーリは不審をおぼえた。
「いや、何もないよ……」
「だったらこんなとこで清潔ぶるのやめろよな。気色悪いんだよ」
「う、うん……」
勇利は赤くなってうつむいている。ユーリはいらいらしてきた。
「何なんだ! 理由があるなら言えよ! 俺が理不尽に怒ってるみたいじゃねえか!」
「え、えと……」
「正当なわけがあるなら俺も何も言わねえよ! ただおまえが、普段はなんもせずに帰るくせに、今日に限ってそういうことするから──」
「だ、だって」
勇利は頬をまっかにし、もじもじしながら言い訳した。
「今日はヴィクトルが帰ってくるから……」
「は?」
なんだ。ヴィクトル帰ってくんのか。そりゃよかったな。ユーリは他人事だったのでそういう感想しか持たなかった。
「……あいつが帰ってくんのとおまえのシャワーと、なんか関係あんのか?」
「……帰ったら、ヴィクトルいるから」
「あいつのほうがさきか」
納得しかけたが、やっぱりよくわからない。
「べつにいいだろそんなの……。なんだ? ヴィクトル、汗くさいおまえはいやだとか言ってんのか?」
「そうじゃないよ……。ただ、ぼくが気になるっていうか……」
「いいだろ。練習のあとなんだから汗かいてんのは当たり前だ。ヴィクトルだってそう言うだろ」
「でもいやなんだ」
「おまえそんな潔癖症だったか? ヴィクトルの前では綺麗でいたいとかいう乙女っぽい思考か? ばかばかしい」
勇利は気恥ずかしそうに指をいじっている。ユーリはさらにいらだった。
「だいたい、そんなに汗くせーのがいやなら、帰ってすぐ風呂入りゃいいだろ。何もここでごしごし洗わなくても……」
「……だってヴィクトル、帰るなり抱きしめてくるから」
「は?」
「そんな暇与えてくれないから……」
「…………」
「そのまま、あの、その……いろいろ……」
「…………」
「だから……」
勇利は耳まで赤くなっている。真相を知ったユーリは、自分で尋ねたこととはいえ、頭に来たので勇利に向かって怒鳴った。
「とっとと帰れ! この色ボケ野郎!」
ユーリ・カツキっておもしろい。それが彼とリンクメイトになったミラの率直な感想だった。どうやら勇利は深くヴィクトルのことを愛しているらしく、彼といるとしごくしあわせそうにしている。とろとろにとろけた表情で、もう貴方だけしか見えない、といった具合である。かと思えば、練習のときは真剣な顔つきになり、甘えた空気などいっさい見せない。ヴィクトルに意見したり、強い口ぶりで言い返したりする。それなのに、練習が終わるとまたにこにこし始め、ヴィクトルが近づいてきて腰を抱くのに身をまかせている。ところが、たまにヴィクトルがやりすぎると、「そういうのやめてって言ってるでしょ」とそっけなくなることもある。
おっかしいの。ミラは楽しくてたまらなかった。
「カツキはヴィクトルがいやになることってないの?」
そう訊いてみたら、勇利は不思議そうな顔をして瞬いた。
「いやになるって?」
「だから、もう顔も見たくないとか、口も利きたくないとか、ここだけはゆるせないとか、あと自分の時間を持たせて欲しいとか」
「え? なに? なんのこと? どういう意味?」
「もういいわ」
「勝手に完結しないで」
「あなたに訊いた私がばかだった。あるわけなかったわね……」
「えぇ……?」
「喧嘩しないのね」
「ヴィクトルと? そんなのしょっちゅうだよ」
勇利は笑って言った。ミラには信じられなかった。
「うそでしょ」
「本当」
「どういう理由で喧嘩するわけ?」
「それはその……」
「あ、わかった。ベッドの中であまりにも泣かせてくるとかそういうことでしょ」
「…………」
勇利はまっかになって黙りこんだ。冗談だったのに当たってしまった。ミラはこの手の話でからかうのはよそうと思った。おもしろいのだけれど、反対にこちらが照れてしまうことになる。
ある日の練習中、いつものように���ィクトルと勇利が議論を始めたのだが、最初は静かに意見を述べあうだけだったのが、だんだんと激しくなり、白熱してきたためミラははらはらした。そのとき彼女はヤコフとタブレット型端末をのぞきこみ、ジャンプの型を確認している最中だったので、思わず言ってしまった。
「大丈夫でしょうか……」
「たいしたことなかろう」
なぜかヤコフはうれしそうだった。
「ヴィクトルにあれほど言い返す選手、初めて見ました」
「あれくらいでなければヴィクトルの生徒にはなれん。そもそもコーチが未熟だ」
リンクメイトやトレーナーたちも、ちらちらとふたりの様子をうかがって気にしているようだったが、間もなくその話しあいは終了し、勇利はバレエの講義を受けるためにリンクを出ていった。ミラには喧嘩別れのような終わり方に見えたので、すこし心配だった。
数時間後勇利は戻ってき、そのときヴィクトルは、ヤコフの見守るさきで通し稽古をしているところだった。勇利はリンクサイドに立ち、フェンスにもたれてヴィクトルをみつめた。ミラは休憩中だったので、彼の隣まで行き、さっきのことを怒っているのか尋ねようとした。しかし、勇利の横顔を見た瞬間、ぽかんとして何も言えなくなった。
「ヴィクトル、かっこよすぎない……?」
勇利は頬に手を当て、とろんととろけた目つきでヴィクトルを見ていた。ミラはぱちぱちと瞬いた。
「うそ……この人がぼくのコーチなの……? 信じられない……」
「は……?」
「え? ほんとに……? ほんとにかっこよすぎない? 大丈夫? あんなにかっこいいひとがそばにいて、ぼくは精神を正常に保ったまま生きていけるの……? だって……」
勇利はまっすぐにミラを見た。
「あのひとぼくのコーチなんですよ」
「知ってます」
彼はヴィクトルに視線を戻し、うっとりとした。
「うそ……もうあり得ない……好き……どうしよう……」
「おかしくなったの?」
「なってる……ヴィクトルがかっこいい……あんなにかっこいいひと……存在していいのかな……」
「…………」
「まあヴィクトルがかっこいいのは知ってましたけど」
そのとき、すべり終わってからヤコフと話していたヴィクトルがさっと振り向いた。彼は勇利に向かってにっこり笑いかけた。ミラは勇利が気絶するのではないかと心配した。案の定、勇利はふらっと身体を揺らし、慌ててフェンスにつかまった。そのまま、まっかになるかと思ったのだが、勇敢にも勇利は顔を上げた。彼はヴィクトルをじっとみつめ、くちびるに二本の指を当てた。そして一瞬まぶたを閉じ、ちゅっ、とくちびるを鳴らして、指をヴィクトルのほうへ差し出してキスを投げた。ヴィクトルは目をまるくし、笑いながらくちびるをとがらせ、ちゅっ、と同じようにくちびるを鳴らして、勇利のキスを受け止めた。勇利は口元に手を添えて、赤い頬でうれしそうにうつむいた。
ミラは、リンクでこれだけいちゃついてるんだったら、家でどんなふうなのかしら、と思った。
勇利はぬくもりの中でゆっくりとまぶたをひらいた。彼の頭の下にはヴィクトルの力強い腕があり、もう一方の腕では腰をしっかりと抱き寄せられていた。ヴィクトルはまだ眠っているようである。そのうつくしい寝顔に勇利はうっとりと見蕩れた。ゆうべのことを思い出すと、勇利の口元に笑みが漂い、頬にはあかみが差した。ヴィクトルはとても優しく、情熱的で、甘かった。甘美な時間だった。
勇利はヴィクトルのすばらしいおとがいの線にくちびるを押し当て、あえかな吐息をついた。ふいにヴィクトルの腕がぎゅっと勇利を抱きしめた。
「あまりかわいいことをしないでくれ」
ヴィクトルがくすくす笑った。
「また一から愛したくなるよ」
「ヴィクトル、起きてたの?」
「いま起きた」
ヴィクトルの長いまつげが上がり、その向こうから、青くきらめく瞳がのぞいた。その目は、きわだった熱意を帯びており、勇利の胸をときめかせた。
「ゆうべはすてきだったよ」
ヴィクトルがかすれた声で低くささやいた。勇利はまっかになった。
「勇利は……?」
「う、うん……」
勇利はヴィクトルの胸に顔をうめた。
「よかったよ……」
「それはうれしいな」
ヴィクトルは優しく勇利におもてを上げさせた。勇利はヴィクトルの目をじっとみつめ、誘われるようにまぶたを閉じた。ヴィクトルがくちびるを重ねる。最初は控えめについばみ、そのうち音をたてて情熱的に……。
「ん……んっ、ヴィクトル……」
「勇利……」
ヴィクトルが勇利の手を取り、指をからませた。勇利は力が入らず、握り返すことはできなかったけれど、その代わり、夢中で彼のくちづけに応えた。いつの間にか身体がすりよってしまい、素足がヴィクトルの足にからんだ。ヴィクトルは熱心にキスしていたが、そのうちせっぱつまったように「我慢できない」とつぶやき、勇利のしなやかな身体をひらかせた。
しばらくののち、勇利はヴィクトルの胸に頬を寄せながら、速い鼓動を聞いていた。だんだんと平常に戻ってゆく心音。この音を聞いていると、安心してねむくなる。みたされたばかりならばなおさら……。
「そういえば……」
「なんだい?」
「昨日、また、言われちゃった……」
「誰に? 何を?」
「誰だったかな……リンクで……」
勇利はうとうとしながらつぶやいた。
「『ヴィクトルと付き合ってるの?』って」
「へえ」
ヴィクトルはくすくす笑った。
「何回目? 多いよね」
「うん……。そんなふうに見えるのかな……みんなそういうこと、興味あるんだね……」
「勇利はなんて答えたんだい?」
「いつもと同じだよ……」
勇利は舌足らずに言った。
「付き合ってないよ、って……」
「そうか。それで相手は納得した?」
「えっと、うーん……」
ねむい。話していられなくなってくる。勇利は吐息をついた。
「……もう一度寝ていい……?」
「いいよ……」
「ん……」
勇利は口の端を吸いこむようにして笑い、ヴィクトルにさらにくっついた。
「……あ、そうだ……」
「うん?」
「相手、納得してた……」
「そうかい? 珍しいな……。勇利、何か言ったの?」
「……えっと……そう……」
勇利はすでにとろとろとまどろんでいた。
「付き合ってないけど、愛し合ってるって……」
4 notes
·
View notes
Text
え? そうだったの?
勝生勇利の第一印象というものをおぼえていない。試合の公式練習で会ったとき言葉を交わしたはずなのだけれど、とにかく彼はごく平凡で、目立たなかったので、頭に残っておらず、どんな挨拶をしたのかわからないのだ。たまたま滑走順がクリストフの前で、そのときに勇利を見たのが初めての彼の記憶だが、日本人はおさなげに見えることもあり、クリストフにとって勇利は、最初、ノービス選手のような存在だった。こんな子どもが自分と張り合うのか、と驚いてしまった。
しかし、スケートは確かだった。勇利は昔からスケーティングがうつくしく、流れるようななめらかなすべりをした。そういう持って生まれたものというのはたいへん重要である。未熟な技術はみがけばよいが、その人の持つ「色」は変えられない。勇利はいずれ光り輝くだろうと思わせる、原石のような秘められた魅力があった。競技が終わったとき、クリストフは自分から声をかけた。
勇利はヴィクトル・ニキフォロフのファンで、語ることはほとんどが彼の話だった。クリストフもヴィクトルのことは知っており、いつか彼と近づきになりたいものだと考えていたので、勇利と話すのは楽しかった。しかし、勇利の好意は度を超しているように思われた。クリストフは一度、「ヴィクトルが結婚しようと言ってきたらどうする?」と言ってひやかしたことがある。本当にたわいない、子どもらしいいたずらのような質問だった。クリストフは勇利が「そんなことヴィクトルが言うわけない」と怒るか、「からかわないでよ」と赤くなるか、どちらかだと想像した。しかし勇利はそんな反応はしなかった。彼はまっかになって口を利かなくなり、どこかへ行ってしまったのだ。
そのあと勇利に会ったとき、彼ははにかみながら説明した。
「さっきはごめん。ヴィクトルと結婚したいと思ってるわけじゃないんだよ。ただ驚いちゃって。ぼくの許容範囲を超えてしまったんだ」
「ヴィクトル」と「結婚」というふたつの言葉だけで姿を消すほど勇利はヴィクトルが好きだったようだ。勇利は自分の心境を、「フリーのジャンプをすべてトリプルアクセルにした感じ。いっぱいいっぱいで死にそう」と言っていた。そのときはまだ四回転は跳べなかった。
勇利を見ていて思ったのは、見かけほどよわよわしくはないし、負けん気の強さも持っているし、何かきっかけがあればひと皮むけるのに、ということだった。それと、あんなに優しそうなのに、割合そっけないところがあるということ。クリストフ自身がつめたくされたわけではないのだけれど、ファンサービスの仕方や、初対面の人に向ける笑顔を見ていると、なかなか手ごわいということが感じて取れた。自分も最初、あんなつくったような笑みを向けられていたのだろうか?
それから幾年か経ってヴィクトルにも会ったが、ヴィクトル・ニキフォロフの印象は、強く正しくうつくしい、というものだった。これは彼と知り合う前からそうだ。ヴィクトルは圧倒的な強さを誇っていた。ときおり、試合用の気分が乗らないのか、妙な演技をすることはあったけれど、たとえ得点がさほど出なくとも、クリストフにはそれさえも魅力的なプログラムに思えた。ヴィクトルがヴィクトルの好きなようにすべった、という印象だ。コーチの言うことを守らなかったのだ。もちろんそういうときは、キスアンドクライで手ひどい説教を受けていた。
金メダルを獲っていなくても、それは、ヴィクトルのスケートがまずいということではなかった。クリストフには、いつもヴィクトルは強い者に見えた。強い者は正しい。そして彼はうつくしい。ヴィクトルは、ほかとはかけ離れてすぐれた正義だった。
ヴィクトルはそれから何年もトップスケーターであり続けた。クリストフはずっと彼を好きだったが、もうただ彼にあこがれるだけの少年ではなく、親密な友人だった。ヴィクトルのほうもクリストフを好もしく思ってくれているようで、それが態度ににじみ出ており、ライバルと言われながらも、ふたりはたいへん仲がよかった。
しかし、そのうちにヴィクトルの表情が曇り始めた。相変わらずスケートは冴え渡っているのだが、何か考えこんでいるようなことが多くなった。ヴィクトルはクリストフにいちいち自分の心情を語らなかったし、クリストフのほうも聞きただしたりはしなかったけれど、王者ゆえの孤独というものは想像できた。一度、それとなく「元気がないね」と言ったところ、ヴィクトルは苦笑を浮かべて答えたものだ。
「クリスの前にいると油断してしまう」
確かに、報道陣やファンの前では、いつだってヴィクトルは晴れやかで陽気な顔をしていた。
そんなときだ。ヴィクトルが休養を取って日本へ行き、勝生勇利のコーチをすると言い出したのは。
「本気?」
クリストフはすぐにヴィクトルと連絡を取った。
「本気」
ヴィクトルは楽しそうに答えた。
「勇利に頼まれたから?」
クリストフはバンケットでのことを指摘した。
「それもある」
「あの動画を見たから?」
「それもある」
「それも、それも、って、結局何が決め手なんだい?」
「スケーティングに惹かれたからさ」
ヴィクトルは率直に打ち明けた。そのときのはずむような声を、クリストフは何年も忘れることができなかった。
「君はスケートに惹かれたらコーチしたくなるのかい?」
「勇利のスケートはそうだ」
「すっかりその気になっちゃって。君、コーチなんかしたことないだろう。わかってる? 優秀な選手が優秀なコーチになるとは限らないんだよ」
クリストフはヴィクトルのやることに文句をつけたかったわけではない。ただ、ふたりの友人のことが心配だった。ヴィクトルの選手としての今後。そして、彼を熱愛している勇利。──あれほどヴィクトルが好きなのに、そのヴィクトルにコーチをされたりしたら、勇利はどうなってしまうのだろう?
「勇利がして欲しいと言い、俺もやりたいと思った。大切なのはそれだけさ」
「ヴィクトルならそう言うと思ったよ」
「俺は人を驚かせること、やってみたいことはためらわずやってみる主義なんだ」
ヴィクトルは笑いながら話した。
「勇利ったらね、可笑しいんだよ。俺を見て信じられないっていう顔をしてるんだ。自分から頼んできたくせにね。すごく他人行儀なんだよ。バンケットのときはあんなに積極的でかわいかったのに。いまは俺と目が合うのも死にそうって感じだ」
「いつもの勇利だね」
「ああ、早く親しくなりたいなあ。もっといろんなことを話したいよ。彼のことを誰よりも知りたいし、俺のことも知ってもらいたい」
ヴィクトルがこんなことを言うのを聞くのは初めてだった。
「……勇利のことを泣かさないでくれよ」
クリストフはそうヴィクトルに頼んだ。
ふたりと再会したのは中国大会のときで、勇利の演技は、これまでとはまるっきり変わっていた。いつも気恥ずかしそうにうつむいていた彼が、堂々と人々の視線を集めている、といったふうだった。もちろん勇利だって、氷の上では昔から輝いていたのだけれど、その時代とは比較にならない優雅な態度、高貴な雰囲気があった。ショートプログラムで見せた女王然としたそぶりは忘れられない。
「クリス、勇利にはね、いろんな顔があるんだ」
ヴィクトルはうれしそうに勇利のことを語った。
「落ちこんだり喜んだりそっけなかったり優しかったり、かわいかったり、人の話を聞いていなかったり、従順だったり反抗的だったり、表情がくるくる変わる」
彼は、最後に会った世界選手権のおりにひきくらべ、見違えるほどいきいきしていた。
「勇利は君の好みに合ったようだね」
クリストフはからかった。
「あんなにおもしろい子はいないよ。とても魅力的だ。クリスもそう思わないか?」
ヴィクトルは自慢した。
「それにね、勇利は俺のことが大好きなんだよ」
「好かれるのなんて珍しくないでしょ」
「そうだけどね……」
「ヴィクトルはどうなの?」
「俺? 俺だってもちろん好きだよ。大のお気に入りだ!」
実際、ヴィクトルの態度を見ていればそれはたやすく知れた。勝生勇利はヴィクトル・ニキフォロフの秘蔵っ子だった。
しかし、翌日のフリースケーティングのときには雲行きが怪しくなった。勇利の様子がおかしいのだ。クリストフだって競技に出るのだから、試合の日にまで友人の心配をしてはいられない。それはコーチのヴィクトルの役目だ。しかし、そのヴィクトルが使命をまっとうできるかどうかは、はなはだ疑問だった。おそらく勇利は、かつてないほどの重圧を感じ、苦しんでいる。彼は繊細なのだ。ショートプログラム一位、ヴィクトル・ニキフォロフがコーチ。それがどれほど大きな意味を持つか。ヴィクトルにはそこの微妙なところは、おそらくわからないだろう。コーチに向いてないんだよ、とクリストフは考えた。
案の定、滑走前に現れた勇利は目をまっかにし、ぎこちない態度だった。ヴィクトルとのあいだがよそよそしい。何かあったな、とクリストフは思った。勇利は泣いたにちがいない。ヴィクトルのやつ、いったい何を言ったんだか、とあきれた。
試合のあと、ヴィクトルはクリストフにこぼした。
「勇利って複雑すぎるよ」
しかしそう報告する彼の目はきらきらと輝き、喜びにみちていた。
「自分の得意なジャンプを跳んでもらえたのがそんなにうれしい?」
クリストフはわざと意地悪を言った。するとヴィクトルが──いつも余裕を示している悠然としたヴィクトルがむきになったのだ。
「そういうことじゃないんだ。ただジャンプを跳んだからじゃない。俺との積み重ねのうえに生まれたジャンプなんだ、あれは」
「あれ、キスしてたの?」
クリストフは唐突に尋ねた。ヴィクトルは「え?」と間の抜けた声を上げた。
「勇利に。キスした?」
ヴィクトルは答えなかった。そのとき、ちょうど勇利が取材を終えて現れたので、「ゆうりぃ」とうれしそうに駆けていってしまった。クリストフは可笑しかった。勇利は変わった。確かに。しかし、それ以上にヴィクトルも変わったのだ。
次に会ったのは、グランプリファイナルのおりだった。ヴィクトルをひと目見てクリストフは驚いた。勇利に向けるヴィクトルのまなざしが、ひどく情熱的だったのだ。中国大会のときからその気配はあったけれど、いまや彼の愛情ははっきりと目にあらわれていた。
「ヴィクトル……、君、本気で勇利にまいっちゃったみたいだね」
「クリス、この試合はね、俺の勇利が優勝するよ。俺は自分の力でファイナル六連覇はできないけど、勇利がそれをかなえてくれるんだ」
ヴィクトルは勇利とそろいの指輪をはめていた。クリストフは、いろいろな者からあれほど愛されているにもかかわらず、彼はなんとなく結婚しそうにないという気がしていたので、指輪をつけてうれしそうに披露する様子がおもしろくて仕方なかった。
「君が結婚指輪を見せびらかすような男だとは思わなかった」
「まだ婚約指輪だよ。うらやましい?」
「そういうのを『うらやましいのではないか』と認識できる力が君にあったことが驚きだ」
「どういう意味だ」
「勇利はすごいね」
勇利はヴィクトルの言うようには、金メダルを獲れなかった。にもかかわらず、ヴィクトルはたいへんうれしそうな様子をしていた。勇利のエキシビションは見ていられなかった。なぜかクリストフは、ふたりの演技を見ながら、ほほえましい気持ちになると同時に、どこかそわそわするような──気恥ずかしい思いも感じたのだ。
「ヴィクトル、君たちのデュエットだけど」
「最高だっただろ」
「ふたりが仲よくしていて結構だったんだが、どうも落ち着かない気分にさせられた」
「なんで?」
「なんというか、他人のセックスを見せられている気になった」
ヴィクトルは目をまるくした。彼は途方もなく大笑いし、クリストフの肩に手を置いてちいさく言った。
「そうだろうとも」
そして口元を上げて続けた。
「でもまだ勇利のことは抱いてな���」
次はヨーロッパ選手権での再会だった。もちろん勇利はこの試合には出ない。ヴィクトルも彼に会っていないはずだ。選手復帰をしたため、ヴィクトルはロシアで稽古に励まなければならなかった。勇利は日本で練習を続けているようだ。それぞれ、ロシア選手権でも全日本選手権でも成績はよかったようだが、ヴィクトルはひどく落ちこんでいた。
「勇利に会いたいんだ」
ヴィクトルは率直に打ち明けた。
「会いたくて会いたくてたまらない」
クリストフは、ヴィクトルが誰かに会いたがることがあるなんて想像もしていなかったので、ついほほえんでしまった。
「電話すればいいじゃない」
「してた。毎日やったら『そんなにかけてこないで』と怒られた」
「ああ……、まあ、勇利にはそういうところがあるよね。どこかつめたいというか」
「ちがうんだ。勇利も俺に会いたいんだ。声を聞いてしまうとその気持ちが激しくなるからかけてこないでと言ってるだけなんだ」
「勇利がそう告白したの?」
「ちがうけど……」
「いいけどね」
そうかもしれないしちがうかもしれない。どちらにしても、ヴィクトルをそんなふうに悩ませるのがいまの勇利らしい。
「まあ落ち着きなよ」
「落ち着けないよ」
「たった三ヶ月じゃないか」
ヴィクトルは溜息をついた。彼は思いつめたようにつぶやいた。
「クリス、俺ね……」
「なんだい」
「勇利とセックスがしたいんだ」
クリストフは溜息をついた。
「……あのね」
「したくてしたくてたまらないんだ」
ヴィクトルは苦しそうに胸を押さえた。クリストフはばかばかしくてやっていられなかった。
「まだ一度もしてないんだ。勇利に入れたい」
「あのね……」
「勇利を抱きたい。気が狂いそうだよ」
「まるで初めて恋を知った少年のようじゃないか」
「つらいよ」
「二十八歳にしてこの始末。こじらせてるね」
「勇利とやりたい」
「黙りな」
「こんな下品な俺を知ったら、勇利は俺を嫌いになるだろうか……」
「そういうくだらないことで悩めるなら、まだまだ元気だね、ヴィクトル」
ヴィクトルの演技はせつなさと愛情を帯びており、ひどく叙情的で、かなりの評判になった。クリストフは勇利の「エロス」を見たときのように、「去年までとぜんぜんちがう」と思った。気取り返ってメダルにキスしていたヴィクトルはどこへ行ってしまったのだろう? いまの彼は、メダルを掲げて笑顔を振りまき、「勇利、金メダル獲ったぞ! これをきみに捧げよう」などとはしゃいでいる。これが「クリスの前にいると油断してしまう」とさびしげにつぶやいたあの男だろうか?
シーズンが終われば、勇利はロシアに渡るらしい。それを世界選手権後に聞いたクリストフは、「よかったじゃない」と祝福した。
「これで毎日会えるね。勇利はヴィクトルの家で暮らすの?」
「ああ……」
「ますますうれしいだろう」
「まあね……」
しかしヴィクトルは浮かない顔をしていた。
「どうしたの。勇利と喧嘩でもしたのかい?」
「いや……」
ヴィクトルはしばらく黙ってグラスに口をつけていた。ふたりはホテルのバーで飲んでいた。クリストフは首をかしげた。何か問題があるのだろうか。
「何を落ちこんでるんだい? 勇利とやりたいんだろ? いよいよじゃないか。一緒に住めば自然とそういうことになるさ。お望み通りセックスできる。やりまくれるよ」
「それなんだ」
ヴィクトルがおもてを上げ、訴えかけるようにクリストフを見た。
「いままで俺は、勇利を抱くのがこのうえなく楽しみだったんだ」
「だろうね」
「でも、考えてみたんだが……」
ヴィクトルは悩ましく打ち明けた。
「俺、愛してる子とセックスするの、初めてなんだ……!」
「…………」
「童貞みたいなものじゃないか……!?」
クリストフは黙って琥珀色の液体を飲んだ。
「どうすればいいのか、いまから不安になって緊張する……」
ヴィクトルは何か大切な教えでも書いてあるかのように、グラスを熱心にみつめている。
「勇利を気持ちよくしてあげたい。彼は正真正銘の未経験だから、恐怖もあると思う。くつろがせてあげたい。大事に、優しく、かわいがってあげたい。でも俺にその余裕があるだろうか!?」
クリストフはあいづちも打たなかった。
「俺が下手なことをしたら勇利は幻滅するんじゃないか? きっと俺のことを、世界一セックスの上手い色男だと思ってるぞ。そんな俺が手間取ったり、うろたえたり、愛撫がじゅうぶんじゃなかったり、何か失敗したりしたら……」
「…………」
「クリス」
ヴィクトルはクリストフの腕をつかんだ。彼は真剣に言った。
「入れる前に暴発したらどうしよう!?」
「……そこまでいろいろ考えるなら、緊張のあまりたたないほうを心配したほうがいいんじゃないの」
「あ、それはないよ。大丈夫」
ヴィクトルはひとしきり、ああどうしよう、ああ不安だ、手際の悪い俺なんて勇利はがっかりする、勇利がセックスを嫌いになったらどうすればいいんだ、と悩み騒ぎ、最後には、セックスがこわい……としゅんとして去っていった。しかしクリストフは知っていた。それでもヴィクトルはやりたくてやりたくてたまらないのだ。
春になり、翌季のプログラムをさっさときめてしまうと、クリストフは休暇を取って、あちこちを好きなように旅した。そのとき、ロシアにも行く機会があった。ヴィクトルに連絡を入れたら、仕事でモスクワにいるという。クリストフはホテルのレストランで彼と落ち合った。
「勇利とセックスしたぞ!」
会うなりそう言われたのだが、クリストフが驚いたのは、その発言のためではなかった。ヴィクトルの表情がいままでとはまったくちがうのである。常にとろけており、にこにこしており、瞳はきらきらと輝いていた。彼は、勇利が、勇利は、勇利に、勇利を、と勇利の話ばかりした。簡単に言えば、ヴィクトルは、完全に腑抜けになってしまっていたのだ。
「ヴィクトル……」
「クリス、聞いてくれ。勇利と初めてした翌朝、俺は感動のあまり口を利けなかったんだ。そしたら勇利がなんて言ったと思う? せつなそうに俺をみつめて、『後悔してるの?』とこうだ。してるわけないだろう!」
「ヴィクトル、声が大きいよ」
「勇利はかわいいんだ。くわしいことは言えないけどね。とにかくかわいかったんだ。かわいかったということだけしか言えない。あんなにかわいい生きものに俺は会ったことがない。何を食べたらああもかわいく育つんだ? この世には不思議なことがあるものだね!」
クリストフの知る限り、ヴィクトルはもう長く、勇利のことばかりみつめていた。それも、いとしくていとしくてたまらない、というとろけたまなざしだった。勇利から視線をそらさないのである。勇利がよそを向いて何か話していても、うん、うん、とうなずきながら勇利だけを見ていた。愛情にみちたとろりとした表情は、まわりのほうが赤面するほどだった。声も勇利に話すときだけこのうえなく優しく、甘ったるくて、たわいないことを口にしていても、愛してるよ、大好きだよ、絶対に離れないよ、とささやいているようだった。そんなヴィクトルだったから、この男、勇利を抱いたらどうなってしまうんだ、と心配になることがあった。その答えがいまわかった。こうなるのだ。
「ヴィクトル、なんか原型とどめてないよ」
「何のことだ?」
「どろどろにとけちゃって、人のかたちをしてない」
「してるよ!」
「今日なんの仕事だったの?」
「撮影」
「服?」
「ああ」
「ダメ出しされただろ」
「よくわかるね」
わからないわけないだろう。
「どうやってオーケィもらったわけ?」
「かっこいい顔をしろと言うものだから、勇利が喜びそうなヴィクトル・ニキフォロフ、という題目を自分に与えてみた」
「ここでも勇利か……」
クリストフはグラスを掲げた。
「童貞卒業おめでとう」
「ちがう」
「でもそんなようなものだったんだろ。ちゃんとできたの?」
「聞きたい?」
「聞きたくない」
「ふふふふふ……」
「ヴィクトル、俺といるあいだは正気を保ってくれ」
「そうそう、俺はクリスに相談があったんだ」
ヴィクトルが思い出したように言った。
「最高にしあわせそうだけど、相談するようなことあるの?」
「あるとも」
彼は、勇利勇利と騒ぎ、うきうきとはしゃぎきっていた態度を改め、まじめな顔をした。お、これはちゃんとした話か、とクリストフも背筋を伸ばした。
「いま話した通り、俺は勇利と結ばれた」
「やっぱり勇利の話なわけね」
「もう毎日がばら色で、最高の日々だ」
「ヴィクトル、顔、顔。またとけてる」
「好きな子とのセックスがあんなにいいものだとは思わなかった……」
「顔」
「勇利を見るたび、ああこの子を抱いたんだなと実感がわいて、うれしく、幸福に、そして苦しくなる。人を愛するとは大変なことなんだね」
「ほんとに相談なの? のろけられてる気しかしないんだけど」
「リンクでも、『でれでれするな』とまわりによく怒られる」
「簡単に想像がつくよ」
「勇利との暮らしのいとなみは喜びだ。しかし……、」
ヴィクトルはそこで眉根を寄せた。いかにも男らしい、苦悩にみちた表情だった。
「……勇利がかわいすぎるんだ」
彼はぽつんと言った。クリストフは聞きまちがいかと思って、「え?」と訊き返してしまった。
「勇利がかわいすぎるんだ」
ヴィクトルはくり返した。聞きまちがいではなかった。
「見ているとつらくなるくらいいとおしいんだ」
「…………」
「心臓が止まりそうになることは一日に両手の指の数を超える」
「…………」
「勇利があまりにもかわいい」
ヴィクトルは声を振り絞って言った。
「勇利はあんなにかわいくて、果たして大丈夫なんだろうか……!?」
クリストフは静かに目を閉じた。落ち着かなければ……。
「……それは誰かにさらわれるかもしれないとか、ファンが過激になるのではとか、そういうこと?」
「それもある」
ヴィクトルはきまじめにうなずいた。
「でもそういう俗っぽいことだけじゃなくて……なんというか……」
彼は言葉を探しながら視線を上に向け、しかし上手く思いつけなかったようで、クリストフをみつめ直して深刻そうに言った。
「大丈夫だろうか?」
つまり、勇利を愛していて、勇利がかわいいから、勇利に関して正体不明の不安に襲われる、ということらしい。とうとうヴィクトルもこんなふうになってしまった。
「大丈夫だと思うよ」
こうして骨抜きになっている手合いに理を解いても仕方がないので、クリストフは適当に、しかし態度だけは誠実に、きちんと請け合った。
「そうだろうか」
「ああ」
「大丈夫かな」
「大丈夫さ」
「あんなにかわいいのに?」
「君がついていれば大丈夫」
それでヴィクトルは納得したらしかった。しかし、この手の病気は、安心したそばからまた「大丈夫だろうか」と発症するので、クリストフは早々に退散した。すっかりどうしようもない男になってしまったが、まあなんだかんだいって、試合に入るころには完璧に仕上げてくるだろう。ヴィクトルはそういう男だ。その点に関しては、クリストフは安心していた。
ふと思い立って、サンクトペテルブルクにも立ち寄ってみた。ヴィクトルの様子があれほどおかしかったので、勇利も変になっているのではないかと心配したのだが、彼のほうはいつもの勇利だった。髪がすこし伸びていた。
「ヴィクトルの好み?」
「何が?」
「髪」
「ああ、いや、ちがうよ。行く時間がなくてね。それに、どこで切ればいいのかわからないし、言葉もまだ不自由だし」
「ヴィクトルについてきてもらえばいいじゃない」
「そうなんだけど、ヴィクトルも忙しいんだよね。あ、ヴィクトルとは会った? いまモスクワなんだけど」
「会ったよ。勇利の話ばっかりされた」
「ほんと? ごめん。やめろって言ってるんだけど……」
「まあいいさ」
クリストフは寛大なところを示した。
「基本的にぼくの言い分を聞かないんだよね」
「自由だからね、彼」
「困ったひとだよね。そこがヴィクトルのいいところなんだけど」
勇利は頬に手を当て、ふう、と吐息をついた。クリストフはなんとなく、「エロス」で表現していたのとはちがう、これまでになかった微妙な色気というものがある気がして、なるほど、と思った。これもヴィクトルが与えたものだろう。
「もう『知っている側の人間』というわけだ」
「え?」
勇利は不思議そうに首をかしげた。一転して無邪気でおさなげなそのそぶりを見て、クリストフはヴィクトルの発言を思い出した。
『勇利が、なあに? という感じで首をこう傾けるのがまたかわいらしいんだ。最高にチャーミングなんだ。俺の勇利はすばらしいんだ』
「はいはい」
「え?」
「いや」
クリストフは別れ際、勇利にほほえみかけ、「ねえ勇利」と呼んだ。
「ん?」
「いま、しあわせかい?」
勇利は目をみひらき、それから頬をほんのりとりんご色に染め、こっくりうなずいて「うん……」と言った。
「それはよかった」
クリストフはにっこりした。
「あ、そうそう、もうひとつ」
「なに?」
「ヴィクトルと初めて寝たとき、あの男、ぐずぐずして、手違いを起こしたり、慌てふためいたりしなかった?」
勇利は口をぽかんと開けた。彼は視線をそらし、あっちを向いたり、こっちを向いたりと落ち着かない態度を示した。そしてまっかになった。クリストフは笑いながら返事を待っていた。勇利はうつむき、気恥ずかしそうにはにかんでつぶやいた。
「そんなことない。ずっと、かっこよかったよ……」
勇利が金メダルを獲ったとき、ふたりは結婚することになった。クリストフは彼らのインタビューをすぐそばで見ていた。
「ずっと仲はよろしかったですが、いよいよご結婚ですね。いつから交際なさっていたのですか?」
「え? 交際……?」
勇利は戸惑ったようにかたわらのヴィクトルを見上げた。ヴィクトルがほほえんだ。勇利は話者に視線を戻し、率直な口ぶりで返事をした。
「交際というのは、えっと、していません。ただ、金メダルを獲ったから結婚だってヴィクトルが……」
ヴィクトルが勇利の肩を抱き寄せ、陽気に片目を閉じて言い添えた。
「交際0日で結婚だよ! ね、勇利!」
クリストフはしあわせそうな彼らを眺め、まあこのふたりだから……という奇妙に悟りきった気持ちを持ちながらも、一応はつぶやいた。
「え? そうだったの?」
3 notes
·
View notes
Text
I miss you.
ヴィクトルはうっすらと目を開けた。ほとんどまどろみながら寝返りを打ち、腕の中にあるはずのぬくもりを抱きしめようとした。何も手にふれなかった。彼は手を差し伸べ、敷布の上をそっと探った。それからはっとまぶたをひらき、急いで起き上がった。ふとんが落ちて背があらわになる。しっかりとした筋肉に覆われた背中には、左右に赤い筋がいくつかはっきりとついていた。しかしヴィクトルは痛みに構いつけず、ベッドから飛び降りて扉へ走った。
「勇利!」
乱暴に戸を開け、廊下へ出る。
「勇利! 勇利!」
台所に入ると、ヴィクトルの絶望的な声に驚いた勇利が振り返った。
「なに? 朝から騒々しい……」
「勇利……」
ヴィクトルはほっと息をついた。勇利は真っ白いシャツに、ヴィクトルがよく「ダサい」と批評するジャージのパンツという姿で朝食をつくっていた。
「もうちょっと待って。あとすこしだから……」
勇利は目を伏せながら言った。
「それより、素っ裸なのをどうにかしてよ。まったくもう……」
ほんのりと頬を赤く染めて勇利が苦情を述べる。彼が着ているシャツはヴィクトルのものだ。大きくてだぶついている。ヴィクトルは胸が痛くなり、勇利に近づいて彼を抱きしめた。
「ちょっと、話聞いてた?」
「ああ……」
ヴィクトルは勇利の肩口におもてをうめ、額をすり寄せた。勇利が苦笑を浮かべてヴィクトルの髪を撫でる。
「早く何か着て。風邪ひくよ」
ヴィクトルが身支度を終えて戻るころには、食卓の上に美味しそうな朝食ができあがっていた。ヴィクトルは無言で席につき、挨拶をして食べ始めた。
「ジャム? バター?」
「バター」
「はいどうぞ」
勇利はほほえみ、すみのほうで食事しているマッカチンを眺めている。ヴィクトルは黙ってパンを口に入れた。
「どうして何も言わないの?」
勇利が笑みをヴィクトルに向けた。ヴィクトルの胸はずっと痛んでいた。ゆうべ、いつもより激しく、熱烈に勇利を抱いたときから苦しかった。いや……、もっと前から。どうして勇利は笑っていられるのだろう?
「きみに捨てられる」
ヴィクトルはぽつりとつぶやいた。勇利が困ったように笑った。
「なに言ってるんだよ」
「俺を捨てて日本へ帰る」
ヴィクトルは反抗的に言った。勇利は答えずにスープを飲んでいる。
「俺を愛してないのか?」
「好きだよ」
「それなのに俺をひとりにするのか。俺をロシアにほうり出して、勇利は勇利の好きなようにするわけだ。俺とマッカチンはどうすればいい? 勇利がいなくなったらすぐによわってしまう」
「大丈夫だよ。ヴィクトルは強いから」
「そんなのは幻想だ。勇利が勝手に俺に押しつけた役割だ」
勇利はサラダを口に入れ、ゆっくりと咀嚼してからヴィクトルを見た。
「さびしい?」
「さびしい」
ヴィクトルは勇利に顔を近づけた。
「勇利はさびしくないのか?」
「さびしいよ」
「おまえは俺と離れて平気なのか? 俺がいなくても生きていけるのか? 俺を愛しているなんてうそだろう。本当は、俺のことなんかぽいっと捨てていけるんだ。美女が色男を捨てるみたいにね。そうだろう」
「ヴィクトル、落ち着いて」
「なぜ勇利は落ち着いていられるんだ。俺がこんなに苦しんでいるっていうのに!」
「わかってたことでしょ。もうきめたって言ったじゃない」
勇利は物穏やかにつぶやき、トーストに赤いジャムを塗った。
「どうしようもないんだよ……いまさら」
「遅くなんかない」
ヴィクトルは必死に言った。
「やっぱりやめよう。ここにいてくれ。離れたくない」
「無理だよ」
「俺がかなしんでも平気なのか? 俺を愛してないのか?」
「愛してるよ……ヴィクトル、おねがいだからそんなこと言わないで……」
「勇利はひどい」
勇利はそっとかぶりを振り、あえかな息をついた。
「俺のことなんてぜんぜん考えてくれない。本当は俺から離れられてほっとしてるんじゃないか? 日本へ帰ったらせいせいするだろう」
「ヴィクトル」
勇利はそっと目を上げると、せつなげにヴィクトルのことをみつめた。ヴィクトルの胸は引き絞られた。勇利の瞳は、いつも通り、「貴方を愛している」と訴えていた。しかし勇利は日本へ帰るのだ。ヴィクトルを置いて。
「……ごめんなさい」
勇利のやるせなさそうな謝罪に、ヴィクトルはかえって苦しくなった。そんな言葉はいらない。ただそばにいて欲しかった。だが勇利は、一度きめたことはやり通す。彼がここに残る望みはない。ヴィクトルは明日からひとりなのだ。
ヴィクトルがソファでマッカチンを撫で、ぼんやりしているあいだに、勇利は手早く朝食の後片づけをした。ヴィクトルの視界には、勇利が部屋から出してきたトランクがあった。あれをいますぐどこかへ捨ててやろうかと思った。燃やしてやりたい。そうしたら勇利は帰れまい。ずっとここにいてくれる。
「冷蔵庫に残ってるものは明日までに食べてね」
勇利がそばにやってき、隣に座った。
「洗濯物は昨日全部きちんとしておいたから。ヴィクトルは自分でするとき、乾燥機に入れたまま忘れちゃうからね。気をつけて」
「勇利が気づいてくれればいい」
勇利はかなしそうにほほえんだ。
「牛乳の期限はちゃんと見て。おなかを壊すよ」
「勇利が気をつけてくれればいい」
「マッカチンのごはんは入れすぎちゃだめ。食べさせすぎ厳禁だよ」
「勇利がしてくれればいい」
「電話にはちゃんと出て。ぼんやりしてるとヤコフコーチに怒られるよ。仕事もきちんとね。下着とか靴下はいちばん上のひきだし。ないないってあちこち探さないで」
「勇利が……」
「ぼくがいなくてもちゃんと寝て、ちゃんと起きて」
「…………」
「ぼくが……、」
勇利はささやいた。
「ぼくがいないからって、何もかも投げ出したりしないで……」
「勇利」
ヴィクトルは勇利を抱きしめた。
「いやだ。いやだ……行かないでくれ……」
「ヴィクトル……」
「離れたくない。そばにいて欲しいんだ。耐えられない……」
「…………」
「勇利がいなくちゃ、俺は……」
勇利は手を伸べ、そっとヴィクトルの背を撫でた。わかっている。もう何度も話しあったことだ。ヴィクトルもうなずいたし、それが勇利のためだと理解している。どうしようもない。
けれど、でも──いやなのだ。勇利と一緒にいたい。離れたくない……。
「……そろそろ行かなくちゃ」
勇利が優しくヴィクトルの胸を押した。けなげな甘い瞳でさびしそうにヴィクトルをみつめる。
「ごめんね、……ヴィクトル」
勇利は部屋へ行くと、着替えを済ませ、洗濯室にヴィクトルのシャツを持っていった。あれを俺が洗濯するのか。勇利がいた痕跡を俺が消す……。ヴィクトルは胸が苦しかった。
「送るよ」
「……ありがとう」
勇利を車で空港まで送るあいだ、ヴィクトルはひとことも口を利かなかった。何か言ったら言葉があふれだし、行くな、俺のそばにいろ、絶対に離さない、とわめいてしまいそうだった。勇利は窓にばかり顔を向け、頬杖をついていた。彼もヴィクトルを見たら泣いてしまうのかもしれない。そんなかたくなさが感じられた。
大勢の人々が行き交う空港のロビーで、勇利はヴィクトルをまどかな目で見上げて控えめに言った。
「ここでいいよ。長く一緒にいるとつらくなるし」
決心がにぶるということだろうか。だったらずっといて気持ちを変えさせたい。
「あんまり裸でうろうろしちゃだめだよ」
勇利は最後だというように無理に笑った。
「ごはん、ちゃんと食べて」
「…………」
「ヤコフコーチを怒らせないようにね」
「…………」
「それから……」
「勇利」
ヴィクトルはたまらず勇利を引き寄せ、力いっぱいかき抱いた。
「やっぱり行くな。行かないでくれ」
ヴィクトルは絞り出すような声でささやいた。
「行かないでくれ……」
「ヴィクトル……」
「いやだ。いやなんだ。そばにいてくれ……」
「…………」
「愛してるんだ……」
「ヴィクトル……」
「行くな」
勇利はいちずで純粋な瞳でヴィクトルをまっすぐに見た。彼はヴィクトルの頬にためらいがちにふれた。彼の可憐なくちびるから、ぽろりと言葉がこぼれた。
「好き……」
「勇利」
「もう行くよ」
搭乗の知らせが流れていた。勇利はヴィクトルから離れると、足元に置いていたトランクをつかみ、にっこりと笑った。
「じゃあね、ヴィクトル……」
「勇利」
「どうもありがとう」
勇利は、泣き顔は見せたくないというようにさらにほほえんだ。ヴィクトルは笑えなかった。勇利はさっときびすを返した。彼は一度も振り返らなかった。泣き虫の勇利は、ヴィクトルよりずっと強いのだった。
ヴィクトルは勇利の背中を見送っていた。胸が苦しい。息ができなくなりそうだ。勇利の姿が見えなくなった。
勇利。おまえをずっと、俺の腕の中に閉じこめておけたらいいのに。
勇利のいない毎日は、単調で色褪せて見えた。退屈などという言葉では生易しい。ヴィクトルの瞳にはすべてがつまらなく映り、何もする気が起きなかった。勇利と歩きながらなんてうつくしいんだとふたりで感心した風景も、いまとなっては味わいもうるおいもない、いかにもそっけないものに思えた。あれほどあたたかそうに見えた自分の家は、冷ややかな、自身を拒絶する場所のように感じられた。好きだった音楽もまったくこころに響かず、聞くのがいやになってしまった。勇利が注意したことを守ろうと思うのだけれど、どうしてもそうすることができなかった。ヴィクトルは勇利と眠ったベッドでマッカチンを抱きしめ、つらい思いで夜を過ごした。食べなければ勇利に怒られるというただそれだけの理由で食べ物を買いに行った。つくる気にはとうていなれなかった。勇利とふたりで料理をした台所でなんて働けなかった。ヴィクトルは総菜を見てまわり、勇利の好きそうなものをみつけると、勇利に買っていってあげよう、と思いつき、次の瞬間、勇利はもういないのだと思い出して苦しんだ。ひとりぶんの食事をどうにか確保し、帰途へ着いたら、花屋がたくさん目についた。勇利に買ってあげよう���また思い、その必要はないのだと気がついてうつむいた。
『これ、ぼくに? ありがとう。綺麗だね』
『わあ、美味しそう。こぶたにならないように気をつけないと』
『どこに売ってたの? 今度一緒に買いに行こうよ』
『ヴィクトル』
『ねえ、ヴィクトル……』
何もしたくなかった。ヴィクトルは昼間は機械的に行動し、夜はソファでぼうっとした。あるべきものがないのだ。勇利がいなくなってから。この家のいたるところに勇利の思い出があり、あれは勇利が寝惚けてぶつかった壁、あっちは花瓶の水をこぼした床、これは図書館のようだと言った本棚、と数え上げてしまう。勇利と親密に過ごしすぎて、思い出すことが多すぎた。
「勇利……」
勇利のところへ行きたかった。彼のいない生活なんて耐えられない。
「どうして俺を捨てたんだ……」
愛していると言ってくれたのに。あんなに熱烈に抱きあって、くちづけを交わし、想いを確かめあったのに。
「なぜ、俺を……」
ヴィクトルは膝に額を押し当てた。マッカチンが心配そうに寄り添った。
「勇利に会いたい……」
勇利のやわらかな笑顔が見たかった。彼の優しい声が聞きたかった。勇利を……。
勇利を、この腕に抱きしめたかった。
日本へ戻ってしばらくは慌ただしかった。勇利は無我夢中で過ごし、ようやくすこしくつろぐことができるようになった。長谷津は変わっていなかった。まったく同じだった。勇利がヴィクトルとロシアで暮らしているあいだも、ここにはずっとなつかしい空気が流れていたのだ。それは帰郷した勇利を優しく迎え、包んでくれた。そう。同じだ。あのころと。
……ヴィクトルがいたころと……。
町を歩けば、「先生はどがんしたと?」「今日はヴィクトルはおらんの?」と尋ねられる。勇利はそれがつらかった。笑顔で「うん、いないんだ」と答えるのは身を切られるような苦しみだった。こんなふうにヴィクトルと離れることになるなんて、思ってもみなかった。ロシアへ行ったばかりのころは……。
「……ヴィクトル」
勇利の目に涙が浮かんだ。ヴィクトルが恋しかった。彼に会いたかった。抱きしめてもらいたかったし、優しいキスが欲しかった。ヴィクトルはいつもすてきに笑い、勇利にいろんなやり方で愛をささやいたものだった。それは言葉だったり、しぐさだったり、まなざしだったり、……情熱的な愛撫だったりした。勇利はヴィクトルの愛を一身に受け、しあわせな日々を過ごしたのである。長いような、短いような時間だった。だが、このうえないすばらしい毎日だった。いまヴィクトルは勇利のそばにおらず、彼を感じることはできない。
ヴィクトルの部屋に入る勇気がなかった。初めて長谷津へ来たとき、ヴィクトルはそこを「こぢんまりしててクラシカルな部屋だね」と批評した。ロシアのヴィクトルの家はひろくてしゃれていて、すてきだった。しかしヴィクトルは幾度も言っていた。
『長谷津が恋しいよ』
『あの部屋でまた過ごしたい』
『勇利とふすま一枚をへだてて眠りたい』
彼は、「いまなら一緒に寝たくなって、勇利の部屋へ押しかけるかも」といたずらっぽく笑ってもいた。勇利も笑顔で「ぼくのベッドは狭いよ」と言った。しかし、ヴィクトルのいないベッドは、果てしなくひろく感じられた。ヴィクトルとともに眠る大きなベッドよりもずっと……。
長谷津は、どこもかしこもヴィクトルとの思い出だらけだった。家はヴィクトルと住んだ家だし、リンクはふたりで長く過ごした場所だった。町にはよく買い物に行ったし、長谷津城のほうは鍛錬場だった。どこもヴィクトルがいなければおかしく、ヴィクトルと訪れなければさびしいばかりだった。
勇利はリンクへ通い、熱心にスケートに打ちこんだが、何か上手くできたときはリンクサイドを振り返り、「ヴィクトル、よかったでしょ!?」といつも言ってしまった。自分のプログラムをすべろうとしても、気がつくと「離れずにそばにいて」を踊っている。どうしようもない。ヴィクトルがいなければ……。
リンクの真ん中から、いつもヴィクトルがいた場所をみつめた。
『思い出してみるんだ。恋人に愛されたこと』
『最高のテーマだね』
『勇利、曲名決めてなかったけど、どうする?』
『見たいね!』
「……ヴィクトル」
勇利は両手でおもてを覆った。こんなところにはいられなかった。ひとりではいられない。ここはヴィクトルとふたりの場所だ。
耐えきれず、建物の外へ逃げ出した。ヴィクトルとの思い出がないとこ、と考え、そんなところはひとつもないし、そんな場所へは行きたくもないのだと気がついた。矛盾している。ヴィクトルと親しんだところはつらくてせつない。しかし、ヴィクトルを思い出せない場所へは行きたくない。
勇利は町をさまよい歩いた。ヴィクトルと歩んだ道をたどった。商店街も、コンビニエンスストアも、田んぼのあぜ道も、ひとりで訪ねた。町を見晴るかす長谷津城でベンチに座り、ヴィクトルとの最初の練習を思い出した。勇利は緊張して彼とまともに話せなかった。ヴィクトルは一生懸命勇利の気持ちをやわらげようとしていた。彼は写真を撮ってと言い、その写真は世界じゅうをかけめぐって……。
なつかしかった。あのとき自分はヴィクトルがそばにいることが信じられず、これは現実なのだろうかと半信半疑だった。しかしいまは、ヴィクトルがかたわらにいないことが信じられない。
「ヴィクトル……」
勇利の目に涙が浮かんだ。勇利は泣き虫だからね、と笑うヴィクトルの顔が思い出された。勇利は立ち上がり、とぼとぼと歩いてリンクへ戻った。スケートをしているときがいちばんヴィクトルを感じられた。勇利は夢中ですべった。「エロス」はヴィクトルが初めてくれたプログラムだった。「Yuri on Ice」はヴィクトルと出会ってから知ったすべての愛を表現した曲。そして──、「離れずにそばにいて」。ヴィクトルとめぐりあうことになった、大切な曲だ。これは勇利のプログラムではないけれど、自分のものと同じくらい身近でいとしい、愛の感じられるプログラムだった。
ああヴィクトル。どうして貴方はそばにいないの。あんなに愛してくれたのに。愛していると言ってくれたのに。離れたのはぼくだ。そんなことはわかってる。でもつらいんだ。貴方にそばにいてもらいたい。抱きしめて、キスをして、愛してるよとささやいて、ぼくを貴方のものに──。
「勇利!」
最後の天を仰ぐ姿勢で静止していた勇利は、その呼びかけに、はっと我に返った。信じられなかった。幾度となく聞いた、あたたかな、はかりしれぬ愛のこもったいとしい声だ。ヴィクトルの水際立った、優しい声──。
勇利は振り返った。ヴィクトルが氷に足を踏み出すところだった。目を疑った。ヴィクトル──ヴィクトル? ぼくのヴィクトル?
「勇利!」
ヴィクトルがすべり出した。勇利も彼に向かって駆け出した。
「ヴィクトル!」
「勇利!」
ヴィクトルはうれしそうに笑っていた。しかし勇利は笑えなかった。泣き出してしまった。勇利は勢いよくヴィクトルにぶつかり、彼に抱きついて胸に顔をうめた。
「ヴィクトル……!」
涙があふれ、ヴィクトルのシャツを濡らした。ヴィクトルは勇利をきつく抱きしめ、「ああ勇利、俺のかわいい勇利」とささやいた。
勇利は混乱のあまり、自分を見失っていた。ただヴィクトルにすがりつき、ヴィクトル、ヴィクトル、とくり返した。ヴィクトルは勇利の髪にキスし、勇利におもてを上げさせると、顔じゅうに接吻した。
「ヴィクトル」
勇利の声は涙に濡れていた。ヴィクトルはくちびるにくちづけた。勇利は目を閉じた。あたたかく、愛情深いキスだった。夢中でくちびるを押しつけた。
「……俺の勇利」
ヴィクトルが熱っぽくつぶやいた。勇利の身体はふるえていた。止まらなかった。
「会いたかった……」
「……ぼくも」
「勇利のことを考えない日は一日もなかったよ。何をしていても勇利のことばかりだった。勇利……」
「ヴィクトル、もっと強く抱いて」
「大事な俺の勇利。俺の最愛。俺だけの、得がたい天使……」
勇利はヴィクトルの胸に頬をこすりつけた。ふたりは身を寄せあい、視線を合わせてはくちづけを交わし、互いがどんなに必要か、どれほど愛しているかを、目で、しぐさで、キスで伝えあった。
「ヴィクトル……」
「ごめんね、何も言わずに」
ヴィクトルはいたずらっぽく笑った。
「どうしても会いたくなって……、我慢できなかったよ」
勇利は伸び上がってまたキスをした。
「驚いた?」
「驚いた……」
「うれしい?」
「うれしい……」
勇利はあえぐように言った。
「なんにも手につかなかった……頭の中はヴィクトルのことばっかり……ずっとヴィクトルの思い出をたどって、ぼく……」
勇利はヴィクトルにすり寄り、甘えてねだった。
「ね、ヴィクトル……ぼくと町じゅう歩いて……」
「うん?」
「ヴィクトルがいない長谷津はさびしくてつらかった……貴方がいなきゃだめだよ……」
「もちろんいいよ。一緒に行こう。どこへでも。またこのリンクでもふたりで過ごそうね。でも……」
ヴィクトルは、きらきらと輝く愛情いっぱいの瞳で勇利をみつめた。
「まず行きたい場所は……」
「なに?」
「俺の部屋のベッドかな……」
「疲れてるの?」
それは大変だと勇利はリンクから出、スケートシューズを脱いだ。そのあいだも、ふたりの手はずっとつながっていた。不便でも離したくなかったのだ。
「そうじゃない」
ヴィクトルは勇利の耳元にくちびるを近づけ、ひそやかにささやいた。
「ふたりで寝たいねってことだよ……」
勇利は目をまるくした。
「思いきり勇利をかわいがりたい……、いいだろう、勇利……」
勇利はまっかになり、ヴィクトルをにらみ、それから彼に勢いよく抱きつくと、純真な瞳をヴィクトルに向けて、舌足らずに言った。
「うん。いっぱい、いっぱい、たくさん……、して」
チムピオーンスポーツクラブのリンクには、今日も多くの生徒が集まっていた。シーズンが終了し、それぞれひと息ついているところなので、まださほど熱心な練習ではない。これからはアイスショーもあるし、国民に名前をおぼえられている選手は、そういった方面での仕事もある。
ミラも取材対応やアイスショーの打ち合わせなど、すこし別のことをしなければならない時期だった。だが、そんな彼女よりはるかに忙しい男がいて、彼はそれでもスケートの水準を保つため、できる限りリンクへかよってくる。皇帝ヴィクトル・ニキフォロフは、才能と努力と情熱を兼ね備えた、スケートをするために生まれてきたような男だった。もっともこの一年は、スケート以外にもこころを捧げていたようだが。いや、一年どころか、さらにその一年前からのことだろう。しかし、それもよい刺激となっているようだ。ヴィクトルは彼が来てからというもの、このうえなく色彩豊かで、感情があふれ出るようなスケートをするようになったのだ。さまざまな意見があるようだが、ミラはいまのヴィクトルのスケートのほうが好きだった。
だが、今日はそのヴィクトルがいないようだ。取材などは入っていないと聞いていたのに。それはなんとなく耳にした情報で、ミラはヴィクトルの予定をすべて把握しているわけではないから、何か変更があったのだろう。
「ヴィクトルはいないのね」
ちょうどユーリがやってきたので、なにげなく彼女は言った。
「取材? 撮影? 忙しいわよね」
適当なあいづちを打ってもらえばそれで終わる話のはずなのに、ユーリはなぜかうんざりしたような目でミラを見た。
「何よ。私、変なこと言った?」
「変なのはおまえじゃねえ。ヴィクトルだ」
「どうしたの?」
「あいつ、日本へ行ったぞ」
「え? なんで?」
反射的にミラは尋ね、すぐに思い直した。
「今日からだっけ?」
「ちがう。でも行ったんだ」
「どうして?」
ユーリは深い溜息をついた。
「あいつがヤコフに必死に訴えてるところを見ちまった……」
「何を?」
「カツ丼がいなきゃ死ぬって」
「は?」
ミラはぽかんとした。
「もう我慢できない、俺は日本へ行く、そのために詰めこんで仕事も片づけた、何も問題はないはずだ、つってものすごい勢いで出ていったぞ」
「それいつの話?」
「昨日」
「だって……」
ミラはつぶやいた。
「……どうせ、来週から日本でしょ?」
そう聞いている。ヴィクトルは今週いっぱいはロシアにおり、それから日本へ発つのだと。オフシーズンを勝生勇利の故郷で過ごし、あちらでアイスショーに出演し、ヴィクトルと勇利それぞれのプログラムを練ってくるのだ。
「仕事の都合で、カツキのほうがさきに帰国したんでしょ? 四日……三日前だっけ?」
「そうだ」
ユーリは疲れたような顔をしていた。
「ヴィクトルはただ一週間遅れっていうだけでしょ? すぐ会えるんでしょ?」
「その『すぐ』が待てなかったんだ」
ユーリはゆっくりとかぶりを振った。
「たったの一週間もひとりでいるのが耐えられないって、いったいどういう感覚なの?」
ミラはこれまでさんざん、「一緒にいなかったら死ぬのね」「目を合わせないと息ができない病気なの?」「身体の一部がふれてないと心臓動かないんじゃない?」とふたりをからかってきたのだが、まさか��れほどまでとは思っていなかった。自分の発言は、あながちまちがいとも言えないようである。
「まあ想像がつくぜ……」
ユーリはやっていられないというように吐き捨てた。
「どうせ離れるときも、今生の別れみてーな気色のわりい雰囲気出してやがったんだろ……」
「……でもカツキが止めるんじゃない? あきれるというか。さすがに」
「おまえはあいつらを甘く見すぎだ」
ユーリが厳しく言った。
「けど、普段わりとそっけないところがあるじゃない」
「あんなのカツ丼の性格がおかしいだけだぞ。あいつだってヴィクトルに負けず劣らずとち狂ってるし、ヴィクトルヴィクトルって頭やべえんだよ」
「そうか……そうね……」
確かに勇利は、ヴィクトルを適当にあしらうこともある。だが、そうでないときは、とにかく乙女もこれほどだろうかという目つきでヴィクトルをみつめ、とろけきっているのである。めろめろのとろとろだ。
「ったく……ばかばかしいぜ……」
「本当に、離れたら死ぬのね……」
それならば、相当にせっぱつまって会いに行ったのだろう。いまごろ再会しているころだろうか。どうせ、生涯会えないと思っていた相手と、困難を乗り越え会うことができた、というような雰囲気たっぷりの逢瀬をしているにちがいない。ミラは笑ってしまった。
「三日しか��たなかったのね……」
1 note
·
View note