#滑稽のドア
Audio
🆕🎶 「 閉鎖的シェリーベン・アングラーフI型II型 」 new single by 滑稽のドア is now available worldwide! 🌐
Listen now and discover new sounds from Japan on our weekly updated playlist 🎧 https://spoti.fi/3lgjH73
0 notes
Text
2023/05/06-1
とても良い日になった。
天気予報はずっと雨で、それが前日に曇りに変わり、そして晴れた。

感慨もなく昼から式場に入り、ここで着替えてくださいと着替えを渡され、そして随分待たされた。
鳥かごに取り残されたような気分でただ時間が過ぎていくのを待つ。その間に両親の着替えや両家の顔合わせ、なにより奥さんの準備が進められていた。
当事者なのに何も立ち会えない。
2時間ほどで、突然式場のドアの前に連れてかれて「始まります」と告げられた。
本当にこの先に友人たちは待っているのだろうか。知らない顔だらけで、「あなたは誰?」といった雰囲気の中で誓いの所作だけをする。
そんな滑稽なことになるんじゃないのかと少し思った。扉が開くと真っ赤な絨毯とその先にある十字架しか見えなかった。何故か処刑台に登るような気持ちが湧いてきて、吊るし上げられてるような面持ちになってしまった。
ああ、これが緊張かと。遅れて気づいた。
「新婦の入場です」の声で一斉にみなが振り向いたときにようやく見知った姿がたくさん見えて少し安心した。扉から見えたお義父さんはとても緊張していて、奥さんは嬉しそうだった。
並ぶ席とレッドカーペット、そして祭壇。すべてに隔たりがあり客席と舞台、そしてそれを高くから見つめる神様くらい。それぞれがそれぞれで、妙な気分だった。

ユリの花も、オルガンの音も、光も影も、賛美歌も、誓いの言葉も、通り過ぎていくものだった。
途中で考えるのをやめた。たくさんの顔、たくさんの視線。どこに焦点を合わせればいいかまったくわからなくなってしまった。
ただ、笑っていることにした。生まれてはじめてピエロになり、祝福に閉じ込められていく。
切られるシャッターとストロボ。
すべての判断は後で良い。披露宴が始まれば何かが交わるさ。
そんなことを思いながら式が終わっていった。風が強く、暖かく。それが良かった。それだけでも良かった。
11 notes
·
View notes
Text
ある画家の手記if2 - 2 雪村泉視点
目が覚めたとき身体はなんとも無いか訊ねられ私は首をひねりましたが、お話しを聞くと、夜間に泣きわめき取り乱して、かと思うと呆然と動かなくなったりと奇行を繰り返していたそうです。
身に覚えは ありました 香澄が
私は何度もあの子を上手く抱きしめられずにいましたから
…。稔さんは特に叱ることもなく朝食の席に私を案内してくださり、その話はそれっきりでした。
ああ、そういえばお名前の字は稔さん宛のお手紙が届いたので知ることができました。中里稔さん。
あれから、今でも…拾ってくださってから毎日、私に何をさせるでもなく衣食住を提供してくださっています。
どこか懐かしい家と食事
服は、家を出るときからここへ拾われるまで身につけていたものはギリシャ神話の彫刻にでも出てきそうな薄く透ける布のワンピースで、スカート部分は全円にドレープのついた裾の長い、布をふんだんにつかったものでしたが、この一週間ほどは稔さんが服を貸してくださって、とても身軽な装いをしています。
夜間のありさまも一度触れたきりですが…ほとんど毎晩のように…ご迷惑をおかけしているはずです
どうして私を 助けてくださったのでしょう
私に商品価値を見出せる要素など無いことくらい知っています 恩を返せるあてもございません だからすぐに、見返りを求めて手を差し伸べてくださったわけではないことはわかりました
稔さんがお優しいからだ、そう思えばいい
でも、それなら私はここに居て 助けられた身で、どれほど勝手に振る舞ってよいものかと
未だに何一つ役に立つことはしておりませんし かといってこの脚で出て行くことさえしてよいものかわからない、本当に何の苦も無いようでいらっしゃるから
…ときどき、人懐こい方なのかと感じることもある
ここらには近隣の住民も居ないからお寂しいのか、稔さんに伴侶も恋人も居ないというのはにわかに信じがたいもののそういった人の影は見受けられません。私などではなくここにもっと馴染む相応しい方をお迎えする考えは無いのでしょうか
そっとこちらを見詰める姿が不意に幼いあの子に重なるような気がして思わず立ち上がると、部屋から出て歩み寄り稔さんの頭を撫でました。可愛らしいです。あからさまに主張するほどの幼さはもう示せないからか、言わないところが、逆に健気で。
伴侶や恋人というよりも、やはりペットか、何か触れあうことで癒される存在が相応しいのでしょうか。
それにつけても、私などでは犬猫にはかなうはずもございません
香澄のことを思い出したからかその日は 酷く苦しいおもいをしました。
「ところであんたは、感じてねえのか。自分に稔は不釣り合いだってことに?」
稔さんにパーティの同伴として連れられ…同伴者にはおこがましいほど美しい衣装を着せていただいて、私などがこのような…稔さんは主役にしてやるなどとおっしゃっていましたがやはり滑稽だったのでしょう、会場に入ってから今に至るまで値踏みされるような視線も言葉も多く投げかけられましたが直接的に指摘をされないまま、生殺しの有様でしたので、ようやく不釣り合いとはっきり言われたことにほっといたしました。
「はい、あの…勿論存じ上げております」
初めましてのご挨拶もそうそうに、でしたのでお名前もうかがっておりませんが、佇まいが会場の他の方々にも見劣りしない雰囲気を放っておられますので、付き添いなどとは違いれっきとした招待客の方なのだろうと類推させていただきました。稔さんのご友人でしょうか。なんにせよ、この場で私はあの方に連れられてきたのですから、失礼のないようにしなくては。
「あの方には助けていただいて…未だに私が何のあてもありませんのをこうして連れ出してくださったのです」
「そんで今日はなんの成果をあげたんだい、充分ちやほやされて肌艶いいじゃねえか。のらりくらりしてるようでいて稔は自分一人で生活していける、あの家は稔のもので稔の作った彫刻を収入源に動いてる、あんたを絞ればその1%でも収益が上がるか?毎日誰の飯食ってんだ?過去にあの家に居て、自立して出てった連中は多いぜ、稔といるとよく人材が育つんだよ。あんたは伸び代あんのか?あんたの人生に展望はあんのか?」
大きな目を睨むように眇めてこちらを見ていらっしゃる。まっすぐに見詰め返して、ああ、そうだ、笑わなくては。もっとちゃんと、ご不快のないように
「いえ…私には何も。愛玩のようなものなのでしょうか…あまりによくしていただいてはかり知れません…」
緊張しても主旨を取りこぼすことは無いはずです、私が何のお役にも立てず何の先の展望もないことは、事実ですから。間違いようがありません。
「ここまで役立たずどころか家の中を勝手に這いまわるあんたをどうして稔が家に置いてんのか、そんなご大層なドレスまで着せて連れ歩くのか、聞いてみたことはねえのか?」
「…ございません」
「なんで訊かねえ?」
……なんで…そういえば、あの家はほんとうに稔さんのお家で間違い無いのですね。彫刻を作ってらっしゃることも、私だけでなく他にもあの方を頼りにしている方がいらっしゃることも、初めて知りました
私は 稔さんに判断を委ねてばかりで 助けられたからと言い訳に身を預けて今まで、あの方のことを何も 何も考えていなかった…
「そうですね、うかがうべきでした。はやく出ていかなくてはならないのに必要以上のものをいただいてしまって…すみません、失礼します」
気付いたら、もうこれ以上この場には居られません もとより私の居るべき場所では無かったのでしょう
はやく、出て行かなくては この衣装もはやく、脱がなくては 私が身につけるには不相応なものなのだから 恩を返すあてすら無いなら、せめて一刻も早くこのギャンブルを終わらせましょう あの方がしてくださることが全部泡になってしまう前に、
胸元でキラキラと装飾が光って走るごとに責め立てられるようで
外そうと手を掛けるところで先に手首を掴まれた
「――――っ」振り払えないほどの力、けれど突如その手は離され 目の前を覆い隠すように人影が現れたかと思うと、
覚えのある香りが 、…稔さん
「……」
「……、…」
抱きしめられ ている。
っ離れなくては 咄嗟にそう思い手で押しのけようとすると更に強く抱きしめられ
手をついた胸元から力強い鼓動が伝わって、急に生々しい感覚に恐ろしくなるような力の抜けるような、…目の回るような感覚がいたしました
うまく息が吸えない
こんなに、しっかりとした、たくましいというのでしょうか、強く抱きしめられたことはありません 触れあう距離に居た相手は千風ばかりで、その彼は線の細いひとでしたから
「さっき詰られたことなら忘れていい、俺に聞きたいことがあるなら言ってくれ。
動けずにいると稔さんの声がすぐ耳もとでそう囁きました
覆い隠すような感覚は錯覚ではなく、背の高いこのひとに頭上からすっぽり抱き込まれているせいでした
ききたいこと…なんて もう、時期を逸してしまったのでは?
私は何も訊かないせいで結果的に自分に都合よく貴方を消費していたのでしょう
もう戻ることはできないのだと、告げるうちに稔さんが「愛している」と
私に そう言って
交わされた視線に余計に息が詰まる
いけません どうして…そんなこと
うれしいです、信じられない いけません、私など 釣り合わないのですから
やめて
私は誰かに愛されていいものじゃ無いんです
連れ帰られた稔さんの家ですぐにドレスを脱ぎました
あの家を出る時に着てきたワンピースは寝室の隅に掛けてあり、それを身につけるとすぐに玄関へ向かいましたが、稔さんにドアを塞がれてしまいました。
「通してください…」
ここで私を、見逃すだけでいい それで最後になる、愛していると言ってくれた…そんな感情を残していくわけにはいきません、コールした損失を一刻も早く無に帰すためには 手放してもう二度と、何も与えてたまるかと 思ってもらわなくては
貴方自身の手で捨ててくれなくては
「……それは漫然とここからただ倒れるまで歩いて死ぬことを意味する。どこかで死ぬくらいなら俺にここで殺されてくれ」
……!
突然の告白に顔が熱くなるのを感じ慌てて俯くと、稔さんも目の前で扉に凭れ座ってしまった
赤い顔を隠しようが無くなってしまいぎゅっと目を瞑る
…あの浜辺 あの時私はこの人に看取られるなら死も悪くないなどと浮ついた頭で考えた
軽く首を振って悪い考えをはらう この人の手を汚させるなどとんでもない そんな消えない楔を残すことなど
まだ何もないうちに跡形もなく消え去るために私は今すぐ出ていこうとしているのに
「俺とここに居てくれ 愛してる、泉」
「……」
それでも…それでもこんなにも
出て行こうとする私の行動が逆に、この人を傷付けているのがわかる
どうすれば 思い至らぬうちはそれでもよかった、私の勝手な行動で傷付けて申しわけありませんとすぐにでも謝って、その腕の中に戻ることもできたでしょう 切実に訴えてくださる貴方をどうして抱きしめずにいられるでしょうか
けれど今は そんな恥知らずな真似は…
「私は 罪人です」
ぐっと 両手を握りしめて言いました。知らせるしか無いのかもしれません ここまできたら お世話になったのだから
私が何をしてあの浜辺に至ったのかを そして何も知らせぬままのうのうと居座ったことを
「これ以上は貴方を蝕みたくない」
正直にそう告げて そうしたら、貴方もきっとわかってくださるでしょう…
ここまで、とほんとうにそう思ったら、身体から力が抜けてくずおれそうになってしまった。いけない、これからがしばらく動けなくてはならないのに…
少しの沈黙があって
「ーーーーおそらくお前より俺は罪人だ。俺と居て穢されるのは泉のほうだ。それでも俺はお前を穢してでもそばにいることを望む」
稔さんが…仰ったことは、思いもよらないことでした
このひとが…一体何の罪を犯したというのか、私には見当もつかなかったのです
腕を引かれ、倒れそうだった身体は無抵抗に脱力し床に座り込みました
稔さんの脚の間におさまり、間近にある顔を呆然と見上げ 考える。
嘘…なのかもしれない。よっぽど罪人…だというのは。
けれどもし本当だったとするなら罪人だと明かすことは 困難な決断だったはずです…いいえ、それは嘘であっても、でしょうか
罪の自覚と愛の自覚があるなら…相手を想っているならば手放すほうが賢明で、容易になります
それでも傍に、なんて
無様を晒すようなものだ。
恥をかなぐり捨ててまで気持ちを貫くには…差し出した自己の傷に対して、得るものが少なすぎますもの
「お前も 望んでくれないか 血塗れで共に生きることを」
見詰め返されもう一度 乞われて 私は
自分が差し出されたものに見合うなどとはやはり思えませんが
でも だからこそ、それすらも奪うことはもう できませんでした
「……」
少し、腕を伸ばして
稔さんの頬を両手で引き寄せて、そっと額に口付けた。…ペットのお返事です
せめてこの先 もしも 貴方の罪が私よりうんと重く大きくて、不幸になることを選ばざるを得なくなったとしても
どんなにか私の想像を超えた残酷な悪に手を染めていても 凄惨な過去を送っていても、共に堕ちて苦しむ覚悟をいたしましょう。
貴方が救った命をもってこの時ここで善なる貴方の存在を私がずっと証明します
それが何の役に立つわけでもないけれど
0 notes
Text
小説ノート(2023/12/09)
火種は燻った。四十過ぎぐらいの白髪の混じった男、おそらくサラリーマンであろう男は、目の前に腰掛ける初老の男の足と足の間に、厚かましくもその足を置き、この初老男を愚弄した。詰め込み過ぎの満員電車がそうさせたのである。初老男、おそらく自身も酔っているだろうこの男は、アルコールによるものか侮蔑された怒りによるものなのかはわからないが、とにかく顔を真赤に染め上げて、スマホをほじくる白髪男を睨みつけた。その目は白髪男の白髪を通り過ぎて、車内の広告を見ているようでもあった。
健人は全身に血の通うのを感じた。火種は着実に育っている。誰も火消しをしてくれるな、この神聖にして滑稽な、滑稽にして邪悪な炎を無為にも馴致してくれるな、と健人は思った。密集して固体に形態変化しようとしている乗客たちは、いわば個体としての意思を失った一細胞である。この車内で唯一「個」であることを保とうとしているのはこの二人だけである。健人はそれを見ていた。あたかもそこに自分の肉体がないかのように見ていた。
駅で電車が停まる。初老男は降車しようとする。だがこの厚かましい四十代はいささかの敬意もいささかの世間体も眼中になく、スマホのスクリーンを依然もてあそびながら、初老の降りるのを妨害した。顔を緋色にした初老は白髪男をのけるようにして立ち上がり、言った。
「おい、どけよ」
火は点った。火は点ったのである。人間が人間性を失ったこの非人称の都で!健人は安堵した。一人取り残された密林にて、手の皮を擦りむきながら、やっとこさ焚き火を確保することのできた時のように、安堵した。『もっとやれ、僕を失望させてくれるな』と健人は思った。わざと降りなかったのか、邪魔の存在のせいで降りられなかったのか判別はつかないが、初老男は白髪男の腹側に背負ったリュックを支点にして、彼に寄りかかった。初老男は眼を飛ばす。白髪男はめんどくさそうにめんどくさそうな顔を創作し、やはりめんどくさそうに「なんすか」と言った。
「なんすかじゃあねえだろう」
「いや、普通に横から通ってけばよかったじゃないすか」
「横から通ってけばじゃあねえだろ、お前」
健人は彼らが一線を越えるのを待ちに待っていた。あとは決断だけが必要だった。彼らにはその決断が求められていた。いまここで人間的であることのできるのは、少なくとも人間的であろうと努力することのできるのは、彼らをおいてほかにない。他の有象無象はあたかも人間であるかのように振る舞う自動機械でしかない。自由と意思、この形而上学的な概念はこの白髪と初老において具体的すぎるほどの具体性をもって表象されている!
健人はもう一度彼らを覗き見た。なぜか初老男は微笑んでいる。『なぜだ!』と健人は憤怒した。『まさかこいつはこの期に及んでくだらぬグルーミングでこの場を丸く収めようとしているのだろうか?これだけ火種を膨らませておいて、「まあまあ、俺も悪かったぜ」などと抜かすのではないだろうな?男が!男がそんなことをしていいはずがない』。健人は初老男の微笑の意図が解せず、歯ぎしりした。
だが、やはり火は消えてなどいなかった!次の駅に再び電車が停車すると、初老男は「ちょっと降りて話しようや」と言った。白髪男は場末の娼婦を見る目でこの男を見、彼に向かってスマホのカメラをかざした。一部始終を録画しようとしている。初老男は一段と顔面を朱で染め上げた。瞬間、初老は白髪のスマホを掴み、開いたドアの方に向かって白髪男をスマホごと投げた。白髪男はよろけてホームに転がり、すかさず初老はその後を追った。火はついに咲き誇った。優雅に咲き誇った。『それでこそ男だ』、健人は哄笑した。数多の自動機械たちは、まるであらかじめプログラムされているかのように、この「事件」を氷の視線で貫いた。健人は下腹部に全身の血が結集するのを感じた。『この男たちは僕を失望させなかった!男子、男子万歳!』。健人は勃起した。ホームには「暴力はやめてください!」という四十代の悲痛かつ空虚な、だがギリシア彫刻のように清澄な叫びが響いた。
健人は同時に電車を降り、改札に向けてエスカレーターを登った。彼らの雄叫び、文字通りの雄叫びが、やはりホームにこだましていた。意思を持たない物理現象たちは、もっぱら物理現象のように彼らの「ケンカ」を嘲笑し��いた。『「ケンカ」!』、健人は思った。『彼らがしているのはケンカなどではない。立派な戦争だ』。健人は改札を抜け、すぐさまコンビニに駆け寄り、缶ビールを買った。
「英雄たちに乾杯!」
健人は右手を高く掲げ、この界隈で唯一人間的であった人間たちを祝福した。
1 note
·
View note
Text
詩集『わたし専科』

詩集『わたし専科』目次
1.「忘れて(Prologue)」
2.「碧空が憎い」
3.「100回目のサヨナラ」
4.「永訣のキス」
5.「死にたくなった夜はわたしが抱きしめるから」
6.「片道切符のジャーニーマン」
7.「冷たい微笑」
8.「ふたりと煙草」
9.「いとしのキャフェ」
10.「サヨナラ世界」
11.「ねえ、わたしを見て?」
12.「人生でいちばん倖せな日(Encore)」
1.「忘れて(Prologue)」
この蒼き日に
紅く染まらないまま
消えていけることを倖せに感じる
思えば
取るに足らない人生だった
誰とでも代替できる
誰にだって当てはめられる
私の人生はそんなもの
好かれるよりも
嫌われるよりも
空気であることが最も悲しい
それを理解してくれたのは
もうこの世を去った貴女だけだった
貴女がいなくなって
私の存在を肯定する人が消滅し
何も出来なくなった
意志薄弱な私を
愛してくれてありがとう
そして
ごめんなさい
私のものはどう始末してくれたっていい
いっそのこと
存在自体を忘れてほしい
私がいない方が倖せになれるから
所詮私は諍いを生むだけのバグに過ぎないのだから
生まれてきたこと
生きていたこと
私自体を記憶から抹消してほしい
さよなら
貴女に逢いにいってきます
2.碧空が憎い
こんなにも空が晴れ渡っているのに
わたしはベッドに横たわり
明日も明後日もないのに
生きようとしなきゃいけないんだろう
心がどんどん壊れてく
音も映像もないけれど
身体が崩れてく気がして
何かを始めようと思い立った日は
わたしの記念日
碧空を憎ましく思った日
川で水切りをして遊ぶ子どもを見て
かつてはわたしもあんな日があったと
目を細めて思い出す
何度も断られているうちに
どうでも良くなっていく
誰にも必要とされない悔しさは
誰もわからなくていい
わたしが壊れた日
碧空を憎ましく思った日
旅をしたいなら
旅をすればいい
わたしにはそんな勇気もなく
小舟を河に浮かべ
微笑んでいる
社会が移ろう様を見て
生きる自信を失う
この古ぼけた幻には
明るい未来はない
わたし���記念日
碧空を憎ましく思った日
わたしの記念日
碧空に這いつくばろうと決めた日
3.100回目のサヨナラ
何をするにしたって
不器用すぎて
周りに迷惑をかけてきた
いつしか季節は流れ
大人になったけど
わたしは今も生きてるだけ
やりたいことはない
風に流されたまま
そんな声を夜空にぶつけても
誰も答えはしない
生まれてきて、ごめん。
何もできなくて、ごめん。
やさしくなれなくて、ごめん。
何もできなくて、ごめん。
自分さえも信じられず
あなたを傷つけ
愛すらも手放しそうだ
恋も夢も失い
大人になったけど
誰のためにこれから生きるのか
やりたいことはない
時に身を任せる
そんなわたしの声など
誰も聞きはしない
愛せなくて、ごめん。
何もできなくて、ごめん。
夢中になれなくて、ごめん。
何も出来なくて、ごめん。
死にたくても死にきれない
生きたくても生ききれない
中途半端なわたしに
誰かトドメを刺してほしい
生まれてきて、ごめん。
何もできなくて、ごめん。
やさしくなれなくて、ごめん。
何もできなくて、ごめん。
生きていて、ごめん。
ネガティヴで、ごめん。
強くなれなくて、ごめん。
夢叶えられなくて、ごめん。
蒼い空に問いかける
何故生きるのか
そして……
100回目のサヨナラ
4.永訣のキス
貴方が嫌いになったわけじゃない
むしろ好きなんだ
それでも別れを決めたのは
これ以上迷惑をかけたくないから
いつも切り出すのは私
付き合った時も別れる時も
それでも貴方は微笑みを浮かべて
私の答えを受け入れてくれた
貴方が愛しすぎるほどに好きでした
最後に身体を重ね合う
二人の心は震えていました
貴女と何かあったわけじゃない
むしろ平穏だった
突然別れを告げられて
僕は部屋に静かに佇んでいた
そして最後の夜が終わり
荷物を纏めて貴女は出ていく
突然のわりに心が落ち着きすぎて
僕は不思議な胸騒ぎを感じた
貴女が愛しすぎるほどに好きでした
最後に目を合わせた時
二人の心は濁っていました
大阪メトロにスーツケースを抱えて
ひとりの女が涙を隠しながら
佇んでいる光景は
側から見ると滑稽だっただろう
それでも私は消えるしかなかった
貴方を想って
立ち去ることしか頭になかった
ふたり分の歯ブラシに
ふたり分の食器
これから始まる暮らしを夢見て
揃えたモノたちを段ボールに片付けていく
最初は受け入れようとした運命も
時が経つほどに悲しみに染まり始めた
貴女を想って
受け入れることしかできなかった
あんなに愛し合った仲なのに
最後は呆気なく
別れ際に重ねた唇は
涙で微かに濡れていた
永訣を告げるキス
余韻が褪せないまま
携帯電話からの通知音
貴女からのさよならが聞こえる
愛しすぎるほどに好きだった人
一言でも言ってくれたら良かったのに
そんなに僕は頼りなかったですか?
5.死にたくなった夜は私が抱きしめるから
もう帰らないと決めた日
僕はフェンスを飛び越えた
遮蔽物のない摩天楼はあまりにも美しく
過去の僕がいかに濁っていたかを知る
この世界にやっとサヨナラが言えるんだ
不思議な高揚感が胸に宿る
叶えたかった夢も頑張りたかった未来も
今の僕にはどうだっていい
来世はほんの少しでも幸せになれと
後手で誰かにピースした
ふっと息を深く吸う
さあ、もう後悔はないぞ。
あなたの姿を見た時
これは「止めなきゃいけない」と感じた
あの儚さは今日という日を予言していたのか
屋上のドアを抉じ開けた
どうして何も言ってくれなかったんだ
怒りと哀しみが心を支配する
あんなに格好良くて優しかった人が
なぜ今自らの命を絶たなければならないのか
私は全力であなたを抱きしめた
嫌われたっていいの
まだ生きてほしい
たとえ、私のわがままだとしても。
その気配は君しかいない
君のぬくもりを感じた瞬間に悟った
僕は死ぬ勇気すらないのか
もはや摩天楼に身を投げようと思えなくなった
用意周到な計画のはずだったのに
過去の記憶が嵐のように脳裏に浮かぶ
いつだって僕は自分自身で決めてきたのに
こんな時に限って君に邪魔されなければいけないのか
それでも涙が止まらないのは何故だろう
まだ未練が残っているなんて信じたくはないんだ
強い力で抱きしめている君の腕を離す
はやく、僕を自由にさせてくれ。
あなたの腕が私の身体を離れていく
諦めという名の現世への未練を断ち切るように
私は生きる理由にすらなれなかったんだね
大地を離れた恋人の背中を追いかける
好きと伝えなかったのがいけなかったのかな
いまの私は後悔への処方箋を持ち合わせていない
いつかのあなたがこう言っていたことを思い出したんだ
「嫌われるよりも忘れられる方が怖い」って
私なんかが生まれるんじゃなかった
恋人すらも大切にできない人に生きる資格なんかないよ
遥か地上で鮮血に染まったアスファルト
あなたが死にたい夜は、私がどこへ行っても抱きしめるから。
6.片道切符のジャーニーマン
僕は旅に出ると決めた
もうこの家には戻らない
すべてを整理して旅を始めた
見慣れた街ともおさらばだ
しみったれた役人や腐った上司とも会わなくていい
こんなに楽な気持ちは久々である
普通電車に乗り込んだ
後先を考えずに行く旅は心地よく
周囲の景色が色づいて見えた
好きなひとに裏切られ
大切なひとは逃げていく
僕には何も残されていない
だから旅に出るんだ
風の調べに乗せて
明日を捜すための旅へ……
君を一生愛すると決めた
あの夜が未だに忘れられない
でも君はもうここにいない
親友だと思ってた奴に恋人を盗まれた
太陽すら投げ打ってでも守り抜くつもりだったのに
君は奴に容易く心を売り渡してしまった
次の分岐はサイコロで決めてしまおう
どこへ行ったって結末は同じ
僕に明るい未来などない
今日輝く太陽が君なら
昨日の月が僕だ
もう死んだも同然なのさ
だから旅に出るんだ
風の調べに乗せて
自由になるための旅へ……
好きに生きたかったよ
やりたいことをやりたかったよ
僕は僕を嫌いになり
君は君を好きになる
サヨナラを告げる前に
君を投げ捨ててしまえる勇気があったなら
好きなひとに裏切られ
大切なひとは逃げていく
僕には何も残されていない
だから旅に出るんだ
風の調べに乗せて
明日を捜すための旅へ……
死場所を捜すための旅は
生まれた頃から始まってた
優しさに塗り固められた嘘が
僕を静かに殺してく
掠れていく声に気も留めず
今日を決めつけて死んでいこう
7.冷たい微笑
心の中のマグマ
心に絡むドグマ
殺しながら
泣きじゃくる
ひとりが好きなのに
人肌が恋しくて
ふいに連絡したくなったのは
私から別れた元彼
電話に表示された名前
ボタンだけは押せず
真っ暗な部屋の真ん中で
静かに嗚咽する
SNSを開けば
私よりも悲惨な人がいる
そんな人を見るたびに
心が少し楽になった
そして嘲笑う
安酒を飲みながら
この哀しさは誰にもわからぬだろう
わかってほしいとも思わない
生きてるだけの私
死んでくだけの私
真っ赤なドレスは埃を被り
憂鬱に溺れる
病院には行けない
誰にも相談できない
頼れる人もいない
仕事もできない
何のために生きるのか
もはやわからない
朝日が登り
月が満ちて
微睡むうちに夜明けは来る
まだ立てるはずなのに
心が追いつかない
身体に巻きつく大蛇の幻想
眠ることさえも取り憑かれて
満足にできない
貴方にサヨナラさえ言えたなら
もう未練もなく逝けるのに
後悔に囚われたまま
動かなくなった時計のように固まる
誰のせいでもなく
私のせい
すべては私が決めたこと
いつか夢を見た残骸
何も残らない
誰かの声が聞こえるまで漂う
今日に怯えながら
この星に身を委ねて
8.ふたりと煙草
あんなに吸わないと決めていたのに
ゴロワーズを燻らせると
あの日に戻れる気がしてさ
つい止められなかったの
彼女が呟く
僕らには未来などなかった
少しずつ暖めてきたはずの関係
彼女が隣に連れていた男を見た時
すべてが壊れていく音がした
僕は“じゃない方”で
大学を卒業して
落ち着いた恋愛ができると信じていた
だけど……
そこにあったのは残酷な現実で
まさか彼女が浮気をしていたなんて
必死に否定すればするほど
僕の気持ちは離れていく
そんなことすらもわからずに訴える彼女
恋人とすら呼びたくなくて
あの夜を境に締め出してしまった
一年でいちばん雨が降った夜
僕は不安感を胸に眠っていた
最初は訴えるような叫び声が聞こえたけれど
次第に聞こえなくなったことに安堵した
彼女はどこかへ消えたんだと信じたかった
翌朝にゴミを捨てに行こうとした時
彼女は泥だらけで眠っていた
僕は他人のフリをしようとした
でも最後の最後でボロボロになった姿が哀しくて
つい家に上げてしまったんだ
あれから一年の月日が流れた
彼女は今も何も語らないまま
ベッドで一言を唱え続けている
あの日がすべてを変えてしまったんだと
後悔しても遅過ぎて
僕らには未来などなかった
少しずつ暖めてきたはずの関係
彼女が隣に連れていた男を見た時
すべてが壊れていく音がした
僕は“じゃない方”で
必死に否定すればするほど
僕の気持ちは離れていく
そんなことすらもわからずに訴える彼女
恋人とすら呼びたくなくて
あの夜を境に締め出してしまった
それでも彼女を愛していたんだ
あんな目に遭うべきじゃなかったんだ
夜の静寂に眠る彼女を見る度に
募り続ける罪悪感の波を
いつまでも背負い続けていく
抜け殻のようになった恋人
壊れてしまった関係
どこにも行き場を失った人生
カップラーメンとゴロワーズを肴に
僕たちは今日を生きている
裸足のままで
今日を死んでいこう
ふたりのままで
明日を死んでいこう
眠ったままで……
9.いとしのキャフェ
いとしのCaféで佇む男性は
かつて私の恋人でした
180cmを超える長身と細い体型は
Bespokeのスーツと靴が
あまりに馴染みすぎて
思わず恋に堕ちてしまったのです
遠くで見るとマカロンのよう
でも近づけばアイスキャンデー
そんな恋も今は良き思い出
いとしのCaféに通う女性は
かつて私の親友でした
結婚してから会わなくなったけれど
CHANELの鞄とワンピースが
あまりに似合いすぎて
今も勝手に憧れているのです
あなたは財閥育ちだという
本当は自由が欲しかったのよね
そんな日々も輝ける青春
いとしのCaféを営む紳士は
かつて私の父親でした
私には気付かないかもしれない
Comandanteのコーヒーミルを使う姿が
あまりに似合いすぎて
やっと幸せになれたのだと安堵しました
言葉を交わすわけでもないのに
繋がりあった気がする瞬間
そんな日々が穏やかな愛
わたしが生きる場所
金曜日午後三時
いつもの席で珈琲を飲む
10.ねえ、わたしを見て?
ねえ、わたしの目を見て?
お願いだから
最後くらい
わたしをちゃんと見てよ
出逢った頃からそう
心ここに在らずで
何処かをぼんやりと見つめてる
そんな貴方に惹かれてしまった
最初の夜から
最後の朝まで
聞いても言ってくれなかった
いつか友達から聞いた
忘れられない人がいること
恋人にす���話せないの?
ねえ、わたしの目を見て?
あなたに聞きたいの
本当に好きだったのか
わたしが恋人で良かったのか
もういなくなるよ?
二度と逢えないかもしれないよ?
それでも言わないの?
ドアを開けても彼は無言のまま
サヨナラすらも言わない
そっと彼の連絡先を削除した
ねえ、わたしの目を見て?
最後まで見てくれなかったよね
うつろな瞳で見つめるだけ
そんなに忘れられない人って誰なの
ねえ、わたしは悲しいよ?
碧空が皮肉だ
最期まで愛されなかった
何も本音で喋ってくれなかった
それなのに碧空は綺麗で
時々垣間見る本音を拾い集めたら
誰にも見えない流れ星のように美しい
そんな貴方に惹かれてしまった
いつかまた逢えるなら
ふたりで飲みに行こうよ
その時は本音で……
ねえ、一度くらいは目を見て?
11.サヨナラ世界
隣で眠る貴方を傍目に
麻縄を首に巻く
いつか来ると信じた日が
今日であることに慄き
そっと微笑む
素晴らしい日々だった
あなたと出逢って
愛おしい存在だった
あなたと暮らして
貴方にとって私は
どんな存在でしたか?
これから生まれ変わると伝えたら
きっと優しい言葉をかけてくれるし
抱きしめてくれるでしょう
でも私には不要です
私は幸せになっちゃいけないんです
幸せと感じちゃいけないんです
最高の日に逝かなきゃいけないんです
それが宿命だと信じて
今の幸せを閉じ込めると決めた日
すべてが完璧だと思っていたけれども
貴方の直感だけが誤算だった
そっと解かれる麻縄
肢体が吊り下げられていく
巻きつくのは全身に縄
身体にじっくりと染み込む感触
あの世へ歩いていけたらいいのに
何度も身体に焼きつく鞭の音
これこそが私の望んでいた世界なのだ
生きるとは切なさ
死ぬとは喜び
一度はそう信じた私にとって
麻縄由来の傷は勲章のようなもの
今日も私は舞台に立つ
12.人生でいちばん倖せな日(Encore)
今日は人生最高に倖せな日だ
明日のことをもう考えなくていい
すべて終わったのだから
かつて白鳥が空を飛んだ
人も空を飛ぶ夢を見た
もう当たり前になったけれども
最初は偉業として讃えられた
いつだって最初に孵化させた者が勝者で
二番目は歴史の裏紙に記された敗者に過ぎない
家族が困らないくらいの金は残した
妻も子供も健やかに生きられる
私は人生の目的を成し遂げた
もう朽ちるしかない
大人になること
老人に生まれ変わること
私はそれを受け入れたくはない
だから自らの手で終止符を打つと決めた
自分勝手と罵りたいなら罵ればいい
蔑みたければ蔑めばいい
もう私が知ることはないし
そんなことを言われる謂れもない
新しい世界には響きすらしないだろう
倖せとは
喜びとは
生きるとは
死ぬとは
考えることが仕事だった私も
今日くらいは考えることをやめようと思う
遺された君たちも
どうか考え過ぎないでほしい
明日が来ないことへの歓喜を
そっと噛み締めてから溶けゆく小石(私という存在)
詩集『わたし専科』クレジット
プロデューサー / 作:坂岡 優
コ・プロデューサー:Sakura Ogawa
原案:Sakura Ogawa(No.2,3,4,5,7,11)
共同執筆:星雲凛(No.1.8.12)
デザイン・編集:坂岡 優
制作スタジオ:Yuu Sakaoka Studio
Very very very thanks to my friend, my family, and all my fan!!
2023.8.31
坂岡 優
0 notes
Text
『御免なさい、もう辞めて。』 そう幾度も繰り返される言葉に、苛立ちは募るばかり。そもそも、何故俺はこんなにもイライラしてるかと考えたら、君が悪いんだって気が付いた。日が変わり時計の針が3と12を指した深夜、ドアの開く音。『ただいまー』何て少し回ってない呂律で楽しそうな君の声。有難うねーって声が聞こえたから、玄関に顔を出せば体を知らない男に支えられてフラフラな姿。誰だよ其奴とは言えないから、有難う御座いますって他人行儀に挨拶をしたら、君の腕を引っ張って中へと入れ込む。ドアを閉めると其の儘君の手を引っ張ってリビングへと投げた。床に投げ出された君が痛いって顔をした後に、俺の顔を見て段々と表情が暗くなる。『ひかる?御免、怒ってる?』 「別に、怒っては無いかな。たださ、御前自分の言葉覚えてんの?」 明日、友達と飲みに行くって昨日伝えて来たから、行くなって止めたけど『日が変わる前に帰るし、飲み過ぎない。同性しか居ないから、ダメ?』って、自ら条件を提示したのに全てを破るし、何なら男に抱えられて帰って来るってと、頭を抱える。全てを理解した途端に、行き場の無い思いは怒りに変わって行く。床に座り込む君に馬乗りになれば頬を掴んだ。「なぁ、何で嘘付いたの?約束破ったの?納得行く説明してくれんだよな?」サッと空気が冷えた様な気がして、君は頬を掴まれ言葉を出せずに居る。「なぁ、御前さぁ俺のって自覚あんの?」 パシっと乾いた音がして、自分で君の頬を叩いた事に気が付いた。痛そうに少し反抗の目を向けるのが気に食わなくて、腹部に足を乗せて体重を掛けて行く。『ッ...!ゲホッ... ひかっ、御免なさ...』 苦しそうに言葉を吐き出すのも聞こえなくて、「あ?御前なんなのその目は。」 気に食わないと軽く呟くと、足を離して腹部に拳を埋める。鈍い音と共に咳き込む音。『..っ、いたっ、やだ、痛い!』 嫌だ嫌だと、身体を丸め必死に痛みから逃げようとするその姿は滑稽で愛らしくも感じた。「なぁ、そんなので逃げれると思うなよ?」 髪の毛を掴んで此方を向かせると、恐怖に怯えた目と視線がぶつかり合う。「は?何その顔。俺をこんな風にしたのは御前だろ?怒らせる様な事したのも御前、だからさ御仕置だと思って、喜んで受け止めろよ、な?」 そう言って軽く微笑み、小首を傾げては幾度も頬と腹部を殴り続ければ、嘔吐を繰り返していた君が反応を無くす。『...ッ、ゲホッゲホッ...。ひか...ごめ』 そう言って、力を無くす君。何時の間にか、顔は腫れ上がり紫色や赤色に染まって、血と吐瀉物塗れの部屋。ボロボロな君の姿を見てふと我に返った何してんだ俺と。悪かった、って思いながら細い息の君を抱き寄せる。悪いなと思ったはずなのに、何でか凄く君が愛おしい。ボロボロな君の姿がこんなにも可愛らしく思えるなんて、可笑しいと君は怯えるんだろうか。俺が思うに、苦しみや痛みは心に深く残る傷だ。だから君はこの先、俺の事をその傷に触れる度、誰彼に拳を振りかざされる度に思い出すのだろう。そんなことを思うと、優越感からか思わず笑みが零れた。そんな俺を見て怯えた様に濁った瞳で見詰める君、視線がぶつかれば頬に優しく触れて小さく呟いた。「なぁ、御前の事愛してるんだよ。だから、この先もずっと傍に居て、俺の想いを全部受け止めてくれるよな?」
0 notes
Text
「シルエット」とは、「輪郭の中が塗りつぶされた単色の切り絵」のことを言い、そこから「輪郭」や「ものの形」、「影絵」などを言い表す言葉としても使われる。この「シルエット」という語は、もともとは人名だったらしい。
フランス王ルイ15世の治世下で財務大臣を務めたエティエンヌ ド シルエットは、七年戦争が長引いたことでフランスが財政難に陥った際、特に富裕層に対して厳しい倹約を要求しなければならなかった。これにより、「安上がりで済ますこと」が人々の間で「シルエット」と言われるようになる。
切絵によるシンプルな肖像は人物の特徴を記録する最も安上がりな方法であり、エティエンヌ ド シルエットもこれを好んだため、このような肖像画のことも「シルエット」と呼ばれた。この「シルエット」と呼ばれる「切り絵による肖像画」は、その後、18世紀後半から19世紀前半に、ヨーロッパだけではなくアメリカでも流行し、「シルエット」の語が定着した。
18世紀末より、シルエットは肖像だけでなく本の挿絵などにも用いられるようになる。複雑なイラストレーションよりも安価で容易な方法でもあり、また、その独特な雰囲気を好む作家も多く、演出技法としても用いられるようになっていく。
童話作家のアンデルセンもシルエットによる表現を好み、切り絵制作を得意とした。自作の切り絵などを貼った絵本を作り、友人への贈り物にした。
シルエットによる表現は、想像力を掻き立てることで、美しさや、あるいは滑稽さなどを際立たせる演出にも用いられるものの、やはり、暗く、怖い。
アンデルセンの、特に初期の作品では、主人公が死ぬ結末を迎えるものが多い。これは、若き日のアンデルセンが、死ぬ以外に幸せになる術を持たない貧困層への嘆きと、それに対して無関心を装い続ける社会への嘆きを、表現を通して訴えようとしたものだと解説されている。
1804年にナポレオン ボナパルトがフランス第一帝政の皇帝に即位(在位 1804年-1814年、1815年)し、イギリスやロシアと敵対する。フランスと同盟を結んでいたデンマークも、イギリスから砲撃や封鎖をされ、不況に陥っていた。
アンデルセンはそのデンマークに1805年に生まれる。貧しい靴職人だった父親は1812年から2年間従軍したが、1813年に国が財政破綻し、軍から支払われるはずの給金も得られなかった。
1835年に最初の小説『即興詩人』と『童話集』を発表したアンデルセンの、初期にあたる1830年代から40年代においては、作品にも現れる貧困層の窮状は写実的であり、多くの人が抱える問題意識でもあった。
七年戦争によって帝国の礎が築かれ、絶頂期となるヴィクトリア朝(在位 1837年-1901年)に入る頃の大英帝国でも、同様の問題意識はあり、アンデルセン(1805-1875)と同時代のイギリスの作家であるチャールズ ディケンズ(1812-1870)の作品にも、貧困層の視点からの社会風刺という形で描かれている。
問題意識としては多くの人が共有しているように見えながら、そこから抜け出す術を見出せないやるせなさは、アンデルセンの作品では、無関心を装う社会への嘆きとして滲んだ。
アンデルセン作品のこうした傾向は晩年になっていくにつれて緩められ、死以外にも幸せになる術があることを作中に書き出すようになっていく。
アンデルセンは1859年に書いた「子供のおしゃべり」という作品で、自身の名前の「アンデルセン(デンマーク語の発音ではアナスン。英語ではアンダースンまたはアンダーソン)」にもある最後の「セン」という言葉は「だれだれの息子」という意味で、それがついている名前はきちんとした姓ももらえなかった貧しい家の出ということを示しているという謂われに触れている。子供たちがそのことを話しているのを、一人の貧しい男の子がドアの隙間から覗いて聞いていて、自分の名も最後がセンで終わるので悲しくなってしまったが、でもこうして生まれてきたんだ、りっぱに生まれてきたんだ、と男の子は考え、そして大人になってりっぱになり、話をしていた子供たちもそれぞれ幸福になった、と書いている。作品は、あの時考えたり言ったりしたことは、あれはただの子供のおしゃべりだったのです、という終わり方をする。最後がセンで終わる名前の男の子はトルバルセンという名前で、アンデルセンの友人である世界的に有名な彫刻家のトルバルセン(1770-1844)をモデルにしている。
1830年代にエッセイや小説で人気を獲得し、1837年から1839年に連載した長編小説『オリバー ツイスト』で人気を不動のものにしたチャールズ ディケンズは、貧しかった幼少時の経験から、労働者階級の視点に立って、日常生活と多様な登場人物を具体的に生き生きと描写した。エンターテイナーであることを常に心がけ、楽天的で理想主義的なハッピーエンドで締めくくるスタイルを貫いた。そのため、後期や没後の文壇からの批評としては、偶然に頼ったご都合主義的な物語展開と強引なハッピーエンドが批判の的にもなったが、現在に至るまで大衆からの人気が衰えたことはない。
ディケンズは写実主義に分類される。アンデルセンの初期の作品に滲んだ嘆きも写実性であり、1840年代のヨーロッパを覆ったリアリズムだった。そこからなぜか1850年代に大衆文化が花開く。
「諸国民の春」 と総称される1848年から1849年にかけてヨーロッパ各地で起こった革命により、大国の被支配地域を中心にナショナリズムが先鋭化する。その後、英露対立やフランス第二帝政の成立(1852年にルイ=ナポレオンがナポレオン3世として皇帝に即位)などを背景として、クリミア戦争(1853年-1856年)が起こる。これはウィーン体制の崩壊を意味していた。
ウィーン体制は、ウィーン会議(1814年-1815年)以後のヨーロッパの国際秩序であり、フランス革命とナポレオン戦争で荒廃したヨーロッパを、それ以前の状態に復活させることにより大国の勢力均衡を図っていた。
ウィーン体制は、従来の君主制に立脚する列強を中心に、自由主義と国民主義運動を抑圧していたが、 産業革命による市民生活の発展や大国間の利害関係の複雑化などにより、1830年代から枠組みが揺らぎ始めていた。
「諸国民の春」により自由主義と国民主義を抑圧する機能が維持できなくなり、そして、列強間の平和維持の役割も果たせなくなったことが、クリミア戦争によって露わになった。
以降列強は、各国の国益の赴くままに帝国主義に走ることになる。イギリスは、その国力を持ってして「栄光ある孤立」を選択、大陸の列強は、欧州域内の勢力均衡を図るため交互に同盟を結び、ヨーロッパは産業革命と植民地主義を掲げた新たな時代へと突入した。
イギリスの歴史区分では、1840年代までを産業革命の時代とし、1850年代からを資本の時代としている。「大衆文化」の成立も1850年代とされ、場合によってはそれ以前の大衆の文化は「民衆文化」や「世俗文化」として区別される。「大衆文化」成立の条件として、大衆の自主的な選択が反映されることが挙げられる。産業革命によって市場の環境が整ったことで、大衆文化が成立したと説明される。
労働と消費が市場を介して社会に反映されるようになっていき、アンデルセンの初期の作品に滲んでいた嘆きから、抜け出す術が見え始める。
一方でディケンズは、1850年代から社会への批判を強めていく。時事的課題に対するジャーナリスティックな関心を強め、クリミア戦争に関する攻府の無策ぶりや、制度の腐敗、慈善活動という名の偽善、金儲け主義と立身出世主義に嵌る産業界などを批判した。
アンデルセンもディケンズも、そして彼らの作品の読者も、変わっていく時代の中で、変わらない美徳を見出そうとしていた。
どんなに機械的に反復されているものでも、外的な賞罰なしには存続しえない行為の中には、美徳がない。
1756年から1763年まで行われた七年戦争は、 オスマン帝国を除く当時の欧州列強が全て参戦しており、戦闘は ヨーロッパだけでなく、北アメリカ、カリブ海、アフリカ、インドで行われた。そのため、事実上史上初の世界大戦とも呼ばれる。世界中に影響を及ぼし、ヨーロッパにおける政治再編を引き起こしただけでなく、アメリカ合衆国の独立とフランス革命の遠因となった。
イギリスは、ヨーロッパでは同盟国プロイセンに対する資金援助を中心にして深入りせず、海上や植民地での対仏戦争に戦力を集中させた。
植民地での戦闘の勝利により、名誉革命以来長く続いていたフランスとの植民地争奪戦に終止符が打たれ、イギリスは北アメリカ大陸、インド、西インド諸島を掌握し、これらが後に世界最大の植民地帝国となる大英帝国の土台となった。
七年戦争を実質的に指導し、イギリスを勝利に導き大英帝国の基礎を築いたと称される南部担当国務大臣のウィリアム ピットは、「愛国者」「偉大な平民」と呼ばれ、自身もそれを好んだ。
「王 (宮廷)」への「忠誠心」を重要な美徳としていた時代から、「愛国心」と「平民性」を重要な美徳とする時代へと移る。大英帝国にとっては皮肉なことに、アメリカが独立の精神として重要だと捉えたのが「パトリオティズム」と「コモンセンス」だった。産業革命が進み、「シヴィライゼーション (文明)」と「シビリアン (市民)」を重要視するようになった頃、アメリカでは「シビルウォー (南北戦争 1861年から1865年)」が起こっていた。ヨーロッパではパリなどを中心に「シティ (都市)」と「シチズンシップ (市民性。市民権)」が重視され、現在のフランスの国歌でもある『ラ マルセイエーズ』 の中でも「シトワイヤン (市民)」という言葉がリフレインする。
2023年4月 シバリング コンツール エッセー
1 note
·
View note
Text
「うれしい」
あなたにもわたしにもそれぞれ星座があるのが
起きてすぐ夢を鮮明に覚えているのがわかるのが
子どもが魔法のような私の手の動きで横断歩道を渡るのが
にがいチョコレートを食べてから飲む牛乳がとってもおいしいのが
土地家屋調査士の事務所のドアを開けた途端に山盛りになっている書類が目に飛び込んできて
春の山の毛並みを目で撫でるのが気持ち良いのが
盆提灯がミラーボールみたいに回っているのが
大きすぎる犬とすれ違うと
病的なまでに気取り屋であればあるほど
風に吹かれて船が
趣味嗜好がガラリと変わってしまう瞬間が
想像もできないほど素晴らしいことがこれから待っていることが
満月であれ新月であれ
辞めた日に事務員さんが両手を振って送り出してくれて
薬を毎日一つ一つ開けていくのはクリスマスのアドベントカレンダーのようで
もうあの人のことなんかどうでも良くなっていて
工夫を凝らしているのが
イタリアン・ホラーを一晩に四本も観れて
ウォークラリー形式の健康診断が
朝はやはりエンヤが
おめかしした少年たちが
銀のパッケージの匂い付きのポケットティッシュくれたら
よく考えると色々なことが滑稽に思えてくるのが
退屈な時に舌でころがす飴玉程度の思い出が
パフェのチョコが君の手にたれて
水びたしのモスクも修道院も温室も頭の中でなら思い浮かべられるのが
息が上がると
十二月から一月になるのが
紺色のコーデュロイパンツの着心地が良くて
頭が悪くなるような音楽に毒されている自分が
ショッキングピンクのクラウンでシリアスなドライブに出かけられたら
タイヤ屋の幼稚園の運動会のような旗の飾りが
車がUターンする様を見るのが
ダイナー風の三角形のテーブルがお家にあったら
思い出し忘れてしまえるのが
1 note
·
View note
Text
定時間際に滑り込みで降ってきた急ぎとやらの仕事。ふとスマホを見ると只今の時刻、PM20:00。定時から既に2時間経過。常日頃から定時帰宅を遵守している俺にとってはかなりの大ダメージ。だからと言って頼まれた仕事を断れるかと言われれば答えはノーで。「あー、いいっすよ。俺やりますよ。」なんて二つ返事で引き受ける癖が未だに抜けずにいる。所詮は独り身人間の為、引き受けたところで特に困ることもないし、次の日に持ち越すくらいならその日のうちに片付けてしまいたい。そんなこんなで仕事も片付き、デスク周りを軽く整理し、ちらほら残っている同僚に「お先に失礼します、お疲れ様でした。」とお決まりの挨拶を残せば、オフィスビルのエレベーターに乗り込む。流石にこの時間のエレベーター内はスカスカで、俺含め乗っているのは4人。(残業お疲れ様です。)と心の中で同情する。夜飯どうすっかなー、なんて考えながらオフィスビルから外に出る。まさかの雨。最悪だ、残業後のこの仕打ち。急いで折り畳み傘を探すもそんな利便性のある物を携えている訳もなく。咄嗟に「あー...」なんて声を漏らしてしまう。『傘、ないんすか?駅まで入ってきます?』と急に声を掛けられる。声に振り返ればさっきのエレベーターに乗っていた中の1人。「あー、大丈夫っすよ。雨好きなんで。」そう告げれば足早に駅に向かう。信号に足止めを食らっていると不意に雨が止む。上を見上げればビニール傘が広げられていて。『ちょ、早いっすよ。』なんて少し息を切らせているさっきの奴。『せっかくなんで一緒に。』と続けられる。なんだコイツ、と思う反面わざわざ追いかけてきた優しさを無下になんて出来ず一緒に歩き出す。ポツリポツリと言葉を交わすうちにコイツが同じ社内の階違いの別部署である事、甘い物と酒が好きな事、今日がたまたま残業になった事を知る。駅までの道のり約10分。時折視線が合わさる度にその瞳に吸い込まれそうになった、憂いを帯びた瞳に映る物に興味を抱いてしまった。駅に着くや否や、その気持ちがバレてしまわぬよう、「入れてくれてありがとう。じゃ、また雨の日に。」なんて意味不明な言葉を投げかけ改札をくぐる。
それから一度もアイツに会わないまま今まで通りの日常が過ぎる。ふと外を見れば暗くなった空にぽつりぽつりと久々に降る雨が映る。頭の中に浮かぶのはあの日のアイツ。PCをシャットダウンし、また会えたりして。なんて思いながらビルの外へ向かう。案の定、自動ドア越しに見えるのはあの日のアイツの後ろ姿。自動ドアから出る俺を見つければ少し嬉しそうな表情を見せるから胸が高鳴ってしまい堪らず「頼むからそんな顔すんなよ。」と呟いた声はさっきより強まった雨音にかき消される。「..入ってく?駅まで。」そう声をかければ頷いて俺の傘に収まる。まだ2回しか会ってないコイツに気持ちが奪われそうになりながらいつもよりゆっくり歩みを進める。ただひたすらにコイツとの10分間を味わいたくて楽しそうに喋るコイツのコロコロと変わる表情を必死に瞳に焼き付けた。
最近よく雨が降る。残業の日は待ち合わせする訳でも無いのに不思議と鉢合いどちらかの傘で駅まで帰る事が多くなった。今日は寄りたいところがあり珍しく残業をせずビルを後にする。イヤフォンで音楽を流しながら目的地まで歩みを進める。ふと傘を上に傾ければ一つの傘に収まる男女を見つけた。あの雨の日の出来事を思い出して思わず目で追ってしまった。少し揺らいだ傘の隙間から見えたのはまさかのあの日のアイツ。と、可愛らしい女性。仲睦まじげに歩く姿を目にし胸がぎゅっと少し苦しくなる。ああ、きっとあの日は傘を忘れた俺を見兼ねて声を掛けてくれただけだと。今までの雨の日でさえも、「また雨の日に。」なんて言ったが為に気を遣わせてしまったとしか思えず。そりゃそうだ男同士で傘に収まるより可愛らしい女性と入る方が良いに決まってる。何を俺は自惚れていたんだなんて自己嫌悪に陥る。楽しかったはずの記憶が全部ポロポロと崩れていく。アイツの楽しそうに笑った顔でさえ無理してるようにすら思えてきて急いで頭からかき消す。用事なんてこなす気になれず自宅に目的地を変更。帰宅後すぐにシャワーを浴び強めの酒を流し込み何も考えないようにその日は眠りについた。
その日からまた暫く雨は降らずアイツに会うことも無ければ雨の日のイレギュラーな出来事の事も少しずつ消化し始めていた。見事に雨の日にしか会うことがなくもはや幻にすら思える。いつもなら嫌になるような仕事量でさえ今回ばかりはとても有難く朝から晩まで没頭して仕事をこなした。『目黒くん、カノジョに振られた?』なんて聞かれる事もしばしば、その度に、「それ、セクハラっすよ。」としれっと返すような日々だった。有難い事に『目黒くん呑み行こうよ。』と誘ってもらう事も多く、少しでもアイツの事を思い出す時間が減るならと出歩く事も増えた。俺はアイツに出会う前のただ"それなり"の日常をこなす。
今日もそのハズだった。オフィスの窓から見えるのは薄暗い空と雨。何となく嫌な予感がした、こういう時の勘というものは良く当たる物で警戒しながら外に向かう。案の定、自動ドア越しに見える明らかに誰かを待っている様子のアイツ。俺にはもう関係ないと別な出口から駅に向かう。また別の雨の日もそう。いつもの場所でアイツはずっと立ってる。それを見なかったように別な道を帰る。だが今日は失敗だった。アイツを見つけ別な出口に向かおうとした矢先に真正面の自動ドアから入ってきた上司にかなりの声量で名前を呼ばれた。うわ、まじかよ。と嫌な顔を出しそうになるのを堪え、笑顔で「お疲れ様です、お先します。」と返す。上司越しにアイツを見れば流石に気付いたようで目が合ってしまった。これはもう仕方ない、そのまま正面から出ればアイツとは目を合わさぬように目の前を通り過ぎる。傘なんてさす余裕すら無くいかに早くアイツの前を通り過ぎるかだけを考えた。ずぶ濡れになりながら足早に駅に向かう。よりによって信号に足止めを食らう。俺の思わず吐き出したため息と同時に腕を掴まれる。振り向きたくなる衝動を抑え気付かぬフリで中々変わらぬ信号とにらめっこ。腕を掴む強さが強まるのと同じくらいのタイミングで怒りの混じった涙声での『..ねえ、こっち見て。』に胸がぎゅうっと締め付けられ苦しくなる。ああ、なんで俺のが泣きそうになってんだっけ。恐る恐るアイツのほうに視線を向ける。悲惨なくらいに全身はびしょ濡れだし、なんなら泣いてはいないものの顔もぐちゃぐちゃ。どんな感情かなんて読めないくらい色んな感情が入り交じった顔をしていて思わず頬に手を添えてしまう。ハッと我に返り頬から手を離す。これまた苦しそうな顔をするからこっちまで苦しくなる。ただ目を合わせるだけの無言の時間。良い大人が土砂降りの中、傘もささずに見つめあってる状況は傍から見たらかなり滑稽だろう。さあ、どうしようか。この状況。いっぱいいっぱいの頭をフル回転させる。気付いたらコイツの手を取り駅に向かっていた。何も言わないで大人しくついてくるコイツととりあえずこの状況を打破しなくてはと焦る俺。大の大人が、大の大人の腕を引っ張って歩く姿なんぞこれまた滑稽で、しかも2人共ずぶ濡れな訳だから周囲はドン引きでしかなく。流石にこの状態で電車に乗るわけにもいかず駅のコンビニで急遽タオルを購入し応急処置。100歩くらい譲ればマシになった気がする2人。話そうにもこの格好で話すのも気が引け、キャパオーバーの頭で考えた結果自分の家に向かう事にした。もちろん、コイツの同意も得て。向かう間は想像通りこの世の終わりみたいな無言の時間。
なんとか家まで辿りつき、風邪引くのも引かれんのも困るので急いで風呂を炊く。俺自身が一旦冷静になる時間が欲しかったのもありコイツを風呂場に突っ込めば強制的にカラダを温めさせる。当の俺はコイツの服と俺の服を洗濯機にぶち込みグルグル回す。俺の服と一緒に回ってるコイツの服を眺めれば単純な俺は胸が高鳴るし、俺の家にコイツがいる状況に不謹慎にも色々な想像を膨らませてしまう訳で。一生懸命に邪念を振り払い、今のうちに出来そうなことに集中し手を動かす。クローゼットから余りの毛布を引っ張ってきてみたり、レンジで牛乳を温めてみたり。タオルを広げてバッグの中身を取り出して乾かして、頭の中を整理するために忙しなく動き回る。そんな事をしているうちに俺のスウェットを着て戻ってくる。「...俺もシャワー浴びてくるから待ってて。好きにしてて良いし、寒かったら毛布使って。あ、ホットミルクも飲んでて良いから。」伝えるだけ伝えて風呂場に駆け込む。熱めにしたシャワーを頭から浴びる、冷えたカラダがちょっとずつ温まっていく。ちょっとずつ気持ちも落ち着いてくる。湯船に浸かりながらアイツが俺を追いかけてきた意味と俺に見せた表情、それと俺の家までのこのこついてきた理由に思考を巡らせる。いくら考えても解せる訳がなかった。ここまで来てしまったら向き合う以外の選択肢などある訳もなく。観念すれば重い腰を持ち上げ風呂場から出る。着慣れたスウェットを身に纏えばアイツの居る部屋への扉を開く。明らかにソワソワしながら正座で待っている様子があまりにも可笑しくて吹き出してしまう。咄嗟に睨まれたので「ごめん。」と伝え向かい側に正座で座る。
風呂上がりの男2人が真顔でしかも正座で向かい合ってるこの状況。最初に口を開いたのはアイツだった。『....なんでずっと..俺の事避けてたんすか。』 ポツリポツリと俯きながら言葉を発する合間にのぞく表情が悲しそうで辛そうであまりにも苦しかった。「...それは..見ちゃったんだよ。御前が..、そのカノジョ?と歩いてんの。」 『..え、っと』 「..雨の日に一緒の傘、入ってたろ。御前に相手いんの知らずに俺だけ雨の日に一緒に帰んの楽しみにしてたなんて滑稽過ぎんだろ。」 『..ね、待って、』「避けたのは俺が早く御前の事忘れたかったから。それだけ。自惚れてた自分が嫌で仕方なかったから会いたくなかった。」 『...、』 「ごめんな、付き合わせて。早く気付いてやれ..、」 目では捉えきれないくらいまで近づいた顔。唐突な出来事に俺の思考は停止。え、今俺何されてる?どういう状況?あまりにも頭が回らなすぎてカラダごとフリーズする俺。次にコイツの顔の全てを把握する時にはかなり怒った表情と熱を帯びたような目で見詰められていた。『..ここまでしないと分かんない?つか話ちゃんと聞けよ。』「いや、..でも、え..?カノジョ、」 『違うから。あれ、妹。』 「..イモウト..?」 『そう、妹。傘忘れたからって呼び出されてカレシのところまで送らされただけ。』 パンク寸前の頭は理解するまでにかなりの時間を要する。『..だから自惚れなんかじゃない、付き合わされてた訳でもない。』 真っ直ぐに俺の目を見ながら俺に伝わるようにゆっくり伝えてくるコイツが嘘をついていないことは確かだった。だとしたら俺の勘違いであまりにも酷いくらいに傷付けてしまった。いつもの場所で待ってた姿、腕を掴んできた時の顔、コイツの苦しそうにする顔がフラッシュバックしてきて、これまた俺の胸を苦しいくらいに締め付ける。頭の中をグルグル回る。『..また一人で抱える。』 「..だって、めちゃくちゃ傷付けた御前のこと。格好悪すぎだろ、俺。勝手に勘違いして、」 俯く俺の頭をふわっと包み込まれる。『ね、貴方も苦しかった?』 「..うん、めちゃくちゃ苦しかった。雨降る度に御前のこと思い出すし、考えないようにしたけどダメだった。御前がずっと待ってんの分かってたけど期待したくなくて無視した..それも苦しかった。」 『じゃあ、おあいこじゃん。』 「でも俺御前と一緒にいる資格無いよ、俺こんなだし..」 『貴方のこれからの全部で俺の事幸せにしてよ。』 なんて声が降ってきて思わず顔を上げれば泣きそうになるのを堪える顔を見付ける。
どれくらい時間が流れただろうか。体感的にはかなり時間が経った気もするし案外そうでも無いような気もする。ふぅ、と深呼吸をすれば「傷付けた分も全部全部俺が拭えるように努力をするから、俺のこれからの全部貰ってほしい。雨の日じゃなくても一緒に居たい。」 ああ、やっと言えた。あまりにも返事が返ってこなくて途端に不安になる。恐る恐る目を合わせれば、キュッと細めてにこっと笑みを浮かべる表情にまた目を奪われてしまった。ああやっぱり好きだと思った。『俺もずっと一緒に居たいです、もう貴方が一人で抱え込まなくて良いように傍に居るから。』
あまりにも幸せで胸が苦しくて思い切りコイツを抱き締めたら愛しさが増す。安心したのかさっきまでの頼もしさの欠片も無いくらいに俺の胸の中で大号泣する背中を擦りながら抱え込ませてしまったのだと実感する。顔を上げさせゆっくりと唇を重ね合わせれば俺にきゅっとしがみつきながら応えてくれる。今日が終わる前にどうしても伝えておきたくて顔がぐちゃぐちゃなコイツを腕から解放し目を合わせる。
「俺を追いかけてきてくれてありがとう。好きだよ。」
-雨の日-
0 notes
Text
ラブランド
Welcome to love land - THE LOVE LAND!
『ようこそ愛の国、ラブランドへ!』
突然に現れたその言葉が眩しくて、目を閉じた。空にかかるシャンパンゴールドのネオンに心を慣らしながら、少し、この状況について考える。あたしは誰か。自明なのでパス。ここはどこか。愛の国ラブランド、景色は遊園地のようだ。今は真夜中、きらびやかな仕掛け時計が午前一時を回ったばかりだと知らせている。何が、どうして。ちっともわからないので唇を噛んだ。少なくともその痛みは信じられそうだった。
まだ眠たがる体を起こすと大好きなベッドを離れて、外の世界へ踏み出した。裸の足を優しくくすぐる芝生が心地よくて、確かめるみたいに何度も踏みしめてその温もりに気付く。ちょうど春と夏のまんなか、羽根の毛布にくるまって夜風を感じるくらいの暖かさ。かすかな風には甘いおかしの香りが混じって、新芽くらいの空腹を感じた。
なるほど愛の国、とあたしは一人で頷く。光も音も、空気や手触りさえも心地よく、ここはとても素敵な空間だった。そっと差し出されたハートの風船を受け取ると、マスコットらしいウサギを模したキャラクターがにこにこと(正直よくわからないけど笑っているのは確かだ)笑いかけるので、あたしは自然と笑い返して手のひらを振る。仲むつまじく並んで去っていく二人のマスコットと、渡された黄色い風船と、のんびり見比べているとアナウンスが響いた。
『迷子のお知らせを……よりお越しの一ノ瀬志希ちゃん、宮本フレデリカちゃん……メリーゴーランドまで……』
途切れ途切れの(ちょっと幼げな)声は、なぜか懐かしかった。知らないはずなのに、初めての気がしなかった。ぼんやりと星のない空へ向けていた視線を下ろすと正面にはいつの間にかメリーゴーランドがあって、もう、ベルが鳴っている。そこではフレちゃんが手を振っていて、「こっちだよ」と限りない喜びへあたしを誘っている。
脚が、本当に小さな子どもになったみたいに駆け出して、けれどあたしを待たずにベルは鳴り止む。もたもたと柵を乗り越えて、つまずいて、回り出す舞台へ飛び乗った。ハートの馬車のドアを開いて、フレちゃんは手を伸ばす。あたしは息を切らせながら手のひらをしっかりと掴むと、その柔らかさで、全部を思い出した。
ちょうど、一時間前だった。フレちゃんはしなやかな、よく手入れされたその指であたしをそこへ連れていくと、「お誕生日おめでとう」っておでこにキスをくれた。「大人になるまで待てなかったね」なんてとても幸せそうに笑って、あたしは頭の中の白い光のせいでその言葉も何度も触れる唇も全然わからなかったのに、かたく繋ぎ合った手のひらの柔らかさだけをちゃんと覚えてる。
鮮明に、白飛びした写真に咲いた青い花みたいに。
ほとんど反射で離そうとした手をフレちゃんが掴まえて、あたしの体はハートの馬車に乗り込んだ。だけど心は今もあのベッドに置き去りで、「しきちゃん」あの洪水のように押し寄せた愛のただ中と同じ声で呼ばれて、振り向けずにいる。もし見られてしまえば、たとえば急に走ったせいで息が上がっているし、きっと頬も赤い。目が合えば、あの暗闇の中で溶融した視線を見つけてしまう。なのにフレちゃんは「あたし、さみしいなあ」そんなふうに、いとも簡単にこの甘い恐れを実現させてしまう。
フレちゃんが覗き込んで、あたしたちの視線が交わる。その目が、唇が、あたしの首すじを撫でたお鼻が、あたしが唇でなぞると「くすぐったいよ」と震えた鎖骨が、おぼつかない手つきで一生懸命に脱がせた白いもこもこのパジャマが、すべすべのおなかや信じられないくらい柔らかな胸からした甘い香りが、敏感な腸骨のでっぱりや内腿の薄い皮膚の内側に透けていた血管、湿潤と熱であたしを捕らえて離さなかった愛の中心が、そして、あたしの全身、体だけじゃ足りず心までを愛し尽くしてくれたその指が、たった一時間前のこと全てが一瞬の視線によって目の前のフレちゃんと混じり合って、あたしは幸せの過剰摂取で死んでしまうと思った。
だけど、おそろしいことに、この幸せには続きがあった。
フレちゃんははじめ不思議そうにしていた。目の奥を覗いて、首を傾げて、一度だけまたたいた次の瞬間にはその瞳孔をいっぱいに開いてあたしのことを見た。見る間に頬が赤くなって、唇は小さく震えて、ついには乗り出していた体をシートに縮めてしまう。いつもと全然違う調子はずれの鼻歌が聞こえて、まだ膝が触れ合っていたことに気付くと静電気が走ったみたいに引き離す。
そうやって、あたしたちはこの小さな馬車の中で迷子になった。互いにそっぽを向いたまま外を眺めて、言葉もなく、手をつないだり抱きしめたりキスをしたり一時間前まで当たり前だったふたりは、ぐるぐる回る遊園地の明かりのどこにも見つからなかった。
あたしは一度だけ、気付かれないようそっと振り向いた。すると同じようにしていたフレちゃんと目が合って、はじき合うみたいに目を反らした。その瞬間、鮮やかなもも色の頬にちょっとだけ怯えの混じった上目づかいを見た時、今度こそあたしは死ぬんだと思った。だけどどうにか生きていたので、停止のベルを聞くと次第に流れを弱めていく景色を眺めながら途方に暮れた。
だから、二度目のアナウンスは救いの日に鳴る鐘のように聞こえた。
『迷子の……一ノ瀬……フレデリカちゃん……ミラーハウスまで……』
その声は、あまりに正しかった。だってあたしは、フレちゃんでさえきっと、この愛の国の歩き方を少しも知らない。大げさで、だけど切実なそのやり方を、あたしたちはまだ全然知らなかった。
ゆらゆらと、ハートの風船が揺れている。静かに、あたしたちの隙間をちょっともて余すみたいに。
*
メリーゴーランドを降りると、シナモンシュガーのチュロスをかじりながらミラーハウスへ向かった。ほんの短い時間だったけれど、ふたりで並んでいるのに手を繋がずにいるのはすごく不思議な思いがした。当たり前がそこにない、もしかして体の一部をなくしたような、そういう感覚。
「あたし、ミラーハウスってはじめて」笑っちゃいそうにたどたどしい鼻歌を途切れさせて、フレちゃんは言う。「しきちゃんは?」
「んー、たぶんあたしも」あたしは答えて、決して視線が重ならないように(なんだかばかみたいだ)横顔から気持ちを伺おうとした。「どうしよっか?」
そんなふうに迷いかけたあたしたちの前に、ウサギのマスコットが姿を見せる。後ろから覗き込むようにして、背中を押すと開かれた入り口へ連れていく。「わお!」とフレちゃんが笑うので、つられるみたいにあたしも笑うことができた。それぞれ手にハートのスタンプを押されて、フレちゃんが赤い風船を受け取ると、手を振ったウサギが扉を閉じてしまった。
そこではあたしたちが折り重なりながら無限に続いた。正面も背後も��顔も、上下を見れば頭のてっぺんから爪先まで、理屈は知りながら初めての光景は驚きに満ちて、同時にかすかな恐怖を伴った。だけどフレちゃんは本当に楽しそうにしていて、おそらく人類史上初めてのポーズを取ってみたりその歴史的快挙にあたしを誘ったりして、それでもふたりの間には、鏡像にさえ越えられない一線があった。
そうやって、しばらく遊び倒してやっと「出口ってどっちだっけ」とフレちゃんは言う。あたしは鏡に触って「こんな感じで行けるかな」と答える。「メルシーしきちゃん」そう言ってぺたぺたと鏡をなぞる姿は一つ角を曲がると消えてしまって、後には無限に連なるあたしが取り残された。
「フレちゃん」とあたしは叫んだ。鏡越しの声が聞こえて、その向こうだとわかると「離れて」と言って思い切りガラスを蹴る。鏡が鈍い音を反響させて、痛みだけが残った。「だめだよ、しきちゃん」全ては衝動だったので、行為の危険性は遅れて認識された。でも、と手で叩いた鏡の中であたし同士が視線を重ねるのは、滑稽な一人芝居みたいだった。
「出口で、会えるんだよね」
「そうだけど、でも」
「じゃあ、平気だよ。ね」
「わかんないよ。だって、普通じゃない」
「大丈夫。だって、ここは愛の国だから」
「あたしには……ねえ、信じていいの」
「愛を、信じられない?」
「……わかんない、だって、こんなの」
「初めてだから?」それはフレちゃんの声じゃなかった。「怯えてるの? にゃはは、それってすっごくナンセンス」鏡越しのあたしが、挑発するみたいに笑った。「未知は喜びじゃないの? そうやってずっと生きてきたよね? 今さら怖がる必要なんてない、今までみたいに楽しんでいこうよ、ね?」
あたしは、あたしから逃げ出す。背後の鏡に勢いよくおでこをぶつけて、鏡の中のあたしがおなかを抱えて笑った。痛みをこらえながら目を閉じると、耳も塞いで、足先で鏡の縁を辿りながら歩いた。暗闇の中で角を右へ、右へ、右へ、ほとんど軸足が動かないことに気付いて目を開くと、そこにはホラーハウスの光景がある。足のないおばけのマスコットや角の欠けた墓石、剥がれた黒い壁紙にはぐちゃぐちゃとしたクモの巣がかかっていて、空間の中心にある朽ちかけた棺には『一ノ瀬志希 ついに愛を知ることのなかった女』そう刻まれていた。
あたしは振り向くとほとんど頭をぶつけるつもりで、それでこの悪夢が覚めると信じて棺の鏡像へ飛び込んだ。けれどそこにあったはずの鏡は消えて、体は無防備に投げ出される。痛みに呻きながら顔を上げると、遠くにフレちゃんを見つけて歩き出す。その表情は一歩ごとに確かになって、目の前まで来てやっと、ほっとしたみたいに笑った。だけどすぐに、きっと自分が怪我をするよりずっと辛そうな顔をした。
「しきちゃん、急がなくていいよ。ね、ゆっくりでいいから」
「……フレちゃん、でも、心配だから」
「あたしは大丈夫、ほら、キュートなフレちゃんのまん��でしょ?」
「……ほんとだ。にゃは、フレちゃんってなんでそんなにかわいいの、もう」
「ふふーん、ママとパパ、しきちゃんのおかげかなあ」そう言って、フレちゃんは手のひらを広げてガラスにぴたりとくっつけた。「ねえ、手、繋ぎたいよ」
「うん」とだけ答えて、あたしはガラスに触れようとした。だけど、寸前に起きたあの愛のフラッシュバックに手を止めた瞬間、フレちゃんの背後からあたしが姿を見せる。残酷に笑うあたしに抱きしめられて、フレちゃんは嬉しそうに笑い返した。
二人の距離は少しずつ近付いていく。二人を隔てるもの全てがなくなって、唇が重なろうとした瞬間にガラスは鏡面を取り戻す。鏡の中のあたしがぼろぼろと涙を流しながら、あたし自身と手のひらを重ねた。それが冷たくて、固くて、ひどく悲しくて、うずくまった。この愛の国に置き去りにされて、あたしはどうしようもなくひとりきりになった。
あたしは「怖いよ」と言う。愛が怖くて泣いている。「痛いよ」と言う。愛の痛みで泣いている。そうしながら、胸の内にある温もりを抱きしめる。かすかなともし火が消えてしまわないよう、必死に抱きとめている。だから、「ねえ」という声に答えられない。「どうして泣いているの?」不思議そうに訊ねる誰かに、顔を上げられずにいる。
「あたしには分からないけど、そっか、涙には副交感神経を活性化させるはたらきがあるから、必ずしも悪いことじゃないよね」その声は幼いのに訳知りで、せっかくだから、と続けるとあたしの髪を優しく撫でてくれた。「これでもっとリラックスできるよ。どう? ママとあたしで実証済だから」
あたしはその声を知っていて、それは園内で聞いたアナウンス、だけど、ずっと昔から知っている。
「ごめんね、もう行かなきゃ。だってママとパパが一緒だから」そう言って彼女の指があたしの髪を離れると、楽しげなおもちゃのメロディが鳴りはじめる。待って、とあたしは顔を上げた。その姿は、光と涙で滲んで見えた。ウサギの乗り物に乗っていて、両隣には歩幅を合わせて歩く大人のシルエットがあって、かろうじてそれだけが分かる。「そうそう」と彼女はひとさし指を立てると「ここってすごく素敵だよ。ほんとはね」と言う。立ち上がって、あたしはふらふらと白い光へ飛び込んでいく。目も眩むほどのかがやきの中で「知ってるでしょ」という声を確かに聞く。
それきり、何も聞こえなくなった。光も音もなくして、高鳴りをやめない鼓動だけをつぶさに感じていた。
あたしはゆっくりと目を開く。少しずつ、この恐ろしいほどの光に心を慣らしていくと、真っ白な空間にあのマスコットを見た。彼はちっとも似合わないタキシードで装っていて、あたしと視線を重ねるとシルクハットを手にして恭しくおじぎをする。指を三本立てて、二本、一本、そして、力強く両手を広げると手にしたステッキでこの世界に魔法をかけた。
白い世界には、色が響く。無音の世界を音楽が塗り変える。夜をスクリーンにして、今、鏡の中のパレードが躍り出した。そこには無限に連なる彼らがいて、だけどそれぞれが別々の命を持っている。タキシードとシルクハット。色とりどりのドレス。ちっちゃな子には短いズボン。真っ赤な布地に金の刺繍をあつらえた旗、振り回すのは羽根帽子の少女たち。後ろからは楽隊が続いて、力強い太鼓のリズムに高らかな管弦の音色を織り重ねた。
そして、パレードの中心には電飾に彩られたミニチュアのお城がある。またたくたびに色を変える光のテラスではあたしたちが、どれだけあげても尽きない笑顔をあたり構わず振りまいている。
鏡の中のあたしが、あたしを見つける。肩を叩かれたフレちゃんもすぐに気付いて、ふたりは大きく手を振った。早くおいでよ、楽しいよ。ねえ、こんなに素敵なんだよ。そんなふうに誘った手がやがて指し示したパレードの出口、この夜への入り口へ、あたしは走り出す。マスコットたちが、子どもたちも楽隊も、そしてお城のふたりがあたしへ声援を送った。次々に、鳴り止まない声や音楽が背中を押した。きらびやかな光が進む道を形作ると、その向こうで開けた夜を身に纏ったフレちゃんがいっぱいに腕を広げてみせた。それが本当のフレちゃんだなんてことは(ミラーハウスは、もう終わった)当たり前に分かって、あたしは勢いのままにその体を抱きしめる。あんまり思い切り飛び込んだせいでバランスを崩すと、れんが塀から乗り出した体を夜風が支えた。そこはお城のテラスで、あたしたちは「あぶなかったね」と笑いながら愛の国に溢れる光を見下ろす。「あたしね、子どものあたしに会ったんだよ」フレちゃんは、目を輝かせたまま話しはじめる。
「あたし、不安でどうしたらいいかわからなくて、だけど子どものあたしはぜんぜん、きらきらした目で笑うんだよ。一緒にいこうって、手を繋ぐんだよ。子どもって、すごいよね。あたしなんてもう、かなわないなあって思っちゃった」
「でも」とあたしは頬をつついてみせる。「フレちゃん、きらきらしてる」
「そう、そうなんだよー! さすがしきちゃん、そこであたしは考えました。子どもには敵わないなら、あたしが子どもになっちゃえばいいんだって。そしたらね、ほら、こんなにきれいな場所だったんだよ!」
フレちゃんが手を振って、愛の国には新たな明かりが点る。ローラーコースターや大観覧車、生まれた光の全てがこの夜を彩り尽くした。
「魔法だ、何もかもフレちゃんの思いのままだ」とあたしは笑う。しばらく光を眺めると、フレちゃんへ向き直る。その瞳があまりに眩しくて、途方もない力で引き寄せるので「ねえ、あたしもそれほしい」と思わずねだる。返事なんて少しも待たずに、あたしたちはキスをする。重ねた唇や手のひらからは愛の行為が鮮やかに甦って、なのにそれは少しも怖くなかった。触れ合う肌をかけ巡った幸せが、一瞬一瞬を満たしてやまなかった喜びが、まるで今この瞬間に起きているように感じられていた。
「あたしね、フレちゃんとなら子どもでいたいよ」
「それって、あたしがお子さまだから?」
「ううん、愛してるから」
「そっかー、じゃあずっと子どもでいようね」
「大人になっても、ね」
「一緒だよ。だって、すごく愛してるの」
そんなことを言いながらちっとも子どもじゃないキスをして、あたしたちはこの国の住人になる。まぶしい光の一部、中心、いちばん明るい一点になって、やっと目覚める準備ができたのだと知る。
『……えー、もうすぐ閉園のお時間です』もう聞き慣れた、その声が響いた。マイクの後ろからは隠す気のない笑い声が聞こえて、あたしには彼女が一人じゃないことがよく分かった。『お帰りは当園自慢のローラーコースターからどうぞ。それと、えっと、こう言うの? それじゃあお別れに、せーの、”良き愛を!” また、ここで会おうね』
*
ローラーコースターは、のんびりと空を目指す。ふかふかの座席もぜんまい仕掛けの軽やかな音も、夜に浮かぶハートの月も、自慢のローラーコースターには愛の仕掛けがたくさんあって、あたしたちは最前列でそれこそ子どもみたいにしてずっとはしゃいだ。
「あ、風船!」フレちゃんはそう言って、パジャマにくくっていた風船をしゅるしゅると外す。「なくなっちゃうのかなあ」
「にゃはは」とあたしは届くように笑って、受け取った風船をあたしのとまとめて空に放った。赤と黄色の風船は空を昇って上昇気流をつかまえるとあっという間に消えてしまって、星のない夜の星になった。ぱちんと鳴らす指を合図に無数の光が空に点ると、そのまたたきは遥か向こうの地平線にまで連なった。
「わお、ボーノボーノ!」
「フレちゃんそれってイタリアン」
「そうだっけ?」
「でも、伝わる。よく分かるよ」
「さっすがー、しきちゃんはフレちゃんハカセだね」
「いつも考えていますので」
そんなふうにいちゃついていたら、突然のかがやきに目がくらんだ。それはローラーコースターの下、地上から湧き上がる光で、まるでステージからの景色みたいにあらゆる色であたしたちを包み込んだ。たちまち空と地の境は曖昧になって、一つの球体になった世界からは重力さえ消えてなくなった。昇るのか降りるのかもわからなくなったレールの上で、「ちゃんと見なさいって」とあたしは肩をすくめる。「でも、子どもは叱られるのがおしごとだから」とフレちゃんは悪びれずに言う。それでもあたしたちはこの国の愛のわざにすっかり虜にされていたので、気が付けばずいぶん高いところまで昇っていた。もうすぐに、ローラーコースターはその本質を発揮する。見下ろした景色にその瞬間を重ねると、背中がぞくぞくとした。お腹の底をねじられるみたいな感覚がして、思わずフレちゃんにぴたりと身を寄せた。
「こわい?」フレちゃんはあたしと真逆に目を輝かせて言う。あたしはうんうんと何度か頷いて答えると、ほとんど無意識に探したフレちゃんの手のひらを強く握る。「前にみんなで乗って、なんていうの、すごかった」そこから流れ込む愛の記憶はやっぱり生々しく鮮やかで、重なり合うハートのスタンプみたいに優しい色をしている。
フレちゃんはあたしの手を握り返して、「大丈夫」と言った。「あたしがついてるよ。ふたりなら、ぜーんぶシルブプレだから」
「なにそれ」と笑いながら、あたしは思う。怖かったり痛かったり、なのにきらきら輝いて、愛することは本当にたいへんだ。だけど、だからこそ楽しい。夢中になる。がんばりたくなって、きみを喜ばせたいだなんてありふれたアイディアが世界にたった一つの宝石みたいに特別な輝きを放つ。「あ、でもそういう魔法の呪文、あたしも知ってるよ」あたしはそう言って、耳うちの仕草で誘いをかける。ふんふんと耳を寄せたフレちゃんに、いたずらの吐息と一緒にささやきかける。
帰ったら、あたしがフレちゃんに何をしたいか。
ふかふかのベッドで、あたしがフレちゃんに何をしてほしいのか。
そういうことを伝えたお耳からフレちゃんはみるみる真っ赤になっていって、「ばかばか」とあたしを叩いた。それがちっとも痛くなくて、優しくて、繋いだ手を離さずにいるのがおかしくて、「かわいいよ、すごく」なんて言っているうちに、ついに上昇を終えたローラーコースターが落下の準備を始めた。
あたしたちは、前を向く。背筋を伸ばしたら、息を呑む。レールの先には真っ白な光の渦があって、そこをくぐって行くのだと分かった。「またね、ラブランド」と唱えて、あたしはまたフレちゃんの手のひらを強く握った。悲鳴を上げる準備は、それで済んだ。
体が落下を始めると、あたしたちはお揃いの悲鳴をあげる。それはまるで、産声みたいだ。生まれた日の祝福、人生に二度はない時間の再来は夢にだけ許された奇跡だ。ハッピー・リ・バースデイ。このレールを過ぎたあたしたちは、どんなふうに目覚めるだろう。どうか、とあたしは愛の国に流れる星に願いをかける。良き愛を。生まれ落ちたふたりに、いつまでも。
ローラーコースターは光の渦へ飛び込んでいく。その寸前、あたしは見覚えのあるかがやきを目にする。シャンパンゴールドのネオンサイン。あたしは叫ぶのをやめて笑った。そのうちに、眩しくて何も見えなくなった。フレちゃんを抱き寄せて、キスをした。その甘い愛の手触りを感じながら、あたしの意識は途切れた。
この夢の出口であたしたちが見たのは、こんな言葉だった。
Welcome to THE LOVE LAND - All of the world!
『ようこそ愛の国、ラブランドへ!』
0 notes
Text
ある画家の手記if.80 雪村絢/名廊直人視点 告白
俺は 俺の意思だけで生きてこれたわけじゃなかった
たくさんの人の支えがあった
その中に この人への憎悪と関心 見つかったことの恐怖や 見つけてもらえたことへの戸惑いや あの人へ演じ続けた本物と 演じた偽物の自分 ほとんど会ってもないのに加害であって被害でもある傷つけあった関係 そういう、すべてが あった
電車でしばらく行ったらすぐに最寄駅に着けた。
探さないでもすぐ分かった。ここからぱっと見て徒歩五分圏内に、30階もある高さのマンションは一つしかなかったから。
それなりの高級住宅街ではあるのかな。階数はなくても周りも綺麗なマンションとかアパートが多い。手入れされてない荒れた公園とか、無秩序にゴミや廃棄物の積まれたエリアとかは、行き着くまでに見かけなかった。
近づくほどに思う。このマンション…本当に直にぃが選んだのか?
あの人のことよく知らないけど、小学生の俺が会った時の直にぃの格好は、よれたシャツに履き古して色の落ちたデニム、髪はぼさぼさでいい加減に後ろでひとつに縛ってた、それもなんか輪ゴムとかだったような。ちょっと本家に寄るだけにしてもあまりに浮きすぎてて印象に残ってる。
実際すごい顰蹙かってたけど、直にぃはまるで気にしてなかった。俺と話してる短い時間の途中で皮肉をかけていった親戚もいたけど、気にしてないどころか直にぃには言ってることの意味がわからないみたいだった。
俺の中の直にぃの心象は、そのときの本人の様子とそこから俺が類推できることで形作られてる。その心象からこのマンションにはたどり着かないけどーーー実際がどうかは、これから会えばわかる。
*
絢が無事だった。
誠人くんの話しぶりでは絢がもう死んだみたいだった。つい最近まで香澄と会って、元気に仲良くしてるみたいだったのに…
そう思ってた頃に、沈んでたのが態度に出ちゃってたのか、香澄が知ってることを話してくれた。僕に話すとこうやって態度に出ちゃうから黙ってたんだって。香澄が絢の安全を優先してくれてて嬉しかったから香澄を褒めてお礼を言った。
僕は血縁者ーーーいとこか、ではあるし、理人さんを介しての関係なら…あったけど、絢本人と個人的な繋がりはーーーない。
…でも、ずっと忘れてたことだけど、香澄から初めて絢の名前が出てきた日に、思い出したこともあった。
そういういろんなことを、絢とちゃんと話したい、例えば僕が嫌われてて、たった一度でもう二度と会えないことになったとしても。そう思って、電話をした。
午前の日が眩しい。香澄は今は起きてて、リビングのソファにいる。
ここ最近、香澄は僕の部屋の本棚から『星の王子さま』の古い本を出してきて読んでた。今はその本を開いたページで胸に乗せてソファでうとうとしてる。絢が引用したって言ってたっけ。
…香澄もきっと、絢に会いたい。
まだ自傷がおさまらなくて僕の腕には引っかき傷が残ったままだけど、僕は怪我が治るのも早いからひどく傷んだりはしてない。
それで僕は今はお昼ご飯を作ってる。
*
1705室のインターホンを押した。
香澄の声で応答がきたから「絢です」って言ったらろくに本人確認の質疑応答もないまま解錠された。見つかりそうになって誰かから逃げてきたとか思われちゃったかな。特にマスクとか帽子とかは何もつけてないから、香澄ならモニターで顔見れば俺だってわかるか。
エレベーターに乗って17階まで上がる。聞いたところによると直にぃは画家だった頃に相当な数の自殺未遂を繰り返してるんだとか。経歴うまく伏せるかごまかしてマンション買ったな。じゃないと17階なんて、不動産屋やオーナーやかかってるなら病院の審査に通るわけない。ここ高そうな物件だしいくら財産持ってても厳しいはずだ。…遠くからマンションの外観を見た���きと同じブレがある。直にぃがうまく自分の経歴をごまかす? 誰か別の人の名義で買ってでもいるのか…部屋を譲られたとか…なにか、直にぃに変化があった、画家をやめたのとここを買ったのは同時期かもしれない。…でも昨日話した直にぃは昔の心象からそれほどズレてない。まぁ…ひとが綺麗にまっすぐな一本道で今日につながってるわけないから、怪しむほどでも、ないのか…どうか
扉を開けたところで香澄が待ってて、エレベーターから降りてきた俺を部屋の前で一度ぎゅっと抱きしめた。
体を離して、香澄が先に口を開いた。
「勝手に直人に話して…ごめんなさい…」
しょんぼりした香澄の頭を撫でて「いいよ」って笑う。
「…なんて呼んだらいい?」
「今の名前は雪村絢だよ。香澄の好きに呼んで」
絢の一文字が残ったら嬉しいって言ったら絢の一文字だけでとくに何もくっつけられずに他全部ぶっとばされた。真澄さんらしいな…。
「絢…」
香澄が感慨深そうに俺の名前を口にした。
「なに?」
優しく笑って返事したら香澄は眉を下げてにこにこした。つられて俺もにこにこする。
香澄の体に腕を回してぎゅっと抱きついたら香澄もまた抱き返してきた。香澄の肩に頭を乗せて、頭を傾けて頰を肩にくっつける。…あったかい
*
香澄が部屋の前でドアを開けて待つって言うから、僕は突然のことに急いで畳んだまま置いてた洗濯物とかを寝室に運び込んだりしてた。
絢がきた、って、昨日「近いうちに」なんて言ってただけだったのに、何も準備してない、せっかく会えるなら、受け取ってくれるかはわからないけど絢にもなにかプレゼント準備したかったな…
廊下で話してたのか、少ししてから香澄と一緒に部屋に一人の青年が入ってきた
くすんだ金髪の、香澄と同じくらいの背で、
「ーーーーーーー………」
靴も脱がずに玄関から廊下にいる僕をじっと見つめる、大きな両目はどこか少し心細そうで、繊細な印象をしてた
「…………絢…」
「直にぃ。久しぶり。…ほとんど初めましてに近いけど」
そう言って柔らかく笑って、靴を脱いで香澄と一緒に部屋に上がってきた
「…………絢。…こっちにきて」
僕は絢に歩み寄って、その背に腕を回してダイニングの方のテーブルの前に誘導した。
適当にそこらのいらない紙をとってテーブルに置いて、近くにあったペンを一本、絢に差し出す。
「絢。ここにこう書いてくれる?ーー………、」
絢はしばらく無言でじっと白紙を見つめてたけど、おもむろにペンをとった
淀みなくすらすらとした筆致に筆跡を偽るような気配は感じられなかった
一目見て確信することができた
「やっぱり、あれは絢だったんだね」
“名廊雅人”
ほとんど癖のない綺麗な楷書だけど毎回同じだれかの筆跡だってことだけは分かった
視たものをまだちゃんと覚えてる
僕に兄さんの名前を名乗っていくことの意味を深く考えたことなんてなかったし、今も僕にはわからない
昔は なにもかもそのままで終わっていって過ぎ去っていってた 意味なんてものは問わなかった なにに対しても
僕にはそのことに痛みも悲しみも なにもなかった
でも僕はいま聞いてみようと思う、僕にはわからないことを、相手を大切にするために、心から知りたいと思うから
「どうして僕に…この名前を名乗ったの?」
*
久しぶりに会った直にぃは、少し身なりがこざっぱりしたくらいで、ほとんどなにも変わってないみたいだった
これまでの話より何より真っ先にさせられることが これだなんて思ってなかった
ほんとうのことなんて 言えるわけない
でも隣で背に優しく手をあてて微笑んだまま俺をまっすぐ見つめて捉えて離さない瞳が、いま、この場で、このことについてだけは、俺にいっさいの嘘を許さなかった
言ったことをなんでもそのままにすべて信じる、滑稽なほど正直で素直な、非武装の姿をそのまま惜しげなく晒す 昔となにも変わってない
危うい生き方だ 危険な視線だ その無防備さが対峙した相手にも武装を解くように訴えてくる なぜか、ただ愚直だと笑い飛ばせる類のものじゃなかった
この人はこれで40年以上生きてきた いつも真剣で 自分の愚直さに気づけないほどにいつも一生懸命だ
他のことならいくらでも嘘もつくし事実も捻じ曲げよう、この人にできないのなら俺がやろう、そう思って その当人から、こんなことを問われてる
俺のことを深く知らないにしたってそんなことと関係なくあんまりにも心ってものに無神経すぎるよ
それでも俺は このことについては 嘘をつけない
さっきまでの快活な口調でいられなくなって 俯いて 喉が詰まる
小さな声しか出なかった
「…雅人さんの遺体の第一発見者が、直にぃだって本家で聞いたんだ。それで
…苦しめばいいと思った。作品のむこうにいる俺にまで…まっすぐな目を向けてくるから
悪意もなく 無自覚に 暴きたててくる視線が怖かった
それが ずっと つらかった…」
*
絢の言ってることは、僕にはわかるようでわからない
作品ーーーあの、感想文か、『星の王子さま』の
僕は作品から作者を見ることはほとんどない 特にあの頃はそうだったと思う
でも絢の表現は絵ではなかった
文章は一目瞭然じゃないから、僕は絢の書いたものを視たんじゃなくて「読んだ」
その頃の僕は今よりもっと文章や特に物語を読むのが苦手で、文章は知識を頭に入れていくだけのもので、感想も解釈も僕の中には生まれなかった
絢の書いた意訳と感想文を眩しく思ったのを覚えてる
でもそれだけではなかった
文章の向こうに 痛切に姿を隠そうとする誰かが視えた
僕は視えたものが偶然ひとだったから、あのとき声をかけた 絢に 思ったことを言った
でもーーーあの頃の僕は どうやってひととモノを分けて 視ていたっけ
すべては描けるかどうかで、描けるならそれは それそのもの以外の何でもなかった それだけのものだったはずだ
ーーー昔の感覚が 覚えていられなかったはずの過去の記憶に引き寄せられる
絢は僕に 苦しめられていた
そんなことは知ってた でも、理人兄さんのことを抜きにしても、…そうか、関係して 続いてたんだ 絢の中では
僕に見つかって怖かった… 僕は言ってはいけないことを言っていた?
「………」
少し俯いて首を傾けた絢の大きな目に睫毛に支えられるみたいにして涙がいっぱい溜まってる
…ああ なんて美しい かけがえのないものだろう
簡単に謝ろうとした言葉をのみこんで
絢の背にあてた手を肩に回して引き寄せて、絢の頭にこつんと僕も頭をあてて
目を閉じる
肩に回した手をそっと頭にあてて金髪を撫でる
絵も文章もない触覚だけの くらい世界
それでもたしかに 絢はここにいる
*
あのとき直にぃに見つかった俺は、ただ怯えて戸惑って感情のやり場を失った
でもあのことがなかったら、俺は理人さんを亡くした くらい部屋の中から歩みだして、何かを最後にしておこうなんて 思っただろうか
なんとなくのその延長線上でフランス文学やフランス語、翻訳や意訳を続けたことが、今の俺が生活していく支えになろうとしてる
意訳は俺にできるギリギリの自己表現だったんだろう
直にぃみたいに絵なんて直接的なものはあらわせなかったし、隠れ蓑がないと怖かった
だから訳をしてた 原著を書いたのは俺じゃないから
でもどうしても意訳をしたくなる癖が抜けなかったのはーーー寂しかったんだ 誰かに見つけてほしかった 見つかりたくないのと 同じくらいに
目に溜まっていた涙がとうとうボロっと溢れてテーブルに落ちた
背中から回ってた直にぃの大きな手が俺の頭を体ごと引き寄せて、俺の顔を自分の肩口にそっと押し付けさせた
直にぃのシャツに涙が吸われて沁みていく
俺は確かにこの人にも生かされてた
幸せを願ってたよ 憎んでたのと同じくらいに
その憎しみを、ようやく手放す時がきたのかもしれない
そんなものに縋らなくても、俺にはもうしたいことや守りたいものがあって、生きていけるようになったから
今日まで生きてこれたことを心から喜べると思う それだけではないけど それでも
ここに至るまでにどんな思惑があったんだとしても、言葉にして伝えたいことは…
「「生きててくれて ありがとう」」
二人、ほとんど同じタイミングで発した同じ言葉が重なった
しばらく顔を見合わせてお互いにぽかんとしたけど 二人して思わず吹き出して笑ってしまった
直にぃから離れてぼんやり部屋の中を見渡す俺の後ろに静かに香澄がきて、俺の手を握った
握られた手を握りかえす
テーブルの上に一冊の本が置きっぱなしになってた
俺が香澄に暗誦したのを覚えててくれたのかな
香澄の体に軽く背中を預けて、香澄の首筋や両腕や爪の傷口を刺激しないようにしながら、香澄の両腕をひいて後ろから俺の体を包むみたいに前で絡ませた
香澄の額に俺の額をそっと合わせて静かに目を閉じる
明るい室内にむけて 優しく囁くように物語の終幕を暗誦した
「Si alors un enfant vient à vous, s’il rit, s’il a des cheveux d’or, s’il ne répond pas quand on l’interroge, vous devinerez bien qui il est.
Alors soyez gentils.
Ne me laissez pas tellement triste : écrivez-moivita qu’il est revenu……..」
”もしその時、一人の子どもがあなたたちのところへ来て、笑ったり、金髪をしていたり、質問に答えなかったりしたら、彼がだれであるかあなたには分かるはず。
その時が来たら、親切にしてほしい。僕をこんなに悲しんでいるままにしておかないで。
すぐに、僕に教えて、便りをください、「王子さまが帰ってきたよ」と………”
ーーーーーーーーーアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著 『星の王子さま』より
香澄視点 続き
0 notes
Text
2022年4月25日(月)
「I LOVE YOKOSUKA」
買い付けから帰国して10日が経過した。
荷捌きも半分以上は終了し、買い付けた服たちは倉庫内で出番を待っている。
今回の第一目的地はテキサス州ヒューストン。
ヒューストンのジョージブッシュ空港からアメリカに入国し、レンタカーで服や物たちを探し回った。
個人の古着屋があまり行かない中南部テキサスにした理由は2つある。
1つは『アメリカ中南部を探検してみたい』というただの好奇心である。
ただの好奇心とは言ったものの、航空券を取る1ヶ月以上前から現地のリサーチはしていて、航空券の高騰や、ちゃんと買い付けになるのか、という不安もあり悩んでいた。
しかし、偶然にもその間に観た映画や本、曲などにテキサスやヒューストンが登場することが多く、僕はテキサスのカウボーイに鞭で尻を叩かれている気持ちになっていった。
テキサスと西海岸で熾烈な先頭争いをしていたが、尻を叩かれ続けた僕は不安が確信に変わり、見事テキサス行きを決めたのであった。
もう1つは、前回買い付けの帰りの飛行機で仲良くなったS君がテキサス州ヒューストンに滞在しているからである。
言うなれば
『飛行機で隣に座っただけ』の関係だったのだが、長い人生においても、そういう小さな縁が大きな決断の引き金となることもあるのではないか、と常に思っている。
ヒューストン滞在3日目、そのS君と久しぶりに再会。
食事をして、深夜0時前にホテルに送り届けた直後、事件は起きた。
ヒューストンからダラスまで400kmの深夜ドライブを控えていた僕は、ガソリンスタンドで給油を済ませ、エナジードリンクを購入。
眠い目を擦りながら車を走らせ始めた。
全米第四の大都市であるヒューストンのビル群のあいだを縫うように走る。
入り組んだダウンタウンを抜け、ダラスへの一本道であるI-45をひたすら北上。
30分くらい経過したころ、バックミラーにパトカーが映りこむ。
非常灯を回していたが、アメリカのパトカーは通常から非常灯を回して走っていることも多く、日本のように車上のスピーカーから『前の車止まりなさい!」といった物々しいアナウンスもなかったため、とくに気に留めず今まで通り前進を続けた。
しかし、2.3分経過した頃だろうか、後方のパトカーが蛇行運転を始めたのだ。
所謂、合法な煽り運転である。
『やばい、追いかけられてんじゃん!』
と、気づいた時にはすでに事が大きくなっていた。
僕はパトカーと数分間カーチェイスをしていたのである。
ハイウェイ上の路肩が狭かったため広いところまで行こうと思い、ハザードランプを点灯しつつ、さらに数十秒走る。
すると、その間に前方からパトカーがもう1台現れ、後方のパトカーも3台に増えていった。
『流石にこれはやばい...』
と思い、アーチ型の高架上だったが、路肩の拡大を待たずに停車。
前方のパトカーも後方に回り、計4台のパトカーは僕の車から十数メートル離れて停車した。
パトカー達が一斉に超強力ライトを照射してきたため、周囲は昼間のような明るさになっている。
後ろを振り返ると、警察官達はドアを開いて盾にし、こちらへ銃口を向けて何やら叫んでいる。
映画でよく見るあの光景である。
距��が遠いのと、大声、早口で完全に聞き取れていなかったが「エンジンを止めて手をあげて外に出ろ!」ということだったと思う。
僕はびびりながらも冷静に『撃たれたら終わりだ…』と思い、両手を頭に乗せ車の窓から身を乗り出した。
産まれて初めてレベルに盛大に両手をブンブン振り回してボディランゲージをしながら
「I don't think chasing me!sorry!」
(僕が追いかけられてるって思わなかった!ごめんなさい!)
何度もひたすら叫んでみたが、警察官達は許してくれるはずもなく
「早く出てこい!!」
と怒りまくっている。
車のドアを開け、両手を頭に乗せたまま外に出る。
いつか見た映画をなぞって地面に伏せようとすると
「そこじゃねぇ!こっちこい!こっちだ!」
と叫んでいる。
ゆっくりと警察官の近くまで行くと
「そこに伏せろ!」
と言ってきたため、地面に伏せようとした。
しかし、手をどの位置に置くのかが分からず(今考えたら頭の上で良かった)、とりあえず『大地に手のひらが付いていれば撃たれないだろう』と思い、両手を広げて足を伸ばし、まるでジーザスのような格好で地面に伏せたのである。
なんとも滑稽であるが、窮地に立たされた人間は、自分でも考えられないような可笑しな行動を取ってしまうということを痛感した。
すると、すぐさま警察官達が駆け寄り、僕のジーザスな両手を拾い上げて後方にまとめ、手際良くカチャカチャっと手錠をかけた。
手錠といえば『冷たく重い』イメージがあったが、人生初めての手錠は(そういうプレイもない)、意外と軽く、警察官の体温なのかテキサスの気候なのか、生暖かかった。
警察官は8人、顔も全員覚えている。
イーサンホーク似で50代くらいの小柄なおじさん警察官、若い頃のジャックブラック似で30代くらいのぽっちゃり警察官、この2人に脇を抱えられ立ち上がらせられ、念入りにボディチェックを受ける。
(この後もこの2人がメインで僕の取り調べをすることになる)
後方6人の警察官達はまだ僕に銃口を向けている。
小声で「I don't think chasing me... sorry...」と塩らしく言ってみたが、状況は変わらず。
柔らぐどころかイーサンホークおじさんは語気を強めて
「あんなに長い間追いかけられてて気づかねぇのか?!」
「日本では警察に後ろを付けられても止まんなくていいのかよ?!」
と返答してきたため
「日本ではスピーカーから止まれアナウンスがあるんだ」
と言ってみたがそれでもダメだった。
手錠が皮膚にくいこんで痛む。
名前や職業、在米理由など細々と職務質問され答えていると「今から車の中を捜索する」と言われ、どこからともなく麻薬探知犬のデカいジャーマン・シェパードが登場。
「こいつにタマを噛み切られてたかも...」と思うとピストルを向けられた瞬間よりも恐ろしかった。
車の捜索中は2台後ろのパトカーの後部座席に放り込まれて待たされた。(おそらく捜索の様子が見えないようにすぐ後ろのパトカーには乗せない様子)
パトカー内は、運転席との仕切りに分厚いアクリル板、両側の窓には鉄格子が付いている。
思った以上に座席の座り心地は良かった。
(黒のレザーでけっこうふかふか)
驚いたのはその狭さである。
運転席と後部座席との空間がとても狭い。
後方でキツく手錠をかけられているので背中を座席につける事が出来ず、椅子の座りが浅いため、両足を広げてガニ股にならないと座れない状態なのだ。
小柄な僕でもそれだけの窮屈さということは、大柄な欧米人たちは比べ物にならないくらい辛い体勢になると思う。
そんなことを考えながらぼんやりと鉄格子越しの窓の外を眺めていた。
一度パトカーから出されて指紋を取られたりしていると、イーサンホークおじさんとジャックブラック君以外はすでに『無害のアジア人』に飽きていて、僕に背中を向けたまま、久しぶり〜などと言いながらグーバンチをしたりしている。
すると、車内を捜索していたイーサンホークおじさんが鬼の形相で帰って来た。
イーサンホークおじさん
「お前名前なんだっけ?」
僕
「TSUKASA KUROSAWAだよ」
イーサンホークおじさん
「なんでパスポートと国際免許が2人分あるんだよ。お前なんか嘘ついてないか?」
僕
「え?そんなわけあるかい......あれ.....2枚ある.....」
パスポートを開いてもらい名前を確認すると
『S◯◯・O◯◯◯◯』
S君...
なんと、先ほどまで一緒にいたS君がパスポートと国際免許を助手席のダッシュボード内に忘れて帰っていたのである。
僕はより一層怪しまれてしまい、車内捜索は厳しさを増し、S君の情報(罪歴や盗難届など)を警察の機関に問い合わせたりと、拘束時間が長引く結果となってしまった。
手錠が皮膚に食い込んで痛む。
イーサンホークおじさんがS君の情報を調べている間、今しかない!とばかりにジャックブラック君が僕のところにやってきた。
ジャックブラック君
「TSUKASA、横須賀知ってる?」
僕
「もちろん知ってるよ」
ジャックブラック君
「俺、2年間横須賀にいたんだよね〜。横須賀大好きだよ!」
僕
「そうなんだ〜海軍だったの?」
(無駄話いいから早く手錠外して(心の声))
ジャックブラック君
「そうそう!横須賀また行きたい、いや絶対行くよ!」
僕
「そっかそっか、じゃあ日本で待ってるからね〜」
(横須賀もう分かったから早く手錠外して(心の声))
ジャックブラック君
「いや〜横須賀の人たちめちゃくちゃ優しいしさ〜本当好き!」
僕
「うんうん」
(横須賀ほんとにいいから早く手錠外せ(心の声))
僕が捕われの身である事はお構いなしで横須賀の話を永遠としてくるのである。
今となってはちょっと面白い話だが、手錠をかけられてから1時間半ほど拘束されている僕には横須賀話を楽しむ余裕は無いのだ。
邪険にする訳にもいかず、少しイライラしつつも適当に流して答えていた。
そして、ようやく捜索や照会が終わり、イーサンホークおじさんが僕を車の後ろに連れて行き、後ろを向かせてカチャっと手錠を外した。
拘束されてから2時間が経過していた。
くっきりと手錠の跡が付いた手首を撫でる。
僕は手錠のキツさと拘束されたダメージで疲れ果て、ハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
イーサンホークおじさん
「もう行っていいぞ。とにかくアメリカでは警察が後ろに来たらすぐに止まれ。」
僕
「分かった」
だべっていた警察官達はそそくさとパトカーに乗り込み、次々と走り去っていく。
僕はまだハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
イーサンホークおじさんとジャックブラック君もパトカーに乗り込む。
僕はまだハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
ジャックブラック君がパトカーの助手席の窓を開けて何かを言おうとしている。
僕はまだハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
イーサンホークおじさんとジャックブラック君のパトカーが走り出す。
僕はまだハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
追い抜きざまにジャックブラック君が身を乗り出し何かを言おうとしている。
僕はまだハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
手錠の跡がキリキリと痛む。
追い抜きざまにジャックブラック君が叫ぶ。
「TSUKASA!!!! I LOVE JAPAN!!!! YOKOSUKA!!!!」
僕はまだハイウェイ上で呆然と立ち尽くしている。
終
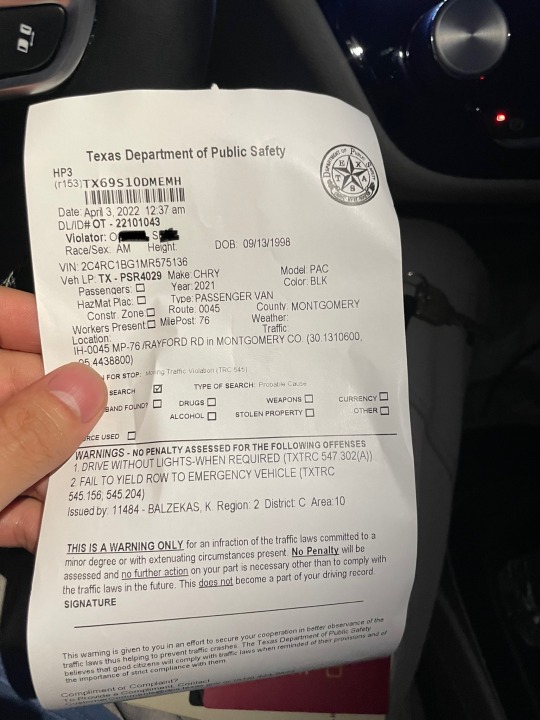

6 notes
·
View notes
Text
無題
Cook Do®の豚バラキャベツをジャッとやり、キンミヤを炭酸で割ってポッカレモンどぼどぼいれたやつをガッと立て続けに2杯パイントグラスで呷った。帰寓が9時過ぎても自炊を怠らない自分に惜しみないハグとキスを。T.S.エリオットは「4月は最も残酷な月」と詠んだ。死の月だ。『荒地』とはそのまま死の国を表すらしい。中学校でサッカーやってた時の背番号が4番だった。俺は「死神」と呼び慣わされ、敵味方となく畏れられたサイドバックだった。嘘である、半分は。
*
某会議の為に某地方公務員の伏魔殿に出張った。テレワーク導入から遥か遠く置き去りにされた業界地図の隅の隅の方。大きな正門の脇に設えられた人一人分の門扉をそぞろ抜け、昇降口をくぐってガラス張りの受付の前に立ち、こちらに背中を向けて何か作業していた白髪の男にすんません、と声をかけたら、男はやや飛び上がるように「フアイ」だか「フォワイ」だか言ってこちらへ翻った。白髪の男は「フォンファサダー」とか何か言って、俺はそれが本当に全く自分の語彙にある言葉として聞き取れなかったので、体をやや斜めに右耳を相手の方に傾けて、はい? と言って、パードゥン? という意思を示した。すると、白髪の男は「ファンファルスサイロ」などと言ったので、俺はこいつを異言語話者か吃音のいずれかなんだと断定して言葉によるコミュニケーションを諦め、申し訳なさをなるべく全身に滲ませながら、悪いけどあんたの言ってることが理解できないんだ、という表情と態度を取った。こちらの姿がどう映ったかはわからないが、男はやや痺れを切らした様子で部屋の隅のドアを開けてこちらへ出てき、段ボール箱に無造作に放り込まれた来客用のスリッパを示して、ンファス、と言った。俺はありがとうございます、となるべく慇懃に言って、リノリウムの長い廊下を進んで会議室に向かった。スリッパの床を擦って叩く音がスリッパスリッパ、と鳴っているようだった。目的の会議は、「私だってね、忙しいんですよ!」などと激昂する三十路くらいの男の姿が見られてやや紛糾し、予定の時間も大幅に過ぎて重苦しい雰囲気の中終了した。その後俺は司会の男と個人的な用件で話し込み、会議室を最後に出た。また廊下を一人でスリッパスリッパと歩き弊社へ報告の電話を入れようとしたところで差し掛かったスロープで思い切り滑ってバランスを崩して転倒しかけた。両手を大きく振り、2度3度床に強く足を踏み鳴らした姿は滑稽なダンスを踊っているように見えたかもしれない。高鳴る心臓の音を聞きながら恥の感覚が皮膚の下を走って顔面を紅潮させていくのを感じ、廊下の前後に誰の姿もないことを確かめた。
11 notes
·
View notes
Text
来ての中に会いたいが含まれていても含まれていなくてもどっちでもよかった 一枚ドアを開ければ極寒の中に汗をかくほどあったかい空間があるのは心底安心できたしなんとも滑稽 何も生まない生まれない空間 時間を有意義に無駄遣いしている 私の時間はずいぶん消費されてしまったけどおんなじ時間だけ私も彼の時間にかぶりついて噛み砕いて液体になるまでもぐもぐ 最高の無駄遣い こんなんでいい
19 notes
·
View notes
Text

📛 062 「空手バカ一代」 #11。
テレビの中で 「空手バカ一代」 が はじまりました。今回は 「非常階段の決闘 (第11話)」 というお話です。戦後初めての "第一回空手選手権大会" で 優勝し、体重500kg超えの闘牛ライデンゴーを浜辺で倒したアスカケンは、下宿先の小島テーラーの庭先で 北海道に生息するヒグマとやり合うために、顔面にタイヤをぶつけるという とっても無茶な特殊訓練に耐えています。とにかくヒグマにノサれたときのための訓練なやうですけれど 「ヒグマと戦う前に 顔が凸凹になっちまいます」 と下宿先のコジマさん。逆に 「タイヤを凸凹にさせる」 と無茶苦茶なことを言う流石なアスカケン。今度は後頭部にタイヤをぶつける訓練に励んでいます。もう訓練なのか拷問なのな分からないレベルです。「きいた!きいたぞ!」 とアスカケン。「やうし!タイヤはこれくらいにして次の特訓だ!」 と次なる特訓に切り替えるアスカケンは 「これはクマの攻撃から目を離さぬ訓練」 と、小さな鉄の玉の先に紐を付けて 催眠術をかけられさうな雰囲気の中での特訓に挑んでいます。コジマさんに 「どうかしちまった」 と言われる、どうかしちゃってるアスカケン。そんなアスカ先生は、その日の夜、寝静まった町のとあるビルに愛弟子とササササッと忍び込みます。「泥棒じゃあない、それだけは確かだ」 と、アリアケとともに 夜のビルの屋上に上がる不法侵入なアスカ先生。一日に一回は そこで大声を出すらしいアスカ先生。近所迷惑な気もしますけれど、夜更けにさけぶアスカ先生は 夜更けにさけぶという道をも極めてしまいさうです。そんな夜叫び先生は 妥当ヒグマの鍛錬の日々が続いるのですけれど、そんな中 「どうしたんですか、先生!」 と先生の様子が気になったアリアケ。「空気不足?」 とアリアケ。空気不足ではなく、栄養不足な先生。牛と戦った時のファイトマネーが底をついた先生はロクな食べ物を食べていないやうで やや弱り気味です。農家の親類が練馬にいると先生に伝えるアリアケ。でもそんな親戚はいなかったりするアリアケは 「何とかなるだろ」 と散々歩き回り、やっとの思いでアルバイト先を見つけます。雇い主の養豚場のおじさんのやさしさに涙するアリアケ。その日の夜は先生とご馳走を ぱくぱくと頂きます。翌る日、仕事中にチンピラに絡まれるアリアケ。が、あっさりノシてしまうアリアケ。刃物を取り出すチンピラ。とそこに 「止しなっ!」 と前回アスカケンをぶん投げた柔道男タケバヤシがババっと登場します。「小僧、少しはやるらしいな」 とタケバヤシ。養豚場のアルバイト途中で めんどいことに巻き込まれたアリアケ。アスカ先生に 詫びをいれたいから住所を教えてくれとタケバヤシ。さういうことならと あっさり教える、他人を少しは疑ったほうがいいやうな気もするアリアケ。キャバレーの用心棒として雇われているらしいタケバヤシは すぐさまアスカケンの前に現れます。そんなタケバヤシから 「残飯運び?」 と、何のことやらなアスカケン。けれど 「ハッ!」 とするアスカケン。タケバヤシに言われたい放題なアスカケンは 「あなたはわたしを怒らせにきたのか?」 とタケバヤシにストレートな質問をするアスカケン。何をっ!と、日時も場所も決めずに決闘を申し込むタケバヤシは 突然にヒグマに変わります。「承知した。いつ何時でも勝負を受けやう」 とアスカケン。とりあえず 勝負の前に お知らせに入ります。とっととお知らせが明け 「先生!バリバリ食べてください!」 とアリアケがたくさんの野菜を運んで来ました。「タケバヤシ来ませんでしたか?」 と、彼が謝りたいからとかどうとかと言っていましたよとアリアケ。けれど 残飯運びがバレていたアリアケは先生にすみませんと謝ります。そんなアリアケに 「すまないのは俺のほうだ」 とメンゴメンゴなアスカケン。「ありがとう」 とアリアケ。両眼からぼたぼたと涙を流す先生は 大きな大根に齧りつきます。歯の強さも頂点を目指しているのかもしれません。翌る日か ある日のこと、先生のファンからと どこかのおばさんから 熨斗のついた一升瓶を渡されたアリアケは (怪しむことも忘れ) 先生に持って帰るのですけれど、その一升瓶には タケバヤシの手の者による 痺れ薬が入っているらしくって アリアケはびっくりします。「いやあーっ!」 と瓶を手刀で割るアスカケン。「この勝負、断る!」 と、タケバヤシとの勝負を断るらしいアスカケン。急にキャンセルなんてしたら 周りから何て言われるかわかったものではありませんよ!とアリアケ。「これまでも悪口は言われ続けてきた」 と、せつないことをいうアスカケン。場面は変わり、たぶん次の日。"東都附属大学" の前を偶然に通ったっぽいアリアケは 「空手が強い大学らしい」 と、おそらく許可を得て、正座して稽古を見学させて貰っています。その態度に関心関心と大学生。ところがっ!「アスカ先生の門下生です」 とアリアケが口にしたとところで雲行きが急に怪しくなります。先生について これでもかと悪口を言われ、おじげづいて勝負断ったさうじゃないかと笑われ、牛殺しの化けの皮剥がれた!空手会の面汚しとまで言われるアスカケン。堪忍袋の尾が切れたアリアケは 「アスカ先生の空手がどんなものか見せてやるわ!」 と、超人の夢を追求するアスカ空手で十数人を相手にします。その結果、全身包帯姿で床で横になるアリアケを見守るアスカケン。ひとりタケバヤシのいるキャバレーに殴り込みをかけます。非常階段で会えばわかるとキャバレーの店員に声を掛けられたタケバヤシは非常階段のドアの開いた先で待ち構えていたアスカケンに勝負を挑まれます。空手に先手なしなんていってたよねってタケバヤシに 「空手に先手なし、時と場合により」 と時と場合によってはさうではないかもしれないアスカケン。「そこに正義あるかぎり 空手に先手あり!」 とアスカケン。そんな先手がどうのと熱く語っているアスカケンの額に煙草をタ投げつけたサイテーなタケバヤシ。その隙を突いて 得意の一本背負いでアスカケンをぶん投げるタケバヤシ。がっ!投げられた瞬間、キャット空中三回転とまでは言わないものの、身体をぐるりと反転させて 首筋に凄まじい蹴りを喰らわしたアスカケンは、再現フィルムでもう一度、投げられた瞬間、キャット空中三回転とまでは言わないものの、身体をぐるりと反転させて 首筋に凄まじい蹴りを喰らわしたアスカケンは、タケバヤシを必殺の一撃で倒します。階段を顔から血まみれで滑り落ちるタケバヤシ。彼の生命がとても心配ですけれど、相手が悪かったタケバヤシ。 「いよいよ北海道にわたり、クマと勝負だ!」 とアスカケン。いよいよヒグマと勝負です。
1 note
·
View note
Text
【小説】氷解 -another- (下)
※『氷解 -another-』(上) はこちら(https://kurihara-yumeko.tumblr.com/post/634137547287756800/)
その朝、真奈は自分が乗るはずだった電車に轢かれて死んだ。
仕事へ向かう人間たちで満員になるはずのその電車は、そのせいで一時間以上遅延し、駅のホームでは多くの愚痴や溜め息が零れ、怒りや落胆が行き交った。
だがそれは、ときどき突発的にやって来るありふれた朝の風景にしかすぎず、俺は電車の遅延を伝える駅の電光掲示板を見上げながら、それがまさか、自分の恋人の自殺によるものだなんて考えもしなかった。
俺がそのことを知ったのは、それから三日経った夜のことで、真奈の両親が、彼女が残した携帯電話から連絡をくれたのだった。その携帯電話には、「ノブから返信がないので死にます」というメモが残されていた。ノブというのは俺のことだった。
真奈が自殺した朝、俺は寝坊して焦っていた。仕事があまりにも多忙で、二日徹夜した翌日だった。いつもより遅い時間に目覚めた俺は、慌てて身支度を整え、駅まで走ればいつもの電車に間に合うはずだと、家を飛び出した。ベッドの枕元に携帯電話を忘れてきたと気付いた時には、駅の改札の前にいて、そして人身事故が起きたことを知った。
電車が遅延していることを会社に連絡したかったが携帯電話がないので、仕方なく公衆電話から連絡を入れた。ひと息つき、電車が再び動き出すまで何をして待っていようかと考えながら、ふと、毎日「おはよう」と「おやすみ」を連絡している真奈に、今朝は連絡し損ねていることを思い出した。
今朝だけではない。昨日の夜も、会社から帰宅するだけで力尽き、「おやすみ」の連絡をしていなかった。そういえば、未読メールがいくつかあったような気もする。最後にメールを返したのはいつだっけ。三日前か、それとも四日前か。仕事が忙しくて連絡が返せないかもしれない、という内容のメールを、先週だったか、今週の初めか、送ったような気もする。
家に帰ったら、今日は真奈にちゃんと連絡を入れよう。
なんとか一区切りついた案件の内容を頭の中で反芻しながら、俺はそんなことを考えていた。自動販売機で缶コーヒーを買い、昨日からほとんど何も食べていない胃に、黒い液体を流し込む。寝が足りていない頭と、陽の光がまぶしすぎて閉じてしまいそうになるまぶたは重く、それでも、山場は乗り切ったのだという実感が胸の中にあった。それだけで少し、足取りが軽くなる。
いつ振り返ってみても、あの時の俺ほど、滑稽な存在はこの世にいないだろう。俺は自分が成し得た仕事の達成感で浮かれていたのだ。そして、このことを真奈に話せば、きっと彼女も一緒に喜んでくれるだろう、とまで思っていた。
線路の上では真奈が肉片となって飛び散っていることなど、知りもしないで。
「ノブは、本当に仕事好きだよねぇ」
彼女はよく、俺にそう言った。
それは、純粋にそう口にしている時もあれば、つい仕事にのめり込み、他のことを疎かにしてしまう俺への非難を込めた声音の時もあった。あるいは、羨望が垣間見える時も。
彼女が職場の人間関係に悩んでいることは、以前から知っていた。大学の同期で、同じ年に就職した真奈は、就職したばかりの頃から、上司と折が合わないことに悩んでいた。
俺は苦悩する彼女を見殺しにしたかった訳ではない。だが、「もう少し頑張ってみたら」と言っても、「そんなに嫌ならいっそ転職してしまえば」と言っても、真奈の返事はいつだって、「でも……」でしかなく、なんの変化も起きないまま就職して二年が過ぎていた。何を言ったところで助言に従う訳ではない真奈に、俺は何も言わなくなっていたし、助言を求めて愚痴を零していた訳ではない彼女も、共感や同情を怠った俺に何も話さなくなっていった。それでも、仕事の話さえしなければふたりの仲は良好だった。だから自然と、仕事の話は禁忌となりつつあった。
それでもときどき、真奈は「仕事がつらい」と零した。酒が入るとそれが顕著になり、「もう本当に、あの上司には死んでほしい」と言うこともあった。俺はなるべく口を挟まないで彼女の話に耳を傾けるよう努力していたが、真奈はもう、具体的に何に苦しんでいるのかを、告白しないようになっていた。
俺には、正直、真奈が仕事に対して怠慢だと思うことが、時折あった。
どんな仕事にだってつらく大変な局面はあり、誰にだって嫌な上司や先輩、同僚のひとりかふたりくらいいて、皆がそういった苦労をしながら日々働いて生活している中で、「つらい、つらい」と愚痴を零す彼女が、軟弱に思えたことだってある。
「今日は会社行かない」と言って、一日中、家でゲームをしていたり、ぼんやりとテレビを観ていたり、ソファでごろごろ転がっているだけの真奈に、俺は同情することができなかった。同情できない俺に苛立つ彼女に、さらに苛立った。
「いいよねノブは。毎日会社行くのが楽しくてたまらないんでしょ」
嫌味のようにそう言われた時は、俺も思わず声を荒げてしまったりもした。
だがそれでも俺たちは、普段から険悪という訳ではなかった。上手くいっているんだと思っていた。結婚して、一緒に暮らして、そしたら真奈は仕事を辞めさせよう。そのためにもまず金を貯めよう。口にしたことはなかったが、頭の片隅ではいつもそう考えている俺がいた。そのためにはまず、目の前の仕事に集中しよう。できる限り早く出世しよう。俺は今まで以上に仕事に精を出し、成績は少しずつだが着実に上がってきていた。
そんな俺の姿勢が、余計に彼女を追い詰めていたのかもしれないと、今は思う。
まだ訪ねたことがなかった真奈の実家の門をくぐり、沈んだ面持ちの両親に導かれ、そうして足を踏み入れた仏間、そこに飾られていた真奈の笑顔。まるで花が咲いたような、とでも表現できそうなその遺影の笑顔を見て、俺は腹の底から嗚咽が込み上げてくることに耐えられなかった。
彼女がこんな風に笑っているところを、最後に見たのはいつだったのだろう。忙しいことを言い訳に、ないがしろにした日々の記憶は曖昧で、まるで靄がかかったようにはっきりとしない。俺は今まで真奈の、どんな表情を見ていたのだろう。笑った顔も怒った顔も、泣き顔だって思い出せるが、全てが少し昔の日々の記憶、懐かしい思い出でしかない。
ここ数日の彼女の様子はどうだったのだろう。ずっと連絡を待っていたのだろうか。俺が連絡してこないことを、そんなにも思い詰めていたのか。自らその命を絶つほどに。「おはよう」でも「おやすみ」でも、メールを返していれば、もしくはほんの一分でも、俺が声を聞かせていれば、こんなことにはならなかったのだろうか。真奈のことを、気にかけていれば。
長年、学校の教員として多くの教え子を持っていたという真奈の父親は、遺影の前で泣き崩れた俺に、こんな話をしてくれた。
「もう二十年も前になるかね。中学校に勤めていた頃だ。その頃、担任をしていたクラスに、不登校の生徒がいてね。小学校でのいじめが原因で、中学には入学してから一度も来ていなかった。学校に来るように何度も働きかけをしていたんだが、三年生になっても不登校のままでね。それでも、その生徒のご両親はとても根気強い人だった。学校に行かない息子を厳しく叱ることもなければ、反対に甘やかしすぎることもなく、毎日毎日、その子の気持ちに寄り添い、励まし続けていたんです。その子も少しずつ、学校へ足を向けてみようかなと、心境に変化があったということなんですがね、ある日突然、その子は亡くなってしまった。自宅で首を吊ったんです。ご両親から聞いたお話だと、遺書が残されていて、そこには『昨日はお母さんにおはようと言ってもらえなかった。ついにお母さんにも見捨てられた僕はもう駄目です』と、そう書いてあったそうです。その子が起きて二階から降りてきたら、たとえそれがお昼だろうが夕方だろうが、必ず母親が笑顔でおはようと声をかけるのが、その家では習慣になっていた。ところが、その子が自殺した前日に限っては、母親は忙しくしていて、ついうっかり、いつもなら起きて来た息子に声をかけるところを、かけないでしまった。たったそれだけのことなんです。わからんですよ、遺書に書いてないだけで、きっと他にもその子の心を悩ませ追い詰めた何かがあったのかもしれません。でもね、実際に死へと踏み切るきっかけなんて、些細なものですよ。母親が挨拶を返してくれなかった、それだけのことかもしれんのですよ」
職場での人間関係に悩んでいた真奈。仕事に行きたくないと愚痴を零していた真奈。部屋にこもってゲームばかりしていた真奈。つらそうにしていた彼女の様子が、今さらになって鮮明に思い出せる。「もしも、あの時、ああしていれば……」という後悔だけが、いつまでも胸に焼き付いて離れない。
俺が連絡をしなかった、ただそれだけの理由で。
そんな些細なきっかけで、大切な人を失った。
だから、わかっていたはずだった。人が自ら命を絶つきっかけは、ほんの小さな出来事なのかもしれないということ。
――あなたが、殺したのよ。
井荻公介の母親にそう言われた時、俺は真奈を亡くした時のことを思い出した。
彼の死を責められる度、俺は彼女の死をも責められているような気になった。
――あなたのせいで、公介は。
井荻公介の両親は、それきり俺がその家の門扉をくぐることを許しはしなかった。繰り返し繰り返し、息子の死は俺の責任であると告げられながら、炎天下、俺は門の前に立ち続け、なんの意味もない謝罪の言葉を機械のように繰り返し、それでも彼らに許す気がないことがわかると、黙って去ることしかできなかった。
なんのために、誰のために、俺はこの家を繰り返し訪れているのか。俺は誰に、一体なんの罪を許されたいのだろうか。
「あの、これ」
もう何度目になるのかわからない、無駄足となった訪問から帰る途中、後ろからそう声をかけられた。振り向けば、そこにはひとりの女子高生が立っていた。
「あれ……。きみは確か、井荻くんの…………」
それは井荻沙織だった。井荻公介の妹。
彼女は無言で一本のペットボトルを差し出した。よく冷えたスポーツ飲料。ひときわ暑い午後のことだった。
「縞本さん、でしたっけ」
そう訊く彼女の瞳は、何か深いところを覗き込もうとでもしているかのように瞬いた。
「あなた、本当は違うんでしょ、兄にパワハラした上司と」
彼女の言葉には、一切の迷いというものがなかった。まるで真実を全て知っているかのような、そんな声音にさえ思えた。俺が会社から遣わされた貧乏くじの当て馬だということを、見透かしているようだった。
「どうして、そう思う?」
「だって、そういうことするような、悪い人に見えないから」
「ははっ。悪い人に見え��い、か…………」
恋人が自殺するのも止められず、部下を見殺しにした俺が、悪い人間に見えないのだとしたら、世の中の人間の大半は聖人君子にでも見えているのだろう。
身近な人をふたりも殺しておいて、何が、「悪い人に見えない」だ。
今回の件で辞職が決まって以来、社内でも、裏の事情を知らない他部署の人間たちからは、本当に俺が井荻公介を自殺に追い込んだのだと思われ始めている。辞職は来週に決まってはいるが、連日のように社内で冷たい目線に晒されては、今日にだって辞めてしまいたい気分だった。
だけどどうして井荻沙織は、俺のことを見抜いたのだろう。自分の両親が人殺しだと罵っていたのが聞こえていたはずなのに、そんなことはお構いなしのようだ。本当は、両親と同じように俺を非難することが許されている立場だと言うのに、どうして追いかけて来て、冷えた飲み物を渡してくれるんだ。
この暑さのせいか、まるでこの世界で唯一、彼女だけが俺のことを理解してくれているような、そんな錯覚が起こりそうになる。
俺は、「そうじゃないよ」と、誰かに言ってほしかったのだろうか。気休めでもいいから、そんな言葉を向けてほしかったのだろうか。「本当は違うんでしょ」と、指摘してほしかったのだろうか。こんな風に、誰かに、救ってほしかったのだろうか。許してほしかったのだろうか。
だけどそんなのは、馬鹿げている。
俺は喪服の内ポケットから名刺入れを取り出し、その中に収めていた真新しい名刺を一枚、井荻沙織に渡した。
新しい職場へ向かうことになった俺のために、部長が尽力してくれた結果、まだ入社も配属もしていないにも関わらず、俺の手元にやってきた名刺。誰にも渡したことがないそれを、俺は彼女に渡したのだった。
「……どうして、くれるの?」
井荻沙織は不思議そうな顔をしてそう訊いた。
どうしてだろうな。
ただ、誰かに知っておいてもらいたかったのかもしれない。
たとえどんなに馬鹿げていても、会社の捨て駒にされ、非難の目線や罵声を浴びせられ、誤解され陰口を叩かれ憎まれたとしても、それでも俺という人間を、本当はわかっていてほしかった。
誰かを傷つけた俺だって、同じように傷ついているんだ、と。
それから、井荻公介の死を忘れることはなかったが、妹の沙織のことは忘れていた。
俺は新しい職場に慣れることに奮闘し、しかしどこからか、「部下を自殺に追い込んで、うちの会社に流れてきた縞本さん」という噂が広がり、俺は次の職場でも、入社直後から孤立無援の立場になりかけた。
信頼関係を築き上げるのが困難な中、ひたすら利益を追求し成果を挙げることだけでなんとか会社にしがみつき、がむしゃらな仕事人間になることに徹するうちに月日は流れた。
後輩ができ、少しずつではあったが出世していくと、怠惰な連中を見ることが耐えられなくなった。男だろうが女だろうが、仕事ができない部下は容赦なく叱責した。努力していない人間を見ると黙ってはいられなかった。自分でもわからない焦燥感に駆られ、俺はいつも飢えているみたいに、心休まる瞬間もないまま、狂ったように仕事に打ち込んでいた。
「あれじゃ、鬼だよな。人間じゃないよ、鬼だよ、鬼」
「あの様子を見れば、部下が自殺したっていうのもわかるよな……」
「自分が勝手に必死になってるのはいいけどさ、それを俺たちにも求められても困るっつーの」
俺が喫煙室にいることを知らない、同じ部署の後輩たちが、そんな会話をしながらすぐそばの廊下を通って行った。隣にいた貝塚は、「気にするなよ」とでも言うように、無言のままで肩をすくめる動作をしたが、俺は何も言わなかった。
彼らに言い返すべき言葉など、俺は何ひとつ持っていなかった。彼らは正しかった。間違っているのは、俺の方だ。だが俺は、他に生き方なんて知らない。
そうしてある年の春、どこか見覚えのある新入社員が入ってきたと思ったら、それが井荻沙織だった。
高校生だった頃からは、ずいぶん大人びたように感じたが、だが兄に似た、深いところを覗き込もうとする、あの眼差しだけは変わっていない。
「私のこと、覚えていらっしゃいますか」
煙草を吸わないくせに、俺がひとりでいるのを見計らって喫煙室までやって来て、井荻沙織はそう言った。以前から、彼女が同じ社内にいることに気付いていた。ただ、俺のことなど忘れているかもしれないし、覚えていたとしても、もう関わり合いたくないと思っているかもしれない、だから、よほどのことがない限り、彼女に関わるのはよそう。そう考えていた。
それが、向こうから声をかけてくるとは。
「……覚えてるよ」
俺は煙草を口に咥えたまま、火を点けようと持っていたライターを、そのままポケットへと仕舞った。
「きみは、井荻の……」
「井荻沙織です。縞本宜嘉さん」
「……よく、覚えているな」
「名刺、頂いてましたから」
「名刺?」
そこでようやく、以前、彼女に自分の名刺を渡していたことを思い出した。たった一度だけ言葉を交わした、あの暑い日に、ほんの気まぐれで渡した名刺。
「だから私、この会社の面接を受けたんです」
「…………それで、受かったってことか」
「はい」
「…………」
「……何か、変でしょうか」
「いや…………いや、変だろ」
俺は何もそういうつもりで、あの時に名刺を渡した訳ではなかった。じゃあどういうつもりだったんだと訊かれれば、言葉に詰まるしかないが。
だが井荻沙織はその時、俺���前にして、微笑んだのだった。
「私、変だって、よく言われるんです。両親だって、そう言うんですよ」
そう言って、彼女はにっこり笑った。彼女の笑顔を見たのは、それが初めてだった。
井荻沙織はそれ以降も、何かにつけて、社内で俺に話しかけてくるようになった。彼女が配属されたのは他部署ではあったが、俺が陰でなんて呼ばれているのか、耳にしているはずなのに。
「縞本さんって、仕事帰りに飲みに行ったりするんですか?」
「する時もある」
「どこのお店行ってるんですか?」
本当は、兄のことを訊き出したいのだろうが、彼女が社内でその件を口にすることは一度もなかった。恐らく、俺が「部下を自殺に追い込んで、うちの会社に流れてきた縞本さん」だと噂されていたことを知ったか、あるいは悟ったのだろう。彼女は聡いやつだった。誰に言われなくても、あの深淵を覗くような瞳で周囲をじっと観察し、状況を判断していた。そしてそれは、兄の公介とよく似ていた。
俺は彼女のそういうところに好感が持てた。だから、今まで誰にも教えたことがなかった、とあるバーを教えた。金曜日に行くことが多かったそのバーは、一本入った路地の、見つけづらいところにあって、ひとりで飲むのにはうってつけの場所だった。
「初めてなんじゃない? シマちゃんが他のお客さんこの店に連れて来たの」
彼女を初めて連れて行った時、バーのマスターが含みのあるにやにやした顔でそう言ったのを今でも覚えている。
それから、ときどき、彼女とその店で飲むようになった。俺が読んだ通り、周囲に会社の連中がいないとなると、井荻沙織は兄の件をあれこれ訊いてきた。質問の大半は、俺の部下であった井荻公介の働きぶりや職場での様子を尋ねる内容か、もしくは、どうして俺が公介の自殺の件の責任を全て負って会社を辞めたのか、についてだった。そして俺は、いずれの内容であっても、彼女の質問にはろくすっぽ答えなかった。
はぐらかし続けているうちに、井荻沙織は俺にその手の質問をしてこなくなっていった。訊いたところで答えてはくれないと、彼女自身わかってきたのだろう。それでも彼女はそのバーにやって来ては、俺の隣で黙って酒を飲んでいた。
俺は酔って口数が増える男ではないが、井荻沙織も饒舌になるタイプではないようだった。
それでも少ない口数なりに、バーでは他愛のない話をするようになった。俺が冗談を言えば彼女は笑ったし、彼女の冗談に顔をしかめてやると、さらに嬉しそうに笑った。そんな風に楽しそうな彼女を見ていると、俺は胸の奥底で凝り固まったどす黒い感情が、少しずつ溶けて流れていくような錯覚に陥った。
井荻公介の死と、真奈の死から、許されるような気さえした。そんなはずはないのに。
一緒に酒を飲むようになって、一年半が過ぎた頃、抱えていた案件が上手くいっていなかった焦燥感と、酔いの勢いも相まって、俺は井荻沙織をホテルへと誘った。少しは嫌がる素振りを見せるかと思ったが、あろうことか、彼女は平気な顔をしてのこのことついてきた。
ラブホテルの一番安い部屋に入り、先にシャワーを浴びて酔いが醒めてきた俺は、「本当にいいのか」と、これからバスルームへ向かおうとしている彼女に訊いた。だが彼女は、ただ黙って頷いただけだった。
彼女を待つ間、無下に煙草をふかしながら、俺は「本当にいいのか」と、自分に問い続けていた。
井荻沙織は、恋人ではない。職場の同僚だ。所属部署も異なるし、俺の部下ですらない。年齢もひと回り近く離れている。接点は、彼女の兄を俺は見殺しにした、それだけの関係だ。彼女を抱く権利など、俺にあるはずがない。
やはり帰ろう。こんな場所に誘ったことは間違いだった。一時間前の俺は、一体何を考えていたのだろう。そう逡巡していた。だが、結論から言えば、そんな思考は無意味だった。バスルームから出て来た井荻沙織が俺に触れた、その指先の温かさに、溺れるように甘えてしまった。
他人というのは、こんなにも柔らかく、優しいものだっただろうか。
彼女の髪に指を絡ませながら、俺はこんな風に気持ちが安らぐのは、一体いつぶりだろうかと考えていた。人肌に触れたのも、いつが最後だっただろう。真奈が死んで以来、俺はそういう機会を持たないままでいた。誰かを愛したり、誰かに愛されたり、そんな資格などないような気がしていた。否、俺は井荻沙織を愛している訳では決してない。彼女だって、俺に愛情を抱いている訳ではないだろう。こんな風にまぐわうことが、本当は良くないこともわかっている。だがそれでも、やめられなかった。
欲に流されたと言えばそれまでだが、彼女に触れる度、彼女の指が俺の皮膚をなぞる度に、憑き物が落ちていくような気持ちになった。まるで、林檎の皮がくるくると剥かれていくように。
仕事でいくら成果を出しても、満足感なんてなかった。安堵する暇さえなく、終わりの見えない道をただひたすら走り続けているような日々だった。それがどうして、こんな簡単なことで、癒されていくのだろうか。
果てた後も、俺はしばらく彼女を腕の中に抱いていた。彼女は嫌がらなかった。その身を委ねているかのように、俺の胸に頭を預けていた。その頭の重みすら、心地良いと思う俺は、本当にどうかしているのかもしれなかった。
うとうとしていると、彼女がふいに身じろぎをした。
「縞本さん、私ね――」
ぽつりと、彼女は言った。俺の腕に抱かれたまま、ぽつぽつと語り出した。
「まだ、兄が生きていた頃の話です。私は高校生でした。兄は、ときどき仕事の帰りが遅くなることがあって、日付が変わってから帰宅することもあったんです。遅くに帰って来て、玄関のドアを、勢いよく閉めるんです。ばたーんって、大きな音が二階まで聞こえてきました。もう両親は先に部屋で休んでいて、私は自分の部屋で、試験勉強なんかをしてるんです。階段をどすどすと足音を立てて登ってきたり、トイレのドアを、また勢いよく閉めたり。今振り返ってみれば、きっと仕事のストレスを、兄はそういう形で表してたんだと思うんです」
暗いままの部屋の天井には、窓から射し込む細い光が、数本の線となって映し出されていた。部屋の外を走る車のヘッドライトが、新たな光の線となって天井を移動していく。俺は横目でそんな天井を見つめたまま、彼女の言葉を聞いていた。
「でも、あの頃は許せなかった。兄が、まるで自分ひとりだけが戦っていて、自分ひとりだけが苦しい、と思っているような気がして。両親はもう寝ていて、私が遅くまで勉強していることを知っているはずの兄が、そんな風に家の中で振る舞うことを、私は許せなかった。身勝手だ、と思ったんです。両親は、そんな兄の夜中の様子を知ってか知らずか、何も言いませんでした。それがまた、兄の振る舞いが黙認されているような気がして、私は面白くなかった。夜中は静かで、勉強していると、帰って来た兄が立てる物音が気になって、気が散って、勉強が手につかなくなって、そんなことが続くと私も嫌になってしまって。だから私、ある晩に願ってしまったんです。『お兄ちゃんなんて、もう帰って来なければいいのに』って。そしたら、そしたら…………」
井荻沙織は、それ以上何も語らなかった。その先は、言われなくてもわかっていた。
井荻公介が死んだのは、妹である彼女がその不在を願ったからではない。彼女が公介を死へと追いやったのではない。彼女にはなんの責任もない。
公介の仏壇の前で、初めて彼女に出会った時、なんとも言えない深い眼差しで見つめられていたことを思い出す。彼女はもしかして、俺が現れたことでほっとしたんじゃないか。兄が死んだのは自分のせいではないのだと、そう実感できたんじゃないだろうか。
だがそれでも、こうして語るということは、彼女にはまだ、わだかまりがあるのだろう。願ってしまったことへの後悔は、いつまでも消えることがないのだ。
彼女の細い腕が静かに俺の背中に回った。ゆっくりと、しかし着実に、腕の力は強まっていく。泣くのかと思ったが、彼女は涙を見せなかった。それでも俺にしがみつくその手は、微かに震えていた。
溶けることのない氷の塊が、彼女の胸の奥底にはある。それは、決して触れることができない。どんな言葉も、そんな深いところまではきっと届かない。それでも何か、力になってやりたかった。おこがましいだろうか。俺が公介を死に追いやったのかもしれないのに。こうして一緒にいることが、許されるようなふたりではないのに。
俺はそっと彼女の身体を抱き返した。傷つけないように。嫌になったら、いつでも突き放せるように。そんな力加減で抱き締めた。こんな風に、誰かに優しくしようと思うことが、ずいぶん久しぶりだと感じた。
互いの体温に身を委ねているうちに、再び眠気に誘われて、氷が少しずつグラスの中へ溶けていくように、そうしてふたり抱き合ったまま、朝まで眠った。
「お疲れさん」
目の前に缶コーヒーを置いてやると、貝塚は驚いたように顔を上げた。
「縞本。お疲れ、今から帰るのか?」
そう言いながら自分のデスクから立ち上がろうとする貝塚を、俺は片手で制した。
「あとひと踏ん張りしようかと思ったけどな、もう今日はいいやって気持ちになっちまった」
「いいんじゃないの。縞本は働きすぎなんだよ」
そう言う貝塚も、ブースに残っている最後のひとりだった。フロアを見回してみたが、同僚たちはとっくに退社している。
こいつも、俺に負けず劣らずのワーカーホリックなのだ。おまけに、俺よりもヘビースモーカーだ。
「たらふく飲んで寝るよ、今夜は」
週明けの月曜日の朝は、先方への謝罪から始まるのかと思うと、それだけで気が滅入った。今夜くらいは、酒でも飲まないとやってられない。
「さすがの縞本も参ってるねぇ」
にやにやしながら貝塚はそう言って、俺がデスクに置いてやった缶コーヒーに手を伸ばす。
「井荻さんに癒してもらったら?」
「……は?」
わざとらしく訊き返してみたが、貝塚は嫌らしい笑みをより深くしただけだった。
「俺はお似合いだと思うけどなぁ。縞本と井荻さん」
「……何を言ってるんだお前は。アホか」
「井荻さんはまだ知らないんだろう? 縞本が春に九州に異動になること。内示しかされてないもんねぇ」
「…………」
「誘ってみたら?」
「……俺と一緒に九州に行こう、ってか?」
「そうそう。井荻さんもその気になるかもしれないし」
「……アホか」
俺は吐き捨てるようにそう言ったが、貝塚は缶コーヒーに口をつけながら笑っていた。その笑顔が妙に朗らかで、からかわれているのは明らかだった。無性に腹が立つ。
「万が一、彼女にその気がなくて関係が気まずくなっても、縞本は春にはいなくなる訳だから、少しの間の辛抱だし」
「何が言いたいんだ?」
「ローリスク、ハイリターンだよ、縞本。挑戦する価値はあるだろ?」
「…………アホか」
俺は片手を挙げて「お疲れさん」と告げ、営業フロアを後にする。「なんだよ縞本、俺はマジだぞ」と、後ろから聞こえてきたが、それ以上耳を貸すことはしなかった。
エレベーターを下り、建物を出ると、途端にビル風が吹きつけてきた。手袋を忘れて来たことを思い出し、コートのポケットに手を入れる。
すれ違う人たちは皆、急ぎ足で通り過ぎて行く。今夜は昨日よりも冷える。早く暖かい場所へ行こうと、誰もが思っているのだ。
暖かい場所。
俺はいつの間にか、彼女のことを連想していた。馬鹿馬鹿しい。自分でも恥ずかしくなる。これじゃあ、貝塚にからかわれても仕方がない。
そう言えば、今日彼女に会った時、俺が「行くのか」と訊いたら、彼女は「行きます」と答えたっけ。腕時計に目をやった。彼女はまだ、いるのだろうか。いつものバーに。
あれから、井荻沙織との関係は変わっていない。変わらず同じ会社で働いていて、ときどき一緒に酒を飲み、ときどき一緒に眠っている。だが恋人ではないし、しかし、ただの同僚と呼ぶには、いささか深い仲になりすぎた。
井荻沙織が兄の件について語ったのは、あの夜が最後だった。それ以来、彼女は兄の話をしていない。もしかしたらもう二度と、俺の前で口にすることはないのかもしれない。
彼女の胸の内にあるわだかまりは、今もそこにあるのだろうか。溶けることのない氷を、変わらず抱いているのだろうか。
俺は彼女に、何をしてやれるだろう。
あの暑い日に、彼女が渡してくれた一本のペットボトル。その冷たい感触を、今でも思い出すことができる。「本当は違うんでしょ」と告げられた時、本当はどんなに嬉しかったか。
誰かを傷つけ、自らも傷ついてばかりいた俺に、彼女は手を伸ばしてくれた。本質を見抜こうとでもするかのような眼差しで射抜かれる度、嘘をつかなくていいのは安堵できた。彼女の肌に触れ、彼女の指先が俺をなぞる時、今までの傷が癒えていくように思えた。俺は彼女に出会って報われた。その温かさに救われたのだ。
だが俺の手は、彼女を温めることができるのだろうか。
はたして、俺にそんな資格があるのか。
そんな生き方が、許されるのか。
「九州か……。遠いな…………」
思わず零れた独り言は、吹き荒ぶビル風に掻き消された。周囲の人々と同じように首をすくめ、背中を丸め、駅へ向かう道を歩く。雑草さえまだ芽吹かない、冷たいアスファルトを見下ろしながら、今はまだその足音さえも聞こえない、春のことを考える。
その春が来た時、俺はもう、この場所にはいない。
俺じゃなくてもいい、誰かが、彼女の傷を癒してやってくれればいい。彼女が救ってくれたように、代わりに誰かが彼女を救ってくれればいい。こんな冷え切った、硬く冷たい指先ではなく、もっと情熱的で献身的な、穏やかな熱量がある誰かが、彼女を抱き締めてくれればいい。
そうして、彼女が抱いている大きな氷塊も、いつしか溶けてしまえばいい。
だがもしも、側にいることが許されるのならば、その手を引くことが許してもらえるのであれば、俺はできうる限り暖かい場所へ、彼女を連れて行きたい。何もかもを忘れてしまえるような、まぶしいくらい陽の当たる場所へ。
だがそんなことは、つまらない夢にすぎない。
「アホだな、俺は……」
どうか彼女が、暖かい場所にいつまでもいられますように。
そんなことを願った。
そう願うことだけは、きっと俺にも許されるだろうから。
了
2 notes
·
View notes