#ウインクは嘘
Text
Crazy:B
youtube
こはくくんセンターおめでとう!!!かっこいいハロウィンすぎるし好きだよ!!!ナチュラルにウインクすんのやめなね^^?最後の顔も好きだよ!!!
youtube
最初が治安悪いお兄さん達って感じ。こはくくん可愛いねぇ、可愛い……(定期)クレビの歌でこれが一番好きかも、嘘ついたかも。でもそれくらい好き。
youtube
あ、嘘です!!!この歌が一番でした!!!!!まじで好き!!!最初のりんねとHiMERUがハイタッチみたいなのするのも好きだし、カメラアングルが好き!!!オラオラしてるのめちゃくちゃ良!!!キキララ組可愛い!!!足捌きがいい!!!(?)
0 notes
Text
【ボーイミーツガール4】
頂点を超え帰路に着く太陽が長い廊下を照らしている。
「この後は何処に行くの?」
アリスはまたもや無垢な目をして聞いてきた。
「んー。そうだなあ。授業も中途半端にサボってしまったし今日は煙草でも吸って帰って来たる戦に備えて準備に勤しむ事にしようかな。」
「私も喫煙所に同行して宜しい?」
「嫌煙じゃあ無いなら良いけど。」
「犬と猿じゃあ、あるまいし大丈夫だよ。」
「雉がいた頃は共闘していたのにな。」
「前後の時系列によって解釈が変わってきちゃうね。」
“そうだな”と、この空気に返事をして2つ並んだ影帽子は歩み始めた。
喫煙所に向かう途中でアリスは知らない女生徒の集団に声をかけられていた。
有り余る人望を振り撒いて歩いていればこんな顛末になるのは大いに予想出来たもんだが今日の俺には不可能である。
ごめんねとウインクをして詫びた後小走りでその集団の輪に打ち解けていた。
あっけらかんと遠くなる集団を眺めていたが自分には未だ山積みのタスクが残っていた事を思い出し足早に憩いの場へと向かう。
この時間の喫煙所は授業中ということもあってか人は居なかった。
寧ろ心の整理をするにはうってつけの場であった。
胸ポケットに入れたソフトパッケージを振って一本だけ飛び出させて口元に迎え火で燻す。
ふうと一息つくと肺胞を覆う煙に大層な満足感を覚える。
上の方を向いて煙を宙に舞わせる。
脳内が澄んできた頃、視覚外から突然声をかけられた。
吃驚して声が上手く出せず反応が遅れてしまったが視覚神経を辿って脳内に届いた情報はもっと反応速度を鈍らせるには過不足無かった。
何を隠そうとも目の前にはキサさんが立っていたからだ。
色んな言葉や感情がびゅんびゅんと駆け巡る。
人はソレを困惑と呼ぶのだと理解した。
困り果てている俺をよそにキサさんは再度“ライター貸して頂けませんか?”と言った。
喫煙所というフィールドでは他のスモーカーには何かの仲間意識からか何かをお願いされるとどうも断り難い。
実際、草臥れたお爺さんが若者に煙草の一本をせがむ様子を見た事が何度もある。
この様に俺には断る義理が何一つ無い。
増してや意中のキサさんだ。
「あ、どうぞ。」
「有難う御座います。」
ジッと砥石を回し火を付け終え直ぐに返してくれた。
ふうと息を吐いたのを確認してから俺は、こう尋ねた。
「どうしてそんなに他人行儀なんですか。」
「あら、バレちゃってた?」
「バレるとかの問題じゃあ無いです。何の迷いも無くキサさんだと認識出来ました。」
「そっかあ。流石だね。」
「如何してここに居るんですか。」
「如何してだと思う?」
「鸚鵡返しじゃあないですか。そうだなあ。偶然同じタイミングで居合わせたとか?」
「そんなつまらない理由じゃあないわ。退屈しちゃうでしょう?」
「全く見当も付きません。脳が完全に思考を放棄しています。」
「じゃあ秘密ね。」
「悪戯っ子ですね。幼少期の渾名は悪童とかでしょう?」
「残念だなあ。私これでも生徒会長とかやってるタチだったんだよ。」
「はあ。生徒達じゃあ飽き足らず学校もろともを支配していた訳ですか。」
「私は君が切望する様な母性は持ち合わせて無いよ。」
「増してや僕はチェンソーを持っていないのでママにもならないですよ。」
「古い漫画なのに知っていたの。流石だね。」
「凄いのはあの作品でしょう?何年経っても民間伝承のように言い伝えられているんだから。」
「それもそっか。有り余る寓話も誰かの創作な訳だからね。」
「そんなことよりもどうしてここにいらっしゃるのですか。この謎を解き明かさないと今日ご飯に集中出来ないと思います。」
「んーじゃあ教えてあげよっか。先ず手始めに私から質問しても良い?」
「何とでも訊いてください。それが答えに繋がるのであれば。」
「君はどんな恋愛を望む?」
「そうですね。いざ答えを出すとなると難しいですけど強いて挙げるなら劇的な恋がしてみたいですね。」
「そう言うと思った。君は知らないと思うけど劇的な出来事は必ず双方どちらかの能動が無ければ成立しないの。受動的に待っているとなあんにも世界は変わらないんだよ。」
「ただ、それとこれとがどう繋がるのかさっぱりです。」
「だから私からわざわざ会いに来てあげたんだよ。言わせないでよ、こんなこと。」
赤らんだ頬を持つ顔は綺麗であったが直ぐに煙に隠されてしまった。
「それはそうとどうするの?これから。」
「任せてくださいよ。わざわざ会いにまで来て頂いている訳ですし。」
どう足掻こうとも見切り発車の嘘だ。
実際問題、教授やアリスに訊いても理想的な答えは得られなかったからだ。
「頼りになるね。今日の私はなーんにも考えないからね。」
「取り敢えずゴブルにでも向かいましょうか。」
“うん”と相槌を受け取り根元まで火元が迫った煙草を消して大学から出た。
この大学からゴブルまではモノレールが通っている。
始発駅から終着駅へと向かうので道中は快適そのものだ。
自分でもびっくりしたが気がつけばゴブルに着いていた。
普段活発的では無い人が突如活発的になるとどうも身体が追いついてこないらしい。
初デートに寝てしまうのは心底申し訳なかったけど満更でもなさそうな顔して起こしてくれた。
電車からホームに降り立つ。
「寝ていてしまってすみません。」
「ううん。滅多にお目にかかれない貴重な姿を見れたから良しとするよ。」
「優しすぎやしないですか。」
「君こそ優しさに耐性でも無いの?」
「そんな事は無いと思うんですけど移動時間に寝ると大概、憤慨されるかなとお思いまして。」
「三大欲求は誰にも邪魔されたく無いじゃんかあ。」
「その思想、素敵過ぎますね。」
切符を投入口に投げ入れて駅構内から出た。
駅のホームからもそうだったがこの辺りは眠らない街と謳われるだけある。
人の数がうんと多くなる。
これだけの人に囲まれれば自分の存在がまるで思っていた程尊大なもので無いと気付かされる。
「ちなみに行く当てはあるの?」
「見栄ばかりで申し訳ないです。」
「君らしいなあ全く。」
「いや、今決めました。兎に角ついてきて下さい。迷子にならない様、手を繋いでて下さい。」
「繋いだその手は離さないでね。」
「任せて下さい。」
まるで花火大会の帰り道みたいなやり取りをして一心不乱に俺は人の波を縫って目的地へと向かう。
キサさんの手はほんのり冷たかった。
人盛りを抜けても言われた通りに繋いだ手を離す事は無かった。
この時間は永遠に続けと心底から願った。
その願望も虚しく直ぐに目的地が目下まで迫っていた。
店内の喧騒が外に漏れ出している。
勘の良いキサさんは“ここ?”と訊いてくれた。
「癪に触りましたか?」
「ううん。君が懸命に考えたデートなんだから私は満喫するよ。」
「ありがとうございます。楽しみましょう。」
そう言って赤い暖簾を潜った。
0 notes
Photo

今日もかけ小を注文しようと列に並んだら、揚げ物コーナーでAtuAtuの天ぷら各種の隣でKuttariしたコロッケ多数が目に入った。明らかに供給過多。(ったく、しょうがねぇなぁ)って心で呟いた俺は、自分の番がくると釜場のおばちゃんに「カレー小おねがいします」って元気よく伝え、ウインクしたよ。大人になったなと思う。ミランダジュライの言葉を少しだけ借りるなら「いちばんここに似合うコロッケ」って感じかな。ごちそうさま。#ウインクは嘘 https://www.instagram.com/p/CTtVgWuFMSc/?utm_medium=tumblr
0 notes
Text
2022/01/02
壽 初春大歌舞伎(ことぶき はつはるおおかぶき)
第三部
『難有浅草開景清 岩戸の景清』
(ありがたや はながたつどう あけのかげきよ)
『義経千本桜 川連法眼館の場』
(よしつねせんぼんざくら かわつらほうげんやかたのば)
■四代目の狐忠信が帰ってきた!
あけましておめでとうございます。
とてもラッキーなことに、新年の初観劇を歌舞伎座で迎えることができた。しかも、猿之助さんの四の切で。
ずっとこの時を待っていた。歌舞伎を好きになり、猿之助さんにハマったのは2017年の冬。あの大怪我をされた直後だった。初めて猿之助さんを「猿之助さんだ」と意識して生で歌舞伎座で観たのが2018年の初春大歌舞伎。白鸚さん、幸四郎さん、染五郎さんの三代襲名披露の公演で、寺子屋の涎くり与太郎で出ていらした。それから4年の間、スーパー歌舞伎ワンピース、黒塚と、復活を象徴するかのようなマイルストーンを次々打ち立てて、それでも、四の切だけはすぐには観る事ができなかった。もうそろそろ?と思っていた頃に、世界的パンデミックが起きた。今回の公演はその意味でも特別だ。感染対策の制約が緩和され、ついに子狐が観客の頭上を飛んで古巣に帰る。桜吹雪の中白い狐が宙乗りをする姿のイメージは、いつしか、猿之助さん個人の身体的な快復の証を越えて、全観客にとっての「復活」の観念そのものになっていたように思う。
■猿之助さんも、本当は人間ではないんじゃない?
欄干の上をツツツツと走り、欄間を抜け涼しい顔で正座し、新体操の種目かと思う程の驚異的な跳躍力を見せつける。人間そんなことできるの?というケレン味的要素への驚きを、しかし、親狐を慕う子狐のドラマが超えていく。
「さてはそなたは狐じゃな」 と詰められ、さっと姿を消したかと思うと、薄紫の美しい着物から真っ白で毛足の長い狐の衣裳に変わってささささと這い出てくる、その速度。早替わりは猿之助さんの代名詞、先月の”伊達の十役”も早替わりが見どころだったが、あれは「早さを楽しむ」余裕がこちらにあった。ところが狐忠信の早替わりはエンタメ的早替わりとは違う。怪異としての早替わりだ。怪異を目にした人に許される反応は、ただただ驚愕のみである。
静御前に切られかかり「そんなことされる覚えはないですゥ!」と口を尖らせてみたり、本物の忠信さんに不信がかかってしまって申し訳ない…と反省してみたり、鼓の音に耳を傾け”ん-むむ”と首を小さくふったり、義経の前で恐縮して階段の死角に小さく座ったりと、小動物的Kawaiiを炸裂させる猿之助さん。
そして、悪僧たちと舞うあの姿!なんて楽しそうなんだろう、なんて自由で、喜びに溢れているんだろう。あの笑顔、あのウインク!胸が痛い…もっかい観たい…。
ついに宙乗りになり、鼓を胸に抱きはしゃぐ子狐。その姿を舞台上から義経と静御前が寄り添い見守る。そんな二人の姿に、子狐の両親のイメージが重なっていく美しい幕切れ。
■静御前と(狐、あるいは本物の)忠信
義経の忠臣、佐藤四郎兵衛忠信(さとうびょうえただのぶ)。
『義経千本桜』は、「忠なるかな忠、信なるかな信」という言葉から始まる。最初に言葉があり、言葉は神と共に…と言うのは完全に的外れな余談になってしまうけれど、初演から大当たりで、その後数百年にわたって上演され続けている程の大名作の冒頭の文句なのだから、当時気鋭の作者たちが魂込めて書かなかったわけがない。そうして書かれた言葉に、神や霊が宿らないはずもない。
もしかしたら、狐が化けていない”本物の忠信”という男を理解することが、『義経千本桜』が観客に何を信じさせるために書かれたのか理解する手がかりになるのではと思う。そしてまた、義経の周囲に数多くいる人物の中から佐藤忠信を子狐が化ける対象として選んだ作劇の意図を、純粋に知りたいと願う。
モノホン忠信の居る時間は非常に短い。あんないい男なのにもったいない。なんか、スピンオフで「忠信の休日」とか、あと「忠信のお勤めルーティン」とか見たい。
源平の合戦を生き延びる程武勇に優れ、鎌倉から追われる立場に変わった義経にもブレずに忠義を尽くす信念の篤さ。そんなトップ・オブ・ザ・武士のような男に、いや、そんな男だからこそなのか、義経は自分の愛妾の護衛を言いつける。実際は狐忠信が代行したとはいえ、「兄貴は戦場で武勲を立てて死んだのに、俺は女のお守りかよ…」 なんて、モノホン忠信が不貞腐れるところを想像すると楽しい。あるいは、「兄さんみたいに人の身代わりになって死ぬのはしんどいし、こうして護衛しながらしずしず歩くのも悪くないよな。」なんて思う可能性もある。
そんなことに思いを馳せていると、自然「兄・継信が上司・義経の身代わりになったため、家族を失った忠信」 と 「両親が人間社会の行事のサクリファイスになったため、家族を失った子狐」の立場に相関関係があるのが見えてくる。このあたりが狐忠信誕生の理由のひとつかなと短絡的に考えてみたりする。
モノホン忠信を演じる猿之助さんの怜悧な眼光の鋭さ、あの眼が素敵。義経たちの会話を聞いている間の訝しがる顔つきも男前で見惚れてしまう。偽物忠信の詮議のためその場を立ち去るモノホン忠信が駿河・亀井を交互に睨み堂々と去っていく姿には、「俺は場当たりで適当な嘘は言わないからな」という男の矜持が滲み出る。ごく短い時間でこれだけの魅力、頼むからスピンオフしてくれよ。
そして雀右衛門の静御前。こめかみから頬にかけての血色感メイクがちょっと地雷メイクっぽくてバリ可愛い。
長旅を共にしてきた(と思っている)静御前は、モノホン忠信に対してとても気安くて砕けた感じだ。「途中でどこか行ったかと思ったら、私より先に来てたなんて!真面目な方、まだ世の中が戦場だと思ってるのね」とかなんとか、そういうフィーリングのことをおっしゃる(間違ってたらごめんなさい)。忠信が自分には覚えがないですと反論するも、取り合わず「チャラチャラ冗談言っちゃって~」と流す。やっとのことで再会した恋人のどフロントで何でそんな他の男といちゃつけるんだ…?と疑念が僅かながら生じるものの、その短いやり取りの中には、静御前と(狐の)忠信が道中でどんな関係を築いてきたのか、またモノホンの忠信とだったらそこまで仲良しにはならなかったろうなということを二重に思わせる要素が詰まっている。
狐忠信の正体を見破った後、おののきながらも子狐に情をかける様子、最後にはすっかり落ち着きを取り戻して義経を呼び寄せる物腰に、静御前という人の優しさ、情け深さ、知性が表れていた。
■A Little Fox in my Stomach
大舞台の前の緊張や、遠足の前の日の夜のようなソワソワ落ち着かない感じを英語で"Butterflies in my stomach”という。
猿之助さんの四の切を観て、私は殆ど何も手につかない。いつもあの子狐の姿を思い、考えてしまう。胸がきゅっと締め付けられるようで、お腹がモゾモゾする。舞台で観た子狐の精霊が体に入ってきて跳ねまわっているような。
人が皆「猿之助の四の切」を絶賛する理由が分かったような気がする。すでにおかわりチケットを購入したので、 次回はもっと予習して、忠信について考えつつ、狐の可愛さを存分に味わいたいと思う。
1 note
·
View note
Photo

[Kuroshitsuji Collab] 4★ Ronald Knox (Normal) Translation
第2話 これでも死神DIE
Chapter 2: I’m a Death God no matter how I may seem, DIE
CV: KENN
*Spoiler free: Translations will remain under cut
*Name will remain as my normal ( ラン )
あれから数日…-。
It was a few days after that.
私は今日も、ロナルドさんが元の世界に戻る方法を彼と一緒に探していた。
I was helping Ronald find a way back to his original world together today as well.
ロナルド「はあ~。今日も手がかり、ナシか……」
Ronald: Haa~ Nothing today either, huh...
ラン「……ですね」
Ran: ...So it seems.
私の横で、疲れた様子でロナルドさんが大きく伸びをする。
He stretched and shook out his shoulders beside me, seemingly exhausted.
ロナルド「先輩は今日も俺に調査押しつけて買い物してるってのにさ。 ま、あの化け物騒ぎも落ち着いたことだし、いいっちゃいいんだけど」
Ronald: Senpai pushed all the investigation work on me again today and went off shopping. Well, I suppose that’s fine and all now that all the fuss with the monsters has settled down.
(ロナルドさん、意外と真面目なんだよね)
(Ronald’s surprisingly serious about his work...)
(文句言いながら、毎日手がかりを探してて)
(He still searches for ways to return back to his original world even if he complains about it all the time.)
ロナルド「これってさ、後輩イジリってヤツだよね?」
Ronald: Isn’t this what they call bullying your juniors?
おどけたように肩をすくめる彼の様子がなんだかおかしくて、思わず笑みが漏れる。
Seeing him shrug his shoulders in a rather odd fashion made me snicker at the action.
ロナルド「あれ? 笑った? なんで? 今の、笑うとこ?」
Ronald: Huh? You just laughed, didn’t you? Why? Was that something to be laughing about?
意外そうに聞かれ、私は…-。
He asked, surprised. And I...
ラン「いえ、すみません」
Ran: Sorry, my bad.
ロナルド「ああでもキミ、笑ってた方がイイね! うん。断然イイんじゃん?」
Ronald: Ahh~ But having a smile on your face suits you better! Yeah, definitely much, much better!
ロナルドさんの弾けるような笑顔が、私の心を明るくす��。
The sudden bright smile that broke out on his face warmed my heart.
(ロナルドさんって、本当に楽しい人だな)
(He’s such a nice person, really.)
その場の空気を軽くしてくれる彼の笑顔は、とても心地よいけれど……
(His smile really lightened up the atmosphere and it was a very pleasant thing indeed, but... )
(でも…-)
(But…)
ふと、彼の職業のことを思い出す。
I suddenly remembered what this guy’s job was.
(最初に聞いた時は、耳を疑ったけど……)
(I honestly thought that I had heard him wrongly when he first told me about it…)
ラン「ロナルドさんは……死神、なんですよね?」
Ran: You’re...You’re a Death God?
ロナルド「そ! これでも死神DIE!」
Ronald: That’s right! I’m a Death God no matter how I may seem, DIE!
ロナルドさんは、飄々とした笑顔を浮かべてウインクした。
He winked at me, a soft smile playing at his lips.
(えっと……)
(Uh…)
私の想像する死神とはかけ離れた彼の明るさがまぶしくて、言葉を失う。
I was at a loss for words. He was a far cry from how I pictured Death Gods to be, what with how bright and cheery this guy seemed to be.
ロナルド「庶務課の女の子に考えてもらった決め台詞なんだけど……サムかった?」
Ronald: Hm...This was a catchphrase the girl at the General Affairs Department thought up for me but it fell cold, didn’t it?
ラン「いえ、サムイっていうか…-」
Ran: No, it’s more of a...
(ロナルドさんが死神……やっぱりピンとこない)
(I really just can’t picture him as a Death God...even if he really is one.)
ラン「死神って、人の命を奪うんですよね……?」
Ran: Death Gods take the lives of people, right…?
ロナルド「そうだよ」
Ronald: Yup.
(やっぱり……)
(Just like I thought.)
ロナルド「正確には、これから死ぬ予定の人間を審査して、魂を刈り取るのがオシゴト」
Ronald: Or in more correct terms, it’s our job to investigate people who are slated to die soon and decide whether we should reap their souls or not.
首を傾げる私を後目に、ロナルドさんはなお明るく笑う。
He turned to look back at me and laughed when I tilted my head to the side in confusion.
(想像していた死神とは全然違うけど、嘘だとは思えないし)
(It really is a far cry from what I thought Death Gods are but I can’t sense a lie either.)
ロナルド「で、俺は残業しない主義なんで」
Ronald: And I have a principle to not work overtime.
ロナルドさんがさらりと口にした言葉に、また耳を疑ってしまう。
I couldn’t help but to doubt what I heard again.
ラン「残……業……?」
Ran: Overtime…?
ロナルド「そう。マジ勘弁してほしいよね」
Ronald: Yup. I really don’t wanna be working those hours.
買い物客で賑わう街を歩きながら、彼は言葉を続ける。
He continued on as he weaved through the streets that were crowded with shoppers.
ロナルド「今回の件もさ、二人で1000人以上の魂を回収しなきゃなんないなんて……ありえないよね。 この世界は労働のホーリツ、ちゃんとしてる?」
Ronald: See, we’ve got this case we’re handling now that requires us to collect over a 1000 souls with just two people...It’s really unheard of. Say, are the labour laws of this world any better?
ラン「……」
Ran: ……
(命のやり取りなのに、まるで一般の会社の仕事みたいに話すなんて……)
(We’re talking about actual lives here, but he’s speaking as if it’s no different from a job in the office…)
(どんな世界なんだろう……)
(I really wonder what kind of world he came from.)
彼の言葉にただ驚くばかりで、私は何も言えなかった…-。
I could do nothing but keep mum as I reeled in shock from everything he just said.
つづく…
To be continued…
#夢100#yume100#translations#yume oukoku to nemureru 100-nin no oujisama#夢王国と眠れる100人の王子様#Otome#Ronald Knox#kuroshitsuji#Black Butler#KENN
15 notes
·
View notes
Photo

菅原りこさんのツイート: 皆さん こんにちは🤗 今日から『ウインクあいち』さんにて 罪のない嘘 愛知公演が始まります。 ウイルス対策をしっかりしつつ、今自分に出来ることを精一杯頑張ります✨ https://t.co/PJC3vJ4BD9
2 notes
·
View notes
Text
無印04(12歳)「今の頃に受けたイジメなんて、大器晩成型の俺にとって””緒戦””だ(赤き真実)、お前は必ずこーかいする、新しいケツゾクの頂点が[[[[��黒の真実]]]]を」グスッグス… 虐め加害者A(12歳)「情けねえなw大人になったお前は廃人だよww」虐め加害者C(11歳)「ケツゾクとか下ネタ…w」無印04(12歳)「グスッグス…いつか死を懇願するだろう…グスッ」
youtube
〜現在〜 元虐め加害者A「改めて謝る、悪かった。必ず償うと約束する、だからお前も大罪を償え」無印04「何が大罪だ、おまえだって負けてない‼︎お前だって同じだろ?同じじゃないか、馬鹿にしてからかってテストの点を晒して……その癖今更善人ぶって…一度でも、俺を友達だと思ってくれた事あんのかよ?(ぽろぽろぽろ)」彼は泣いていた 元虐め加害者A「その通りだ、何も言い返せねえ。でもさ、お前だって女の子を好きになった事あるのかよ。」無印04「…」元虐め加害者A「誰かに会話を楽しんで欲しい、それだけが目的なのに。恋するフリなんていらねえって」無印04「うっ……グス」元虐め加害者A「ある世界に行けるまじないをかけてやる、一番お前が人気者になれる世界に」
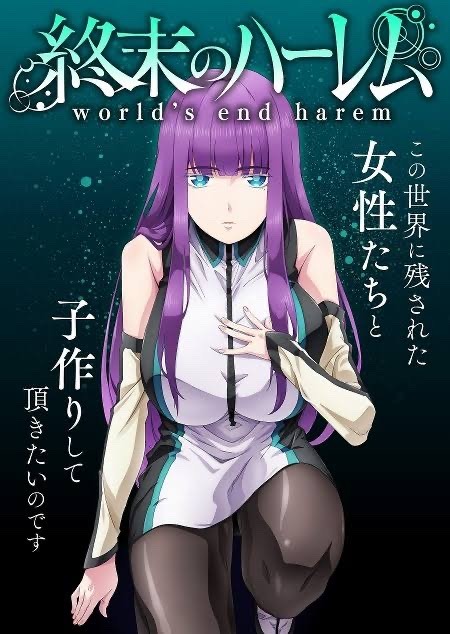
交信して話す異なる世界の5人 女性職員「異世界から一人だけ、そちらの男性を召喚出来るのです、冒険旅の卵を送るので相応しい有名人をお願いします」 一方通行「地平線世界の果てを目指して走っただけなのによお、どうしてこうなっちまったんだよ」ミハエル=ケール「俺はパス」球磨川禊「じゃあ僕が行く🎵」霧島狩魔「問題です、千個紛れた猛毒フェイクの内どれが本物でしょうか❗️」球磨川禊「君を警戒するのを怠って…」一方通行「やっちまった…」 ミハエル=ケール「お前が分かんねえとか言ったら…何もかも終わりだ……」霧島狩魔「あ、」



無印04「(話を逸らして…)お前の括弧はイカれてるぜw」 球磨川禊「いやいや、君の赤き真実よりマシだって…」 霧島狩魔「ムカ…オールフィクションの使い手!!」 球磨川禊「真っ赤な大嘘憑きと闇黒の真実のダブルパンチ野郎❗️」 霧島04「フールズメイトの天才!!!」球磨川禊「[[[人生存在ボイコット野郎❗️❗️❗️❗️❗️]]]」 霧島04「ギャグ補正でボコボコにされる前に死んでやる❗️ 猛毒卵!俺の命を持ってけドロボー❣️(バクバクむしゃむしゃ)」 異世界に召喚されます、目的地。終末のハーレム
四人「ゑゑゑゑゑゑゑゑゑ!!!!!」
「第一章、結局無印04が本物を当ててしまった」 霧島狩魔「変質者踊りを三日続けられなかったらエッチしてやる(o^^o)」 サキュバス「良いわよ〜❤️」 〜5時間後〜 霧島04「蝶のように舞い〜蜂のようにチンポを刺す男!ピュレグローマン!」 サキュバス「(イライライライライライラ💢)」 彼はまだ踊っていた 〜頭に来たサキュバスはとても熱い夜だったと、純粋硬派柱なんて嘘っぱちのプライドだと捏造した(他の女の子が泣くだけ、ていうか大火傷じゃ済まない。きっと未来はハンバーグ)〜 女の子D「私格闘技してるの、勝負してかったら…メイティングしてくれない?💜」霧島04「いいだろう(問答無用)」 バギャ❗️ボグボグゴギリ❗️‼️ 女の子C「ひ、人殺しーーッ」霧島04「いや、これは同意の上で…」 〜一ヶ月後〜 宇宙人の襲来に備えて大量の水素爆弾を””””エルンスト・フォン・アドラー様””””から輸入した霧島04 〜数日後〜 女の子A「霧島様ー何それ?」霧島狩魔「水素爆弾、落としたらみんな死ぬ」女の子B「ワイルドなんだね〜💛」抱きッ♪ 無印04「あっ」ツルッ⭐️
ボガアアアアアアア❗️❗️❗️
〜異世界端末の会話〜 ハーレム職員A「お前は人類を滅ぼすのはウイルスみたいな雑魚じゃなくて自分だって言いたいのか!?ハーレムを一体何だと思ってる?!?」霧島04「………鼻くそコレクションの完成と同じ位楽しい暇つぶし、腐ってしまうまでの儚い旬が、素晴らしいんだぜ(赤き真実・ザ・遠い目)」ハーレム職員B「」霧島04「皆んなにウインク❣️」パチっ☆ ハーレム職員C「(ブチッ)チクショーやってられっか!!辞めてやる!!!」霧島04「え…俺なんかした?」ハーレム職員D「だめだコイツ自分がどれだけイカれてるか全然分かってない(こんなにみんなが怒ってるのに……)、メイティング係は辞めて貰う!!ていうか…全部辞めてもらおうか!!!???」
元虐め加害者A「……何でこんな事したんだよ」無印04「お前だって同じだろうが(ニチャア)」それは本当の嘲り 元虐め加害者A「…」 無印04「いい奴になったら罪が消えるのか?タバコも吸う、お酒も飲む、暴力を振るった過去。そんな自傷、破滅的にお前を蝕む素晴らしい行いを責めてる訳じゃねえぜ(赤き真実) そもそもやらなきゃ良かったのに今更余計な懺悔に縋って…俺を何も知らないお前が……一度でも友達だと思ったことがあるのかよ」その真顔は暗黒の真実 元虐め加害者A「…お前をイジメた時だけはあんなに上手く行ったのに…なんで、こんな時ばっかり………」無印04「簡単だよ、それはお前らの魅力が最低で[[[暴力が最高だからさ]]]」

元虐め加害者A「”””あいつ”””と…同じ目だ…お前は産まれた時からクズだったんだな?、でも虐めの被害者なんかにしたのは間違いだった。償うのもやり直すのも全部間違いだったんだ。……俺の身勝手なエゴで女の子達をみんな死なせてしまった、もうお前の手で俺を殺してくれ」

“”””新種””””が持ってきたのは元虐め加害者BとCとDのハンバーグ
元虐め加害者A「無印04…お前こうなるって12歳の時から全て””””裏ストボス””””から知らされてたんだな❗️❓全部見抜いてたんだ。男達の夢を返せ、この悪魔❗️❗️❗️」霧島04「力があっても悪を振り翳すと、大体こうなっちゃうんだよ(赤き真実)」元虐め加害者A「こんな奴の余興の為にわざといじめられて…自分の青春すら””””悪””””に捧げて…負け犬が❗️ちくしょう……」
1 note
·
View note
Text
好きな人
一郎くんとまっすーが話しているのを、感慨深い気持ちで見ていたら、私が好きな人はみんな自分の気持ちや心をとても大切にしている人たちなんだなぁと改めてわかった。交わることのないと思っていた2人が、すごく気が合っている、わかり合っている、ファンとしてはとても堪らない光景だったけど、根本的に私が好きになる理由、みたいなものが共通しているだけなのかもしれないなと思った。ジャンルとか関係なく、人���として。
メディアでたくさんのものを見て、聴いて、膨大な表現の中から、ふと自分にぱちっと繋がる瞬間があったら、その人を深く知ってみたくなる、表現しているものを正座してちゃんと一度見てみないと、という気持ちになる。一郎くんに繋がった瞬間は、スペシャでアルバム発売の特番か何かで、曲についてのインタビューを受けているのを見た時。大概、このようなインタビューって、素人の私にはアーティストの言ってることがよくわからず、眠たくなったり、もやもやとしてしまったりすることが多かった。でも一郎くんは、歯に絹着せぬというか、なんのオブラートにも包まず、はっきりとした言葉で自分の気持ちを話していた。こんなアーティストがいるのか!と、内心びっくりして、その瞬間にこの人のことを知りたい!と思った。それから、どんどん好きになってサカナクションの曲を全て聴いて、ライブに行って、改めて実感した。あの時見た、真っ直ぐに自分の全部を表現する姿が、全ての表現の要になってるんだなと。だから、今でも、どんな表現をしてもサカナクションなら大丈夫、みたいな信頼感がある。手を抜くわけがないし、嘘をつくわけもないなって。
NEWSに繋がったのは、たまたま見た映像の中で、熱唱している4人の姿を見た時だった。
ジャニーズは、キラキラして、華麗にターンを決めて、カメラが来るとばっちりウインクを決めることのできる王子様。そういうイメージがやっぱりあった。でもその時みたNEWSは、カメラの方も向かず、髪を振り乱して、しゃがみ込んで顔も映らないような状態で心の底から熱唱していた。わたしは、その姿におもわずぽろっと涙がこぼれてしまっていた。自分でも、泣いてることに驚くくらい自然に溢れていて、心が揺さぶられた。そこから、もっと知りたくなり、DVDを買っていろんなライブをみたり、インタビューやトークでどんなことを考えている人たちなのかに触れて、かっこよくいるという事、アイドルでいる事にプライドを持っていて、その上で素直に自分を表現している人たちだと知った。だから、アイドルだということにプライドを持ってあの時熱唱していたんだと思うと、心の底からかっこいい人たちだ!と思った。
好きな人、ぱちっと自分に繋がる人は、そんなに多くはいないから出会う瞬間は嬉しいし、出会った後はその人たちの活動を見るのがとても楽しみだし、ファンでいるっていうのは決して依存ではなく、とても充実した、大きな意味での芸術鑑賞だと思うから、たくさん好きな人がいることは、幸せだなぁと改めて思った。これからも出会いたいし、好きな人がもっともっと面白いことをしてくれるのを、楽しみにしている。
0 notes
Photo

うちの店には、10歳の女の子の常連さんがいる。彼女は塩ラーメンのファンでいてくれている。880円の塩ラーメンを食べる為にお小遣いを貯めてたまに来店してくれる。先日、彼女が来店してくれた。いつものか?俺の問いに今日は何も食べないと答える彼女。どうして?と更に問うと、今日は募金しに来たと言われた。不思議がる俺に彼女が言った。医療関係者に100円でやってるんでしょ?私も協力したいから、2000円貯めて来たの。彼女は俺の活動を支援したいが為に、お父さんの肩揉みや、お母さんの手伝いでお金を貯めたらしい。10歳の子の2000円は大金だ。彼女に言った。おじさんは、貴女の気持ちに感動したわ。だから、ありがとう返しをしたい。おじさんとゲームをしない?首を傾げる彼女に提案したのは、右手左手どっちに箸立てが入ってるかということだ。彼女は負けて俺の提案を飲んだ。それは、ただで塩ラーメンを食べること。兄弟にデジカルビをお土産で3個持たせるということ。食事を済ませた彼女が帰り際言った。おじさんは嘘つきだ。さっきのゲーム。両手に箸立てを忍ばせてたんでしょ?鋭い、その通りだ。自転車に跨り彼女がウインクをした。また来るね。その言葉が嬉しかった。 (ぼうずママ) https://www.instagram.com/p/CBLhgnIAZ7ss7-5vUmDUCdgjikW-hH-8S6O-fE0/?igshid=1l8baw30ponoj
0 notes
Text
永い夜の瀬でぼくらは、
1
熱い湯が素肌を叩いて、眠気を醒ましていく。ハンドルを回してシャワーを止め、濡れた髪を無造作に掻き上げた。
浴室を出て、バスタオルで肌についた水滴を拭い、ドライヤーで髪を乾かし、質のいいワックスを使ってセットする。下着を重ね、クリーニングに出したばかりの白いニットに袖を通し、黒のジーンズを合わせた。
動くたび、鈍い痛みが微かに腰に走る。しばらく会えないからと言っても、これから長旅に出るというのに、あの男は容赦ない。
二年ほど暮らした、都心にそびえ立つマンションの高層階の一室も今日で見納めだ。泉の荷物はすでに向こうのホテルに送ったため、この部屋には手荷物以外、何も残っていない。カーテンから外を覗くと、十二月の空は分厚い雲で覆われ、昼頃になっても気温はさほど上がらないだろうと思われた。ジャケットを羽織る方がいいか、と考えながら、短針が八を指す腕時計を左手首につけた。
「……泉、」
不意に名前を呼ばれて、振り返る。目をこすりながら起き上がった男は、眠たげな声で尋ねる。
「もう出るの?」
「うん、」
「来て」
泉がベッドの側へ行くと、手を引かれ、キスをされた。
「たった二ヶ月離れるだけなのに、恋人の関係を終わらせるの?」
悲しみを宿した瞳を向けられ、泉は罪悪感を噛み締めながら、彼の寝癖を手櫛で直してやる。
「俺の気持ちは変わらないよ」
「……僕も、離れても泉を愛する気持ちは変わらない」
泉は彼の手を離した。彼は繋ぎ止めようとはしなかった。
「そういう優しいこと言ってくれる人ほど、離れていくんだよねぇ」
だから、ごめん。今までありがとう。そう続ければ、彼は諦めたように笑った。
手荷物だけを持って、泉は寝室を出る。その直前、彼が声を掛けた。
「泉、向こうでも元気で」
泉は微笑みを浮かべただけで何も言わずに、静かにドアを閉めた。
ロビーを出れば、真冬の朝の冷たい空気が頬を撫でる。
呼んでいたタクシーは路肩に停まって乗客を待っていた。後部座席に乗り込み、運転手に行き先を告げた。
「成田空港まで」
正午頃のフライトまでに時間があったため、泉はラウンジでカクテルを頼んだ。長いフライト中に睡眠を取るためだ。適度に酔っておけば眠れなくなる心配はない。
ちまちまとそれを飲んでいると、スマートフォンに着信があった。
朔間凜月、の名前に驚きながらその電話に出る。
「もしもし、」
「これからロンドン行きって言うのに、辛気臭い声だなぁ」
クスクスと笑う声に、泉は溜息を吐いた。
「くまくんが早起きなんてするから、こんなに天気悪いんじゃない?」
「嫌味は健在で安心安心」
「ぶっ飛ばすよぉ?」
そう言いながらも、昨日、気をつけてね、なんて言いながら泉愛用のパックを一ダースもくれたので可愛くないことはない。凜月はそういう男だ。
「で、なんでわざわざ電話なんて掛けてきたわけぇ?」
「昨日はナッちゃんもス〜ちゃんもいたから訊き損ねたから。ちゃんと振ったの?」
あいつのこと、と問われて、
「振ったよ」
とキッパリと返事をした。少しの沈黙の後、嘘じゃなさそうだねぇ、と間延びした声が返ってきた。
「俺にとってはやっとか、って感じだけどね。別れて正解だよ、あんな男」
凜月は、交際当初から泉の恋人————つい先ほど別れたが————二つ年上のカメラマンの男を嫌っていた。一度ふたりがエンカウントしたとき、凜月は目も合わせなかった。普段、自分とはそれほど関わりのない人物を嫌わない凜月にとって珍しいことだった。
泉はグラスを揺らした。オレンジテイストのカクテルが小さな波を立てる。
「……それを確かめるためにわざわざ?」
「そうだったら悪い?」
「な���でそこまで……」
「前に言ったでしょ、『王さま』が可哀想だからだよ」
その言葉に、カクテルを一口飲む。仄かな苦味が喉を焼く。
「……その呼び方よしなよ」
「じゃあ、『れおくん』」
押し黙った泉に、凜月が溜息を吐くのが聞こえた。
「ほら、こっちでも嫌がるじゃん」
「うるさいなぁ」
不機嫌を露わにしながら、泉は足を組み直す。
「……あいつの話ももうよしてよ、何年前のことだと思ってんの」
「二年前」
と正確な数字を出してくる男に舌打ちをすれば、
「怒んないでよセッちゃん」
悪気のなさそうな声がして、少し間が空いた。
「……それだけだから。じゃ、気をつけてねぇ」
泉は、うん、と小さな声で返事をした。
「お土産よろしく〜」
そう言葉を残して、凜月は電話を切った。スマートフォンを耳元から離し、ポケットに入れ、カクテルを一気に飲み干す。苦味が喉を通り、真っ逆さまに、胃に落ちていく感覚がした。
搭乗案内のアナウンスが響く。泉は席を立ち、搭乗口へ向かった。
◇
瀬名泉は、夢ノ咲学院を卒業後、進学をせずにモデルの道を選んだ。ありがたいことに、卒業前から大手芸能事務所から声が掛かり、所属先には困らなかった。キッズモデル時代、学生時代の知名度もあり、期待の新人モデルとして優遇されることが多かった。
現に、世界的に有名なイギリスのブランドの広告塔に選ばれた。日本人初の快挙に、日本のファッション界隈はその話題で持ちきりだ。泉は、これから約二ヶ月間、撮影やショーへの出演のためにイギリスのロンドンで生活し始める。
それをきっかけに、約二年間付き合った男に別れを告げた。
カメラマンの彼は、紳士的で、穏やかで、素の泉を理解してくれる数少ない人物のひとりだった。その上、カメラマンとしての腕も良く、国内の賞を総ナメにしていた。だから、付き合ってほしい、と言われても嫌な気はしなかった。いいよ、という一つ返事でふたりは後藤が元々住んでいたマンションの一室で生活を始めた。
彼のなにが嫌で別れたのではない。ただ、自分はこの男を愛しているのだろうか、と自問しても、答えは出てこなかった。
————泉、愛してる。
彼の腕に抱かれながら、そう囁かれても、泉はいつもなにも言えなかった。
ありがとう、とか、俺もだよ、とでも言えばいいのに、その言葉たちはいつも浮かんでは消え、声ではなく吐息となった。
優しくて、穏やかで、料理もキスもセックスも上手いのに、泉は、最後まで、彼を愛せなかったのだ。
2
着陸を知らせるアナウンスの声で、浅い眠りから目が覚めた。分厚い窓の外を見れば、夕方の空とコンクリートの地面を、滑走路の端が隔てていた。
飛行機はゆっくりと着陸し、人々は荷物を持って立ち上がる。彼らに続いて、泉も飛行機を降りた。
広いロビーには多くの人がいた。出発を待つ人、誰かを迎えに来た人、荷物を取りに行く人。みな足早にロビーを歩いていく。
泉は入国審査を待っている間に、すでに数日前に入国していたマネージャーに連絡をしておいたため、すぐに落ち合えた。
「泉、お疲れさま」
泉のマネージャーは、四十歳手前の女性だ。テキパキと仕事を捌き、ハキハキとした物言いで泉との相性は良い。
「お疲れさまです」
「タクシーでホテルに向かうけど、何か食べる?」
「いや、まだ大丈夫」
そう、と彼女は返事をして、タクシー呼んであるから、と泉のスーツケースを引いて歩き始める。彼女は結婚して十年の、テレビ局のプロデューサーの夫がいるが、子供はいない。だからなのか、彼女は泉を自分の息子のように接するし、泉はそれが嫌だというわけではなく、むしろ心地良かった。
タクシーの後部座席に乗り込むと、マネージャーは流暢な英語で目的地を告げた。
ホテルには一泊し、その次の朝には、これから暮らすスタジオフラット、いわゆるワンルームマンションに移動した。中心地近くに建つ赤茶色の壁のフラットに、泉とマネージャーは一部屋ずつそれぞれ借りた。撮影からコレクションを二ヶ月かけて全てロンドンで行われるため、ホテルに長期宿泊するよりも賃貸の方が安上がりだという理由からだ。
「ブランド側との顔合わせは明後日だから、それまでに時差にも慣れてね。八時頃、一緒に夕食でもどう? 近くに美味しい店を見つけたのよ」
「うん、行く」
マネージャーに言われて、高校時代の頃と食生活は少し変化した。サプリメントに頼ることもほとんどなく、バランスの良い食事を三食しっかり摂ることを徹底している。
彼女は、泉より一つ上の階に上っていった。その後ろ姿を見送って、泉は受け取った鍵で自室の玄関扉を開けた。
小ぢんまりとした部屋だったが、家具は全て揃っている。ベッドの側のドアの先は、床が青いタイル張りになっているトイレとシャワールームだった。
悪くない、と思いながら窓を開けた。夜の冷たい空気が部屋に入り込む。
それから絨毯の上でスーツケースを開け広げる。その他の生活用品はこっちで買えばいいと考えていたため、中身は洋服ばかりだ。それらを備え付けのクローゼットに移し、同じく備え付けの電化製品たちがちゃんと動くか確認した。テレビでは夕方のニュースが流れていた。
近所を散歩でもしようとまた外に出る。聞いていた通り、ロンドンの気温は低い。日本の十二月は、これほど寒くないはずだ。
若いカップルが寒さに肩を寄せ合いながら、泉の横を通り過ぎた、そのときだった。
泉より少し先を歩く、その背中。
車のタイヤがコンクリートの地面と擦れ合う音も、ざわめきとなった人々の話し声も足音も、膜をかけたかのようにくぐもって聞こえた。
ハーフアップにまとめられたあの長い赤毛、立てたコートの襟、軽快な歩き方とその歩幅と足音、すべてが、懐かしく感じた。
気づいたときには走り出してその背中を追いかけていた。
「待って!」
ぐい、と腕を引いて、振り向かせる。ゆらり、とエメラルドの中の光が揺らいだ。
目の色形も、手の大きさも、高く小さな鼻も、間違いなかった。この目の前にいる男は———……。
「……れおく、」
「Who are you?(おまえ、誰だ?)」
その声もレオのものにそっくりで唖然とした。だから、その喉から発されたのが流暢な英語だと気づくのに数秒かかった。
————れおくんじゃ、ない。
そう理解して、慌ててその手を離して謝った。
「Oh,I’m sorry. I thought you were someone else.(ごめんなさい、人違いをしました)」
彼は驚いたように目を見開いてから、ゆっくりと微笑みを浮かべた。
「……英語も話せるのか。さすが日本が生み出したモデル界の新星、イズミ・セナ、だな」
日本語でそう、はっきりと自分の名前を発音され、泉は目を丸くして彼を見つめた。
「……俺を知ってるの、」
「知ってるよ、ファッション業界は君の話題で持ちきりさ。こっちのブランドの広告塔をするって噂には聞いてたからなぁ。まさか本物に会えるなんて嬉しいよ」
レオの声なのに、話し方は似ても似つかない。大きな違和感を咀嚼しながら、差し出された手を握り返した。
「おれはレナード。日系のイギリス人だよ。これも何かの縁だ、どうぞよろしく」
「よろしく……」
彼は屈託のない笑顔を泉に向けた。
「そんなに似てたの?」
黙って頷けば、彼は緑色の瞳を細めた。
途端、息苦しくなって目の前が真っ暗になった。
ぐらり、と傾いた身体を彼が支える。
セナ、と呼ばれた気さえして、泉は参ったなぁ、と思いながら、瞼を閉じた。
次に目が覚めた時には、泉は見知らぬ部屋の天井を見つめていた。身体は痛まない、背中越しに感じる柔らかな感触に、自分がベッドの上に横たわっているのだと理解する。
「……気がついた?」
そう声がして、泉は上半身を起こした。そこにはマグカップを二つ持ったレナードがいた。そのうちの一つを泉に差し出す。
「ホットミルクだ、飲めるか?」
「ありがとう……」
微かな甘みが乾いた口の中に広がり、泉の意識を鮮明にさせる。レナードは、ベッドサイドの小さなテーブルに自分のマグカップを置き、ベッドの端に腰掛けた。
「急に倒れたから驚いたよ」
「ここは……?」
「俺のバイト先の休憩所。仮眠を取るためにベッドが備え付けられてるんだ」
「あんたが運んでくれたの、」
「うん」
泉も、彼に倣ってマグカップを置いた。
「ごめん、なさい。迷惑かけて、」
「謝ることない。寝不足か、貧血だろ。飛行機で眠れなかったのか?」
「まぁ、うん……」
いつもなら熟睡できるのに、今日は違った。意識はいつまでも泉のそばにいて、機内のざわめきや外から聞こえる微かなエンジンの音に鼓膜と神経が震えて眠りに身を委ねることが上手くできなかった。
ふと、窓の外に目を向けて、夕食の約束を思い出した。
「ねぇ、今、何時か分かる?」
「今? 六時半過ぎだけど」
その答えに、ほっと息を吐く。一度自分の家に戻ることはできそうだ。が、しかし、
「まさか、俺、一時間もここにいたってこと……?」
「まぁ、そうだな」
さらっと答えた彼に、泉はさらに罪悪感を覚えた。
「本当にごめん。いろいろとありがとう。またお礼をさせて」
と言いながら、泉は立ち上がる。
「もう行くのか?」
「うん」
と頷くと、彼は一度部屋を出て、泉の着ていたジャケットを手渡してくれた。それに袖を通す泉の横で、彼も上着を羽織り、鍵を尻ポケットに入れていた。
「ちなみにどこまで? 案内するよ」
「そこまでしなくても……!」
「おまえ、道分かんないだろ」
気絶してる間に運ばれてきたのだ。ここがどこだか、泉はもちろん知らない。
「……ごめん、ありがとう」
そう言えば、彼は、「いーえ」と無邪気にはにかんだ。それは、少しばかり彼を幼く見せた。
出会ったばかりの素性も知らない男に助けられ、その男とふたりきりの部屋で一時間も死んだように眠り、そのうえ道案内までしてもらうなど、我ながらどうかと思った。
しかし、彼があまりにも昔の恋人に似ていたから、悪い人じゃない、と思ってしまったのだ。
泉は彼の半歩後ろをついて歩いた。狭い階段を降りると勝手口があり、人気の多くない路地に出た。そのドアの鍵を掛ける彼の背中に話しかける。
「レナードさんは、」
と言いかければ、
「レナードでいいよ」
と口を挟まれ、レナードは、と言い直す。
「仕事はなにしてるの、」
「アルバイトだよ、今はこのバーで働いてる」
「なら、どうして俺を知ってるの。自分で言うのもなんだけど、俺はファッション業界では話題に上がるだろうけど、ロンドンにいる一般人で俺を知ってる人はまだ少ないでしょ」
仕事を終えた鍵を再びポケットにしまい、今度は胸ポケットから煙草とライターを取り出した。吸っても?と尋ねるように片眉を上げた彼に、どうぞ、とだけ返事をする。彼は煙草の先に火を点けながら、にやりと笑った。
「いいね、『まだ少ない』ってところにおまえの自信が見える」
答えを急かすように泉が肩を竦めれば、レナードは細い路地を出た。夜の街はどこの国も賑やかだ。ほろ酔い気味の男女が楽しそうに笑いながら、ふたりの横を通り過ぎていった。
「この町はブティックが多いから、おれが働いてるバーも、デザイナーやモデルたちの御用達なんだ。プライベートな話はもちろん、仕事の話も嫌でも聞こえてくるってわけ」
「へぇ……」
「また飲みに来いよ。安くしてやるから」
「ありがと」
「あ、でも気をつけた方がいい」
急に声色を変えた彼の目線を辿ると、体格のいい男ふたりが、手を繋いで、またちがうバーに入るところだった。
「おれの働いてるところも、いわゆるゲイバーってやつだから。まぁ、ストレートも大歓迎なんだけど」
レナードは泉の方を見て悪戯っぽく笑った。
「おまえは綺麗だからさ。狙われやすいよ」
「……レナードもその気があるの?」
率直に尋ねれば、レナードは、
「俺はバイだよ」
とウインクした。
夕方、泉が倒れた場所で別れた。レナードは、自分の働くバーのカードを手渡した。泉がそれを受け取ると、
「Good night,sweet dream!(おやすみ、いい夢を!)」
と手を振って、電飾が輝く繁華街の方へ歩いていった。長い赤毛が靡くのを見て、泉は彼と逆方向へ歩き出す。
カードには店の名前と住所が記されていた。その下には「Homosexuals and heterosexuals are also welcome!(同性愛者も異性愛者も大歓迎!)」と綴られており、レナードの言葉は本当だったのだと知る。
このカードを見たら、マネージャーはまた呆れるに違いない。彼女には一度、男とキスしているところを目撃されたことがあるのだ。
3
夢を見た。
雪に包まれた、白銀の世界だった。
広いグラウンドに積もった雪の上で、彼は笑っていた。
セナ、と呼ぶその男に、泉は手編みのマフラーを巻いてやる。赤い毛糸で編んだそれに、彼は嬉しそうに顔を埋めた。
————おれはね、セナがだぁ〜いすき!
————おまえが一緒にいるなら、おれは幸せだから。
————あいしてるよ、セナ!
無邪気な笑顔と、まっすぐな言葉が遠のいていく。
いつのまにか、粉雪は、身体を叩きつける吹雪になって��た。
————もう、終わりにしよう。
赤いマフラーが風に吹かれて、彼の首から離れていく。
音にならない声で、彼の名前を呼んだ。
マフラーが、彼の姿が、雪にまみれて、消えていった。
◇
「Nice to meet to you,Mr.Sena.(はじめまして、瀬名くん)」
打ち合わせの場所であるロンドン市内のスタジオで待っていたのは、ブランドのプロデューサーとスタッフたちだった。
「Nice to meet to you,too.(はじめまして)」
握手をしながら、プロデューサーの男性は泉の顔をじっと見つめた。
「You’ve got beautiful eyes.(とっても綺麗な瞳をしているね)」
「Thank you.(ありがとうございます)」
彼は人好きの良い笑みを浮かべ、泉とマネージャーに席に座るように促した。
テーブルの上に広がった書類、椅子の後ろに並べられた真新しい服たち、誰かの香水の匂い。
通訳を交えながら、泉とブランドスタッフは話し合いを進めた。撮影のこと、コレクションのこと。すべてが新鮮で、泉の胸は高鳴った。
打ち合わせの最後に、プロデューサーは嫌味のないウインクをしてみせた。
「I’m counting on you,Izumi.(期待してるよ、泉)」
その言葉に、泉は頷いた。
「I’ll do my best.(頑張ります)」
打ち合わせが終わった後、スマートフォンを確認すると、レナードからのメッセージが入っていた。
『一緒にディナーでもどう?』
その誘いに嫌な気はしなかった。先日のお礼もしたいし、と思いながら、
『七時以降なら』
と返信した。するとすぐに既読の文字がついて、
『終わったらおれの店に来て』
と新しいメッセージがその下に浮かんだ。
ねぇ、という泉の声に振り返ったマネージャーに尋ねる。
「この後は仕事入ってないよね」
「ええ」
彼女は泉の手の中のスマートフォンを見て、驚いたように瞬きした。
「もう知り合いができたの?」
「まあね」
「スキャンダルはやめてちょうだいよ」
念を押されてしまった泉は苦笑いしながら、
『分かった』
とだけ打ち込み、送信した。
◇
街はクリスマスソングに溢れ、電飾が輝いていた。
ソーホー地区では、同性カップルたちが楽しげに腕を組みながら、店に入っていく。
その後ろ姿を見送って、泉はマフラーに顔を埋めながら、足早に歩いた。
スマートフォンのマップに頼りながら、レナードが働く店に辿り着く。店の灯りは点いていない。そのうえ、店のドアには『CLOSED』のプレートが掛かっていた。
レナードはまだ来ていないのだろうか、と思いながらドアと睨めっこする。泉の後ろを、カップルたちが笑いながら通り過ぎていった。
それと同時に、バーとその隣の店の間の路地からの入り口から、レナードがひょっこりと顔を出した。
「Good evening,Izumi.」
彼の笑顔に、泉は肩の力を抜いた。
「店長が風邪ひいて臨時休業なんだ。裏から入って」
レナードについて、裏口から店の中に入る。
スタイリッシュな店内は、他のバーとはなんら変わらなかった。レナードに促されて、泉はカウンター席に腰掛ける。
「なにが食べたい?」
そう問いながら、レナードはエプロンの紐を腰の位置で蝶々結びにし、髪をポニーテールに結った。
「お任せする」
そう言えば、彼は少し困ったように眉を下げて笑った。
「お任せか〜」
彼は奥の厨房に入っていった。
店の中は見た目の割に広く感じた。テーブル席もあり、その奥には小さなステージがあった。ここで酔った客たちが歌うのだろう、と思った。
「今日は仕事だったのか?」
と厨房からレナードが尋ねた。
「そう」
と少し大きめの声で返事をする。ジュー、となにかを焼いているような香ばしい音がした。
「ロンドンコレクションに出るのか?」
「まあね」
「さすがだなぁ」
彼の感心したような声に、泉は少し誇らしく思った。
世界四大コレクションの一つであるロンドンコレクションは、一ヶ月後に行われる。それに泉は出演する予定になっているのだ。泉にとって、今までで一番の大仕事だ。ここで結果を残せば、瀬名泉という名は世界に知られることになる。
しばらくして、レナードが完成した料理とともに厨房から出てきた。
ミートパイとチップス、トマトサラダのセットだった。
「ワイン飲む?」
と訊きながら、レナードはセラーからボトルを取り出す。
「明日も仕事だから一杯だけね」
グラスに注がれた白ワインが煌めいた。ふたりでグラスの縁を合わせれば、チン、と軽やかな音が響いた。
「ふたりの出会いに」
「クサいセリフ、」
「ロンドナーだからさ」
ふたりは笑いながら食事を楽しんだ。
レナードが作ったディナーはどれも美味しかった。頬張る泉を見て、レナードは嬉しそうに笑った。
食事を終えると、レナードは煙草に火をつけた。彼が換気扇のスイッチを切り替えると鈍い音を立てて、どこにあるか分からない換気扇が回りだす。
「イズミ、」
少し酔いが回ったらしいレナードが、蕩けたような瞳で泉を見つめる。
その甘い表情に、泉は息を呑んだ。
「歌ってよ」
「……そんなとこまで知ってるわけ」
「おれの情報網をナメてもらっちゃいけないなぁ」
腕を引かれ、ステージの目の前に立つ。小さな円形のス��ージの中央には、スタンドマイクが待っていた。
聞き慣れた音楽が天井についたスピーカーから流れ出す。ピアノをメインにしたバラード。学生時代に所属していたユニット————Knightsの曲だった。
泉はレナードの方を振り向いて、静かに言った。
「……俺に、歌う資格なんてない。俺はアイドルじゃない。今歌ったら、あいつら……昔の仲間に、失礼だから」
"アイドルの瀬名泉"は、もうどこにもいなかった。瀬名泉を"アイドル"としてたらしめているのは、レオと凜月と嵐と司と、レオが作った曲だった。それらを失った今、泉は"モデルの瀬名泉"として生きるしかないのだ。
レナードは驚いたように見開いた目を二度瞬き、申し訳なさそうに眉を寄せた。その表情には、先ほどまであった酔いはなかった。
「……そうだよな。無理言ってごめん」
泉は慌てて首を横に振った。泉のわがままを、レナードが知る由もないのだ。自分の言葉に後悔した。
「……でも、」
そう言葉を続けたレナードに、泉は顔を上げた。
「おれは、悲しそうな顔をしてるおまえを、楽しませることはできるよ」
まっすぐな瞳に、泉は息を吐いた。懐かしいピアノのメロディーが、よけいに切ない。
レオにそっくりで、そしてレオではないこの男にだけは、言ってもいい、甘えてしまいたい、と思った。どうせお互い酔っているのだ。明日には忘れているかもしれない。
溢れそうになる涙を乱暴に拭って、喉に絡む言葉を吐き出した。
「……本当に、大事な人がいた。でも俺は、二度もそいつを守れなかった……ううん、二度も、傷つけてしまった」
滲む視界の中で、レナードはじっと泉を見つめ、泉の声に耳を澄ましていた。
「……俺は、強くなるために、ここに来ることを選んだ。自分を変えるために。もう二度とあいつに、あんな思いをさせないために。あいつに、見つけてもらうために」
レナードはゆっくりと泉に近づいた。
「触れていい?」
と問われ、その指が濡れた頰を拭う。
「……おまえなら大丈夫だよ、」
その言葉も、その眼差しも、目がくらむほど眩しくて、あぁ、レナードも強いのだ、そう、思った。
4
なぁ、セナ、そう呼びかけられて、なぁに、と振り返る。楽譜が散らばった床の上に寝転び、その右手を動かし続けていた。
夕焼けの色に染まった窓の向こう側で、カラスが鳴いた。
「……おれがいなくなったら、どうする」
その問いに、泉は答えを見つけることなどできなかった。そんなことを想像したくなかった。
レオは仰向けになって、楽譜を片手に立ちすくむ泉に、力なく微笑んだ。もとも細い身体がさらに細くなっているのが嫌でもわかる。
「こっち来て」
レオの頭の方にしゃがむと、レオの左腕が首の後ろに回される。そしてそのまま引き寄せられて、唇を重ね合わせた。顎の先にレオの柔らかな前髪が触れた。
「……セナ、愛してるよ」
————そんな悲しそうな表情で、そんな優しい言葉、言わないでよ
掠れた声は喉の奥に張り付いて音にはならなかった。ただそこから微動だにせず、泉の喉を絞めるのだった。
その後、レオは本当にいなくなってしまった。取り残された泉は、夢の残骸を拾い集めて足掻き続けることしかできなかった。
戻ってきたレオと日々を重ねても、レオに対する罪悪感と後悔が、時間の経過によって消えるはずがない。今でもそれらに苛まれる夜もある。だからといって、償いとして献身しているわけではない。
ただ、ただ純粋にレオのことを愛しているから、彼のそばにいた。泉の気持ちにも、ふたりの関係性にも、名前などつけられないのだった。
卒業後すぐに上京し、泉とレオは、さほど広くない郊外のマンションの一室で暮らし始めた。
レオから手渡された部屋の鍵は冷たかった。握りしめているうちに温まって、金属独特の匂いが右の掌に染み付いてしまったけれど、それさえも気にならなかった。
「一緒に、暮らそう」
泉に拒否権など最初からなかった。いつもそうだ。声色も言葉も優しいのに、その瞳に宿された光に、泉はいつも逆らえなかった。
一緒に食事をし、風呂に入り、ダブルサイズのベッドに潜った。
たまにセックスもした、次の日がオフでも、オフじゃなくても。レオが泉の背筋や頸に指を這わせるのは、しよ、という言葉の代わりだったし、たまに泉から誘うこともあった。
レオは、泉をほぐすように優しく抱いたり、肉食獣のように激しく抱いたりもした。彼はキスもセックスも上手だったが、途中で曲を書き出すのはさすがに勘弁してほしかった。
その頃が、一番幸せだったのだと、今になって気づく。
二年前のある寒い冬の日の朝、レオは忽然と、泉の前から姿を消したのだった。
同じベッドで寝ていたはずのレオの姿はなく、彼の服も、靴も、食器も楽譜も消えていた。窓の外で降る雪がコンクリートの地面に触れる音が聞こえそうなほど静まり返った部屋に、心臓がドクドクと脈打っている。
スマートフォンを手に取ると、その液晶画面に『留守番電話に一件のメッセージがあります』という通知が浮かんだ。発信元は非通知だった。恐る恐るそれをタップし、音量を上げる。
機械的な音声案内の後に、ピー、と甲高い音がなる。少しの沈黙、そして、微かな雑踏と、聞き慣れた声がスピーカーから溢れてきた。
「……セナ、急に出ていってごめん。でもいつか、この関係も終わりにしようと思ってた。セナも、その方がいいだろ?ごっこ遊びはもうおしまいだ。おまえとはもう会わない。じゃあな、元気で」
メッセージの終了を告げる機械音が鼓膜を震わす。
冷たいスマートフォンを握ったまま、泉は身動きできなかった。
そのメッセージは、つまり、ふたりの間にあった関係に終止符を打つもので、レオはあっさりと泉の傍を離れてしまった。昨晩だってあんなに優しく泉を抱いたのに、所詮それは演技にすぎなかったのだ。そんなことを信じたくないし、信じてもいないけれど、ただ、レオがふたたび泉のそばからいなくなってしまった、ということだけが事実として残った。
いつから、どうして、という疑問が浮かんでは消える。そんなの直接言いなよ、という怒りを覚えて、どこが悪かったの、と問い詰めたくなる。
————ちゃんと愛してるってれおくんみたいに言葉で伝えれば良かったのかな。きっと、俺の愛は、れおくんに、伝わってなかったんだ。
悲しみも怒りも虚しさも悔恨も、すべてをぐちゃぐちゃに掻き混ぜてできた感情が喉の奥から迫り上がり、泉はベッドに飛び乗って枕に顔を埋めた。涙と嗚咽がひとりの部屋に響いたのが、滑稽で、無様で、哀しくて、泉は声を押し殺して泣いた。
レオのいない部屋はひどく寒くて広く感じた。
ふたりぶんのうち、ひとりぶんが消えた。
レオがいなくなってしまった。
実感が湧かないまま、食事も取らずに仕事に没頭していた。あっという間に減っていった体重にも、なんとも思わなかった。
そして、とうとう撮影現場のスタジオで倒れた。その頃のことはよく覚えていない。ただ、目を覚ますと楽屋のソファーに横になっていて、そばにはカメラマンの男がいた。
「気がついた?」
その優しい声色に、勝手にレオを重ねていた。
だからその出来事の数日後、一緒に洒落たバーに行ったとき、告白されて嫌な気はしなかった。いいよ、とだけ返事をした。
彼の住むマンションは都心にあり、主に泉の撮影現場となるスタジオにも近かったため、ほとんど同棲状態になった。
彼は写真の腕ももちろん、優しく紳士的で、料理もキスもセックスも上手かった。
それでも、レオを失った虚しさはいつもどこかにあった。泉はたびたび留守番電話に残された彼の声を聞いた。
いなくなったあの日から、レオのスマートフォンに何度も電話を入れた。しかし、聞こえるのは無機質な自動音声だけだった。
カメラマンの男といても、考えるのはレオのことばかりだった。
れおくんだったらもっと乱暴にしてくれるのに、優しくしてくれる���に、笑い飛ばしてくれるのに。
触れ合う肌がレオのものより冷たいことに、泉は泣きたくなった。
泉が求めているのは、レオだけなのだ。
◇
カメラマンの男と付き合い始めて二ヶ月。運の悪いことに、彼と一緒にいるところを同じスタジオにいた凜月に目撃され、強引に個室のあるレストランに連れて行かれた。
赤ワインとトマトサラダを頼み終え、店員が個室から出て行くと、凜月は泉に向き直った。
「……あのカメラマンと付き合ってんの?」
凜月は心底嫌そうな顔をしながらそう訊いた。そうだよ、と答えるとますます嫌悪感を露わにした。
「『王さま』はどうしたのさ。最近急に見てないし連絡も来てないけど」
先ほどとは違い、泉を咎めるような声ではない。
「……その呼び方よしなよ」
「あぁ、ごめん。もう大人だもんね、じゃあ、れおくん」
本当に意地の悪いガキだと思いながら、目の前の男を睨む。ほら、と凜月が促したところで店員がやってきてグラスと赤ワインのボトルを一本置いていった。
凜月は黙って二つのグラスにワインを注いだ。その色は、凜月の瞳と同じだった。
「……れおくんが、」
この先の言葉を、続けたら。そう考えると唇が震え、喉が締め付けられ、声が出なかった。
言って、と凜月が柔らかな声で宥めた。泉はグラスを傾けて、アルコールを胃に流し込んだ。それを終えたと同時に、 小さな声で絞り出すように呟いた、
「……れおくんが、いなくなった、」
大きく息を吐くと、アルコールの匂いが嫌でも分かった。
凜月は、真紅の瞳を泉に向けた。
「探さないの、」
そう言いながら、泉のグラスに赤ワインを注ぐ。それをまた飲み干す。だめな飲み方だと分かっていても、身体がアルコールに頼ってしまう。
「……探してる、けど、」
泉の言葉の続きを凜月は求めなかった。代わりに、泉を見つめて目を細めた。
「またおんなじこと繰り返すの? もういい大人なのに?」
「大人だから、しょうがないこともあるでしょ」
「『王さま』に会いたくないの、」
ふたたびグラスを手に取ろうとしたとき、一気に酔いが回った気がして、胃の奥から何かがせり上がってくる感覚がした。口元を押さえた泉に、凜月は、げ、と顔を引きつらせ、慌てて泉を立たせてトイレへ向かう。
個室に駆け込み、泉は空の胃から吐き出した。
「ほんっと、今日のセッちゃん、チョ〜うざい」
トイレのドア越しに凜月の声が聞こえた。
◇
スマートフォンのアラームで起こされる。目を開ければ、下瞼の縁に沿って、一滴の雫が流れた。それに気づいて、慌ててそれを手の甲で拭う。
さきほどまで見ていた朧げな幻を思い出そうとする。五人で籠城していた学院内のスタジオ、その窓から射し込む淡い夕焼け色の光が彼の頰を照らしていた。その首に手編みのマフラーを巻いてやれば、彼は嬉しそうに笑って、なにか口にした。その声を思い出そうとしても、懐かしい夢は淀んで消えていく。
寒さに身を縮めながら、ベッドから身を起こす。窓の外では粉雪がちらちらと舞っていた。
レオは、渡り鳥のように、どこか暖かい場所に向かっただろうか。ひとりで冬の寒さに凍えていないだろうか。
温かいココアでも作ろうとお湯を沸かす。やかんが鳴るまで、寒さに鼻を赤く染めた夢の中の彼のことを考えていた。
5
ゲイバーらしからぬ外観には、電飾が増えていた。開け放たれたドアからは大音量のクラブミュージックが流れてくる。
ヘアアイロンをかけてまっすぐになった髪を流し、薄く色づいた縁なしサングラスを掛けていれば、スキャンダルに発展することもないだろう。黒いシャツの上にはファーコートを羽織り、ボルドーのベロア素材のパンツを合わせた普段しないような格好だから、なおさら。
腕を組んだレナードは、長髪をひとつにまとめたためか、幾分大人っぽく見えた。服装はTシャツに薄手のパーカーと革製のジャケットを重ね、ダメージジーンズに厚底のブーツ。泉の見立ては間違っていなかったらしく、よく似合っている。
「恋人らしく、って言っても、おまえは普通にしてていいから」
と言いながら、彼が泉の腰に腕を回す。普通でなんかいられるものか、と思いながら、緊張が伝わらないように頷いた。
なぜ泉がゲイバーのパーティーに来ているのか、もちろんレナードの誘いだった。
出会ってから、ふたりは友人として距離を縮めていた。一緒に食事をすることはもちろん、買い物をしたり、レナードが好きなジャズの店に行ったりもした。
数日前、衣装合わせの終わりにスマートフォンを確認すると、レナードからメールが入っていた。
『二十時に俺の店に来れる?』
そのメッセージに泉は躊躇うことなく、
『分かった』
とだけ返事をした。
泉の方が先に席に着いていると、レナードは申し訳なさそうな顔をしながら、エプロン姿でやってきた。
「ごめん、ちょっと打ち合わせが長引いて」
「打ち合わせ?」
泉がそう聞き返すと、レナードはジャケットを脱ぎながら頷いた。
「来週の週末に、あのバーでパーティーを開くんだ」
「パーティー?」
「そう。開店五周年祝い。歌って踊って一晩中飲み明かす、ってわけ」
「へぇ……」
「だから頼みたいんだけど、おれの恋人役してくれない?」
だから、が意味をなさない脈絡のない頼みに、泉は眉間にしわを寄せた。
「……なんで?」
「実はさぁ、ひとりの客からすごいアタックされてて。おれはバイだけど、誰でもいいってわけじゃないからさ、恋人がいるって嘘吐いてはぐらかしてるんだよ。でも今回のパーティーは恋人がいる奴は、その恋人を連れてくるっていう暗黙のルールがあってさぁ、困ってるんだよね」
「嘘吐くあんたが悪いでしょ、それは」
「分かってる、分かってるけど……! このままだと俺の貞操が危ないんだよ!」
だったらゲイバーのアルバイトなんて始めなきゃ良かったのに、と思いながらも、彼に恩を感じていないわけではない。だから、
「しょうがないなぁ」
と肩を竦めて承諾してしまうのだった。
レナードは、
「ありがとう、イズミ」
と嬉しそうに言いながら、メニューに手を伸ばした。
店に入ると早速レナードは声を掛けられた。女装した男たちだった。
「Wow! Is he your boyfriend?(そちらがレナードの恋人?)」
「So cute!(やだ、可愛いじゃない)」
その言葉にレナードは笑って、そうだろ、と流していた。
彼女ら(と言うべきなのだろう)の横を通り過ぎて、レナードが誰かを見つけたらしく、足を止めた。
「俺、オーナーに挨拶してくるから、そこのカウンターに座って待っててよ」
と言われ、レナードは出入り口のドアの横へ向かって戻っていく。泉は彼の指示通り空いている席に座ってカウンター越しに、バーテンダーにアルコール度数の低いサワーを頼んだ。
差し出されたそれをちびちびと飲みながら、辺りを見渡す。ゲイじゃなくても入れるこの店は、多くの男女で溢れていた。ダンスフロアではDJを囲み、アルコールに酔った人々が曲に合わせて踊っていた。壁に背中を凭れて酒を飲みながら楽しそうに談笑している人々も多い。隅では、ゲイのカップルがキスを交わし、周りの友人たちから冷やかされて恥ずかしそうに、しかし幸せそうに、はにかんでいた。
自由に踊り、笑い、キスをする彼らが羨ましかった。大事な人とこんなふうに一緒に時間を過ごせることほど幸せなことはないと、泉はもう知ってしまっているから、余計にひとりで心細くなった。
ハァイ、と声を掛けられて振り返った。背の高い細身の男が、グラスを片手に人好きのする微笑を浮かべていた。
「Is the seat free? (ここ、いいかな?)」
と問いながら、泉の返事を待たずに隣の椅子に腰掛ける。
「Did you come alone today? (ひとりで来たの?)」
「No.(いえ)」
首を横に振りながら答えると、彼はグラスの中のワインを一口飲み、それからまじまじと泉を見た。
「Are you Japanese? You’re very beautiful.(君は日本人? とっても綺麗だ)」
それが分かりやすい口説き文句だとすぐに理解できた。サンキュー、と愛想笑いをしながら、目だけでレナードを探す。彼の貞操を守るどころか、これでは自分の貞操が危うくなりそうだ。
実際、彼は既に相当アルコールを摂取しているらしい。香水に混じって酒の匂いがするし、目尻は赤く染まっている。彼が何か言ったが、泉は聞き取ることができなかった。気づけば、彼の手が泉の耳に伸びる。こういうとき、何と言ったらいいか分からない。
彼の腕を掴もうとしたところで、後ろから声がした。
「Keep your hands away from my sir.(おれのツレに手ぇ出すなよ)」
振り返れば、煙草を唇から離して白煙を吐くレナードがいた。目の前のイギリス人は驚いたように目を見開いて、優しい声色で言った。
「Such a beautiful sir is yours?(レナードのツレ? こんな綺麗な子が?)」
どうやらこの店の常連客らしい。レナードは呆れたように、悪いかよ、と答えていた。
彼は不機嫌な顔で近くにあったカウンターの上の灰皿を引寄せて無造作に火を消して、泉を見た。その目がこちらに来い、と言っていた。泉が立ち上がって近づくと、腰に腕が回され、耳元で囁かれる。
「ごめん、キスさせて、」
驚いて彼から離れようとしたが、さらに身体を引かれて泉は顔をしかめた。
「どうしてそこまで、」
「こうでもしないと、あいつ、おまえを犯しかねないんだよ、」
その言葉は間違ってはいない。溜息をひとつ、いいよ、と言い終わらないうちに唇を塞がれた。
レナードは泉の腰にあった腕をほどき、今度は首の後ろに回した。
泉が柔らかな感触に驚いて唇を閉じ切らなかったのをいいことに、彼は乱暴に舌を入れてきた。熱と重たい煙草の味が、泉の理性を溶かしていく。泉が苦しげに鼻から息を吐けば、彼は時折唇を離し、また重ねてきた。そのたびに、透明な糸が切なげにふたりの唇の間で光る。
「ん、」
思わず声が漏れ、体温が上がっていくのがわかった。いつの間にか周りの人々が観衆となっていた。彼らの冷やかす歓声と大音量のクラブミュージックで満ちているから、周りの人々には聞こえなかっただろう。
しかし、目の前にいる男は違う。
さらに泉を攻め立てる。首に回った右手は頸をなぞり、そして耳裏に触れた。左手はシャツの裾から入り込み、背中を這う。硬い指の腹は、まっすぐな背筋を辿っていく。
薄目を開ければ、彼は緑色の瞳を満足気に細めていた。その表情に悔しくなって、泉も反撃の一手に出る。
彼の細い腰に回していた手を離し、シャツの隙間から露わになった鎖骨に触れる。間の窪みを押せば、彼は興奮し切った瞳で泉を見た。
熱を持ったその肌に、舌に、眼差しに、泥酔した気分になって、腰が砕けそうだ。下腹部が限界を訴えて痛む。
泉は彼の胸元を軽く叩いた。
彼は、薄い唇の端から垂れた、もはやどちらのものか分からない唾液を拭った。その指先が、あまりにも扇情的で。
「……イズミ、来い」
手首を掴まれ、泉の返答を待たずに歩き出す。周りの男たちは楽しそうに笑い、手を叩き、そしてグラスを空けた。
「It’s getting hot here!(お熱いねぇ!)」
観衆のうちの誰かの冷やかす声を背中に受けて、ふたりは賑やかな狭い店を足早に出た。
レナードが連れてきたのは、裏口を入ってすぐ横にある、従業員用のトイレだった。タイルの壁や床には汚れが残っていれば、使用期限の切れた芳香剤が汚い便器の横に転がっている。それでいて窓はなく、低い天井の小さな換気扇が音を立てて回っていた。
レナードは後ろ手で鍵を閉め、変わらず熱っぽい瞳で泉を見つめた。
「……野次馬の中に、例のやつもいた」
「あんたのことを好いてる人?」
「あいつ、諦めはいいから、もう大丈夫」
我慢できない、というふうに彼が泉を引き寄せる。それを制止しながら、泉は彼を見つめる。
「俺の貞操の方が危うくなるところだった」
「うん、ごめん、ひとりにして、」
レナードの指が泉の唇の輪郭をなぞる。
「……キスしてるときも綺麗だ、」
「当たり前でしょ」
きっと、自分も同じ��らい熱のある眼差しを彼に向け��しまっているのだろう。興奮し切った身体は、自分自身で制御できない。
彼は、今度は優しく啄ばむようにキスをしてきた。いじらしくなって、思わずその腕を引いた。
まるで、レオとキスしているかのようなのだ。容姿も、キスの仕方も、そっくりで嫌になる。ただ、こんな苦い味はしない。彼は煙草を吸わなかった。
「……泉、」
彼の手が泉の腰を撫でた。
「したい、」
まっすぐ向けられた視線に侵食される。目の前にいる男が、月永レオにしか見えなくなって、縋るように彼を抱き締めた。
「……俺も、」
ゆっくりと意識が浮上し、泉は瞼を持ち上げた。冬の朝に相応しい寒さに、泉は布団を引き寄せた。
昨晩隣で寝ていたはずのレナードの姿はない。腕を伸ばしてスマートフォンを引き寄せれば、その液晶画面には午前九時を示す数字が浮かんでいた。
上半身を起こしてから後悔する。ずきずきと腰が痛み、目を伏せた。
昨晩、レナードは泉を慰めた。トイレでキスをしただけなのに、泉の足腰には力が入らなかった。レ��ードは呆れたように、けれど欲情に満ちた目を、黙って細めた。泉を軽々とおぶり、バーからさほど離れていない彼の部屋に向かった。
暗がりの中、レナードは服を脱がなかった。最初はそれをずるい、と思った。隣室から壁を叩かれもした。しかし、すぐにそんなことはどうでも良くなって、泉は快感によがった。お互いを擦り合わせるだけでも、死んでしまうのではないかと思うほど、気持ち良くて、ふたりは大きく息を吐いて同時に果てた。あのときの、彼の濡れた瞳が脳裏に浮かんで、腰とはまた違う場所が微かに痛んだ。
バスルームからは水が弾ける音がする。昨晩、行為の後に泉がシャワーを借りて脱衣所から出ると、彼はそのままベッドで寝ていた。泉より早く起きて、身体の汚れを落としているのだろう。
獣を連想させた瞳は伏せられ、寝顔は少し幼くて、あまりにも、彼に似ていた。
それを思い出して、泉は柔らかな毛布に顔を埋めた。
レナードは、レオじゃないのに。
「……ごめん、」
小さく呟いた言葉は、冷たい空気に吸い込まれて消えていった。
6
泉とレナードが身体を重ねたのは、あのパーティーの夜だけだった。その後、レナードも泉もお互いを求めはしなかったし、泉の方は求めてはいけないような気がしていた。
レオは他の誰でもないのに、他人のどこかにレオを重ねようと必死に足掻いて、寂しさを埋めようだなんて、レオに、重ねられる彼らに対して、あまりにも不誠実だと気付いているから。
月永レオはただひとりであって、その代わりなどいないのだ。
パーティーの三日後の夜のことだった。その日は日暮れから雨が降り出し、夜が更けるにつれて雨脚は強まっていった。
十一時を回った頃、チャイムが鳴った。マネージャーだろうか、と思いながらドアスコープを覗くと、濡れ鼠になったレナードがいた。
慌ててドアを開けると、
「Good evening.」
彼はへらっと笑った。
「なんで傘差してないの」
「途中で折れたんだ。その上飛行機は欠航だよ。もちろん部屋も引き払っちゃったし、空港に寝泊まりするのは嫌だし……だから、な、泊めてくれよ」
彼の右手には大きなスーツケースがあった。どうやら本当に飛行機に乗ってロンドンを発つつもりだったらしい。髪の毛先やコートの裾からぽたぽたと水滴を垂らすレナードを訝しげに見ながら、他の住人が外廊下を歩いていった。
「……分かった、いいよ」
そう答えれば、ありがと、と彼は笑い、シャワールームへと直行した。
新品のバスタオルと自分のパジャマを脱衣所に置いといてやり、彼の濡れた服を洗濯機に突っ込んだ。
熱い湯を浴びた彼は、髪を乾かしながら泉に話し出した。
「母さんの具合が悪くなったから、実家へ帰るよ」
「……ロンドンには、もう帰らないの」
「うん。元々こっちに来ること、反対されてたから」
長い髪はドライヤーの熱風に晒され、乾いて靡いた。
「だから、おまえと会えるのも今日で最後だ」
「別に、スマホがあるから連絡なんかいつでも取れるでしょ」
「……うん」
ドライヤーの電源を切って、彼は寂しそうに笑った顔を泉に向けた。
ベッド使っていいよ、と言ってソファーで眠ろうとすると、腕を引かれてベッドに連れていかれる。彼は壁際に寄って、
「いいじゃん、一緒に寝れば」
ほら、と空いたスペースを手で叩いた。
「あんたのベッドじゃないけどねぇ」
という文句を言いながらも、泉はおとなしくベッドに潜った。
「人肌が恋しいんだよ」
「よく言うよ」
「本当だよ。おまえと離れるのが寂しい」
レナードは泉を見つめた。その眼差しに、泉は目を逸らす。
「それ以外はしないから、抱きしめてもいい?」
静かな声に、泉は黙って頷いた。彼は泉の背中にそっと腕を回した。その温もりと重さに、泉は唇を噛んだ。
「おれと、おまえの大事なひとが似てるって、言ったじゃん」
「そうだねぇ」
出会ったあの日、そんなに似てる? と言った彼の表情が脳裏に浮かぶ。
「……イズミは、そいつのことが好きだったのか?」
レナードはそう訊いた。泉は寝返りを打ち、彼に背中を向けて答えた。
「愛してる」
レナードは、エメラルドの双眸を瞠り、そうか、とだけ返事をした。泉は、うん、とだけ言った。そのあとは、ふたりとも、もうなにも言わなかった。
窓の外、雨が地面を打つ。その音を包み込むように夜は深まっていく。目を閉じれば、背中越しに彼の鼓動が聞こえた。
目を覚ますと、レナードの姿はなかった。ベッドには彼の分の温もりが残っている。
今頃、空港に向かっているのだろう。何時のフライトか聞き忘れたことを後悔しながら、泉はベッドから出て、キッチンへ向かった。
ペットボトルのミネラルウォーターを飲みながら、ふと、ダイニングテーブルに目をやった。
その上に、マフラーがあった。赤い毛糸で編まれたそれに、泉は、まさか、と思いながら手を伸ばす。
編み方から、手作りだと分かる。端の方に、小さな王冠のワッペン、金色の糸で、"L.T"のイニシャルが刺繍が施されていた。
間違いなかった。そのマフラーに顔を埋めた。懐かしい匂いに泉は目を閉じた。
————ありがとな、セナ!
思い出すのは、さきほどまで隣で眠っていた男ではない。
ぱっと顔を上げて、泉は素早く着替えてコートを羽織った。スマートフォンを引っ掴んでマネージャーに、
『体調が悪いから打ち合わせは俺抜きでやっておいて』
とメールを送っておく。マフラーを手に部屋を出て、タクシーに飛び乗った。
◇
空港は、相変わらず多くの人で溢れていた。クリスマス休暇を使ってロンドンへ来る人、ロンドンから他国へ出る人が多いのだろう。
そんな人混みを縫うように泉は走った。
搭乗を知らせるアナウンスと雑踏、売店から流れるBGMのクリスマスソングが入り混じっている。
もう飛行機に乗り込んでしまったかもしれない。どこの国へ行くのかも聞かなかったから時間も分からない。
出るとは思わなかったが、彼の番号に電話を掛けた。自分のスマートフォンから呼び出し音が虚しく聞こえる。
留守番電話にメッセージを残そうと思った————その時だった。
近くで誰かの携帯電話が鳴っているのが聞こえた。
その着信音は、彼のスマートフォンのものと、同じだった。
ぐるりと周りを見渡した。
人々が身に纏う服の色がやけにくすんで見え、動きもゆっくりに見えた。今まではっきり聞こえていた音も遠ざかる。
泉の視線の先、揺れる赤毛が見えた。
人混みの中、異様な存在感に泉は息を呑む。
泉は無意識のうちにふたたび駆け出した。
「待って!」
そう叫べば、周りの人々が驚いたように泉の方を見て、また素知らぬふりして、スーツケースを引っ張りながら歩いていく。
彼は振り返らずにすたすたと歩く。聞こえてるくせに、そう思うと泣きたくなって、大きく息を吐いた。
「待ってよ、ねぇ、……れおくん!」
震えた声に、赤毛の男が立ち止まった。
彼に追いついた泉は、その腕をぐい、と強く引いた。
振り向いた彼が、は、と小さく息を漏らした。
ゆらり、とエメラルドの中の光が揺らぐ。
それは、泉の姿だけを映していた。
空気に晒された細い首に、そっと、赤いマフラーを巻いてやる。
「……こんなの、まだ持ってたの、」
震えた声でそう問えば、張り詰めていた緊張が解けたように、彼は、優しく笑った。
泉の大好きだったそれが変わっていないことに、堪えていた涙が零れて頬を伝う。
「……大事な、おまえとの思い出だから」
ずっと、この日が来るのを願っていた。
セナ、と呼ぶその声を、ずっと、ずっと聞きたかった。
間違いなくそれは、レオのもので。
強く腕を引かれ、抱き竦められる。背中に回された腕も、顔を埋めた肩も、泉の頰に触れる赤毛も、ぬくい体温も、ぜんぶ、ぜんぶレオのものでしかなかった。
「……二年間、おまえのことしか、考えてなかった、考えられなかった」
「うん」
耳元で囁かれる言葉に、上手く返事ができない。涙がレオのコートの肩を濡らす。
「ひとりにしてごめん、勝手にいなくなってごめんな」
「……ほんとだよ、バカ」
「愛してる、愛してるよ、セナ。もう、いなくならないから、離れないから、おれと、一緒にいて、おれの、傍にいて……」
レオの声も、肩も、震えていた。彼の背中に両腕を回し、力を込めた。彼がもうどこかへ消えてしまわないように。
「うん、ずっと一緒にいる、もう二度と、離れないから」
涙で濡れた声を絞り出す。
「……ずっと、れおくんを、探してたよ」
7
二年前の、クリスマスも近い夜だった。街は煌びやかなイルミネーションで飾り立てられ、浮かれたクリスマスソングと人々のざわめきで満ちていた。
レオと泉は久々にオフが重なり、レストランで食事を取ることにした。
ふたりは向かい合って、美味しいディナーとワインを嗜みながら、他愛の無い話をした。
泉は、以前テレビ局の廊下で偶然会ったらKnightsで集まりたいと駄々を捏ねられたこと、クラスメイトだった千秋が特撮の主演に選ばれたこと、今度UNDEADのライブに凜月と行くことになったこと、自分がブランドの広告塔に抜擢されたこと、などを楽しそうに話した。レオは、適度にお酒が入ると饒舌になる泉を愛おしく思いながらそれを聞いた。
店を出る頃、夜は静かに深まっていた。紺色の艶やかな空には、白い星々が人工の光に負けないようにと明るく光っている。南にはオリオン座が一際輝きながら浮かんでいた。
泉は、お気に入りのコートのポケットに両手を入れながら、寒そうにレオの半歩前を歩いていた。
「セナぁ、」
と呼べば、
「なぁに、」
と少しだけ火照った顔をレオに向けた。ワイン数杯で十分酔った泉はあまりにも無防備で、今すぐに食べてしまいたい、と思った。だから、その首の後ろに腕を回してキスをした。サングラスの下、彼が驚いたように目を見開いたのがわかった。
「……外だよ、」
「誰もいねえじゃん」
「そういう問題じゃ、」
ないでしょお、と文句を言おうとしたその口を再び塞ぐ。下唇を噛んでやれば、期待を含んだ濡れた眼でレオを見つめた。たぶん、ここからホテル街が近いのを、泉も知っている。
「……セナ、行くぞ」
泉はなにも言わない代わりに、繋いだ右手に少しだけ、力を込めた。
あの時の温かい手を、今でもレオは忘れていない。
その数日後のことだった。
打ち合わせが終わり、スタジオを出たレオは、ロビーのソファーに座っていた男に呼び止められた。
「……月永レオくん、だよね?」
「そうだけど、」
と立ち止まって答えれば、レオの前に立った彼は名刺を差し出した。そこには、名前と職業が印字してあった。それを見て、あ、と思った。
泉が仕事で世話になっているらしいカメラマンだ。泉と一緒にいるのを見かけたことがあるし、泉からも度々話題が出るので、レオもなんとなく覚えていた。
どうも、と名刺を受け取りながら、背の高い彼を見上げる。彼はにこり、と微笑んで言った。
「折り入った話があるんだ。あまり人に聞かれたくないから、会議室を借りた。そこで話せるかい?」
レオは、嫌な胸騒ぎを抑え込むように黙って頷いた。
小会議室に入ると、彼は丁寧に内鍵を掛けた。
そして、カバンから取り出したのは一枚のプリントだった。怪訝そうな顔をするレオをよそに、彼は見開きページを開けて、レオの前に差し出した。
画質のいい写真数枚と、大きな見出し、そして記者が書いた文章が並んでいた。
それに、レオは思わず息を呑んだ。
「こ、れ……」
その写真には泉とレオが路上でキスをしたり、手をつないだりしているところがはっきりと写っていた。
「週刊誌の原稿だ。まだ印刷も発売もされる前のものだよ」
服装や場所からして、先日、ふたりで夕食を食べた後のものだ。
「その反応は、間違いないってことだよね?」
男は真剣な瞳でレオを見つめた。沈黙を肯定と受け取った男は、写真を一瞥する。
「僕は、この写真を撮った男の弱みを握っている。僕の力でこれを揉み消すことができる」
は、と顔を上げたレオに、男は優しく微笑んだ。
「……君が条件を飲むなら、ね」
その低い声に、レオは、全身の筋肉が強張るのが分かった。
「……条件って、なんだよ」
「なに、そんな身構えなくていい、簡単なことさ」
男は優雅な手つきで煙草を咥え、その先にライターで火をつけた。
「瀬名泉と別れろ」
突きつけられた言葉を瞬時に理解できなかった。ただ、言葉がひとりでに溢れる。
「どうして、」
「どうして、だって? 分かるだろう、この記事はそのまま来週の週刊誌に載るよ。メディアに取り上げられ、未だ同性愛に厳しい世間は大騒ぎだ。フリーで活動する君とはちがって、唯一無二の宝石のようなイメージを持たれている瀬名泉にとって、このゴシップは大ダメージだろう」
口を開きかけたレオの言葉を遮るように、彼はまくし立てる。
「加えて、君の母校にとっても。同じユニットメンバーだった後輩が、まだ在籍中だろう?きっと彼も被害を被るさ。君ら���せいでね」
その言葉に、真新しい衣装をまとった司の姿が脳裏に浮かんだ。
泉は、司のことをよく気にかけていた。どこまでも面倒見が良い男は、弟が心配なのだろう。レオにもその気持ちがわかる。
まだ長い煙草が、灰皿に押し付けられた。彼は追い討ちをかけるように、にこりと微笑を浮かべる。
その表情には、冷徹さしか感じない。
「君のせいで、瀬名泉は穢れるのさ、月永レオ」
どくどくと心臓が脈打っている。喉を絞められているかのように苦しい。
れおくん、と呼ぶ彼の姿が瞼の裏に浮かぶ。
有名なブランドの広告塔に選ばれたんだよねぇ、と言いながら見せた、昨晩の嬉しそうな表情。
店頭に並ぶ、彼が表紙を飾った多くの雑誌。
群青のブレザーを纏い、かつての仲間を睨む瞳。
————あのとき、彼は泣いていた。
おれが、セナを汚してしまった。
あの赦されない罪を、また、ふたたび、おれは繰り返してしまうのか。
レオは、記事から目を離し、目の前の男をまっすぐ見据えた。
「……分かった」
別れるよ。
そう告げると、男は満足そうに目を細めた。
◇
泉の部屋に帰ってきて、レオはベッドに腰掛けて、二年前のことを話した。そしてその後、泉のスマートフォンに留守番電話を残して、日本を出たのだ、と。
泉は、呆然と、レオを見つめた。
「あのとき、酷いこと言って、ごめん。おれ、けっきょく昔と変わってなかったんだ。おまえのことが大事だからって、セナを傷つけるような道を、選んで、おまえを、傍で守り続けられなかった、離れることしか、できなかった……なぁ、セナ、ごめん、ごめん……」
ぽろぽろと溢れる涙は、宝石のように美しく、哀しい光を放った。その煌めきを一粒一粒、零さないように泉は指で拭う。
「……泣かないでよ、れおくんは悪くないでしょ。あんたは俺を守ってくれたよ。寂しかったけど、でも、でもこうして、またちゃんと会えたから、ねえ、れおくん、もういいよ、だいじょうぶ、だいじょうぶだから、」
言葉を紡げば紡ぐほど、涙が溢れ出してきた。いずみ、と呼ばれて、涙で濡れた頰をレオが撫でる。
彼の瞳に映った自分は、見たことのない、みっともない顔をしていた。でも、今なら言える気がした。
「……もう、二度と離れないで、」
ずっと、言えなかった。言葉にしたら叶わない気がしていた。けれど今なら。
レオの小指が、泉のそれを絡め取る。
「約束する」
本当に? と訊けば、キスをされた。熱い唇が離れていき、は、と吐いた息が混じり合う。
「……今の、誓いのキスな」
レオが紡ぐありきたりな言葉に、泉は笑った。
レオが慣れた手つきで泉のシャツのボタンを外していく。
「……いつからこっちにいたの」
「おまえと別れてすぐ」
細くくびれた腰をレオの指がなぞり、思わず声が漏れた。
「で、学生時代知り合ったやつがあのバーで働いてて、そのツテでバイトさせてもらえることになったわけ。ゲイバーって思ったより危険でさぁ、おれは何度ケツを狙われたかわかんない」
「……したの、」
「してないって」
「うそ」
「セナこそ、あの変態カメラマンと何回もしたんだろ」
言葉に詰まった泉を、レオは冷たい目で見下ろした。自分の被虐心を許しそうになってしまうその目線に、泉は息を吐いた。
レオは、泉が一番触ってもらいたいところには触れず、胸元に唇を寄せる。
「おれ、あの後スランプにも不能にもなってさ。おまえとバーのトイレでしたときに治ったんだよ、両方」
「ば、バッカじゃないのぉ!?」
と絶叫すれば、レオは舌を這わした。
「や、ァ、それ、やだ……っ」
泉は羞恥に自分の顔を覆った。レオの長い指が、泉が履いたパンツのジッパーを下げ、下着を脱がす。
おれさ、という声がいつもより低く聞こえて、心臓が痛いくらいに脈打った。そっと目を開けば、劣情と興奮を混ぜた色の捕食者の瞳が泉だけを見つめていた。
「おまえにしか興奮できないんだよ、セナ」
反らした首筋に優しく噛みつかれ、泉ははしたなく嬌声を上げた。レオは満足げに目を細め、今度は歯型が残るほど、強めに噛まれる。
レオの汗が泉の鎖骨に落ち、泉のものと混ざっていく。
あちこちに紅い痕が浮かぶ身体を捩れば、強い力で押さえられ、身動きが取れなくなった。
肩で息をしながら、泉はレオを睨んだ。
「明日、撮影なんだから、さぁ……!」
「二年越しのおれとのセックスと、毎日してる撮影、どっちが大事なんだよ!?」
と凄まれて、
「……れおくん、」
と答えてしまった泉の自業自得だ。明日、現場でなんと言われるか分からない。
しかし、あっという間にそんなこともどうでもよくなる。
触れる汗ばんだ肌はレオのものでしかない。その汗の匂いも、獣じみた深緑の瞳の光も、二年前となんら変わっていなかった。舌は煙草の味がするし、苦しそうに眉を寄せるその表情は、少し大人びたかもしれないけれど。
「あの後、おまえが、あんな男とセックスしてたとか本当にムカつく!」
あんな男、とは、あのカメラマンしかいない。
「俺だって、自分に、腹が立って、る!」
「ねぇ、あいつと何回した? どういうふうに抱かれた?」
「思い出させないでよ、萎える、」
「おまえの口から萎える、とか聞きたくなかった、な!」
「あっ、ちょ、ばか……っ」
意地の悪い目に、背筋が震えた。
「おれとのが、気持ちいいだろ、セナ」
彼の首の後ろに両腕を回して引き寄せ、キスを求めれば、レオはそれに応えた。
「……れおくんがいいに、決まってるでしょ」
それからは、泉にも、レオにも、余裕などなかった。
泉は抵抗さえできず、ただよがって喘いだ。
レオは満足そうに舌舐めずりをし、薄い唇で泉の肌に口付け、強く吸った。そのとき、わざとらしく立てられる、ぢゅ、という音と、レオの熱い吐息を、敏感になった耳が捉え、その毒が全身に回っていく。
長い赤髪を、形の良い耳にかけてやった。彼は、まだ涙の跡が残ったままの、上気した顔を綻ばせた。
「いずみ、好き、愛してるよ」
「俺も、」
愛してる、と答えたと同時に、ふたりで果てた。
◇
目を覚ましてから、二年越しではなく、三日ぶりじゃないか、と冷静な頭が気づいた。
あぁ、でも、彼はレナードとして泉を抱いていたから、れおくんとのセックスは二年ぶりで正しいのかなぁ、なんて思いながら、隣で眠る彼の頬を撫でた。薄い瞼が震えて、ゆっくりと彼が眠りから覚醒する。微かに揺れたエメラルドが泉を映す。
「……セナ、」
そう呼ばれて、泉は、は、と短く息を吐いた。
何もかもを投げ出してしまいたい。ここから何処にも行きたくない。このままこの瞬間が続けばいい。そう、願った。
気づかぬうちに、涙が頬を伝っていた。レオの指先がそっとそれを拭い取る。
その優しさに、泉は目を閉じて、彼の胸元に頭を押し付けた。レオは黙って、その首の後ろに腕を回す。
「もう、おれ、どこにも逃げない。何があっても、誰が邪魔しても、セナのそばで、セナを愛し続けるよ」
顔を上げた泉の唇に、レオは優しくキスを落とした。
「もう泣くなよ、今日、撮影なんだろ?」
「うん、」
「何時から?」
「夜の六時」
「分かった。朝メシ、食べれる?」
泉が頷くと、彼は裸体を起こした。しなやかな筋肉のついた背中に、いくつもの自分の爪の痕を見つけて体温が上がった。
ふと自分の身体を見下ろせば、至るところに唇の跡が紅く残っていた。腹や背中、脚は百歩譲っていいとしても、腕や手首など人の目線に晒されるところにもお構いなしだ。
「れおくんのばか」
と言えば、ベッドから降りたレオが、え〜?と悪戯っぽく笑う。反省の色など微塵もない。
「だって気持ちよかったじゃん?」
そう言い放った彼に、泉は枕を投げつけた。
レオは慣れた手つきで朝食を作ってくれた。トーストに焼いた目玉焼きを乗せ、軽く塩胡椒を振った。その横に付け合わせのポテトサラダが添えられる。香りのいいコーヒーはマグカップに並々と注がれた。
レオは自分のコーヒーに砂糖を2杯、ミルクを少々入れながら、口を開いた。
「セナが来るって聞いたのは本当だ。あの日、おまえを見かけて、相変わらず綺麗だな、って思った。もしこれで話しかけてもらえなかったら諦めよう、そのまま違う国へ移ろうと思ってた。でも、おまえが泣きそうな顔しておれの名前を呼んだとき、おれはなんてばかだったんだろうって思った」
その言葉に、マグカップを取ろうとした手を引っ込める。
「……じゃあ、なんで、偽名で名乗ったの。れおくん本人だって、言ってくれれば良かったのに」
「……勇気がなかった」
レオは泉の手を離して、目を伏せた。
「おまえに嫌われてたら生きていけないと思った。勝手におまえから離れたおれを許してくれなかったら、って思ったら怖かった。だから咄嗟に別人として振る舞ったんだ」
でも結局、と彼は申し訳なさそうに微笑んだ。
「おまえを苦しめてることには変わりないよな、ごめんな」
れおくん、と呼べば、なぁにセナ、と彼は答える。
「……俺がどんだけれおくんのことを愛してるか、ちゃんと、解ってよ」
8
「I must apologize to you.(プロデューサーに謝らなければいけないことがあります)」
現場に入った泉の第一声に、プロデューサーをはじめ、スタッフたちは驚いたように目を瞬いた。
泉は視線の中、コートとセーターと、シャツを脱ぎ捨て、上半身を露わにした。
それを見たスタッフたちの何人かは驚き、何人かは苦笑いをした。そんな中で、
「It was a hot night,wasn’t it?(熱い夜だったんだねえ)」
とプロデューサーは楽しそうに笑った。
「I want take your skin if you don’t mind.(君が嫌でないなら、その肌を撮りたい)」
その提案に、泉は、安堵の息を吐き、
「Yes, my pleasure.」
と短く答えた。
◇
「れおくん、頼みがあるんだけど」
真剣な顔で泉にそう言われて、レオは緊張で肩を強張らせ、なに、とだけ返事をした。
ロンドンコレクションの当日。レオはファッション界の重要人物たちに囲まれながらコレクションの始まりを待っていた。泉が見立てたスーツをまとい、短く切った赤毛も美容院でセットしてもらったため、見劣りはしないだろうが落ち着けなかった。そんな中、胸ポケットの中のスマートフォンが震え、泉に呼び出されて、レオは今、関係者以外立ち入り禁止の楽屋にいるのだった。
目の前に立つ泉は、来冬の新作のファーコートを裸の上半身に羽織り、レザーパンツで脚のラインを強調している。化粧もすでに施しており、その美しさは何倍にも際立っていた。
泉はこのコレクションのファーストルック、つまり、最初にランウェイを歩く、という大役を務める。そこから業界からの泉に対する期待が窺えて、レオは泉を誇らしく思ったし、泉の他に適役はいないだろう、と思った。
その姿に見惚れていると、
「聞いてる?」
と足を踏まれた。
「痛い! ……ごめんって、セナがあんまり綺麗だから」
彼の横髪に伸ばそうとした手を掴まれ、そのまま楽屋を出てトイレへ向かった。個室に入って後ろ手で鍵をかけた泉を、レオは見つめることしかできない。
「あの〜、セナさん、もう、あの、出番まで三十分くらいしかないのでは……?」
三十分じゃ終われないけど、というレオの言葉は泉に塞がれた。
「キスマークつけて、」
「……は?」
早く、と彼はコートの前を開けて胸元を晒した。
レオは泉に問いただすことをやめ、彼の言う通り、胸元に口付けた。
泉の細い腰を掴んで引き寄せると、コートの下の肩がびくりと小さく跳ねた。
ぢゅ、という音を立てて皮膚を吸えば、紅い痕が残った。胸から鎖骨、それから首筋、耳朶を食んで、最後に唇にキスをした。下唇に歯を立てれば、泉の長い睫毛が震えた。
顔を離すと、お互いの濡れた息が絡み合って消えた。涙が滲んだ瞳でレオを見つめながら、泉はコートを着直した。
「……セナ、どうしよ、」
「なに、」
「勃った」
泉は照れたように、バカ、と呆れ笑いしながらドアを開ける。その笑った顔は、初めて出会った頃からちっとも変わっていなかった。
「……俺の出番に間に合うようにしなよね」
そう言い残して、さっさと出て行ってしまった。あまりにも横暴だ。でも、これが二年間の罰だとしたら、あまりにも甘すぎる。
あと二十分か、と腕時計を確認して、もう一度個室の鍵を閉めた。鼻腔には、泉の香水の匂いがいつまでも残っていた。
観客席の照明は落とされ、中央に通る広いランウェイだけが照らされる。スタイリッシュな音楽が流れ出し、観客たちは皆スマートフォンを取り出し、その内蔵カメラを、世界中から集まったカメラマンたちは大きな一眼カメラをランウェイへ向けた。
ひとりのモデルが舞台に上がる。一斉にシャッターが切られ、フラッシュの光が彼を照らす。
決して高いとは言えない背でも、その身体には一切無駄がない。セットされた銀色の髪、ルージュを引かれた形の良い唇、まっすぐ前だけを見つめる薄青色の宝石のような瞳、ファーコートの前立てから覗く肌に点々と残された紅。
ランウェイの突き当たりで、彼はファーコートをはだけさせてみせた。蠱惑的で挑発的な笑みを、その美しい顔に浮かべて。
踵を返し、舞台へ戻る彼が一瞬だけ、レオの方を見た。その流し目に、レオは思わず息を呑んだ。
「Who is he?(彼は誰?)」
隣に座っていた女性が、連れの男性に問い掛ける。その男性は泉から目を離して彼女に答えた。
「He will be next top model. He is Izumi Sena,Japanese model!(次のトップモデルだ。イズミ・セナだよ、日本のモデルさ!)」
そうしてショーの直後に、あるブランドが公開した写真は、各界から絶賛された。
モノクロ加工が施され、色づいているのは澄み渡ったブルートパーズの瞳と、肌に刻まれた微かに見える官能的な赤いキスマークだけ。デザイナーの手書きでブランドのロゴとテーマが綴られた黒色の背景に、白い肌と身体を模る線がよく映えている。素肌にファーコートを羽織り、カメラから視線を外しているのは、日本人モデルだ。その美しさと危うさに、誰もが息を呑んだ。
期待の新星、瀬名泉に世界中が心を奪われたのだ。
◇
改札に向かう人々が足早に歩く。その足音と電車の出発を知らせるアナウンスが壁や天井にぶつかり、はねかえり、またぶつかって、絶えることなく駅を満たしていた。
その人混みの中に紛れて、ふたりは歩く。横に並んで歩いていたレオが急に立ち止まったことに気づくのに二秒かかって、その分遅れて泉は振り返った。
レオの目線は、壁の広告だけに注がれていた。少しだけ踵を返し、相変わらず細い手首を掴みながら、ちらりとその広告を見る。
「セナだ!」
まるで隠された宝物を発見した子供のように、レオは無邪気に笑った。
「うん、そうね。分かったから早く歩いて!」
足早に歩くサラリーマンや学生のうちの数人が、広告の前で立ち止まるふたりを煩わしそうに見ては、その横を通り過ぎていく。
泉はレオの手首を掴んだまま、出口に向かって歩き出す。
「ただでさえ電車が遅れて、あいつら待たせてるんだから急がないと」
「確かにあいつらには早く会いたいなぁ!」
「だったらさっさと歩く!」
しかし、レオが名残惜しそうに、泉が映った広告を振り返って見ているのが分かる。
一度強く手を引けば、レオは驚いたように泉を見た。
「……本物が隣にいるのに、満足できないわけぇ?」
嫌味ったらしく言ってやれば、レオは楽しげに笑った。
「どっちのセナも見てたいんだよ」
なんて言うのだから、やはり、レオの方が一枚上手だ、と思ってしまった。
ふたりが着いた頃には、他の三人はすでに席についていて談笑していた。
「も〜、遅いわよ、『王さま』、泉ちゃん!」
子どもみたいにわざとらしく両頬を膨らませた嵐を、泉は呆れた目で一瞥する。
「電車が遅れてるって連絡したでしょぉ」
「俺たちは待ちくたびれちゃったんだけど〜」
凜月は頬杖をつきながら、司からメニューを受け取った。
「ともあれ! 久々に先輩方とこうして集まることができて嬉しいです!」
と、司はまだあどけなさが抜けない顔でレオと泉に笑いかけた。
泉とレオの帰国の報せを聞いて、五人で集まろうと言い出したのはもちろん司だ。自ら寿司屋の個室を予約し、五人のスケジュールを考慮しつつ日程を決めたのも司だった。
「leader、今までどこでなにをしていらっしゃったのか、ちゃんと説明していただきます」
レオの腕を掴んで自分の隣に座らせる司の背丈は伸び、精悍な顔つきになっていた。高校を卒業して二年が経つ。大学に行きつつ芸能界の仕事もこなすことが、彼をここまで成長させたのだろう。
レオは、そんな司に呆れたように溜息を吐きながら、さっそく日本酒を注文していた。
「聞いているのですか、Leader!」
「まぁまぁ、司ちゃんもなにか飲むでしょう?」
興奮気味の司の隣に嵐が腰を下ろしてそう宥める。
そんな彼らを見ていると、
「セッちゃんはこっち〜」
と、凜月に横から腕を引かれた。
「なぁに、くまくん」
「『王さま』とは向こうで散々イチャついたんでしょ」
「ちょっと、そういう言い方やめてくれない?」
横目で睨めば、凜月は楽しそうに笑った。
注文していたアルコール類が来て、機嫌を直した司が音頭をとる。
「それでは、Leaderと瀬名先輩の帰国と、Knightsの再結集に、乾杯!」
「かんぱ〜い」
グラスやお猪口を合わせ、冷たいそれらを飲む。泉の頼んだウーロンハイは飲みやすく、この一杯だけにしておこう、と思った。
凜月は慣れた手つきで自分のグラスに二杯目の日本酒を注ぐ。
泉と凜月の向かいに座る三人は、さっそく寿司に箸を伸ばしている。数貫を確保すると、凜月は、
「じゃあ本題ね」
と声を潜めた。
「いいもの見せたげる」
凜月はにやりと意地の悪い笑みを浮かべながら、嵐のカバンから新聞を取り出した。どうせ、コンビニで買ってからこれを入れるカバンを持っていないことに気づき、嵐に持っていてもらうように頼んだのだろう。
でもなんで新聞なんか、と疑問を口に出そうとした泉の前に、一面が広げられた。
「これ、読んだ方がいいよ」
凜月が指差したそこに大きく書かれたのは、”有名カメラマン、モデルらへの性的暴行で逮捕”の文字。その下には見覚えのある男の顔写真があった。
「別れて良かったねぇ、セッちゃん」
にやりと笑う凜月に、泉は眉間にしわを寄せながら、新聞を手にとってその記事を読む。
一緒に撮影していた男性モデルの複数人を襲ったらしい。被害者は皆新人モデルだというから、きっと、逆らったら仕事がなくなる、とでも脅されたのだろう。被害者の何人かが被害届を出したことで明らかになったそうだ。
「怖いのはさ、セッちゃんと別れてから、急にだからね」
「そうだねぇ」
素直に頷けば、凜月は物言いたげに目を細めた。その虹彩の色は昔とまったく変わっていない。それだけじゃない、その風貌も18歳の頃とあまり違わない。
なにを言うでもなく、黙ってお互いを見つめていると、向かいから低い声がした。
「リッツ、」
は、と振り返れば、猪口に日本酒を注ぎながらレオが言葉を続ける。
「近すぎ」
凜月は悪戯を咎められた子どものようにぺろっと舌を出して、ごめんね、と謝った。
レオが顔を上げて、泉を見た。長い前髪の間から緑色の瞳が覗いた。その光に、泉はすぐに目を逸らす。ドク、ドク、と心臓がうるさく脈打った。
特別なステージの上や、幾度も重ねてきた夜に、泉だけに向けるそれだったから。
なんで、今、と鼓動が速まっていく。レオに向けられた熱がじわり、と泉を侵食していく。
それに気づかないふりを装って、泉は凜月からお酌してもらった日本酒を喉に流し込んだ。
9
五人揃った飲み会は午前十二時ちかくにお開きとなった。司は家の使用人の、凜月は兄の、嵐はマネージャーの車で帰っていった。
なんとなく、レオと泉は迎えを呼ばなかった。どちらからともなく、ふたりは歩き出した。
夜の東京は明るかった。ロンドンのものとは違う人工の光が、今は止んだ雨で濡らされたコンクリートを照らす。
「三人とも相変わらずだったなぁ」
「れおくんは会うの二年ぶりだもんね」
頷いたレオは楽しげに笑う。その笑顔が相変わらず眩しくて、泉は目を伏せて微笑んだ。
「スオ~もすっかりでかくなって……」
「あいつ、れおくんが卒業式に来なかったこと、相当怒ってたよぉ」
「うん、説教された。最後らへんはほとんど呂律が回ってなかったけどな」
下戸の司は、レオに負けまいと意地を張っていつも以上に飲んでいた。崩れた敬語には、彼本来の子供らしさが露わになっていて、レオは微笑ましそうに司の説教を聞いていた。
スクランブル交差点の信号は赤だった。大勢の人々に紛れるようにして、泉とレオも立ち止まる。
通り過ぎていく車の窓に、ビルの光が反射した。タイヤの擦れる音に紛れて、繁華街のざわめきが聞こえてくる。
信号待ちをする若い女性たちの何人かが、スマートフォンの内蔵カメラを目線の先の大型モニターに向けていた。
それに、映像が映し出される。
数年前に日本進出を果たし、若者たちから人気を集めているイギリスの有名ブランドの広告だった。
ひとりの男がカメラを睨む。その細められた薄青色の瞳に、彼女らは溜息を吐いた。
「瀬名泉、ほんとかっこいいよね」
「それね〜、なんであんなに美人なんだろ……」
車が停まり、歩行者用の信号が青に変わる。仕事終わりのサラリーマンや、飲みに来ていた大学生たちが重い足取りで交差点を渡る。
レオと泉も、その人の波に押されるように歩き出した。
「美人だって」
レオが陽気に笑いながら、泉の顔を覗き込む。
「言われなくても分かってるでしょ」
そう言い返せば、うん、と彼は泉の手を取る。そんなふたりを、誰も見咎めはしない。
「おれがいちばん分かってる」
素面で言うのだからずるい、と思う。レオは酒に強いうえ、今日はそれほど飲んでいなかった。その顔にアルコールのせいの赤らみなどはない。
どこまで歩く、とは尋ねなかった。レオが満足するまで着いていこう、と思った。
ただひとつ分かるのは、二年前まで一緒に暮らしていたあのマンションの方向に向かっていることだけだ。
「セナ、あの家、売ってなかったんだな」
「俺の家なんだから売るわけないでしょ」
「でも、二年間の間、ほとんどあのカメラマンの家にいたんだろ」
「まだあいつの話する?」
するよ、と彼は言う。
「まだおれは怒ってるもん」
「俺だって、置いていかれたこと、まだ根に持つからねえ、レナード」
そう呼べば、彼は困ったように眉を下げて笑った。
「じゃあお互い様だ」
繋いだ手は熱い。彼が寒そうに吐いた息は白く、闇に溶けるようにして消えた。
人気のない跨線橋の上で、レオが立ち止まった。彼の目線の先、細い線路が延びていた。そびえ立つビル群、その屋上では赤いランプがゆっくりと点滅していた。
真冬の透明な空気のおかげで、ふたりを取り囲む世界は美しく、鮮明だった。
唐突に腕を引かれ、唇が重なる。
彼らの下を、電車が通過した。
「……また、撮られるよ」
冗談めかしにそう言えば、レオは細めた瞳で泉を見上げた。
「そうしたら、ふたりで駆け落ちしよう」
その表情がひどく真剣で、泉は目を逸らしながら、ばか、としか言えなかった。
「おれだけのセナだったのになぁ」
なんて言いながら、レオは泉の顎をなぞる。
「……俺は、昔も今も、あんたのものでしかないよ」
そう言い返せば、彼は驚いたように瞬きした。まっすぐに伸びたまつげが震えるように揺れた。
レオの右手が首の後ろの方に回って、もう一度、そっと顔を近づけられる。
泉は黙って、優しい口づけを受け入れた。
唇を離したレオは、愛おしそうに泉を見つめた。
「……セナに出会えて良かった」
絡めた指先から伝わる熱も、昔から変わらないその眼差しも、泉は心の底から愛している、と思った。
「愛してるよ、セナ」
「……俺も、」
恥ずかしさにその胸元に頭を埋めれば、どく、どく、とレオの鼓動が静かに聞こえた。レオが笑えば、その肌が震えた。
彼の心臓が作り出すリズムに身を委ねるように瞼を閉じる。
最終電車が金属音を立てながら、轍を残していく。その音と窓から漏れる光が遠のいていった。
瞼の裏に思い浮かぶのは、この電車が行き着く先————夢の残骸が散らばった砂浜と、その先に広がる大きく青い海だ。
きっと、あの水平線の向こうから、永い夜の終わりがやってくる。
終わらないでほしい、と願った幸せな夜も、哀しみと息苦しさに首を絞められた夜も、レオと熱い肌を触れ合わせ抱き合った夜も、ひとりで冷たい布団にくるまり目を閉じた夜も、いつだって永遠を感じさせた。
けれど、それとは裏腹に、夜は明ける。泉の幸せにも、涙にも、素知らぬ顔をして。音さえ立てず、ただ新しい光を引き連れて。
そんな夜明けが来るのを、寂しい、とも、待ち遠しい、とも思う。
赦されるとか、赦されないとか、世間の目とか世論だとか、そんなことはどうでもよかった。
この男が好きだ。
月永レオを愛している。
今はただ、それだけでいい気がした。
「セナ、」
絡められた指先が、切ないほど愛おしい。
手を引かれて立ち上がる。夜風に彼の赤毛が靡いた。
星の見えない夜に、レオの瞳だけが優しい輝きを放ちながら、揺れた。
「帰ろう」
れおくんがそばにいる、ただ、それだけでいい。
そう思いながら、温かい手を握り返した。
永い夜が、ゆっくりと、静かに、深まっていく。
◇
20171210
2 notes
·
View notes
Text
砂浜の教室
「アヅサはいいよね。学校以外に行くところあるんだから」
小5の夏、人間関係に悩んでいた友人にそんなことを言われた。
嫌なら話さなければいいじゃん、とかそんなことを俺は言ったのだろう。
彼の目にかすかにちらついていた怒りとも憎しみともわからない火の粉は俺の皮膚を焼いた。火傷みたいに。
「アヅやっぱり制服似合うね、中学の学ランもよかったけどブレザー着るとカッコイイ感じ。指定ジャージも送って! 友達とお昼食べてる写真とか送って、ていうかもう毎日何か撮って送って」
「そんな撮るものなくね? 」
「あるよ、もうね鞄とか文房具とか教科書ノートとか全部見せて欲しい。あー高校生いいな、俺もアヅと制服デートしたい」
机の上に立てたタブレットの向こうで、頭に寝癖をつけたユウくんがぼやいている。日本とカナダ・トロントの時差は約13時間。こっちが夜ならあっちは朝だ。練習を終えて帰宅するとユウくんからのスカイプが入っていた。朝ギリギリまで寝ている彼からすると珍しいことだ。
「昨日帰ってきたらそのまま寝ちゃってさ。9時間寝てんのこれでも。目が覚めたらもう寝れなくって、アヅが帰ってくるまで待ってよーって。あ、俺ね✖️✖️に日本に帰るよ。東京で仕事。平日なんだけどさあ」
リラックスして喋っていたユウくんの声が少し早口になる。先週新しくしたiPadはトロントとのスカイプもほぼ時差なく映すけど、目元のこわばりや声の硬さが伝わるほどではない。そのはずなのに、ユウくんの早口が俺の凪いだ心に雫を落とした。波紋が音なく広がりユウくんの緊張が伝わる。
「ごめ、平日は学校行かなきゃいけないから」
「だよね。東京からアヅんちだとギリ日帰りできないしなー。仕方ないね」
俺は一年の半分を海外で過ごす上、日本にいるときも調整や大会が入れば遠征にでかけてゆく。だからスノボ関連のスケジュールがない日は絶対に学校に行くことにしている。小中から父に厳しく言われたことだが、今は俺の意思だった。
けど、時々後ろめたくなる。ユウくんは俺以上に忙しく競技の他に取材や撮影、さまざまなタイアップをこなしていて、俺たちが会えるのはオフシーズンのそれも俺の学校のない夏休みか土日、そしてユウくんが帰国していてスケジュールの空く日。これらが合致する奇跡的なタイミングのみだ。学校、というのは恋人に悲しい思いをさせても優先するべきものなんだろうか。一日くらいいいんじゃないのか。けれどひとつ特例を作ったらほかの何かも瓦解する気がして、俺は未だ頑なだった。そしてユウくんはそれに対して何を言うでもなかった。
「シーズン前の帰国はそれでラスト?」
「ううん、お盆に帰れると思う。じいさんの初盆なんだ。時間作るからさ。会お」
それでもこの半年の付き合いでその奇跡が何度も起きて、話もしたし手も繋いだしキスもセックスもした。世界の未知をふたりでつかむような心地だった。「俺ら運命だよね」と言うユウくんのポジティブさを、俺は結構愛している。
「じゃあそろそろ支度するね。愛してるよアヅ」
7インチの画面の中で、小さなユウくんがウインクをする。ラテン系のスクールメイトと仲良くなってからよく使うようになった仕草だが俺はいつも即座に反応できない。曖昧に笑って通話を切った。
なだらかでない世界を克服してゆく、本質的な強度を備えているユウくん。不器用で怠惰であるがゆえに、世の中に振り回されて日常生活の些細な達成に喜びを見出す人とは違うところにいる。でも、無神経ではない。
石川さんの唇が数回、何かを言いかけて震えた。
初夏の日差しが教室に差し込み、学校指定のハーフパンツから覗く彼女の膝を照らしている。進学したと思ったら球技大会が始まり、間を空けずに体育祭がやってきた。俺は体育祭当日は遠征。一年はコスプレをしての応援合戦に棒倒し、四人5脚にリレーと種目が多い。当日不在なことと接触系が多いこともあって俺は競技の練習には不参加。いよいよ準備に大詰めのラスト一週間、俺にあてがわれたのは横断幕の作成だった。
俺は絵も字も書けない、というかペンキ自体触ったことがない。ペイント用のクラッカーの方がまだ馴染みがある。幸いにもひとりではなくて、足首を捻挫していて体育祭に参加できない石川藍は俺より少しは頼りになりそうだった。
「いいフォント探して、それ拡大コピーしてレタリングしよ」。石川さんはスマホに「黎明」と表示させて俺に突き出した。チームのお題、というかテーマ。読み方を尋ねると石川さんは呟くように「レイメイ」と教えてくれた。
そうしてスマホとコンビニのコピー機を駆使して、俺たちは横断幕サイズの「黎明」の文字を手に入れた。カーボン紙を敷いて、A3のコピー用紙をパズルのように並べてゆく。コピー用紙の上を膝で移動するとぺたぺたと音が響く。それくらい教室は静かだった。ブラバンの音が遠く響いている。
「…音楽かけてもいい?」
静寂と、慣れない人が至近距離にいるのが落ち着かなかった。かと言って何を喋っても続かない気がする。
石川さんの唇が何かを言いかけて震え、恐らく始めに思いついたのとは違う言葉を差し出した。是。
iPodを取り出して、あまりハードでないプレイリストをタップする。ゆるいヒップホップが教室の空気を眠くしていった。
体育祭は来週の水曜日。土日を考えると明後日の金曜までには完成させておきたい。なるべく忠実に元の字をなぞっていく。
「北野って結構几帳面なんだね」
「…そうかな。やったことないから怖くて」
「すごい丁寧だと思う。私もちゃんとやろ。今日美術の松田に‘もっと丁寧に書けっていわれちゃったよ」「…そう」「北野は芸術、何とってるの」「音楽」「ああ、それっぽい。河野くんとかと一緒だ」クラスの半分は名前と顔が一致しない俺だが、コウノとは初日に‘やべえ! 銀メダリスト!’と声をかけてきて以来、多分そこそこ仲がいい。「河野くん、歌上手いよね。応援歌練習のとき隣だったんだ」「そうかも。桑田佳祐のモノマネも上手いよ」「あーそれ聴いたことある! わかる! ぜつみょーに上手い!」石川さんは鉛筆を掲げるように振って歯を見せた。靄がかかっていた教室に花が咲いたみたいだった。「あいつノートとか貸してくれるし、助かってる」「ああ北野いないこと多いもんね」「体育祭の日も遠征だからこの横断幕、デビューするとこ見れない」「じゃあ写真送ってあげる。LINE教えて」言われるままに画面を開く。俺のアイコンはチョコバナナ。ボード仲間のタクミが勝手に設定した。「片山じゃん」「…?」「かたやま」石川さんは俺が聞き取りやすいようにか、気持ちゆっくりと発音した。ゆるい川のように流れていた会話が俺の側で滞る。石川さんが顔を上げた。ああこれきっと、いつものやつだ。俺だけがわかんないやつ。「世界史の片山、タイと靴下の色合わせるじゃん。前に茶色いスーツに黄色いタイと靴下履いててさ。それがチョコバナナっぽいって。私の周りだけの内輪ネタだったかも、ごめんね」石川さんは過剰に笑う。笑顔にペンキをぶちまけるように。ペンキの飛沫は俺の膝を汚して、それ以上は侵食してこなかった。プレイリストのヒップホップが会話の空白をゆるく埋めてゆく。
中学は小学校からの持ち上がりで、義務教育は同じメンツで過ごした。あまり行けない学校はそれでも人見知りの俺にとってはどこか安心する場所だった。「高校で色んな出会いがあるといいね。俺とかアヅは普通の学生やってたら全然会えない人にたくさん会えるけど、学校の友達って特別だから」俺の入学前にユウくんが言っていた。俺には地元の友達もスノボ仲間もスケボー仲間もたくさんいて、仲間を積極的に増やす必要はないような気もする。けれどそれらはほとんど年上の人たちだった。そのことに対する漠然とした危機感と、新しい制服に身を包んだ高揚感が俺の舌を走らせた。
「俺、あんまりそういうのわかんないんだ、一年のうち8ヶ月くらい海外にいるから、日本の流行りとか全然わかんない」言いたいことはそれではないのだけれど、伝える語彙がない。世界史の教師のスタイリングは日本の流行りではないのわかっているが、もっと言うなら暗黙の了解だとか、これを言うとみんなが笑う、みたいなのがわからない。言語、価値観、それはなんて言うんだろう。もっとつかみどころのない、明日になれば忘れるランディング。
「そういうのってかっこよさじゃん」
石川さんは手をとめず、ハーフパンツの裾をまくるの同じナチュラルさで言った。
「ううんと、北野がそう言えるのってかっこよさじゃん。内輪ネタなんて大事なことじゃないし、学校を一歩出たら伝わらないしね」
その通りだ。この学校の広さはどれくらいだろう。そして世界はその何倍あるのだろう。教室の30人と、この時間にしか存在しない頼りないマークのようなもの。けれど時々、そんな薄雪のようなものが欲しくなる。ピンで刺した場所だって、ピンが増えればいつか大陸になる。ユウくんもこんな気持ちになったことがあるだろうか。
「わかったらわかったで面倒だよ。私とかそういうものばかり気にしちゃう。ソフトやるために来たのにさ」
「…ソフト部なんだ」石川さんは恐らく気を使って、自分を下げて言ってくれているのだろうに、俺のコミュニケーション能力ときたらこれだ。石川さんは足首のギプスを振り返って「これだけどね」と呟いた。まつげの先に光が粒を作っている。骨を感じさせないまるい頰が、やけに幼くみえた。
「体育祭出れないメンツふたりで横断幕つくることになった。相手女子だし俺人見知りだから沈黙作業になるかと思ったけど、少しコミュニケーションがとれた。俺も少し成長してね???」
帰り道、バスの中でユウくんにメッセージを送る。時差があるのでリアルタイムの返事はない。ユウくんがくれたイヤフォンは重低音がよく響く。窓の外を景色が流れてゆく。田植えの終わった水田から短い���がまっすぐ天に向かってのびている。その清々しさと黄色くなってきた光の物悲しさがせめぎ合う時間帯だ。作業着のじいさんが腕を組んで農道に佇んでいる。次の角を曲がると海が見える。俺はこの山と畑と田んぼと海しかない田舎を結構愛していた。冬はこの町にいることはほとんどないから、春と初夏の風景を。
横断幕を作る作業はあと1日。嫌な作業でなくてよかった。学校に行くのが億劫になってしまうのは避けたかった。夜、練習から帰ってきたユウくんと少ししゃべった。「どんな子? かわいい?」「んー、運動部って感じ」「そうでもないってことね。何話したの?」「暗黙の了解。教師のあだ名とか。俺がそういうのわかんないって言ったら北野はそれでいいんじゃないみたいなこと言われた」「あー、俺らあるあるだよね。学校の内輪ネタみたいなのわかんない」「そうそれ。寂しいわけじゃないけど、わかんねえなって思う」「アヅは気になるの?」「んー…」画面の向こうではユウくんがストレッチをしている。股関節がべったりと開く。「気になる、っていえば、なる。…」沈黙が落ちる。俺は思ったことは似たような言葉に乗せないでちゃんと船を作って相手に届けたい。面倒なときもあるけど、少なくともメディアで喋る時とユウくんと話すときは逃げないでトライしたい。ユウくんはこの沈黙を許してくれて、かつ罪悪感を持たなくて済む珍しい人だった。「小中は同じメンツだったから、あんまり感じなかったけど。俺はクラスの人全部覚えてないけど向こうは俺のこと知ってて。お客さんみたいに扱われてる感じがする。それが学校だっていうのが、何か、俺だけ置いてかれてる気がする。みんな同じバスに乗ってるところを原付で追いかけていくみたいな」でもそれって、内輪ネタがわかんないからってだけなんだろうか。「ああ、置いてかれる、ね」ユウくんは笑うと目がすっと細くなる。「ちょっとわかるよ。あー、アヅの近くに行きたいな。嫌かも知れないけど、俺と次会うまでその気持ち持っててよ。消化しないで時々思い出して、新鮮なままにしてて」
俺が所属するのはスポーツ科で、学校が力を入れている野球と陸上、ソフトボールの生徒が多かった。スノーボードをやっているのは俺だけだ。寮生活をしてる奴も多いからか、自然と部活ごとにグループができる。自然とぼっちになりかけた俺によく絡んでくれるコウノは陸上部だった。日焼けしていて手足が長く、眉と髪がいつも嫌味なく整えられている。コウノと一緒にいる陸上部の奴らもよく声をかけてくれる。石川さんからみたら、俺もこのグループにいるように見えるんだろうか。
三限の移動教室の帰り、講義室Bに忘れ物をした俺はひと足遅れて階段を降りていた。視界の端には教室の前に備え付けられたロッカーが見える。その手前で女子がひとつの生き物のように塊になっていた。抱きついたり顔を寄せたり、女の子のコミュニケーションは密だ。みんな短髪で日焼けしている。制服と同じようにそれが揃っていて、その中に石川さんを見つけた。これがソフトボール部の子たちか。ふと、楽しそうにじゃれあっていた女子たちが動きを止めた。ほんの一瞬。その瞬間に彼女たちは分裂するように個々の生き物になった。石川さん以外の女子はお互いに顔を見合わせて、困ったような含み笑いをして教室に入っていく。
不安げに視線を上げた石川さんと目が合った。彼女の唇はわなないていたけど、言いたいことがあるようには見えなかった。喉の奥にぬるいものが引っかかる。石川さんはこの光景を誰にも見られたくなかったろう。迷った末に挨拶のつもりで左手を挙げた。彼女は眉を釣り上げ、肩をいからせて教室に駆け込んで行った。
さらさらと天気雨が降っている。教室は昨日より暗くて、机を寄せて作った作業スペースが昨日より広く感じた。
下書きを終えた俺たちはペンキで文字の縁をなぞり始めた。黎明。レイメイ。石川さんは俺の斜め向かいで筆先を睨むように作業していた。今日のプレイリストはトゥデイズヒッツ。洋楽邦楽男女ソロバンドグループ。スマホは脈絡のない音を流し続けて、音は砂のように俺たちの間に積もっていった。「…この曲」「うん?」積もった砂を蹴ちらさない、静かな足取りのような声。「✖️✖︎駅ってタイトルじゃん。うちの実家の最寄駅なの。待合にこの曲の宣伝ポスターたくさん貼ってあってさ、この人のファンクラブみたいになってる」「…そうなんだ。✖︎✖︎駅ってどこにあるの?」「S区」「へえ。じゃあ実家東京なんだ」「そう」砂が積もり続ける。このままでは泥になる。こういうときユウくんならどうするんだろう。石川さんがすごくコミュニケーションが上手いとか、すごく美人だったら俺の舌ももう少し饒舌だったのだろうか。興味を持って。昼間見た光景が蘇る。俺は何もしてやれないし、それについて聞くのも気持ち悪がられる気がした。この場だけの会話を楽しく進める方法も思いつかない。泥に足をとられる。
石川さんが立ち上がり、部活用のウインドブレーカーを羽織って戻ってきた。日焼けした指先には血の気がない。女の子には今日の気温は寒いのだろうか。このまま泥に膝まで浸かって時間をやり過ごすのはダサい気がした。小学生のときに言われた「アズはいいよね」という言葉を思い出す。そうだ、だって俺は命がけでその居場所を作っているのだから。でも本当にそれでいいんだろうか。誰かのことを一生わからないとしても、まだ諦めるのは早い気がする。ユウくんのことを思い出した。石川さんの額をじっと見た。ユウくんは俺から言葉を引き出したいとき、何も言わず目に力をこめる。自分の視線の力を疑わないかのように。「…何?」石川さんの声がざらついた。胸の奥が冷えた。逃げないためには地面を踏みしめなくてはいけない。期せずして我慢比べのように石川さんと睨み合うかたちになってしまった。
泥から抜け出したい。
開け放した窓から入ってきた風が布と床の隙間に入り込み、布を波打たせた。文字とそこに停滞していた空気がふわっと動き、視界が揺れたみたいな印象を与えた。見ていた俺の脳髄が揺れたのかもしれない。
先に表情を解いたのは石川さんだった。肩を落としてゆっくりと静かに息を吐く。「何か言いたいことあるなら言ってよ。先回りして私に考えろっていうの。いくら北野がスゴイ奴だからってそこまで私にさせる権利ない」石川さんが身体中にトゲを立てた。今度は俺が唇を震えさせる番だった。うん、とか、えーと、とか言えば言うほど自分を追い詰める言葉しか出てこない。「…4限の前」「やっぱりそれかあ。北野って結構おせっかいっていうか、スマートじゃないよね」踏み入った報復とばかりに、石川さんが俺の心を刺す。その声は低く、けれどふくらみがあって、どこか優しかった。丸い頰の石川さんんが俺よりずっと年上に見えた。
「なんか、気になって」「うん」
「4月の初めにたくさん雪が降ったの覚えてる? さすが新潟だね雪ヤバイ、って言ったの。ちょっと調子に乗ったようにか、無神経に聞こえたのかな。みんなに、直接は何も言われないけどすごく嫌がられた。東京から来たんだもんね、って。なんかそれから、部活も寮も馴染めない。シカトとかハブるとかはないけど、私が話すと、まあ見たとおりだよ」石川さんは所在なさげにギプスに触って、ぐにゃりと顔を歪めた。「でもまだ学校入って2ヶ月だし、家にも帰れない」「…ごめん」「謝るくらいなら聞かないでよ、何がしたいの」「うん」
プレイリストはいつの間にか終わっていて、ハードなヒップホップになっていた。ラッパーのしゃがれた声が教室に似合わない。‘SNSでくだらねえことを垂れ流す豚になるな。俺らは先へゆく。’ボードに乗っているときはあれほど高揚感をくれる音や言葉が、はるか遠くに聞こえた。雨はいつのまにか上がっていて青い空だけが浮かんでいた。
「じゃあ私も北野に聞くよ。何がいいかなあ…」
石川さんが、きっと優しさでもって空気を動かす。彼女が新潟の女の子にとって無神経に見えたとしても彼女が優しいか否かとは別の話だ。
「北野、彼女いるの」
相変わらず俺はダサく絶句するしかなかった。絶句。四句。杜甫。テストに出すって今日古典の中村が言ってた。行く先々で聞かれる質問なのでそれなりに答えは用意してあった。けれど今は、自分の心の柔らかい部分のベールをあげてくれた石川さんには、それで答えるのはフェアじゃない。不道徳や道ならぬことより今は嘘のほうが罪が重い。
「あっ人に言えない感じ? 人妻とか⁉︎」
「…人妻じゃない。年上だけど」
「ふうん。どっちから告白したの? 北野?」
首を振る。テーブルの下で手を握られた日のことを思い出す。‘俺ら付き合うべきだ。そう思わない? ’初めて目が合った時から、俺はユウくんの言うがままだ。
「何だ違うの。いいね、私も好きな人がいるんだ」
気づけば文字の着色が終わっていた。石川さんが四隅を引っ張って布をぴんと張り直す。その一方で、俺たちを繋ぐ微かな糸がたわむ。
「これで乾かして終わりだね。今日はこのまま帰ろ。私明日、朝練の前に来て後のことやっておくから」
「…ありがとう。頼む。コウノとかに手伝わせる? 俺、言っとくけど」
「今の私が男子に手伝ってもらったりしたらまじでハブられかねないからやめて。北野と作業してるのだってギリギリなんだよ。大丈夫、あの子たちこれくらい手伝ってくれる」
石川さんは安心しきれない悲しい顔で笑った。
下足箱の前でスニーカーに履き替える。いつの間にか雨はやみ、外は白いほど明るくて、校舎の中は真っ暗だった。しばらく学校に来れないから、教科書やワークブックを詰め込んだデイパックが肩に食い込んだ。校門を出るとようやく深く息が吸える気がする。帰ったらスケボーに乗って体を温めて、夕飯を食べて体をよくほぐしてから車に乗ろう。
校門を出て左に曲がって、フェンス沿いを歩くと公園が見えてくる。いつもはうちの生徒もたむろしているけど、今日は体育祭の前だからか小学生ばかりだった。ひとりだけ、フードを被った若い男がリフティングをしている。フリースタイルフットボールだろうか。あまり上手くはないけれど、この辺では珍しい。ウエアがアンダーアーマーなのが日本っぽい。サンクレメンテで見るボーラーたちはみんなNIKEかPUMAだ。
「…はっ?」
腹筋が動いた。結構なボリュームで俺は間抜けな声を出して、耳からイヤフォンを引き抜いた。
ボーラーは俺の姿を目に止めると手を振ってゆっくりと近づいてきた。背後の民家の二階の窓が揃って青く浮かび上がる。
「アヅお疲れー。わあ本当に高校生してる、制服眩しー。そろそろかなって電話しようと思ってたところ。アヅから見つけてくれるなんて、俺たち本当に運命だね」
「いや何してんの。は? 東京で仕事って言ってたじゃん」
「明日からね。空港から直で来ちゃった。北陸新幹線サイコー」
「じゃなくて帰りは」
「新幹線じゃ間に合わなくても、車なら明日の朝までに帰れるんだなあ。プータローしてる友達がいたからバイト頼んだの、あとで合流してレンタカーで帰るから安心して。車の中で寝てけるし。アヅ電車の時間まであと50分あるでしょ。っていうかせっかく来たんだからもっと喜んでよ」
何で俺の通学電車のダイヤを知っているんだ。いやユウくんならそれくらい調べる。GoogleアースとGoogle検索を駆使して、徒歩電車バスの乗り継ぎまで把握してるだろう。
「マジで? そのために来たの? その、50分のために?」
「うん、本当はアヅの家まで送って行きたいんだけど、車の中じゃふたりきりになれないからね」
そういう問題ではない。ベンチに座らされてミネラルウォーターを渡される。俺の好きな銘柄。ユウくんが使っていたサッカーボールはところどころ擦り切れていた。誰かの忘れ物を使っていたのか、それくらい使い込んでいるのか。全く判断がつかなかった。 されるがままにペットボトルを開けて水を口に含む。キンとした冷たさが額に響いた。渦を巻いていた言葉たちが凪いできた。
「ユウくんがうちのうちの学校の前にいんの、なんかシュール」
「ええどういう意味? 夢みたいってこと?」
「夢みたいにありえない。ていうかユウくんいつからフットボール始めたの」
「んんーついこの間。ネットでストリートスポーツ見てたら見つけて。スケボーとかスノボはできないけど、これならできるかな? って」
それであんまり上手くなかったのか。氷上でなら世界一をとるユウくんが���ールを転がしている姿は結構不恰好だった。俺は微塵もスケートに関心を示さないのに、この人はエクストリームスポーツやストリートスポーツに興味を持ってくれる。こういうところがユウくんと俺の違いなんだろうか。いやもっとシンプルなものか。時間だとか体力だとかを考慮して、たぶんほとんどの人は50分のために片道6時間をかけて移動はしない。けれど最後に決めるのは自分だ。自分で決めて、欲しいものは手に入れる。それを突き詰めるとこんな変な人間になるのだ。俺はユウくんのつるりとした頰に触れた。
ベンチでの時間は瞬く間に過ぎた。ユウくんと肩を並べて駅までの道を歩く。身長差が7センチもあるので、俺がユウくんに話しかけるときは自然と斜めから見上げる格好になる。
「ユウくんは高校の友達と今でも会ってる?」
「んー? 俺高校で友達ほとんどいなかったよ。うちのスポクラ、男子は野球部多かったから。俺とかすごく嫌われてた。わかるでしょ?」
「え、自分は友達いないのに俺には友達作れって言ったの︎」
「そうだよ。俺友達欲しかったし。アヅ、この間のLINEで‘ちょっとコミュニケーションとれた’なんて無理してたけど、その女の子と少しちゃんと話せたみたいだね。この間俺がそのままでいてって言ったのに、今寂しくなさそうだよ」
それはユウくんが来てくれたからだろう。ふと、学校を振り返った。駅までほど近いところまで来てしまってはもう校舎は見えない。石川さんはもう帰っただろうか。居辛いという、寮に。
改札は人がまばらだった。「キスしたいな」というユウくんを小突いた。肩を引かれ、7センチ上から唇を寄せて囁かれる。「じゃ、次会ったらエッチしよ」もう一回小突く羽目になった。ユウくんは目を糸のように細めてケラケラ笑っている。得体の知れない魔物のように。フィストバンプをして別れを告げる。「来てくれてありがとう」「んん、いつでも。アヅがいるところに行くよ」
定期を通して改札を通って、何度も振り返った。ユウくんは胸のあたりで手のひらを振っていた。テレビで見るより少し無骨な仕草だった。‘アヅサ’と、声を出さずに口のかたちだけで俺を呼ぶ。普段呼ばない本名を呼ばれて、どうということはないのに鼻の奥がじんわり熱くなって、イヤフォンを耳に突っ込んだ。会えない時間より別れの瞬間の方が、心が台風みたいになる。
翌日、空港に向かう道中で車であくびをしていると、石川さんからメッセージが届いた。「頑張ってね」の言葉と櫓にかけられた‘黎明‘の横断幕。雨は降らなかったようで、まだ人のまばらなグラウンドに俺らの旗がひらめいていた。
1ヶ月の遠征を終えて帰国すると、田んぼは力強く青さを誇っていた。俺は初めての夏服に袖を通してユウくんに写真を送った。帰ってはきたがひと息ついている暇はなかった。南半球のオンスノーで得た手応えとか課題を日本でこなさなくてはいけない。そうしているうちにあっという間にシーズンインだ。俺の一年は子どもの頃からスノボでまわっている。
久しぶりの学校は少し緊張した。コウノはわざとらしい大声で歓迎してくれた。そこで俺はやっと石川さんが退学したことを聞いた。コウノは「体育祭から後くらい? からこなくなった。先週HRで川北先生が退学しましたって言ってたわ。家庭の事情だって」と特に何も知らない様子だった。やがて石川さんの話題は夏の高校総体の話や考査の範囲にこぼれ落ちて波に飲まれ、ゆっくりと俺たちの足元に沈んでいった。
あのとき石川さんのメッセージに俺はなんて返したっけ。ありがとう、とかそんなだった気がする。もっと何か聞くべきことがあったのは知っていたけれど、帰ったら会えるしまあいいか、と手を止めていた。トークルームを開くと石川さんのアカウントはunknownになっていた。昼休みにベランダで電話を鳴らしてみたが使われていない番号です、というアナウンスが遠く響いた。
石川さんのギプスと、ユウくんのことを思った。担任に食いさがって連絡先を教えてもらうとか、クラスの女子たちに手当たり次第に聞くとか、やってるかわからないけどSNSを辿るとか、きっと何かしら石川さんに連絡をとる方法はあるだろう。けれどそれをして、俺は彼女に何を言うんだろう。ユウくんとのトークルームを開いて閉じた。ユウくんは誰よりも好きな人だけどこの気持ちは共有できないし、間違わずに手渡せる自信がなかった。石川さんは辛さを俺に渡してくれたのに。
みぞおちの奥に、さらさらと砂が積もっていく、砂浜のようなあの教室を思い出す。退屈で薄暗くて、蜂蜜みたいに濃密だった時間。「きたのーメシ食おうぜー」とコウノが窓から顔を出した。上手く笑えない笑顔で返して、俺は教室へ戻る。外の明るさに慣れた目が、一瞬教室の中を暗くした。すぐに目は慣れてしまって、俺は教室の喧騒に溶けていった。
0 notes
Text
つまらない男
パラレル「御使命入りました」のさーらーに、パラレルの世界を書いてみた。 例えこんな話でも 一護お誕生日おめでとう
気合いいれまくった男女に紛れて、
その女は特につまらなそうというわけでもないが、やる気を見せることなく友人が薦めた赤ワインをちびりちびりと嘗めていた。
「難しいゎ、なんつーか俺に誘われてもウレシくなさそう……心、折れそう」
やはりウマイこといかないのか
煙草を吸わないくせに、わざわざ喫煙所まで報告に来た友人は愚痴を聞いて欲しいようだ。
「他にも女いっぱいいるじゃねぇか」
「いや、なんつーかあんまりガツガツしてんのもめんどくさくね?」
「俺にはこんな処に金払って出会い求めに来てる奴等全員めんどくせーよ、おまえ含めてな」
「そんな事言うなよ~、そりゃおまえはリアルにモテるからよこんなのばかみたいに思えるだろうけどさ、結婚してて相手いても寂しい時ってあるじゃん。後腐れない関係作れるのわかって皆こうやってさ、楽しめる誰かを探してるんだよ」
へ・ぇ~
と黒崎一護はあからさまに馬鹿にした声を出した。
全然わっかんねーと一護は思う。
知らない誰かと出会うために金を払って気を使って。
そんなことをする事自体面倒臭いしそんな事で体力も気力も使いたくない。
だいたいー
「既婚者パーティー」ってなんだよな。
そのネーミング自体最悪だし、ホテルを会場にして爽やかに小綺麗に真っ昼間から集まってきてんのは、結婚してるけど仲良くしませんか?セックスしませんか?なんて相手を探す場所だろ?
恥ずかしいとかいう羞恥なんかない女ばかりかと思うとどんなに可愛らしくされても萎えるだけだ。
「悪かったよ……おまえがこういう場所好きじゃねーのわかってたけどさ……
俺もう離婚確定してるし、せめてバツイチっつーレッテル貼られる前に来てみたかったんだよ……」
「バツイチのがモテんじゃねぇの?」
「ぶゎぁーか! バツイチバツニなんてモテねぇよ、何か問題ある男と思われるのがオチなんだぜ?それよりは家庭を大事にして仕事もあって余裕がある男の方が今はモテんのよ」
「ふ~ん……」
適当に返事をしながら
家庭を大事にしてる男が女がこんなとこに来るかねぇと思ったが口にはしなかった。
「結婚しちゃうとさ、恋愛とは違う愛情にしかならないだろ?友達とか家族みたいな。でもやっぱさ、いつまでも恋愛してたいじゃん。俺んとこはもうダメだけどさおまえは奥さんは奥さんで好きだろ?でも昔みたく好きじゃないだろ?」
「……いや、あんまり。変わんねー……けど」
「ごちそうさま!」
ケッとわざと吐き捨てるように、笑いながらではあるが友人は唾を吐く真似をした。
あ、そうか
今のは俺が
昔と変わらず妻を愛してると思ったのか。
まぁ
そう思われてる方がいいよな
人として
「……悪かったって。愛妻家のおまえを無理矢理こんなとこ連れてきちまって。じゃああと一時間適当に飲んだり食ったりしてくれよ。ホテルなだけあって飯は旨いからよココ。シャンパン飲み放題だしな」
「あぁ、そうだな」
「やっぱ、絵にかいたような夫婦もいるんだな……
おまえんとこ、奥さんおまえにメロメロだしおまえも一途に奥さん変わらず愛しててさ……幸せだよな、それが一番だしな」
「……さぁねぇ?」
それ以上突っ込まれるのも嫌で、笑いながらフラりと喫煙所から出れば友人も追いかけてくる。
「それにしても、なんであの子もこんなとこきてんのかねぇ」
「ん?誰?」
「俺が口説こうとしてた子。おまえと同じかな、誰かのつきあいかな。でも前もいたとおもうんだけどなぁ……」
「単におまえが好みじゃねぇんだろ?」
「うっせ!!でもあの子いつもあんなよ?可愛いから気になってよく見てんだけどさ。いつもフラフラ~としててさ」
「……ふぅん」
「がっついてないから声かけてみれば?暇潰しに。もしおまえがあの子口説けたら今度からお前を師匠と呼んでやるよ」
「呼ばれたくねぇし」
くだらねぇ、と笑いながらホテルのその一室に戻る。
いつのまにかテーブル移動の時間になっていて、主催会社の司会の人間にこちらのグループですよーと案内された。
連絡先の交換は任意との話しだったが
とてもじゃないが嫌とは言えない雰囲気だった。
おかげでラインリストがいきなり華やかになった。
どうせ後で消しちまうけど���
楽しそうにしている男女を見ていると、自分は冷めてるんだなぁとなんだか少し悲しくなる。
結婚していて、30~40歳の男女が
普段ならいい大人で
いい親であるような奴等が
学生に戻ったかのようにはしゃげるのは
楽しいことなのかもしれない。
それに便乗できない自分は
このまま年老いて死を待つだけなんだろうか?
孫でもできれば生き甲斐になるのだろうか?
気が付けば友人は、一人の女に声をかけられて楽しそうに話していた。
俺の視線に気がついてちょいちょいと手招きをしている。
「真澄ちゃん、コイツ、俺の友達!大学教授なんすよ」
「ぇえ~!この若さで教授ぅ?すごぉい!」
「昔から勉強しか好きじゃなくてね、こいつの趣味は論文書くことだし。でも生意気に結婚して子供もいてなんかムカつくよね!」
「え~でもぉ、此所にいるってことは新しく出会い求めてるんですかぁ?」
「イヤイヤイヤ、俺が無理矢理連れてきちまったのよ、こいつあんま遊ばねーし息抜き必要かなって」
「え~?うそーぉモテそうですよ~?」
モテそうってなんだよな
つーかまじ意味の無いこんな会話、疲れるだけだ。適当に笑ってがんばれよと友人の耳許で囁けば、右手の親指をグイっとたててウインクしてきた。キモい。
時間までどうすっかな、と思ったところで
さっきの彼女を、みつけた。
綺麗に微笑んで、男と談笑している。
確かにこの女はあまり気合いが入っているようにはみえない。
白いワンピースに焦げ茶のハーフブーツ
グリーンのカーデガンと可愛らしい装いだが
ここはセックス前提の「お友達」を探す場所なんだろうから
それでその装いは色気がない。
確かにガツガツはしていなさそうに見える。
俺と同じで誰かのつきあいなんだろうか?
「何飲んでます?」
声をかければ俺の方に顔を向けた。
背も驚くほど小さいが顔はもっと小さく感じる。30越えてるとは思えない。
まるで少女のようだ。
「マティーニ。さっきの人にいただいた」
「昼間からそんなの飲んで平気なの?」
「別に、たいしたことないよ」
「酒、強いんだ」
「どうかな、普通かな?」
ふふ、と彼女は俺から目を反らしてまたグラスに口をつけた。
「イイ人みつかりましたか?」
こっちを見もしないで彼女が聞いてきた。
「そっちは?」
「どの人も素敵で、よくわからない」
「品定め中?」
「いや、もう目だけでお腹いっぱいだ」
「へぇ。話して酒飲んで、もういいんだ」
「あぁ、もういい。楽しかった」
「楽しかったんだ」
「楽しくないのか?」
「俺?」
「他に誰がいる?」
くすくす、と笑う。
「俺は…あんまり。こういうとこ、苦手で」
「…へぇ」
話が続かない。
せめてじゃあなんでここにいるの~?とか
そんな感じ~とか言ってくれればいいのに
と一護は思う。
「こういう場所で何が楽しいの?」
「ぅん?」
問うような顔で俺を見上げる。
澄んだ紫色の大きな瞳だった。
「楽しいよ、色んな人がいて。こうしてお酒もおごってもらえるし」
「……酒なんて、こういう場所じゃなくてもあんたならおごってもらえるだろ?」
「何だ?バーとかであちらのお客様から、みたいな?ふふ、そんなドラマみたいなことこそあるのか?」
「……や、わかんねーけど」
「一人でバーなど行かないし」
「行かないの?」
「行くのか?」
「……行かないけど」
くすくす、とまた彼女は笑う。
話が噛み合わないような、それなのにもう少し話してみてもいいかなと思わせる不思議な女だと一護も笑った。
「よく、これ、参加してるのか?」
「たまぁに。楽しいし」
「……仲良くなった奴とかいるの?」
「いたら、来てないんじゃないかなぁ」
「そだな」
かわされてる、と思う。
この女は自分に興味がないのだと鈍い一護でもそのくらいは気づいてしまう。
そしてそのことが少し悲しいような寂しいように感じてしまっていることに戸惑いを感じた。
一護は今まで生きてきて、常にちやほやとされていた。だからこの女の態度にどうしていいのかわからないのだ。
「楽しまないと、損だぞ」
「……ここで?」
「ここだけじゃない。どこにいても自分の在り方で楽しくもつまらなくもなるんだ。あとどれだけ生きているのかわからぬが、人生楽しまねば損だと思わぬか?」
この時だけは彼女はふわりと笑ってそう言った。
あれ?
笑うと可愛いんだ、と和むのが自分でもわかる。
「なぁ」
「ん?」
「ここ、出たら飲みに行かないか?」
「何故?」
「……もう少し、あんたと話してもいいかなと思って」
「はなしてもいいかなと思ったのか」
一護の言葉を復唱して彼女は初めて顔を崩してケタケタと笑った。
「やめておくよ」
さらりと断られて一護はたじろぐ。
誰かに断られたことなんてない一護は、即答で断られたことにまたしても戸惑う。
「話、別に面白くないし。そんな上から誘われても私も困ってしまう。私もそんな面白い女ではないから」
「…………え?」
「私は男は顔じゃないんだ。一緒にいて笑わせてくれる人がいいんだ。すまないな、でも貴方はどこの女達も噂していたから飲みに行く相手などすぐ見つかるよ」
ではな、と
マティーニを飲み干して彼女はにこりと笑った。
「待てって」
反射神経だけは無駄にいいから
逃がす隙なく彼女の腕を掴んだ。
「……何?」
「ひでぇ言い種じゃねぇの、話つまんないとかさ。たいして話してもいねぇのに」
「今話していたではないか」
「社交辞令みたいなもんだろ?」
「……貴様、何の仕事をしている?」
「大学の、講師」
なんとなく
教授と言えなかったのは
この女はその単語に飛び付くこともなく、興味もないと思ったからだった。
ましてや教授と言ってそれで?と言われそうな気がしたのだが
「講師?それでやっていけてるのか?」
大きな瞳を真ん丸にひんむいて
結局同じような言葉を返された。
「話が面白くないからてっきり、普段人と話さない仕事でもしているのだろうと思ったよ」
「失礼すぎやしません?アンタ」
「そうか、すまぬ」
「旦那もそうなのか?話がつまらねーの?」
ふるふる、と彼女は首を振る。
「とても面白いよ。誰といようといつでも相手を楽しませてしまう人だ」
少し自慢げに言う彼女に一護はとてつもなく意地悪な気持ちになる。
「あんたのことは楽しませないとか?」
「いや、同じだ」
「そうか?ならこんなとこで楽しませてくれる相手を探す必要ないんじゃねぇの?」
「違う、私のこともいつでも全力で楽しませてくれるよ」
「嘘つけ、おまえの話は矛盾だらけだ。相手にされないかおまえのことは楽しませてくれねーから、こういうとこで男探してんだろ?楽しい男を」
ついむきになってそう言い返してから
言い過ぎだ、と瞬時に反省してごめん、と呟いてしまう。
「……謝る、か。貴様はやはりバカなんだな」
「……は?」
「それだけ酷いことを言ったのなら、謝らないで言いっぱなしでいればよいのに。即座に謝る方が人を傷つけるとは思わぬのだな」
「…………」
ぱん、と掴んでいた腕を華麗に跳ね返された。
「じゃあな、顔だけセンセイ」
そう言うと彼女は一護を見ることなく扉から出て行った。
なんだよ
なんなんだよあの女
いや今のは俺が悪い。
多分俺が傷つけたんだ
ていうか
顔だけセンセイってなんだよそれ!
「あれ……?」
今、一護が走ってた?
帰ったのか?
まぁいいか。あいつには此所楽しくなかったみたいだし。たくさんの女に囲まれてたら愛する奥さんに会いたくなっちまったのかな?
走る一護なんて初めて見たなぁ
そんなに早く奥さんに会いたいのかねぇ
友人はぼんやりそんな事を頭の片隅で思いながらも、この女の子とこの後ホテルまで行かれるだろうか、どう口説こうかと思い始めれば
一護のことなど簡単に忘れた。
◾
◾
◾
なんとかとっ捕まえて、何処でもいい、と雑居ビルの韓国料理の店に入った。
彼女はあからさまに不貞腐れた顔をしていたが、マッコリを一口飲むと
「……美味しい……」
と小さく呟いた。その声が少しだけ許されたように聞こえてしまうのは一護の思い過ごしかもしれないが。
「連絡先の交換もしないで店に連れ込むとは、随分強引だな」
「アンタ逃げるから……逃げなきゃ、ちゃんとしてたよ」
「……ちゃんとするとはどぉするのだ?」
こてんと首を傾げて、多分態とであろうかわいい声にかわいい顔をしている。
騙されねぇけどなと心で呟きながら
「……連絡先を聞いて、ラインとかで話して……それから飯に誘うとか、普通なら俺だってー」
「つまらん。やはり貴様はつまんない男だな」
「…………」
「あのなぁ」
「なんだよ」
「わたしはサディストではないのだ。だからいちいち貴様に傷ついた顔をされるとげんなりするんだ。楽しくないのだが」
「じゃあテメェも言葉を選べよ。さっきから何回俺のことつまんない男だって言い続けりゃ気がすむんだよ」
「だって…………その顔で立ち振舞いとか話すことがまんまで。そんな少女漫画のヒーローみたいではつまらないではないか」
「……それ、褒めてねえよな、やっぱ馬鹿にしてるよな」
「あぁ、褒めてはいない」
「……いやな女だな、おまえ」
「貴様も大概いやな男だからオタガイサマだな」
「じゃあ肉は自分で焼け」
「……わかった」
あれ?
最後の声は少し拗ねたような声だった、と一護はちらりと彼女を見る。
彼女は唇を若干への字にして肉をポンポンと鉄板において、またマッコリを両手で飲んだ。
「焦げるぞ」
「ん?」
「肉」
あぁ、と肉をひっくり返せば脂が落ちたのかボッと火が上がった。
「きゃあ!」
鉛の重い菜箸をすっ飛ばす彼女に一護はプッと吹き出した。
「生意気なくせに肉も焼けねぇのかよ」
「違う!驚いただけだ!」
「あーぁ、焦げちまってるし」
絶対普段男に焼いてもらうタイプだなコイツと思いながら一護は焦げた肉を自分の皿に取ると、新しい肉を手際よく焼いて、彼女の皿にぽんと投げ入れた。
「…………焦げたの、私のだから」
「いいよ、旨いの食えよ。焼けねぇならそう言えよ。焼いてやるから」
「…………すまぬ」
トーンの低い小さな声で謝る彼女に
あ、少し反省してんだ、と一護は何だか愉快な気持ちになる。
「普段もそうやって、貴様が肉を焼くのか?」
「いや?ウチは奥さんがやる。俺に何かされるのいやみたいでさ」
「ふぅん。うまいのにな」
「お、褒めたな?」
「良いところは褒めるに決まっておる」
「そうなんだ、ありがとな」
「別に……話はつまらなくても肉焼くのは巧いと思っただけだ」
可愛くねえ
やっぱりコイツ可愛くないわと思いながらも
一護に肉を焼いてもらって嬉しそうな顔をしているのを見ているのは嫌じゃないと思う。
妻は自分の世話を焼きたがる。
それは出会った頃からそうで
それが女だと、愛する男にする事だと思っている節がある。
それをわかっているから一護も妻の好きにさせていた。
でもー
「さっきみたくしてもう一回食べたい」
「はいはい」
サンチュに肉と葱と味噌を挟んで渡すと当たり前のようにぱくんと食べる目の前の女の世話を焼くのは楽しい。
「旦那は焼き肉あんまり好きでないから、来たことそんなにないのだ。この野菜のくるくる巻きは凄く美味しいな」
「サンチュな」
「サンキュー」
「何今の?」
フフフ、と女は頬をリスみたく膨らませて笑った。ふと、焼き肉嫌いな男って珍しいなと
「旦那何してる人?てか、肉が嫌いなのか?」
と聞いてみた。
彼女はモゴモゴと咀嚼しながら首を振る。
「いや。……仕事先で、よく焼き肉行くから、家でまで食べたくないそうだ」
「……へぇ? 接待か?」
「……まぁ、そんなとこだろうなぁ」
「でもおまえは焼き肉好きなんだ」
「うむ。この店、気に入ったぞ」
「たまたまだ、俺も初めてだし」
「韓国語、知ってるぞ?」
「なに?」
「うんとな、ケンチャナヨ」
「なにそれ」
「大丈夫!という意味だ!」
どうやら美味しい酒と肉で女の機嫌は大変良くなったらしい。ちょろいじゃねぇかと思わず笑ってしまう。
「なんだ?」
「いや、ちょっとは俺に気を許したのかなって」
「美味しいものを食わせてくれてるからな!」
「……アンタ、それ、ちょろくね?」
「そうか?」
「そうだろ?結局話がつまんない男でも旨いもん食わしてくれたら心開くのかよ」
「う~ん、そうだなぁ…… 」
悩むのかよ!と突っ込めば女は笑う。
なんなんだこいつは。酔っぱらっているのだろうか。じゃあ聞いてみようか、と自身も少し酔いが回ってきた一護は女に話しかけた。
「なぁ、さっきの話だけどさ。旦那は誰にでも、おまえにも楽しませてくれるのに何が不満で既婚者パーティーなんかに行くんだ?」
「それは、だから言ったであろう?皆に同じな事が時々とても嫌なんだ」
「……はぁ」
「わたしは、妻なのに、奥さんなのに。でもおなじ。甘えられたり頼られればすぐに相手のために全力で力になろうとするんだ」
「……それ、悪いことじゃねーじゃん」
「……だから貴様はバカだと言うのだ。……私が泣けば頭を撫でてくれる。でも、仕事仲間が泣いても、頭を撫でてやるんだ。そういう、人なんだ」
「…………」
「誰とでも、距離が同じなのは、寂しいものだよ。だから……夫が誰かに頼られて、その人のことばかり真剣に一緒に考え出すと、わたしは今日の場所に行くんだ」
「……は?」
「浮気してやる!って悪い醜い私が顔を出すのだ。私が浮気したら、私のこと怒るかなみてくれるかなって、でも……」
「ちょっと待て待て待て。おい、それさ、焼きもちから随分な子供じみた事してんじゃねーか。要は旦那の目を自分に向けたいだけだろ?」
思わず呆れてそう言えば
彼女は少し泣き��うな顔をして唇を尖らした。
「あんなとこで会った相手にこんなこと言われるの嫌なのはわかるけどさ。おまえそれ、悪質だよ。それとも旦那はすぐ相談してきた女と寝ちまうのか?」
「……それはない!」
「じゃあ既におまえはやっぱり同じじゃねーじゃん。特別なわけだろ?」
「そうだけど、でも、夫が他の女の頭とか平気で撫でるのとか本当にいやなんだ。だから相手の女もすぐ勘違いする。それで平気でウチに来たりするんだ。旦那様にはお世話になっております~とか言って。夫もこいつの世話大変でさ、とか、も~ひどぉいとか……そんなの見せつけられると、浮気のひとつでもしてやろうかと、思ってしまったり……」
へぇ……
何だかうまく言えないが
女って難しいなと思う。
「で、あそこでそういう相手みつけられねーの?」
「というか……」
「何」
「結局、誰見ても話しても、夫を思い出して終わるんだ。帰ろう、と思ってしまうんだ」
「…………意味ねぇんだ」
「まぁな。でも、色んな人と話したりするのは刺激になるよ」
「へぇ……」
「元々ファンだったのだから。私は彼を裏切るなんてできないのだ」
「ファン?」
「……あぁ、……俳優業だから」
「まじで?」
「まじだよ」
「……あんた、名前は?」
「志波ルキア」
「志波?……まさか、まさか旦那、志波海燕とか言わねぇよな?」
「その、まさかだよ」
志波海燕??
今度は一護が菜箸を落とす番だった。
志波海燕とはカッコ良くて人がいい兄貴的存在の人気俳優だ。
それの、奥さんだというのか。
「……妄想じゃねえよな?」
「好きにとってくれて構わぬよ」
「……まじかよ」
志波ルキアは寂しそうに笑った。
「でも結局焼きもちからあんな処で出会い求めて気にかけてもらおうなんて、幼稚だぞ」
「……煩い」
「そのくせ、誰にも落ちないんだろ?浮気の1つできねぇんだろ?
旦那もそんなアンタのこと見抜いて笑ってるかもな」
「……!煩いぞ貴様!」
「図星だからって怒るなよ」
いつのまにか形勢逆転していた。
ふん、とそっぽを向いた彼女の横顔が震えていたのは見ない振りをした。
賢くて気丈な女だと思っていたが
悪いことをしようとして出来なくて
たかが頭を撫でるくらいのことで悲しんでる目の前の女は
ただの女だ
焼きもちを妬かれる
不貞したくてもできないこの女に愛される志波海燕が憎たらしく思えてくる。
なにも怖いものなんかないみたいな爽やかなあの笑顔の下で
奥さんが寂しがっていることなんか
知らないのだろう
芸能人の奥さまも大変だな
嫌味に聞こえないでくれと思いながら
そうつぶやいた。
志波ルキアはやはり煩い、と言った。
散々飲み食いして気が付けば12時近くになっていた。
終電もあるしそろそろ帰るか、と店を後にする。
「お腹いっぱいだ、もう白玉しか食べれない」
「白玉食えるのかよ」
「あれは別腹なのだ」
ふふふ、と笑う彼女の白いワンピースに
焼肉のたれが飛んでいたのかシミになっている。
妻が勝手に鞄に常備してくれているウェットティッシュで拭ってやれば
志波ルキアは大人しくされるがままで
まるで小さな女の子のようだと思った。
「なぁ」
「旦那の目を向けたいんだよな」
「うん」
「じゃあ俺と寝る?」
「……は?」
「浮気相手に俺、選べよ」
「な、何を言っておるのだ貴様は!」
自分でもそう思う。
何言ってんだろうと思う。
でも
まだ
この女といたい自分がいて
願わくばこの白いワンピースの中も見たかった
「願い叶うし、俺、あんたに興味あるし」
「いやだ!」
そんな全力で否定しなくても、とさすがにこれ以上迫るのは無理かと思ったその時
「せっかく、仲良くなれたのに」
「は?」
「最初は、顔だけイケててつまらぬ男だとばかにしてたけど
貴様とご飯食べてたら楽しかったのだ。
肉を焼いてくれるのも、私の焦げた肉を自分でたべてしまうのとか、そういうの……」
「……そういうの、何?」
「そういうやさしさは嫌いじゃない。だから、仲良くなれたのに、それなのにそういうことしたら、もう仲良くなれなくなるから……そんなの駄目だ……」
なにそれ?
つまらない男からいつのまにかだいぶ昇格してんだけど俺
と一護は思わず笑った。
だめだなこれは
これはだめだ
「おまえさ、たち悪い女だな」
「……悪く言ってすまなかった、謝る」
「ちげーよ、俺もアンタといて楽しかったし、今のアンタの言葉スゲー嬉しくて。だからごめん、我慢できない」
人様に迷惑かけることなく
普通の生活をして
それが当たり前のことなのだと悩むことなく生きてきた真面目な俺が
優等生の俺が
獣みたいに本能で
コノオンナヲジブンノモノニシタイ
そう願っている
そうするべきだと思ってる
「アンタの顔がグシャグシャになるのが見たい」
志波海燕が頭を撫でるというのならと
彼女の細い首を掌で包んで指で撫でた。
小さい体が少しの抵抗を見せたが最後の悪足掻きでしかなかった。
「焼きもちだけじゃすまねぇかも。天下の志波海燕からおまえ奪う」
そう言って唇を重ねれば
彼女はふぁっと言葉にも声にもならない吐息で俺を受け入れた
別に師匠と呼ばれたくなんてなかったけれど。
友人は未だに俺を師匠と呼ぶ。
そして彼女を弄びたい時は
全然会いたくなくても、元妻が子供の事で相談あるらしいからと会ってみたりする。
俺の気持ちを引こうとしても何もできないのは知ってるから
そんなとこが可愛くて
でも俺みたいな男が現れたら簡単に盗られる可能性があるのも確かで
しっかりしているようでふわふわしている天使であり小悪魔のような彼女に
いつまでたっても目を離せないまま
翻弄されている。
だから毎日彼女に触れている
彼女といると毎日が楽しい
彼女の言うとおりだ
生きてる間は楽しんで過ごすべきだ
何かが壊れても
誰からか奪うことになっても
あれから
彼女と過ごすようになった毎日
俺はとても、楽しい
3 notes
·
View notes
Text
ゆ
外国の女の子と日本の男の子のピュアプラトニックラブストーリーみたいな ヴィクトルは髪の毛長いから女の子だと思っちゃう勇利「ヴィッちゃん」呼び ヴィっちゃんは長い髪の毛がをふわふわさせて、きらきらして、ふわふわのいい匂いをいつもさせていた ヴィッちゃんが通ったあとはいい匂いがする うちの旅館にやってきた外国の女の子 名前が難しかったからぼくはヴぃっちゃんとよんでいた お互い使う言葉は違ったけどなんだかフィーリングは合ったみたいで 四六時中一緒に遊んだっけ ヴィク勇ユリの選択肢 ひとつでもルートをま違えるといけない 選択に慎重になるヴィクトル (補足 勇利の姿をした妖精が間違えた選択を正してくれる、ヴィクトルが勇利と恋仲になろうとするので毎回それを阻止 恋仲になるためのアプローチをはじめたら警報がなる) なんでさっきから不機嫌なの、何かあった?俺がなにかした?誰かになにかされた?ねえ、言ってくれないとわからない (親子連れ、男女カップルをみた勇利) ぼくがヴィクトルの普通の幸せを奪ってる なんで? ぼくとヴィクトルは一緒にいて、ぼくがヴィクトルを独り占めして… 勇利は俺の普通を奪って、幸せ? うん… なら俺も幸せだよ、と勇利を腕の中にいれるヴィクトル? 俺が幸せなら勇利も幸せだろう? ジャニの衣装きてるヴィク勇 見る前のユーリ!!! on ICE観(二人のユーリ) 見た後のユーリ!!! on ICE観(師弟love) ピーテルのリンク、ヴィクトルと勇利の距離感を改めて見てあいつらできてんのかよとげんなりするユーリ それに対してミラが、あら、でもあいつらできてないからああやっておおっぴらに人目も気にさずやってんのよ あいつらがほんとに付き合っちゃったら、隠そう隠そうってすると思うわ だってこういうお国柄だもの わ、わけわかんねー。。。とユーリ 現地妻ヴィク勇?(同性愛の迫害を恐れて) 紛いもない師弟としてピーテルで暮らす365日のうち、1日だけ恋人として過ごすことを許される かぐや姫?彦星?週末婚? キスされながらヴィクトル、メガネのフレームゆがんじゃう… ぼくフレームゆがんだら困るからキスする時絶対メガネはずさせてよね プリプリ!と怒る勇利 ヴィクトルが勇利のメガネを外そうとする度ぼくこれからちゅーされちゃうんだ…と思うハメになる勇利 僕達の花畑は冷たい 人間の勇利くんを見守る天使のユーリ、勇利くんが愛しい存在にかわる。しかし愛しい勇利はヴィクトルに横取りされてしまう。 僕達の関係は2人だけの秘密だよ うん、そうだね 勇利、でもねお前を想う気持ちを無かったことにはしたくない お前を思い続けるこ���は許してね ふふ ヴィクトルにそれができたらね ヴィクトルは飽きっぽいからね 僕にとってはもちろんのことだけどさ 2人の思い合う気持ちを封印する指輪を外す儀式 夢の象徴として正しく模範的であり続けたヴィクトルが僕のために背こうとする様が僕には耐えきれない その感情と矛盾してどうしょうもなくその姿に劣情を覚える自分の存在もあるのだ 転がり落ちることの甘美なことよ 羨望の的、あのヴィクトルニキフォロフが僕の真下でプライドを捨て娼婦の振る舞いをする ―ミスターニキフォロフはかなり饒舌だとか、現役時代の二人のインタビューでも仲睦まじい様子を我々はうんと子供の時テレビで見ていました。 ああ、なんだか恥ずかしいな。そっか、あの頃子供だったあなたがこんなに大きくなるほど。そうですね。昔のヴィクトルはなんだか必死だったのかな。誰かがいる時はとにかくボディタッチがすごかった、2人きりの時は別にそこまでベタベタしてるわけじゃなかったんですよ。牽制してたんだろうなあ。僕と2人だけの時はその代わりに言葉がねえ、コーチと選手をしてる時はそうでもないんですけど僕が過去に1回だけ、あれ、他にもあったかも、まあ僕が彼をとんでもなく傷つけちゃった事があって、それ以来言葉がもう、重い重い。 歯の浮くようなセリフはもちろんなんですが。 ―今は違うんですか? もうお互いそんなこと言い合う歳でもないですしね。僕なんか言葉にしない日本人の中でも殊更そんな質じゃなかった。昔に比べたら素っ気ないですよ僕もヴィクトルもね。 いいんです、昔のヴィクトルが普通の人が一生かけて言う量の言葉を僕にくれましたから。僕の知り合いのイタリア人も青ざめるくらいのね。もう言い尽くしちゃったのかな。僕もささやかですけど彼に応えるためにこんな僕の一生かけてもきっと言わなかったであろう量を口にさせてくれました。 だから、いいんですよ。 ピーテルは寒いだろう勇利 その無防備な耳を暖めてあげる 余計なことに耳を傾けなくて良いように 俺が風除けになってあげるよ 勇利が世界を魅了した期間より俺のものである期間の方が長くなるしこれからも更新されていく 勝生勇利は開花していた 勝生勇利の花を散らし実をつけてやった 果実は腐りかけほどおいしい ロシア人の距離感ってこんなもんだよと笑うヴィクトルにみんなにこうだったんだ…とちょっとむっとする勇利くん そんな勇利くんをみて 嘘、勇利だけだよ というヴィクトル 関係が終わるのが怖いから本当に2人だけの世界にきた 相手が自分にも秘密にしていることを自分が知ってしまっていることに喜びを感じる 勇利は秘密にしてたつもりなんだろうけど、俺は知ってたよ クリス「世界中から勇利の処女を奪った罪は重いよ」 ヴィ「」 俺、勇利には申し訳ないけど勇利の人生今までの成功よりも失敗に感謝してしまってる、その積み上げられた失敗の先に立っていた勇利と俺は出会えて嬉しいと思ってる ごめん、実はもう競技者としての意識のウェイトより指導者として勇利のための指導者としての意識の方が大きくなってたんだ 勇利の事が男性がとして好きなんだ!! つ、、付き合うとか無理だよヴィクトル… だって僕、ヴィクトルと一緒にいる喜びを知ってしまったのにいずれ別れが訪れることを考えるとたえきれないよ!また1人で生きてけっての??! と、勇利は言うと思ってました、なので勇利には悪いが5段飛ばしでお前には俺の家族(マッカチン旦那 ヴィクトル嫁 勇利子供)になってもらう これで墓まで離れずに側にいるぞ ダーツが異様にうまい勇利くん クリス「ゆっとくけど一緒にいるのがユーリ(16)じゃなくて俺(25)だからって目の前でいちゃいちゃして言い理由にはならないからね」 夜分ヤコフの家の前 ヤコフが家から出てくるやいなや、ヤコフにハグするヴィクトル ヴィーチャお前いったいどうし…っ ヴィクトルの顔についた血しぶき、汚れた上着 ヤコフ頼みがあるんだ 手伝ってくれるよね ヴィーチャ… という感じのヤコフとヴィクトルの関係 母親が息子が殺した人間の死体を井戸に隠す話みたいな 会計をしてくれるヴィクトル、 「ええっ!ヴィクトル、悪いよ!」 「いいんだよ勇利ぃ〜、勇利も将来こんな立場になったら後輩にしてあげるんだよ、俺がしたこと、後輩に返してね」ウインク ポーッとした勇利くんがはにかんで「うん…!」 そのハニカミ笑顔に心を鷲掴みにされるヴィクトル「やっぱだめ!勇利はずっと俺と一緒にいること!俺がずっと払います! ユウリーちゅうしてくんろーちゅうーちゅうー😚 どこでそんな言葉覚えたきたの😞😓 ヴィクトル家の洗面台で全裸でしゃがみこんで柔軟剤の詰め替えを入れこんでるゆうりくんみてニコニコしたい 事後、無防備なゆうりくんにカメラを向けるヴィクトル、シャッター音がしてから目をゆっくりとあけて蠱惑的な笑みをうかべるゆうりくん そんなゆうりくんのすがたにゆうりだめだよ、無防備すぎる、そんなんじゃいつかリベンジポルノされてしまうかもしれない 何言ってるのヴィクトル、ぼくこれから先ベッドで誰かに裸見せるつもりな���ったんだけどな、それにあなたが賞賛するぼくの身体に恥ずかしい場所なんてある? なんか変なスイッチはいっちゃってる勇利くん スイカ食べるヴィク勇 シャリシャリシャリシャリ(ゆうりくんがずっと食べてる音) ちみちみちみ(ヴィクトルが食べては種を出す音) ゆうりさっきから種全然出してないけどまさか飲み込んでる?! ええ、まさか ほら (口の中に溜まった種を舌に乗せてヴィクトルにみせるゆうりくん) ギョッとするヴィクトル えろえろえーってティシュにだすゆうりくん まだギョッとしてるヴィクトル 視線に気づいて、あ、ごめん汚かったよねと謝るゆうりくん、そのまま立ち上がってどっかいく 視線をずっとゆうりくんに向けたまま赤面するヴィクトル(精子飲んだあと見せつけるAVみたいだったので) カランとなる麦茶で時間経過 ゆうりくんが影で『はずかしかあああヴィクトルにぜったい下品って思われてるよーーーたしかに品のないことしたけどさあーーー』と悶えてる 日本のユーリもヴィクトルもそーとー変 酔っ払ってOut of Controlなカツキに惚れちゃうところとか ヴィクトルぼくがダサイの嫌がるじゃん燃やそうとするし 最初はもっさりしてたのがなんか気に食わないところもあったけど今では…こう…ダサイのも愛しいし…オシャレなのも…そう!オシャレ、オシャレなのはねえ、最近はダサくないようにというか、単に俺の好みのどこそこの服を着たゆうりはきっとかわいいだろうなあとか、ゆうりがきるともっとかわいくなるよねとか…そういうことばっかり… (なんかこの延長でいつかぼくコスプレさせられそうだな…※させられた) 下ネタではしゃぐフォロふ あれ、今日ヴィクトルタートルネックじゃん ふふ、勇利これはね… 包茎手術の広告だ…ガビーン あっ、ヴィクトル指輪 と言って指輪をヴィクトルの指から簡単にはずす勇利 勇利〜どうした?洗う? いや、違うよ ヴィクトルとはこれからも一緒にいるんだし付けてる必要ないじゃん 勇利の手で勇利から嵌められた指輪を勇利の手によって外されるなんてここは地獄かっ!! 愛されれば愛されるほど勝生勇利の存在の輪郭ははっきりと確かなものになる あなたを愛している 知ってるよ でもあなたに憧れたり、うらやんだり、よろこんだり、がっかりしたり、いろいろな感情が恋だって、そういう目で見るようになってたんだって気づくのが僕遅すぎたね 俺は気づいてたよ おまえが、勇利は俺に恋してるんだって、うぬぼれなんかじゃないって、そうなった瞬間さえ俺は言い当てることだってできるんじゃないかなあ そう ぼくは自分のことに敏感じゃないから、わからないや 知ってる、すっごく繊細ですっごく敏感なのにどこか鈍感 ヴィクトル、 終わりにしよう、なんて言うな、言わないで勇利、お願い、頼む 違う、終わりになんてしたくない、僕が僕に正直になれってうるさいんだ、ヴィクトルと離れたくないよって そう、そうだよ勇利 だからけじめをつけよう けじめってったって勇利それって… ぼくと、ヴィクトルの、けじめだ、 これを、 指輪? 僕達これを身につけすぎた、これがお守り以上の意味にならないうちに、もう遅いかも、でも、僕が何も考えずにいられるお守りのうちに、外して 勇利は俺が勇利に恋してたの気づいてた? まさか…いや、どこかでそうであって欲しいって思ってた 俺が勇利に撃ち抜かれたのはバンケット、でもコーチとしてはどこか自分のアバターのような、そんな感覚もちょっとあったよ そんな気がしてたよ、だってヴィクトルのコーチどこかおざなりなんだもん でも本当に愛し始めちゃった時、あ、手遅れだって思った、だって自分を投げ打ってでも、ガラスのハートでどこか図太くて余計な事を考えずにはいられなくて自己管理がへたくそで体から素晴らしい音楽を奏でて輝かずにはいられない、勇利に何かしてあげたいしてあげなきゃって警報が鳴り響くんだ。ダメな所ごと愛しいなんて、こんなのはじめてだって。 勇利のために生まれてきた ヴィクトルのために僕は生まれたって自惚れてもいいでしょ?
1 note
·
View note
Text
日曜日の家具
先週の日曜日の話。太陽が居眠りをし出す時間帯で、空気は清んでいる。公園では子供たちがシャボン玉を吹いたり、男女が酷く退屈な夢語りをしている。退屈とはなんだろう?恐らくこのテーマで大方の人々は(各々がしかるべき訓練をすれば、だが)本を一冊書けるだろう。それは恐らく私の目に写るみんなが固有財産として持っている。しかしそれを考えだすのが、退屈なものだ。少女のひとりがつまずいて膝に擦り傷をする。母親があわてて駆け寄り、おまじないをとなえる。おまじない。おまじない。私は咳払いをすると新聞をまるめてごみ箱にほおり、馴染みの居酒屋へ行く。店内は繁盛しており、休日のサラリーマンの集団やら、競馬に行ったであろう中年の男たちに挟まれて、綺麗な女の子がひとり客でいる。歳はハタチくらいか。ビールを頼みマッチに火をつける。火は心臓まで届かない。ハートに火が付くことなんてそうそうあるものじゃない。横で飲んでいる、色の深い緑のセーターに染み付きのチノパンを履いたじいさんが言う。「だいたいは家で作れる」私は反復する「だいたいは家で作れる」「でもな」つまみのブリのあら煮をつついて言う。「なぜか来てしまう」「わかっちゃいるけどやめられない」じいさんは酒を一杯おごってくれた。
時計を見ると午前一時四十二分で私は家のこたつで横になっていた。酔っていつの間にか自室に引き上げたらしい。ダルマが大きくなったり小さくなったり、昨日食べて洗い場に持って行かなかった深皿の食器の中のスプーンがくしゃみをしていたり、必要な物として取っておいたスクラップブックが酷いかんしゃくを起こしたりしていた。「スージーはあんたのせいで風邪を引いた」「クリームチーズ?」私はとっさに答えてしまった。茶色の棚の引き出しが舌を出すかのように二度ほど開いては閉まり、蛇口は弱者なのさ、と笑った。TVショウが突然流れだしその場にいた者は皆息をのんだ。トムはみんなのカリスマでこれはいわゆる良いものらしい。優れものだ。いつでも熊だって殺せる。「佐野忠臣、軍忠前の八日」と言う題名の書物はマスをかいている。とりあえずここは日本だよな。私は思った。なぜ深夜の通���に外国人が必要なんだ?熊をわざわざ殺す必要はない。タンスが私の頭の中を読んだように言った。深夜の通販は日本人である必要があるの?私は混乱した。酒のせいだ。すべてそうだ。明日にはすこしは良くなっている。照明はここぞと言うばかりに光の鍵盤をなぞり、窓は外界を写るものが今生すべてのイマジネーションだと嘘ぶいている。皆がやりたいほうだいだ。皆がやりたいほうだいだ!私は言った。「誰の日でもない日曜日にこうやってパーティーを開けたことは嬉しく思う。でも、家具は家具で、食器は食器だ。私も君らも少し疲れているんだ。幸運を祈るよ」男は息を荒立て喋ると、すべての物たちが静まった。静まり帰るほかなかった。
あくる日男が部屋を見渡すと、それはおのれの酔いと疲れが引き起こした幻影以外の何者でもないと思った。部屋は土曜日の夜にきれいに片付けられた状態のままで、日曜日の夜にあったであろう狂乱のひとかけらさえ見当たらなかった。片方白目のダルマがさりげなくぱちりとウインクをした。
2017.4.3(mon)
1 note
·
View note
Quote
政治の効用として「架空の上位者」を設定するのなら、それは法の根本の部分に「フィクション=大嘘」を組み込むことを許容する、ということだ。
「それってウソだよね?」「ぼくたちに権利を与えた天、造物主、最高存在…って存在するの??ウリウリ」みたいなからかいは、それは聞こえないふりをするしかない、
あるいは「よく気づいたね。そこはフィクションなんだ。だけどナイショな」とウインクするしかない。
憲法11条補論〜架空の「上位者」によって、例えば奴隷も自由になれる/「ヴィンランド・サガ」を題材に - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
0 notes
Text
3years
2019.8.6.22:44
よよよ
三年前のニアミス
そんなものあったりするのかな
洗濯物が揺れていて
わたしたちは儚いというのにこんなにもしぶとくて
さきほど夢を作って 見ました
おばあちゃんの家がどちらもまだあって
わたしの変な器を
お茶屋さんにおいてくれる
みんな仲良しで
楽しそうです
わたしはいつものように
抹茶の飴を貰って食べる
ありがとうってちゃんと言う
わたしは好きな扇子があって
ある日それが売れてなくなってしまう
悲しくて
それは恋に似た
そこにかけられた違う扇子が
新しい言葉を喋って
わたしはふと
それをためしにと買ってみることにしました
大きな扇子
踊るための
九華扇
湯気ただよって
裏のお尻の痛い滑り台が戻ってくる
みんな仲良しで
どこにも隔たりのない
わたしはなんにもしたくなくて
みんな楽しそう
わたしは変な器と変な瓦の石を作って
変なお孫さんねと
どちらでも言われながら可愛がられながらほっといてもらえる
お金のことも何にも気にすることがなくて
みんなそれぞれに愛し合ってる
わたしはなにも気にすることがなくて
誰かを愛してる
あの瓦屋さんガラスの瓦も作ってはるんやって
あそこのお茶屋さんへんな���売っとるんやって
わたしはなんにも気にすることがなくて
守られてて愛されてる
なんにも大きくならなくてよくて
ただ調和が続け��良い
それなのに風が吹いて
誰かが躓いて
みんな倒れてく
みんな不健康になって
小さく幸せらしくしていく
断絶の空間の中で
愛らしい言葉をぽつりと吐いて
テレビからつまらない笑いがけたたましく鳴る
あなたはわたしにすこしあたえる
わたしはそれを受け止めきれないで
嬉しく少し俯いてる
わたしはわたしと仲良くなって
早くあなたと手を繋ぐ
わたしはわたしと仲良くなって
いつか何かと手を繋ぐ
なにもかもが手を繋ぎなおして
美しい絵がまだそこにある
ここはとてもさむい
わたしたちは嘘をつかない
エアコンを消せば暑すぎて
寒くて毛布にくるまってる
なくしたまんまの鍵は新調されて
もう誰も気に留めない
大事なものなら戻ってくるから
もうわたしも気に留めない
誰にも知られなくて良いことを
ときに誰かに知ってほしいと思ったりする
地上の神様に出会うため
頭が痛いな
春
穏やかに時を過ごすでしょうなんて言ったけど
そんなことはあり得なくて
わたしの中身がもっと穏やかに整えられない限り
日々の厄介はこれからも永遠に続きます
Why do we keep when the water runs
I blame it on your love
結局のところ誰なのかもよくわからないといって
怖がられることを怖がっています
わたしはあなたという誰かがここに来てくれるまで
一生懸命
そのためだけに
そのことだけを思って
できる限りの準備をしようと思います
願わない会話というものは本当に疲れてしまいます
わたしはまた
人に会う仕事というのをやめたほうがいいと
強く思いました
もっと作品が語るものにしていかないと
わたしが死んでいく
あるいは立たせる場所が違う可能性は十分にあって
わたしは毎日を楽しく過ごしたいです
キャットの創造水面下
水上スキーはあっても
水下スキーはないし
わたしは泳ぐのが得意じゃない
でもお魚が沢山いるなら楽しいかな
ダイバー
九華
外国
お茶
わたしが自由になるために
勉強しようか
なにから
なにから
天上の話をしても
誰もついてきてくれないから悲しくなる
地上にしがみつくために
わたしは過去のわたしに繋がる人たちに助けをもらって
勉強します
よくわからない
本当は
毎日もっとティーパーティ
洋服の話ばかりして
フリルや薔薇
新しい石鹸やクリーム
そういうものの話
髪を触りあえる
贈り物のしあいっこが楽しい
かわいい女友達たち
ふわふわのぬいぐるみにかこまれて
弱ってたあの時わたしが文集に書いたみたいに
ベッドの上に天蓋がかかってて
ピアノの音
バニラの匂い
かわいい下着と口紅ばかり買って
この世に居ないみたいに過ごすはず
私にはなぜかそれができない
誰を責めたいこともなくって
ただわたしは彼女にも愛されたいというのがあったんだと思うのです
花柄の服はだめらしかった
上機嫌で歩いていたらそれは許されないというような天からの仕打ちがあって
ウインクはうまくできなくて
わたしもハイヒールがほしかった
もっとヒラヒラした服の方がほしくて
彼女はいつだって不満だった
女の子らしい様子を見せると顔を歪められて
いつもフラットでいようと心がけることが仇になる
良い子なんて無意味
気を使えること
人の気持ちがわかること
そんなことはいつの日もけして自分自身を幸せにはしない
気がつくことと気持ちがわかることは違って
感情はわかっても内容を知ることはない
彼女の中身は誰かの感情でいつも混雑してる
それでいて何をしたらいいのかはずっとわからない
今だって
化粧のこととか下着のこととか
からだのこと
かわいい彼女たちと
なんの目的もなく
わいわいお菓子を食べられるような女の子に育っていたら良かったのにって思う
グラビアアイドルみたいに自分の身体を愛して晒して
男の人からちやほやされながら守られて
自分自身が存在��るということだけで
生きていけていたら良かったのに
何もかもが遠くて
でもこんど
久しぶりに
アンティークの服屋さんとか
骨董屋さんとかを
みにいこうかなと思います
わたしは毎日同じような
パジャマみたいな姿で
よくわからないものを作ってる
髪を切りに行きたくても美容師の彼と休みが合いすぎて
代わりに切ってもらった髪がわたしの首を攻撃して
とうとう自分で切ってしまって
展示を見にきてくれたというのにわたしは町へ歩いてしまう
本物のバルボラが
黒猫を触って
手についた毛を
嫌だなと思って洗う
猫なんて飼いたくなくて
わたしを猫にしてほしい
猫のようにわたしをかわいがって
猫のように誰かをかわいがりたい
猫のように気ままに
もうすぐできっと一年が経ちます
終われといいながら
彼女はまだ終わらないでと泣いています
血が不足
明日も誰かと会ってしまう
それはとても嬉しいこと
わたしの身体がそれを受け容れる余地がないだけ
わたしが彼女に、本当に好きなことをしたらいいのにというのが本当に暴力だということを示すように
わたしだって本当に好きなことをしようとしてるのか本当のところわからないです
腰が本当に痛いです
こんなにわがままにやっているのに
我慢が過ぎて歩けない
すぐに誰かを祈ろうとするの
自分のことだけ考えようって思い直します
わたしの祈りが優しいままで
誰のことも所有しようとかしないで
何もかもを自由のままにしておけるのなら
なにもかも癒せるのに
0 notes