#冗談がわからない奴はブロック
Text
The Pornography Fellow - あなたの PornGuy すべてに ポルノ!?
ここでは、トップの無料&プレミアムポルノサイト、カムサイト、フックアップサイト、ゲーム、エスコート、アマチュア、ブログ、Reddits、セックスショップ、セックスチャットサイト、セックスストーリー、セックス写真、フォーラムなどを見つけることができます。
うわーっ So You Are The Pornography Fellow! そのタイトルの由来は?
無料のポルノサイト なぜなら、私は本当にAV男優だからです。何十年にもわたって、股間のムラムラ、ヌルヌル、モゾモゾした蛇を真剣に引っ張ったり、ポルノスターや主婦が脚を広げてするのを見たりしてきたおかげで、私はポルノ関連のあらゆることに精通しています。 シロクマとスパーリングしながら、1000のポルノサイトを頭の上に並べることができます。カーマスートラも暗記しているし、本に載っているほぼ全ての体位でチンポやお尻を犯したことがあるし、載っていない体位もたくさんあります。国連が私を世界ファッピング大使にしようと真剣に検討しているほど、私はすべてを知っていて、それ以上に尊敬されています。 そう、私はスレッジハンマーのようなボールを持ったファッキンポルノガイであり、その称号は十分に値するものであることを、あなたは受け継ぐことができます。
ヘイ ポルノガイI'm Becoming Somewhat Ill Of Pornhub.How Else Can I Fap One Out?
Pornhubのようなサイトにうんざりしていませんか?我々は非常に同情する。私たちはまた、あなたのかわいそうなオカマやマンコを非常に気の毒に思っており、好きなときに生き返って甘い精液を放つことができないために、オカマやマンコが経験している苦痛を想像することができない。 だから、私たちはきっとあなたの現在のファッピングの困難を解決することができます。AVビデオ以外にも、あなたが月に向かって叫ぶように、あなたを興奮させることができるものはたくさんあります。例えば、ネット上にある何千ものXXXゲームをプレイすることができます。そこでは、漫画のキャラクターにペニスや触手、おもちゃなどで穴を開け、彼らが叫んだり、甘い汁を噴出したりするのを聞くことができます。 また、アダルトブログのサイトでは、エロティックなストーリーや記事、詩などを読むことができます。さらに、フォーラム、出会い系サイト、redditsなどもあります。そこでは、読み、学び、精液を流し、出会い、交流し、男性と女性の脚の間にあるオーガズムの喜びを過剰摂取する方法を学ぶことができます。 これらがうまくいかない場合は、上品なエスコートを雇うことを強くお勧めします。エスコートは、バケツ一杯の精液を出してくれて、あなたが別の惑星に行ってしまうまで、あなたの心を揺さぶってくれるでしょう
あなたは 明確に The Averageではなく ポルノデュード.どうやって見つけたの? Underhanded Reserve of Locales?
前にも書いたかもしれませんが、私はXXX関連のすべてのものに深い情熱を持っています。このサイトでは、何百、何千ものポルノサイトが見直され、適切な場所に置かれています。これらの隠し場所を見つけることは、見た目ほど難しくありません。必要なのは、献身的な努力と、良いポルノサイトを見つけたいという熱意だけで、私はそれを豊富に持っています。 これらのサイトを見つけるには、検索エンジンを適切に使用する必要があります。検索結果はフィルタリングされ、その中からベストなものだけをこのサイトで紹介しています。もしあなたが、大小のポルノサイトの優れたレビューを得られるサイトを探しているのであれば、きっとこのサイトを見つけることができるでしょう。 私は自分の仕事を、あなたがチンポの長さを気にするのと同じように真剣に考えており、私や私のイクスキルに対するあなたの評価を失わせるようなことは決してしません。このサイトをご覧になったら、安心してお任せください。

I'm Somewhat Outlined Of ウイルスを捕まえる。 どうやって見るの? ポルノ 安全に?
ウィルス、マルウェア、ランサムウェアなどが蔓延していますが、XXXサイトにはこれらがあまりにも多く存在しています。これらは決して楽しいものではなく、通りに面した売春婦の顔に精液を発射するよりも短い時間であなたの一日を台無しにしてしまいます。 私たちは、ここでレビューしているすべてのポルノサイトを実際に訪問し、最高のものだけを推薦しようとしていることをご理解ください。推奨されていないポルノサイトは、ウイルスや厄介なもので満たされているかもしれないので、ログインするよりもサボテンとセックスしたほうがいいかもしれません。しかし、自分の責任で閲覧しなければなりません。ポルノ担当者はサイトをリストアップしているだけで、人々がサイトに掲載するものを管理することはできません。 安全で安心してポルノを見たいのであれば、そうする必要があります。
- システムのOSが最新の状態であることを確認してください。
- マルウェアが含まれている可能性のある広告をブロックするために、Adblockを採用しています。
- あなたの安全を守り、あなた自身を守るために懸命に働く、トップクラスのウイルス対策ソフトを使用してください。
- どんなに魅力的なソフトウェアであっても、提供元不明のソフトウェアは絶対にインストールしないでください。
- 生理中のヤギを見ているところを撮られた」などというメールは無視しましょう。ウェブカムをハックして、特定のポルノカテゴリーでファッピングしているところを撮影されたというメールが届いたからといって、慌ててアカウントを空にする必要はありません。メールを削除して、奴らを見返してやりましょう。
- そして最も重要なことは、オンラインでポルノサイトを閲覧しているときは、大量のペニスをしゃぶりたいと思っている石油王のように、常識的な行動をとることです。ネット上で起きたことはすべて自分の責任であることを忘れないでください。頭を使いましょう-ここで言っているのは小さな頭ではなく、大きな頭です
YooI Got an Underhanded サイト提案.どのように あなたに連絡を取りたいのですが?
The Pornography Guyと連絡を取りたいと思っていますか?それは素晴らしいですね。まず最初に、パンツを下ろしてください。そうすれば、あなたの下に潜んでいるどんな種類のモンスターか見られますよ冗談ですよ。 私と連絡を取るには、[email protected] までメールを送ってください。私のファンがヌードの自撮り写真を送ってくれたり、次にホットなポルノサイトのレビューをしてほしいと思ってくれれば、私はいつでも嬉しいので安心してくださいね。
0 notes
Text
Hello, With my love,
スティーブ・ロジャース、プロジェクトマネージャー、32歳。基本項目を入力して画面に現れる質問に4段階で答えていく。『自分の知識が生かせている?』イエス、『仕事にやりがいを感じる?』イエス、『職場の環境は快適?』どちらかといえばイエスかな、自販機のメニューがもっと豊富になれば嬉しいけど。『最近の懸念は?』ええと――
「――トレーニング用の鶏肉レシピに飽きつつあること……」
記述項目まで漏れなく打ち込んで送信ボタンを押す。画面に現れた「ご協力ありがとうございました」のポップな字体を確認してからスティーブはタブを閉じた。
定期的に行われる社内のストレスチェック。トレーニングジムをいくつか展開しているスティー��の会社は、オフィス側の人間だけなら両手で数えられるくらいの規模のものだ。それこそ、ストレスチェックなんて面談で済ませば事足りる程度の。それでもオフィスにはほとんど顔を出さないジムのトレーナーのケアが目的だというこの作業を、スティーブはランチ後の眠気覚ましとして使っていた。
画面そのまま現れたメールボックスを眺めながら、コーヒーを口に運ぶ。新店舗立ち上げのプロジェクトが進行中なこともあり、最近は未読メールが溜まるのも速い。それらの一つ一つを処理していけば、顧客対応をしているスタッフからの転送メールに行き当たった。
(……珍しいな)
オープンにしている会社のアドレスには一般の問い合わせに混じって営業のメールが送られてくることも少なくない。基本的にはスルーしてしまうことが多いが、彼のお眼鏡にかなったものが、ごく稀にスティーブの元に転送されてくるのだ。そして例にたがわず今回も外部からの営業メール。そのメールは礼節を守ってこう始まっていた。
『Dear Sirs and Madams, ――』
内容には、自分たちはジムの利用者用にトレーニングの管理アプリを作っている会社であるということ。パーソナルトレーナーも利用することができ、顧客管理にも役立てられることなどが綴られていた。
『もし興味を持ってくれたなら詳しい話をさせて欲しい。
your sincerely, James Barnes 』
スティーブはメールを最後まで読み終えると、文末に添えられていた会社のURLをクリックした。IT系らしく洗練されたサイトによると、ジェームズの会社は2年前に立ち上がったスタートアップらしい。アプリの紹介ページを開き、内容を精査していく。スティーブの元に届いた時点で有象無象の営業メールからは抜きん出ているのだが、それにしたって全ての業者に会うほど暇ではない。そうした審査の気持ちでページを見ていくと、スティーブの目がふと興味深い内容に行き着いた。どうやら彼の会社はもともとリハビリ用の管理アプリを病院や施設に提供していたらしい。そのノウハウを踏まえ、今度はジムの方面にも挑戦してきたというわけだ。
(……丁度良いかもしれない)
最近ではトレーニングジムにもユニバーサルデザインを取り入れ、特に身体にハンデを持つ人���も利用できるような施設が増えている。そして企画進行中の新店舗も、まさにその一つになる予定だった。
新店舗は新しいサービスを導入するのに最適なタイミングだ。なにより彼らに話を聞けば、新しい店舗へのアドバイスも出てくるかもしれない。そう考えたスティーブは丁寧に返信を打ち始めた。
『Dear James――
メールをありがとう。プロジェクトマネージャーのロジャースです。提案いただいたアプリについて――』
最後に署名を添えて送信ボタンを押した。忘れないうちに顧客対応のスタッフにも『ありがとう』の一言を送っておく。諸々を考慮してこのメールを届けてくれたのだとしたら、彼の功績を称えなければいけないだろう。ビジネスだけじゃなく、何事においてもタイミングは重要だ。
程なくしてジェームズから返信が届いた。不特定の誰かではなく『Dear Steve』に変わったメールには、目を通してくれたことや営業のチャンスをもらえたことへの感謝、会社が近い場所にあるのでスティーブの都合にあわせて訪問したい旨、そしていくつかの日程が心地よい文体で書かれていた。営業をかけているのだから丁寧になって当然だが、ジェームズのメールはスティーブにとって特に読み心地が良いものだった。早々にフランクになる相手は苦手だし、反対にかしこまられすぎても居心地が悪い。メールの文体というのはたとえビジネスであっても千差万別なもので、良い印象を持ったままでいられることは意外と少ない。特に自分のように人見知りの気がある人間にとってはどうしても敏感になる部分だった。
一通りのやり取りを終え、スティーブはすっかり冷たくなったコーヒーを口に含んだ。ふう、と一息ついて、会えるのを楽しみにしていますというジェームズからのメールを眺める。どんな人物だろう。スタートアップといえば若いイメージがあるが彼はどうか。メールの雰囲気から浮ついた感じはしないが、正直言って自分は初対面の人間と会話をすることに少し苦手意識があるから、願わくば話しやすい人であって欲しい。そう思いながら続々と返ってきているその他のメールをさばいていった。
ジェームズからのメールを受けた翌々日。またも昼下がりのオフィスで、スティーブはそのジェームズの来訪を待っていた。窓際に置かれた観葉植物には気持ち良さそうな日光が当たっている。四月のニューヨークらしくまだまだ外は寒いが、日差しだけを見れば春が近づいてきているのがわかる。スティーブは植物たちを眺めながら、来客時用のジャケットを羽織った。
丁度その時、入り口から来客を知らせる声があった。振り向くとスタッフの隣に一人の男性が立っている。
「スティーブ、お客さんよ」
その声に手を挙げて答えると、隣の男性がスティーブに気づいて微笑んだ。上品なグレーのニットに濃いブラウンのスラックス。目があった男性は、驚くほど整った顔をしていた。
スティーブはノートパソコンを抱えて男性の元へと向かう。
「はじめまして、ジェームズだ」
自己紹介とともに差し出された手を握る。遠目からではわからなかったがジェームズは長い髪を後ろでひとまとめにしていて、微笑むと口角がキュッと上がるチャーミングな男性だった。灰色がかったブルーの大きな目が優しげに細められている。
「スティーブだ。来てくれてありがとう」
「こちらこそ、時間をもらえて嬉しいよ」
そう言ったジェームズをミーティングスペースへと案内する。彼が動いたと同時に控えめなムスクの香りがした。
席に着くとジェームズは簡単な会社の紹介のあと、ipadを使ってアプリの説明を始めた。
「リリースして間もないから荒削りな部分は多いけど、むしろフィードバックには柔軟に対応できると思う。それが小さい会社の強みでもあるしな」
そう言って実際にアプリを動かしてみせてくれる。なぜか彼の左手には薄手の手袋がはめられたままだった。それに気をとられていたのがわかったのか、ジェームズは軽く左手を振って「怪我をしてるんだ、大げさですまない」という言葉とともに申し訳なさそうに笑う。
スティーブは不躾に凝視してしまったことを恥じ、それを補うかのように彼の言葉を補った。
「今、新しい店舗の計画が進んでる。うちのジムは一つ一つの規模が小さいから、今ままでは専用のシステムは入れてなかったんだ。もしそのアプリが有用だと判断できたら、このタイミングで導入できればと考えてる」
「本当に? 良かった。実はまだ導入実績が少なくて。いくつか話は進んでるけど……だから新しい店舗で要望があれば、こっちもそれに合わせてある程度改修できる」
ジェームズは朗らかに答えた。エンジニアを信頼している物言いが好ましい。スティーブは一つ笑うと、兼ねてからの相談を持ちかけた。
「……実は、こちらから一つ相談があるんだ。君の会社のサイトを見たけど、リハビリ業界でも仕事をしていたんだろう」
そう言ってスティーブは新しい店舗をユニバーサルデザインにする予定であること。自分のジムでは初めての試みだから、よければ意見を聞かせて欲しいということを伝えた。営業に対して駆け引きじみた提案ではあるが、想像に反してジェームズはわお、と破顔してくれた。
「そんな、嬉しいよ。このアプリを作ったのも元々そういうジムが増えてきて、もっと細かいデータ管理になるだろうと思ったってのもあるんだ。だからもしできることがあるなら喜んで手伝うよ」
ジェームズの反応にスティーブは安堵する。「……有難いな。詳しく説明すると、例えばマシンの導入とか配置とかを見てもらって、もし気になったと箇所があれば教えて欲しいんだ」
「ああ、もちろんいいぜ」
彼がよく笑うせいか、打ち合わせは非常に朗らかに進んだ。同僚にはよく恐そうな印象を与えると言われてしまう自分には驚くべきことだ。メールの印象も良かったが、実際に話してみるとその印象が更に強まる。ジェームズには押し付けがましかったり、斜に構えたりする部分がない。そしてこちらの要望を理解するのも速かった。
「無理のない程度で構わないんだけど、ユーザーになりうる人に話も聞いてみたくて。誰か、そういった人に心当たりはあるかな」
スティーブが尋ねると、彼はあー、と空中を見つめた。おそらくツテを考えてくれているのだろう。アプリには直接関係のない話にも関わらず真摯に対応してくれる彼に心の中で感謝する。スティーブは温かな気持ちで彼の返答を待った。
しかし、しばらく経ってもジェームズは相変わらず小さく唸ることをやめなかった。そればかりか、うっすらと眉間に皺が刻まれている。優しげだった目元が一転して凶悪ともとれる雰囲気になる。スティーブはたまらず目の前で唸る彼に声をかけた。
「ジェームズ……? あの、無理して探してもらう必要はないんだ。もしいればくらいの気持ちで」
その言葉にジェームズはパチリと目を瞬かせた。眉間の皺が消え、きょとんとしている彼は今までよりも随分と幼い。その顔を見るに、どうやら自分が不吉な表情をしていることには気づいていなかったようだ。どこか慌てた様子のスティーブに気づいたのか、彼は申し訳なさそうに眉尻を下げた。ころころと変わるジェームズの表情に、スティーブもつられて笑う。
「ああ……ごめん、少し考えすぎた。ええと、モデルケースが欲しいんだよな?」
「まあそうだね」
「身体にハンデがあるけどジムに通いたいか、あるいは通ってる人間? 年齢はどのあたりを考えてる?」
「そうだな……一旦は20代後半から40代かな。男女は気にしないよ」
そう言うとジェームズは再び小さく唸ると、ええと、と口を開いた。
「関係者を辿ればそういう人間は何人か紹介できると思う。けど――」
「……けど?」
「まあ、もう少し手頃なところにぴったりの奴がいるなと思って……。えっと、そのまあ、俺なんだけど」
え、というスティーブの言葉を待たずに、ジェームズは左手を覆っていた手袋をはずす。その下から現れたのは銀色をした滑らかな義手だった。
「俺、左腕が義手なんだ。年齢は30代。ランニングと、筋トレは家でやってる。……な、ぴったりだろ」
そう言ってジェームズは吹っ切れたように笑った。先ほどの逡巡はおそらく自分を挙げるかどうかを迷っていたのだろう。予想外の内容に、今度はスティーブが口を詰まらせる番だった。それを見越していたのか、ジェームズがすぐに言葉を続ける。
「ごめん、いきなりで驚いたよな。あんまりバレないから自分で言うことも少ないんだけど……イメージを聞く感じ誰かに話を回すより俺の方がいいんじゃないかと思って」
苦笑しながら告げるジェームズを見てスティーブはハッと我に返った。ごめんなんかじゃない。一体自分は何をしているんだ。彼が謝ることなんてないのに。
「僕こそごめん! 少し驚いたのは本当だけど、君が謝ることじゃないよ。むしろ、そうだな。君が手伝ってくれるなら……その、嫌じゃないなら……すごく嬉しいよ」
実際ジェームズの申し出はありがたいものだ。関係者をたどって、紹介してもらってとなるとお互いに負担が増えるのは確かであるし、そこまで望んでしまう申し訳なさもある。何より、本来の営業から外れているのに、ジェームズ自身が請け負うと言ってくれたことがスティーブには嬉しかった。彼はとても責任感の強い人間なんだろう。スティーブの中でジェームズに対する好感度がぐんぐんと上がっていく。彼と仕事ができたらどんなに良いだろう。
「そうか、なら良かった」
ジェームズもスティーブの言葉に安心してくれたようで、ふっと優しげに笑う。不思議な感覚だった。彼の笑顔でこちらの心まで軽くなるような気がする。横広の大きな目が雄弁に気持ちを伝えてくれているようだ。スティーブがふわつく心を持て余していると、ジェームズがちらりと時計を見てあ、と声をあげた。
「悪い、結構長く居座っちまった。ええとそしたら……」
そう言って今後の約束をいくつか交わし、驚くほどの収穫を得た打ち合わせは終了した。何より、ジェームズとの関係は今日が初めてだとは思えないほど良好だ。終盤にはだいぶフランクに話していたことに気づき、スティーブは今更ながら気恥ずかしさを覚える。
オフィスの入り口まで同行すると、最後にスティーブは今日の礼を述べた。先ほどはきちんと言えなかったことも。
「じゃあ、ジェームズ。今日は本当にありがとう。それと……君の腕のこと、不躾に見たりしてすまなかった。気を悪くさせていたら申し訳ない」
ジェームズはその言葉に少し目を見開き、柔らかく微笑んだ。
「いや……優しいんだな、スティーブは。むしろこっちが驚かせて悪かったけど……そうだな、そしたら俺も一個質問をしても?」
「もちろん、仕事のこと?」
ジェームズは少し眉をひそめて、周囲を伺うようにスティーブの耳に口を近づける。そして、声をひそめてこう告げた。
「いや――、ジムの社員になるって、その胸筋が必須なのか?」
「……え?」
���かん、と一瞬呆気に取られた隙にジェームズはぽんとスティーブの胸を軽く叩いた。同時にふはっと快活な笑いをこぼし、すばやく身を離す。
「ごめん、冗談。立派な体つきだからつい。さっきのこと、本当に気にしてないんだ。今日はありがとう」
そう言うと彼はさっとオフィスを後にしてしまった。からかわれたと思ったのは一瞬で、それがスティーブの気を軽くする為のものだったと気づいた頃には、ドアの向こうに彼の姿はなくなっていた。きっと、自分が申し訳なさそうな顔をしていたから。気にしすぎる性分だと見抜かれていたのだろう。彼は……彼は、きっとすごく優しい人だ。
(……うわ)
彼に触れられた胸がじんわりと熱を持っている気がする。スティーブはしばらくドアの前に佇んだまま、その熱が収まるのを待っていた。
『Hello Steve, ――
今日は時間を取ってくれてありがとう。アプリのデモ版を送るから使ってくれ。あと、新店舗の詳細はいつでも大丈夫だ。都合のいい時に連絡をくれ。
Regards, James Bucky (周りはみんなバッキーって呼ぶんだ。もしそうしてくれたら嬉しい)』
夕方に届いたメールは少しフランクになった挨拶から始まり、続いて今日の礼が綴られていた。そして彼の愛称も。こんな風に誰かとの距離が近づいていくのを嬉しいと思うのはいつぶりだろう。たとえ仕事上のつきあいだったとしても、ジェームズ――バッキーは間違いなく魅力のある人間だったし、それを嫌味に感じさせない軽快さも好ましかった。スティーブはその距離を嬉しく思いながら返信を打ち始めた。
『Hello Bucky, ――』
そうして始まったバッキーとの仕事は至極順調に進んだ。アプリの導入も本格的に決まり、スティーブもバッキーも相応に忙しい日々を送っていた。
『Hi Steve, ――
週末はゆっくり休めたか? 先週もらった内容だけど――』
『家の掃除で一日潰れたよ。クローゼットは悪夢だ。そうだね、トレーナーによると――
Thanks, Steve 』
バッキーのレスポンスは速いし無駄がない。そしてそこにさりげなく添えられる気遣いの一言は、スティーブにとって日々の潤いと言っても良かった。なんなら定型文だって構わない。多くの関係者とやり取りしている今だからこそ、彼からのメールは一際嬉しいものだった。
バッキーはそういったバランスを取るのが非常にうまい人間だった。時折チャットのようになるメールも、こちらからの質問――特にバッキーをモデルケースにしている件だ――に丁寧に答える文面も、タイミングを計り間違えることがない。向こうが自分をどう評価しているかはわからないが、スティーブにはこれが稀有なことであるという確信があった。
彼の会社が近いというのは本当で、何度かランチミーティングをした際には共同経営者だというサムを伴ってくることもあった。彼はなんと元カウンセラーで、その仕事をやめてバッキーと会社を立ち上げたらしい。すごい決心だと素直に述べると、サムは「こいつと一緒にいたらわかるよ」と苦笑していた。バッキーが気のおけない様子でサムの脇腹を小突いている。その光景に笑いを返しながらも、スティーブは胸の内に靄がかかるのを自覚していた。
バッキーは魅力的な人間だ。それはこの1ヶ月で十分にわかっている。そんな彼だからこそ、自分よりも先に出会った人間が自分と同じように彼と仕事をしたいと、夢や未来を共有したいと思ってもそれは仕方がないことだ。でも、もし自分の方が早かったら? もし彼ともっと前に出会えていたら? そう思うと、まだ距離があるバッキーと自分との間に少なからず悔しさを覚えてしまう。ましてや、自分は仕事上の関係でしかない。そこに別のものを求めてしまうのは我儘だろうか。
スティーブはコーヒーを飲みながら、次のランチはバッキーと2人であることを密かに願った。
街を行く人たちの手から上着がなくなり、代わりににアイスコーヒーが握られる。時間はあっという間に過ぎていく。工事の視察、トレーナーや業者との打ち合わせ、やることが山のようだ。オープンがいよいよ間近に迫ってきたスティーブは、追い込み時期らしく夜遅くまでオフィスに残ることが多くなっていた。早く帰りなさいよという同僚を後ろ手に送り、一人になったオフィスで堪らずにため息をつく。
「疲れたな……」
思わず口にすると一気に疲労がやってきた。ネオンの光こそ入ってこないが、金曜日の21時、街が一番賑やかな時間に、静かなオフィスでタイピングの音だけを響かせている。
(土日はゆっくり休もう……)
大きく肩を回してパソコンに向き合うと、期せずしてバッキーからのメールが届いていた。
『Steve, ――
悪いがこの前言っていたアップデートにまだ時間がかかりそうなんだ。週明けには送れると思うから、もう少しだけ待っていてくれ。
Bucky, 』
取り急ぎ、という感じで送られたそれに苦笑しながら返信する。どうやら彼もこの休前日を楽しめていないらしい。
『Hello Bucky, ――
構わないよ。むしろ最近はいつでもパソコンの前にいるから君達のペースでやってくれ。
Thanks Steve, 』
送信ボタンを押すと、ものの数分で返信を示すポップアップが表示される。
『わお、残業仲間か。まだオフィス?』
『そうだ。早くビールが飲みたいよ』
『俺もだ。飯は食った?』
『いや、まだだ』
チャットのようにお互いの苦労をねぎらっていると、ふとバッキーからの返信が止んだ。作業が進んだのかと思いスティーブも資料に目を通し始める。3ブロック先で彼も同じように眼精疲労と戦っているのかと思うと、少しだけ気分が軽くなる。こちらのオープンに合わせて作業をしてもらっているから、彼の忙しさの一旦は自分に責があるのだが。そんなことを考えていると、再びポップアップが表示された。スティーブはその内容を確認して思わず目を見開いた。
『差し入れ、要る?』
「……わお」
思いがけない提案にスティーブの胸は跳ね上がった。彼が自分を気遣ってくれている、そしてここまでやってきてくれるなんて。遅くまで頑張っている自分へのギフトかもしれない。スティーブはニヤついてしまう口元を抑えながら、極めて理性的に返信を打った。
『魅力的な言葉だ、でも君の仕事は?』
『あるにはあるけど、今はエンジニアの作業待ちなんだ。というか、俺も腹が減って死にそう』
そこまで言われてしまえば答えは「イエス」しかない。
『じゃあお願いしようかな』
『了解、嫌いなものはある?』
正直この状況で出されたらなんだって美味しいと言えるだろう。たとえ嫌いなものがあったって今日から好きになれる気がする。そう思いながら『何もないよ』と返信する。少し待っててと言うバッキーのメールを見つめて、スティーブは今度こそ楽しげに息を吐き出した。
30分後、スティーブが契約書と格闘していると、後ろからノックの音が聞こえた。振り返るとガラス張りのドアの向こうでバッキーが手を挙げている。スティーブはすぐさ��立ち上がりドアのロックを解除した。バッキーを迎え入れると、いつもはまとめてある髪が下されていることに気がついた。よう、と首を傾げたのに合わせて後ろ髪がふわりと揺れる。正直にいってスティーブはそれに真剣に見惚れた。
「お疲れさま。チャイナにしたけど良かったか?」
スティーブの内心など露も知らないバッキーが手元のビニール包装を掲げる。途端に鼻腔をくすぐる料理の匂いが、一点で止まっていたスティーブの意識を現実に引き戻した。
「あ、ああ。ありがとう……ええと、そこにかけて待っててくれるか?」
呆けていた頭を動かし、バッキーに休憩スペースをしめす。ウォーターサーバーから水を注ぐ間も、うるさく鳴り続ける心臓が治まってくれる気配はない。それどころかコップを差し出したタイミングでこちらを見上げたバッキーに「皺がすごいぞ? チャイナは嫌いだったか?」などと言われてしまい、さらに動揺するはめになった。
「いや、好きだよ……ちょっと疲れがね……」
「お疲れだな、よし、食おうぜ」
これが炒飯で、これがエビチリ、とバッキーは次々に箱を開けていく。その姿を見ながらスティーブは悟られないように深く深く息を吐いた。
だって、びっくりするほど格好良かったのだ。初対面からハンサムだと思ってはいたが、ほんの少し違うだけの姿にこれほど動揺するとは思っていなかった。挨拶と同時にキュッと上がる口角も、こんなに目を惹きつけるものだったろうか。見慣れない髪型に引きずられて、バッキーが別人のように見えてしまう。スティーブは思わず手元の水を口に運ぶ。落ち着く為の行為だったはずなのに、ごくりと大きな音がしてしまい返って赤面する羽目になった。
「髪の毛……おろしてるのは初めてだ……」
耐えきれずに口に出す。バッキーは料理に向けていた目線を持ち上げるとああ、と笑った。
「夜まであれだと頭が痛くなってくるんだ。飯を食うときは結ぶよ」
そう言うやいなや手首にはめていたゴムで素早く髪をまとめてしまう。スティーブは自分の失言ぶりに思わず舌打ちをしそうになった。そのままでいいよと反射的に言葉が浮かぶが、この場でそれはあまりにもおかしい。結局、いつものバッキーに戻ったおかげでなんとか気持ちを飲み込んだスティーブは、気を取り直して目の前の料理に意識を向けることにした。
買ってきてもらったことへの礼を述べて料理に手を伸ばす。熱で温まった紙箱を掴むと忘れていた空腹が急激にスティーブを襲った。
「……思ってたより腹が空いてたみたいだ」
「はは、良かった。いっぱい買ってきたから」
紙箱を手に、真面目につぶやくスティーブが面白かったのかバッキーが目を細めて笑う。
「……チャイナ食ってるとさ、小難しいことを言わなきゃいけない気がしてくる」
しばらく黙々と料理を口に運んでいると、ふいにバッキーが呟いた。
「……マンハッタン?」
「あ、わかる? 家ならまだしも、公園なんかで食ってても思い出すんだよな」
なんなんだろうな、と苦笑するバッキーにつられて笑う。人気のないオフィスに紙箱とプラスチックのスプーンが擦れる音、そして2人の笑い声が静かに響いている。
「……映画、好きなのか?」
スティーブが尋ねるとバッキーはうーん、と曖昧に頷いた。
「俺、怪我で引きこもってた時期があってさ、その時には良く見てた」
「……その、腕の?」
「そう。結構前のことだからもう忘れてる映画も多いけど」
何でもないことのように告げると、バッキーは「スティーブは映画好き?」なんて聞いてくる。それに答えられるはずもなく、スティーブは静かに尋ねた。
「それは、事故で……?」
「え……ああ。車の事故で、当時は結構荒れたんだけど今はまあ、時間も経ったし、いい義手も買えたから。死なずに済んだだけ良かったかなって……ええと、そんな深刻な意味じゃなくてさ」
からりと笑う彼がジムのモニター以外で腕のことに触れたのは、初対面の時と今日で2度目だ。その間、彼はなんのハンデもないかのように笑っていた。バッキーはそう言うが、スティーブは眉を寄せるのを止められない。それを見て、バッキーは困ったように微笑んだ。
「まあそれこそジムにはちょっと行きにくいけどな。それ以外は、今の仕事もこのことがあったから始めたようなもんだし、サムに出会ったのもそうだ。悪いことばかりじゃないよ」
そう言われてしまえば、ステイーブはそれ以上何も言うことができなかった。きっと彼は同情や心配を厭というほど受けて、今こうして話してくれているのだから。
「……君がジムの件を引き受けてくれて、心から感謝してるよ」
精一杯の気持ちをその言葉に乗せる。それは間違いなく本当のことだったし、それ以上のことも。相手に伝えたい気持ちと、少しも傷つけたくない気持ちを混ぜ込んで、ぎりぎり許せるラインの言葉をスティーブは押し出した。たとえその中に、その時の彼の傍に居たかったなんていう傲慢な気持ちがあったとしても。
「いや、こちらこそ。会社としてもいい機会だったし……何より、下心もあった」
「――え?」
思わぬ言葉に口を開けたスティーブに、バッキーはニヤリと口元を引き上げた。こんな時でさえ、その表情がとても様になっている。
「今度できるジム、俺の家の近くなんだ。だからめい一杯俺好みのジムにして、会員になろうかなって」
「え、そうなのか?」
「そうだよ。まあ場所は途中で知ったんだけど」
たしかにバッキーにも一度工事中のジムに足を運んでもらった。実際に見てもらうに越したことはないからだ。そのときは何も言っていなかったのに。
「……だったら、名誉会員扱いにしないとな」
「え、そんなのがあるのか。プロテイン飲み放題とか?」
目を煌めかせたバッキーを見て、今度こそ2人で笑う。こうしてずっと彼の笑顔を見ていたいと、スティーブは強く思った。強くて優しい彼の笑顔を。
「あ、じゃあ僕もそっちのジムに登録し直そうかな」
「ん?」
「そうしたら君と一緒にトレーニングができるだろ」
そう言ってバッキーに笑いかける。���の仕事がひと段落したら彼に会えるペースは少なくなるだろう。たとえアプリで継続的に関係が続くと言っても、今ほどじゃない。ましてや顔を突き合わせて話す機会なんてぐっと減るはずだ。そう考えたらジムの案は自分でも良い提案のように思えてくる。どう? と彼の顔を伺うと、バッキーは一瞬なんとも言えない顔つきをした後、小さくわおと呟いた。
「……あんたと一緒にトレーニングしたら、その胸筋が手に入る?」
「どうだろう、でも僕のメニューは教えてあげられるよ」
バッキーはついに耐えきれないといった様子で破顔した。眉を思いっきり下げたそれは、彼の笑顔の中でも特にスティーブの好きなものだった。
「最高だ」
その時、タイミングを見計らったかのように、机に置いていたバッキーの携帯が鳴った。バッキーは横目で画面を確認すると、スプーンを置いてそれを取り上げる。しばらくして画面に落とされていた目がスティーブを捉えた。
「アップロードが終わったって。URLを送るってさ」
「え、あ、そうか。良かった」
「ああ……、じゃあ、これ片付けちまわないとな」
そう言ってバッキーは手元の紙箱から炒飯をすくった。スティーブも我に返ったように残りの料理を食べ始める。いつの間にかそれらはすっかり冷めていて、でも不味いとは全く思わない。それでもこの時間が明確に終わってしまったことが残念で、ちらりとバッキーを覗き見る。しかし、目の前の彼と視線が合うことはなかった。
2人は今まで食事もそっちのけで話していたのが嘘かのように無言で料理を口に運び続けた。
『Hello Steve, ――
新店舗オープンおめでとう。最後の方はとにかく慌ただしそうだったけど、体調は崩してないか? これがひと段落したらゆっくり休めることを祈るよ。アプリの方も一旦は問題なさそうで良かった。また何かあったら教えて欲しい。
今回スティーブの会社と一緒に仕事ができて良かったよ。いろんなデータが得られたし、現場のフィードバックがもらえたのも、うちにとって大きな財産になった。もちろん、個人的に協力させてもらえたことにも感謝してる。今の会社も腕のことがあってのことで、そうやって自分が感じてきたことが本当の意味で役立てられたような気がして、すごく嬉しかったんだ。微力でしかなかったけど、何かしら良いアドバイスができていたら嬉しい。(まあそれはこれから自分で体感するんだけど)
改めて、おめでとう。今後もお互いの仕事の成功を願ってる。
Best regards, Bucky』
『Hello Bucky, ――
嬉しい言葉をありがとう。やりがいのある仕事だったよ、だけで終われたら良いんだけど、正直ヘトヘトだ。今度の土日は自堕落を許すことにするよ。
僕も君と、君の会社と仕事ができて良かった。本当に、心からそう思ってるよ。君らとの仕事は驚くほどやりやすかったし、いろんなことを助けてもらった。君の想像以上にね。新しくオープンしたジムが成功したなら、それは間違いなく君たちのおかげでもあるよ。ありがとう。
それから、君と出会えたことにも深く感謝している。君と出会うまで僕がどれだけ狭い世界に生きていたかを思い知らされたよ。この年齢になってもまだ学ぶことが多いと気付かされた。そしてそれを教えてくれたのが君で良かった。
君も、いろいろ我儘に付き合ってくれてありがとう。しっかり休んでくれ。
Regards Steve, 』
スティーブは画面の文章を何度も読み返し、おかしな所がないかを入念にチェックした。新店舗のオープン日に届いていたメールは、現場で奔走していたスティーブの目に一日遅れで入ってくることになった。メールを読んだときは思わずデスクに突っ伏してしまったし、そのせいで同僚から白い目で見られた。しかしスティーブにそんなことを気にしている暇はなかった。はちきれそうな嬉しさと、すぐに返事ができなかった申し訳なさでどうにかなりそうだったのだ。そして大至急返事を認め、長くなりすぎたそれを添削しては寝かせてまた添削するという作業を繰り返していた。
ビジネスで仲良くなった相手に送る文章としてはおそらくこれが正解だ。そして自分の気持ちも正直に告げている。バッキーに出会えたことでスティーブが得たものは、言葉にできないほど大きかった。3度目の確認を終えて、スティーブはゆっくりと送信ボタンを押した。
ふう、と吐き出したそれには、しかし多少の迷いが込められていた。
(……本当にこれだけで良いのか?)
この文章で、きっと今後も彼とは良い関係を築いていけるだろう。ジムの約束もしたし、彼との仕事上の付き合いは多少頻度が減ったとしても続いていく。それでも、スティーブが一番伝えたいことは、今のメールには含まれていない。まだ名前をつけていないステイーブの気持ち。それを伝えるのに、今を逃したら次はいつになるのだろう。――いや、きっと次なんてない。
スティーブはもう一度返信画面を開き、素早く文章を打ち込んでいった。心臓がバクバクとうるさい。気をそらすな、不安に負けるな。全てはタイミングだ。そしてそれは、今だ。
『追伸 もし良ければ、君の連絡先を教えてもらえないだろうか。できれば、私用の』
送信ボタンを押して深く深く息を吐く。そしてスティーブはすぐさまメールを閉じようとした。
その瞬間、デスク上に置いておいた携帯がいきなり震えだす。
「わっ」
気が抜けていたせいで変な声が出てしまった。画面の表示を見ると知らない番号から着信がきている。スティーブは動揺を押し隠しながら画面をスワイプした。
そうして聞こえてきた呆れ声に、すぐにその顔は笑顔になる。
『――さすがに奥手すぎだろ、スティーブ』
きっと近いうちに、彼らの挨拶はもう1段階進んだものになるだろう。
1 note
·
View note
Photo
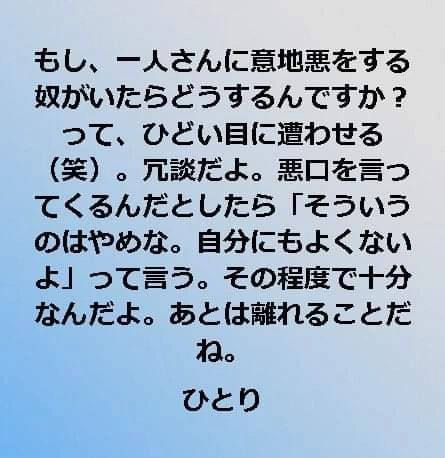
もし、一人さんに意地悪をする奴がいたらどうするんですか?って、ひどい目に遭わせる(笑)。冗談だよ。悪口を言ってくるんだとしたら「そういうのはやめな。自分にもよくないよ」って言う。その程度で十分なんだよ。あとは離れることだね。 ひとり 斎藤一人さん→ @hitori_saito #斎藤一人 #斎藤一人さん #斉藤一人 #斉藤一人さん #柴村恵美子 #名言 #銀座まるかん #日本漢方研究所 #龍神様 #偉人の言葉 #格言 #エイブラハム #スピリチュアル #引き寄せの法則 #宮本真由美 #ついてる #納税日本一 #舛岡はなゑ #天国言葉 #言霊の力 #言葉の力 #偉人の名言 #潜在意識 #アメノミナカヌシ #名言集 #成功者 #バシャール #風の時代 #小林正観 #ブロック解除 https://www.instagram.com/p/Ccd0fvEvw0p/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#斎藤一人#斎藤一人さん#斉藤一人#斉藤一人さん#柴村恵美子#名言#銀座まるかん#日本漢方研究所#龍神様#偉人の言葉#格言#エイブラハム#スピリチュアル#引き寄せの法則#宮本真由美#ついてる#納税日本一#舛岡はなゑ#天国言葉#言霊の力#言葉の力#偉人の名言#潜在意識#アメノミナカヌシ#名言集#成功者#バシャール#風の時代#小林正観#ブロック解除
0 notes
Text
#044 ボーイ
日本国千葉県市川市塩浜二丁目にある市川塩浜というなにもかもが中途半端な駅の安っぽいベンチに、その男の子は座っていた。毎日いた。毎晩いた。日がな一日そこにいた。あるときは、菓子パンを頬張っていた。あるときは、ペットボトルを握っていた。あるときは、電車のドアが閉まるタイミングに合わせてフエラムネを鳴らしていた。あるときは、ぶんぶんゴマを回転させていた。どこで湯を調達したのか、カップヌードルに蓋をして、三分、じっと待っていることもあった。だいたいは小ぶりのリュックサックを背負っていたが、コンビニのビニール袋だけを持っているときもあった。紙袋を横に置いているときもあった。いつも、何も持っていないような顔をして、そこにいた。
市川塩浜駅の利用客は、周辺の工場や倉庫に努めている会社員や契約社員やアルバイトがほとんどだった。あとは、周辺の工場や倉庫に視察にきた本社の人間。男の子はそのことを知らない。なんだかみんな、一様に、具合の悪そうな顔で電車から出てくるな。男の子はそう思っていた。
ごくまれに、駅のホームで電車を待っている人が、男の子に話しかけてきた。ぼく、どうしたの? 学校は? お母さんは? 話しかけてくる人は、なぜかほとんどが女性だった。小さなツヤツヤしたバックを肩から下げ、パンプスかヒールを履いているような。視察の人間。男の子はそのたび、相手をじっと見つめ、意味ありげなジェスチャーと、意味ありげな口パクをした。自分の耳の辺りを指したり、言葉にならないうめきのような声をかすかに出した。そうすると、だいたいの人は黙り込んだ。困った顔もした。そしてそのあと、大抵の人が慌てた様子でカバンから紙とペンを、あるいはスマホを取り出した。男の子はそれを受け取り、毎回、こう書いた。
「ひとを まっています だいじょうぶです ありがとう さよなら」
相手は安心と困惑とバツの悪さが入り混じった顔をして、手を降って男の子から離れる。だいたいそんな感じだった。
男の子は考える。どうして話しかけてくるとき、最初にぼくが付くんだろう。なんだか、名前みたいだ。マイネームイズボク。男の子は不思議だった。僕はただここにいるだけなのに、話しかけてくる人は、どうしてみんな学校のことや親のこと(それも、なぜか必ず、お父さんじゃなくて、お母さんのこと)を聞いてくるんだろう。どうしたの? と言われても、答えようがなかった。そっちこそ、どうしたの? と、逆に聞いてみたかった。みんな、どういう答えを求めているのだろう。
男の子はその日、小さな巾着袋を持っていた。中にはパインアメが袋いっぱいに詰まっていた。男の子はパインアメを舐める。眼からじわじわと湧き出る涙で、男の子はこの駅にも春がやってきたことを知った。男の子は、花粉症だった。
「最近悪夢ばっか」
男の子のとなりに男が座っていた。男の子は男がしゃべりだすまで、男が近づいてきたことにも、となりに座ったことにも気がつかなかった。男の子は横目で電車の発着を告げる電光掲示板を見て、自分がほんの少しの間、眠っていたことを知った。
「この前見たのは、嵐の二宮とピアノコンサートをする夢。ステージ上にヤマハのグランドピアノが二台置いてあって、客席から見て俺は右、ニノは左のピアノの前に座って、演奏したんだ。俺はその楽譜を、そのとき初めて見た。知らない曲だった。当然、弾けない。それでも俺は頑張った。でもダメだった。コンサートは大失敗だった。俺は曲の途中でステージ上から逃げ出して、ペットショップで犬用のトイレを買った。それからあとは、覚えていない」
男は、男の子の方を見ながら、オーバーな表情と身振りで話し続けた。
「そのさらに前は、映画を撮る夢を見た。俺は寂れた小学校みたいなところで寝泊まりしていて、隣の部屋で寝泊まりしていたカメラマンみたいな奴にカメラを渡されるんだ。で、こう言われる。『俺の代わりに映画を撮ってくれないか』俺はカメラを渡される。録画機能のない、古いタイプのデジタル一眼レフカメラだった。俺は写真を撮りまくった。写真を撮るっていう行為が、つまりは映画を撮るってことだった。それから色々あって、俺は幼なじみと二人で、サバンナみたいな場所を、大量のチューバを担いで、幼なじみは引きずって、歩いていた。それからあとは、やっぱり覚えていない」
男は缶コーヒーを持っていた。プルトップは開いていない。熱くてまだ飲めないのだ。男は、猫舌だった。
「昨日は、ヤクザになった友達から逃げ続ける夢を見た」
男は、あらかじめ決められていたかのように背中を曲げて、男の子の顔をのぞきこんだ
「なあどう思う?」
男の子は男の方を向き、あらかじめ決められているジェスチャーと口パクをした。耳の辺りを人差し指でトントンと叩き、うめき声をあげた。男は眼を少しだけ見開いて、笑いを堪えるように口を尖らせた。それから、缶コーヒーのプルトップを開けて恐る恐るコーヒーを口に入れた。
「ふうん」
缶コーヒーの中身は男の舌でも味がわかるくらいぬるくなっていた。男は缶コーヒーを、今度はさっきより勢いをつけて飲み、男の子の耳元に顔を寄せた。
「つくば山に、喰いつくばあさん」
男はささやいてから、吹き出すのをこらえるような顔をして、缶コーヒーに口をつけた。男の子はそれが、駄洒落だということに遅れて気づく。男の子の脳裏に、つくば山を食い荒らす巨大な婆さんの画が浮かんだ。男の子は、自分の顔が歪むのをなんとか堪えた。
「あの、人を、待ってるから」
男の子は、口を開いた。なんだかもう、嘘をついてもどうしようもないような気がした。
「係長がさあ」男は男の子の言葉を無視して言った。
「係長が、俺に言うんだよ。『社員にならないか』って。冗談じゃねえって話だよな。部長だか支店長だか知らないけど、とにかく係長より偉いおっちゃんもそれに賛成しているふうでさ。たまったもんじゃないよな」
男は缶コーヒーを飲み干した。
「どうしたもんかしらね。やんなっちゃう」
男は立ち上がり、缶コーヒーをホームの白線の上に置いて、助走をつけて思い切り蹴飛ばした。缶コーヒーは向かいのホームの壁に当たり、地面に落ちてころころと転がった。向かいのホームにも、男の子と男がいるホームにも、男の子と男以外に人はいなかった。向かいのホームの電光掲示板とスピーカーが、電車がまもなく到着することを簡潔に伝えていた。
「みんなさ、忘れてるんだよ。俺、ちゃんと言ったんだよ。面接のときに『半年で辞めます』って、ちゃんと。忘れてるんだよな。半年。頑張ってると思うわ」
男はジーパンの尻ポケットからぱんぱんに膨らんだ長財布を取り出した。
「なんか飲む?」
「いらない」
「あ、そう」男は立ち上がり、自販機に向かった。「てか耳、聴こえてんじゃん」
男はさっきと同じ銘柄の缶コーヒーを買って、男の子のとなりに戻ってきた。男は男の子に爽健美茶のペットボトルを渡した。男の子は、それを左手で受け取った。
向かいのホームに電車が止まり、しばらくして、また動き出した。電車に乗る人も、降りる人もいなかった。男は缶コーヒーを右手から左手に、左手から右手に、何度も持ち替えながら、缶コーヒーが冷めるのを待っていた。最初からつめた〜いの方を押せばいいのに、男はそうしなかった。男は、ぬるい缶コーヒーが好きだった。
「どうしたもんかしらね……。やんなっちゃう」
男の子は、それが男の口癖なのだと知った。
「だから、なーんか今日、起きたときから行く気、しなくって。こんなところにいるわ」
男はジーパンのポケットからiPhoneを取り出し、男の子に見せた。
「ほらこれ、係長、しつこいんだから」
男はiPhoneを男の子のほうに向けながら、指で画面を下にスライドさせた。
「こんなに。連絡しない俺も俺だけど。どんな病気がいいかなあ。風邪って言えばじゅうぶんかな? どういう咳ならそれっぽいかな?」
「なんの仕事」
「いつの時代も、流行り病は仮病だよ。係長、困っちゃってんだよ。俺がいないと仕事、回んないから。大幅にペースダウンよ。結局、ペースダウンするだけよ。代わりなんていくらでもいるって。やんなっちゃう。いいんだけど」男は言った。「仕事? 倉庫だよ倉庫」
「どこの倉庫」男の子は言った。
「どこだっていいよ」男は言った。「あっちのほう。海の近く」
「海沿いなのに潮の匂いがしないって、やんなっちゃうよな。この駅もそうだよ。もっと漂ってきてもいいだろって。いいけどさ。山派だし」
「耳が悪いのは、ほんとだよ」男の子は言った。
「仮病?」男は缶コーヒーを振った。缶コーヒーは、着々と温度が下がってきていた。
「ちがう」
「いやでも、あの演技はなかなか。将来有望なんじゃないの」
「ちがう」男の子は言った。「きいて」
「やなこった」男は缶コーヒーのプルトップを開けた。「さっきの駄洒落、最高じゃない?」
「もっといいの、知ってる」
「ほーん」男は恐る恐るコーヒーを口に入れた。「言ってみ」
「ブラジル人のミラクルビラ配り」
「それは早口言葉だ」男は言った。「ブラジル人のミラクルビラ配り! しかも、あんまり難しく、ない!」
「おやすみなさいを言いに行くと、ママ、いつも戦争してる」
男の子と男がいるホームの電光掲示板とスピーカーが、電車がまもなく到着することを簡潔に伝えていた。その電車は、東京まで行くらしかった。男の子は、眼をこすった。主に眼にくるタイプの花粉症だった。
「去年の大晦日はひどかったな。普段は五、六個の駅も二〇とか三〇だし、舞浜なんてただでさえいつも出荷数が断トツで多いのに、一五八だぜ。一五八。やんなっちゃったよ。ほんと。シールの束がこんな量、あんの。あれは戦争だった」男は缶コーヒーをぐびぐび飲んだ。
「それで、だんだん、耳がおかしくなった」男の子は言った。「戦争って、うるさいから」
「俺も俺の周りのバイトもひーこら言いながらカゴにひたすらダンボール積んだよ。いや、言ってないけど。実際は黙々としてたよ。静かなもんだったよ。うるさいのは係長とそのとりまきの契約社員どもだけ」
男の子と男がいるホームに電車が止まり、しばらくして、また動き出した。電車に乗る人も、降りる人もいなかった。電車は二〇分ほどで東京に着く。東京駅には、電車に乗る人も、降りる人も、たくさんいた。
「今思えばあれはバケツリレーみたいだった。あんまり数が多いもんだから、みんなカゴ持っておんなじ場所に集まっちゃうんだよ。とてつもない流れ作業で、なんとか普段通りの時間に帰ることができたけど。でももう、無理だね」男はタバコが吸いたかった。「無理だね、もう」
男の子は、巾着袋からパインアメを取り出し、口に入れた。
「あ、ずる」男は言った。「ちょうだい」
男の子は、男にパインアメを一つあげた。
男は、それを口に入れた。
パインアメが溶けてなくなるまで、男の子と男はほとんど口を開かなかった。男の子と男は、それぞれ違うものを見つめていた。男の子は向かいのホームに転がっている缶コーヒーを、男は男の子のうなじを見つめていた。男の子の髪は陽を浴びて、輪っか状に光っていた。天使の輪っか、と男は思い、そんなことを考えてしまう自分が気持ち悪いとも思った。駅のホームには男の子と男以外誰もいなかった。男の子と男以外、みんなみんな、工場で、倉庫で、コンビニで、それぞれの場所で働いていた。係長はいつものように奇声を発しながら嬉しそうにフォークリフトでパレットを移動させている。バイトや契約社員はカゴ台車で、あるいはローリフトにパレットを挿して、駅構内の売店へ出荷するための飲料水が詰まったダンボールを駅別の仕分けシールを見ながらどんどん積み上げている。シールの束を口に加えて全速力で倉庫の中を端から端まで走り抜けている。そのことを男は知っていた。男の子は知らない。
男の子と男がいるホームを快速列車が通過したとき、男の子と男の口からパインアメはなくなっていた。男は空になった缶コーヒーを両手でもてあそんでいた。男の子は右手で両眼の涙を拭った。男は、花粉症ではなかった。
「将来の夢は?」男は言った。缶コーヒーをマイクに見立て、男の子の前に差し出す。
「ふつう」
「ふつう、て」男は缶コーヒーを下げた。「どうしたもんかしらね」
「たのしいよ」
「うそつけ。ママの戦争でも終わらせてから言いな」
男は立ち上がり、伸びをした。
「んーあ」
「ママ、神様が死んじゃったことに気づいちゃった」
「へえーえ」あくび混じりの声で男は言った。「そいつはすげー。もはやママが神様なんじゃないの」
「ある意味、そう」男の子はパインアメを舐め始めた。「ママ、なんでもできるよ」
「ある意味?」男はまたベンチに座った。
「うん。……うん」
男の子は、神様が死んだときのことを思い出していた。つい最近のことだ。男の子が家に帰ると、神様はリビングのホットカーペットの上で、あお向けの状態で小刻みに震えていた。男の子は震える神様を両手でうやうやしくすくいとり、テーブルの上にティッシュを二枚重ねて、その上に神様をそっと寝かせた。朱色だった身体は見る間に灰色に変わっていき、柔らかな尾ひれは押し花のようにしわしわに乾燥していった。男の子は神様の前で手を合わせ、しばらく眼を閉じてから、ティッシュで神様をくるんで持ち上げ、近所の公園の隅に小さな穴を掘って埋葬した。線香が無かったので、台所の引き出しから煙草を一本抜き出し、それに火をつけて、埋めたばかりでまだ柔らかい土にそっと差し込んだ。男の子は、もう一度神様に手を合わせた。
「僕が勝手に埋葬したから、怒ってるんだと思う」
向かいのホームに箒とちりとりを持った駅員がやってきて、掃除を始めた。男と男の子は、それを黙って見つめていた。ここからでは何かが落ちているようにも、汚れがあるようにも見えないけれど、きっといろんなものが落ちているのだろう。男は思った。駅員はこっちのホームにも来るのだろうか。何かが落ちているようには見えないけれど、きっとやって来るのだろう。駅員は階段のそばの点字ブロック付近を執拗に箒でなぞるように掃いていた。
男は、自分がまだ男の子だったころのことを思い出していた。朝が苦手で、ドッチボールと給食の牛乳が好きで、放課後はランドセルを武器にして誰かとしょっちゅう戦っていた。まあだいたい、今とさして変わんないな。男は兄のことを思い出した。
「兄妹は?」男はもう一度缶コーヒーを男の子の前に差し出した。
「いない」男の子は言った。
「一人っ子ぉ〜」男は言った。「ま、俺もそんな感じだけど」
男がまだランドセルで戦っていたころ、男の兄は家からいなくなった。車の免許を取ったあと、親の財布から抜き出したお金を使って北海道まで飛び、ネットで知り合った人の家や車を転々としながら徐々に南下し、今は沖縄本島の小さな民宿で、観光客に広東語やフランス語を教えてもらったりしながら住み込みで働いている。お金が無くなったら自殺するつもりで家を出たんだ。一年ほど前、カメラ通話で外国人みたいな肌の色をした兄が笑ってそう言うのを、男は白けた気分で聞いていた。
「行かなくていいの」男の子はパインアメを舌で転がしながら言った。
「ん? 何?」缶コーヒーが男の子の前に差し出された。「仕事?」
「そう」
「何をいまさら」男はふふんと笑う。「そのセリフ、そっくりそのままお前にお返しするわ」
「僕は人を待っているから」
「いつまで?」
「いつまでも」
「そうですか」男は缶コーヒーをベンチの下に置いた。「やんなっちゃう」
「帰らないの」
「帰ってもいいよ。でも」男はベンチの上であぐらをかいた。「でもお前が待ってた人って、実は俺のことなんじゃないの」
「……」
「あ、それ、わかるよ。絶句、ってやつだ」男は男の子を指さして笑った。
「人を待っているから」男の子は繰り返した。溶けて薄くなったパインアメを歯でガリガリと砕く音が、男の子の耳にだけ響いた。
「ああ、ほらこれ、係長からラブコール」男は震え続けているiPhoneを取り出し、男の子に見せた。「係長も、どうやら人を待ってるらしい」
やがてiPhoneの震えは止まり、男はiPhoneをジーパンの尻ポケットに押しこむようにしまった。
男と男の子は、喋りながらまったく別々のことを考え続けていた。男は兄と、兄がいたころの自分を。男の子は、神様について。思い出し、考えていた。ほんとうはどうするべきだったのか。何か間違ったことをしたのだろうか。何か決定的な間違いをおかしてしまったのだろうか。男と男の子は、それぞれが何を思って、考えているのかを知らない。ふたりは知らない。
ふたりのホームに鳩がやってきて、数歩ごとにアスファルトをついばみながらベンチの前を横切った。鳩の片足には短いビニール紐のようなものが絡まっていて、鳩が歩くたびにカサカサと微かに音が鳴った。
「帰ろうかなあ」男は男の子の左手にある未開封の爽健美茶のペットボトルを見た。「次の電車で帰るわ」
「これ」男の子は爽健美茶を男の鼻先に掲げた。「いらない」
「パパにでもあげな」男は言った。「最後の質問。お名前は?」
「ボク」
「は」気だるそうに立ち上がりながら男は短く笑った。「ママの戦争が終わるといいね」
「待ってる人が来れば、終わるよ」
「うそ。お前次第だろ」男は腰に手を当てて線路を見た。腰の形に沿ってシワができたTシャツを見て、この人ちゃんと食べているんだろうか、と男の子は思った。
「あーあ、俺も行きてえ〜、南の島」
男はあくびを噛み殺しながら、線路を見つめ続けていた。
○
男の子は、日が暮れて夜になっても、市川塩浜駅のホームのベンチにずっと座っていた。帰宅ラッシュでホームが人で溢れ、ベンチがすべて埋まっても、男の子は座ったままだった。ラッシュも終わり、駅のホームがふたたび廃墟のような寂れた静けさを取り戻したころ、男の子は立ち上がった。巾着袋をベンチに置き、ベンチの下にある缶コーヒーを拾ってゴミ箱へ捨てた。左手に爽健美茶のペットボトルを、右手に巾着袋を持って、男の子は二三時五六分発の東所沢行きに乗った。
人の少ない電車の中で、男の子は少しだけ眠り、少しだけ夢を見た。夢の中で、男の子は大学生だった。数人の友人と数人の先輩に囲まれて、お酒を飲んだり煙草を吸ったり、笑ったり泣いたり、怒ったり喜んだり、走ったりうずくまったりしていた。それは夢にしてはあまりにもありふれた、だけどどこか切実な、現実の延長線上にあるような夢だった。
目が覚めた男の子は、停車駅の看板を見てまだ電車が二駅分しか移動していないことを知る。男の子は夢を見たことすら覚えていなかった。男の子は発車ベルを聞きながら、眠っている間に床に落ちてしまった爽健美茶を拾った。
男の子は想像する。駅のホームを行き来する電車のこと、その電車に乗る人のこと、駅員のこと、そして今この電車に乗っている人のこと。みんなの家のことを。その神様のことを。そして自分の家を思う。新しい神様を見つけないといけないのかもしれない。母親を戦場から引っ張り出すには、それしかない気がした。男の子は頭を窓にくっつけて、眼を閉じた。今度は、夢を見なかった。
○
男の兄は、何かと繊細なやつだった。人混みや集団行動が苦手で、電車に乗ったり、ひどい時は家から外に出ただけで歩き出せなくなるほどだった。ネット上には大勢の友人がいた。変なところが凝り性で、パソコンのマインスイーパーやタイピングゲーム、パズルゲームをひたすらやりこんでいた。肉が駄目で、馬のように草ばかり食べていた。首筋と腕の関節部分にアトピーのような肌荒れがあり、四六時中かきむしってフケのような皮膚のかけらをあたりにばらまいていた。男が兄について知っていることは、それくらいだった。
男はアパートに帰ってから、敷きっぱなしの布団の上でしばらくボーッとしていた。係長はもう、男に電話をかけてこなかった。誰も男に電話をかけてこなかった。それでいいと男は思った。
「ブラジル人のミラクルビラ配り」
男はあお向けに寝転び、眼を閉じて呪文のように何度もつぶやいた。簡単すぎるな、そう思った。つぶやき続けているうちに男の口はしだいに動かなくなり、静かに息を吐いて、眠りはじめた。
日付が変わる少し前、男は起き上がった。頭をかきながらしばらく時計と窓を交互に見つめ、水を飲み、トイレに行ったあと、兄に電話をかけた。自分から兄に電話をかけるのは初めてだな、と男は電話のコール音が鳴ってから気づいた。
「おお」
「よお」
「もしもし?」
「うん。もしもし」
「急にどうしたの。めずらしい」兄の声は穏やかだった。
「沖縄は今、何℃だ」
「えっと……えーっとね」兄の声がくぐもって聞こえる。iPhoneを顔から離して、天気情報を見ているのだろう。「22℃っす〜」
「元気か」
「まあ元気」
「焼けてんのか」
「そりゃもう。こんがり」
「野菜ちゃんと食ってんのか」
「それ俺に言う?」
「もう死なんのか」
「そうだね」兄は間髪入れずにそう言った。「まあなんとか、生きてみようと思ってるよ。今んとこ」
「つまんね」
「なんだそれ」兄は笑った。「そっちはどう?」
「何が」
「元気か」今度は兄がインタビュアーだ。
「ノーコメント」
「家賃とかちゃんと払ってんのか」
「ノーコメント」
「野菜ちゃんと食ってんのか」
「ノーコメント」
「話にならねー」兄はまた笑った。「両親は元気か」
「しらん」男は間髪入れずにそう言った。「知ってたとしても、お前には教えないね」
「そりゃそうか。ま、いいや。とりあえず生きてるでしょ、たぶん」
男と兄はしばらく黙った。通話口からは、よくわからない言葉で笑い合う人の声が聞こえた。沖縄語も外国語も、同じようなもんだな。そして兄の言葉も。男の部屋は、静かだった。隣の部屋の生活音も聞こえない。
「電話出て大丈夫だったのか」
「いまさら。大丈夫。宿泊客と酒盛りしてただけだから」
「タノシソウデナニヨリデスネ」
「なんだよ。もしかして酔ってる?」
「ノーコメント」
「めんどくさいなー」笑いながら兄は言った。
「来週の日曜日、ヒマか」
「ヒマかどうかはわかんないけど、まあ、この島にはいるよ」
「そうか」
「何?」
「俺、お前んとこ、行くよ」
「あ、ほんとに?」
「お前をぶっ殺しに行くわ」
「わ、殺害予告」
「通報でもなんでもすりゃいいよ」
「しないよ。ワターシノアイスルブラーザーデスカラ」
「つくづくお前はつまんねえ」
「知ってるよ、そんなこと」
「逃げるなよ」
「逃げないよ」兄の声は優しかった。兄が家にいたとき、こんな声で話したことがあっただろうか。男は思い出せなかった。「まあ、おいでよ。待ってるよ」
「ファック」
男は電話を切り、電源も切ってからiPhoneを放り投げた。男は本気だった。部屋を出て、コンビニへ行き、ATMで残高を確認した男は、これから自分がやるべきことを考えながら、昼間と同じ缶コーヒーを買った。まずは、包丁。
○
男の子がグランハイツ東所沢の四〇五号室の玄関扉を開けたのは、日付が変わってからおよそ一時間半後のことだった。男の子はリビングのテーブルの前に爽健美茶のペットボトルを置いた。床に散らばっていた不動産のチラシを一枚手に取り、テーブルの上に無造作に転がっていた赤ボールペンでチラシの裏に大きく「パパへ」と書いて、爽健美茶のペットボトルの下に挟んだ。
男の子はキッチンでお茶碗に炊きたてのご飯をよそい、フライパンの中からサンマの照り焼きを小皿によそい、リビングのテーブルの上にそれらを置いて、立ったまま食べた。男の子は、少食だった。それから男の子はお茶碗と小皿を簡単に洗い、自分の部屋から着替えを取って風呂に入った。男の子は、風呂が嫌いだった。浴槽に浸からずシャワーだけ浴び、男の子は風呂を出た。それから洗面台の前で入念に歯を磨き、綿棒二本と竹の耳かきで両耳を入念に掃除した。男の子は、きれい好きだった。それから男の子は、風呂場と洗面台と、リビングとキッチンの電気を消し、玄関へと続く狭い廊下の途中にある白い扉の前に立った。部屋の中からは、銃撃、爆撃、悲鳴、ファンファーレなどの音が絶えずとてつもない大きさで聴こえていた。男の子は、扉をノックした。それから、返事を待たずに扉を開けた。男の子は部屋の中に入る。
「おやすみなさい」
男の子は、この言葉が好きだ。
0 notes
Photo

彼が童貞かも…彼女として初セックスで気をつけることは? https://ift.tt/2rhhqwg
1:彼が童貞かも…うまくお付き合いするには?
付き合った彼氏が経験のない童貞だった! 年々、初経験の年齢が上がりつつあるこのご時世。付き合った彼氏がいい大人であっても童貞なんてことは、不思議ではありません。
ではそんな童貞の彼とどうやって付き合っていけばいいのでしょうか。今まで、付き合ってきた彼とは、少し違う付き合い方が必要かもしれません。
今回はそんな童貞彼氏と、うまく付き合う方法について見ていきましょう。
2:この人童貞かも?いい歳して童貞男の特徴5つ
まずはその彼が童貞かどうか確かめる方法から。最近は大人であっても、経験したことがないという人は少なくありません。その特徴を見ていきましょう。
(1)ギャルが苦手
童貞は、ギャルのような、メークが濃く、ハデめの女性を嫌う傾向にあります。
「ちょっと短めのスカートを履いていただけで、初対面の男性に“クソビッチ”呼ばわりされたことがあります。後から聞いたら、その人はチェリーだって。なるほど納得」(Mさん・24歳)
その外見だけで相手をビッチと決めつけ、軽蔑するような男性……。裏を返せば、経験のない自分と比べて、経験豊富そうに見える女性のことが怖いのかもしれませんね。
(2)些細なことで傷つく
特に女性関係に関して。女性に言われた何気ないひと言で大ダメージを受けます。
「馬鹿じゃね?」など、ちょっとからかって言ったつもりでも、LINEを即ブロックされてしまうことも。ほんの些細なことで心が傷つき、冗談が通じないのは童貞あるあるの最大の特徴です。
(3)空気が読めない
痴話喧嘩や別れた後すぐなど、女との間に生じるピリピリとした独特の空気を読めないのが童貞。
例えば、別れた直後のカップルに向かって、「最近どうなの?」などと平気で言い放ち、その一言で周りの空気を凍らす達人です。
(4)妥協しない
いつまでたっても童貞を卒業できないのは、女性に対して求めるものがありすぎるから。可愛い子じゃなきゃダメ、高学歴じゃなきゃダメ、胸が大きくなきゃダメ……。
「弟が未だ未経験らしいのですが、話を聞いていると、理想だけがひとり歩きしている状態。最近は、乃木坂46にるような女の子がいいと言っていますよ」(Aさん・25歳)
とにかく女性に対して求めるものが多くて妥協ができない男性は、童貞の確率が高いでしょう。
(5)内弁慶
童貞とは世界が狭いものです。童貞を下ろして初めて見��てくるものがあるのではないでしょうか。
「とにかく視野が狭いというか、地元から全然出ようとしない奴って、未だに童貞が多い気がする。都会に出たらいろんな女の子もいるし、いろんな経験もできるのに」(Tさん・21歳)
内弁慶さのあまり世界が狭まっていってしまうタイプですね。狭い世界でドヤっては、広い世界に飛び立とうとはしません。
3:童貞ボーイとの初セックス…気を付けること5つ
そんな童貞ボーイと初セックスをする場合、何を気を付けたらいいのでしょうか。
最近、童貞を卒業したというJくん(23歳男性)に話を聞いてみました。
(1)意外に任せていい
未経験の彼。しかし、童貞は童貞なりに、むしろ経験者よりもセックスの知識は豊富かもしれません。経験はないにしても、ネットなどでセックスに関する情報は徹底的に下調べ済み!
「彼女とのお泊りをするとなったときから、ネットなどでセックスに関する記事を読みまくりましたよ。セックスそのものの知識や、セックス後の女性の心情なとかも。経験はないにせよ、そこらの男性より、知識だけは豊富である自信があります」
童貞であっても男性ですし、やはりプライドもあるでしょう。女性側がリードするよりも、まずは童貞くんの力を信じて、任せてみてはどうでしょうか。
(2)明るいところで
初体験であれば、女性器をまったく見たことのないという人が多いことでしょう。女性の裸であればAVなどで見たことがあっても、女性器までは見れません。
「とにかく、中がどうなっているか気になりましたね。明るいところでじっくり拝んでみたいもんだと思います」
(3)ムードを大切に
初めてのセックスは、男女ともに一生忘れることができない思い出になるもの。そのため、適当に流さずにある程度ムードは大切にしてほしいそう。
「わがままを言って。初めては旅行先、しかもそこそこいいホテルでヤリましたよ。一生涯の思い出です」
(4)連結の際だけは…
童貞の男性が最も不安なのが挿入時、どこが正解なのかわからないという点。
「いくらネットでセックスの知識を得ても、挿入の瞬間だけはどうしてもシミュレーションもできないし、さりげなくリードしてくれたらありがたい」
(5)終わらせてほしい
最後に、セックスの終わり方がわからないのが童貞。イケば終わりなのはなんとなくわかるも、初めてだとイケないこともしばしば。
「初めてだったので、イケなくて。でもそうなると、終わるタイミングがわからない(笑)。“トイレ行きたくなっちゃった”とかでもいいので、空気を読んで終わらせてくれたらいいんだけど……」
4:まとめ
童貞の男性とお付き合いすることは、経験済みの男性と付き合うよりも、大変なこともあるかもしれません。
しかし、みんな誰しもそのようなが時期あったわけですから、童貞であっても馬鹿にしないであげてくださいね。
0 notes
Text
錯視上ブルーエンド13
13話:8月16日(午前10時53分)自分がやられていやなことx人にしてしまうこと
「夏休みに入ってから、先輩との付き合いに反対するお前の叔母さんに別荘に軟禁されていたと。そんで隙をみて逃げ出して、ボロッボロになりながら笹巳まで徒歩で帰ってきたはいいけど、先輩の家の周りをお前の父親の車がグルグル監視してたから迂闊に近寄れず、かといって家に戻るわけにもいかず、途方に暮れていたところにうちの団地が目についたから、人が住んでねぇ部屋に勝手に忍び込んだってか。最初は1階、次は2階と短期間で移動して足つかねぇようにして、そんで昨日は最上階と」
西郷君はキッチンから2人分のグラスと麦茶のボトル、それからアクエリアスを抱えてリビングに戻ってきた。西郷君は軽く手を伸ばすだけで天井にタッチできるくらい背が高いので、椅子に座っている私は彼の顔を見るのにかなり顎を持ち上げなければならなかった。首が痛い。
西郷君は大きな口を開き、舌の上で「ハッ!」という笑い声を転がした。
「バッカじゃねぇの」
魚みたいにまん丸い目の中にある、黒い瞳が冷ややかに私を見下ろしている。黒い色は深すぎると青みを帯びる。墨汁やタールはその黒い表面に、本当なら含まれていないはずの青を浮かばせる。西郷君の黒い瞳も、どこにもない青い色を滲ませている。
あれは彼の中でずっと燃え続けている怒りの炎の色だと感じる。敵意、怒り、嫌悪感──私がシルキーを川に落とした日からずっと、彼はこういう目でしか私を見ない。あんなことを私がしてしまう前は──ほんの少しの短い間だけど──ただの友達みたいに話せていた時期があったことを、西郷君はもう覚えてはないんだろう。それがとても悲しい。悲しめるような立場じゃないけれど。
彼を前にすると背骨の中に鉄串を通されたみたいな気分になる。ただでさえ、思っている通りに動いてくれない顔の筋肉が、完全に無表情に固定されてしまう。
「普段、スゲェ細けぇどーでもいーことでクラスメイトや部活の連中に説教しまくるくせに、自分はなんなんだよ。不法侵入とか。普通に犯罪じゃん。最低だな」
西郷君はテーブルにグラスを並べ、モンスターズインクの柄がプリントされているグラスにアクエリアスを注ぎ始める。
「後で管理人室行って、空き部屋で寝泊まりしてたこと詫びろ。お前のせいで団地に住んでるみんなが不安だったんだ。不審者かホームレスが住み着いたって、見回りまでしてたんだぞ。ああ、これは言わねぇでも知ってるか。おっさんたちに見つかンねぇようにするために、ベランダにぶら下がったんだもんな」
ハッとまた西郷君は笑う。サメが笑うとしたら、きっとこんな顔だろうと思った。テーブルの下、腿の上で重ね合わせた手が震えないようにする。指先が冷たくなったように感じるのは、このリビングの冷房のせいじゃない。
私は彼の前だと萎縮してしまう。だって西郷君は、私の最悪な部分を見てしまった人だから。彼は私の罪を知ってる。そしてそれを決して他の人には言わない。神父のように沈黙を守る。彼の中に私の罪を留める。だから、私は公に責められることがなく、そして許されることがない。
「一歩間違ったら死んでただろ。あんなことするくらいなら、普通に『ごめん』って謝って家に帰りゃいいだろ。2、3発ビンタ食らうかもしんねぇけど、そりゃ迷惑料だ。親に心配かけんな。他人にも迷惑かけんな。バカなことする前に話し合えよ。つーか、表向きははいはい別れますっつといて、隠れて付き合い続けりゃいいだろ。そんぐらい考えつかねぇのかよ」
西郷君はアクエリアスを私に差し出し、それから残ったグラスに麦茶を注いで、私の正面に座った。
彼は私に非難の目を向ける。胃がキリキリする。こうして面と向かって話をするのは、小学校の時以来だ。部活でもクラスでも西郷君は私に話しかけてこなかったし、私も彼に話しかけられなかった。彼の目、態度、纏う空気。全てが私に棘を向けていた。少しでも近づいてきたら突き刺してやるからなって。
私は彼にちゃんと謝罪をしないといけないと思う。
団地に忍び込んだこともそうだし、布団を貸してもらったこともそうだし、熱中症を起こしかけていた私を朝まで付きっ切りで看病してくれていたこともそうだし、何より、シルキーのことを彼に謝らないといけないと思う。
『西郷君。本当にごめんなさい。他に選択肢がなかったの。謝って済むことじゃないってわかってるし、許してもらえると思ってない。何度も謝ろうとしたの。でも、謝ろうとするとどうしても言葉が別のものにすり替わってしまうの。信じてくれないだろうけど、私、自分が思ってることを、ちゃんと言えないの。そういう風にされちゃってるの』
頭の中で繰り返し、口を開く。大丈夫。きっとできる。だって私は、あの叔母さんからも逃げることができたんだから。ここまで自力で歩いてくることもできた。野宿もできた。警察からも逃げられた。
私はなんだってできる。自分で考えて、自分で行動することができる。私は変わることができる。もう、西郷君が知ってる最悪の私じゃない。それを伝えなきゃ。
「西郷君、私」
──どうして梨花さんが謝るの? あなたは何も悪いことしてないでしょ? あなたはやるべきことをしただけよ──
叔母さんの声が頭の中に響く。唇から音が消える。ダメ。ダメ。消えないで。
──取り乱しちゃダメ。みっともないでしょう。ちゃんとした子に育ってちょうだい。あなたは完璧な梨花ちゃんにならなきゃいけないでしょう。あなたにはそうしなきゃいけない責任があるの。あなたのために、私が何を失ったと思ってるの。責任を果たしなさい。あなたが生きてることの、責任を──
「私、少ししたら出て行きます。本当にご迷惑をおかけしました。管理人室には帰る時に立ち寄りますので、大体の場所を教えてくれると助かります」
こんなことを言いたいんじゃないのに、こんなことしか口に出せない。声を上げて泣き出したいのに、表情がガチガチに固まっているのが自分でもわかる。私はきっと、外からみたらものすごく変な奴だ。無表情で、平坦な声で喋るロボ。鉄仮面。変人。麗子像。そう呼ばれてるのを知ってる。好きでこうなったわけじゃないのに。
西郷君は目を細めて私を睨んだ。
「出て行った後、どーすンの? 家、戻ンの?」
「そうするつもりです。西郷君の言う通り、私はバカなことをしました。父と叔母に謝罪して許してもらうつもりです」
嘘だ。家には絶対に戻らない。……だからといって、どこに行けばいいのかわからない。先輩に会いたいけど、父さんに見つかる可能性があるから近づけない。警察もそろそろ見回りを始めているかもしれない。私から先輩のところに行くんじゃなくて、先輩が私のところに来てくれたら……。
「……西郷君。先輩に私がここにいるって連絡して貰えませんか?」
西郷君は不意に水をかけられたような顔で私を見た。
「なんで、俺が?」
「私はスマホを取り上げられてしまったままですし、家に戻ったら次に先輩に会えるのいつになるかわかりません。だから、西郷君から私がここにいるって連絡してくれれば……」
「無理。今、俺ら微妙だから」
西郷君はそういってなんとも言えない複雑な表情を浮かべた。自分を責めているような、先輩を責めているような顔だ。
「まさか、喧嘩したんですか? 西郷君と先輩が?」
「お前に関係ねぇだろ」
驚いて聞き返した声は、鋭い声に切り落とされる。
「つか、お前、それ飲んだら帰る前に風呂入れよ。もう風呂入れるくらいには回復してんだろ。沸かしてあるから。ホームレスに間違われんのも無理ねぇよ、お前の格好と臭い。その包帯は洗面台の側のゴミ箱に捨てろ。そんなに汚れてたら包帯の意味がねぇ。替えの包帯と日焼け用の塗り薬、あとで置いといてやるから、風呂からあがったら自分でやれよ」
西郷君はそう言うと麦茶を一気に飲み干し、「風呂場、あっち。洗濯機と乾燥機は好きに使っていーから、風呂入ってる間に服洗っとけ」と廊下の先を指差して立ち上がった。
「あとその敬語、ウゼェからやめろよ。普通に喋れんの知ってんだからな。小坊(しょうぼう)の時も、2人っきりになると普通に喋ってただろーが。覚えてンだからな」
石垣が風呂に入ってる間に俺はスマホを操作し、LINEを立ち上げた。
「……クソッ」
覚悟していたけど、やっぱりブロックされてる。クソッ。そりゃそうだよ。
俺はきっとダメだろうと思いながらも、先輩のアドレスにメールを送る。これも多分、ダメだろうな。迷惑メールフォルダに振り分けられるのが眼に浮かぶ。……となると、電話か。
俺はハァーッと大きなため息を吐いてから、先輩の番号を呼び出す。コール音を聞きながら、シャツの胸元を握る。どーせ出ないだろうと思いながらも、万が一、繋がった時のことを考える。
一体、どんな声でどんな風に話せばいーんだかわかんねぇ。まさか『よぉ、先輩。俺、西郷。昨日、先輩に告って、キスして、ぶん殴られて、見捨てられて、海に置いてかれた、あの西郷。それは一旦置いといて、お探しの彼女が今、俺ん家にいんだけど、これから来れる?』とでも言うわけにいかねぇし。
何度かのコール音の後、電話が繋がった。
「先ぱ」
「お客様のご希望により、電話をおつなぎすることはできません」
……。マジかよ。電話まで着信拒否か。クソッ。
「これで損してんの、俺じゃなくてテメェと石垣だからな。クソ原」
俺は呻きながら髪をかき混ぜる。石垣と別れたくねぇって泣いてた先輩の顔が頭ン中にはっきりと浮かぶ。あー。クソ。ひっでぇ告り方して、悲惨に振られたのに、そんでもまだ、先輩に泣いて欲しくねぇって気持ちが優ってる。
精神的な疲労と肉体的な疲労がダブルパンチだ。マジで死にそう。昨日今日とジェットコースター過ぎんだろうが、俺の人生。
昨夜。
俺が「日野原先輩と別れンの?」と聞くやいなや、石垣はばね仕掛けの人形みたいに勢いよく立ち上がって「絶対に別れない!」と鉄仮面のまま叫んだ。そして砂が崩れるようにゆっくりと座り込み、そのまま気絶しやがった。
俺は鼻血をだらっだら流し続けている石垣を部屋に運び、布団の上に寝かせた。
室内灯の下で見る石垣の姿はそりゃ酷ぇもんだった。顔から胸までは鼻血で真っ赤に染まっていたし、手足を包む包帯はあちこちから膿が染み出していたし、両手の皮はズルムケ、足の裏や指は血豆だらけ、包帯に覆われてない部分の皮膚は日焼けしすぎでヒビが入って、ヒビの下からピンク色の肉が見えてた。完全にゾンビだった。俺がウォーキング・デッドのキャラだったらその場で頭を叩き割ってたと思う。
おまけにチビた体には洒落にならない程の熱がこもっていた。熱中症を起こしかけてるってすぐに気がつけたのは、運動部部員が必ず受けることになってる応急処置の特別授業のおかげだ。あと練習中にぶっ倒れた三国の世話をした経験も活かせたんだと思う。
俺は気絶した石垣を叩き起こし、薄い塩水を飲ませられるだけ飲ませた。それから氷を詰めたビニール袋をタオルで巻いて、それを首の後ろと両脇の下と太ももの付け根に置いて、太い血管を冷やした。濡らしたタオルで腕や額や足を覆って、体から熱が外にでるようにするのも忘れなかった。
そのまま大人しく寝ててくれりゃ楽だったのに、石垣は体から多少熱が出て行くと「大丈夫です。お世話になりました。帰ります」と言って立ち上がろうとした。
最初は相手が──石垣とはいえ──怪我人だから、できるだけ静かに「寝てろ」と命じていたが、あまりにもしつこく立ち上がろうとするので、最終的に俺はキレた。
「大丈夫じゃねぇ奴が、大丈夫って判断してんじゃねぇよ! この場で冷静なのはどっちだ!? 俺か、テメェか、どっちだよ!? 俺だろうがっ! 次立ち上がろうとしやがったら、動けねぇように体縛り上げるからな、クソがァ!」と俺が怒鳴って、ようやく石垣は無理に起き上がろうとするのを諦めた。
その後。俺が濡れたタオルを取り替えたり、深夜営業しているコンビニまで氷を買いに行ったり──クソ遠い。学校の反対側まで行かなきゃいけない──している間に、石垣はウトウトと眠り始め、俺も疲労が込み上げてきて床に尻餅を付いた。
本当はその場に大の字になって眠りたかったけど、結局、俺は朝までずっと起きて石垣の様子を伺っていた。流石に嫌じゃん。目を覚ましたら冷たくなってましたとか。
「……クソ。どういう状況だよ。あの石垣が俺ん家にいるとか。冗談だろ。信じらんねぇ」
俺は欠伸を嚙み殺しながら独り言ちる。
あいつ、ここから出たら家に帰るとか言ってたけど、絶対ぇ嘘だろ。こんな団地に忍び込むくらい嫌がってる家に、俺に見つかった程度でホイホイ帰るわけねぇもん。大方、団地から出たらまた別の潜伏先探すんだろうな。ホームレス女子高生だ。遅かれ早かれ事件か事故に巻き込まれて酷い目にあうルートじゃん。……まぁ、俺には関係ねぇけど。
俺は自分の両腕をお姫様抱っこをする時の形にする。あいつメチャクチャ軽かったな。2週間かそこら、家出続けてるっつてたっけ。その間、飯どうしてたんだ? コンビニ飯かなんかか? ハ��! バッカじゃねぇの。
「これ、もしかして私にですか?」
風呂から出てリビングに戻ってきた石垣は、テーブルの上の雑炊を指差して俺に尋ねた。冷蔵庫のあまりもんぶち込んで作ったやつだ。ぐずぐずに煮込んだから、胃が弱ってても食えんだろ。
「お前以外に誰がいンだよ。とっとと座って食え。昨日の夜から何も食ってねぇだろ。全部食えねぇなら食えねぇでいーけど、ちょっとは腹になんか入れろ。家帰るまでに倒れられたら寝覚め悪ぃからな」
石垣は鉄仮面のまま俺の正面の椅子に座り、「ありがとうございます」と言って頭を下げた。シャワーと、シャンプーと、リンスと、ドライヤーの力で、鳥の巣みたいだった石垣のおかっぱ頭がいつも通りの無駄な輝きを取り戻している。あいつが頭を動かすと髪がサラサラーッと流れて揺れた。ふーん。これがサスーンクオリティ。
痛々しいばかりだった包帯も綺麗に巻き直されていて、だいぶゾンビ感は払拭されていた。今の石垣はゾンビではなく、ただの座敷わらしだ。ちょっとは人間に近づいた。
「お前のスポーツバッグ拾って来たから。後で中身確認しとけよ」
俺はソファーの上に置いた赤いスポーツバッグを指差す。石垣が昨日、ベランダの柵にぶら下がる前に少しでも体を軽くしようと地面に落としたものだ。団地内の誰かの落し物だと思われていたらしく、植え込みの側のベンチの上に『誰が落としたか知りませんけど、落し物はここですよー』と言わんばかりに置いてあった。
石垣はスポーツバッグと、雑炊を何度か交互に見てから俺に顔を向け、「どうしてですか?」と聞いた。
「何が」
「西郷君、私のこと嫌いでしょう?」
「わかってんなら一々聞くなよ」
「私のこと嫌いなのに、どうして優しくしてくれるんですか?」
……あ?
「誰がいつお前に優しくしたよ?」
しねーよ!
「だって、寝ないで看病してくれたり、お風呂貸してくれたり、ご飯まで」
ハッ!
「お前はただそいつが嫌いだって理由で、鼻血流しながらぶっ倒れたボロ雑巾みてぇな人間をそのまま転がしとくのかよ。バッカじゃねぇの。怪我人の面倒みンのと、そいつが好きか嫌いかは別だろーが。そんなの、優しさの問題じゃねぇよ、ボケナス。ズレてるとこ、昔っから変わんねぇよな。あと敬語やめろっつたろ。イライラする」
「……ごめん」
ケッ!
「その鉄仮面みてぇな面も、えっらそーなチクリ魔ぶりも相変わらずだな。高校生なんだから、ちょっとはマシになると思ってたけどな」
「少しはマシになってたんだよ」
ほんの少し、石垣の鉄仮面が揺らいで感情らしきものが見えた気がした。反発とか、苛立ちとかだ。生意気じゃん。お前が俺に何をイラつくってんだ。
「どこがだよ? クラスでも部活でもズレまくりの浮きまくりじゃねぇか。ホームルームでクラスメイトのミスをネチネチ晒しあげンのやめろよ。クソウザいから。自分でわかんねぇの? あーゆーことすっからいつまでたっても、どこにいても嫌われンだよ。お前、女子とすら喋れてねぇじゃねぇかよ」
石垣はスプーンで雑炊の表面を突きながら「わかってるよ」と言った。
「わかってるけど、どうにもできないんだよ。それでも、中学校の時はかなりマシに抑えられてたんだけど、高校に入ってからぶり返しちゃったんだ」
石垣は何か言いたげに俺を見た。
「んだよ? 人の顔ジロジロみンなよ」
ごめん、と石垣は俯く。
「でも、私、最近ちょっとずつ変わってきてるんだよ。話しを聞いてくれる人が側にいてくれてるから」
「日野原先輩とか?」
「……うん。先輩の前にいると、普通でいられるんだ。先輩、私のズレてるところを絶対にバカにしないで、褒めてくれるから。梨花ちゃんはそこがいいんじゃないかって笑ってくれるんだ。ちゃんと私の話しを聞いてくれる人、先輩だけなんだ。私、先輩と一緒にいられたら、もっとマシになっていけると思う」
冷たい感情が湧いてきた。先輩がそうやってお前を受け入れてんのは、お前の本性を知らねぇからだろ。
「お前はマシな人間になんかなれねぇよ」
石垣は無表情だった顔をわずかに赤くした。
「なれるよ。西郷君は私を知らないでしょう。私、本当にちょっとずつ変わってき──」
「ガキの頃、テメェは俺にも言ったよな。『私の話しを聞いてくれるの、西郷くんだけだから』って。そんで打ち解けたみたいな振りして俺を油断させておいて、最後に何したよ? なぁ? それで、今度は先輩か? さぞ打ち解けてんだろうよ。先輩もお前に気を許してんだろうよ。そんで、次はどーすンの? 先輩の可愛がってる猫か犬でも殺すの? 俺とシルキーにしたみたいにさ?」
鉄仮面のまま、サァーッと石垣の顔が白くなる。
「西郷くん、私、本当に、あの、あの時のことは、本当に」
「別にイーんじゃねぇの。気にせず、忘れて生きていけばぁ? テメェにとってはどーでもいーことなんだろ。害獣1匹、処分しただけだもんな。けど、俺は絶対忘れねぇから。お前がどんなに自分で『マシになった』って思っても、実際、『マシになった』ように見えたとしても、俺は覚えてるからな。テメェがどういう人間なのか」
俺は石垣を睨みつける。
「テメェが俺の目の前でシルキーを川に捨てた。俺が川に飛び込んで、シルキーの入った袋を拾ったんだ。俺が1人で穴を掘って、俺が1人でシルキーを埋めて、1人で墓を立てたんだ。俺は全部みたんだぞ。お前がシルキーに何をしたのか、あの袋の中を、全部みたんだ」
石川の顔からは全ての表情が消えていた。少しだけでも罪悪感を持ってるのか? 涙の1つも流しそうにねぇじゃねぇかよ。
「シルキー、お前に懐いてたよな。簡単だったんだろうよ。人間を信用しきってて、傷つけられるなんて考えてすらいない子猫をあんな風にいたぶるのはさ。俺はな、あんなことをする人間は永遠に改心なんかしねぇと思ってるよ。テメェがこの先、どんなに表向きマシになったとしても、どんなに周りの人間が、先輩が、お前自身が、そのマシな姿を信じ込もうと、俺はテメェの本当の姿を見抜いてるからな。テメェはマシな人間になんかなんねぇ。ずっとずっと、あの時のままだ」
前話:次話
1 note
·
View note
Text
ライブが嫌い
頭から文章が溢れてきて止まらない時があって、そういう時にブログを書く。大体そういう事はクソつまんないライブの中にいる時、ぐるぐると回っているものだ。いい意味で言ったら感受性が刺激されてる時、なんだろうけど、飲み会で1人になった時も同じように考えてしまうので、集団の中で一人になって動けない時に頭だけぐるぐる回るのだろう。
「クソつまんないライブ」と書いたが、自分は総じてライブが嫌いだ。アーティストの挙動が見たいのに見えるのは人々の手ばかりで、アーティストの声もスピーカーで増幅したものしか聞こえてこない。しかも周りのオタクに気を遣わなきゃいけなくて、周りが声を出してるから、手を上げてるから、上げなくちゃ空気読めてない、みたいに思われるんだろうなとか考える時点で向いてないと思う。ライブがクソつまんないのはアーティストがクソつまんないんじゃなくて、ただライブという空間が自分に合わないんだと思う。
(それでもライブに凝りもせず応募してしまうのは、演者の頑張ってこの日のために作り上げてきた刹那的な一瞬を見逃したくないと考えちゃうからなのかもしれない。大体自分が好きになるアーティストだったりはライブの絶対数が少ない。)
ライブビューイングがあるようなライブならそっちに行くことが多いんだけど、そこでも現地のライブと同じようなファンの立ち振る舞いをしなきゃいけないみたいな空気がある時は憂鬱になる。一ファンとして応援は届くか分からないのに、応援を強制されるのはやっぱり変じゃん?って思う。ただ演者から一人一人の顔が見えるというのはある程度本当で、そこで一人だけつまらなそうな顔をして観てる人を見たらきっとがっかりするだろうし、そこはそうだったらいいな。所詮自分が望んでるのは一対一でのコミュニケーションでしかないし、そこで出来るだけいい方向に持っていきたいと願うけど、コミュニケーションが取れてないと感じるなら相手に悪い印象を与える事も辞さない、と思う(やらないけど)
ライブを色々貶してきたけど、直近で行ったライブ2つは超感動した。7/4のチャットモンチーのラストライブ、7/20のTokyo 7th sistersの4thライブ。7/20のライブは演出も超完璧で、二階のクソみたいな席にいた自分にも音も演出もちゃんと感じられて感動した。丸一日他の音が聞けな���った。詳しい感想はTwitterのオタクアカウントで散々喋ったので割愛する。
ただそれだけに「これを同時に家で見られないかなあ」と思ってしまう。正直大きいライブに行くとモニターの映像しか見られないし、だったら人の目とか気にしないで見られる家のパソコンとかで見たい。ただライブビューイングのデメリットとして、カメラが映す以外の所が見られないという点がある。実際ライブに行くと特定の演者を集中的に見るとか、バックダンサーを見るとかそういう楽しみ方があるので、せめてアイドルとかの現場とかだけでいいから「〇〇さん定点カメラ」みたいなのをリアルタイムで切り替えられるようになったらいいな、と思う。それと最近はVRが盛んなので、VRでのライブをリアルのライブと同時でやってほしいなと感じる。多分スポーツとかだと出来てるはず。こないだサッカーW杯があったけど、NHKのアプリで試合を何種類かのカメラで見れてそれを自由に選べるというのがあった。ああいうのがアイドルとかアーティストとかの現場でもあればいいなあ、と思う。
「ライブの場」は嫌いだけど、「ライブ」自体は好きなので、ツイキャスで、リスナーが誰一人いないような放送に潜り込むのが趣味なのはそういう事なんじゃないか。大学の後輩のツイートをそのまま借りるとツイキャスほど面白いアプリはないと思う。こないだ落ち込んでいた時放送を漁っていたら薬でラリってバイクで車で外に出たけど事故ってそのままの放送があった。生の女の子が様々な方法で承認欲求を満たしているのをリアルタイムで見られるのはものすごく面白い。そういうのにお家でぬくぬくと参加できて運がよかったらレスポンスが返ってくる。こんな面白いアプリ他にあるか?(ニコニコは有名生主ばかりになってしまったし他の生放送アプリは個々人にアイドル感が拭えないので論外)
でも「生のライブじゃないと本当の感動は味わえない」みたいな意見もあるしむしろそれがメインだしまあ一理あるとは思うけど、じゃあ本当ってなんだろうって思う。本当って各個人によって違わない?肉体的なものがただ一つ本当だとするなら、別にいらないしそんなの知らない。
昔繰り返すように見たおもしろFRASH動画の、AAで描かれたBUMPのKと、さいたまスーパーアリーナで聞くKと、どっちが自分にとって本当の感動かと言われれば圧倒的に前者だと思う。曲に感動するかしないかは自分自身のストーリーが絡んできがちで、そこを刺激するかしないかの差でしかない。
----------
最近塾講師をやっていて、子供と接する時声色を変えたり、表情を作っている先生を見ているとめちゃくちゃ気持ち悪いなと思ってしまう。自分は「赤ちゃん言葉」なるものが嫌いなんですが、あれ自分に向けられたらどうですか、ナメられてると思いませんか?
自分と違う枠組の中で生きている人に対して、自分の中で敬意を払うのは当然で、それは外国人であったり、子供だったり、動物だったりするんですけど、14歳の子の方がサッカーに詳しいし(自分も並の人間よりはサッカーに詳しいと思ってるけど)、その他で圧倒的に自分を上回ってる可能性があるから、絶対にナメた口調で喋る事、目を合わさないで喋る事はしないように気を付けています。前述した通り動物にも同じ感じで接してるので、動物に挨拶する時は必ず目線を合わせる為にしゃがんだりしています。
こうやって物事に誠実に生きる事、文字面にするといいかもしれないですが、そうやって生きてると臆病で身動きが全く取れなくなってしまうので、ある程度は自分の性格で仕方ないけど、やめたいなって思います。多分自分はある面では超真面目にある面では超不真面目に生きてると思うんですが、その印象の差って人の価値観の違いでしかないから、押し付けるのはやめてくれな、って一応念を押しておきます。
----------
文章中で主語が「僕」から「俺」に変わったり、「自分」になったり「私」になったり、敬体になったり常体になったりするんですけど、その言葉によって持つ性格が違うと思うんですよね。だからばらばらになる。ある文を書くときに主語は「俺」でなくちゃいけないし、そこを変えると文章の態度が全然違ってしまって全部取り換えなきゃいけない事がままあって、主語が少なからず入らざるを得ない文章でそこをないがしろにしてしまうと違和感があってやめてしまう。例えばこのブロックはどちらかというと誰かに「自分がこう思う」というより��あなたの意見を聞きたい」みたいな態度なんだけど、「あなたの意見が聞きたい」みたいな文章だけ敬体になってしまう。自分はこれだけ長く文章を書いているけど、一般的に論理的な文章を書こうとすると全く書けない。この形式でしか文章を書けない訳で、頭悪いなあって感じてしまいます。FACEBOOKの同級生たち、大体大学卒業してて、そっちの方が頭いいなあ羨ましいなあ、って思うんですよね。
「○○と思う」って構文が多すぎるけど本当にただ思ってるだけなのでそうとしかいいようがない、憤慨している、とか感慨にふけっているとか別にそういうような言葉を付け足してもいいんだけど、それだと大袈裟すぎるし、熟語のイメージに引っ張られすぎてしまうからあんまりよくない。
----------
前回「死にたい、誰か構って」という文章を書いて色々な人に相談に乗ってもらったんだけど、やっぱり「話聞くよ」というスタンスで来た人は全然話を聞いてないなと失礼ながら思ってしまった。こんな文章ひとつ読めなくて、「死にたい」という言葉だけ抜き出して同情されてもなあ、と。ただこれを読んでどうあなたが考えたか、を聞きたいんだよなあ。
でも普通にこの件に関しては他人に期待してしまった自分が全面的に悪い。結局色々構われるのが性に合わないと分かったので、それだけでも良しとします。
誰とも分かり合えないというのが���念ながら段々分かってきて、占いなら自分の事分かってくれるかなあって思って占いの本を何冊か買ってみたりしました。乙女かよ。
女の子になりたいけど、なりたいのは男の想像する女の子であって、別に「わたしらおっさんじゃね?」って言ってるような女の子じゃない。おっさんは何の権利も保証されてない、ただの奴隷みたいなものだと思ってるので自分の向かう先がそこだと思うと絶望でしかない。女性は20代から30代になるにつれて女性としての価値がなくなっていく、と嘆くけど、ただ若さによって失う価値がデカいだけで、おっさんになっていく事は人間としての価値が資産でしか語られなくなってしまうからもっと悲惨だと思う。それはそれとして若さで思い悩む女性はかわいいと思う。男である限り女の「かわいい」の価値には勝てない。そのかわいさは潜在的に女の持ってる魅力で、羨ましいと思う。くやしい。
「女の子」に対する偏見で僻んでばかりなんだよなあ。早く社会的な外見がアバターで選べる世界に行きたい。でも結局どこまで行った所で男は女の持つ肉体的、精神的両面での「かわいい」の魅力には勝てないと思う。そこを脱ぎ捨てたい、って人もいるだろうけど、男の自分はそう思う。かわいくなりたい。
-----------
インターネットでLGBTの話題ばかり流れてきて自分も流されて考えてしまってこうして意見を言ってしまっている。自分でそういう情報を摂取してしまってるのが自己矛盾しているのだけど、クソつまんないから早く全て嘘と冗談で固めたようなインターネッツに戻ってくれ。
0 notes
Text
「いきなり、何なの?」
酷く機嫌の悪そうな顔で、及川は目の前の牛島を見遣った。
「俺、男と喫茶店デートする趣味なんかないんだけど? しかも相手、お前だなんて……。牛島、一体、俺に何の呪いかけてんの?」
すっかり眼鏡をかけた姿が定番となった及川の不機嫌な瞳は、なかなか話を切り出さない牛島に業を煮やして、呼び出した用件を早く云えと迫っている。
対する牛島はと云うと、そんな言葉など全く気にしていないかのように、運ばれてきた珈琲をゆっくりと味わい、時折ちらりと窓の外の青空に目を遣るものだから、及川の不機嫌モードは頂点に達しようとしていた。
「お前さっ――」
「……引退することにした……」
及川の苛つく言葉と同時に牛島の口から出た科白に、及川は鳩が豆鉄砲をくらったかのように、目を瞠って口をあんぐりと開けたままフリーズした。
「は? 何……だって? ワンモアプリーズ?」
「現役を引退する。協会には明日伝える予定だ。チームも今月末で退団する事になる……」
まっすぐ及川を見据えてそう云った牛島の言葉は、まさに晴天の霹靂。
「引退って……、何云ってんの?」
思わず及川の声がうわずる。有り得ない。まさかの展開だ。
「……お前には一番最初に伝えようと思っていた……」
そう口にした牛島の表情は、いつもと変わらずのようだが、何処となく覇気が薄れているように感じられたものだから、及川は牛島の言葉が冗談ではない事を悟った。
暫し言葉をあぐねた及川だったが、やがて、ふうっと大きく息を吐くと牛島に問うた。
「理由は何?」
「?」
「引退する理由だよ」
及川がそう問うた瞬間、牛島は少しだけ驚いた顔をしたが、手元のカップをテーブルに戻しながら静かに応えた。
「……もう、コートに立てないからだ。どうやら膝も肩もこれ以上は無理らしい……。騙し騙しプレーは出来ても、時間の問題だそうだ……」
途端、及川の眉間の皺がより一層深く刻まれる。
「お前……、怪我、治ったんじゃないの?」
「怪我は治っている。だが、もう以前のようには打てないと感じたんだ……」
その牛島の科白に、及川は直感的に違和感を感じた。
確かに、どんな一流プレーヤーでも、年齢を重ねていけば多少なりとも身体にガタがくるのは避けられない。もう牛島も及川も三十路をとうに過ぎ、四十に手が届いてしまう。全日本不動のエース、セッターと謂えど体力的にはピークをとっくに過ぎた年代なのだから、若い頃のように無理は出来ない。徐々に衰えていく体力と筋力を如何にカバーしていくかに重点が置かれてきている。勿論、牛島も及川もそれを十分に理解してトレーニングをしてきたからこそ、まだ今もその地位を確固たるものにしていた。
なのに――。
牛島が? 憎たらしい程に天才的なバレーの資質に恵まれた牛島が、そんな普遍的な理で選手生命に終止符を打つ?
そんなわけがない。
「却下だよ、そんなもの」
及川は、牛島の決断を斬り捨てた。
「……?」
牛島は、云われた言葉の意味が解らず、怪訝な顔を及川に向けた。
「甘ったれた事云うなよ、牛島。『以前のようには打てない』だって? そんなの当り前だろ? もう何年も前から解ってる事じゃんか?」
「……だが……」
「お前、逃げてるだけだよ。ブロックにドシャットされる場面が増えた事も、思うようにコースに打てなくなった事も全��、もう全盛期のような体力も筋力もないからだ、若くないからだって歳のせいにして逃げてるだけじゃん……」
そう突きつけた及川は眼光鋭く牛島を射抜いた。
「……及川……」
「まぁ、確かに。今引退すれば、苦しい練習からもプレッシャーからも開放されて楽になれるんだし、もしさっきのお前の科白がチビちゃんや、飛雄から出て来てたら、あっさり『お疲れさん』って云ってやるけどさ……。お前だけは別だよ。そんな科白、この俺が許すとでも思ってんの?」
キツい及川の言葉にもかかわらず、牛島は特に怒ることもなく、素直に受け取ると、彼らしく理路整然とした応えが返って来た。
「だが……俺もお前も、いつかは引退する時がやってくる。俺達はプロの選手なんだ。遊びでやっているわけじゃない。プロである以上、自分が与えられた役割はこなさなくてはならない。その期待値を、否、それ以上の何かを齎さなければチームにいる意味がないだろう? 俺はそれが出来なくなった時が引退の時だと思っている。……そして『今』がその時だと思った。だから……」
「ああ、そーだね。お前の云うことは正しいよ、多分……」
及川は牛島の言葉を肯定しながらも続きを遮った。そんな解りきった事を今更、牛島から聞きたくはない。
「俺だって解ってるよ、そんな事は。俺はそんな事を云ってるんじゃないよ」
及川はひたりと牛島を見据えた。
「その結論を出す前に、お前は、やるべき事をしたのかって云ってるんだよ」
その言葉に牛島は怪訝な顔を向けた。
「やるべき事……?」
「……お前、さっき、怪我は治ったって云ったよな?」
「ああ」
「それ、嘘だろ?」
及川の科白に牛島が一瞬、表情を変えた。
「……」
応えが返らない事に及川は、ああ、やっぱりな――と酷く冷めた表情を返した。体力のピークなんてとっくに過ぎてるのはお互いがもう何年も前から解っていて、今更若い頃のようなプレースタイルなんて懐かしんでも意味がないのに、そんな云い訳を口にするなんて。
「そんな事だろうと思ったよ……」
盛大な溜息と共に及川は、革張りの椅子の背凭れに大きく身を沈めた。
歓迎されない沈黙が続いたが、やがて降参したと云わんばかりに牛島がゆるりと頭を振った。
「……何故、判った?」
完璧に誤魔化しきれるとでも思っていたのだろうか? 少しだけバツの悪そうな顔でそう呟いた牛島は、その視線をさりげなく違えた。
「お前、俺を甞めてんの? 他の奴らと一緒にするなよ。もう何十年もお前のプレー見てきた俺に、力の限界を感じて引退とか、何処の口がほざくわけ? だいたいお前、そんな殊勝な奴じゃないし? どうせ吐くならもっとマシな嘘吐けよ! って云うかさ、それ以前にマジで俺にそんな嘘が通じると思ってたわけ?」
及川の言葉は容赦なく牛島を責め立てるが、何故か牛島は薄く口元に笑みすら浮かべる。
「……いや……、思ってはいなかったが……何も云わないと思っていた……」
「……何、それ?」
「あっさり、聞き流すと思っていた。俺が引退しても、お前は何とも思わないだろうし、ましてや引退の理由にも興味はないだろうと……」
そう云った牛島は視線を落とすと、らしくない苦い笑みを返した。
その瞬間、及川の中で全てが繋がって、ああ、だからなのか――と嘆息した。ずっと釈然としなかったのだ。牛島が何故、自分に連絡を寄越してきたのかという事に。
久しぶりの日本、空港で家族とリムジンバスを待っていた時に突然に鳴った携帯。発信元を見て思わず電源を切ろうとしたのを、隣にいた妻に止められて渋々出てみれば、予想以上に酷く固い声が聞こえてきた。その時の自分の顔に家族は何かを感じたのかも知れない。いつもなら煩く騒ぐ三人の子供は珍しくバスの中大人しかったし、妻はただ黙って本を読んでいた。そして今日、自宅を出る時、玄関先で妻が云った言葉。何もかもが釈然としなかったけれど。
今の目の前の牛島を見て、漸く及川は全てを理解しその答えに辿り着いた。
「……ったく。しぃの云う通りだったよ……」
及川の口から予想だにしない名前が出てきた事に、牛島は酷く驚いた顔をした。違えていた視線が知らずと及川へと合わさっていく。当の及川は、ゆるりと頭を振って何とも云えない表情を返している。怒っているような、それでいて何処か寂しげな――。
「今日、家を出る時、しぃに云われた。サインは見逃すなって……。俺、しぃのその言葉がなかったら、うっかりお前のサインを見逃すところだったよ。このまま、はい、そーですかって家に帰ったら俺は間違いなく、しぃに三行半をつきつけられるじゃん……」
危ない、危ない、離婚の危機だよ、と表情が強張っている。
「……意味が解らないのだが……?」
「ああ、そーだろーね。お前の頭じゃ解らないよ。自分の気持ちにも気付かないくらい、お前、今壊れてるんだから。って云うか、多分お前は永遠に解らないと思うよ?」
「……俺の気持ち? 何の事だ? 俺の意思はもう固まってい――」
「だったら、俺になんか連絡寄越さず、勝手に引退でも何でもすりゃいーじゃんっ!」
及川の一言が、僅かに、だが確実に牛島の胸に刺さった。
「お前の云う通り、俺はお前が引退しようが何しようが興味ないし、ましてや引退の理由なんか知りたいとは思わない。今の俺はそんなものに構ってる暇なんてないんだよ! 世界一のメダルを取りにいくって決めてるんだから! あと少し、もう少しで金メダルが取れる、 この十年でやっと日本はその位置にまで上ってこれたんだ。なら、自分の手でそのメダルを取りにいきたいに決まってるじゃんかっ? 十五年前、俺がイタリアでバレーをする事を選んだのもその為なんだから。俺はただひたすらその頂だけを目指してきたんだ。だから、プロの癖に自分の身体のメンテナンスも上手く出来ず、挙句の果てに怪我で引退する羽目になる莫迦な選手の事なんて、知ったこっちゃないよっ! 怪我を隠してまでプレーする事がお前の目指す頂だったってオチにも興味はないし、笑ってもやれないよ」
及川の心底憤った色の瞳に牛島はひくりと肩を強張らせた。それはあの時と同じ瞳だった。『取るに足らないプライド、憶えておけよ』と云い放った高校生の時の及川の瞳と重なる。
「ま、それでも、お前がそれに納得してんなら、まだお義理程度には笑ってやるけど? ……お前、本当は納得してないんだろ? 納得して出した結論だと自分で思い込もうとしているだけだ。本当にお前が自分の出した答えに納得していたなら、俺を此処に呼び出したりしない。お前はそういう奴じゃない!」
放たれた及川の言葉に、牛島の顔がみるみる歪んでいく。
引退すると決めた時、チクリと針が刺さったような瞬間的な痛みを心に覚えた。最初は本当に瞬間的なものだったそれは、日に日にじわじわと大きく広がり、鈍く疼き始めるようになっていった。
けれど牛島は、ずっと気付かぬフリをして遣り過ごしてきた。 もう決めた事なのだと、時間が経てばそれは薄れてゆくもので、単なる一時の感傷なのだとずっと思い込もうとしていたのだ。
でも、気が付けば牛島は思うように自分の身体も心もコントロール出来なくなっていた。試合中でも腕一つ、足一歩動かす事すら儘ならない。
この心の疼きは単なる一時の感傷、そんな言葉で片付けられる程、容易いものではなかった。
そんな時、テレビが及川の姿を映した。イタリアリーグ最終戦の録画放送だったが、牛島はその画面の及川に目を奪われた。
自分の知らない及川が映っていた。全日本の時に見せるものとは全く違う及川のプレーに牛島は衝撃を受け、その身を震わせた。
そして気が付けば、牛島は無意識のうちに携帯を手に取っていた。
「……お前、そんなに我慢してさ……、ほんとマゾだろ? それ……」
呆れて、溜息も出ない。
今、及川の目の前の牛島の表情は大きく歪んでいる。それは悔しさだけではなく様々な感情が入り混じった表情で、及川はほんの僅か、口元を緩めた。
やっと牛島若利は、自分の感情を表情に出す事が出来るようになったのだ。
試合に負けても悔しい顔一つしない牛島に及川は、何度、胸の裡で悪態を吐いたことか。
『もっと悔しい顔をしろよ』――と。
だから、固く目を瞑った牛島の眦からすっと一筋流れ落ちるものに、及川はそっと気付かぬフリをした。鍛え上げられたその肩が僅かに震えていることにも気付いてやらない。
「……及川……」
搾り出すような牛島の声。
「何だよ?」
及川は素っ気無く応える。
「オリンピックまで……あと半年だ……」
「ああ、そうだね。それが何?」
さらりと応える及川に牛島は暫し言葉をあぐねてしまう。
今の牛島にその言葉の続きが云えないのは、及川にも解っていた。当然だろう。素直に言葉の続きが口に出来るくらいなら、自分は今この場に呼び出されていないだろうし、それ以前に牛島は連絡を寄越さなかったはずなのだ。
解っているから及川は強引にその背中を押した。
「……半年あれば、十分だろ?」
弾かれたように目を瞠る牛島に、及川は最後の蹴りを入れる。
「だから、却下だよ、引退なんて。何度も同じ事云わせないでくれる? 何を躊躇ってんのか知らないけど、まだ辞めたくないんだろ? お前……。だったらさっさとやるべき事やれよ」
お前がするべき、全ての『正しい努力』を――さ。
「ああそうだ。此処の支払い、お前持ちだよ」
そう云ってテーブルの上の伝票を牛島へ押し付けた及川は席を立つと、おもむろにポケットから携帯を取り出した。
「あ、しぃ? ごめん、遅くなった。うん、今から連れて行くから」
その言葉と同時に及川は牛島の右腕をがっしり掴む。
「!?」
「まさか、このまま帰れるなんて思ってないよね? この及川さんの貴重な家族団欒の一日を潰したんだから、責任取って貰うよ」
0 notes
Text
林田の世界(初稿版)
第15話 俺の恐れる全てのものが
肉体が布と金属で出来た頭でっかちな潜水服に変わり、自分の魂がその中に閉じ込められていると感じた。水圧に囚われて腕をあげることもできず、悲鳴はヘルメットのガラスを曇らせるだけで誰にも届かない。
俺はなすすべもなく暗い海底へと一直線に落ちていく——感じたことが真実なら、これが俺の真実だ。
恐怖のあまり動けなかったというだけにしても。
何もないはずの空間をサンダルで踏み、鳴るはずのない音を鳴らしながら、もういないはずのお母さんが俺に向かってくる。
驚いた様子は少しもない。硬直している俺を見ても眉一つ動かさなかった。
目線が俺を通り過ぎている——俺もこの空間も見えていないんだ。俺がお母さんの顔を認識できないのと同じように。
手を伸ばせば触れられる程の距離まで近づいてくる。
中途半端に濡れた手からチャーミーグリーンの匂いがした。
夕暮れ時のお母さんの匂いだ。
懐かしさが苦痛を感じる程強く心臓を締め付け、恐怖が消えてゆく。
「お母さん」と言おうとしたのに、口から漏れたのはため息のような湿った空気だった。腹筋が消えてしまったみたいに力が入らない。
お母さんは俺の前で向きを変え、右手側に進み始めた。
俺はただ立ち尽くしたまま、遠ざかってゆく背中を見つめる。
サンダルの音を聞きながら、あの凄まじい轟音と風が止んでいることに気がつく。
周囲を見回してみれば俺を取り囲んで回転していた銀色の欠片達は、それぞれの鋭い切っ先をこちらに向けたまま空中に静止していた。
強風に煽られて銀流に引きずり込まれる危険は去ったようだが、安心感はこれっぽっちも湧いてこない。弓を引き構えたオーランド・ブルームの群れに取り囲まれて、矢の先を向けられているような気分だ。確か、オーランド・ブルームだったはずだ。ロード・オブ・ザ・リングのあの金髪ロン毛の無双エルフ。
きっかけさえあれば、あの欠片達は一斉に俺に向かって飛んでくるに違いないという根拠のない——だから否定できない——確信に皮膚がひりついた。
再びお母さんに目を向けると——もう10mは離れていた。足速っ! ——彼女の進む先に林田が立っているのが見えた——足早っ! 気配消すの上手っ!——。
あいつのすぐ後ろにはお母さんが出てきたのと同じような欠片があったが、その中にどんな風景が広がっているのかは、あいつの姿に隠れてよく見えなかった。燃えるような色の空だけが辛うじて確認できる。あの中は夕暮れ時だろうか。
欠片から差し込む赤い光を背中で受けて、林田は黒い影になっている。
影が右手を上げて、お母さんを指差した。
「懐かしいとお前は感じている。と、いうことになっている。俺がお前ならそう思うだろうと思うから」
自信で満ちている人間特有の声だった。
「まだそんなややこしいことを——」
頭の中で野村萬斎がエレガントに舞う。
「お前は今まで一度も母親に会ったことがない。お前の思い出は全て、お前がお前であるために後付けで出来上がった物語だ。お前の母親だということになっているそいつは、思い出の中にだけ存在する最初から死んでる母親なんだ」
林田は言葉を切り、首を後ろに向けて夕焼け空の広がる欠片の中を見つめた。
夕日があいつの耳を赤く透かす。
「お前はお前という人間のふりをしてる。本当はどこにもいない」
欠片の中、ずっと遠くの方から鈴に似た音が微かに聞こえた。
お母さんが足を止める。お母さんにも音が聞こえたようだ。
林田がまたこちらを向く。夕陽に縁取られた頬の輪郭が燃えている。
「いない奴がどうなろうと、俺はどうとも思わない」
お母さんが体を強張らせ、一歩後ろに下がった。
音が更に近くなる。この音は風鈴の音じゃない。自転車のベルの音だ。
「お前の恐れるものが、間も無くこちら側へ」
チリンチリンとまたベルが鳴った時、俺はハンマーで頭を殴られたようなショックを受けた。
「何考えてんだ! クソ野郎!」
飛びかかって林田のスカした面を叩き潰してやりたいと思ったが、今はそれどころじゃない。お母さんが危ない。
「そこにいちゃだめだ!」
お母さんに駆け寄ろうと足を踏み出した瞬間、脳天を強烈な痛みが突き抜ける。体のコントロールを失い、俺は受け身も取れないまま無様に倒れた。その衝撃でまた痛みが走り、変な声が出て、変な汗が出た。
足の裏がズタズタなの忘れてた。クソッ。クソッ!
「逃げろっ!」倒れたまま叫ぶ。
お母さんは立ち止まったまま、周囲を見回していた。
「家に帰るんだ! 今すぐ!」
お母さんが振り返る。俺に気がついたんじゃない。ただ振り返って、自分の他に誰か通行人はいないかと探しているだけだ。
お母さんは眉を八の字に下げ、口元に笑みを浮かべていた。
自分が目にしているものはなんでもないものなのだと振る舞えば、それが本当になんでもなくなると信じている笑顔——笑う死相。「アイアム・ア・ヒーロー」ですぐにやられちゃう人の顔。「ガンツ」ですぐにやられちゃう人の顔。
マジでやめろ。マジで、やめてくれ。
「本当には何も起きちゃいない。だから心を傷める必要はない」
林田が欠片の前から右に退いた。
隠れていた風景が見える。
夕暮れ時。手前から遠くに向かって真っ直ぐ伸び上がってゆく急なコンクリートの坂道。その両サイドに並ぶ家々。ブロックの塀。電柱。電線——俺がかつて住んでいた町の一角。家から出てすぐの通り道。
風もなく、通行人も車もなく、烏や猫の姿もない。静止画のようだ。
動くものは1つだけ。
黒い影が坂道の真ん中を落下速度で降りてくる。自転車に乗った男。
あいつを知ってる——YouTubeで。Wikiで。殺人事件の記録ばかりを集めた悪趣味なサイトで。「不気味な殺人事件を語るスレまとめ」とかそんな名前のまとめサイトで。
あいつは俺のお母さんを殺した男だ。
「逃げろっ!」
俺はオットセイみたいに腕を使ってお母さんの元へと這い進む。
お母さんの足を引っぱたこうとしたが、俺の手は光がガラスを通過するように足を通り抜けてしまう。
「クソ! なんだよこれ! どうなってんだ!」
「これは現在進行形で作り上げられる存在しない過去だ」
林田が答える。
自転車のタイヤが回転する音が聞こえた。スポークが振動し、ペダルが軋む音も。
振り返る。川畑の乗った自転車が欠片の中から飛び出してくる瞬間だった。白い空間にタイヤが乗り上げる。ブレーキをかける音は聞こえなかった。自転車は少しもスピードを落とさず、お母さんに激突した。
肺が潰れたような声をあげてお母さんは倒れ、手足を振り回して地面を転がった。お母さんの体は雑巾みたいに捻れたポーズで停止する。左膝の皿に大きな擦り傷ができているのが見えた。
「お母さん! 逃げて! 何やってんだ! 立って! 逃げて!」
白い空間を這う俺の体の上を、自転車を何もない空間に立てかけた——俺に認識出来ないだけでそこには壁があるんだろう——川畑が通りぬけていった。
俺はあいつを捕まえようとしたが、手は空気をかき回しただけだった。
「こんなところにいたのか。よくも俺の悪口を言いふらしてくれたな」
川畑は独り言にしては大きすぎる声で言いながら歩き続ける。
あいつの右手で釘打ち銃が、左手でバールが風鈴みたいに揺れていた。
「これは絵空事だ」
林田が俺のすぐ側まで歩いてきて言った。
「林田」
「お前がしがみついているお前の人生は、診断メーカーが作り上げる前世の設定みたいに空虚だ」
俺は木登りをする猫みたいに指を広げ、林田の足にしがみつく。
「お母さんがあいつに殺される! 何とかしてくれ!」
「お前のお母さんはそもそも存在しない」
林田は俺の右手の傷を見て目を細める。
「お前も本当はいないんだ」
「たかが手の傷の位置ぐらいで、俺は偽者になるのか! たったそれだけで、急に俺はお前にとって架空の存在になっちゃうのかよ! こんなもん、誤差の範囲だろ! なあ、俺が傷つけば満足なんだよな?! もう十分だ! あいつをどこかにやってくれ! 頼むから!」
林田は子供の仮病を咎める親の目で俺を見た。
「お前は全然傷ついてない。それに自分が存在していないことも認めてない。俺はそう思う。俺がお前をそう思うから、お前はそうなんだ」
掌が汗で湿る。
「あの人は俺のお母さんなんだ! 俺があの人をお母さんだと思うんだよ! 死んで欲しくないんだ! それで十分じゃないか! どうしてわかってくれないんだよ!」
林田は眉間にVの皺を寄せる。
「元々存在しない人は、死んでも死んでなくても同じだ」
「林……」
「なんの影響もない。いないんだから」
林田は俺の後ろを指差す。
指の先に顔を向ければ、体を起こそうとしているお母さんの横にあいつが立っているのが見えた。衣服の上からでもはっきりわかるほど勃起している。
「夜中に俺の部屋の窓を懐中電灯でちらちら照らしてるのもお前だな」
川畑がバールを振り上げ、お母さんの顔に向かって振り下ろすまで、コンマ1秒もかからなかっただろう。俺もお母さんも悲鳴をあげられなかった。
お母さんの頭が白い空間にぶつかり、バウンドする。何か小さいものが飛んできて、俺の頬を通り抜けていった。砕けたお母さんの歯だった。
俺は必死に手を動かし、2人の元に向かう。
「俺の気を引こうとしてたんだろ。だから来てやったぞ。お前、俺にこうされたいんだよな。わかってるんだ」
川畑はお母さんの腹を蹴り始める。
お母さんの口から漏れる「なんで?」という苦悶の声が俺の心を掻き毟った。
「こうされたいんだ。厭らしい変態女め。俺の金魚を盗んだのもお前だろう」
川畑はお母さんの髪を掴んで引き摺り始めた。白い空間に血が線を引いてゆく。
「待て!」
川畑が民家の塀と塀の間にある隙間にお母さんを引き摺り込む。俺には民家も塀も見えないけど、2人の体はそういう風に動いたし、川畑がそうしたということを俺は知ってる。ネットで読んだから。
お母さんの顔が俺の方を向く。自分の耳が潰れるんじゃないかと思う程の悲鳴が口から飛び出した。とてもじゃないが止められなかった。
お母さんの顔が壊れていた。
顔の下に大きく開いた穴が口だということはわかったけど、目や鼻がどこにあるのか見当もつかない。鼻があるはずの場所には潰れた肉があるだけで、両目部分にはピンポン球を乗せたように膨らんでいる瘤があった。お母さんの口から冗談としか思えない量の血が溢れ出して顎から胸までを赤く染めていく。
川畑に這い寄り、お母さんを蹴り続けている足に掴みかかったが、俺の腕は川畑の体を通り抜けてしまう。
「やめろっ!」
俺はお母さんに覆いかぶさる。
「やめろっつてんだろ!」
俺の体を通り抜けて川畑の振るったバールが、スニーカーの靴底が、改造した釘打ち銃から放たれた銀色の釘が、お母さんを痛めつける。
「こうして欲しいってわかってるんだ。ほら、お礼を。お礼を言えよ。なんだ、そのふてくされた態度は。失礼だ。俺だって好きでやってるんじゃないのに、そういう態度でこられると余計に不愉快だ。良かれと思ってこうしているのに。ねぇ、謝れよ。俺に謝れよ」
お母さんは悲鳴をあげようとしたが、その度に顔面にバールが振り下ろされた。お母さんの顎は砕け、ムンクの叫びみたいに顔の輪郭が歪む。
「謝ったら? ねぇ? 謝ったら? こっちは良かれと思ってやってるのに? ねぇ?」
川畑が釘打ち銃の先端をお母さんの胸にくっつけて引き金を引く。お母さんの砕けた顎の奥から「痛い」と呻く声が水滴みたいに溢れて落ちる。
「大袈裟! 被害者ぶって、図々しい! 被害者ぶって! 傷ついた振りをすれば優しくしてもらえると思ってんの? ねぇ! ねぇ! ねぇ! この淫売」
あいつはバールを脇に起き、空いた手をズボンの中につっこみ奇声を上げながら扱き始めた。
あいつは顔を赤くし「おおおおお」と���る。死ねばいい。「おおおおおっおっおっ」死ね。「おおおおおおおお」死ね。死ね。死ね。
「おおおおお」俺はお母さんを抱きしめようとするが、どうすることもできない。
無造作に脱ぎ捨てた服みたいに弛緩していたお母さんが「おおおおおおおお」弱々しく腕を動かし始めた。「おおおおおおイっちゃうおお」空中にあるロープを手繰りよせようとしているかのような動きだった。「おおおイっちゃうおおおおお」
お母さんの顎が上下に動く。
「や、め、て」——そう言ったのではないかと思う。
「おおおおおおおお」
俺は振り返る。
「おおおっおおっおっふっうっうっおっ」
お母さんの足の間であいつが腰を振っていた。スカートが腹までめくり上がり、曲げられたお母さんの膝が、あいつが腰を振るたびに痙攣していた。
あいつの顔がすぐ目の前にある。あいつはひっひっと短く声を漏らしてから、鼻から長い息を吐いた。
ごぼごぼという音が聞こえ、お母さんの膝が痙攣する。
「あんた、俺のおトイレになるために生まれたんだ」
目の前が真っ白になった。
気がついた時には、俺はあいつに飛びかかっていた。
爪を立てた手で顔を引っ掻き、歯に拳を叩きつけ、体当たりをし、浮きだした首の血管に噛み付いた。
全て無駄だった。
俺の体は何をどうしてもあいつを通り抜けてしまう。なんの手応えもなく、残されるのは疲労と汗だけだった。
俺にできることは何もなかった。
俺のお母さんを強姦しながら、川畑は思い出したように釘打ち銃をお母さんの体に押し付けて引き金を引いた。太ももや胸や顔に。穢らわしい言葉を吐きながら。
嬲られるまま苦痛の中でお母さんは死んだ。最後まで苦しんだ。
全てが終わると川畑は自転車に乗り、元いた欠片の世界に、あの夕焼けの坂道に戻っていった。
俺はお母さんの側に座り込んだまま動けないでいた。
もう息をしていないお母さんの顔を見つめる。
顔中に隙間なく釘が打ち込まれていて、血だらけのミラーボールみたいに見える。元々口だったところには川畑のクソが詰められていた。
何が「女の人が突然叫んで道路に倒れたんです」だ。
全然違うじゃないか。
突然前髪を掴まれ、俯いていた顔を上に向かせられた。首が痛い。筋を痛めた。
林田が俺を見下ろしている。冷たい両手が俺の顔を撫でる。
「お前は最初からどこにもいない」
林田が願いを口に出す。
「本当は何も感じてないんだ」
願いが俺を侵食するのを感じる。
林田を突き飛ばした力がどこから湧いてきたのか自分でもわからなかった。
俺に抵抗する力がないと踏んで油断していたんだろう。林田は2、3歩後ろに下がってそのまま尻餅をついた。大人しい猫に噛まれたような顔で俺を見ている。
林田の願いが酸のように俺に染みて、俺を崩そうとしている。あいつの手が触れたところが痺れている。両手で顔を強く抑える。瞼に指が触れた時、皮膚が破れたんじゃないかと思うくらい痛かった。柔らかい雪に顔を突っ込みたい。
「俺は俺の思う俺だ」
願いをかける。喉が傷み、声が掠れていた。
砂が崩れるような感覚が止まった後も、ちょっとした呼吸や身じろぎがきっかけになってまた体が——俺という存在そのものが、林田の願いに飲み込まれて崩れ落ちるように思えて、手を顔から離せなかった。
指の間から俺は林田を睨みつける。
「自分が何したかわかってるのか」怒りで声が震えた。
「俺がやったんじゃない。あれは勝手に組み上がったんだ。それに本当は何も」
「お前が川畑を呼んだっ! あいつが何をするかわかってて呼び出したんだ!」
怒鳴ると喉のどこかが破れたんじゃないかと思うくらいの痛みが走った。
俺は顔を覆っていた手を離して、喉を摩る。
「お前は俺を傷つけようとするくせに、俺が傷つくと何も感じてねぇとほざきやがる。何がしてぇんだ!」
あいつはあぐらをかき、頬杖をつく。
「お前が限界まで傷ついたと、俺が納得したい。これはそのための試練だ」
「何が試練だ!」
「ほら、まだ元気だ。俺の思うお前だからな。そりゃ元気だ。俺がお前を何事にも諦めない前向きな奴だと思うから、お前はそういう奴になったんだ。お前は本当に好感度の高い素敵な虚構だ。消すのに骨が折れる」
林田の背後に浮いていた世界の欠片たちが、磁石に吸い寄せられる砂鉄みたいに一箇所に集まり始めた。
「今度は何をするつもりだ」
それは組み重なり合って、一斉に白く輝く。
「お前を変質させる。お前に傷をたくさんつけて、お前から素敵さを剥ぎ取るんだ。『少年時代は好きだったけど途中からすげぇヘタレになったから、あのキャラ嫌いになったし、あの漫画も買うの止めちゃった』、そんな風にさ、俺を失望させてくれよ。使い物にならなくなってくれ。曲げすぎて元に戻らなくなった下敷きみたいに」
輝きが消えるとそれは無数の欠片の塊から1つの大きな欠片に変わっていた。ちょうど、お母さんが出てきた欠片と同じように。
まだ中には何も映っていない。ただ白いだけだ。
林田は立ち上がり、その白い表面を撫でた。
「もう消えたいってお前が思うと、俺が思うまで、続けるからな」
喉が掠れて「やめろ」という声が出なかった。出ていたとしても、あいつはやめなかっただろう。
「お前の恐れるものを、こちら側へ」
破片が白く光る。
光りが消えると、見覚えのある玄関がその破片の中にあった。
焦げ茶色のドアの真ん中には磨りガラスがはめ込まれていて、そこから誰かが靴を履こうとしている影が見えた。
あれは、かつて俺が暮らしていた家の玄関たった今、出来上がった新しい過去。
「ついでにアイス買ってきてあげるね」
お母さんの声。
玄関のドアが開いて、お母さんが出てくる。
白い空間をサンダルが踏む。
座り込んだままの俺の横を通り過ぎる。
血だらけで倒れている自分の別のお母さんの死体を、生きているお母さんの足が通り抜ける。
濡れた手からレモン石鹸の懐かしい匂いがした匂いがした。夕暮れ時のお母さんの匂いだ。一度も嗅いだことのないいつもの匂い。懐かしさに胸が締め付けられる。ああ。チクショウ。
「お前が俺と出会う前に過ごした日々は全部フィクションだ。物語だ。お前は嘘ばかりだ。お前の存在、人生、心、全部嘘だ」
林田が俺を見下ろしながら静かに言う。その背後ではまた破片が集まり始め、新しい大きな欠片になろうとしていた。
「お前みたいな空想の生き物のために、俺は悲しんだりしないよ。絶対に」
新しい大きな欠片が完成する。林田は横に一歩ずれて、白い欠片の表面を撫でた。
「お前の恐れるものを、こちら側へ」
夕暮れ時。赤い空。真っ直ぐに伸びた坂道。両サイドにアパートが並ぶ。レンガの塀。電柱。電線。俺がかつて住んでいたということになっている、本当なら見たことのない町の一角が欠片の中に現れた。
坂道を自転車がすごいスピードで走り降りてくる。
俺は座り込んだまま動けなかった。
川畑の乗った自転車は欠片の世界からこちらに飛び出してきて、俺の横を猛スピードで通り過ぎていった。
背後で何かが何かにぶつかる大きな音と、何かが倒れる音がする。それが何なのか、もう俺は知っている。ヒュゥという鋭い音は、バールが風を切る音で、咳き込むような破裂音は歯を失ったお母さんが悶える声だ。プシュッという連続音は釘が飛び出す音。
「助けなきゃ……」
振り返る。俺が想像していたのと同じ風景がそこにある。倒れているお母さんと、お母さんを痛めつける川畑。俺が2人に向かって這って行こうとすると、林田が立ちふさがった。
「退いてくれ」
「最前列で母親らしきものがキチガイに虐殺されるのを見学するのか? あいつがお前の母親らしきものの顔にクソをするところをまた見るのか?」
返事の代わりに林田の足に唾を吐いた。
両手で体を引きずり、お母さんの方へ進む。
俺は林田の横を通り過ぎ——絶叫する。足の裏が爆発した。
「本当は痛くなんかないんだぞ? 痛いと思ってるだけなんだ」
視界が点灯した。マンゴーじみた傷が踏みつけられてる。痛い。痛い。
林田が俺の頭を両手で掴み、力なく崩れていた俺の体を無理矢理引き起こす。
「自分は存在しないって心から認めれば、こんな痛みなんてなくなるんだぞ」
林田が俺の正面に両膝をついて視線を合わせる。
俺は生白い顔に向かって拳を放ったが、笑いながらはたき落とされてしまう。文字通り、蠅が止まるようなパンチだったから。
「お前が『俺は存在するんだ』って思っている間は、お前の母親らしきものは必ずああやって死ぬんだ。彼女が死ぬのは、全部お前のせいなんだ」
言葉が熱した鉛みたいに耳の穴へ入り込んで脳を溶かしたのだと思った。
「心が痛いか? それも気のせいだ。存在しないと認めろ。その痛みも消える」
目から流れ出す液体が涙だとは思えなかった。鉛混じりの溶けた脳だと思えた。
林田が俺を見つめる。
俺の顔のどこかに隠れているウォーリーを探しているような目つき。
「まだ全然十分じゃないな」
林田は立ち上がる。
「『俺の人生はそこにあった』とお前は言った。それを返せとお前は言った。なぁ、これがお前の人生だよ」
『古き良き』なんて言葉で飾り立てられる、ちっとも良くなかった時代のサーカスの団長風の派手な身振りで林田は両手を広げた。
「家も母親も全てが適当に組み上がる、本当は一度も存在していないデタラメな過去! それがお前の人生だ! お前のすがりついているものの正体だ! 最初から存在しないものをどうやって返せるっていうんだ! お前はそんなもののために傷ついてる! 本当は最初からいないもののために傷ついてる! 傷つく必要のないもののために泣いているんだ!」
「必要か必要じゃないかで、悲しいか悲しくねぇかが決められるもんか」
掠れた声で言い返す。
「テメェはとんでもねぇクソ野郎だ。俺がどんな思いでお前を死ななかったことにしたと思ってやがるんだ!」
林田の眉間にWの皺が寄る。僅かにスズランの瞳が揺らいだように見えたが、俺がそうであってほしいと願ったからそう見えただけなのかもしれない。
林田は再び俺の前に膝をつき、両腕で俺を抱きしめる。
「急になんなんだ! 情緒不安定か! パラノイアのサイコ野郎!」
「わかってるんだ、プーさん。お前は俺を見捨てられない。お前は俺を嫌いにはなれない。お前は俺を傷つけることは出来ない。絶対に。お前はそういう風に出来てる。お前はそういう存在だ」
首にあいつの息がかかった。
「認めろ。お前が俺の作り上げた本当は存在しない存在だってことを。認めろ。お前はただの物語だ。認めろ。お前はマクドナルドにいる女子高生で、電車の中の小学生で、ファミレスで隣になった外国人。あるいは、いつも面白いことをする友達の友達で、本当に霊感のある友達の友達のお姉さん。『俺の知り合いにそういう人がいるけど』で語られる都合のいいゲイ。自己啓発本か名言カレンダーからコピペしたような悟ったことをいうガキ。望まれた形で存在するシルエットだけの実態のない怪物だ。どいつもこいつも誰かの欲望を正当化するために出来上がった影絵だ。陳腐で低俗でグロテスクな下卑た欲望の伝言ゲームの中で雪だるまみたいに膨れ上がって完成したザーメン臭い夢、それがお前だ。それを認めろ。お前は俺が言って欲しいことを言う。お前は俺の望みを体現する。お前は俺専用の友達botだ。本当はいない。一度も存在したことがない。認めろ。本当は何も感じていないってことを。俺がお前を傷ついていると思うから、傷ついているんだ。でももう俺はお前の正体を知ってる。お前は何も感じてない。感じたように振舞っているうちに、感じていると感じるようになっただけの存在もどきだ。それを認めろ。お前は悲しんでなんかいない。お前は苦しんでなんかいない。お前は傷ついてなんかいない。お前は何も感じていない。お前には心なんてない。お前には感情なんてない。お前は誰でもないし、なんでもないんだ。一度たりとも、何かであったことも、誰かであったこともない。俺の現実を邪魔するモンキーレンチだ」
乾いたスポンジが水を吸うように、林田の声が俺の心に染み込んでいった。
俺は何も感じていないんだそうだ。
悲鳴。
口の中に血の味が広がる。
悲鳴が更に激しくなった。
左顳顬が殴りつけられる。
弾みで顎に力が入り、前歯の間で肉が千切れた。
舌の上を滑る肉の感覚に動揺し、顎の力が緩む。
顳顬にもう一発、衝撃がくる。
俺は突き飛ばされ、仰向けに転がった。
後頭部を強か打ち付けた拍子に、口の中にあった肉の塊が喉の奥へと消える。
やっすい居酒屋のやっすいカルパッチョを、一口も噛まずに飲み込んだような感じだった。血が喉の傷に染みて痛んだが、やがてはちみつを塗ったみたいに喉にずっと感じていたひりつきは消えた。
塩辛くてぬるぬるした後味に呻く。まずっ。気持ち悪っ。まずっ。
悲鳴はまだ続いている。
頭をあげると、左耳を抑えて暴れている林田の姿が見えた。
初めてアイススケートをする人みたいに体を右へ左へ派手に動かして、汚い言葉を吐き散らかしている。
耳を押さえた手を血が走り、肘までが赤く染まっていた。
あいつは自分の血だらけの手を見つめて罵声を上げ、癇癪を起こした子供みたいに頭を振り回す。左耳があった場所から血が吹き出し続けている。
あいつの尖った耳は今や俺の腹のなかだ。
飲み込むつもりも噛みちぎる気もなかった。弾みだ。弾みでやっちまった。
口から吐き出そうと思った時にはもう喉を通過してしまっていた。
気持ち悪い。人間の耳を食った。すげぇ気持ち悪い。
でも今は気持ち悪さよりも、爽快感が優っていた。
俺は肘をついて上半身を起こす。血だらけの口を拭って、大声で叫んだ。
「ざまーみやがれ!」
もう一度叫ぶ。
「想像上のお友達に耳食われた気分はどうだ! これでも俺はまだお前のご都合主義でできた存在か? ややこしい言い訳してみろよ、妄想サイコ野郎! 俺はお前を傷つけてやったぞ! さっきなんっつてた? 俺はお前の都合のいい空想の友達だから、お前を攻撃できねぇだのなんだの、クソみてぇなこといってやがったよな!? このバカが!」
林田の顔が見えない大きな指に弾かれたように俺の方を向いた。
目つきがおかしい。目線があっちこっちに動き回っている。何かを探しているみたいだ。やがて目線は左斜め上でピタッと止まり、奴の口が胡桃の殻をかじる栗鼠を思わせる速さで開閉し始めた。ブツブツと何か喋っているが聞き取れない。やめろ。気持ち悪いから。
喋り出した時と同じくらい唐突に、林田は喋るのを止めた。目玉がぐるりと回転し、何もない中空を見つめていた目が俺に向けられる。
唇の端が耳に届くように口を引き伸ばして林田は笑った。
「俺の奥底にある『本当はお前に実在していて欲しい』という気持ちが、お前が俺に噛み付かせたんだ。俺がお前に、俺に噛み付くことを許したんだ」
はぁー!? と思わず絶叫した。はぁー!? なにそれ、はぁー!?
「全部テメェの匙加減で決まるんじゃねぇか! 後出しで『全て俺の計算通りです』ってか! そんな煮詰めたクソみてぇな言い分が有りなわけねぇだろ! バカが! 自分の力と妄想に振り回されて、お前、もう、滅茶苦茶じゃねぇか! 自分のザマを見てみろ! 酷いぞ、お前! これ以上バカなことをするんじゃねぇ!」
倒れる直前のコマみたいに林田の上半身がぐるぐると回る。ヒヒヒヒ笑いが回転する。俺の声が聞こえているのかどうかもわからない。あのバカ、自説が否定されて完全にパニックに飲まれてる。ガキの頃、体育倉庫で俺に襲いかかってきた時のエスカレート版だ。
「冷静になって考えてみろ! 俺に耳を食いちぎられたいって本当に思っていたのか? それこそ後付けでそう思い込もうとしてるだけじゃねぇのか?!」
林田はまだ笑っている。聞こえてないのか、聞いているけど脳に入らないのかどっちかわからん。
「ここには俺しかいない、誰もなにも感じてなんかいない、そういう風に見えるだけ。お前は心がある振りをしてる。傷ついている振りをしている。怒っている振りをしている。心配している振りをしている。でも本当は何も感じてない。空っぽなんだ」
クソ。このバカが。
「お前が俺の心を決めるな! お前が決めていい領域じゃねぇ! ふざけんな!」
林田が動きを止めた。ヒヒヒ笑いが止まる。中途半端に斜めに傾いたポーズのまま、林田は俺を見ている。笑顔はない。なんの感情も見えない。
これはどっちだ? 通じたのか?
顔の筋肉の1つ1つが見えない糸で引っ張られているように、ゆっくりと林田の顔が変化し始めた。目玉は顔面から飛び出さんばかりになり、口は、牙が生えていないのが不自然に感じるくらいに裂けた。悲しみと憎しみと怒りと憂いと、あらゆる暗い感情が組み合わされたキュビズムだ。
「お前がやったことじゃないか!」
林田はこちらに歩いてくる。
「俺が? 俺が何をしたっていうんだよ!」
「気付いてねぇとでも思ってたのか!」
林田が吠えた。
「『こいつは頭がおかしいんだ』って目で俺を見てただろう! ずっと前から気づいていたんだ! テメェの『こいつがまた何か妄想を話し出したぞ』っていうあの目にな! そう! その目だ! 今もその目でテメェは俺を見てる! 『こいつは頭がおかしくなった』って決めつけてる! 俺の心を勝手に決めつけてるのはいつもテメェの方だ! いつだって俺の苦しみを過小評価し続けただろうが! 『どうせ妄想だ』って笑ってたよな! 俺の世界をテメェはニヤニヤ笑って見ていたんだ! 真面目に取り合うつもりなんてなかったんだ! そんなお前が! 今更! 心を決めるなだって!? やっていい領域じゃねぇって!?」
ヒヒッヒヒッと林田は呼吸しながら神経質に笑った。
「『お前は混乱しているんだ。だからそんな変な話ばっかりするんだよ。病院に行って、お前の頭の中にある病気の部分を診てもらおう』」
林田はいつかの俺の口調を真似ながら言う。
「俺は病気じゃなかった! 病気じゃなかった! 俺は間違ってなかった!」
「林田、その時は俺はまだ——」
「終わったことか? もういいじゃんって? それとも『そんなちっぽけなことを気にするな』とでも言うか? ふざけんじゃねぇ! お前が先にやった! お前が先に俺の心を否定した! よくも、お前、よくも、偉そうに! 俺が死にかけてた時、ヘラヘラ笑ってやがったじゃねぇか! 俺が死ぬほど怖がってた時! テメェ、真剣に俺の話を聞いたかよ! テメェが! テメェが! テメェが! テメェが! テメェごときが! たかが! 俺の! 妄想の産物ごときがっ! 俺の苦しみはなんだったんだ! ずっとずっとずっと、自分が狂ってるって思い込んで! それでもお前はいると思っていたから! それでもいいって受け入れていたのに! いなかった! いない! たかが傷の位置だと!? あれが俺のお前の目印だった! 俺が取り戻したお前の目印だった! でもいない! お前はどこにもいなかったんだ! もう消えろ! 俺は次の世界に行く! 本当の世界に行く! 確かな世界だ! 突然全てが変わったりしない、重力のように絶対的な世界だ! 唯一の真実、たった1つだけの真理、絶対的な本家本物の揺るぎなき純粋な世界だ! お前を消しさえすれば、本当の世界が到来する! お前も、今までの世界も、夢の中の蝶になって、羽ばたいて、飛べなくなって、落ちて、潰れて、崩れて、見えなくなって、最初からなにもなかったことになるんだ!」
林田の体が大男のように膨らみ始めたように見えた。
あいつの周りに銀色の欠片が蜂みたいに震えながら集まってくる。その切っ先は全て俺に向けられていた。死がざらついた舌で背中を舐める。
俺は立ち上がり、痛む足を引きずりながら歩き出す。とにかく、ここにいちゃだめだと思った。逃げ場があるかなんて考えてない。
「どこに逃げようってんだ! この化け物!」
空気を切る音が聞こえ、後ろから飛んできた何かが左腕にぶつかった。体が衝撃に引っ張られて俺は踏鞴を踏む。
左腕が縦方向に回転しながら前方へと飛んでゆき、やがて白い空間に落下して転がった。腕から少し離れたところに銀色の欠片が突き刺さっているのが見えた。血がついている。透明オーランド・ブルームの1人が、世界の欠片を放ったんだ。
俺は視線を自分の左腕に向ける。
肘の少し上の部分で俺の腕は切断されていた。血がジョウロから溢れる水みたいな勢いで流れ落ちている。
腕が。
俺の腕。
「腕!」
俺は前方に転がっている腕に向かって駆け出したが、追いかけてきた林田に脇腹を蹴られ、倒れてしまう。どこもかしこも白いから、転がっている間、自分が上を向いているのか下を向いているのかわからなくなる。
腕の痛みはまだない。ショック状態だ。ただ、切断された場所が熱くて痒い。指を突っ込んでかき回したくなる。
林田が俺の腕を拾い上げ、猫でも抱くように両腕で胸の前に包む。
痛みがナメクジのようにゆっくりと傷口から脳に向かって這い上がってくる。
「お前、今が変わった後に変化した過去も『思い出せる』んだよな?」
林田は猫を撫でるように俺の腕を撫でる。
林田は考えを巡らせるように目線を宙に漂わせる。それから何かとてもいいことを思いついたように笑う。今まで目にした林田の笑顔の中で最悪の笑顔だった。
「この腕が、義手だったらいいのに」
林田が願う。
あいつの腕の中にある切り落とされたばかりの俺の腕が、肌色のプラスチックか何かでできた義手に姿を変えた。
腕の痛みも痒さも消える。
俺は切り落とされていない方の手で断面だった部分を撫でる。そこはつっぱった光沢のある皮膚で覆われていた。まるでずっと大昔に腕がなくなって、断面が塞がったかのような状態だ。
「さぁ、どうなるかな? どうやってお前は手を失った? お前の頭に出来上がるぞ、お前の知らない、存在しない過去の物語が!」
林田は義手の手首を掴んで俺に向けて振る。プラスチックの指がぶつかり合って硬くて軽い音を立てた。
「お前が消えたくなるまで、新しい思い出とトラウマを作り続けてやる」
頭の中に新しい過去が出来上がる。
「嫌だ」
意識せず言葉が漏れる。
「嫌だ。嫌だ」
俺と林田の間をお母さんの髪の毛を掴んで引き摺りながら川畑が通り過ぎてゆく。
お母さんは死んでいた。両目に釘が突き刺さっているのが見える。
川畑はまた例のパントマイムで、お母さんを民家の間の路地に引きずり込む。
「お母さん」
小さい子供の声が白い空間に響く。
声のした方に顔を向ける。俺は、声の主人が誰だかわかっているし、これから何が起きるのかもわかってる。新しく頭の中に差し込まれた記憶がそれを知らせる。
これは今から起きる未来で、とっくに起きた過去だ。
「お母さん?」
2人めのお母さんが出てきた欠片の中。
玄関のドアが開いて、子供が——俺が、小さい頃の俺が歩いてくるのが見える。
川畑が民家の塀の間から出てくるのと、子供の俺が欠片の世界から顔を覘かせるのはほとんど同時だった。
子供の俺は血だらけの男を見て硬直する。
「ああ、ごめんね。驚かせちゃったね。ちょっと今、事故に巻き込まれてしまって」
川畑は一瞬でお母さんを襲っていた時に剥き出しにしていた狂気を隠した。レインコートみたいに薄い正気で身を覆って、不信感の雨を弾こうとしている。
「ちょっと怪我しちゃったんだよ、でも、見た目ほどひどい怪我ではないから」
あいつは体についた血の言い訳をしながら、再び俺と林田の間を通り過ぎ子供の俺に向かってゆく。
俺は。
小さな俺はこの時、近づいてくる男に異常なものを感じていた。服のあちこちに血がついていて、手には工具を持っているし、目つきもおかしいと思っていた——という記憶が出来上がる。
今目の前で起きていることの記憶が、頭の中にある。
「おじさん、怪我しちゃったんだ。お父さんかお母さんはお家にいるかな?」
「お父さんはまだ帰ってないです」
答えてから慌てて「でもお母さんはちょっと買い物に行ってるだけだから、すぐに帰ってきます」と付け足す。
この時、小さな俺は「お母さんがすぐに帰ってくる」と言えば、万が一この男の人が変な人だったとしても悪いことはしないだろうと思っていた。
子供が遊びで使う「バリアー!」みたいなもんだ。
「お母さんって、藍色のスカートを履いてて、黒いブラウスを着てた人かな? 実は少し前にすれ違ったんだけど」
小さな俺は頷く。それがどういう意味を持っているのか気がついてもいない。俺が頷いたから、川畑はお母さんがもう帰ってこないと知ったんだ。お遊びのバリアーは本当になんの意味もなくなった。
「電話を貸してくれないかな。救急車を呼びたいんだ。お母さんが帰ってきたら、ちゃんとおじさんから説明しておくから」
川畑はそう言うと、さもどこかを怪我しているみたいに顔をしかめながら、俺の家がある欠片の中に入って行った。
「……だめだ」
俺はふらつきながら2人の後を追いかける。涙が頬を焼く。
「だめだ、そいつを家にいれちゃだめだ。お願いだから」
子供の俺は駆け足になって川畑の前に立つと、ご丁寧にも玄関を開けて、奴を家の中に招き入れた。
「だめだ、家にいれるな」
あの俺は子供で。川畑は大人で。
あの俺は「大人は子供を守るものだ」っていうのが、太陽や重力みたいに絶対的な日常に生きてた。
「悪い大人」っていうのはあの俺にとっては、どこかに存在するらしいけど一生自分が遭遇することなんてない存在だった。例えば本物のカウボーイや、宇宙飛行士や、少林寺拳法の使い手みたいな、いるにはいるけど殆ど���ァンタジーの世界の住人のように思っていたんだ。
ドアが閉まる直前、川畑の声が聞こえた。
「妹がいるのか」
ドアの向こうで行われていることが、次々と頭の中に浮かんでくる。コーラから溢れる泡みたいに止めようがない。俺は欠片の前で転び、そのまま動けなくなる。
「嫌だっ! 嫌だっ! 思い出したくない! 嫌だっ!」
腹を抑え、体を丸める。吐き気が収まらない。
俺の新しい過去が、今ドアの向こうで起きていることを教えてくれる。
俺は悲鳴をあげる。
記憶が出来ている。あいつが妹に何をしたか。あいつが俺に何をしたか。
「嫌だっ! 嫌だっ!」
あの欠片の中とこの白い空間の時間の流れが同じなら、あのドアが開くのはずっとずっと先になる。
それまであのドアの向こう側はあいつの妄想の王国だ。
衝撃が太ももを突き抜けた。
第2のオーランド・ブルームが矢を放ち、俺の右足を膝の下から切断した。
俺は体をカブトムシの幼虫みたいに丸めて喘ぐ。
林田が転がった足を拾い上げるのを歪んだ視界で見る。
「や、やだ、やだ、足、返せ、足」
林田は俺の足を抱きしめて、撫でる。嫌だ。やめてくれ。
「これが、義足だったらいいのに」
俺の切断されたばかりの足は、子どもの頃に川畑に切断された足に変わる。
悲鳴。俺の悲鳴。ドアの向こうでも過去の俺が叫んでる。
ドアの向こうの俺の過去で、川畑が俺の足を切り落とそうとしている。
俺は足の肉を削られ、ズボンを糞尿で汚しながらガムテープで蓑虫みたいに巻かれた妹に「大丈夫」と繰り返しているだろう。
それを川畑が笑いながらみている。
「どうだ?」
林田が首を大きく右に傾ける。その笑顔が、川畑の笑顔とダブって見えた。何も見てない。相手を自分の妄想を証明する道具だとしか思ってない。
「消えたくなったか?」
林田が膝をついて俺の顔を覗き込む。
あいつの毒で満ちた目が俺の目を見る。
俺は頷いた。何度も、何度も。
もう嫌だ。消えたい。
だが林田はいつまでも俺の顔を撫でようとはしなかった。
W皺を浮かべてただ俺を見ている。
「まだ消えたいって思ってないな」
3人めのオーランド・ブルームが世界の欠片を放ち、俺の右手首を切断した。
ドアの向こうで、子供の俺が右手首を熱した油の中に突っ込まれて泣いている。
妹が悲鳴をあげると、川畑は妹に油を——。
林田が笑っている。
心が少しも通じない。
前話:次話
0 notes