#レンチキュラー天野
Photo

ぺぱぷんたす006号の発売を記念して、『ぺぱぷんたす』×福永紙工Presents「紙となかよくなる夏休み」~かみの すきなこ、あつまれ~ 8月1日(月)~8月31日(火)まで、立川GREEN SPRINGSの「SUPER PAPER MARKET」にて開催中! 発売になった『ぺぱぷんたす』の最新号はもちろん、ぺぱぷんたすゆかりのアーティストのグッズも販売。『ぺぱぷんたす』の世界を体感していただけます。 期間中は、随時「ぺぱぷんたす」のかみあそびミニワークショップ(たくさんの種類をご用意しているので、気に入ったものを選べます)を開催するとともに、ぺぱぷんたす参加アーティストによるワークショップも開催! トップバッターは、すでにTwitterでも話題になっているレンチキュラー天野さんによる「ふしぎなレンチキュラーの世界」 細かい凹凸のあるレンチキュラーのレンズを使うと、見えないものが 見えたり、動いたり、色や形が変わったり…あっと驚くふしぎなことが起こります。このレンズを使った魔法のような遊びを、レンチキュラー天野さんと一緒に楽しみながら、最後は、特製レンチキュラー台紙と紙を使って、自分だけのふしぎな絵を制作します。 【ワークショップ概要】※要予約。但し、定員に満たない場合は、当日参加可能。 日時:8月7日(日) 1回目 11:00-12:30 2回目 14:00-15:30 定員:各回20名 参加費:1800円 対象年齢:はさみの使えるお子さま~ 制作した絵や、レンチキュラーレンズはお持ち帰りいただけます。内緒のお土産付き。 参加希望の方は @paperpuntas ページのプロフィールの下にあるURL→ぺぱぷんたすサイト→イベントのバナーよりお申し込みください。 https://greensprings.jp/shop/super_paper_market/shop_news/4568/ ※ワークショップにご参加の際は、マスクの着用をお願いいたします。 ※状況によりやむを得ずイベント内容を変更、または中止する場合がありますので予めご了承ください。 <イベント概要> 『ぺぱぷんたす』×福永紙工 Presents「紙となかよくなる夏休み かみの すきなこ、あつまれ~!」 会期 :8月1日(月)-30日(火) 営業時間 :11:00-19:00 ※最終日は18:00まで 場所 :SUPER PAPER MARKET 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E2 209 (2Fフロア) <参加アーティスト> @kamone 石川将也 @kanakoogawa 小川かなこ @oguroeri オグロエリ #かこさとし #きくちちき #北澤平祐 @cochae COCHAE #五味太郎 @thecabincompany ザ・キャビンカンパニー @yushichiji 七字由布 @junaida_ig junaida @noritake.suzuki 鈴木のりたけ #せなけいこ @sobueshin 祖父江慎 @takeiharuhi 竹井晴日 @太公良 @tanibataminoru 谷端実 @tamasakuu 玉川桜 @tupera_nakagawa tuperatupera @norio_nakamura_ 中村至男 @nakayamashinichi 中山信一 @nishi_shuku 西淑 #原田郁子 @kenjioikawa_100 100%ORANGE #ひろせべに @2016pinkpepper @wakidaasuka @zu_s_a @fancomi @aikofukawa布川愛子 @h_bobfoundation Bob Foundation #Murgraph #マグネット @n_toz @mame_ikeda マメイケダ @misawadesigninstitute 三澤遥 #三谷純 @mina_perhonen.jp #ミナ ペルホネン @mirocomachiko ミロコマチコ #明和電機 @lenti_amano レンチキュラー天野 https://www.instagram.com/p/Cgsl4vtP9r6/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text
動きはじめる身体のために
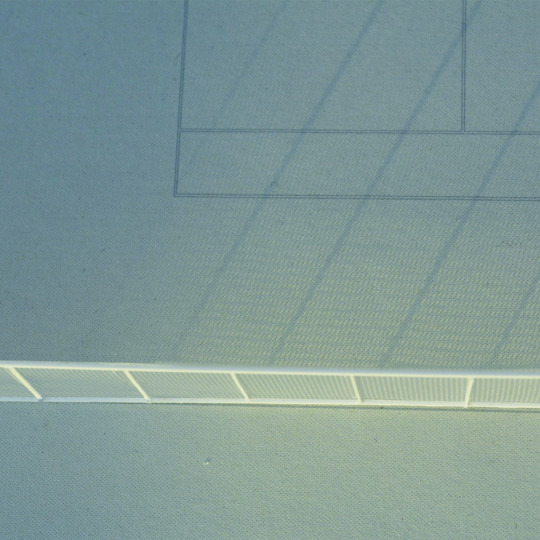
-
かつて、世界は今よりずっと、見通せるものだった。だだっ広く広がる土地には、はるか遠くに、水や地面の終着する線だけが見える。教科書で習った知識に基づけば、その線の向こうは、きっと地球が球体であるから見えないのだろうし、はるか遠くの地面の小さな凹凸がまるで気にならないのは、われわれの視力が、そこまで鋭敏ではないからだろう。それから長いときが経って、世界の多くは、細かく細かく分割され、整備された。そこで暮らす人間の分だけ家ができ、彼らが快く暮らせるように、数多くの機能を持つ構築物が生まれた。川の向こうに難なく渡れるようにもなり、地面から離れた場所に上っていく経験を簡単に得られるようにもなった。辿り着ける場所が広がるにつれ、街は見通せなくなっていった。身体の自由はおそらく増えた。人は、かつての人が、一生のうちに移動していた距離をずっと超えて、想像できたよりもずっと突飛な場所に、行けるようになっただろう。そうして、目は、随分と近くを見るようになった。構築物が周囲全方位から眺められるということは、ほとんどなくなったし、見えないくらい遠いものに出会うことも少なくなっていった。目は、多くの制限を受けるようになったとも言えるし、目のための足掛かりが、この世にたくさん作られたとも言えるだろう。
意識を持ち、自分の身体が自分のものだと気づき、概ね自由に動かせることも把握したとき、人は、世界が自分の身体とは関係なくただ周りにあるのだ、ということをすでにわかりはじめている。さて、どこまで関係なく、しれっと存在しているものなのだろうか、なにせ私たちは、この地面に支えられているのだ、この壁のせいで向こうが見えないのだ、この窓のお陰で陽を浴びるのだ。身体と世界の関係、と言ってしまうと随分と大げさな響きだけれど、身体と身の周りのもの、自分の扱う範囲で言えば、身体と建築の間にある緊密な関係、そこに興味のすべてがあった。身体が動けば、見えているものは変わる。乗り物の動きに合わせて、車窓から見える風景が後方に滑っていくのと同じように、世界は、建築空間は、私の身体の動きと逆方向にぬるりと動いていく。そしてその身体の可動範囲は、建築によって定められている。床がなければ進めやしない。建築は、人の身体の位置を規定しながら、人の視覚の中に動きとして立ち現れるのだ。そして、足掛かりのたくさんあるこの世の中で、視覚は身体よりも、遠くまで届く。建築空間は、動きはじめる身体のためにあった。そして、動かずに建築を訪れる、ということはできない。
-
leaf throughという言葉を、タイトルに掲げてみることとした。自分の思う建築体験を、的確に表していると考えたからだ。〈(本の)ページをめくる、ぱらぱらと繰る〉というこの言葉には、フリップブック、いわゆるパラパラ漫画についての記述を読んでいたときに、ふいに出くわした。『観察者の行方−ポスター、絵本、ストーリー・マンガ』(鈴木雅雄) の中に出てくるその記述は、映画と同時代、19世紀末以降に流行・定着したこの装置を取り上げて、” 単純と言えばこの上なく単純なこの遊具が、映画の時代にそれと並行して存続し、今にいたるまで命脈を保ってきたという事実には、何か感動的なものがある。それは映画の代理ではなく、自らが出来事を作り出しているとともに、その出来事が自らとは切り離されたものとして現象してしまうというあの矛盾した体験−動いてしまうイメージという体験−を、何度でも生成させるためにこそ要請された装置ではなかっただろうか。” と、装置のもつ〈運動を自ら操作する〉という側面に重心を置いたものである。ここに続く記述は、女性が衣服を脱いでいくようなポルノグラフィックなフリップブックが多数存在することを取り上げ、単に〈彼女〉が服を脱ぐだけでなく、〈私〉がその出来事を作り出すということに対する、危うい欲望に触れている。“ 私は出来事を作り出し、そのスピードを操作することさえできる。思いのままに出来事を止めて、気に入ったポーズに見入ることすら自由なのだ。それは単に運動への欲望ではなく、動かすことができ、また止めることもできるという驚異への欲望である。”
この危うい欲望は、建築空間を体験するわれわれの快楽そのものだ。ある空間は私たちを、機能や好奇心などの要請により、その先へと歩かせる。そのとき私たちは、身体の動きと逆方向にぬるりと動きながら、徐々に展開していく建築空間に直面するわ���だが、足を早めればそのスピードは上がり、のろのろと歩けば緩やかになる。また、ぴたりとその動きを止め、もと来た道を引き返し、それ以上知らずに帰ることもできる。さすがに、ばっとページを開くように、ランダムなあるシーンだけを不意に知るということは、実空間には難しいが−ただ、建築写真などで、不意に知ってしまうこともある断片的なシーン同士の繋がりを、実際に流れで見てみないと全貌は知り得ない、という点は、また似ている。知ってしまっても、何度でも、もう一度見ることができる。先ほどとはまた違う速度で。少し違う角度で。建築空間は、視点の埋め込まれていないフリップブックだ。対象を観る目の角度は、鑑賞者が選ぶことができる。場合によっては別の順番で観ることもできるし、〈私〉と同時に、横に並んで入った〈あなた〉の目に展開する建築空間は、また少しだけ角度の違うものになるはずであるし。
建築は時間芸術ではないというのは自明すぎる命題だが、映画や音楽と比較するとそうなのだ、と言えるだけであり、実際には、流れていく時間と切り離して語ることはできない。鑑賞する目、もちろん目に限らず、空間を知覚する身体は、その身体能力によって制限を受けている。フリップブックをめくる速度がどんなに自由だと言えども、実在する紙である以上そこには限界があるように、空間を体験するわれわれの身体には、歩く速度、走る速度、見える角度や視野などの限界がずっとつきまとっている。動いていく身体とともに、ある程度規定された見えが移り変わっていく、という当然の事実を、あらゆる建築物に当てはめてみるところから、リサーチを始めた。
-
〈第一の部材としての身体〉と名付けた1つめのリサーチは、物質として立ち現れ、この世に確固とした存在感を放っている建築物と、それをふらりと訪れる〈私〉の身体の位置関係を記述したものである。空間は、〈私〉以外のものとして体験することはできないために、このリサーチはかなり主観的な性格を帯びるはずだが、〈私〉がごくごく一般的な〈人間〉の形をしている以上、記述されている図は一般化できるものになる。図はすべて〈鑑賞者の身体の位置を含んだ空間構成のコンポジション〉だと言い換えられる。そして、コンポジションの問題として扱うと、広大な地平線から展示室に置かれた椅子までを、身体との位置関係で見え隠れするものとして並列に考えることができる。こうして、furniture・architecture・landscape・earthという4つの区分で、今までに訪れた建築における空間体験を記述していった。
リサーチは、ひどく単純なところから始まる。初期のいくつかの図版が示すものは、ドイツ・ケルンにある教会Bruder-Klaus-Feldkapelle、スリランカの名作ホテルLunuganga、ドイツ・ミュンスターの中心街にあるLWL-Museum für Kunst und Kulturなどに通じる、身体の動きと共に移り変わるシークエンスである。ここでは、自由に歩く鑑賞者に委ねられていると言えるはずの建築空間の体験が、外部からの要請によって生まれる〈人間〉一般の常識的な動きによって、思いのほか画一化されていることが見いだせる。例えば、広大な広場の上に道が1本あれば人はその上を歩くし、ホテルに到着し荷物を置いて腰掛けるとき、身体の向きはベンチに影響される。階段を後ろ向きで上ることもないし、空間の幅によって見通せるものは定まる。図面には身体に対して持っている強制力があること、やさしい言葉を使えばエスコートの意図が張り巡らされていることを再確認することができる。
この動きと連動した視界の変化は、アサヒビール大山崎山荘美術館の下り階段や、Boa Nova tea-houseのエントランスのように〈徐々に視界が閉じていく/開けていく〉など、人間を包み込む空間全体に影響する使われ方をすることもあれば、Tomba Brionの、手前の飾りと奥のスリットのように〈観る位置によって揃って/ずれて見えてくる〉ことで、身体の位置により細かな影響を及ぼすこともある。また、Church in Marco de Canavezesの祭壇の向こう側の〈観る位置にかかわらず見えない〉空間を構成する角や目地などのように、視線の届く範囲を制御することによって、建築物側を知り尽くせないものとして保つ、ということもあり得る。
身体の位置をさりげなく/強制的に定める建築物によって作られるのは、建築空間の立体的な造形に対する〈観察者の位置〉である。動きを伴う場合、移動していく〈観察者の位置〉は、空間を動くカメラワークの動線のようなものであった。続いては、この動線の中で、人がふと足を止めるような場面を想定するときについて考えてみる。もっともわかりやすく極端な例は、Villa Malaparteだ。この作者不詳のヴィラは、Jean-Luc Godardの映画に登場したこともあり名が知れており、容易に場所を知ることもできるが、敷地に向かう道は途中で、扉と有刺鉄線により閉ざされている。恐らく数多の人間がここまで来たのだろうという証拠に、インターネット上にはその扉の前から撮影された、一定の角度のVilla Malaparteの写真が並ぶ。ここでは、立ち入り禁止という強制力によって外観を見るための〈観察者の位置〉が限定され、逆説的にその建築を代表する外観のショットが決定されている。
多くの建築物においては、Villa Malaparteの例のような動線の行き詰まりとは無関係に、立体的な造形に対する気持ちのいい見えというものが存在する。これは、建築のファーストイメージが描かれたドローイングのように、設計者によって意図される場合もあるだろうし、偶然生まれる場合もあるだろう。また、外側から建築本体に向かう視線ではなく、景色を観る外側への視点場として設定される場合もある。いずれにせよ、つい足を止めて眺めてしまったり、カメラを取り出したくなるような場面についての話である。リサーチの図版を見ていくと、建築物のもつ象徴的な見えというものが、その建築のもつ平面・立面・断面形状という独立した形の問題である以上に、どこから眺め得ることができるか、というその土地の制限に関わる〈観察者の位置〉の問題であることが浮かび上がってくる。
例えば、スイスの山奥に建つCappella Santa Maria degli Angeliでは、山を登り入り口までまわり込んでいく道の途中で、山頂に突き刺さるような教会全貌の造形を真横から眺めやることができる。建築家、Mario Bottaがどんなにこの見えに拘り完璧な立面造形を作り上げたとしても、この道がなければこの見えに到達するものはいなくなるのだ。もう少し偶然に近いもので言えば、FirminyにあるUnitéd’Habitationの台形形状の列柱が挙げられる。この柱と柱が重なる見えは、三角形の空隙を作り出す。この空隙に丘の上で遊ぶ子供がボールを追って入り込んでくると、この三角形は、ユーモラスな光景を再生し出す窓として機能し始める。また、見通せたり覗き見たりできることばかりではない。パリの都市部に建つTafanel Logistics Hub and Officesは、長く長く続く三角形の連続屋根が特徴であるが、あまりの長さと都市部の道の狭さにより、どんなに身体を目一杯引いたとしても全貌を視界に収めることはできない。
このような事例から、建築において重要な問題は〈どのような形が存在するか〉ではなく、〈どのような形に対し、どの位置に立つことができるか〉であることが実感される。そしてこの先、空間を移動するカメラワークのような動いていく身体、また不意に足を止めシャッターを切るような静止する身体が、純粋なビデオ・カメラではなく、われわれの身体、曖昧な知覚を持つ〈人体〉であることが問題になっていく。
-
形と身体の位置の書き出しは、観る位置と角度の問題にとどまらない。このリサーチが単純なコンポジション以上の問題を含み得ることに一番初めに気がついたのは、ブリュッセルの町外れにあるKersten Geers David Van SeverenのDrying Hallに、車で近づいたときの体感である。この建築物は出荷前の植物を24時間乾燥させるための風通しのいい倉庫であり、白く閉ざされたような外観をしている。この倉庫の周囲をぐるりと周って内部に車のまま入り込み、内側の壁全面から外の景色を透かし見ることができた瞬間、一体どうして、と息を飲んだことを覚えている。知ってしまった今では単純な話であるが、風通しのために倉庫の壁は小さな穴が無数に空いた素材でできていて、走る車の中からは確認できなかったが、車を降りて近づけば、光が差し込む方に透けている理由も端的に理解できるというわけだ。
ここで、建築物からの身体の拘束方法に〈乗り物〉という可能性が足されると共に、〈視力〉という〈観察者の位置〉よりも、一歩人体側に踏み込んだ要因が取り上げられた。Azkuna Zentroaの多様なデザインの柱にひとつずつ近づいてみたくなってしまうことや、Insel Hombroich Museumの異様に遠く美術館本体がなかなか見えてこないアプローチも、視力と造形の問題になるのだろう。そして、視力の問題が細かいデザインに用いられているのが、集合住宅OFFICE 131の屋上にある柵である。この柵は、細い縦部材と少し太い横の部材で構成されており、その端部はすぱっと断ち落とされたような状態になっている。地上階から眺めるしかない住人以外の人々にとって、断ち落とされた柵は、密接する隣家の壁に接続しているように見えるのである。
また、Grundtvigs Kirkeの美しい全体造形が、近づいていくほどに異様なレンガのディテールとして現前することも、無関係ではないだろう。このとき〈観察者の位置〉が変わることによって起こるのは、単に見えていなかった細かい部分が見える/見えなくなる、ということ以上の、見え方の変化である。漠然とした空間の形、が、積み方のわかる煉瓦の集積へと瓦解していくこと。見る距離と視力によって変化するのは、空間から捉えられる意味の総量でもあるのである。〈見る距離と視力によって、空間から捉えられる意味の総量が変化する〉ここから派生していくのは、人間は見たものの意味を読み取る、という、目が紐づいている身体を含めた側面と、人間の視覚と距離の関係、視覚自体の性能という側面である。
前者は、建築のボキャブラリーとしてしばしば登場する。人は何かを見た瞬間にその対象を自動的に理解しようとする。自分の周囲で起きていることや、視界に入り始めたことを、秩序立て理解できるものに変換する。その精度は必ずしも正確なわけではないために、一瞬で受けた印象が実空間とは異なるものとなり、続けて体験する空間から意外な印象を受ける、というようなことも起きる。ここでの好例は、富山にあるミュゼふくおかカメラ館と、イタリアの海岸沿いに建つOscar Niemeyer Auditoriumである。円筒形がパッと目につくミュゼふくおかカメラ館は、その内部形状も同時に想像されてしまうような、明快な佇まいをしている。しかし、エントランスから内部に入ったときに見えるものは、想像していた円筒の内部ではなく、あるはずのない奥行き方向に伸びていく空間と中庭である。Oscar Niemeyer Auditoriumにおいても似たようなことが起きている。外観で特徴的なアーチ型の形状は、奥に見えるホールの空間の硝子に近づき沿っているように見える。しかし、裏手に周りそのアーチのなかに入り込んだとき、思いのほか広いその隙間から不意に海を見渡し、私たちは立ちすくむ。
一瞬で受けてしまう初期の印象、は、部材や素材の話と接続することもある。スイス、Plantahof Auditoriumの建築全体を支えているような部分。大阪に建つ住宅Tritonの、一見すると分厚い石に見えるファサード。空間体験ではっと立ちすくむこととはまた別の、意味により絡め取られるような足止めも、建築には起こり得る。
そして後者、人間の視覚と距離の関係は、意図的に設計へと活かされるというよりも、自然の摂理として起きていることだと考えられるが、顕著に現れているものとしては、パリに建つCinémathèque française、また、ローマ近郊の都市EURにあるPalazzo della CiviltàItalianaのことが思い出される。
Cinémathèque françaiseでは、大小さまざまな造形を施された搭状の空間が上に伸びており、それらを地上階から眺めやる天窓が作られている。この天窓から見える上の部分は、ほとんど垂直に建っているはずのものでありながら、中心部に向かって、ぎゅうと密集しているように見えてくる。遠くのものは小さく、近くのものは大きく見える。また、これは聞いた話だが、Hagia Sophiaの大空間の内部では、同時に視界に入る、人間の近くまで吊り下がる照明と遠い天井の動きの差異を観ることで、遠すぎる天井への妙な実感が湧くという。距離と大きさの問題は、距離と移動速度の問題でもある。
Palazzo della CiviltàItalianaで扱えるのは、距離と立体感の問題である。近づいてもかなり抽象的な造形を持つ建築物だが、不気味なまでの存在感を発揮するのは、都市を横断する道路沿いに遠く遠く離れたときである。道路の中心に見えるこの建築は、決してよれない紙をぺらりと置いたような、平面的で硬質な様相を帯びている。マッシブな造形が紙に姿を変えてしまうというのは一体どういうことなのか、を考えていくと『観察者の系譜−視覚空間の変容とモダニティ』(Jonathan Crary)、及び『造形芸術における形の問題』(Adolf von Hildebrand)のなかで度々触れられている、目と視覚対象の距離の問題まで遡ることができるだろう。
以上、建築と建築を観る身体の位置、というシンプルな記述方法から、観る位置、順番、角度、距離に留まらない、視力、見立て、判断、遠近法、移動速度、触知的な視覚と遠隔像、などという、さまざまな視覚の問題が立ち上がった。これは建築の、身体と世界の間に建つ触媒のような側面に着目して設計を行うための試論に向かう、足掛かりである。
-
リサーチ〈第一の部材としての身体〉で触れてきたのは、既に存在する建築物を注意深く観るための技法であった。つまりここでは、物質の実際の建て方を扱う設計者という立場以前に、観察者としての立場に立って調査をしていると言える。また、建築物は原則として実際の世界に建つものであるし、調査方法も〈実在のものを/実体験をもとに〉と限定していることから、ここまでで提示されているのは、自然の摂理に即した、ありのままの世界で起きている現象である。
観察から立ち現れる建築とはなんであるか。設計、という行為は、まだそこにないものの組み立てを定めることだと言える。そして、まだそこにないものを作り出すとき建築家は、その敷地と、そこに作られるであろうものに対する0人目の観察者であると捉えられる。いかになにもない敷地だとしても、現実の世界である以上は、完全になにもないということはない。建築を建てるということは、敷地と敷地の周囲に既にあるものを観察し、その中心にある空白に、身体と目を制限するような場を増やしていくことに他ならない。
ここで着目し始めたものが、映画、小説、漫画、アニメーションなどの〈なにもないところから世界を立ち上げる〉視覚文化の表現技法である。
なにもないところから始まる表現芸術において、描かれないものは存在しない。このとき古くから人は、現実に存在するものをいかに正確に書き写しとるか、ということに拘ってきた。表現芸術の発展の歴史をすべて追っていくにはあまりに力不足なのだが、例えば、カメラ・オブスキュラに関するJonathan Craryの記述、 ”視覚的=光学的基盤を理解していた者にとっては、この器具は、完全に透明に働いて、再現=表象(リプレゼンテーション)の光景を提供してくれるものだったし、原理に無知な者にとっては、それは幻覚=幻像(イリュージョン)の快楽を与えてくれるものであった。” これだけを見ても、現実世界の表象を取り出し切り離して観てみること、に価値が与えられていたことは明らかである。また、有名すぎる話だが、Eadweard Muybridgeの撮影した写真から、人々が走る馬の正確な形を初めて知ることができたことなども、身の周りの物事は技術の発展とともに徐々に把握されはじめ、真実に近づいていった、という流れが感じられる代表例だろう。
しかし、物語世界−必ずしも、物語(ストーリー)を伴うわけではない、作品世界−を作り上げようという欲望は、そのように現実の写しとしての精度を上げていくことだけに執着した訳ではなかった。ここから、現実を再現=表象するだけにとどまらない幻覚=幻像への欲望、正確さを欠いていたとしても魅力的な架空の世界を描き出すこと、への舵取りが始まる。この方向性の先には、3DCGなどを駆使したあたかも実在するような虚構を描き出す道も想像されるが、ここで注目していきたいのはそういった〈過保護〉な表現ではなく、観察者である受け手本人の身体に補われることによって完成する、物語世界の表現手法である。
例えば、建築に近しいものでいうと、現代アニメーションには、遠近法やイラストレーションに馴染んでいる私たちであれば容易に空間を認識することができる、簡潔な表現が多数見受けられる。なにもない場所、奥行きも動きもない場所に空間性を描き出すようなアニメーションの試みに関しては、( http://okuizumi-risako.tumblr.com/post/175221555384/奥行きなき世界の奥行き) にまとめている。また、フレームを固定し、その内部に描かれるキャラクターの大きさが変わることによって、キャラクターが接近していると思わせる漫画表現や、登場人物の顔が画面に近づくにつれ、睫毛など顔を構成する部分が仔細に描かれるゲームやアニメによく見られる手法などからも、現実の世界の見えを紙面や画面の中で再現=表象し、より効果的に感情を喚起させるような工夫を感じられる。また、より普遍的な、ふきだしやテロップ、ワイプなども、見慣れているから疑問を感じないというだけで、かなり独創的な、声や別空間の表象方法の確立であると見ることもできるだろう。これらに共通するのは、鑑賞する身体が、その表現物が前提とする規則をきちんと理解し、必要に応じて現実から関連項目を引き出し重ね合わせてくれるだろう、という、観察者の身体への素朴な信頼である。
忘れてはならない前提は、多くの視覚芸術が前提としている観察者の目の動きは、さほど自由で多岐に渡るものではないということである。観る距離によって像を正確に結ぶ絵画や、観る位置の差異により像を切り替えるレンチキュラーなど、わずかな身体の微動をその想定に含むものはあるが、基本的に視覚芸術は、動かずに対象を見つめる身体のことを、鑑賞者と呼んでいる。これは〈動かずにはいられない〉建築の鑑賞者とは大きく異なる。そのため、視覚芸術の中から見つかった技法は〈物語世界で自由に動くことのできない〉鑑賞者が〈実在しない〉虚構を見出していくこと、つまり、こう描かれたものはこう見えるはずだ、という視覚の仕組みの側からの逆引きにより、虚構の世界が構築されていくというわけだ。このとき、人間の身体こそが、見知った現実世界の情報を適度に虚構世界に照射して、描かれた世界を立ち上げていくための装置となっている。
よって、視覚芸術を観る身体と、表現されている虚構のバリエーションを見ていくことは、人間の知能の中で行われる処理の構造を知ることに繋がる。しかし、ここで建築との大きな差異として立ち現れるのは、観ている身体が動かない、ということだけではなく、観ている身体が、その身体が誰であれその鑑賞がいつであれ、ある一つの点/シーンごとに切り替わる一つの視点に固定されているということである。映画館の座席は、その位置によって異なる鑑賞体験を期待させるものではない。受け手の性格・感情・その日の気分など不確定な要素が鑑賞体験に影響を及ぼすことや、ある一つの作品が人によって異なる受け取られ方をすることはあれど、視点の位置は固定されているのだ。それにより起こるのは安全圏にいる鑑賞者の特権化であり、それ以前に立ちはだかる作者の特権化でもある。鑑賞者は与えられるままに、安全な場所から目の前で起こることを享受し、飽きたら消してしまうということができるし、作品に目を留めている以上は、その目の位置を定めているのは作者である。
さて、建築の場合も、ある程度の身体の位置は設計者により定められており、その範囲の中で鑑賞者は自由に動き回ることができた。このことだけを考えると、あらゆる視覚芸術と比べて、建築はもっとも自由で能動的なものであると言えるような気がしてくる。けれども実際には〈鑑賞物〉と対象を括った時点で、私の身体とは無関係な鑑賞対象、見る−見られるという二項の向こう側に対象を当てはめてしまうものであり、身に迫る鑑賞、自分の身体にまで影響を与えてくる鑑賞というものは難しい。
もっと言えば、建築は〈鑑賞物〉として享受されているのだろうか、という疑問すら湧く。建築を観る、という意識は、本来建築を観に行くのが好きな人だけが使う言葉だ。一般的に建築というのは、生活のために必要で、機能に合わせてその場の雰囲気に寄与することもある〈道具〉であると捉えるのが妥当だろう。あるいは、広義の建築…屋外広場や、東屋の屋根、そのような漠然とした建物未満のものも含めて考えると、建築というのは床があり、そこに立つことができ、ときに屋根や壁があって風や雨から身が守られる、というような、生まれたときから親しんでいる世界そのものと同じ見えをしている、というべきかもしれない。いずれにせよ、建築を観はじめた、建築を観終わった、などという判断を下すことは、実生活においてほとんどないものだと考えた方がいいのだろう。建築は〈世界〉と〈生活〉のあいだで透明化している。
以上のことから、鑑賞している身体とその鑑賞物(あるいは、身体とその視界に入っている物)は、それが実空間にせよ物語世界にせよ、その関わりが意識されにくいものだと言える。鑑賞物は、人間の知覚能力に半分乗り上げるようにして立ち現れているというのに。
-
ここから、視覚文化に対するリサーチは、漠然とした鑑賞者に対する工夫を集めるものから、無自覚のうちに、観る側、という立場に安堵しきった鑑賞者を揺さぶる可能性のある表現を探る試みへと変わった。その取っかかりとなった、安全圏を脅かされることに関するテキストは( http://okuizumi-risako.tumblr.com/post/175562702374/観客の安全圏) であり、ここでは、パフォーマンスアートのように見られる身体が現前する例からはじめ、どちらかというと映像の中のものごとを自分ごととして受け取れるような、感情移入に近い問題を扱っている。ただ、感情移入の問題は〈現前する事象が自分のいる世界線とは切り離されている〉という前提のもとに、それでも入り込んでしまうものとして有効なのである。目の前の現象も、全て現実の出来事であるのが当たり前である建築の場合、この話はあまり有効だとは言えない。
ここで思い出しておきたいのは、”〈私〉と同時に、横に並んで入った〈あなた〉の目に展開する建築空間は、また少しだけ角度の違うものになるはずである” という、この文章の序盤で確認をした事実である。建築において特筆すべきことは、その空間を体験しているのはあなたひとりではなく、同時に体験しているいくつもの身体があること。そして、その身体たちにはそれぞれ、空間を立ち現せる知覚の能力があり、その身体は別々の角度から空間に対面しているということである。
視覚文化のうち、鑑賞者に影響を及ぼすような表現を探っていくと、このような、異なる水準に属する��・物たちがその階層を明らかにするような表現に出会うことがある。例えば、クロアチアの現代アニメーション作家による『Technement』では、SFのようなテイストで描かれた登場人物たちが物語を進めていくのだが、最後のシーンで不意に、鳥のような女性のようなかたちをしたキャラクターが、画面に向けて手を広げ、画面(あるいは、光景を記録していたカメラ)を覆い隠す、という出来事が起こる。そのとき私たちが直面するのは、油断しきって画面を見つめていた自分の存在が、登場人物たちにずっと前から勘付かれていたかのような気まずさであるが、これは、画面のなかの登場人物たちに、私たちと同等の知覚の能力を認める瞬間、ということでもある。私たちの娯楽のために、台詞や振る舞いを徹底し、物語を遂行しているかのように見えた身体が、〈知覚する身体〉であったことを知る、という話である。
このような、作品世界の側が、その作品を成り立たせる仕組み自体に自覚的になるような表現は、小説の1ジャンルとして始まったメタフィクションや、自己言及型芸術などと呼ばれるジャンルに属している。
鑑賞している自分以外の身体に知覚能力を認めること、作品世界を閉じたものとして捉えずに、鑑賞者の世界と地続きのものとして扱うこと。それを意識したときから、こうした工夫のある作品を収集し、建築の問題と関係して考える可能性を検討し始めた。今までに述べたような、鑑賞者の目への映り方に自覚的な表現であり、複数の階層の知覚する身体を扱っている、ということに加えて、多くの自己言及型芸術が、普段は見えていない仕組みを可視化してしまう工夫である、という点も可能性を見出した理由である。
例えば、先ほど取り上げたアニメーション『Technement』においては、独立しているように見えた作品世界を覗き込んでいたカメラが、最後に姿を現した、と考えることもできる。アニメーション『カモにされたカモ〈Duck Amuck〉』、Lucio Fontanaによる『空間概念 〈Concetto spaziale〉』、手塚治虫の『ビッグX』などの例を通すと、このイメージをより明確に伝えることができるだろう。これらの作品の当該の場面において作品は、キャラクターの動きや、色彩や、表情や意味内容から、鑑賞者の気を逸らせるような要素を持っている。『カモにされたカモ〈Duck Amuck〉』におけるその場面は、画面の中でユーモラスに動きながら台詞を言っていたダフィーダックが、その身体が描かれたフィルムごと上にずれ込んでいってしまうというものであり、『ビッグX』においては、漫画のキャラクターが作者・手塚治虫に、気を失ったキャラクターの目を開かせるよう懇願し、作者のペンが登場してそれを描き直す、という表現である。また、『空間概念 〈Concetto spaziale〉』は、絵画であるため性格は異なるが、絵画において前提となっているキャンバスそれ自体を切り裂く、という革新的なシリーズを指す。ここで一般的に鑑賞対象とされている〈内容〉と呼ばれるような要素から、私たちの意識が移る先は、動きを生み出しているフィルム・漫画を描いている作者・前提となっているキャンバスであり、これらは普段、アニメーションや漫画、絵画などを鑑賞するときには、ジャンルを成り立たせる〈形式〉として、透明化されているものだと言える。
-
建築は〈世界〉と〈生活〉のあいだで透明化している、と先ほど記述した。ここで、他の芸術における〈形式〉/〈内容〉と、建築におけるそれを比べてみると、建築において〈形式〉は生まれたときから親しんでいる世界そのものであり、〈内容〉は生活のために必要で、機能に合わせてその場の雰囲気に寄与することもある道具的な側面である、と当てはめて考えることができる。
あらゆる形式をもつ芸術において、メタフィクションは、前提を盲目的に信頼する我々を軽やかに欺く態度、あるいは、形式すらも物ともしない果敢な表現である。ただ、その形式が世界そのものと一致する存在であった場合− その形式にまとわりつく制約が、紙の大きさでも、ビデオテープの録画可能時間でも、美術館の搬入口の大きさでもなく、この世界の重力や光や影、風が吹くことや、雨が空から降ること、それから使い慣れたこの身体のことであった場合− メタフィクションは、生活に塗れ透明化している都市を、空間を、もう一度見つめるための表現となる、と、言い切ってみることもできるだろう。
建築における透明さ、〈形式〉としての透明さは、他の芸術と同じく、そこにあることが前提となりあえて気にする必要がない物事のことだ。その代表格として、1つめのリサーチで述べていたような、次々と露わになる視覚の問題、身体にかかっている制約、また、知識や経験があるからこそ自動的にできてしまう判断などの、鑑賞する〈私〉自身の身体の性能があるのである。そして、もう一つ意識から消えているものは、慣れ親しんだ自然の摂理そのものだと言えるだろう。透明化しているそれら二つの要素は、冒頭で掲げたフリップブックと建築の、数少ない相違点でもあると言えよう。
-
以上のことを踏まえて、リサーチ〈第一の部材としての身体〉と視覚文化についてのリサーチをベースに、実空間の中で、各人物が固有に持っている知覚が、不意に隣接したり遠く離れたりするようなことを起こし得る設計の技法を探っていく。つまり、視覚文化のリサーチを建築にそのまま転用するのではなく、透明さを可視化する表現として参考にした上で、あくまでも現実世界での現象を基準に考え、複数の階層の接し方・離れ方の図式としての転用可能性を検討する、ということである。
設計には2つのフェーズがあり、2つめのフェーズは、現在ようやく手法が定まったという状態である。まずは、1つめのフェーズ、都市の中で透明化しているものを見出すことや、複数の〈知覚する身体〉の関係を描き出すことに着目し、具体的な敷地を設定して行った4つの設計の実験について記していく。
-
敷地は具体的な場所である必要があった。なぜならこの制作は、現実世界に建つ〈建築〉の問題を扱うものであるからだ。メタフィクションは、鑑賞者と作者の間にフィクションをまず描きだし、それを共有してから始まるものである。この制作において、作者の頭の中で作られた敷地や抽象的な敷地から考え始めてしまっては、他の作品世界のメタフィクションのコピーとなってしまい〈建築〉を考えることにはならない。
よって、フェーズ1の設計はすべて、都市の中に既に存在する公共空間や空き地を足がかりに行なわれるものとなった。
敷地は、目黒川沿い、及び山手線目黒恵比寿間の線路沿いから選び出した。それぞれ、既存部分の形状や環境など、よく見ているとどこか引っかかりのある場所、を理由として選んでいるが、ここで川や線路など視界の抜けが目立つ敷地ばかりが揃ったことには、身体の位置によって視界の到達範囲が大きく変わるような場所を選ぼうという意思が働いていたのだろうと考えられる。また、小さな実験の場として公共空間に取り付くような形式をとることに関しては、1から10まで自分で作り出し完全なフィクションになってしまうことを避けようという意図でもある。
1つめの敷地は、目黒区目黒1丁目付近の交差点、橋上道路の上から見える、向かい合うビルに挟まれた川とその周辺道路である。この土地には、東から西陽が射している。そういうと嘘か出鱈目のように聞こえるのだが、実際には、西に向いた大きなガラス窓が連なるファサードに光が反射し、反対側のアパートの東側立面を照らし出している、というわけである。この、ふたつの太陽がある状態だとも言える場所に、橋をかけ、その橋の上にベンチを並べる計画を立てる。橋は、橋上道路へと向かう川沿いの坂道の下部分の構造体、アーチ状になっている空間への出入りを可能にする。この空間は、反射した光が当たるため草が生い茂り、整備すれば都市から不意に離れた休憩所になりそうだが、現在はアクセスする方法がないために放置されているのだ。ここで注目すべきところは、川の流れる方向と西陽の射す方角が、垂直に交わってはいないという点である。そのため、反射を起こすビルと光を受けるビルの間には、a.西陽だけが射す空間/ b.西陽と反射光、ふたつの光が当たる空間/ c.西陽はビルによって阻まれ、反射光だけが当たる空間 の3つのゾーンが存在することになる。これにより、均等に並んだベンチは、東側・両側・西側へと、リズミカルな影を落とす。この場所に人が増えていくと、その人々もそれぞれ、立つ場所によってさまざまな方向へ影を落としていくことになる。橋の上から眺める人々の中には、自然光しかないはずの屋外空間に複数の影が落ちていることに、ふと足を止める人もいるかもしれない。
2つめの敷地はこの橋上道路の反対側、道路へと上がる階段と坂道、及び橋上道路の欄干である。川沿いの道路は標高5m、橋上道路は10mであり、道路の上に出るには西側の上り坂か、東側の階段を上がることになる。ここで考えていたのは、人は、自分の身体が直面している以外の知覚を想像できるのかということ、近くて遠い別の場所と、関係を持つことはできるのだろうか、ということである。ここでは、東側の川沿いの道と階段横の手すり、そして橋上道路の欄干の形状を変え、その一部を広場とする計画をした。東側の川沿いの道の傾斜は非常にゆるく、ここを歩く人は、対岸の上り坂を上がっていく人の身体の上昇をずっと横目に見ながら、最後の最後に階段を駆け上がり追いつく、という形式を持つ。しかし、15mを越える川幅を隔ててそれを意識することは少ない。そこで、傾斜の少ない地面の手摺を外し、対岸の斜面と同じ角度を持つ斜めの壁を建てる。この斜めの壁にはスリット状の窓をいれ、道を歩く身体が、向こう岸で上がっていく斜面を意識に留めながら見え隠れするように設計する。西側から眺めるとこの水平窓は、東側の道を歩く人が徐々に見えてきて、その身体が川を難なく覗き込めるようになった次の瞬間、急に駆け上り、足だけが見える、という状態を映し出すのだ。また、橋上道路の欄干は、道路へと向かう斜面を歩く身体の角度と同様に傾ける。この細かい操作によって、斜面を平行に見下ろす道路の上の身体と、斜面を登っていく人から見て、奥行きの見え方がずっと変わらない開口部分ができるのである。手摺、欄干の形が変わることにより、両岸とそれを繋ぐ橋上道路の上の身体たちは、別の場所を眺め、意識することになる。
3つめの敷地は、目黒川を北へと遡り、目黒区民センターの2階部分と対岸を繋げる大規模なタイル貼りの橋である。橋の上のタイルは9cm角で、1cmの目地によって繋げられ、橋の床一面を埋めている。この橋の階下には、川沿いの道がある。現状では、対岸に渡るには一度川沿いの道から上がり、2階のレベルまで上がってから再び降りるという動線になっている。ここでは川沿いの道同士を繋ぐ地面を、この橋の下に計画する。着目するのは、人の視点から見た足元のタイルの大きさである。通常、成人の目は、地面からおよそ140-170cmのところについており、距離を隔てるほどに視界に映るものは小さく見えていく。そのため、タイルの大きさが9cmであると頭で理解していても、その大きさがありのまま9cmに見えているわけではない。ここで、既存の橋の欄干をやや外側に付け替えるとともに、広い橋の床面に吹き抜けを空けて、計画する階下の橋の床面を見通せるようにする。そして、階下の橋の床面には、既存の橋から見通したときに9cmのタイルと同じ大きさに見えるように、サイズの大きなタイルを敷いていく。既存の橋から階下の橋の床面までの距離は4.7m、この距離を隔てて9cmに見える正方形は、一辺が40cmのものとなる。また、1cmだった目地は、5cmにまで広がる。スケールの問題を扱うことにより、5cmの目地をもつタイル貼りの床、という不自然なディテールが生まれていく。上から見下ろす人々は同じ大きさに見える床にすぐさま疑問を抱かないかもしれないが、階下で人が滞在しているのを見るとき、その人と、人が立つ地面のグリッドの大きさのバランスに、疑問を抱くかもしれない。
また、このとき、追加で行う操作として、人間の目に近い手すり子の上面の正方形を、それぞれの床面のタイルと同じ大きさに見えるように設計していく。そうすることで、同じ高さに手摺を設定しているのにも関わらず、既存の橋では20mm角、階下の計画部分では75mm角と、手摺の有り様が変化し、掴んだ時の印象にも差異ができるのである。
余談ではあるが、既存の橋に空ける吹き抜けの位置は、橋の上にもともとある二股に分かれた街灯の、低い方の光の下を基準にしている。都市の中の街灯の形状は逐一着目するものではないが、高さの違う光源の片方が階下のための照明に見えたとき、街灯の存在感は少しだけ後押しされることだろう。
最後に、4つめの敷地は、目黒川沿いからは離れ、山手線の線路沿いにある一つ���空き地である。ここは、線路を越える橋上道路から覗き込める位置にあり、線路からおよそ3m上/橋上道路からおよそ3m下、というレベル差を持つ土地で、山手線が平均3分に1度は通過するために、3分に一度は振動している土地であるとも言える。敷地の手前にはバス停があり、現状では、バス停のすぐ後ろにある簡易フェンスとロープにより仕切られた穴、という様相をしていて、土地を見学するための簡易階段が階下まで取り付けられている。この土地を線路から区切るコンクリートの擁壁は、分厚く安定したものだと言える。この擁壁の内部を掘り込んで地下空間を作り、100角の鉄骨で組んだ華奢な構造体で屋根をかけることによって、電車による振動を可視化するような建築物を計画できないかと考えた。建築物は2階建てとし、1階部分は、擁壁によって堅く守られた地下空間、そして二階部分は、バス停を待つ人が休憩に気楽に降りていけるような、橋上道路から階段4段分ほど下がった半屋外空間とする。そして、2階部分の床にはグリッド状に6cmの孔を空け、天井梁から階下へと続くランプを吊るしていく。最大で8mほどに及ぶ紐で吊られたランプは、電車の振動を屋根が拾う時、暗い地下空間を緩やかに動きながら照らすことになる。通常、人は、地面が不意に揺���たとしても、その揺れ自体を見ずにすぐその原因に思いを馳せてしまう。都市の振動は直裁的に、車や電車の存在、あるいは災害を意味するものであった。ここでは、観る対象となっていない揺れそのものを、ただ観測する、という経験を作り出している。
また、副産物とも言える地上階の部分は、わずかな柱を除き、天井から吊られる華奢な紐と椅子のみで構成された空間となる。人の身体がこの紐に不意に触れるとき、その衝突は、また階下の暗がりに影響を与えることになる。
-
これらの設計はそれぞれ、知覚する身体が都市のなかでなにを観るか、なにに気がつくのか、ということを意図しているが、その実験的な性格ゆえに、具体的な建築の計画として提示するにはあまりに局所的であり、テーマがひとつに絞り込まれすぎているような感覚を覚える。これらの設計で起きたこと、具体的な実感を持って示せそうなこと、というのを基に、空間構成の問題として、より複雑な内部空間の作り方を実践してみたいと考える。ここからが、フェーズ2に向かう試論である。
また、ここで自覚すべきことは、各設計物が、自ら人の知覚に訴えかけるような要素を持つために “作者が気づき、鑑賞者が未だ気づいていないことに気づかせる” という、押し付けがましい性格を帯びてしまうことへの危険性である。この特権的な、全てを把握している作者の立場、とでも言えるようなものは、多くのメタフィクション作品が陥っている “結局のところ作者の手のうちであるのだ” という興ざめにも繋がるものであるし、建築が訪れる身体によって再生され立ち現れる、という、理想とする体験の快楽から離れてしまうものである。このメタフィクションのマンネリ化と、ではそこで、鑑賞者が能動的であるためにはどのようなあり方があるか、という問いの投げかけは『あなたは今、この文章を読んでいる』(佐々木敦)の中心を担うテーマでもある。
この本の序章で佐々木敦は〈メタフィクションの問題〉という見出しのついた章の中で、どんなに複雑に仕掛けられたメタフィクション作品にも、その外延には常に現実の作者がいるという事実と、その〈作者の実在〉という事実こそが担保になって、読者が様々な仕掛けを安心して享受することができる、という実状に触れている。そして、この提起に続く一説は、建築のメタフィクションを考える上での大きな問題を提示してくれているとも言える。
”「メタフィクション」の「仕掛け」とは、じつは「作者」と「読者」が暗黙に協力し合いながら行う演戯のようなものである。そして、この「演戯」は、それがどれほどリアルに感じられたとしても、やはり本物の「現実」とは断絶した、つまりは誰かが造った絵空事なのであり、そうでしかないという事実性をあらかじめ/どこまでも保証されている。つまり、「メタフィクション」こそは「フィクション」が本来的に有する安全無害さを強調するものなのだ。”
設計において、鑑賞者よりも先に設計者がその内実を知る、という順番は、逆転し得ないものだ。ただ、ひとつの設計物において、 “作者が気づき、鑑賞者が未だ気づいていないことに気づかせる”という性格が出てしまうと、いかにその設計物が見えていないものを見せる効能や興味深い要素を持っていたとしても、ある単一の目的のための〈装置〉になってしまう。そのとき建築は、世界の複雑さのほんの1要素だけを提示する、作者から与えられた安全無害なフィクションに成り下がるのだ。
『あなたは今、この文章を読んでいる』の副題は、『パラフィクションの誕生』である。この〈パラフィクション〉という考え方は、本文章のはじめの方で触れたフリップブック、鑑賞者がいることによって生まれ出でる動きの創出、という話と通じるものがある。”ある小説は作者以外の誰かに読まれた時にはじめて実在する。そうでない場合、それはいわば存在はしていても実在はしていないのだ。” という言い切りは、まさに鑑賞者と鑑賞物が接したところから体験が立ち上がる、物は物だけで実在するのではなく〈知覚する身体〉に受け取られてはじめて動き出す、という態度である。そして、この問題に最も差し迫るのが、作家・円城塔の技法に触れながら展開する〈README〉の章である。
”「README」は際立って特殊であると言える。「README」というアルファベット六文字それ自体にかんして見るならば、それは常に既に読まれているからだ。「私を読みなさい」と読んだ時、私はもうそれを読み終わっている。まさしく自己回帰的な行為遂行文。このような意味で「README」と完全に同じ次元にある同様の指令文は他には存在していない。ある文章を読んでいる時、私たちがしているのはそれを読んでいることである/でしかないのだから。”
この、「README」という一つの理想形、これは、行為と指令の不可分で同時間的な一致である。この六文字は確かに人間に対する乱暴なまでの強制力を持つのだが、ここで起こっているのは、作者の押し付けがましい意図ではなく、もっと大きな〈そうなってしまう他はない〉システムの動きによって、鑑賞者の身体が動かされている現象だ。
文字を見るときほど素早く確実なわけではないが、現実を生きる〈知覚する身体〉は視界に入ったものを、自動的に確実に処理していくという事実を、私たちは信用すべきである。これもまた、作者だとか鑑賞者だとかという区分を越えた、大きな自然の摂理である。見なさい、と誰かに命じられているわけではなくても、目は周りを見て、自動的に理解していく。設計はやはり、ただ何もない場所を分割していくことであるし、そうしてできる空間には、更の敷地よりも多くのピントの受け皿があり、見える/見えない、という問題が大量に発生する。そして小説と異なり、実空間においては、鑑賞者は同時に複数のところに存在し、それぞれの〈知覚する身体〉に対して、身体の可動範囲/目の可動範囲を持つ。この、身体と目それぞれの可動範囲を持つ複数の〈知覚する身体〉を考えていくということに、この知覚を扱う試論を、空間構成の問題へと接続する鍵があると考える。
-
“ 二十七階分の距離を隔てた場所で、信号待ちをしている人たちがいて、いちばん先頭にいる女の人が、こっちを見上げているように見えた。一時間くらい前、同じ場所にわたしが立っていて、同じようにこのビルを見上げていた。(…)一時間前、そこには、交差点を見上げているわたしを見下ろしている人がいたかもしれない ”
−柴崎友香『寝ても覚めても』
この小説のさりげない一節が感じさせるのは、人物の移動とそれに伴う時間であり、空間が身体に与える制限の範囲で、〈私〉の位置は、別の身体の位置と交換可能であることの証明である。また、建築を一望し、全てをひとたびに把握することは原理上不可能であるため、少し過去である〈私〉と少し未来にいるところの〈私〉という、時間を隔てた同一人物同士の関係も見出せる。ある1本の柱をぐるりと周って把握するだけのことだとしても、その柱の裏側については、1秒前にそこを見ていた〈私〉の知覚と協力し合うしかないからである。
さらにここでは、二十七階分、という、身体が自力で移動するにはあまりにも遠い距離が、視覚によって容易に飛び越えられていることも示されている。小説の文章の中では軽やかな時間を感じさせるこの記述だが、現実の世界で想像してみると、信号待ちをしている人たちのいちばん先頭にいる女の人にとっては、この窓枠は、ぺたりとひらべったい遠隔像であるし、二十七階から見下ろす〈私〉にとっては、窓枠は質感も厚みも確かにそこにある窓枠そのものなのである。遠隔像と触知的な知覚の転倒、過去と未来の自分の身体も含む、他者との視覚範囲の交わり。複数の〈知覚する身体〉が、効果的に空間を立ち上げていくこととは、交換可能な身体と視覚の可動範囲が、重なったり離れたり、線引きされたりすることだろう。このとき、身体も目も、作者の意図によってある一点に誘導されるのではなく、切り替わり交換されていく前提として扱われ始める。
この前提を付加した上で、1つめのフェーズで行なったような透明化している人体と自然の仕組みを探る空間の構成を、立体的に展開していく。このとき、勿論、空間の各場所にいる身体から、そのとき見えるものを扱っていくのだが、2つめのフェーズでは、見せるべき限定したものを示すのではなく、敷地の各場所から認識できる身体の可動範囲〈身体のための敷地〉と、視線の可動範囲〈視覚のための敷地〉両方を別のものとして分け、すべてプロットし、取りこぼすことなく扱っていく。〈視覚のための敷地〉は、敷地境界線の範囲内に収まっているとは限らない。開口部などを通して視線が建築物を通り抜けるとき、隣家の壁までを、川の向こうの岸壁までを、無限遠とも言える空までを、〈視覚のための敷地〉の内部として扱うことができるからである。また〈視覚のための敷地〉は身体を越えて自由に拡張されるように見えて、簡単に阻まれ失われてしまうものでもある。なぜなら、ある更地の中央に柱がたった一本建てられただけで〈視覚のための敷地〉には把握できない空隙が生まれてしまい、その土地をぐるぐる歩こうにも、その空隙は方角を変えて残り続けるからだ。
ある敷地を設定したとき、あらかじめその周囲を囲んでいる隣家や周辺の構築物が〈視覚のための敷地〉の臨界線となるわけだが、どの構築物が臨界線としての役目を担うのかは、観察する身体の位置との関係による。同一平面上での〈視覚のための敷地〉の範囲は、計画される壁と開口部によって定められていくが、ここで最も広範囲の〈視覚のための敷地〉に影響するものは、観察する身体が立っている地面のレベルである。例えば地面から高さ2200を越えると、一般的なコンクリートブロック塀は視線を阻まなくなる。一軒家の高さを越えると視線の広がる範囲はさらに増え、遠くの団地が臨界線として登場する。さらに団地の高さも越えると、ほとんどの屋根は飛び越えるが、遠くのゴミ処理場の塔にはぶつかるかもしれないし、遠近法により縮んだ塔は、視線の衝突を免れるかもしれない。鑑賞者の視覚は〈身体のための敷地〉に制御された上で、任意の〈視覚のための敷地〉を体感するというわけである。
以上を踏まえて2つめの設計実験では、壁や柱を1枚建てるごとにこの2種類の敷地をプロットし、各箇所にいる〈知覚する身体〉のもつ〈視覚のための敷地〉の重なり合いや、見える範囲と距離の変化による認識の変化を取り扱っていく。こうしていくことで初めて、建築空間のもつ、人の身体の位置を規定しながら、人の視覚の中に動きとして立ち現れてくる側面や、知ってしまっても何度でももう一度見ることができるという性格を、設計手法のプロセスの中で取り扱うことに近づけるのではないか。
〈どのような形に対し、どの位置に立つことができ、どこまでのものが、どう見えるのか〉 これは余りに当たり前のことにも感じられるが、誠実に扱い切れる問題だとは到底思えないのである。よって、引き続き試してみたいと思う。
8 notes
·
View notes
Photo

ぺぱぷんたす006号の発売を記念して、『ぺぱぷんたす』×福永紙工Presents「紙となかよくなる夏休み」~かみの すきなこ、あつまれ~ 8月1日(月)~8月31日(火)まで、立川GREEN SPRINGSの「SUPER PAPER MARKET」にて開催中! 発売になった『ぺぱぷんたす』の最新号はもちろん、ぺぱぷんたすゆかりのアーティストのグッズも販売。『ぺぱぷんたす』の世界を体感していただけます。 期間中は、随時「ぺぱぷんたす」のかみあそびミニワークショップ(たくさんの種類をご用意しているので、気に入ったものを選べます)を開催するとともに、ぺぱぷんたす参加アーティストによるワークショップも開催! トップバッターは、すでにTwitterでも話題になっているレンチキュラー天野さんによる「ふしぎなレンチキュラーの世界」 細かい凹凸のあるレンチキュラーのレンズを使うと、見えないものが 見えたり、動いたり、色や形が変わったり…あっと驚くふしぎなことが起こります。このレンズを使った魔法のような遊びを、レンチキュラー天野さんと一緒に楽しみながら、最後は、特製レンチキュラー台紙と紙を使って、自分だけのふしぎな絵を制作します。 【ワークショップ概要】※要予約。但し、定員に満たない場合は、当日参加可能。 日時:8月7日(日) 1回目 11:00-12:30 2回目 14:00-15:30 定員:各回20名 参加費:1800円 対象年齢:はさみの使えるお子さま~ 制作した絵や、レンチキュラーレンズはお持ち帰りいただけます。内緒のお土産付き。 参加希望の方は @paperpuntas ページのプロフィールの下にあるURL→ぺぱぷんたすサイト→イベントのバナーよりお申し込みください。 https://greensprings.jp/shop/super_paper_market/shop_news/4568/ ※ワークショップにご参加の際は、マスクの着用をお願いいたします。 ※状況によりやむを得ずイベント内容を変更、または中止する場合がありますので予めご了承ください。 <イベント概要> 『ぺぱぷんたす』×福永紙工 Presents「紙となかよくなる夏休み かみの すきなこ、あつまれ~!」 会期 :8月1日(月)-30日(火) 営業時間 :11:00-19:00 ※最終日は18:00まで 場所 :SUPER PAPER MARKET 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E2 209 (2Fフロア) <参加アーティスト> #石川将也 #小川かなこ #オグロエリ #かこさとし #きくちちき #北澤平祐 #COCHAE #五味太郎 #ザ・キャビンカンパニー #七字由布 #junaida #鈴木のりたけ #せなけいこ #祖父江慎 #竹井晴日 #太公良 #谷端実 #玉川桜 #tupera tupera #中村至男 #中山信一 #西淑 #原田郁子 #100%ORANGE #ひろせべに #pink pepper( #脇田あすか ・ #栗原あずさ) #fancomi #布川愛子 #Bob Foundation #Murgraph #マグネット( #高橋鴻介 ・ #和田夏実 ・ #たばたはやと ) #マメイケダ #三澤遥 +#三澤デザイン研究室 #三谷純 #ミナ ペルホネン #ミロコマチコ #明和電機 #レンチキュラー天野 #ぺぱぷんたす #superpapermarket #原田郁子 https://www.instagram.com/p/Cgsl4vtP9r6/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#中村至男#中山信一#西淑#原田郁子#100#ひろせべに#pink#脇田あすか#栗原あずさ#fancomi#布川愛子#bob#murgraph#マグネット#高橋鴻介#和田夏実#たばたはやと#マメイケダ#三澤遥#三澤デザイン研究室#三谷純#ミナ#ミロコマチコ#明和電機#レンチキュラー天野#ぺぱぷんたす#superpapermarket
0 notes