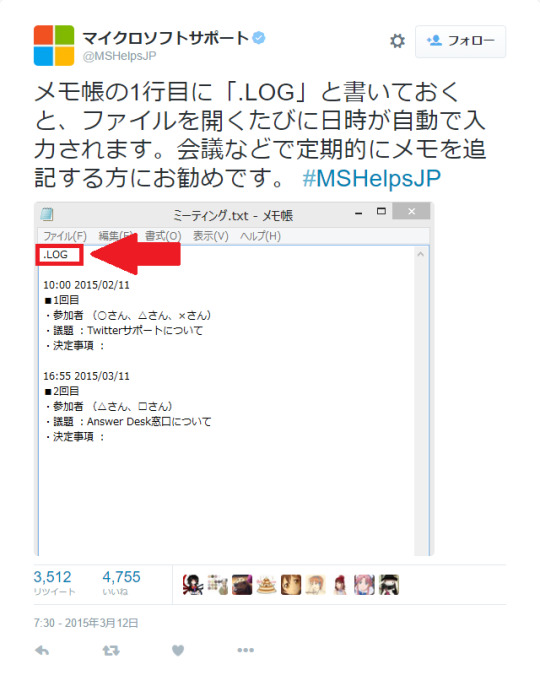Quote
本を読む時間がない日々忙しい人のために、ロングセラー、ベストセラー、話題の本etc…ダ・ヴィンチニュース独自の視点で選書した名著を紹介する本連載。第6回目は特別編として、「スピード狂」の外資系マネージャーとして知られる日本IBMシニア・プロジェクト・マネージャーの木部智之さんにインタビュー。著書『仕事が速い人は「見えないところ」で何をしているのか?』(KADOKAWA)も好評の木部さんに、仕事が遅い人に読んで実践してほしい5冊を紹介いただいた。
■『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣』
(ケリー・グリーソン:著、楡井浩一:訳/PHP研究所)
■『先延ばしにしない技術』
(イ・ミンギュ:著、吉川南:訳/サンマーク出版)
■『1分間マネージャーの時間管理』
(ケン・ブランチャード、ウィリアム・オンケンJr、ハル・バローズ/パンローリング)
■『アメリカ海軍に学ぶ最強チームのつくり方 一人ひとりの能力を100%高めるマネジメント術』
(マイケル アブラショフ:著、吉越浩一郎:訳/三笠書房)
■『考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則』
(バーバラ ミント:著、山崎康司:訳/ダイヤモンド社)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
勉強は学校を卒業しても続けざるを得ないんだよなぁ
http://ddnavi.com/news/356201/
2 notes
·
View notes
Quote
298 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2017/01/31(火) 01:25:48.03 ID:xdopAmTs0息子の小学校時代の担任がいじめを無くす能力に長けた人だったな。・あだ名禁止・席替えは児童の意見を一切聞かないこれだけで相当抑止できる。いじめる子はほとんど家庭に問題があるって言ってた。問題と言っても大きな事じゃなく、上の子が受験とか下の子が幼いとかで構ってもらえない子が多いらしい。そういう子は親に対して「1日10分でいいから話を聞いてやれ」と指導したりクラスの懇親会で子供の話をよく聞いている親に発言させて「うちはその話を知らない」と自覚させる。一方でいじめる子はポジションを確立しようとして、いじめを始める傾向にあるからクラスの中ではあえて孤立させるようにする。そうすると孤立する恐怖から周りに取り入ろうとして協調しようとする。それでも駄目ならクラスや全校集会の場で些細な事で叱りつけて威厳を失墜させる。弱い子を強くしたりフォローするのではなく強い子を弱くしてしまう方法
息子の小学校時代の担任がいじめを無くす能力に長けた人だったな 続・妄想的日常 (via onibi-onibi)
2K notes
·
View notes
Quote
大学に入って、はじめてまともな体育の授業を受けた。入学生全員に運動能力テストなるものを課し、その結果が一定レベルに達しない学生には、『トレーニング』なる恐ろしげなクラスを受講させるのだ。
このトレーニング・クラスは、わたしがそれまで受けた中で別格、いや、次元が違うくらい、まともな体育の授業だった。まず、教師の説明が科学的だった。トレーニングの内容は、小さなダンベル(重量がkgで表示されている)をつかったウェイト・トレーニングに始まり、ついで全身を使うサーキット・トレーニングが加わる。学生は各人、硬い紙のスコアカードが渡される。それに毎回、自分のスコアを記録して行く。たとえば右手にダンベルを持ち、右肩の上において、肘を伸ばして持ち上げる。その単純な、要素的な運動を、何回やれるか記入していく。
教師のインストラクションは、こうだった。「もし君らが、8回未満しかその運動ができなかったら、それは負荷が重すぎるのだ。そのときは、1kg軽いウェイトを使え。また、逆に16回以上その運動ができた場合、負荷が軽すぎる。だから1kg重いウェイトを次回はトライすること。重すぎるウェイトで無理を続けてりしてはいけない。それは筋肉にむしろ障害を与える。軽すぎる負荷では、もちろん筋力の向上にはつながらない。」 そしてまた、こうも言った。「こうしたトレーニングのための運動は、週1回では足りないことが統計で明らかになっている。7日たつと、獲得された筋力がもとに戻ってしまうのだ。週2回やれば、筋力は維持される。だから本校の体育の授業は教養過程の間、週2回に設定している。」
そして極め付けは、これだった。「諸君は別に他人と比べる必要はない。各人の運動能力はそれぞれ別で、個性があるのだ。だから、過去の自分とだけ比較して、向上を確認すればいい。」
実際、毎週同じトレーニングを続けて行くうちに、少しずつだが自分のスコアは着実に上がって行った。それは、とても喜ばしいことだった。自分にも運動面で向上する余地が、あるいは可能性があるのだ。トレーニング内容は少しずつ組み合わせで複雑になって行ったが、プログラムが緻密に設計されているため、ついて行くことができた。何より、他人と比較されて、劣等感を感じずに済んだ。それは、生まれてはじめての事だった。
そして逆に、それまで10年間受けてきた体育は、いったいなんだったのか、と思わざるを得なかった。運動部の、ほとんどプログラムも設計もない、ただむやみなジャンプやダッシュや筋肉運動の数々。そして体力をつけるため「体をいじめる」という、不可思議な観念。それは単なる精神主義の産物ではないのか。こうしてスコアに記録して数値化し、それを集めて分析し、さらにプログラムの設計を向上させる、という科学的発想はどこにも見られなかった。だが、あきらかに体育は科学の対象なのだ。目から鱗が落ちる経験とは、まさにこのことだった。
大学の体育の授業で学んだ、人の自発的な育て方
http://brevis.exblog.jp/20829444/ (via kyo-ju)
3K notes
·
View notes
Quote
ドラマ『ファイティングガール』
日本のドラマで珍しくとてもフェミニズム的だと思っていたのに全く有名でもなくて、ソフトも普及してないんですが、深キョンが18歳くらいの頃にユンソナと一緒に出ていた神山由美子脚本の作品です。深キョンがギャルの役をやっていて109で働いている設定なんですが、その時の彼女が今とは別人なくらいマックスに太っていて、女子プロ���選手みたいに強そうなんです。そんな彼女が電車でメイクをしていたら、注意をしてくる嫌な女がいて、それを叩きのめしてやろうと思っていたところ、ひょんなことから彼女と一緒に洋服屋を始めることになるという話です。
深キョン演じる主人公は父親とも喧嘩ばかりの誰ともうまくいかない女の子で、腕っ節がすごく強くて、すぐに人を殴るんですが、だんだんと人との付き合い方を学んで、最終的にはほんの少しだけ成長します。でも、こんなに仕事が上手く行かないドラマは見たことないというくらい、彼女の仕事がうまくいかないんです。外で服を売ろうとしたらデザインを盗まれたりして。
冒頭で深キョンが109で働いている時に万引きする女の子を見つけて、センター街の中を走って追いかけていって、その子を捕まえてボコボコにするというシーンがあります。このシーンは深キョンが109を走っている間、お店から色々な音楽が流れていて、当時のヒットチャートが分かる名シーンなんですが、とにかくその時の彼女が二の腕がたくましくて、むくむくしていてすごく良くて。だから今みんなが見ている深キョンは、牙を抜かれた深キョンなんですよ。
第1話で遊び人の坂口憲二演じる大学生に彼女が押し倒されそうになるシーンがあって、そこで彼女はそいつをバッキバキにのして、「私は絶対に負けないんだ」と宣言するんですが、このシーンがすごく良いです。
最近の深キョンは可愛くてちょっと頭の悪いアラサーのOLの役ばかりやっているんですけど、私はこの時の深キョンがベストだったと思っています。見ていてすごく元気が出る、とてもアマゾネスな女の子なんですよね。深キョンが夜のプールに忍び込んで泳ぐシーンもあって、そうすると視聴者はお色気シーンを期待したりすると思うんですが、その時の彼女は原色の色の服でがっと飛び込んで泳ぐから、プールにすごいデカい生き物がいるとしか思えないという。主人公が蒲田の工場の実家に住みながら、ファッションの勉強をしたいと頑張っているところも良いですし、私は本当にこのドラマが好きなので、もっと再放送されればいいなと思っています。
http://scarletandjune.com/2017/02/interviewwithmsyuzuki/
0 notes
Link
0 notes
Quote
もはや亜熱帯と言ってもいいのに、今年もまた、サラリーマンは背広を着せられ、結果、会社では冷房をガンガンに入れ、女子社員は冷え性に苦しみ、エアコンの排気熱で都会はさらに灼熱の亜熱帯になり、そんな炎天下で生徒の体調はまったく無視した高校野球がおこなわれ、試合終了と共に脱水症状で担ぎ込まれる選手が日本各地で続出し、しかし球児の健全な生育と行動を求める高野連は何人倒れようとスケジュール通りに試合を進行し、日本人は必死に仕事を続けるのです。
あたしゃ、この連載が始まった20年近く前から、「夏にバカンス。大型バカンス。最低でも二週間のバカンスが普通になる国、日本!」と言い続けているのですが(二週間は、ものすごく妥協してます。ヨーロッパだと一か月、四週間が平均ですからね)、日本が変わるまで言い続けるぞと言っているんですが、あんまり変わらないのでくじけそうになっていますが、負けるもんか。こういうのは、言い続けないとダメなんです。あきらめたら、そこで試合終了なんです。はい。でもつらいです。
「なぜ日本人は暑い季節にスーツで働いてるんだ!?」外国人が驚愕 | 日刊SPA! (via tnoma)
461 notes
·
View notes
Photo



Tumblrユーザーボイス: 栃木県在住・テツ君 (9歳)。
今回のインタビューはなんとキュートな柴犬、テツ君です! テツ君の毎日をブログ「Bread and Towel」で紹介されているのはテツ君の飼い主代理人さん。テツ君の気持ちをたくさんのコメント入りの写真で代弁されていますが、今回のインタビューでも翻訳のお手伝いをいただきました。最近では猫ブームだったりとか、Tumblrでもちょこっと猫派の方が多いような気もしますが、世界で人気のSHIBA代表として、テツ君に”赤裸々に”語っていただきました。湿気と暑さにやられ気味な日々は、かわいい柴犬写真で和みましょう♪
- まずは、簡単な自己紹介をお願いします。
オレは、赤い流れ星・柴犬テツ。海のそばで生まれて、高原で育った。散歩はあんまり好きじゃない。森に住んでるけど、完全なインドア派。どっちかというと、石橋を叩いて渡るタイプ。ブログ「Bread and Towel」で、大好きなものを並べてみた。モットーは"赤裸々"。
さらに読む
262 notes
·
View notes
Quote
子どもの人数が増えたので学校に入れない子が出てきた、病院の救急病棟の待ち時間が4時間、不動産が値上がりして一般サラリーマンが普通に家が買えない、EUの押し付ける法律がバカらしい・・・これらはこの国が抱える問題としては全て事実である。 ところが、問題の元凶が移民にある、というのはこれを政治利用したい保守党一部と右派である独立党(UKIP)のレトリックである。
Brexitというパンドラの箱 | 世界級ライフスタイルのつくり方 (via mangangrowup)
1 note
·
View note
Quote
先日、ウェブ上で「結婚不適合者」と題された匿名の記事を読んだ。彼氏を作っても月に一度デートすれば満足で、それ以上を求められると「時間が奪われる」と感じてしまう。毎日のようにくだらないメールをやりとりするのがしんどい。趣味の時間がとれないと体調が悪化する。きっとこのまま誰とも結婚できないのだろう、と綴る若い女性の手記だった。
他人事とは思えなかった。孤独を失ったら、私はきっと死ぬ。言うなればこれは「持病」のようなものだ。狭心症患者がニトロを手放せないように、糖尿病患者がインスリン注射を打つように、私が健やかに生きていくためには、「番いの相手」は要らずとも、「一人の時間」は必需品なのだった。そのことを理解してくれる人とでなければ結婚できない。自分の心を偽ってまで他者と関係を保ちたいとは思わない。口で夫にそう伝えるより先に、身体が動かなくなってしまった。
協議の結果、新居には「籠もり部屋」を設けることにした。寝室と居間が一体化した開放的な1LDKをすべて内見候補から外し、同等の面積で、間取りが2LDK以上に仕切られた物件を選ぶ。幸い条件ぴったりの部屋が見つかり、私は5畳半の個室を手に入れた。ルールは単純だ。二人でいるのが精神的につらくなったら、私は「籠もり部屋」のドアを閉める。扉が閉じていればその内側は「一人の時間」で、たとえ配偶者といえども干渉してはならない。ただし、事前に約束した食事の時間は守ること。
この話をすると「うちの夫と同じだ!」と言う友達が結構いた。物理的なシェルターを必要とする人は、なぜか女性より男性に多いようだ。曰く「最初は何に参ってるのかわからなくて、塞ぎ込んでるのを心配してずっと側にいてしまった」「籠もり部屋を作ってあげてからは二人でいても気性が穏やかになった」「部屋では趣味に没頭しているらしい。まったく理解できないけど、無理に知ろうとするよりそっとしておいたほうが夫婦円満」……そう、そうなのよ!
嫁へ行くつもりじゃなかった――私の新婚日記 (7) 寂しくないと死んじゃうんだよ! | マイナビニュース (via katoyuu)
2013-11-16
(via mmtki)
2K notes
·
View notes
Link
0 notes
Photo
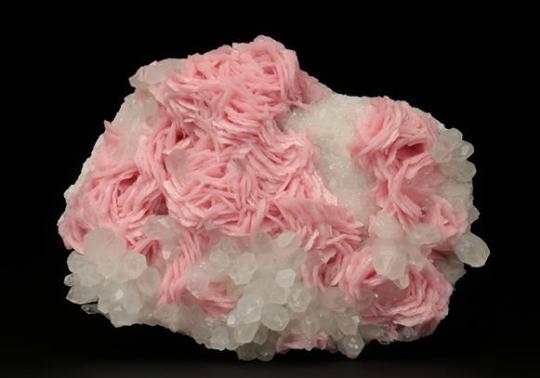

Rhodochrosite on Quartz - Cavnic, Maramures Co, Romania
2K notes
·
View notes
Quote
本当にもう、うんざりなのだ。僕自身がもう10年以上、子供や若者や女性の貧困をルポしてきた当事者報道の急先鋒でありながら、そして日本にある貧困問題を「可視化」すべきだと強く訴え続けてきたくせに、昨今の貧困の当事者報道には、ほとほと嫌気がさしている。メディアは貧困者を選別して報道してきたうんざりの理由はいくつもあるが、たとえばそのひとつは「メディアが報道する貧困者の選別加減」である。この点で貧困報道ではマスメディアはずいぶん前から大きな失敗をいくつも犯してきている。たとえばリーマンショック、派遣切り、ネットカフェ難民、年越しホームレス問題などで浮上した、ホームレスからワーキングプアまでさまざまな貧困者の報道で、どんな当事者がピックアップされていたかを思い出してほしい。自戒を込めて思い出せば、忘れもしない僕自身、その当時、取引先の出版社の編集部から取材をしてほしいと言われたのは、「昨日まで一般的な社会生活を送れていた人々」で、「思わぬキッカケで貧困に陥ってしまった人々」だった。具体的に言えば、昨日まで普通に幸せに生きてたサラリーマンで、今日はホームレスになって炊き出しに並んでいるお父さんだ。失職を契機に妻子を失ったりしているとさらに御涙ちょうだいでよろしい。だがどうだろう。そのコンテンツの意図はこうだ。第一に、読者視聴者のあなた方もいつか貧困に陥るかもしれないという脅し、こうしたコンテンツは視聴者読者の引きが強い。その理由は単純で、テレビ朝日のキラーコンテンツ“本当は怖い家庭の医学”をはじめとする多くの健康バラエティが一定の視聴率を取るのと同様に、人は自分の身に降りかかるかもしれないリスクの情報には、本能的に注目するからだ。さらにこうした定型の貧困コンテンツでは、その当事者がなぜ貧困に陥ったかのプロセスを描く。これがいわば病気の「セルフチェックシート」に近いもので、提示された身近な危機に実際に自分が陥るのかどうか、陥らないためには何をすればいいのかが描かれる。そして、こうしたコンテンツに飛びついた読者視聴者たちは、「あたしヤバいかもしれないから対策しないと」もしくは「俺はまだ大丈夫だわ」となるわけだ。が、はたしてこれは貧困報道として、購読数・視聴数を稼ぐ以外の何の意味があるのか? それは単にエンターテインメントのひとつであって、貧困にいる人々の救済には何の役にも立ってこなかったどころか、大きな弊害すら生んできたように思えてならないのだ。はたして「貧困=自己責任」なのか?こうした紋切型の貧困啓蒙(警戒)コンテンツには、いくつもの問題がある。たとえば貧困者がそこに陥ったプロセスを描く中で、「ここでこの人は○○をしてこなかった結果、貧困になった」という場合、この○○をしなかった当事者に、貧困に陥った「自己責任」があるとも取られる。だが実際はそうではない。少なくとも僕が取材してきた貧困者とは、いくつか自発的なリスク回避をしたぐらいで「貧困に陥らずに済む」ほど、軽い事情の持ち主たちではなかった。本人の資質や周囲の環境がからみあって、縁も運も何もかも尽き果てて、もうやむをえず、あがいても何をしてもはまり込んでしまって抜け出せないのが、貧困だ。そう感じてきた。だが、多くの報道からはそうした複雑なバックグラウンドが抜け落ち、短い尺の番組や記事の中で、単に「非貧困者」のための予防情報を提供するだけだった。一方で、「昨日まで普通のお父さん」的な読者視聴者に近いライフストーリーを過去に持つ貧困者を意図的に選択・報道することには、もうひとつ大きな問題がある。たとえばあの年越派遣村報道の際には、公園の炊き出しに並ぶ多くの野宿者の中から、20代や30代といった若年ホームレスをピックアップして取材する姿が目立った。行列の中から彼だけをピックアップする姿に、吐き気を催した。公園で取材を受けていた「彼」以外の行列を成す野宿者が、見事に背景扱いだったからだ。ネットカフェ難民報道についてもそうだ。テレビさんや新聞記者さんは、実際に何日かネットカフェ生活を体験してみることすらしなかったのだろうか。そこにいるのは何も若い男女や派遣労働者だけじゃない。売れないセックスワーカーのおばちゃんや、住所不定、職業(半ば)犯罪といった怪しいオッサンまでがたくさんいたはずだ。ネットカフェという新しい業態と派遣労働者問題という新低所得層が時流にマッチングしたからか、やはり選択的に若い失職者や携帯1本で生き抜く派遣の若者ばかりがピックアップされた。背景になった彼らは、何年も前から貧困者だったかもしれないし、その公園はそれこそ日本経済が頂点を迎えたバブルの時代から路上生活者への炊き出しをやっていたはずだ。ネットカフェのおっちゃんおばちゃんもそうだ。ネットカフェなんて業態が生まれるずいぶん前から、町の汚いサウナやカプセルホテルなんかには、住民票の住所に住める人間と路上生活者の境界線にある貧困者がたくさんいたものだ。そんな彼らを背景とし、���ャッチ―で今風貧困な取材対象者だけをピックアップすることの最大の問題は、はやりで紋切化したコンテンツはいずれ飽きられて、人が目を背けるようになることだ。飽きられないように新しい当事者、よりキャッチ―な当事者へと取材はエスカレートしていくだろうが、いずれは飽き去られ、「またこの手の貧困ネタっすか、ゲップ」という感じに、タイトルだけで読み飛ばされるようになりかねない。昨今の「貧困女子報道」「子供の貧困報道」では、すでにその読み飛ばしモードまでコンテンツの消費が進んでいるようにも思える。貧困問題は、消費されてはならないだが、貧困問題とは本来、こうした消費コンテンツとして決して消えてはならない、社会全体の大きな問題だ。そもそも昨今の貧困報道で「背景扱い」されたような、過去からずっとずっと世の中にあって、無視され差別され続けてきた貧困者を放置してきたことが、社会全体の底が抜けて、貧困が身近なコンテンツになるまでに至ってしまった原因だと思っている。先日、知人の先輩編集者から、「鈴木さんは貧困報道の一人者ですよね」的なことを言われたがとんでもない。僕などは何の専門ライターかと言えば「売春と窃盗と詐欺」の現場取材専門ライターにすぎない。底辺も底辺だけど、自身が底辺だからこそ、この社会から逸脱した人々への取材は、ずいぶん前から貧困の当事者取材でもあると認識して続けてきたし、今、こうして貧困コンテンツが「ブーム」になって大手メディアもこぞって紋切コンテンツを垂れ流しているのを見て、十数年間、裏の人々取材の中でたまりきった感情が暴発寸前である。彼らを見世物にしないでほしい。コンテンツとして消費しないでほしい。けれど彼らの抱えた苦しみをきちんと報道し、可視化するべきだ。
昨今の「貧困コンテンツ」ブームが危険な理由 | 「貧困報道」は問題だらけだ | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 (via yaruo)
355 notes
·
View notes
Quote
人間、馬鹿になってたほうが楽です。わざわざ余計なことを考えない。でも、なにかに気付いてしまったり、考えてしまったら、それは止められないんです。「考えるな」と言われるからこそ、考える。それが人間というものですから。
じゃあ、とことん考えればいい。ただし、結論を急がないで考え続ける。何十回も何百回も、何十時間も何百時間も、考えに考え続ける。一番イケナイのは、悩むことです。「考える」と「悩む」の違いは大きいです。考えるとは、答えを出そうとすること。悩むとは、堂々巡りをしているだけ。だから、悩んじゃいけない。考えるのです、とことん。アッと驚く名案なんか、めったなことじゃ出てきやしません。でも、考えに考え抜いた末に導かれた結論だったら、その後に後悔はありません。
ckc様のご同僚、今、苦しんでるん… by 梟小僧 | ShortNote (via kotoripiyopiyo)
222 notes
·
View notes