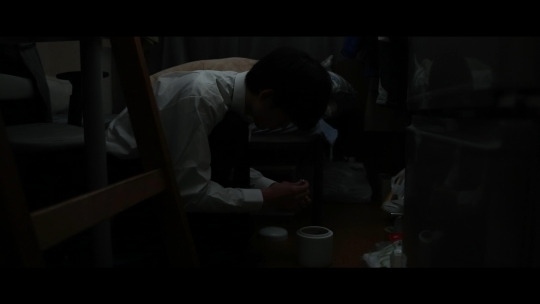Text
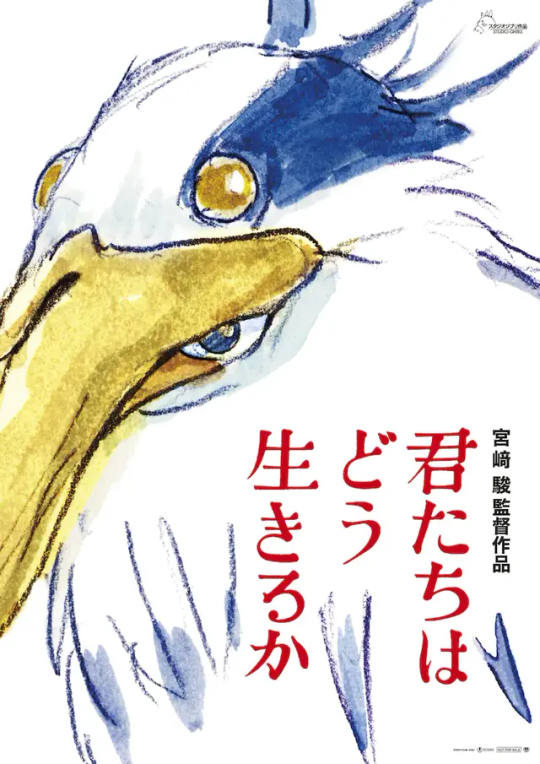
君たちはどう生きるか
宮﨑駿監督最新作にしておそらく最後の作品になるであろう。そう感じる「総括感」が散見される作品であった。
その最たる例が「物語を作ることを物語る」ことにある。今年はこの手の視点の作品が何作か公開されている。ジョージミラーの「アラビアンナイト」、スピルバーグの「フェイブルマンズ」、少し立場や趣向が違うがデイミアンチャゼルの「バビロン」。ジョージミラーやスピルバーグは巨匠の域にかかり、宮﨑駿もまた巨匠という立場からこの作品を生み出している。彼らにとって物語るとは結局どういうことだったのだろうか。「フェイブルマンズ」では自分の撮ったフィルムが予想を超えた力を発揮したり、見せたくない事実をエディットすることができる様を見せつけたが、最後は映画に対するポジティブな回答で終わる。「アラビアンナイト」では枠物語の形式から物語自体に恋をすることで生き生きとしていく様が伺えた。
今作の宮崎駿はそこに少し悲観的だ。物語に没頭した結果失ったものを提示する。また、物語ることの無意味さ、非現実性も現実と対比して語る。私は鑑賞中宮崎吾朗の名前が何度も頭を駆け巡った。彼は父、駿の元何作かの作品を作り上げたが、そのどれもが父には及んでいないという評価を受ける。また制作中に父が介入してきたりと、その仲は我々の視点からは想像ができないほど特殊であろう。そんな吾郎に向けたメッセージにもとれる。物語を作り続けた結果失われた家族との時間や関係、そこに言及しているのではないだろうか。
また今までの作品に比べ場面や設定が抽象的であった。映像表現やアニメーションも説明をするというより、表現することの喜びに満ちたアニメーション独自の表現が多かった。冒頭の火事の描写は正直異常なほどおかしいアニメーションで、それを見れただけでも今作の価値があるほどだ。この抽象性溢れる表現は商業の大衆映画の中では異質である。ここに宮崎駿の意地のようなものを感じた。宮崎駿は何を作り上げてきたのだろうか。トトロのようなアイコニックなキャラクターなのか、泣ける物語なのだろうか。何かそういった消費される作品の側面に追いやられていくことに強く反抗したような作品に思えてくる。アニメ監督ではなくアニメ作家なのだという強い意志の表れだ。なので全体を通し自己批評的である。戦時中の場面は風立ちぬを想起させるが、風立ちぬに比べてフェティッシュは抑え気味だ。ポップなキャラクターもそれ以上のインパクトはなく、主張が抑え気味になっている。(宮崎駿の作品はたまにいつトイレに行くのかわからないリアルにかけた作品と言われたこともあるが、そこも今作はカバーしている。)大きなラブロマンスもなければ主人公の心情もよくわからない。ただ一つそこに横たわるのは物語を作ることの決意と誇りだ。
彼にとって制作をし続けたこの人生とはどういったものだったのだろうか。社会は変化しながら、彼は作品を作り続けてきた。作品を作ることで世界は何か変わるのであろうか。戦時中から始まることでこの映画は物語ることと現実世界との矛盾を強固に提示している。戦時中の少年は戦時中で日本国にいるので戦争の渦中にいるのだが、戦争に加担しているわけではない。この視点は現代日本人の視点と何ら変わりはない。歴史的な戦争の責任や記憶を有するが、直接的な責任は現代人には存在しない。そんな社会で物語を作り続けてきた宮崎駿。世界は変わらないと感じながらも直向きに何かを伝えようとしてきたのではないだろうか。そして我々次世代へ託した問い、「君たちはどう生きるか」なのだ。
私を含めものづくりに携わる人間は強く共感をしてしまう作品であった。これはフェイブルマンズを見た時にも感じたことだが、制作することはつまり身を滅ぼすことなのである。しかしそこに価値を見出し作り続けなければならないのだ。それが生き甲斐であり使命である。そしてそれが生きていくことの証明なのだと私は思う。
0 notes
Text

borns and all
肉欲をそのままカニバリズムへと比喩したこの映画は肉を貪る姿が象徴するように、官能的だ。キスという愛情表現と食肉が奇跡的な親和性を帯びる。
80年代アメリカで人肉を欲することで社会から逸脱せざるおえない彼らの姿は当時のヒッピーなどに似たものを感じる。
初老のカニバリストのサリーは敬虔なルールのもと生活をする。おそらく彼は女性との経験がないのであろう。そこにはキリスト教的価値観も窺える。彼はアメリカ社会の産んだ奇妙な属性のメタファーであろう。
物語は恋人を喰らうという最大の愛情表現で幕を閉じる。血と肉が真に同質化され訪れる最後の風景は心象的であり、楽園のようでもある。性愛をここまでグロテスクに、そして美しく描いた今作は間違いなく今年の一本だ。
0 notes
Text

2022年 「私たち」5min (監督/脚本/編集)
※文化庁主催NDJCワークショップ内で制作
vimeo
0 notes
Text



2020年 「瞬き(またたき)」13min (監督/脚本/編集/製作)
youtube
0 notes
Photo

「イニシェリン島の精霊」
古代ギリシャ語に「スカラ」という言葉がある。意味は”余暇”。この言葉は英語のスクールの語源である。古代ギリシャ人は学問の一つとして、余暇を重んじていたと言われる。
人生に必要な時間とはなんであろか。仲間と過ごす時間か、一人読書をする時間か、大義をかけて戦うことか、意味あることをすることか。この単純な問いこそが人生においての核心であり、人生の命題を突きつけられる。テーマはシンプルである。コラムの拒絶から二人が突如としてその命題を意識していく様は”映画を鑑賞している”私たちに突き刺さる。映画を見るという自己完結した行為になんの意味があるのであろう、、、。
人と関係を築くとき、大なり小なりの犠牲が伴うことを再認識させられる。それはどんな些細な関係であろうとも、その他者をある種束縛する。関係が深くなればなるほどそれは強くなる。そうして知らずのうちに相手の大切な時間、他の人物との関係を遮断していくのだ。
この映画で奇妙なのはどちらの見方にもなれることだ。主観としては拒絶されるパードリック視点なのだが、個人的には意義ある事をしたいと拒絶をするコラムに強く心打たれた。私自身5年前に完全に心を閉ざし、家族と一言も口を聞けない時期があった。その頃私は挫折を味わい、本格的に美術の道に行こうと決めた。その結果それまでの価値基準だった家族の話を信じることができなくなった。また家族の優しい言葉が辛かった。その頃を思い出さずにはいられなかった。約一年前、今度は私が拒絶の対象になった。家族ではなく当時の彼女であるが、拒絶されるという経験は耐え難い恐怖であった。人生はこの繰り返しのような気もする。それでも尚地平線を見つめる映画上の二人はこれから先も途切れることのない関係を続けていくのであろう。
映画の話に戻すと、彼らの関係とはなんだったのであろうか。友人なのだろうか。私はそれ以上に感じた。特にコラムに。拒絶してしまうとはどういった感情なのだろうか。あの小さな孤島で二人は妻もいない。ここで重要なのが妹の存在だ。妹も当時の価値基準からすると独り身にしては高齢だ。コラムは妹に私の気持ちがわかるだろう、と尋ねる。二人は鏡合わせの人物なのだ。
私はこの断定できない他者に抱く愛情が心地よく、胸が苦しくもあった。
最後に映画の構成について語りたい。映画とは基本的に突如としてとある世界に放り込まれる体験だ。故にぶつ切りになった時間にいきなり入れられ、慌てて状況を把握する必要がある。その映画的構造が突如として拒絶されるという設定と完全にシンクロし、最大限の効果を生み出していたと感じた。のちの展開は言わずもがなだが、この切り口で始める大胆さを故意的に仕組んだ脚本が本当に素晴らしく感じた。
多分数年に一本レベルの作品であった。
ブースト
0 notes
Photo

「2001年宇宙の旅」
2022/12/31
2022年の映画納めは奇跡的に劇場で「2001年〜」をやっているのを発見し、鑑賞。2022年は個人的にしんどい一年だったが、もうそれらを忘れるくらい最高な映画体験だった、、、。もう何度見たかわからないこの作品を改めて感想を書くのも少々馬鹿馬鹿しい気もするが、書いてみる。
改めて原点にして頂点、究極の詰まった映画であると確信した。これが60年前に作られたということだけで圧倒される。そしてまだどの作品も越えれぬ境地に一人咲き乱れている。冒頭の惑星直列からのタイトルで鳥肌と涙の嵐。超越した何かを目撃する準備を僅か数分でやり遂げてしまう。恐ろしい。
よくこの映画は説明が少なく、難解だと言われるが改めて見ると卓越した映画的演出法が凝縮している。猿が初めて武器を覚える瞬間、一瞬モノリスのショットが挿入される。その僅か数秒のワンカットが説明的な印象を排し、直感的に理解できるよう意識を誘導させている。さらにハルが暴走する場面でも極限まで緊張感を煽り、決定的な犯行を犯すシーンでは犯行の方ではなく段々とカットを割って拡大されるハルのランプが映される。この圧倒的なテンポ感と映画的手法によってぎりぎりのラインで理解の領域を保っている。
ストーリーの軸もモノリスが人類を導くようにストーリーに点在しながら話自体も引っ張っていく。人類の夜明けから月面、そして木星とその彼方で迎えるモノリスは惑星直列のタイミングに現れる。この象徴的なイメージの連続によって我々は宇宙と壮大な繋がりを見出していく。
果たして2001年とはどんな話なのだろうか。私は今回改めて鑑賞し、新たな発見を得た。この物語は人類へ送る人間讃歌であると感じた。もちろん進化論を否定したり、超常的な存在であるモノリスの不明さ、時間と空間を超越したボーマン博士などそこには多分に人類史の否定や非科学的事象、説明を過度に落とした作風が渦巻いている。故に既存の価値観の否定に感じるが、そうではない。偶然モノリスに触れた我らの祖先は他の猿と何も変わらなく怯えて暮らしていた。しかし偶然にもモノリスと出会い知恵を得たことで生き物の頂点へと上り詰め、そして地球を飛び出し宇宙へと羽ばたくことができる様になった。さらに人類は金属や電子回路の集積を用いて人間より高度な知能を作り上げ、それさえも克服していく。そうやって試練を乗り越えた人類(ボーマン博士)は宇宙の誕生を目撃し、生物としての限界である時間と空間さえも超越していったのだ。最後のスペースチャイルドの誕生はボーマンの成れの果ての姿とも捉えられるが、人類全ての根源的な誕生を讃歌している様にも感じられる。思えば劇中では人間的幸福感に満ち満ちている。クラシックと宇宙船のランデブーはその最たる例ではないだろうか。キューブリックのインタビューで見たことがあるが最後はスペースチャイルドが地球の軌道上にある衛星(核弾頭のついた砲台型の衛星→人類の夜明けからのジャンプカットで出てくる人工衛星がそれ)を一掃して幕を閉じる予定だったが技術の関係でできなかったと語っていた。つまり暴力で幕を開けた人類が暴力さえも克服したことの暗示と捉えられる。その意志はエンディングに込められていると思った。エンディングでは「美しき青きドナウ」が再び流れる。ENDという表示が出た後も流れ続け、暗転しても最後まで曲を聴かせる。これは紛れもなく人類の芸術に対する賛美であることに間違いない。この曲の流れる様な旋律を聴きながら映画を反芻し、希望を胸に抱けるラストは感動を超えた充足感があった。
キューブリックの作品の中でも特筆して真っ直ぐな問いかけをしてくると思う。ちっぽけな自分も壮大な宇宙の中で確かに生きる権利があると教えてくれている様な感覚だ。我々は「2001年宇宙の旅」という理解を超越したものを作れる、そして知覚できるまで進化したのだとモノリスに胸を張って生きていけるのではないだろうか。
2023年はきっといい年になる気がした、そんな暮れでした。
0 notes
Photo

「MEN」
思わず嘔吐してしまいそうになった最後の展開を目撃した時、この映画のホラー映画であるクライマックスだ、ときっと誰もが思う。しかしそのシーンで恐怖しているのは我々観客のみであり、追い詰められた主人公は冷静にそれと対峙している。
この映画は果たしてホラーだったのかさえも疑問に思えてくる。最後の表情が脳裏に残る。この映画は社会や歴史に深く刻まれた男性の中にある男性性がテーマであるのだろう。アダムとイブが禁断の果実を食べたことで性というものを認識したように冒頭リンゴを口にする。トンネルの中で声の残響を利用して音楽を奏でる印象的な歌声が苔の生えた男をこちらへ誘う。それは股を広げた像の如く男を誘う。(誘われていると錯覚する)彼氏の自殺と顔の同じ田舎の男達は一見関係なさそうに見えるが底に埋もれた、社会や教育、歴史によって刷り込まれた底にある男という本質は同じなのだ。劇中に出てくるマリリンモンローのお面はセックスシンボルとして消費された女性達を想起させる。(お面を取ると男の影が絶対にある。)社会の中で刷り込まれている根の深い腫瘍のような男性像がつきまとう。それが結果として最後のクライマックスへと帰結する。男性は男性を産み続けてきた。男性を男性へと確立させるためにその価値観を��の代にも託して行ったのだ。この男の金太郎飴式出産シーンをまさに自分も経験してきた。それは親から教師から男は男としてこうあるべきであるという意識の刷り込みだ。それを受け取った子供はきっとそれが正しいと思い成長し、また同じ価値基準の元我が子を育てていくであろう。最後に彼氏がいう「愛してほしい。」という一言はきっと理想の女性像である主人公に愛されたかったということだと思った。それは男性が何百年と刷り込ませてきた価値基準によるものだ。
最後の主人公の哀れみに満ちた表情はこの映画が女性目線のホラー映画というものから完全に脱却した瞬間なのかもしれない。そこには近年の女性がメインとなる映画ともまた違ったさらに達観した眼差しであった。(男性を克服するといったホラー映画的解決方法では男性の否定へと繋がっていくのに対し、そんな男性を哀れんで見つめる方が両者の軋轢を産まずに済む。)
この眼差しは貴重なのではないかと感じる。この失望感を我々は感じなくてはならない。言葉にするのが難しい、というのは自分もその男性というカテゴリーの一部だからだし、そこに眠った男性性に思い当たる節があるからなのかもしれない。
このような男性批判的な映画であるのと同時にパンフレットにはいくつかの興味深い記述があった。それは主演のジェシー・バックリーのインタビューだ。彼女はこの映画を何についての映画かと問われたら、「男性と女性にとっての人間関係というものがなんなのか、問いかける作品だ。」と答えている。ここには男性と女性の平等な眼差しがあった。MENは有害な男らしさの否定をしているわけだから少し意外だった。さらにアレックス・ガーランド監督はシーラ・ギク(女性が股を開いた像)から発想していったが、それがどういったものなのかは学者ですらよくわかっていない、と語っていた。古代より性器をかたどった象の様なものはよくある。石棒や神輿というものがその象徴だろう。私の通っていた大学の芸術祭でも男性器を模した神輿を女性器に見立てた穴状のものに入れるというものがあった。(今もあるのかは不明。)私はいつも見るのが嫌だったし気持ち悪かった。ただ他の生徒は男性も女性も盛り上がりを見せていた。こういった伝統的にある性別の露骨な表現に関して考えれば考えるほど現代社会において男女で区別して考えるのではなく、人間関係として男女というものを再定義する必要があるなと感じる。
そういった本当の意味で男女が平等になる社会を目指すべきであると感じた。
0 notes
Photo

「マッドゴッド」
究極の地獄へようこそと様々なレビュアーや評論家が語っているが、私はむしろ天国の様にさえ感じた。それはフィルティペットが制限無く自由に制作しているというのももちろんだが、私個人的には終末の世界に人間らしき存在が全くいなく非力であるところに希望を感じるからだ。時たま人類が絶滅したらいいのにと思ってしまう時がある。それはあまりにもたくさんの人間にあった時や自分ではどうにもならない大きな問題が顕になったときだ。映画は昔からディストピアを愛している。私もまた子供の頃からそんなディストピアな世界に逃げ隠れしていた気がする。だから私はマッドゴッドの中の何かのクリーチャーを夢見ているのかもしれない。一番最後に出てくる顔にデキモノがたくさんついた男が望遠鏡で映画やキノコ雲を覗く。彼らにとって人間の核戦争が無かったら生まれてないわけで、彼らにとってのモノリス的存在なのだ。故に��の世界は人間から見たら地獄だが、出てくるモンスターたちからしたら天国なのだ。私は全く戦争推進派でも核推進派でもない(むしろ逆)だが何故かこのシーンに感動を思えた。
この映画は臓器やら糞尿やらと生物の汚い面が巡り巡って世界が構成されている。この価値観にとてもハッとさせられた。生の営みを語る時単にセックスや親とこのつながり、死と生などを用いる作品を山の様にある。そこに作家のフェティッシュが加わりより濃度の強いセクシャルなものやエモーショナルなものになる。しかしティペットの視点はもっと平等なのだ。そこに優劣はなく全ての生物が糞をし、臓器が動き、死んでいく。体とは、生物とは、人間とはそんな輝かしいものでもなんでもなく、ただ気持ちの悪いものの集積なのだ。私はこの映画を見て人間がシリコン状の皮だと考えた時にベロンとひっくり返して仕舞えばどんな人間でも臓器はあるし、うんこも出てくる汚い存在なのだなと特殊な勇気を貰えた。
人の見栄を気にしすぎる我々現代人のルッキズム思考に突如として現れたこの楽園が静かに嘲笑っている。
3 notes
·
View notes
Photo

「グリーンナイト」
この作品の印象を問われたときどう答えるべきであろうか。神話的?英雄伝的?ファンタジー?おそらくそのどれにも当てはまるが、それら全てを否定している様な印象も受けた。
宣伝文句にはA24史上最大のファンタジーやロード・オブ・ザ・リングの原作者が訳したなど壮大な物語を想起させる文言が並ぶ。確かにファンタジックなキャラクターや雄大な風景など映画の建前はそういた映画なのだが、全くもってスッキリしない展開に驚く。
主人公のガウェインは身の上話のできないくらいの男であり、頼り甲斐がない。彼を形作る価値観も何もない。唯一あるのは騎士としての名誉がないという引け目だけだ。それは逆に潜在的に騎士道的名誉を重んじていることの表れである。この価値基準によってガウェインは緑の騎士との決闘を受けてしまう。そんなガウェインだが道中も騎士として名を挙げられるような功績は挙げられない。何かに怯え、盗まれ、誘惑に負ける。そして最後の首切りゲームでも覚悟が決まらず逃げ出してしまう。そこから始まるIFの世界で迎える最悪の結末。ガウェインはそんな未来を一瞬の間に想起し、初めて本当の覚悟を決めたところで映画自体が終わる。
映画の存在自体危うくなるその達観した終わりが潔く、そして気持ちよかった。思えば騎士による名誉なんて戦争で人を殺しただのそんな程度だろうし、その結果として民衆は殺され、森は焼かれる。この騎士道的名誉のどうでも良さを2時間かけてじっくり問いただす。待っているのは破壊のみ。古来から存在するこのお話を再解釈し、大胆に”無価値”を表現することを選んだ監督と制作プロダクションに改めて感服するのみだ。
1 note
·
View note
Photo

「あのこと」
12/13
この映画を見て思ったことそれは、フランス映画凄すぎる...!
おそらく日本映画には到達できない領域をぐいぐいと攻め込んでいる。センシティブなテーマ、じわじわと伝わる焦り、そして掴み取る安堵。おそらく簡易的な感動で満ちた我が国の映画業界では味わえない心の揺れを味わえ��。
感動とは何か、映画とは何かを考えさせてくれる。カメラはずっと主人公を追従し、真実を垣間見えている感覚は「サウルの息子」を想起させる。(と感じ、パンフを見たらやはり参考にしていた!)映像の質もフィルムの粒子が美しく、光も自然。画角は4:3で視界が狭く、彼女の心理的閉塞感とマッチしている。一方で徹頭徹尾ステディで彼女を追っていくため、いわゆるきまり絵の様な強い構図はなかった様に思える。しかし平凡なショットにはならないようにカメラと被写体の距離や被写界深度など慎重に選ばれている。
私個人的に今年は子供が生まれるシーンのある映画をたくさん見た気がする。思い出せるものだけでも、「TITANE」「戦争と女の顔」「灼熱の魂」「バルド」「パラレルマザーズ」などを劇場で見た。改めて私の属する男性という生物の何も生み出せなさ、女性の命を生み出していく存在感、一つの肉体から別の個体が生まれるという畏怖を痛感する。逆説的な見方ではあるが私は一生をかけても生物を生み出すことはできないし、別の個体が自分の体と共存するという瞬間も訪れないのだなあと深い孤独感に襲われる。
この作品ではそういった生物の美しさといったステレオタイプ化された生の営みに対し女性が一人の人間として堕胎を選択し自分の人生を生きる選択をするという話だ。つまりこういった能天気なことを考えてしまうのもまた男性性の表れな気もして、自分の意識の成熟もしていかなければと感じた。
おそらくどんな人が見ても主人公の痛みや不安を完全に体験できる作りの映画であり、この領域にたどり着ける邦画は現状皆無だと思った。
0 notes
Photo

「Parallel Mothers」
12/12
2人の母親が子供を取り違えられるという、ある種定型化されたような設定からその母同士が恋仲になったり、1930年代でスペインで起こった内戦で命を落とした先祖の遺体を見つけ出す話も絡んでくるためプロット最高!とはなったのだが…
娘をDNA鑑定することにより生物上の母親では無いと判明したり、先祖の遺骨を見つけ出す過程があったりと「血」の繋がりが強調されていく。ただそれが有機的にうまく絡んでいたのかといえば疑問が残る。取り違えた母同士が共に寝るところ辺りの想像を超えた関係性への発展を期待させる展開は「TITANE」などを思わせたが、この作品はあくまでも自分の血筋の話であるため、もっと遠くへと行けそうな脚本が小さくまとまってしまったような印象であった。きっとそれだけスペイン内戦という「国民の中で生まれた不毛な争い」が監督の潜在的なトラウマとしてあり続け、自身や家族さらにスペイン国民といった繋がりを語りたかったのかなとも思った。
前述した「TITANE」の通りどこか他のヨーロッパ映画と比較しながら鑑賞した。スペイン映画を多く観たわけでは無いがショットはどちらかというと平凡で会話台詞も多く、沈黙で繋ぐ箇所も少なかったためこちらが想起しながら補完していく映画的余韻も少ないように感じてしまった。(とにかく明るい雰囲気!)デジタルの綺麗すぎるショットも相まって全てを説明されているような感覚を受けた。テクノロジーの進歩が直接的に映画的表現を上昇させるとは限らないと思った。
ペドロ・アルモドバル監督は「Talk To Her」しか観たことないが、異常な偏愛のその先を明るく描いておりこちらの方が不思議な魅力があったと思ったりした。
0 notes
Photo

「afteryang」
今日から映画の感想を掲載していこうと思います。これは個人的な感想であって評価ではありません。映画とは個人の感性や価値基準によって如何様にでも印象は変わってくると思うからです。
初めての投稿はafter yang。おそらく今年見た中で、というより近年見た中でも1番のお気に入りの映画に巡り会えました。この映画のプロットはとてもシンプルで家族の中の一人のロボット、ヤンが物語早々故障してしまうところから始まり、父親は修理をする過程でヤンの中のコアに支障があることを告げられる。そうしてヤンのメモリーを探っていく中でヤンがどの様に家族と接していたかを家族が見つめ���すというものだ。
まず家族構成が面白いと感じた。父は白人、妻はアフリカ系、娘は養子の中国人、そしてロボットの中国系ヤン。近所にはクローン人間を娘にする家族も住んでいる。現代の多様性の行き着く先を予見した様な社会であり、それぞれが多様な人種(ロボットやクローンを含めた)を尊重しているようで、どこか不思議な違和感、居心地の悪さが見えてくる。ただ単純に多様化=美しいというものではないところに妙な説得力があった。親の二人が中国人の娘のためにと、中国系のヤンを迎え入れるところからして多様ゆえに補えない歴史的美徳をヤンによって補完している。多様な社会は理想的だが、理想的な社会や関係を作り上げるのは計り知れない心的、金銭的余裕が必要になる。(価値観の成熟が必要不可欠だ。)
そういった絶妙な距離感の家族がヤンの記憶を辿ることによって、自分達も知覚していなかった視点を獲得していく。
自分はことごとく人造人間の物語が好きだなあと感じる。ヤンの記憶の中にヤンが鏡を見つめながらふっと笑うカットがある。そこにとてつもない哀しさと孤独さがあった。自分は何者なのか。誰の何なのか。そんな感情が渦巻いている様だ。
この映画は好きなところだらけでまとまらない。記憶という現実として「今」存在していた具象だったものがいきなり曖昧なものに変容していく感覚や記憶をたどり、反芻していく様に思い出していく過程をオーバーラップしてくる音声や刹那的な光などによって表現されていた。そのアプローチはどこか写真的表現でもあり(実際に家族写真も撮っている。)、新鮮であった。
最後に劇中で流れ、最後に娘のミカが口ずさむGlideの歌詞が心に染み渡るのも最高である点だ。そこで歌われる「私はなりたい、シンプルな音に」のような無機的な、抽象的な概念に憧れるこの気持ちが人やロボット、人種を超えて生まれる共通の最後の願いな様な気がした。
今週で上映終わるので最後にもう一度見に行きたいと思っています。
0 notes