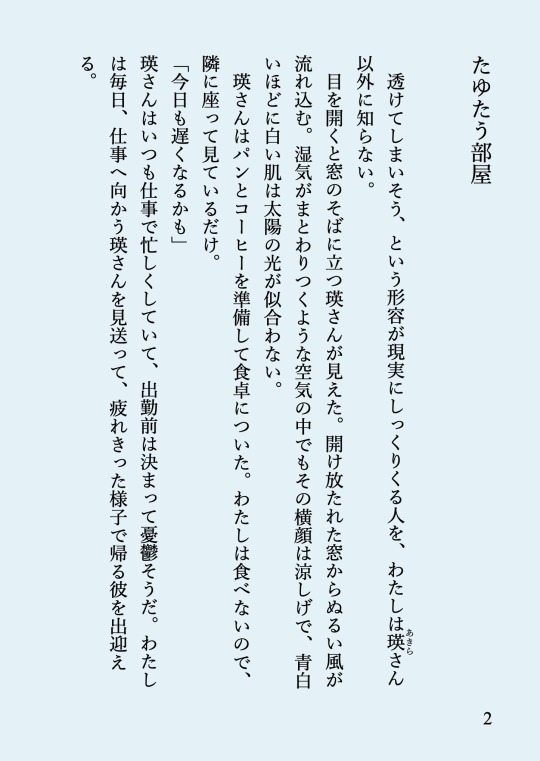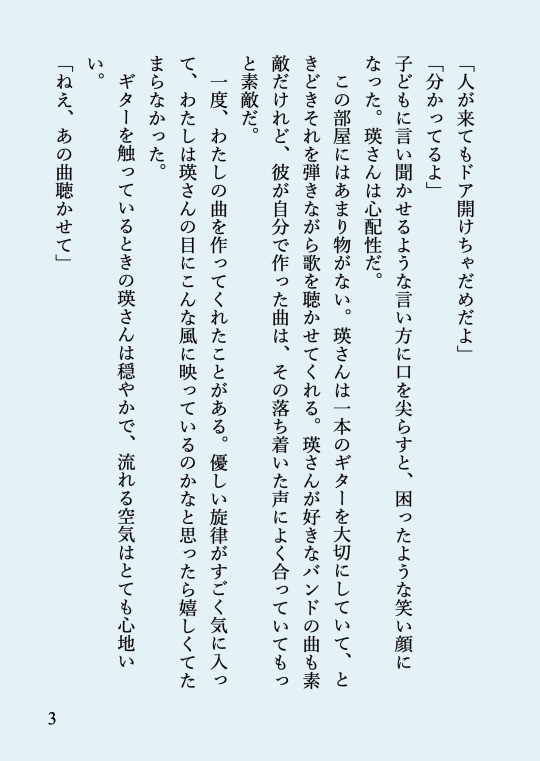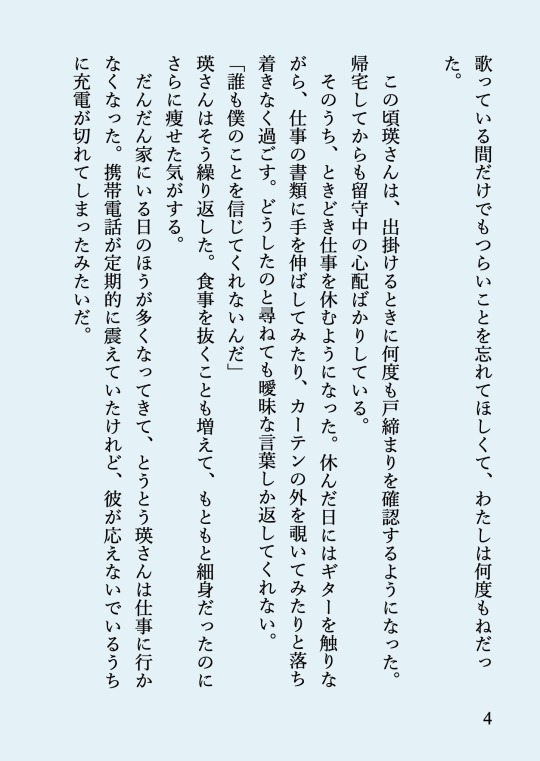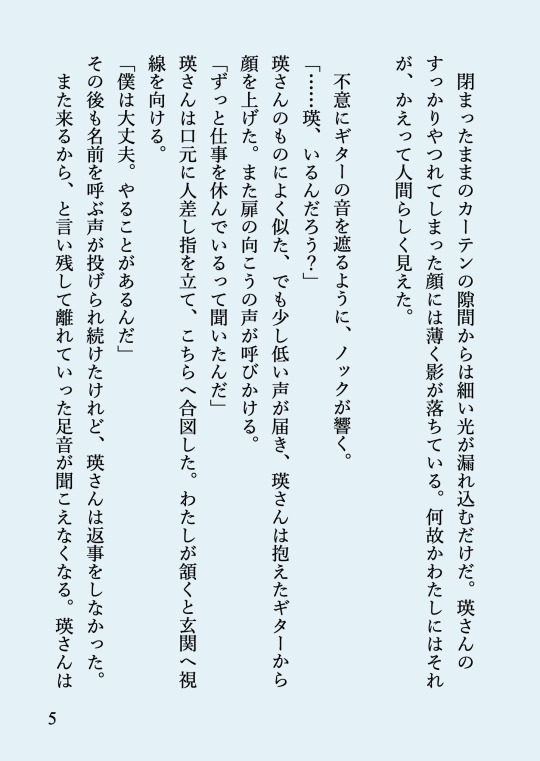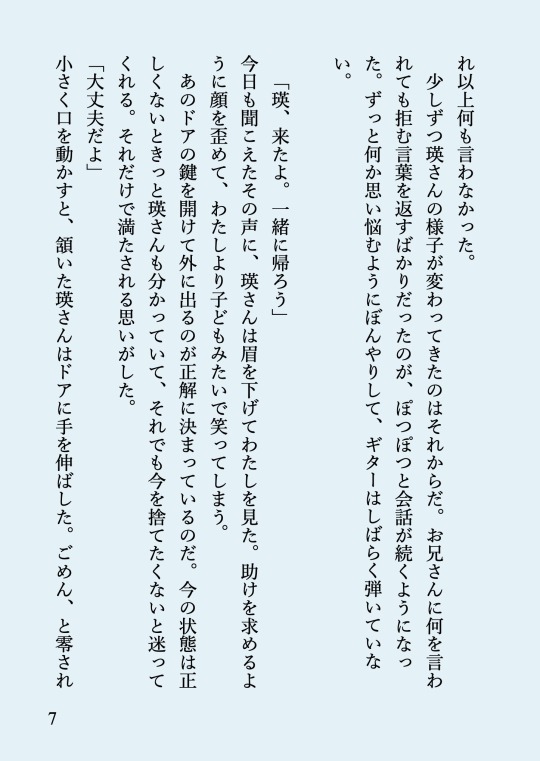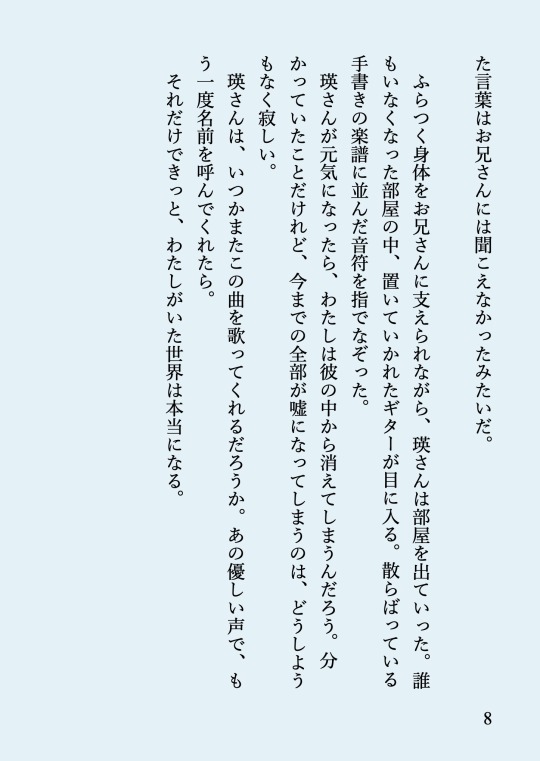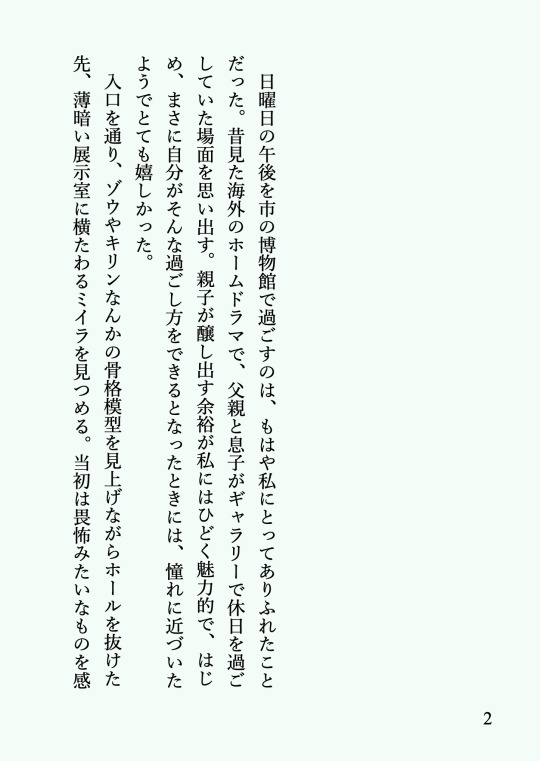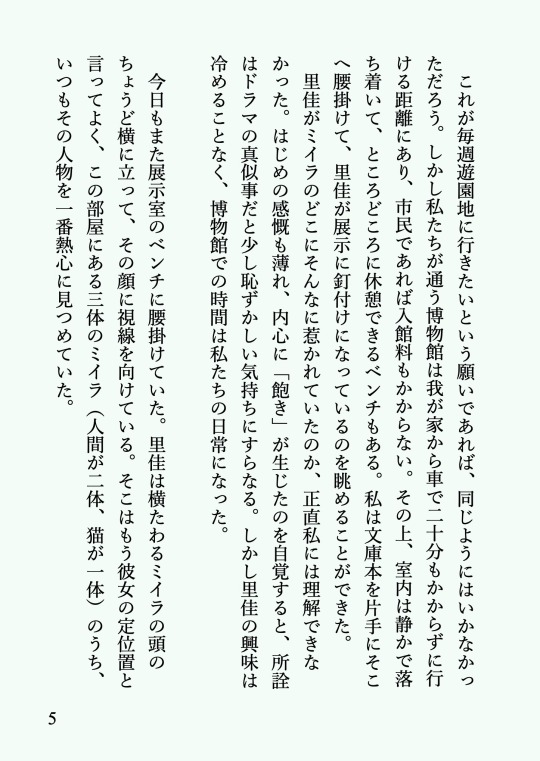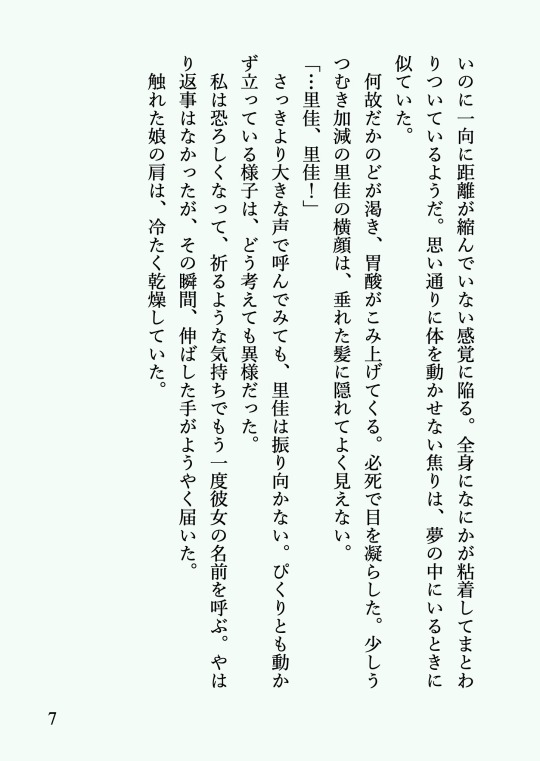Text
サラリーマン新藤剛
1.
男は立ち止まり、目の前にそびえるオフィスビルを見上げた。周囲には真新しいガラス張りの高層ビルがいくつも建っている。それらと比べると背も低く古びたこのビルが、しかし男にとっては一番恐ろしく、雨だれで汚れた外壁に威厳すら感じていた。
新藤剛は墨田商事営業部の部長である。二十五年前に入社して以来営業一筋で、数年前に部署をまとめる立場になってからも、時折こうして自ら取引先に出向くことがあった。
ミネラルウォーターを一口飲み、中身が半分ほどに減ったペットボトルを鞄にしまう。呼吸を整えるように深く息を吐いたタイミングで、後ろから部下が声をかけた。
「部長、大丈夫ですか?体調でも悪いんじゃ……」
いつも闊達で堂々としている新藤の緊張したような様子は、若い部下には見慣れないものだった。急に暑くなり始めたここ数日を思うと、体調を崩したのではないかと想像するのも無理はない。
だが振り向いた新藤は、意外にも普段通りの声色でそれを否定し、にやりと笑って見せた。
「いや、問題ない。……まあ、武者震いというやつかな」
「はあ……」
新藤はそれだけ返すとビルに向き直る。部下もそれ以上何も聞かず、二人は連れ立って自動ドアをくぐった。
2.
受付を済ませるとすぐに応接室へ案内された。新藤にとっては何度も訪れたことのある部屋だが、この場所はいつも新鮮な緊張感を彼に与える。
年季の入った黒い革張りのソファに腰掛けると、わずかに軋む音がした。新藤は案内係が出ていった扉を目の端に入れる。
ここ丸岡社は、墨田商事と付き合いの深い取引先のひとつである。今日は契約の更新と内容確認のため商談の場が設けられていた。新規の契約をとるという訳ではない。しかし新藤は、この商談を重要なものと捉えていた。ある意味では、会社の今後を左右するほどの。こんなとき、新藤はいつも心にある人物の姿を思い浮かべていた。
それは人気ドラマの主人公、高橋真太郎。平凡なサラリーマンでありながら、不正をはたらき私腹を肥やす上司や、理不尽な要求をする取引先と臆せず闘う、熱い男だ。新藤はシリーズを通してこのドラマのファンであることを日頃から公言しており、高橋真太郎は彼の憧れだった。その姿を胸に、新藤は大事な局面を幾度となく乗り切っている。
まるで自分が主人公になったような気分で、この後現れるであろう丸岡社の担当者・戸坂の顔を思い浮かべた。あの食わせ者にしてやられないようにしなければ、と気合いを入れる。
「失礼します」
ノックの音に身を固くしたが、続いて聞こえたのは来客担当であろう事務員の若い声だったので少し肩の力を緩めた。事務員が手に持っている盆から、コーヒーの香りが漂ってくる。
「お待たせして申し訳ありません。戸坂はすぐ参りますので……」
「……いえ、こちらが早めに着きましたので」
実際、約束の時間まではまだ少しあった。新藤は元来せっかちな質で、さらに今日の商談への気合いからかなりゆとりを持って到着していた。待ち時間が生まれるのは想定内だが、こちらがじりじりと時間まで待ってから向こうが現れるとなると、どうも「余裕」を見せつけられているように感じる。しかしそこで動揺しては戸坂の思うつぼだ。新藤はそう思い直し、心を落ち着けて待つべくコーヒーをありがたく頂戴した。
結局、約束の数分前に戸坂が応接室の扉を開くまでに、新藤はコーヒーをほとんど飲み干してしまった。待たせた謝罪を口にしながら戸坂が歩み寄ってくる。彼の後ろに付いて、また事務員も入室した。先ほどとは別の盆を持っている。テーブル上を一瞥して空になったコーヒーカップを引き上げ、代わりに冷水の入ったグラスを置くと、一礼して部屋を出ていった。
「今日は暑い中、ご足労いただきまして」
「いえ、こちらこそ、貴重なお時間をいただいて……」
戸坂が近づくのに合わせて新藤と部下は立ち上がり、三人は互いに挨拶の言葉を口にした。しかし形式ばったやり取りもそこまでで、戸坂は新藤の向かいのソファに腰掛けると、始めましょうか、とやや気軽な調子で新藤を見た。
対して新藤は、目力を緩めぬまま戸坂を見返し頷く。ここで気を抜いて油断を見せてはならない。戸坂は穏やかだが切れ者だ。巧みな話術でそれと気づかぬうちに主導権を握られてしまう。新藤はそう考えていた。
だが逆に、緊張を悟られるのもよくない。冷静に臨むため、新藤はグラスの水を一口飲んだ。
3.
それぞれ手元の資料に目を落としながら、契約内容を確認していく。はじめの二、三ページについて説明している間、新藤は資料をめくる毎にグラスに口をつけた。外の暑さのせいか自身の気持ちの問題か、やたらと喉が渇いたのだ。
途中、増税の影響や原料費の高騰など周辺の話題に寄り道しながらも、話は順調に進んだ。金額が絡む内容になると新藤は身構えたが、戸坂から何か指摘が入ることもない。自身が普段の落ち着きを取り戻しているのがわかる。ひと息つくように口にした水は、先ほどより少しうまく感じた。
「……ところで、前に来てくれた彼、佐々木くんでしたかね?」
「あ、ええ。佐々木がどうかしましたか?」
「いえ、実はこの間、こちらの都合で少し迷惑をかけてしまいまして。しかし彼に対応してもらって非常に助かったんです」
改めて一言お礼をと思っていて、と戸坂は手元のグラスを手に取る。そして休憩の合図とばかりに、脇に寄せられていた菓子盆を引き新藤たちに勧めた。
一見何気ない話題だが、新藤は戸坂の口元に浮かぶ意味ありげな笑みを見逃さなかった。戸坂が特定の部下について発言するのは珍しい。そもそもいつもきっちり仕事をこなす戸坂が、迷惑をかけたなどという状況にほとんど覚えがなかった。
この話題には何らかの意味があるのではないか。戸坂にとってメリットのある、何かが。
落ち着いていた心臓の音がまた煩くなってくる。新藤はそれを隠すようにグラスの水をゴクリと飲み、平静を装って勧められた菓子に手を伸ばした。
取引相手である戸坂から佐々木の名前を出され、礼を伝えたいと言われたことで、新藤としては佐々木にそれを伝言せねばならないだろう。それが戸坂の目的だとしたら。実は佐々木はスパイで、彼のほうから戸坂へ連絡しても不自然でない状況を作るとか、もしくはこの伝言自体が合図で、佐々木は戸坂と共に何か画策しているとか。
いや、佐々木は墨田商社に長く勤めている真面目な男だ。よく気がつく彼に、新藤も助けられてきた。あの佐々木がこんな裏切るような真似をするはずがない。しかし、そういう人物だからこそ疑われにくいとも考えられる……。
気取られずに戸坂の意図を探るには何と返せばよいか。グラスを持つ新藤の手に無意識に力が入る。中身が少なくなったグラスの内で、解けかけの氷がカランと音を立てた。
「そうそう、先ほどのコーヒーはいかがでしたか?」
新藤が探りを入れるより早く、戸坂は話題を変えてしまった。思考を巡らしていたせいで一瞬何のことかと思ったが、待ち時間に出されたコーヒーを思い出す。
「コーヒー、ですか。美味しくいただきましたが……」
「ああ、それならよかった」
満足気に頷いた戸坂と対称的に、新藤は内心の動揺を悟られないよう必死だった。コーヒーが一体何だというのだ。普通、あえて感想を求めるようなことはしないだろう。何の変哲もない美味いコーヒーだったと思うが。
「あれは実は社員が海外で買ってきたものでして。ぜひ味わっていただきたかったんです」
「はあ……」
そう説明されても、新藤は疑いを拭えない。言葉の裏の意味を汲み取る、自分の経験と実力を信じるがゆえだった。まさかとは思うが、薬の類を盛られた可能性はないか。変わった風味には気がつかなかったが、薬の味が分かってしまった場合に備え、ごまかすために海外土産という言い訳を準備していたのではないか。その考えに至ると、緊張感のせいと思っていた動悸も、薬のせいだったのではと思えてくる。
自覚すると、心音はより大きく新藤の身体に響いた。部下はなんともないのだろうか。ちらりと隣に視線を向けると、部下は平気そうな表情で座り戸坂の話に相槌を打っている。手元の水は、新藤ほどではないが減っていた。
それを見て、新藤にある考えがひらめく。そうだ、水だ。薬を飲んでしまったのなら、水で薄めるのは効果的なはずだ。二人ともそこそこ水を飲んでいるから、まだあまり変化がないのではないか。だからこそ焦った戸坂は、コーヒーをちゃんと飲んだか確認してきたのだ。
思うが早いか、新藤はグラスを口元へ運ぶ。しかし冷たい氷が口元へ触れただけで、喉を通る水分はわずかだ。しまった、水はもうほとんど残っていない。こうしている間にさらに薬が回ってしまうのではないかと新藤は焦る。どうする。いや落ち着け、こんなとき高橋真太郎なら……。
「失礼します」
見計らったかのようなタイミングで事務員が扉をノックする。静かに三人の元へ寄ると、グラスへ減った分の水を追加した。まだたっぷり水と氷の入ったデキャンタを机に残し、一礼してまた静かに退室した。
ありがたい。新藤は早速、補充された水を飲み下す。ちょうどいいときに来てくれて助かった。
いや、だがタイミングが良過ぎはしないだろうか。新藤の脳内に新たな疑惑が浮かんでくる。もしかして、この部屋は外から監視されていたのか。もしくは、戸坂が外へ何らかの合図を送ったのではないか。
新藤ははっとして、持ったままのグラスに目をやった。むしろ水のほうに仕掛けがあったらどうする。コーヒーに意識を向けることで、安全なものと思い込ませた水を大量に摂らせる策であったとしたら。戸坂ならば、それくらいの誘導は難なくやってのけるかもしれない。
だがそのとき戸坂自身がグラスから水を飲んだのを見て、新藤は冷静さを取り戻した。そうだ、この水は目の前で同じデキャンタから全員のグラスに注がれていたのだ。そしてそれを戸坂も口にしている。つまり水に薬は入っていない。あるとしたらやはりコーヒーだ。
思い通りになるものかと、新藤はさらに水を飲む。まさかばれているとは思っていないのだろう、怪訝さを隠せていない戸坂の苦笑が可笑しかった。
やがて残っていた書類の確認が済み、商談は終了した。話を終えるまでに新藤は二杯目の水を飲み干し、デキャンタから再度注いでそれも飲んでしまった。
「それでは、本日はありがとうございました」
「こちらこそ。今後ともよろしくお願いいたします」
新藤は部下とともに、丸岡社をあとにした。体調も変化なく、勝ち誇った表情を浮かべ歩く。戸坂は薬でこちらの判断力を鈍らせ、商談を有利に進めようとでも思っていたのだろうか。その企てに勘付き逃れることができたのだ。巨悪に立ち向かう、あの主人公高橋真太郎みたいじゃないか。大仕事をやり遂げた達成感を胸に、来たときよりも堂々とした足取りで新藤は帰っていった。
4.
「失礼します。墨田商社様、お帰りになりました」
「ああ、君もありがとう。すま��いがグラスの片付けも頼むよ」
新藤たちを会社の入口まで見送り、来客対応の事務員が応接室に戻った。戸坂は疲れを滲ませた顔で書類を揃えている。
「お疲れさまでした。ところで新藤様、随分険しい表情をされていましたが……商談中に何かありました?」
事務員に尋ねられ、戸坂はため息を吐いて肩をすくめた。
「……何も。なんてことない、ただの定例の商談だ。まったくあの人は、ドラマの見すぎなんだよ」
.
5 notes
·
View notes
Text
狸みたいな猫を見た。しばらく用水路を眺めていたかと思ったら、まるまるとした体は林の奥へ消えていった。葉っぱが一枚舞って、木の陰から少年が現れる。さっきの猫はどこへ行ったんだろう。
2022/02/20 @meyou_s
0 notes
Text
冷たい空気の中を歩く。もうこの町を離れてしまうから、並んで河原の写真を撮った。緑や水が自慢の町だけれど、便利なところではないから気軽には会えないかもしれない。鼻をすすりながらスマホを構えているわたしたちを見て可笑しそうに笑って、河原は電車に乗っていってしまった。
2021/12/16 @meyou_s
0 notes
Text
「人はしぬと魂の重さ分軽くなるんだって」君は分厚い本からしばらくぶりに顔を上げる。非科学的だと返すと、ロマンがないと言われた。風でカーテンが膨らんで、教室から君と僕だけ切り取られたみたいだ。柔い光の中で君が笑う。この気持ちもたった21gだなんて、僕には到底思えない。
2021/09/25 @meyou_s
0 notes
Text
「またテレビの調子が悪いんだ。家に見に来てくれないかな」「ああ、もちろんいいよ」「ありがとう。ついでに夕食を食べていきなよ」そう言って笑う君は、どうして何度もテレビが壊れるのか、いつまで気がつかずにいてくれるだろうか。 #ウミガメのスープ
2021/09/07 @meyou_s
0 notes
Text
向日葵
手元から黄色がひらひら舞って、コンクリートの地面に音もなく着地する。広げたノートを膝に乗せて足元に手を伸ばし、拾い上げて元の場所に貼り付けた。
「それ、使ってくれてるんだ」
ノートに影が落ちる。顔を上げると、結花ちゃんが嬉しそうにのぞき込んでいた。
「気に入ってるよ」
ページの端を指でなぞる。誕生日に結花ちゃんがくれた、花びらの形の付箋。色味のないノートの上に花を散らしたみたいで綺麗だ。結花ちゃんはへへ、と声を漏らし、緩む口元を持っていた教科書で隠す。
夏休みの課外授業も今日で終わりだ。日に日につらくなる暑さの中、ふたり並んでベンチに腰掛けて帰りのバスを待っている。
もやもやと揺らぐ道路の先に目をやった結花ちゃんは、首元を軽く扇いだ。
「……木曽路はすべて山の中」
脈絡なく零されたのは授業で扱った小説の冒頭。その語感のよさが、彼女は最近お気に入りらしい。
「ねえ、木曽路もこんなに暑いのかなあ」
髪の束がなびいて、白い首に汗がつたうのが見える。遠くに見える鮮やかな緑に視線をやってみても、涼しい気分にはならなかった。
「どうかなあ。ここよりましかも」
あんまり根拠なく予想したけれど、結花ちゃんはうんうんと大きく頷いて、照りつける太陽を見上げた。
「涼しいなら行ってみたいなあ」
ふたりで座っているバス停なんて、結花ちゃんならいつか本当に軽々と飛び出していってしまいそうだ。ためらうわたしの手の中にはきっと、黄色い花びらだけが散っている。
温い風が肌をなでて、道路脇のメヒシバを揺らした。あ、と隣で背筋が伸びる。
「草いきれ」
覚えたての言葉を使って得意げな顔。数秒の後、おかしくなってふたりで吹き出した。
わたしだって汗をかくのは嫌だ。それでももう少しの間だけ、バスが来なくたっていいと言ったら、結花ちゃんは怒るかな。
思わず目を伏せる。その瞬間、不意に結花ちゃんがわたしの手を取って、小指同士を引っ掛けた。
「いつか一緒に行こうね」
ノートを押さえていた手の平が離れて、ぱらぱらとページが捲れる。端に貼った花びらの付箋は、今度は剥がれ落ちなかった。
今が終わってしまっても、そんないつかが本当に来たらどんなにいいだろう。のどに何か詰まったみたいに声が出なくて、頷くことしかできなかった。
満足げに笑う結花ちゃんが眩しい。花びらの付箋を目印にして、わたしはこれからきっと何度も今日を思い出してしまう。
2021/08/20 @meyou_s
モノガタリ大賞応募作品
0 notes
Text
「わあ、変な形の標本」「見たことない生きものだ」「見て、この足の数!」「すごいね、一体どうやって進むんだろう」「先生は動くところ見たことありますか?」「いいえ、とんでもない!それはもうずっと前に絶滅してしまったんです。かつては地球上に70億も生息していたそうですよ」
2021/06/30 @meyou_s
0 notes
Text
地球上の生き物が増えすぎた。神である私は、少し数を減らしてバランスを取ることにした。「それぞれの種のうち、典型的でないものは消してしまおう」手をかざして念じると、人間がほとんど消えてしまった。「おや、人間を特徴づけるのは理性だと思っていたが、違ったのだろうか」
2021/05/21 @meyou_s
0 notes
Text
姉がソファに寝転んで雑誌を捲っている。何読んでるのと尋ねると、今月号のNewtonの表紙をこちらに向けて、進路考えてるの~と間延びした声。前ドラえもん作りたいとか言ってたな。本気か。遠く行ったら寂しい?と聞くので、ソファ占領されなくて嬉しい、と返したら蹴られた。
2021/04/15 @meyou_s
0 notes
Text
あの子には音が見えるらしい。「あの人の声、黄色、とオレンジかな?綺麗な音で好きだな」隣でステージを見つめながら嬉しそうにしている。共有したくて目を凝らしても、照明の白が眩しいだけだ。鼻から大きく息を吸う。フリージアみたいに爽やかで甘い音は、私には何色にも見えない。
2021/04/04 @meyou_s
0 notes
Text
私は迅速な事件解決がモットーの探偵。情報収集は普段から欠かさない。今マークしているのは、やたらと周囲を気にして歩く怪しげな男だ。自宅を出た彼は、居合わせた隣人と立ち話を始めた。「どうしたんです?キョロキョロして」「いえ、最近ずっと誰かに見られている気がするんです」
2021/03/16 @meyou_s
0 notes
Text
「すごいね、また強くなったね」試合を終え、トレーナーはメッソンをぎゅうと抱きしめた。「でもなかなか進化しないねえ」不思議そうに首を傾げた彼女は、しかしまたすぐ笑顔に戻る。「いいんだよ、かわいいメッソン、ずっとこのままでもいいからね」メッソンの変化がとまった。
2021/03/14 @meyou_s
0 notes
Text
リバーシ (5/5)
「タケダ」
翌朝、僕はニシの声で目を覚ました。覚醒しきらない意識の中で、起こされたのは初めてだなと考える。もう一度名前を呼ばれて目を開けると、ニシが僕を見下ろしていた。
咄嗟に、マットレスの下を探る。手に固いものが触れた。口がカラカラに乾いて、言葉が出てこない。ニシは真っ直ぐに僕を見ていた。
「ニシ、僕は」
部屋に銃声が響いた。
部屋を出た男は、部下からコーヒーを受け取ると、研究員が操作するモニターを覗き込んだ。
「どうかな、うまく検出できたかい?」
「バッチリですよ。本当にお疲れさまでした」
男は満足げに微笑むと、カップに口をつける。
「ああ、わざとリバーシに負けるのが、一番疲れたよ」
終
0 notes
Text
リバーシ (4/5)
昨今の電力需要の増加に対応するために考えられた新しいエネルギー源、それは人間の脳の電気活動だった。何かを思考するとき、感情が動いたとき。人間のあらゆる知的活動には脳の電気活動が不可欠だ。それは細胞間で起こる微細な電位の変化だが、多数の脳細胞に広がる変化は脳波として検出され、研究されてきた。
数年前、検出した電気活動を取り出し、それを増幅することで電気エネルギーとして利用できるように変換する技術が開発された。わずかな電気活動から数万倍ものエネルギーを得られるその画期的な技術は、電気エネルギーの不足という問題を解決する手段になり得るとして、人類共通の研究課題となった。
より安定的に、かつ効率的にエネルギー変換を行つ方法が模索された結果、最も適しているのは大きな感情の変化が起こった際の電気活動を検出することだと明らかになった。
特に効率がいいとされているのは、絶望だ。
美味しいものを食べたときの幸福感、何かを成し遂げた達成感、そして性的興奮に至るまで、様々な感情が研究対象になったが、絶望を感じたときの電気活動をエネルギー源として用いたときの効率の良さには及ばなかった。研究者やそれに協力する企業の間でその事実が知られるようになったのと、電力会社の疲弊が叫ばれるようになったのはほとんど同時期だ。
大企業は、末端の社員たち��エネルギー源を得るための実験体として利用するようになったのだ。材料が絶望であるということから、水面下で非人道的な実験が行われるようになった。一般には電力会社の人員不足は度を超えた過労のためと認識されているが、実際には実験体にされた挙げ句に心を病み、退職する者があとを絶たないというのが現実だった。
ニシが勤める会社も、そのような企業の一つなのだろう。働いている社員たち自身ですら、実験の事実を知っている者は限られているはずだ。ニシはすでに同僚が何人もいなくなったと言っていた。その多くは、知らず知らず実験に組み込まれていたのだ。ニシと同じように。
僕がある研究機関を訪れたのは、数ヶ月前のことだ。建築会社で働いていた僕は、勤務中の事故で同僚を死なせてしまった。故意ではない。しかし死なせた相手は仕事が出来る上に人柄もよく、誰からも好かれる男だった。一方の僕は仕事でミスばかりしていて、社交性もなく、職場で浮いている自覚があった。僕がいくら故意ではないと言っても、信じてもらえないかもしれない。彼を殺して、恨まれることは間違いない。呆然としていた僕に声を掛けてきたのは、見知らぬ白衣の男だった。
見ている人間がいたことへの焦りと驚き、そもそも外部の人間がどこから入ったのかという混乱で何も言えない僕に、男は淡々と説明を始めた。
「ある研究に協力してほしい。そうしてくれれば、あの同僚を殺したのは君だと分からないように、うまく処理しよう」
今思えば胡散臭いことこの上ないが、そのときの僕は藁にもすがる思いだった。男が話す研究の詳細はほとんど頭に入っていなかったが、僕は頷いていた。
そのまま僕は男に同行し、研究施設に入って詳細な説明を受けた。いくらか冷静になった頭で、内容を必死に理解する。電力会社の多忙さについてはもちろん耳にしたことがあった。しかし裏でそんな研究が行われていようとは、そしてその研究に自分が参加することになろうとは想像だにしなかった。
実験の内容は、「他の人間と一ヶ月間を共に過ごし、ある程度の信頼関係を築いた上で相手を射殺する」というものだった。信じた相手に銃口を向けられたそのとき生じた絶望感が、エネルギー源として取り出されるのだ。あまりに非現実的で、正しく認識するのに時間を要したのを覚えている。会社で死んだ同僚のことを思い出した。彼の遺体はどうなったのだろう。うまく処理するとは、どういうことなのだろうか。考えてみても分かるはずもなかったし、目の前の男にそれを尋ねることもできなかった。世界には、僕なんかにはとても抗うことなどできない巨大な力が存在することを初めて認識し、僕には同意する以外の選択肢がなかった。
実験開始予定日の前夜、施設内の一室で睡眠薬を内服して僕は眠りについた。そして次に目を覚ましたときには、実験室の中だった。
元来社交的でなく友人も少ない僕にとって、他人とゼロから信頼関係を築くのは難題だった。しかし実験室内で出会ったニシは、何もかもが丁度いい人物だったのだ。終始真面目で、こんな状況でもパニックになることなく、口数の多くない僕を急かすこともない。条件として示された「ある程度」がどれくらいを指すのか正確には分からないが、ニシとリバーシをしながら過ごしているうちに、信頼のようなものを得ているのを実感していた。
日が経つにつれて、僕の中に新たな悩みが生まれていた。あの真面目でお人好し��男を、僕が殺すのか。三十日目の朝、僕はニシを撃つことができるのだろうか。ニシは、一体どれほどの絶望を感じるのだろうか。
今日のニシの様子を見るに、きっと実験は成功するだろう。一月ぶりにこの部屋から出られ、解放されるのは、もちろん僕が望んでいたことだ。だが、そのためにニシを犠牲にすることへの罪悪感は、拭っても拭いきれない。
別の場所で、友人として出会えればよかったのに。らしくもなく詩的なことを考えてしまったことを自嘲する。閉じていた目を開けて、ニシのほうを見やる。昨日までと変わらず、姿勢良く仰向けで眠っていた。僕はマットレスの下に隠された拳銃にそっと手を触れ、もう一度ゆっくりと目蓋を閉じた。
次 (5/5)
0 notes
Text
リバーシ (3/5)
それから、来る日も来る日も、僕とニシはひたすらにリバーシの対戦をして過ごした。寝て起きてを繰り返しても変化も進展もない状況で、現実を話題にしたくない気持ちがあったのかもしれない。食事と睡眠を除くほとんどの時間、僕たちはテーブルで盤を見つめていた。
「タケダは、他のテーブルゲームも強いのか?」
こんなにやっても勝てないとは、とニシは頬を掻く。
僕が強いというよりは、ニシが弱いのではないかという考えが頭に浮かぶ。しかし彼はしきりに僕の実力を褒めた。一つの試合が終わるたびに、あるいは試合の最中にも、僕は知っている限りのコツのようなものを話す。本当に初めから僕ばかりが勝っていたので、少しでも張り合いが出ればという軽い願望だった。
一つコツを知ると、ニシは生真面目にそれを実践しようとした。彼の番が回ってくるたび、先に聞いた手法が生かせないかと迷っていることが伝わってくる。すぐに実力が伸びるような要領の良さはなかったが、努力家であることは間違いないように思った。そしてその努力の結果はだんだんと勝敗に表れるようになる。
最初は何日目だっただろうか。マスが全て埋まったとき、黒が白をわずかに上回っていた。石を数え終えたニシは「ラッキーで勝ったような気がするな」と笑った。謙遜しながらもその表情には確かに嬉しさが滲んでいて、僕は彼の素直さに少し笑ってしまった。
ニシは真面目な男だった。
当初からもっていた実直な印象は崩れることなく、むしろ愚直と言ってもいいほどだと思った。リバーシでの対戦以外の場面でも、その性格が端々に表れる。
例えば、壁から供給される食事。日が経つにつれて当然のようにそれを享受するようになったが、ニシは食べ終えると必ず食器を几帳面に片付けた。この非現実的な状況で、乱雑に返そうが、あるいは返さずとも構わないくらいに思うのに、彼はその子細もないことをないがしろにしなかった。ときには汚れた皿を拭って返していたことすらもある。
それから、シャワーを浴びて濡れたタオル。洗濯などできないので同じものを繰り返し使うしかない。どうせ不潔になるのだからと適当にベッドのフットボードに掛ける僕に対して、ニシはいつも丁寧にタオルを搾り、シワを伸ばして掛けていた。
朝は大抵ニシのほうが早く目覚め、僕が起きるときにはすでに布団は綺麗に畳まれていた。夕食の後も僕たちはリバーシをやったが、決まった数の試合を終えると床に就く支度をした。僕がだらしないのだと言えばそうなのだが、それにしてもニシはあまりに規則正しく、生真面目だった。
しかし、内心どう思っていたのかは分からないが、僕に同じことを強制するような様子もなかった。むしろ僕のほうが何となく気不味く思い、真似て食器を丁寧に片付けるようになった。それに気がついたニシは、気にさせてしまっただろうかとこちらを心配してくる始末だった。
正直初めは不気味にすら思った。ニシのように真面目で、自分よりも他人の心配をするようなお人好しに、僕はこれまで出会ったことがない。ニシには詳細を話さなかったが、会社にいたのも自分勝手に他人を利用するような人間ばかりだった。どうしても人間の良性を疑ってしまう自分には、彼のような裏表のない存在が理解できなかったのだ。
リバーシをしながら、僕たちは色々な話をした。仕事については、職を失ったと言った僕に気を使ったのか、愚痴を漏らした気不味さからか、ニシが話題に選ぶことはなかったけれど。
ニシはシアターで映画を観るのが好きだと言った。
「へえ、古風だな」
かつては絶え間なく長編の映画が作られ、人々はシアターへ足を運んでいたと聞く。しかしネットワーク上に個人で簡単に見られるコンテンツが溢れるようになってからは、次第にその文化は廃れていった。長い映像は好まれないようになり、短時間で楽しみを得られる動画が量産されるようになった。新しい映画が生み出されなくなると当然のようにシアターの数は減少し、現在残っているところも過去の名作と言われる作品を繰り返し上映するだけの施設と化している。訪れるのは、古典を楽しむ趣味をもつ人間たちだけだ。
「映画は面白いよ」
古風と言われたことに気を悪くする様子もなく、ニシは続けた。
「抽象的な表現になるが、自宅のディスプレイで短い映像を見るのとは違った味わいがある。時間をかけてストーリーが展開されるのを眺めていると、確かに自分の感情が変化するのを感じるんだ。最近作られているものは、見てすぐに内容を理解できるように直接的な表現だけが使われているだろう?どれも似たような抑揚が形式的につけられていて、それが次々に消費されていくだけだ」
ちらりとこちらを見て、現在の流行にも良い点はあると分かっているんだが、と付け加えたニシの用心深さはさすがだ。
「そうか。僕も体験してみたいものだな」
シアターは幼い頃に一度行ったことがあるだけだ。石を裏返してニシの顔に視線を向けると、彼は満足げに笑った。
この部屋で目を覚ますのも二十九回目になった。大雑把な僕には日数を覚えておくのが限界で、リバーシの試合の数を数えることは早い段階で止めてしまった。盤が埋まったら石を片付け、また次の試合を始める。一日に何度も繰り返し、それを何日も繰り返してきた。
最初の頃と比べて、ニシとの対戦は確実に手応えのあるものになっていた。一回の試合にかかる時間もだんだんと延びた。あっという間に白が埋め尽くしていた盤には次第に黒の割合が増え、今日は三回に一回は黒のほうが上回っている。
僕が手に悩む時間も延びたが、考えている途中で結局たかがゲームじゃないかと、適当に石を置いてしまう。そういうときは決まってニシの勝ちになった。
「タケダのおかげだな」
自分の勝利になったときにこそ、ニシは僕に感謝した。決してしつこさのないそれは僕の気分を持ち上げ、ほどよい悔しさが自然と次の対戦へと向かわせる。嫌味のない謙虚さは僕を心地よくさせた。自分の単純さに冷めるようでもあったが、裏表のないニシからの言葉には正面から受け止めさせる力があるような気がした。
「やはり、変わりがないな」
ニシが現状に触れたのはいつぶりだろうか。夕食を済ませて食器を片した後、僕たちは一連の流れでリバーシの盤に向かい合っていた。
「いつまで続くのだろうか」
思い出すと、ニシが分かりやすく不安を示したのは初日以来かもしれない。逞しく見えていた顔は、気の強さから来るのではなく、自らを必死に律しているように思える。そう感じるのはニシの内面を知ったからだろうか。
「僕にも、分からない」
僕はニシの不安げな顔から目を逸して言った。石を置く手も止めない。もう二十九日目なのだ。気を保つためにはそうすることしかできなかった。
「こんな訳のわからない部屋に他人と閉じ込められているんだ。困るどころじゃないよな」
ニシも同じように手は止めなかった。
「だが」
不自然に切られた言葉に、つい顔を上げる。
「私は、共に閉じ込められたのがタケダでよかったと思っているよ」
あなたは冷静で、合理的だ。そう言ったニシの顔は不安が薄れ、穏やかに見えた。今度は彼が僕から視線をずらす。リバーシの盤上、空いているマスはあと二つだ。ニシの石が置かれ、一列が黒く染まった。最後のマスは僕が取ったが、一枚を白く裏返しても、黒が過半数を埋めていることに変わりはなかった。
それが今日の最後の試合になった。順にシャワーを浴びた僕たちはそれぞれベッドに入り、相変わらず眩しい明かりの下で目蓋を閉じる。この部屋に来てから寝付きがよかったことなど一度もないが、今日は特に頭が冴えている。
ようやく明日でこの生活が終わるという安堵感と、そのために為すべきことへの抵抗感が、僕の頭の中で渦巻いていた。
次 (4/5)
0 notes