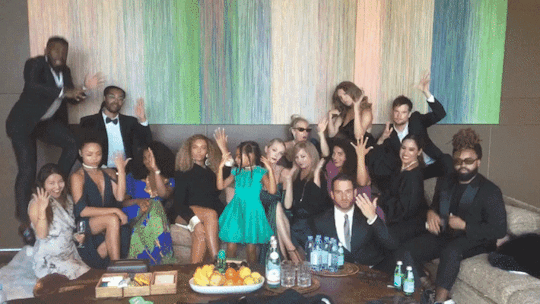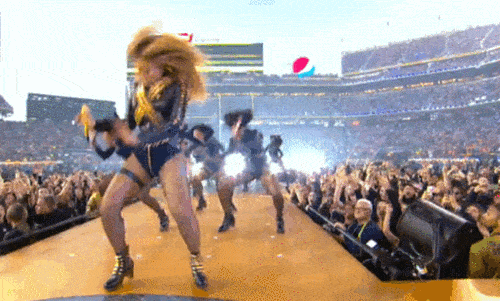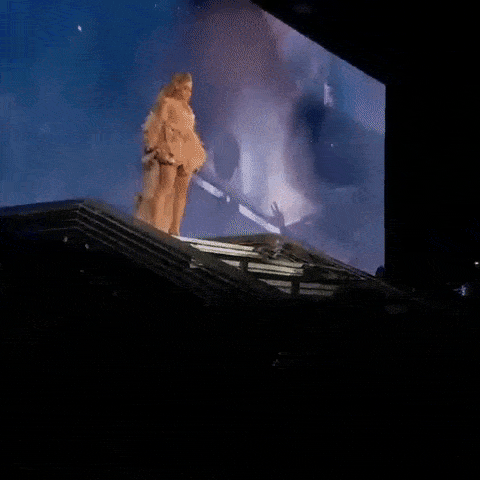Text
「創造のプロセスを管理するということは、それが科学ではないと理解することからはじまる。すべては主観であり、何が正しいかはわからない。何かを生み出すには大きな情熱が必要で、ほとんどのクリエイターは自分のビジョンや流儀が疑われれば、当然ながら傷つく。私は、制作側の人たちと関わる時には、このことをいつも心に留めている。意見や批評を求められたら、制作者がそのプロジェクトに心血を注ぎ込んでいることや、彼らの人生がこの作品にかかっていることを、極端なくらい気にかけるようにしている。 だから決してはじめから否定的なことは言わないし、制作の最終段階でもない限り、細かいことも言わない。正確で俯瞰的な判断力がないことを隠すために、どうでもいいような細かいことにこだわる人は多い。小さなことからはじめる人間は、小さく見える。大筋がぐちゃぐちゃなら、小さなことを直しても意味がないし、重箱の隅をつつくのは時間の無駄だ。」
—『ディズニーCEOが実践する10の原則』ロバート アイガー著
https://a.co/gXRekop
3 notes
·
View notes
Text
「デビッドは今も昔も素晴らしい映画監督だが、テレビドラマの制作者としては失格だった。テレビ番組を制作するには、組織を管理する能力が必要になるが(締め切りに間に合うように脚本を書き上げ、撮影クルーを管理し、すべてをスケジュール通りにきっちり進めなければならない)、デビッドにはその能力がなかった。ドラマの筋書きにも管理能力は必要だ。映画なら観客を二時間釘付けにして、いい体験をさせ、心を躍らせながら映画館をあとにしてもらえばいい。シリーズもののテレビ番組の場合には、視聴者が毎週、また毎シーズン戻ってきてくれなければ困る。」
—『ディズニーCEOが実践する10の原則』ロバート アイガー著
https://a.co/jgSJXPc
2 notes
·
View notes
Text
「鉄のカーテンの向こう側にいる人もまた、普通のアメリカ人と同じ夢を抱いていることを、私は知った。政治家は世界を分断したがり、敵か味方か、善か悪かを決めつけようとするけれど、現実はそれほど単純でないことを、私は知ったのだった。」
—『ディズニーCEOが実践する10の原則』ロバート アイガー著
https://a.co/chHZ3Bg
2 notes
·
View notes
Text
0 notes
Link
“Think about our grandfathers’ generation,” he says, “and what that must have meant to go to World War Two and fight this epic battle against this consummately evil adversary. And to return to your homeland in victory and prosperity and to see the gratitude of your friends and your family and the brotherhood that you shared. You’d carry that with you the rest of your life. But for us younger guys kicking around in 1999, we didn’t have any of that. What are we supposed to do? Get a one-bedroom apartment and furnish it at IKEA?”
0 notes
Quote
「自分の人生ばかり気にしている時期があった。チャンスを得るたびに叫びまくってさ、ガキだったんだよな。大学にいる時は世界を救おうとするのは簡単だったんだ。時間は溢れるほどあって、その上責任も負わなくて済むからね。でもそのうち人生は容赦なくぶつかってくる。その部屋だって食事だってもう保証されてないんだ。払い戻し小切手だってもうなくなる。職を得なきゃいけない、家賃を払わなきゃいけない、車を買って、ケーブル代を払って、一緒に住み始めた彼女はいずれ妻になり、子供が生まれ、出世して、インスタグラムが流行って、レブロンがマイアミを出てって・・・、人生は容赦なくぶつかってくる。人生に振り回され、そのうちまともな感覚が麻痺してしまう。俺はそうだった。でももう違う。だってこれは自分の身にも起こりうることだから、いつ何時でも。犠牲者は俺の親友のあいつだったかもしれない。もう黒人が殺されることを当たり前のように感じてしまう自分にうんざりなんだ。それが警官によるものだろうが、仲間内のことであろうが、そんなのはもう関係ない。とにかくこれは普通じゃないんだ。
Voice of the Voiceless - Hip Hopの和訳: J. Cole - "Be Free" 和訳
1 note
·
View note
Text
ファッションとポストソ連文化 松下隆志
『ゲンロン』本誌の特集でも取り上げたフランス人研究者マルレーヌ・ラリュエルとスウェーデン人研究者マリヤ・エングストロームは、近年の文化においては視覚的なものが言語的なものより優位に立っていると指摘する。「エモティコン」によるコミュニケーションが象徴しているように、視覚的なものがテクストを代替し、しか���言語より多くの意味内容を伝達することができる[★2]。
https://sp.ch.nicovideo.jp/fukuichikankoproject/blomaga/ar1751636
0 notes
Quote
「これはまるで、窓ガラスをこなごなに壊し、その破片を集めてはまた元の姿に戻すことができるような声」(ヒル・イタリー)
「彼女は、おそらく電話帳を読んで歌っても人を感動させられるだろう」(People誌)
マライア・キャリーの選択
0 notes
Quote
マライアが他の歌手と違うのは、こんなところにもある。彼女は、マドンナのように自分自身を改造し続ける必要がなかったし、ホイットニーのように万人受けする音楽へと方向転換しようともしなかった。むしろその逆だった。たとえば、『ミュージック・ボックス』の<ドリームラヴァー>に始まったR&Bの要素はますます強くなった。
マライア・キャリーの選択
0 notes
Quote
アメリカの 「科学捜査班 (Crime Scene Investigation:CSI)」 は元々、テレビドラマ(米2001年~) の名称でした。 放送開始の頃、LABFORは地味な仕事なので 応募者も ほとんどなく、常に 人手不足だったそうです。 ところが、ドラマの大ヒットで CSIが実在する と誤認した就職希望者が殺到したことから、LABFORを改組して捜査権限を持つ部署として CSIを設置する警察署も出て来ています。 ドラマは、DNA鑑定や毒物・薬物の分析結果が 数時間で出るという、現実にはあり得ない展開が 人気の源なのですが、所詮 “臨時的な部署” であることを踏まえておくと、ドラマを 数倍楽しく観ることができます。
子女教育ニュース
0 notes
Text
Time and again, the damaged pride and vanity of the male characters cause them to act without logic and — at their most destructive — extreme violence. Between Walt’s angry desire to be a “pursuer rather than pursued” and Hank’s desperate need to create the illusion of self-sufficiency, it becomes clear that masculinity is twinned with the wholly negative traits of the male characters within the show.
https://m.huffpost.com/us/entry/3945968
0 notes
Quote
ゲーマーゲートに関する書籍を執筆中のジャーナリスト、ブラッド・グラスゴーが行った調査によれば、多くのゲーマーゲート参加者は自分をリベラルだと考えている。オバマに投票した人が多く、死刑反対、公的社会保険賛成など政策的にもリベラル志向が強い。ゲーマー、イコール、オルタナ右翼、というような単純な図式ではないのである。
一方で、ヤノプルスのようにゲーマーゲートからオルタナ右翼へ流れた人も相当数いると考えられる。なぜそうなったかと言えば、一つは冒頭で述べた「気分」の問題だ。ゲーマーゲート以前から、ゲームを巡る状況は少しずつ変化していた。ゲームはサブカルチャーから完全にメインストリームとなり、世界的な一大産業となった。注目度も、動く金も、かつてとは桁違いである。さらにGameSparkの記事にもあるように、かつては男性が圧倒的多数を占めていたゲーマーも、近年では多くの国で男女ほぼ半々となっている。クインのように、ゲーム業界の開発者や管理職にも女性が増えてきているようだ。
http://www.mhatta.org/wp/2016/09/18/alt-right-and-gamergate/
0 notes
Text
「一握りのファンによる少数意見が、インターネットでは大多数の意見に見えてしまうのは何故だろう?
クリスティーナ・ラーマンと南カリフォルニア大学のコンピュータ科学者たちは、そのわけを研究してきた。彼らはこの現象を「多数派幻想」と呼んでいる (中略)ソーシャルネットワークは、特にコンテンツが自由に飛び交うデジタルなネットワークは、大多数の人が同じ意見を持っているような幻想を与えやすいということだ。たとえ、実際にはつながりを多く持つ少数の人たちだけがその意見をシェアしているとしても、大多数がそう思っているような印象を与えてしまう(中略)ということは、一番声の大きいファンを無視した方がいいということだ。ファンはいつも最先端のプラットフォームを通して意見を表明するが、そうしたプラットフォームでは往々にして最も強固で否定的な意見が一番目立ちやすい(中略)
大半の人は商品を買う前にオンラインのレビューを見るが、レビューを残す人は圧倒的に少ない。レビューを書き込む人たちはだいたい、いいにしろ悪いにしろ強い思い入れを持っていて、それをだれかと共有したがっている。ほどほどの意見ならわざわざレビューを書き込まないし、オンラインの議論に参加したりしない。こうした議論に参加する人はそもそも偏りがあると思っていい。
さらに、自称専門家、つまりファンの意見の大半は否定的なものが多いという研究がある。これが問題をさらにややこしくする。「思い入れの強い消費者ほど、目立とうとして低いレーティングをつける傾向がある」と研究者は言う。評価の定まっていない商品やアイデアを認めて自分の評判を危機にさらすより、批判する方が安全だ。たとえば、ある商品について大好きな人と大嫌いな人が集まるグループは、たいてい大嫌いな方に流れる傾向があることがわかっている。しかも、ほどほどの意見の人が集まるグループよりもすぐに、後ろ向きな意見が大勢を占めるようになった。どちらのグループも、平均すれば同じ意見であっても、そのような結果になった。
スーパーファンはそもそも、強い思い入れがあり、その気持を表現するプラットフォームを持つ人たちだ。ひとつの方向に流れが向かうと、ほかのファンたちも勝ち馬に乗ろうとする。批判コメントが殺到すると、それが一握りのファンの意見であることが隠れてしまう。強い思い入れのある少数の人たちが、簡単に議論を支配し会話をゆがめることになる。ほどほどの意見は脇に置かれてしまう。
メイカーズマークの経営陣は、突然世界中が彼らに背を向けたように感じたかもしれないが、炎上は実際にはほんの一握りのファンの意見を反映したものだった可能性は高い。
(『ファンダムレボリューション』p258-260)
0 notes
Text
ファンダムとは、程度の違いはあっても、騙されたふりをするということだ。ファンたちは、その大衆物にまつわるほんの一時的でささいな文脈を、自分に信じ込ませる。それにはおのずと、炎上という要素が組み込まれている。しかし、騙されたふりを演じているうちに、人は現実を相手にしていることを忘れてしまう。現実の人、現実の事業判断、そして現実の生活に関わっていることを、忘れがちになる。
(中略)
企業にとって必要なものとファンが望むものの間には常に相反がある。ひとつのオブジェクトを、ふたつのまったく違う目的を持つグループが分け合っているのだから、当然だ。企業はオブジェクトを使って利益をあげなければならない。そうしなければ、オブジェクトを維持することもできなくなる。ファンはオブジェクトが不変であることを願う。変わらないものに対してファン活動を築きたいからだ。
(中略)
メイカーズマークが突然、通のあいだで価値が下がれば、それまで熱心に支えてきたファンは自分が侮辱されたと感じてしまう。彼らが激怒するのは、商品に手を加えたという事実を超えて、裏切られたという感情が高まるからだ。
ファンはそもそも保守的だ。たとえより良いものでも、イノベーションに抵抗するのが、ファンの特性というものだ。ファンはオブジェクトと親密なつながりを持つ。そのつながりの意味を変える可能性のあるものに対しては、何にでも反対の立場を貫く。たとえ物理的に何も変わらなくても、抵抗するのだ。
マーケターは「お客様は神様です」というフレーズを神聖なものとして祀るが、研究者のスティーブン・ブラウンは、実際は「お客様は右翼的だ」と言う。「保守的で、何にでも反応し、頑固で、変化に抵抗する。イノベーションを毛嫌いする。いつも同じものを欲しがる。お気に入りのものを祀り上げ、そのままの形で永久保存したがる」
(『ファンダムレボリューション』p254-257)
0 notes
Quote
「消費者の時代が始まった。やくざ企業にコケにされるのはもうこりごりだ」
ファンダムレボリューションp253
0 notes