Text
M18とM10の両戦車駆逐車の相対的評価と改善点の提言 (1945)
第805戦車駆逐大隊司令部
APO 464, アメリカ陸軍
1945年6月8日
件名: 戦車駆逐部隊装備
宛先: W.F.ミリス大佐
AGF Board, FAAC
APO 777, アメリカ陸軍
1945年6月6日の貴殿の要請に対し、M10とM18戦車駆逐車の評価および両車の比較について、当方の所見を回答する。
本回答はM10とM18について、以下における当方の私見に基づくものである:
M10 – 中隊長 – 6か月 – 訓練
M10 – 中隊長 – 4か月 – 戦闘
M18 – 中隊長 – 1か月 – 訓練
M18 – 中隊長 – 5か月 – 戦闘
M18 – 大隊作戦参謀 – 4か月 – 戦闘
ベイカー D. ニュートン少佐
第805戦車駆逐大隊司令部
APO 464, アメリカ陸軍
1945年6月8日
-----------------------------------------------------------------
第805戦車駆逐大隊司令部
APO 464, アメリカ陸軍
1945年6月8日
M18とM10の両戦車駆逐車の相対的評価と改善点の提言。
序論
戦闘装備の効率は、該当装備を使用した地形、気象条件、および相対した敵に大きく依存するため、最終的な評価はひとつ以上の上記要因を組み合わせた条件下の経験に基づく、装備の問題点や潜在能力の推定値となる。天候、地形などのすべての組み合わせに対して、装備を試験することは不可能である。したがって状況によってはその発揮可能な能力は推定値となる。またある条件における能力を向上させることは、通常は別の条件での効率を低下させることになる。したがってM10とM18の両戦車駆逐車の優劣を評価する際は、それぞれの長所と短所を比較検討し、おのおのが望ましい性能を発揮できるような改善点を提案する必要がある。
装甲
M10の装甲防御はM18より優れている。20mm徹甲弾は推定400ヤードの距離でM18の(操縦手と副操縦手の前面を覆う)正面装甲を貫通可能である(また実際に貫通している)。これは至近距離ではあるが、20mm耐弾性能を持つ装甲の要望は大きい。徹甲弾はこの戦車駆逐車の正面と側面装甲を容易に貫通する。しかし重量の増加は登攀力、牽引力、操縦性の低下をまねき、この車両の扱いやすさを相殺するため、これ以上の重量増加は望ましくないとも考えられている。
火器
両車両の主兵装は満足できるものではあるが、いずれの機関銃も満足できるものではない。M18の対空機関銃用の銃架はM10のそれより優れたものではあるが、対空・対地両用火器としての機能は期待できない。銃手が露出しすぎているため、地上目標を掃射する用途には適さない。両車両とも、車体前方機銃、可能であれば同軸機銃を装備することが望ましい(いずれも30口径)。
砲塔
砲塔の区画とその機構には、M10とM18のいずれも多くの欠陥が存在する。M10は十分な床面積と乗員が主砲を操作する十分なスペースを持ち、「即応弾ラック」を含む優れた砲弾架を装備しているが、いくつかの場所で危険な砲塔の旋回機構が露出しており、至近距離の敵を確認するための銃眼やペリスコープが備えられておらず、そしてM10戦車駆逐車の最も重大な欠点は、動力旋回装置を備えていないことである。M10で動力旋回装置を装備した敵戦車と突然遭遇する危険に直面した乗員だけが、迅速な砲塔旋回機構の必要性を認識することができる。戦車駆逐車は動力旋回装置を装備していなければならない。
M18は動力旋回装置、方位角表示機(精密照準と長距離射撃に役立つ)、良好な視界を持ち、また全般に砲塔内の装備配置は良好である。欠点は少々窮屈な乗員区画、砲塔乗員用の銃眼や(照準器を備えた砲手用を除く)ペリスコープを欠くこと、そして最大の問題点は、数も少なく扱いにくい弾薬架と、十分な即応弾ラックを備えていないことである。
機動力と操縦性
M18の速度はM10よりはるかに高速ではあるが、これはあまり意味のあるものではない。もっとも重要なのは機動力と操縦性である。M18は扱いやすく、素早く動き、走行はスムーズであり、騒音が少なく、新品であれば相対的なパワーと登攀力に優れている。機動力と操縦性の双方の面で、M18はM10を上回っている;しかしM10には見られないひとつの問題点がM18の機動性を制限している。この車両はM10より若干車幅が広く、最低地上高が低い。これにより岩場での動きが制限され、軟弱な地盤でも行動できるM18の優れた機動力が相殺される。さらにM18はM10より急速に消耗し、最終的にはパワーも登攀力もM10にも劣るようになってしまう。M18は効率の低下を甘んじても、1段または2段低速のギアで取り廻す必要がある。
サスペンションと履帯
M18のサスペンションはM10よりも良好である。大型の転輪は小さな起伏をよく吸収し、乗り心地もスムーズで、転輪の損傷による走行不能の可能性が少なく、より消耗に耐える。M18の(トーションバー方式の)衝撃吸収装置は、転輪の自由な動きを可能とし、M18をM10よりはるかに乱暴に、積極的に扱うことを可能とする。また地雷への耐性も高く、起伏の多い地形での高速走行を可能としたことで、乗員が負傷する可能性も抑えられている。
M10の履帯はM18より優れている。その幅広の履帯は「地面との摩擦力」を利用することに優れている。M18の鋼鉄製履帯は、幅の狭さ、履帯拡張やグロウザーのための装備を欠くこと、硬い地面や凍結した路面での貧弱な牽引力を除けば、すべての面で優れている。履帯の拡張や、適切なグロウザーを装備させるなどの対策が必要である。
優劣
現状の両車両を比較した場合、筆者はM10よりM18戦車駆逐車の優位を挙げるが、いずれの車両も改善が可能であり、適切な改善がなされればいずれも素晴らしい装備となるだろう。
概要
提言する主な改善点:
M10向け:
動力旋回装置の追加。
車体機銃の追加。
ペリスコープの追加。
M18向け:
若干の装甲強化。
速度の低下と出力の増加。
車体機銃の追加。
ペリスコープの追加。
履帯の幅広化。
地上高の増加。
結論
結論としては、戦車駆逐車の高速化は非現実的であり、戦車駆逐車の効率は(M18を基に)速度を捨てて若干の装甲に代え、幅広の履帯を採用して牽引力と登攀力を増大させることで改善が可能である。
ベイカー、D. ニュートン少佐
第805戦車駆逐大隊
大隊幕僚
文書原文
Cpt. Baker D. Newton (1945), M10 & M18 Comparison, TankDestroyer.net, http://tankdestroyer.net/images/stories/ArticlePDFs3/805th_M10__M18_Comparison_2.pdf
2 notes
·
View notes
Text
科学を身近にMaking Science Accessible
Ion Game Designの哲学
科学に参加するのは政府の助成を受けた博士号を持つ専門家だけだというのは、現代の誤謬である。2歳のAdaは、スプーンを落とすと楽しい音がすることを発見した。彼女の科学的発見は、世界中の子供たちが再現することができる。科学が素晴らしいのは、自然法則は普遍的であり、どんな人にも有効であるという点である。
Adaと同じく、筆者もまた科学者である。これは私が学位を持ち、かつてロケット科学者として働いていたからではない。むしろ他の人々が発見した成果を利用し、異なる現象間に相互関係を見出し、それにより物事の仕組みについての知見を増やすことの方が多い。そしてこれこそが科学なのである。科学とはこの宇宙を動かす自然法則を発見し応用するという、人の技なのである。私はこうして学んだことに基づいて現実を再現するため、これらの法則をゲームのルールに変換することを楽しみとしている。
これらの脚注やエッセイに記された内容は、私の知識の範囲内で事実と考えられるものであり、併せて提示されている論理とデータによって検証されたものである。私の活動はWikipediaの原則に基づくものである: その内容に疑問を抱いたり、ルールや事実確認において間違いや時代遅れの知識、そして無効な結論を見つけた場合、ionmg.comのdownloadセクションに置かれたLiving Rulesのノートに、その正しい答えを書き加えてほしい。私は過去40年の間、Living Rulesに関するすべてのコメントに答えることを活動のポリシーとしてきた。自分にはその資格がない、くだらない質問なのではないかと思うことでも、臆さずに発言してほしい。それこそが私たちの発見の航海の一部となるのである。
Phil Eklund, Bios: Mesofauna - Book II, IGD/SMG, 2020.[→]
3 notes
·
View notes
Quote
At CNA, we start every new wargame discussion by asking the sponsor three sets of questions:
1. What is your organization’s desired outcome as a result of wargaming? What do you want wargaming to enable your organization to do?
2. What objective should players pursue in the wargame? What things do you want the players to produce during its execution? What do you want to have in hand at the game’s conclusion?
3. What constraints (“must do”), restraints (“can’t do”), and conditions (“should do,” boundaries) will limit the execution of the wargame?
IS IT A WARGAME? IT DOESN’T MATTER: RIGOROUS WARGAMES VERSUS EFFECTIVE WARGAMING - War on the Rocks
1 note
·
View note
Text
"Scramble for Africa"に起こったこと
本項は「War-Gamers Advent Calendar 2019」の参加記事です。
---------------------------------------------------------------------------
「Scramble for Africaの登場は、2019年のボードゲーム界に突然の大混乱と文化戦争を巻き起こしました」New York Times, 2019/08/01.
2019年2月末、GMT Gamesは「アフリカの探検と植民地化をテーマとした、非常に手軽なユーロ作品」であるScramble for AfricaをP500に追加することを発表しました。しかしわずか2か月後の2019年4月、GMT Gamesは���作の出版取りやめを発表しました。
GMT Gamesは取り下げの理由については「内容に否定的な議論とフィードバックがあった」と述べるにとどまりましたが、その背景にはBordGameGeek(以下BGG)のフォーラムで同作を「植民地主義を肯定的に扱うゲームである」とする議論が発生していたことがあるようです。
2019年12月現在、BGGでいわゆる「炎上」状態となったスレッドのほとんど、そしてScramble for Africaのゲーム情報に関するページ自体も、モデレーターにより削除されてしまっています。本記事では断片的に残された情報を紹介し、2019年のボードゲーム界に突如巻き起こった政治的配慮と表現の問題について記録しておきます。
以下時系列。
2019/02/20 - February 20 Update from GMT: New P500s, Production Updates, and More!
GMTのニュースレターより、P500の更新アナウンス。Scramble for Africaの初登場。
2019/03/16 - Colonialism as a theme for board games
BGGの「植民地主義をボードゲームのテーマとすること」に関する議論のスレッド。どうやら発端はこのスレッドだったようで、3/19頃に議論が炎上。モデレーターが介入し、多数の書き込みが削除されています。
この後にBGGのScramble for Africaのゲームフォーラムを中心に、植民地主義の問題を問う複数のスレッドが立ちあげられた痕跡がうかがえます ( ※フォーラムの検索機能では複数のスレッドがヒットしますが、リンク先のスレッド自体は削除されています ) 。しかし現在、当時のリアルタイムの議論スレッドはほぼ削除されてしまっています。以下はこの削除を生き残った議論スレッドです。
2019/03/27 - [Scramble for Africa] I thought we were past this
プレイヤーの視点が欧州列強のみで、先住民はゲームシステム上は搾取されるためだけに存在している。植民地主義を称賛するゲームになってしまっているのではないか?という問題が争点となっています。
2019/04/06 - P500 Update: Removing Scramble for Africa
GMTのニュースレターより、Scramble for AfricaをP500からの取り下げるとするアナウンス。テーマと内容について議論が発生していたこと、何らかの問い合わせがあったことが報告されています。これに伴い、本作はGMT Gamesのサイト自体から削除されます。発端と思われるフォーラム炎上から、僅か半月ほどでの出来事です。
2019/04/07 - [Scramble for Africa] Further game description from the GMT blog - webcache
GMT Gamesからのゲーム情報削除に際して、ゲーム情報の保存のため立ち上げられたスレッド。冒頭にwebcacheからサルベージされたゲーム情報���引用されています。
2019/04/07 - GMT cancelling the P500 listing for Scramble For Africa
2019/04/07 - [Scramble for Africa] How about a new and better publisher?
2019/04/08 - [Scramble for Africa] The Designer did nothing wrong!
2019/04/10 - Scramble for Africa
GMT GamesのP500撤回を受けた反応のスレッド群。タイトルに[Scramble for Africa]とあるスレッドは、同ゲームのページに設置されていたフォーラム内のスレッドが、ゲームページ削除に伴い一般フォーラムに移動してきたものです。
内容は検閲につながるという憂慮から、差し止めは当然というものまで様々です。
2019/04/13 - A Cancelled Board Game Revealed How Colonialism Inspires and Haunts Games
出版撤回を受けたウェブニュース記事。本件の経過に関する、要領のよいまとめがあります。またここからのリンクで、あるウォーゲームブログが主にシステム面の紹介から本作を擁護する記事をアップしていた事がわかりますが、同ブログは現在削除されています。
2019/08/01 - Should Board Gamers Play the Roles of Racists, Slavers and Nazis?
事件とその周辺の倫理問題に関するNew York Timesの記事。同様の抗議事例として、King Philip’s War (MMP)に対する先住民団体の抗議が紹介されています。また適切な批評メディアが存在しないため、時としてデザイナーへの個人攻撃に発展する場合もあるという踏み込みも。さらに微妙なテーマを扱う先駆者として、Cole Wehrleが西欧視点のテーマをゲーム化する際には「西欧のハイスクールで学んだ以上の視点を提供する必要がある」とコメントしています。
※ Cole Wehrleは、Pax Pamir(グレートゲーム)、An Infamous Traffic(阿片貿易)、John Company(東インド会社)、Root(ファンタジーの対叛乱作戦)などを手掛けたデザイナー。
2019/08/21 - PLAYING GAMES WITH HISTORY: PHILOSOPHERS ON THE ETHICS OF HISTORICAL BOARD GAMES
New York Timesの記事を受け、ボードベームにおける倫理面についての3人の哲学研究者からのエッセイ。それぞれテーマを適切に扱ったゲームの例として、Ghandi (GMT Games), King Philip’s War (MMP), Root (Leder Games)を紹介しています。
1 note
·
View note
Text
読売新聞のウォーゲーム関連記事
先の朝日新聞記事の読売版のつもりで調べてみたのですが、まったく発見できずに挫折しました。
折角ですので関連記事だけでも紹介しておきます。
「[広告]ウォーゲーム エレクトロニクスシリーズ/エポック社」読売新聞,1983/11/29,夕刊,p9.
上半分が映画「ウォー・ゲーム」に絡めて当世パソコン事情について語る三遊亭円丈のエッセイ。下半分に全8作を並べた一面広告。煽りは「現実か、ゲームか?現実の世界とゲームの世界がクロスオーバーすると、まるでメービススの帯のように、渾然一体となった不思議な緊張感が出現する。そんなリアル感覚を体験させます。エポックウォーゲームエレクトロニクス。」
「[海外短波]湾岸戦争卓上ゲーム登場/マレーシア」読売新聞,1990/11/05,朝刊,外電.
※こちらは故あって紙面を確認できず。マレーシア発というのが珍しい。情報求む。
「[いまどきのゲーム]=4 ディプロマシー 知恵と体力の極限に挑戦(連載)」読売新聞,1989/11/05,朝刊,p36.
ボードゲームに関する連載記事より。 「欧州舞台に国盗り合戦 今世紀最高傑作の評」と題したゲーム紹介コラムを併載。 他の回では「モノポリー」「スコットランドヤード」「たんば」「野球盤」「ドラゴンクエスト(ボードゲーム版)」など。珍しいところで海外ゲームのルール翻訳の話題も(第5回,1989/11/12)。
ディプロマシー回は「テレビでディプロマシーというゲームをやる」という仕事をきっかけに、このゲームにはまったという若手舞台俳優、大高洋夫さんのエピソード。前日の一夜漬けインストで本番に挑み、担当はトルコ。「ファミコン若大将の異名を持つ田尻智氏、モノポリー名人の百田郁夫氏らの強力メンバーを見て、大高さんはつぶやいた。 『 オレがこの”メンツ”で生き残れたら一人前だな』」 独伊土対英仏同盟の状況から、ドイツ勝利でゲームは終了。大高さんのトルコは2位に食い込んだとのこと。
1 note
·
View note
Quote
「ウォルフ艦長は、南海で行動するドイツ帝国海軍最後の巡洋艦であるSMSカイザーの甲板から双眼鏡をのぞき込んだ。無線はベルリンから送信された彼への極秘指令を受信していた【謎に包まれた失われた島、レムリアを発見し、ドイツを欧州大戦の勝利へと導く謎の超兵器を持ち帰れ】。どこか遠くのジャングルからはドラムの音が響き、霧に覆われた島の中で何かが蠢いていた……」
没!
こんなストーリーでは駄目だ。プロットは貧困だし、決まり文句が多すぎる。
あの雑誌の編集長から電話が来る前に、この小説を書き上げねば。私の競合相手であるテキサスのボブ・ハワードは、ニューイングランドのラヴクラフトの仲間であり、エドガー・ライス・バローズも彼なら何か面白いものを書けると思っているようだ。
さて、私も仕事に戻るとしよう。レミントンのタイプライターに新しい紙をセットし、コーヒーをもう一杯淹れて、タバコに火をつけこの原稿を終わらせるとしよう。締め切りが迫っているぞ!
Arc of the Kaiser's Last Raider (One Small Step), ルールブック1.0章より
1 note
·
View note
Text
Elusive Victory(GMT) 導入シナリオメモ
難易度順。白紙状態ならEV5,4から、SAMまで手を付けたいならEV6,8から、全要素を試してみたいならEV3から手を付けるのがお勧め。
EV5:War of Attrition(空戦)
空戦シナリオ。飛行と空戦ルールの学習用。このシステムで空戦シナリオは不毛といえば不毛なので、経験者なら飛ばしても問題なし。
EV4:Alert Five(空戦・爆撃)
EAFによる対地攻撃シナリオ。攻撃任務のプロットと爆撃の学習用。BDAが省略されているため、ルール、時間的にもプレイは容易。
EV6:Recon in Force(空戦・偵察・SAM)
EAFによる偵察シナリオ。派手さには欠けるものの、SAMの登場するシナリオでは最もSAMサイト数が少ないため、SAMの運用練習にお勧め。
EV8:Shattered Glass(空戦・偵察・SAM)
個人的にお勧めなIAFによる偵察シナリオ。地味な偵察シナリオと見せかけて、カイロ国際空港を偵察したついでに、大統領官邸ヘクスを超音速で飛行してガラスを割って帰ってくるという馬鹿シナリオ。実際に成功した模様。(1969/6/17)
EV3:Egyptian Phoenix(空戦・爆撃・SAM)
EAFによる対地攻撃シナリオ。貧弱とはいえストライクパッケージらしきものが登場。
EV2:Fighting Back(空戦・相互爆撃・SAM)
EVの新要素となる相互攻撃シナリオ。特にIAF側は近接支援と飛行場攻撃を同時に実施する必要があり、部隊の配分で悩める。またHawkも登場して両軍のSAMが乱れ飛ぶ。
2 notes
·
View notes
Quote
I feel like Phil's games are boutique creations. They delve deeply into one particular topic of science/history/sociology and actually explore that topic through the medium of boardgames. For those who are willing to make the deep dive, Phil's games can reward you with insights, amusing thought experiments and so many other valuable expenditures of your time.
One final thank you, Bios Genesis 2nd edition
Bios Genesis 2nd edition, Kickstarterプロジェクト最後のコメントより。
個人的にPhilのゲームに期待しているのは、まさにこの「あるテーマのゲームを媒体とした探求」なので我が意を得たり、というところ。
0 notes
Quote
こうしてみると、精密さを気にしなければ、DiFやWLのような抽象度の高いゲームの方が現実に近いように感じるのは(他の分野の多くのゲームでも見られる現象とはいえ)皮肉なことのように思えます。
空戦ゲーム、ここがおかしい
2 notes
·
View notes
Text
本邦ウォーゲーム黎明期の朝日新聞記事
本記事は「Muat Attack」内で話題となった、本邦ウォーゲーム黎明期の朝日新聞記事の紹介です。AMIさんの情報で記事がほぼ特定されましたので、昼休みに調べてきました。出典が記事データベースのため記事自体の転載は控えますが、内容は面白かったので概要を紹介しておきます。
※2019/02/27 時系列順に再編しました。
「ブーム 戦争ごっこ 子どもは夢中 教室内でも おとなは複雑」朝日新聞,1972/10/12,東京朝刊,p22.
こちらは検索できた中では、最古のミニチュア・ウォーゲーム(記事中では「戦争ゲーム」)の記事。10月10日に池袋「パルコ」屋上で行われたイベントを報じるもの。「それやっつけろ ヘルメット姿でドイツ軍と連合軍にわかれてゲームに熱中する子どもたち」というキャプションで、ジオラマの盤面を囲む写真あり。
「半年前ぐらいから日本のおもちゃ問屋が紹介したもの」「子どもたちのプラスチックモデル・ブームにのり、東京を中心に広がっている」との紹介。イベントは「5人1組のチームを公募し、自作の「兵器」を持寄り、第二次大戦のドイツ軍と連合軍にわかれての公開戦」。パルコ営業企画部は「十日のデータを分析して、どこまでブームが伸びるかを見きわめたうえ”全日本大会”など次回の計画を練っている」とのこと。
上記のコスプレ写真に加えて「あわれむより殺せ、さ」「こいつは勲章ものだ」などとキャッチーなセリフが散りばめられ、全体的に戦争を知らない子どもたちが、無邪気な遊びに興じる姿に批判的な論調です。
また少々意外だったのですが、この時期のウォーゲームに関する記事はこの一件のみ。1972年のこの記事から次の1981年の記事まで、ミニチュア、ボードともウォーゲームに関する記事は途絶えているようです。朝日新聞は一撃で目的を果たした、ということでしょうか。
「ヤングの遊びにも“軍事色”戦争ゲームが大うけ 首かしげ 不安がる声も」朝日新聞,1981/6/19,東京朝刊,p22.
こちらが本調査の発端となった記事。社会面の紙面1/4ほどを使った比較的扱いの大きな記事で、「東京国際玩具見本市」に今回初めて「戦争ゲーム」が登場したことを報じています。社名不詳の展示ブースの写真あり。写真が荒く判別が困難ですが、辛うじて特徴的な「Stalingrad(AH)」と「The Guns of August(AH)」らしき箱絵が判別できました。TGoA(1981)は当時最新作ですね。また「タクテクス」の創刊がこの年の12月でした。
こうした戦争ゲームは「日本には十年ほど前に入った。ずっとごく一部の愛好家にしかうけなかったが、昨年後半から大学生を中心にファン層が広がり始めた」とのこと。各社の出店状況とゲーム自体の解説が中心で、下記のコメントを除けば本文での批判は薄目です。
記事の最後でミステリ翻訳家の田中潤司が「純粋にゲームとして楽しんでいる」として肯定的なコメント。そして「戦争ゲームも、知的競技には違いないので、それ自体はどうということはない。ただ沖縄戦といったものとなると、ゲームとしてやれる無神経さが気になる。あそこで何が行われたか、といった歴史的事実を知っていたら、とてもゲームなどやる気にはなれないでしょうね」という野坂昭如のコメントで記事を〆ています。
政治性抑えめのビジネス、文化記事と見せかけて、最後に野坂昭如で殴りつけてくる構成はさすがですね(褒めてます)。
個人的に面白かったのが各社の参入状況で、さてそれぞれ何社のことでしょう?
A社:昨夏から輸入を開始。50数種を並べて実演つき。
B社:今春から輸入を開始。80種余りを展示し、マーチを流しての派手な宣伝。
C社:昨年後半から輸入を開始。20種近くを展示。
D,E社:それぞれ数種類を独自に開発。夏休み発売を予定している。
「フジ三太郎」朝日新聞,1981/6/20,東京朝刊,p23.
1コマ目:「いま大うけ「戦争ゲーム」」マップを前にルール読む広げる三太郎
2コマ目:息子と二人で盤面をにらむ様子
3コマ目:番外から「ごはんですよ~」三太郎「終わらせようか」
4コマ目:マップ上にキノコ雲オブジェを置いて立ち去る父子
こちらは「フジ三太郎」ウォーゲーム回。前日の上記記事を受けての時事ネタと思われますが、記事の写真にはなかったコンポーネントの内容も、さほど違和感のないイラストで漫画に登場。「ウォーゲームはこういうもの」という下地が既にあったことをうかがわせます。
「戦争は元々無神経_話題 」朝日新聞,1982/6/24,東京朝刊,p7.
※2019/02/27追記記事。
「二つのサイコロを振って”七”の目が二回続けて出れば、英軍の駆逐艦シェフィールドは撃沈」という「米国シカゴのおもちゃメーカーが売り出した「フォークランド紛争ゲーム」」を「信じ難い無神経」として政府に輸入禁止を求める英下院議員の話題を紹介した海外時事コラム。そんな話題もありました。
「「図上戦」に若者人気 歴史・SF・ファンタジー シミュレーションゲーム 」朝日新聞,1982/11/19,東京朝刊,p20.
※2019/02/27追記記事。
地域面(東京)の5段にわたる記事。「仕事や授業を終えたサラリーマン、学生がシミュレーションゲームに熱中する。午前零時をすぎてもなお続く=豊島区東池袋2丁目のレック・カンパニーで」というゲームを囲む写真有り。
「歴史上や空想の戦い、紛争をゲーム化したシミュレーションゲームが若者を中心に急速に広がっている」として、レック・カンパニーと「ゲーム制作者の鈴木銀一郎さん」への取材から「シミュレーションゲーム」を紹介する記事。「(前略)日本では八年ごろ前、輸入されたが、一年前「関ケ原」「ガンダム」などの国産ゲームが出てからブームのきざしがみえてきた」という国産ゲームを中心としたブームを受けたもの。前年末に専門誌「タクテクス」が刊行されたが、創刊1、2号はプレミア価格でファン同士で取引されているという話題も。
最後は「しかし戦争ものが多いうえ、ゲームに数時間かかるので、受験世代の親には嫌われものだ。「ゲームを母親に焼かれちゃった」という中学生もいる」と締め。批判的な部分はこのくらいで、戦争をほとんど表に出さず「歴史の追体験」をさせる珍しい娯楽、という論調です。
「ウォーゲーム 現代戦争症候群(いまふういくさもよう) 8・15を前に」朝日新聞,1984/8/9,東京朝刊,p22.
※2018/05/28追記記事
終戦記念日に向けた連載コラムの第1回より。「若者を熱くする『遊び』」という煽りで、ウォーゲームとそれに興じる若者の声を紹介。
部隊内のウォーゲームクラブ「A88」で活動する陸上自衛隊第7師団の一等陸士。お気に入りのゲームは「スコードリーダー」。「最高ですよ。部隊や銃の配置など実戦面でゲームが役立つ。指揮官の立場がよくわかる」と軍事訓練を強調したコメントを紹介。
「関東大学ウォーゲーム連盟」理事長で「東大ボードゲーム研究会」会長の大学生。自ら考案したゲームをメーカーに持ち込み、当たれば数千万円の収入が見込まれる、と「商魂もからむ」紹介。同連盟は早大、立教大、東海大、茨城大など12大学のサークルが所属し、この夏にノルマンディー戦を題材にした3泊4日のゲーム合宿を実施したとのこと。
信用金庫から転職したという、ゲーム雑誌「タクテクス」編集長斉藤純氏のコメント。「戦争をヒステリックに騒ぐのでなく、冷静に見つめ、考えるべきなんですが、そこが理解されずにトラブルが起きてしまう」
ゲーム会場としていた青少年会館の使用を禁じられた「岐阜ゲーマーズフォーラム」会長の若者。「当館の設置目的である青少年の健全育成、社会教育の振興になじまない」という通達に「『なぜ、そんなに目クジラをたてるの』と言いたげだ」と記者のコメント。
最後に競技人口を6万人、高校生3万、大学生2万、中学生ら1万と紹介。どんな調査結果なのか気になりますが、典拠不明。「(前略)太平洋戦争に題材をとったものも多い。”戦争ごっこ”へ走る若者は、後を絶たない。」として〆。
「無神経「朝鮮戦争ゲーム」商標登録不許可を申請 大韓弁理士会」朝日新聞,1984/11/13,東京朝刊,p22.
ついでに発禁だ、販売停止だと憶測飛び交う「朝鮮戦争(EP)」の記事も確認してきました。訴えたのは韓国の弁護士組織「大韓弁理士会」で、特許庁に商標登録の取り消しを求めるものでした。
エポック社のコメントは「(前略)不幸な戦争を正しく認識してもらうためのもので、単なるおもちゃではない。しかし一部からでも好ましくないとの声があれば、商標登録について異議に抗弁する意思もない。ゲームは既に製造は中止している。」というもの。もう初期ロットは売り切ったし、放置するから好きにして、というところでしょうか。
「朝鮮戦争」の発売月は不明ですが、「タクテクス」の「内外ゲームガイド 新製品ニュース」で紹介されたのが15号(1984年5月発行)ですから、かなり素早い動きだったのですね。ちなみに記事で言及されていますが、6,000セット販売したとのこと。一年未満でこの個数というのも、現在では考えられない規模の市場です。
※2019/02/27追記
また本件について、新聞記事から外れます���関連情報の提供がありましたのでリンクしておきます。匿名証言ですが、朝鮮総連へ説明に赴いた方のコメントがあります。「第11回ちはら会レポート~朝鮮戦争(EP/SS)」
「人気のウオー・ゲーム(青鉛筆)」朝日新聞,1988/3/28,朝刊,p31.
※2018/05/28追記記事
「(前略)国際問題にもなりかねないような物騒な想定を高度なすごろく遊びにしたシミュレーション・ウオー・ゲーム「自衛隊編」が、人気を集めている」というコラム。「ルールは軍事専門家も驚くほど細かい」「自衛隊員やソ連大使館筋からの注文も舞い込んだといい、思わぬ反響に会社側は、「?」。 」
メーカーは「東京都港区のゲーム製造会社」でタイトルも微妙ですが、前年にスタートしたアドテクノス「SDFシリーズ」の話題と思われます。300字程度の面白コラムという程度の扱いで、批判といっても引用の「物騒な想定云々」程度。Wikipediaにあるような「朝日新聞から名指しで批判された」というほどのことはありませんでした。
4 notes
·
View notes
Photo
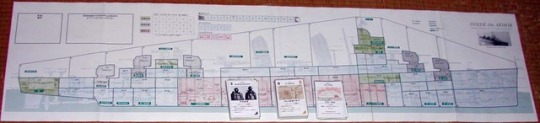
Inside the Armor 2017 v2 testplay kit Japanese localize
2 notes
·
View notes
Link
U.S. Army Center of Military History より夏の新刊。
2 notes
·
View notes
Text
Bios Genesis
A. これは一体何のゲームなのか?
1-4名のプレイヤーは、地球誕生直後の有機化合物を表す、最大3種のバイオント・トークンを所持してゲームを開始する。アミノ酸(赤プレイヤー)は代謝をおこない、脂質(黄プレイヤー)は細胞を形成し、色素(緑プレイヤー)はエネルギーの吸収と貯蔵をつかさどり、核酸(青プレイヤー)は鋳型複製をつかさどる。 そしてこれらは生命の起源となる二つのゴールを目指す: ひとつは自己触媒的生命Autocatalytic Life(自身の組織を再生してはいるが、複製には至っていない代謝サイクル) 、もうひとつはダーウィン的生命Darwinian Life(RNAワールドで鋳型複製をおこなう生命)である。警告するが、これは冷酷なサバイバルのゲームである。C3にあるように、各プレイヤーは競争より協力を選択するだろう。より穏やかなバリアントがC4に記載されている。
0 notes
