Photo

連載:aromatopia「するぶ植物雑話 第10回 「大島紬と養蚕」
奄美の伝統工芸品、大島紬と植物にちなんだお話を、アロマテラピーと自然療法の専門誌 aromatopia (フレグランスジャーナル社)に連載しております。
「するぶ植物雑話」、今回のテーマは「お蚕さまとクワ」。島では、ちょうどクワの実(マルベリー)がたわわに実ってます。たくさん摘んで、そのまま食べたり、ジャムにしたリ楽しんでいます。大島紬に関わるのはお蚕様の好物であるクワの葉。
お着物の好きな方も、植物に興味がある方も、奄美大島に興味がある方も、ぜひご一読ください。
因みに、153号(2019/4/25発行)の特集は「スポーツとアロマテラピー」。東京オリンピックを1年後に控えておりますが、アスリートへのアロマテラピーの可能性について専門家のアプローチが紹介されています。
3 notes
·
View notes
Photo

アロマセラピーと植物療法の専門雑誌・aromatopia152号(フレグランスジャーナル社 2019/2/25発行)のコラム「するぶ植物雑話」では、「大島紬と泥染め」と題し、春の初めに咲く白い花が印象的なシャリンバイを取り上げました。
テーチ木という方言名をもつほど地元では馴染みのある植物で、種を蒔いてからの成長が早いため、我が家でも防風林として畑の周りに植えています。このシャリンバイは、本場奄美大島紬に特徴的な染色法・泥染めにどのように利用されていいるのでしょうか。
ぜひ、お手にとってご覧ください。
1 note
·
View note
Photo

連載:aromatopia「するぶ植物雑話:第8回 「お正月と大島紬」
アロマセラピーと植物療法の専門雑誌・aromatopiaにて、コラム「するぶ植物雑話」を連載しています。
151号(2019/12/25発行)では、「お正月と大島紬」と題して、奄美大島の伝統工芸品・大島紬にまつわる奄美大島ならではのお正月の様子を伝えています。
1 note
·
View note
Photo

連載:aromatopia「するぶ植物雑話:第7回 「大島紬の伝統柄 龍郷柄と秋名バラ柄」
アロマセラピーと植物療法の専門雑誌・aromatopia150号(2018/10/25発行)から、コラム「するぶ植物雑話」のテーマに奄美大島の伝統工芸品・大島紬を取り上げています。
するぶ集落のある龍郷町は、大島紬の発祥の地として知られています。今回は「大島紬の伝統柄 龍郷柄と秋名バラ柄」と題し、奄美大島に馴染み深い植物や自然、生活の風景にちなんだ着物の柄についてのお話を載せています。
0 notes
Photo


くさび石
どれほど一般的だったのか、真意のほどは定かではありませんが
「枝サンゴは焼いて石灰をつくる。それは藍建てに、また黒砂糖つくりに、なくてはならないものであった。サンゴのもつアルカリ性がなくては藍としての発色も、砂糖という名のものも生まれなかっただろう。
サンゴはまた、その適当なものは台所の大根おろしにする石でもあった。くさび石がそれである。きめこまかな年輪のような、深いひだひだの美しい線をもつ。このくさび石で私たちは大根を、とろろ芋をおろして食膳をかざった。」「奄美女性誌」長田須磨著 農山漁村文化協会 p207−208
0 notes
Photo

今までに伝え聞いたこと
するぶ集落にお住いの方を中心に、近隣の方々に身近な植物の活用法について伺っています。食材として、建材や道具作りの材料として、または薬草として、こどもの遊び道具作りにと、その用途は様々です。
いろいろなお話を聞きながら、世代だけでなく、家庭環境(ご実家や嫁ぎ先の習慣や家族構成など)によって、随分思い出や記憶が違うと感じます。現在でも、ジャムやお漬物、味噌や梅干し、果実酒におやつと何でも手作りする家庭もあれば、そうでない家庭もあるのだから当たり前と言ったら当たり前ですが。
その昔は手作りしないと手に入らないので作るしかないという時代だったのでしょうが、そうではなくなった今も、季節ごとに収穫できるものを十分に活かすために保存食にしていたり、家族に手作りのものを食べさせたい、こどもや孫たちにさらには地域の人たちにこのシマの伝統を伝えたいと言う思いで丁寧な手仕事を続けられていることが、私が伝え聞くことができることなのです。
帰り際に「これをお土産に持って行きなさい」と袋いっぱいにお菓子やおかず、野菜や果物などを分けていただきます。初めのうちはご馳走になったものが美味しければ「どうやって作るんですか」と気軽に聞いていましたが、仕込みから、寝かせて美味しく食べられるまで3年かかるものがあり驚きました。本当に手間暇、愛情をかけた品々なのです。さらに「鰹節はどこどこ商店で1本を削ってもらうといい」「黒糖はOO製糖のものがおいしい」「ピーナッツ粉は自分でよく炒ったものをすりなさい」とこだわった素材をつかったものばかり、美味しいはずです。植物を使った知恵は、シマの中に生きる思いやりの心と一緒につたえられていることを改めて感じました。
また同時に、植物を使った暮らしの知恵が失われつつあることも感じずにはいられません。それは、私たちの生活様式や価値観が変わってきたから、また開発や乱獲などで植物資源が失われつつあるからなど理由は様々です。
連載しているコラムのためにインタビューをさせていただくときには、下調べに関連する書籍を何冊か読んで、この季節にはこんな話を聞けるのではないかと質問を準備して望んでいます。
例えば「龍郷町誌 民族編」(鹿児島県大島郡龍郷町 昭和63年 発行)には、日常食、行事食、調味料など食事に関する情報や民間療法についての記載があり、参考にしています。ところが、お話を聞きに行くと自分の親や祖父母はしていた���れど、自分は子供のとき見ただけというような記憶に残るだけのことも多くあったのです。龍郷町誌が発行された30年ほど前、聞き取り調査に協力してくださった方々は明治生まれが多く、情報が1世代前のものだったからかもしれません。
本土と島の人々の行き来が容易になり、島に居ながらにして世界中の情報が簡単に手に入るようになり価値観が変わってくるのは当たり前のことです。廃れていった行事の中には農業に関わるものも多く、農業に従事する人が減れば関連する行事が減るのも仕方がないということを聞いたことがあります。
これからも暮らしが変容していく中、伝え聞いたことから何を残して行けるのでしょうか。共有していただいた話を自分というフィルターを通して、どのように発信していくのか、ゆっくり考えていきたいと思います。
1 note
·
View note
Photo







梅雨のソテツと茶請け味噌
梅雨に入ると、ソテツは受粉の季節を迎えます。ソテツには雄株と雌株がありますが、雄株の中心部が大きく伸びてきて花粉を飛ばします。葉に白く粉が吹いているようになっているのが花粉です。花粉が雌株に届いて上手く受粉ができると、雌株の奥の方にソテツの小さな実がつきます。秋になり、これが赤い実になるまで待ちます。ナリ(ソテツの実)を利用したナリ味噌やナリ粉を作るためには、雄株の先を手折って、雌株にかざして人工受粉をさせます。雨が降ると花粉が流れてしまうので、晴れ間を狙って行うそうです。
種下ろし(たねおろし)という豊年祭で、踊られる八月踊りの歌詞には
「海端の蘇鉄 石抱しゅて育でり 寄て来玉黄金 抱しゅて育でそ(海辺のソテツは石を抱き込んで育つように、かわいい子供は大切に抱いて育てなさいよ)」と歌われています。ソテツが赤い実を抱く姿をみると、この歌を思い出して愛おしく感じられます。
さて、2月上旬に仕込んだナリ味噌が仕上りました。仕込んで4,5ヶ月、早ければ3ヶ月ほどで出来上がるそうです。
蓋を開けてみると、お醤油のような香ばしい香りがしています。このままで食べることは少なく、豚みそ、魚(ゆ)みそ、またはお茶請け用みそに仕上げていただきます。
まずは、教えていただいたレシピに従って、お茶請け用みそをつくってみました。
ナリ味噌 3kg
梅酒 1合
ザラメ1kg
鰹節 1本(削りたてがよい)
落下生 400g(茶色の皮付きのまま、フライパンで炒ってミキサーで砕く)
上記の材料をよく混ぜるだけです。
量が多いので、1kgでつくってみました。鰹節は、1本必要なかったので細かく削られたものを購入しました。落花生は粉に引いたものも販売されていて、実際、購入時にもそちらを勧められましたが、教えていただいたレシピ通り炒ってから砕きました。ピーナツはあまり細かくしすぎず、歯ごたえが残っている方が美味しいそうです。
出来上がったものは、タッパー(密閉容器)につめて冷蔵庫で保存するようにとのことです。
0 notes
Photo








シマの梅雨
5月の大型連休が終わると、早々梅雨入りをする奄美大島。この季節ならではの植物を楽しめます。 ご近所を散歩していて見つけた植物をご紹介します。
こうやって、雨が滴った姿が美しい梅雨の花を集めてみると、白い花が多いことがわかります。曇り空にも映えるようにでしょうか。
まずはショウガ科のクマタケランAlpinia formosana とサネン(ゲットウ Alpinia speciosa)。この2種はそっくりですが、花が小さく上向きに花穂をつける物がクマタケラン、花が大きく花穂が下に垂れ下がるのがサネンです。花が咲く前から、よく見ると花穂の茎の角度が違います。
花の形もよく見ると違いますが、花が付いていないと、なかなか見分けがつきません。実際には葉の幅の広い方がクマタケラン、やや細い方がサネンと違いがあり、クマタケランの大きな葉は、カシャ餅と呼ばれるよもぎ餅を包むのに、また、ふくらかんという蒸しパンを蒸す時に使われます。クマタケランの香りが移って、お菓子がとても良い香りになります。他にも、お料理の下に敷いて保存性を高めたりもするそうです。
シマ(集落)でお話を伺うと、サネンには雄株と雌株があって、クマタケランを雌株で良い香りをもたらし、サネンは雄株でこれでお餅を包むと風味が悪く、苦味があるといいます。
梅雨の季節に賑やかに白い花をつけるのは、ツバキ科のイジュSchima superbaです。まん丸の蕾から開いた花も可愛らしいですが、イジュの活用法は木材の利用です。硬くて虫にも強い建材として利用され、奄美大島では高倉の柱に使われたと聞きました。ちなみに、インドネシアでは、花や実を民間療法に用いるそうです。
夏の楽しみを運んでくれるのは、フトモモ科のバンシロウ(グアバ)Psidium guajava
です。夏は実をナマ食したり、スムージに入れたり、ジャムを作ったりと美味しく頂いています。葉はお茶にして高血圧にいいとも聞きました。
アカネ科のコンロンカ Mussaenda parviflora は、白く花びらのように見えるところが萼だそうです。雨の山でよく目立ちっていました。
6月下旬、雨の合間に夏空が広がってくると梅雨明け間近です。花々が終わり実をつけ、種をつけています。
0 notes
Photo

連載:aromatopia 148号 コラム するぶ植物雑話⑤「懐かしい味とシマの梅雨」
奄美大島では5月上旬に梅雨入りし、青々したソテツの若葉がしっとりと雨で濡れています。そして6月も半ばを過ぎると、ナリ(ソテツの実)を実らせるための受粉の季節になります。
5/25発売のアロマセラピーと植物療法の専門雑誌・aromatopia148号では、「懐かしい味とシマの梅雨」と題し、梅雨に楽しめるシマの植物について、またソテツの栽培・収穫・製粉に携わっている方に伺ったお話を載せています。
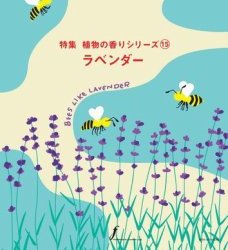
さらに、併せて見ていただきたい記事があります。
朝日新聞DIGITAL(2018.5.26)でも、ナリを今も食材として活用されている方の話が紹介されていました。「ナリと呼ばれるソテツの実とナリ粉を作る様子」を動画で紹介しています。(*無料登録会員になると、全文を読むことができます)
→(食紀行)島民を救った赤い「宝」次世代へ ソテツ@鹿児島県奄美大島
https://www.asahi.com/articles/ASL5R5QVQL5RTLTB013.html
次世代へ繋ぎたいソテツの貴重な知識、次世代に込められた思いとともに受け止めていきたいです。
0 notes
Photo
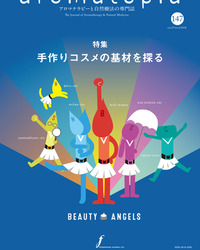
アロマセラピーと植物療法の専門雑誌・aromatopiaに「するぶ植物雑話」と題して連載させていただいています。147号(2017/3/25発行)では、「野遊びとシマの春」と題して、幼少時に身近だった野草の話を聞きました。
0 notes
Photo



タンポポとそっくりさん
タンポポと言えば、多くは帰化植物であるセイヨウタンポポ(西洋蒲公英 Taraxacum officinale キク科)を指し、幼少期から馴染みのある春の植物のひとつです。黄色い花と、手折ると茎から滴る白い乳液、真っ白な綿毛を連想します。ところが、近所を散歩して見かけるのは白花ばかり。島内で黄花を見かけることもありますが、この辺りには少ないようです。こちらはシロバナタンポポ(白花蒲公英、学名: Taraxacum albidum キク科)と呼ばれています。
セイヨウタンポポと和種のタンポポの見分け方は総苞片が反っくり返る、反っくり返らないかだと言われますが、シロバナタンポポでは総苞片が反り返っているものもないものあり、はっきりしません。
タンポポのそっくりさんと言えば、一般にブタナ(豚菜、学名:Hypochaeris radicata キク科)が挙げられますが、先日こんな話を聞きました。もうすぐ90歳を迎えるご婦人が幼稚園教諭をしていた当時の名瀬市内には、タンポポがあまり自生していませんでした。園児たちがオニタビラコ(鬼田平子 Youngia japonica キク科)を見て「タンポポだ」と言っていたそうです。タンポポを見せてあげたいと思い、東京を旅行した時に綿毛を採ってきて園庭や自宅の庭などに撒いたそうです。数年はタンポポが咲きましたが、その後は姿を見なくなったといいます。
奄美の土壌や気候に合わなかったのでしょうか?
以前暮らしていた香港でもタンポポがほとんど自生していなくて、わざわざ種が蒔かれ、花壇に一列に並んで育てられているのを見たことがあります。
下の写真が花の付いてない時のタンポポとオニタビラコです。ロゼット状の葉がそっくりですが、葉の先端が矢印のように三角形になっている方がシロバナタンポポです。引き抜いてみると主根をもつタンポポと、ひげ根をもち抜きやすいオニタビラコという違いがあります。もちろん、花が咲けばその違いは一目瞭然です。


奄美群島生物資源webデータベースによると、民間療法でセイヨウタンポポが「利尿、解毒の作用があり、根または全草を、健胃、強壮、緩下剤、発汗、解熱、にきびや乾癬などの皮膚疾患、骨関節症や痛風の関節炎、胆石の予防、二日酔い、催乳に用いる。」とありましたが、実際によく使っているという方にはまだ出会っていません。
ちなみに、よく見かけるオニタビラコは奄美大島の方言で「タンポポ」と呼ぶことがあり、民間療法での利用方法もあるそうです。「全草に、解熱、解毒、消腫、止痛作用があり、薬疹、食中毒、感冒、乳腺炎、リウマチ性の関節炎、アレルギー性の喘息に、のどの痛み、乳腺炎、結膜炎、尿路感染に、煎服または生の青汁を飲用する。」
タンポポのそっくりさんにも薬草としての利用法があったとは。実際に収穫のタイミングなどをいろいろ試して使ってみたいと思います。
0 notes
Photo

雑草とは
上の写真は、推定ですがマメツブウマゴヤシ(米粒馬肥やし Medicago lupulina マメ科)。似たような植物が幾つかありますが、黒い小粒の種子をつけるところから、マメツブウマゴヤシだと思っています。今年も庭や畑、道路脇などシマ(集落)のあちこちに生えています。今朝は集落で定めた作業日で、近所の方と道端の花壇の草取り(草むしり)としました。すると、一緒に作業されていた老人会の方が「ヤギが好きそうな草がたくさん生えて!」と一言。実際、この植物をヤギが好きなのかわかりませんが、家畜の飼料、干し草、牧草にされるとありました。この植物を見てそういう発想がなかったので何だか新鮮でした。しかも、奄美大島の方言ではワカクサといい、民間療法で全草をムカデや毒蛇の咬み傷に用いるそうです。
ヤギと言えば、葉の裏が白色のカラムシ(苧 Boehmeria nivea イラクサ科)を「この草はヤギしか食べないけど」という言い方で説明されたことがあります。根が張って雑草として嫌厭されがちですが、昔から繊維として活用されてきた有用植物でもあります。
なにか私たちの意図とは違うところで芽を出した強者植物、その活用法がわからないでいるもの、道端に蔓延っている植物、庭から逃げ出して野生化した生命力の強い植物は、往往にして「雑草」と呼ばれています。一方で「雑草という植物はない」ということもよく聞きます。
ここで、「雑草」についてこんな風に考察されているの見つけました。奄美大島出身で南西諸島の植生研究をされていた大野照好先生の「人と雑草」というエッセイです。
「ヒトが食料とするイネやムギ、イモなどの作物を栽培するとき、それらの作物に混じって生える招かざる客である。このような植物たちを、作物に対して雑草と言っているわけである。(中略)
野生の植物であった彼らの中で、定期的に耕し、肥料をやり、除草をし、収穫するという極めて特異な耕作地に順応し得た者たちだけが雑草となり得たのだと思う。
雑草の一般的な性質として、
1. 生育期間が短い(省略)
2.小型軽量の種子をたくさんつける。散布力も極めて大きい。
3.散布した種子が一斉に発芽しない(省略…だから除草しても次から次から生えてくる)
4.肥料(チッソ分)の多いところでも発芽できる(省略)
5.耕されるという条件に慣れている(土をひっくり返されても生える活力が強い)
6.気候や土壌に対する適応力が大きい(省略)
7.一年性や越年性の植物が多い(作付けされる作物と生活環を同じくする者が都合が良い)」
(中略)
「雑草のようにたくましいというけれど、いったん耕作を中止して耕さず、肥料を施さないでおくといつの間にか雑草は姿を消してしまい、それに変わってその地方独特有の野草や山草が生い茂ってくる。雑草はしょせんは人類が長い歴史のなかで創りだした。人類の生活から離れることのできない、最も人間くさい植物たちである。」
「胴乱をかついで―南西諸島植生研究の草分け大野照好の歩いた道」出水沢 藍子著 高城書房 P102−104
実際、雑草、雑草と追いやっていると、姿を消してしまう植物もあるようです。ヨモギやイタドリさえ、どこにでも生えていたのにすっかり減ってしまったとか、探さないと見つからなくなったという話を聞いたこともあります。(2017.6.14 瀬留)(2018.2.25 秋名)
長い年月、私たちのそばで育ち活用されてきた雑草たち。上手く付き合っていくには、有効に活用するには、どんな特徴があるのだろう、そんな気持ちが雑草を食材や薬草として取り入れてきた歴史なのだと思いました。
0 notes
Photo

ソテツの実
奄美大島におけるソテツの実(ナリ)の利用は多岐に渡っていて、例えば先日はナリ味噌作りを体験させていただきました。食材としては、他にもお菓子作りにも利用されていてソテツ羹なるものがあります。どうやら羊羹のようなもののようですが、現在はほとんど作られていないそうでソテツ羹を再現しようとしている方たちを近々お訪ねする予定です。
蘇鉄カン(ソテツ羹)についての記述を見つけました。
名越左源太著の「南島雑話」には蘇鉄カンが描かれています。見る限りでは、薄く切った様子が羊羹のように固めたもののようです。また、同じ著者の「遠島録」には、蘇鉄のせんと餅米をねり、砂糖を混ぜて作るお菓子が紹介されていて、蘇鉄カンを指しているようだとあります。蘇鉄のせんとは、蘇鉄の澱粉のことで実だけでなく、幹や芯からも取れて、お団子のようなものを作ったり、おかゆに入れたりと食材として活用されていたそうです。因みに、蘇鉄のせんの中でも、ソテツの実(ナリ)からできたものをナリ粉と呼んでいます。
蘇鉄は観賞用として江戸時代から日本各地で植えられていたそうですが、蘇鉄の毒抜きの技術が知られていなかったからか、食材としての記録はほとんどなく、本土では鹿児島の一地域で食されていた記録があります。実から採れた澱粉のほうが上等で、幹から採ったものは作り方が悪いと中毒を起こすこともあったとありました。
「名越左源太の見た 幕末奄美の食と菓子」今村規子著 南方新社 より
蘇鉄の澱粉は十分に水にさらして毒抜きをしますが、それは流水に限るとか。昔は川でさらして毒抜きをしたそうです。昭和5年生まれの方の幼少期にお母さんやおばあさんがそういった作業をしていたのを覚えているとお話ししてくださいました。(2018.2.13 名瀬)
近所では山水を引いている家庭が多く、蘇鉄の澱粉の毒抜きは山水を使ってしているという話を聞きました。(2018.2.4 瀬留)
また、蘇鉄の実は、薬草(薬用植物)としては、傷口によいそうです。ヨモギの葉と並んで傷口の手当てによく聞く方法です。今まで50〜80歳代の方から同じ様な話を聞きました。
「止血には、ヨモギの葉をよく揉んで傷口に貼るとよい。ソテツの実も、皮を取り除き中の白い実をよく潰して傷口につける。」(「南風の吹くシマで」松 夫佐江著 あさんてさーな p156)
戦後くらいまでは裸足で遊んでいる子供が多く、よく怪我をしたので、傷の処置に使う薬草はみんなよく知っていたということです。
ソテツの実の皮(殻)を破るのは相当力のいる仕事です。殻の中の澱粉質に食材としての有用性、薬草としての効果を見出したのは飢餓時の必死の思いからの偶然なのか、ソテツが秘めた何かに気がついた人がいたのか。
1 note
·
View note
Photo






洗髪に利用された植物
奄美大島に引っ越して間もない頃、子どもの頃はハイビスカスを洗髪に使っていた��話してくれた方がいました。花を食べたことがあり、ヌルヌルしたようなしっとりとしたような粘液を含んでいると感じたので、てっきりハイビスカスの花を利用するのだと思い込んでいました。
奄美大島で見かけるハイビスカスには様々な色や形があり、南国の雰囲気を楽しませてくれます。園芸種が多いですが、ここでは総称してハイビスカスと呼ぶことにします。
昨年になり、お話を聞いた方から洗髪にハイビスカスの葉を使うときいてびっくりしました。聞き直してしまったほどです。試しに葉を揉んでみると、確かに葉にも粘液が含まれていました。(2017.7.13 久場)
その後、講師として関わっている公民館講座のクラスでハイビスカスの話になると、子どもの頃は川で水浴びをするとハイビスカスの葉でシャンプーしていたと言う話が出てきました。今のシャンプーとリンス、コンディショナーを使った洗髪でいうと、リンスかコンディショナーの役割をしているように思いましたが、どちらかというとシャンプーのように髪を洗っていたそう。リンスやコンディショナーに当たるものはつけていなかったそうです。(2018.8.16 龍郷町)
自分で試しに洗髪したときには、ハイビスカスの葉をちぎって洗面器に水と共に少し浸け混んでこしてみたり、引きちぎった葉をそのまま髪に擦り付けてみたりしてみましたが、用意したり洗い流すのに手間がかかって仕方がありませんでした。
ある日、ハイビスカスのシャンプーにはとっても合理的な方法があることがわかりました。その方は、子どもの頃、川に行くときにはいつも首に手ぬぐいを巻いて行ったそうです。汗を拭うこともできるし、濡れた体をふくこともできるし、万が一、ハブに襲われたら体を縛って毒が回るのを防ぐこともできる。野山を歩くときには手ぬぐいを首にまくとよいそうです。そして手ぬぐいにハイビスカスの葉を挟んで巻き込んで、濡らしてよく揉むと、洗髪に利用する粘液を取ることができます。使い終わったら、手ぬぐいを洗えばいいと。なるほど!
また、ハイビスカスだけでなく、細長い葉をもった別の植物もその葉を同じように利用できるそうです。残念ながら、その植物の名前は思い出せないと仰っていました。(2017.10.21 赤尾木)
ところが、先日「奄美女性誌」を読んでいると、こんな記述をみつけました。
「石鹸は貴重で顔を洗うのにさえ使えなかった。洗濯の汚れにはもっぱら灰汁をつかった。こわれたかめなどにいろりの杯をとって灰汁を作っておくのである。(中略)洗髪はウシンフグリ(さねかずら)の葉をもんで、その粘液で洗った。これも現今の良質の洗剤に遠く及ばないものである。」「奄美女性誌」長田須磨著 農山漁村文化協会 P226
前述の細長い葉の植物とサネカズラが同じものかと同席していた娘さんに確認したところ、ウシノフグリだったかもしれませんとのお返事をいただきました。サネカズラ(実葛 Kadsura japonica マツブサ科)は、奄美大島の方言ではウシンフグリとか、ウシノフグリというそうです。
まだ、近所で実物を見たことがないので試していませんが、サネカズラを見つけたら、手ぬぐいを使って洗髪してみたいと思います。
0 notes
Photo

参考文献リスト
こちらのブログ内の記事を書くに当たって、参考にした文献です。引用しているものについては、各記事内で明記しています。
1. 今村規子「名越左源太の見た幕末奄美の食と菓子」南方新社 2010年
2. 植松明石監修、民俗文化研究所奄美班編「奄美の人・くらし・文化 フィールドワークの実践と継続」論創社 2016年
3. 奄美クラブ55号発刊記念「面白い昔ばなし ふるさとの伝説・民話 奄美今昔 よもやま話」奄美クラブ 平成14年
4. 日高潤郎「シマのことわざ ムンヌ シリハテヤ ネン」鮮明堂 平成16年
5. 蔵満逸司「奄美まるごと小百科」南方新社 2003年
6. 原井一郎「人間選書 奄美の四季」農山漁村文化協会 昭和63年
7. 蔵満逸司「奄美食(うまいもの)紀行」2005年
8. 大野隼夫「奄美の四季と植物考」長征社 2014年復刻版
9. NPO法人奄美野鳥の会編「奄美の野鳥図鑑」文一総合出版 2009年
10. 鳥飼久裕解説「聴き歩きフィールドガイド 奄美」文一総合出版 2007年
11. 名越左源太、国分直一・恵良宏校注「南方雑話1」平凡社 1984年
12. 名越左源太、国分直一・恵良宏校注「南方雑話2」平凡社 1984年
13. 田畑満大・瀬尾明弘. 「『南島雑話』にみる植物の利用」 安渓遊地・当山昌直 編. 奄美沖縄環境史資料集成. pp. 577–618. 南方新社. 2011年
14. 榮喜久元「蘇鉄のすべて」南方新社 2003年
15. 小野寺浩 他「鹿児島環境学 特別編 地域を照らす交響学」鹿児島大学鹿児島環境学研究会 2013年
16. 名越護「南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定」2017年
17. 黒澤彩「日本紀行 奄美大島 蘇鉄と生きる」AGORA第27巻第6号 pp.56−63 日本航空株式会社 2007年
18. 安渓貴子 他「ソテツをみなおす 奄美・沖縄の蘇鉄文化誌」ボーダーインク 2015年
19. 藤井つゆ「新版 シマ ヌ ジュウリ 奄美の食べものと調理法」南方親社 1999年
20. 名越護「南島雑話の世界 名越左源太の見た幕末の奄美」南日本新聞社 2002年
21. 長田須磨「人間選書13 奄美女性誌」農山漁村文化協会 昭和35年
22. ゆらおう会「いじゅん川 Ⅲ号 食をたずねて」新報出版1998年
23. 奄美女性サークル ゆらおう会「いじゅん川 第7号 〜奄美の食 Ⅱ〜」あさんてさーな 2006年
24. 奄美女性サークル ゆらおう会「いじゅん川 第9・10号合併号 躍動する奄美へ スマイル」あさんてさーな 2009年
25. 松 夫佐江「南風(はえ)の吹くシマで」あさんてさーな 2006年
26. 大野照好 編集「琉球弧 野山の花」南方新社 1999年
27. クライナー・ヨーゼフ、田畑千秋「ドイツ人の見た明治の奄美」ひるぎ社 1992年
28. 出水沢 藍子「胴乱をかついで―南西諸島植生研究の草分け大野照好の歩いた道」高城書房 2002年
29. 鹿児島県大島郡龍郷町教育委員会「龍郷町文化財ガイドブック2013」龍郷町教育委員会 2013年
(2018.2.28 更新)
0 notes
Photo

奄美群島生物資源Webデーターベース
奄美大島に生息する植物を特定、同定するために利用しているウェブサイト、奄美群島生物資源Webデーターベース 。学名を確認したり、方言で呼ばれている植物の一般名を検索するのに利用しています。こちらのブログで使っている植物一般名、学名等はこのサイトから引用しています。
「民間療法で利用されている種」についてまとめられている項目があるので、聞き取りさせていただくときに参考にしています。各植物ついてのページでは、参考文献も紹介されています。
0 notes
Photo





イタドリ(ブラ)
イタドリ(虎杖、痛取 Reynoutria japonica、Polygonum cuspidatum、Fallopia japonica タデ科)は、スカンポの名でも知られる多年草です。奄美大島の方言ではブラと呼ばれます。
日本各地で見られる野生植物で、奄美でも古くから自生しているようです。戦前に尋常小学校に通っていた世代には馴染みのある「すかんぽの咲く頃」という曲があります。「小学尋常科」ということろが「小学6年生」と変わった歌詞もあり戦後もしばらく子供たちの間で歌われていたようです。
youtube
イタドリは、世界の侵略的外来種ワースト100(100 of the World's Worst Invasive Alien Species)に数えられるほど旺盛な繁殖力があると言われています。実際、イギリスで暮らしていた時、エジンバラにあるリース川 Water of Leithの川沿いではよく見かけました。イタドリはJapanese knotweedと呼ばれ駆除し難い外来種として悪名高かったのを覚えています。元々は観賞用植物として19世紀に日本から輸出されたものが、野生化してしまったもののようです。(ウィキペディアより)
このイタドリは食材になるそうで、今回は調理方法をを教えていただきました。ワイルドフードとして活用できると分かれば、イギリスに生息しているイタドリも暖かい眼差しで見てもらえるようになるのではないでしょうか。
奄美大島でのイタドリの収穫期は春先まで、今年はもう一回くらい収穫できるとのことです。新芽や少し背丈の高くなったものを手繰り寄せて、ポキっと音を立てて折れる部分が利用できるという話でした。利用するのは茎で、葉は使いません。茎は黄緑色の部分が見えるくらいまで皮をむきます。大きなお鍋に沸騰したお湯に入れて冷めた頃にこぼし、2回ほど水を変えて下準備をします。この作業が不十分だと、出来上がりが酸っぱくなり美味しくないそうです。
既に味付けがされ仕上がったものをいただきながらお話を聞きました。少し濃いめの出し汁に煮た出せないようにほんの5分ほどつけて、ツナを一緒に煮たものと鰹節と煮たものを味見しました。少し下ゆで時間が長くて歯ごたえがなくなってしまったとのお話でしたが、たけのこのような食感があり美味しくいただきました。この料理は、実は奄美大島の郷土料理ではなく、本土で習って帰ってこられた方がご近所の方に振舞って知られるようになったものだそうです。(2018.2.25 秋名)
また、こんな植物だという見本に実際の植物を手折ってきてくださり、植物の特徴を確認しました。葉の形や節の赤い色、何よりも折った時のポキっという音を頼りに近所に探しにいったら、ありました。畑の縁や道端に。場所によっては花の咲いているものも見つかりました。
春が来る前に、収穫して料理しようと思っています。
0 notes