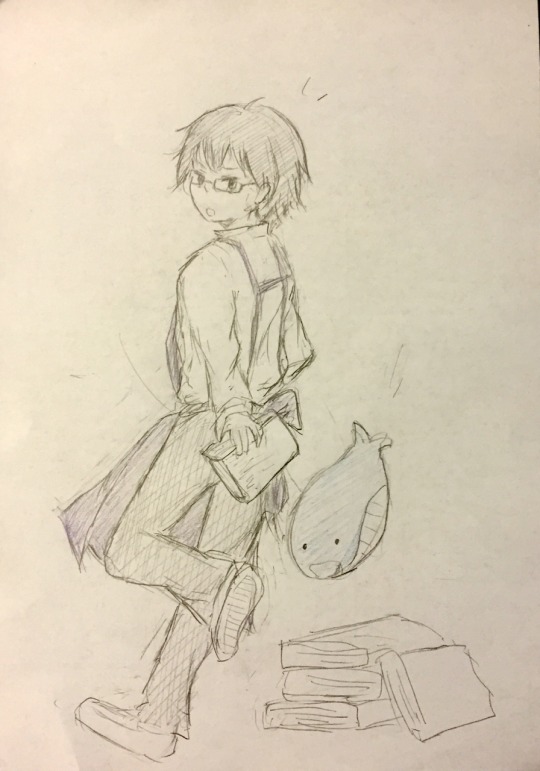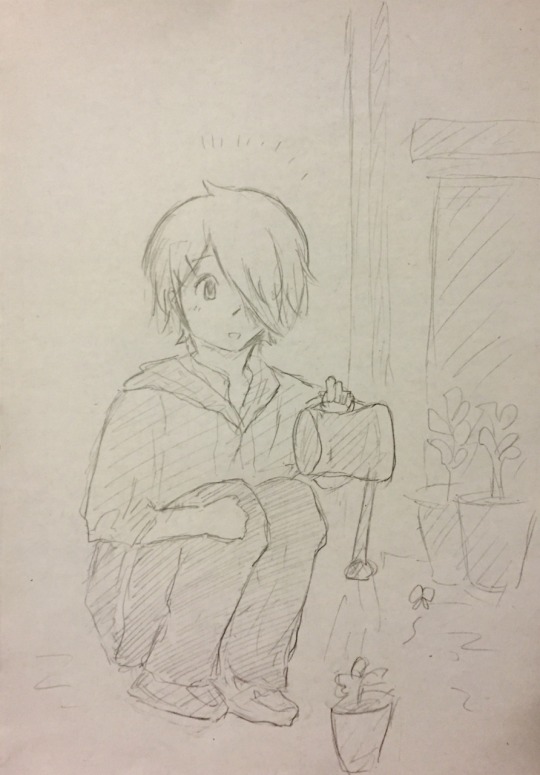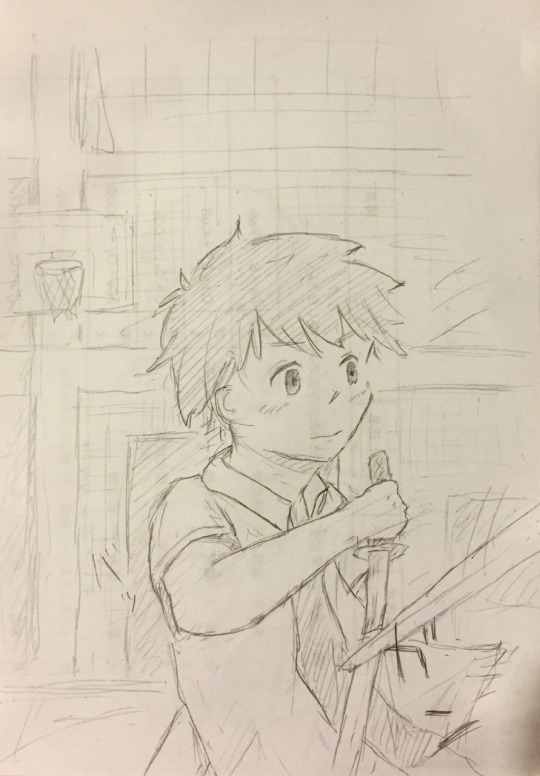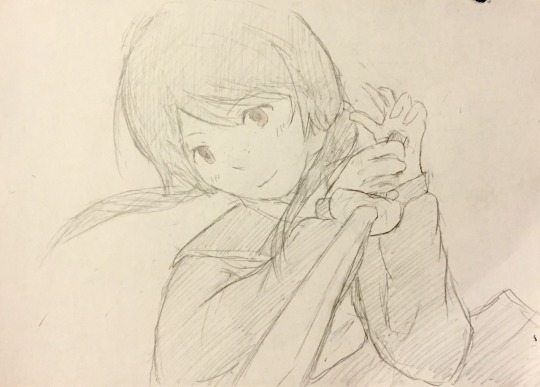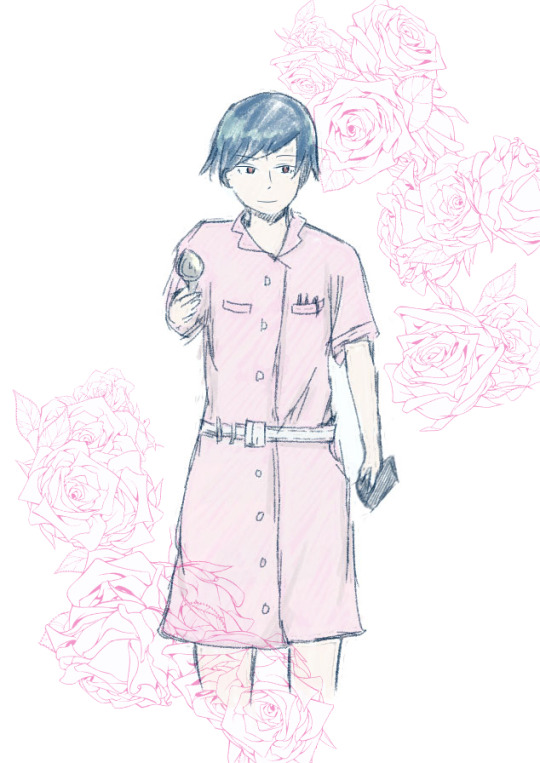Text
寒い寒い、変わりだてしない冬の晩のこと。
夕陽もすっかり落ちて、街には雪だけが降り続けている。
積もりに積もった雪は教科書地区の石畳のほとんどを埋めつくして、白銀の世界を作り出していた。オレンジ色に揺らめく光は、煉瓦造りの家の窓から漏れる暖炉の光だろう。すりガラスの窓は曇って、中の暖かさを伝えている。
石畳の大通りから少し外れて、入り組んだ路地にあるその家からは、砂糖の焼ける甘い香りが漂っていた。並んでいる家と同じく、窓からは暖かい光が漏れて、外の雪を照らしている。
――ふと、光が動いた。窓の近くにあった何かが動いて、遠ざかったように、広くなる。少し遅れて、明るい声が響いた。窓から離れたそれが、部屋の奥から出てきた家主に、声をかけたのだ。
「ねぇイリニ、それつまみ食いしていい?」
「もう〜、ダメよ。いま食べたら、お腹壊しちゃうわ」
オーブン皿を持ちながら、イリニ・オデンスが微笑む。皿の上にはクッキングシートが敷かれ、その上には花や星などの形に取られたクッキーが並べられていた。
「大丈夫よ。あたし偉大な魔女だから」
「ん〜……ゲルダがそう言うなら、そうなのかしら……?」
そのうちのひとつが手に取られる。雪の結晶の形をしたそれは、ぐにゃりと形を変えながら口の中に放り込まれていった。放り込んだのはイリニよりもずっと小さく、手のひらのサイズほどしかない魔女――ゲルダだ。溢れるような金の髪を揺らしながら、彼女は苦い顔をした。
「……甘さが足りないわ」
「あら、あとで調整しなくっちゃ」
イリニはオーブンのドアを開けて、慣れた手つきで皿を入れた。余熱は十分で、すでに炉の中は火傷しそうなほど熱くなっている。熱が逃げないうちに閉めて、タイマーを入れた。さて、次は……。
「ねぇ、完成はまだ?」
「あと30分くらいかしら……?」
「違うわ。お菓子じゃない方」
ゲルダは退屈そうに、イリニの周りを飛んでいた。彼女が通った空気に、髪と同じ金の光がわずかに残って、とても綺麗だ。イリニが手を出すと、ゲルダは我が物顔でその上に座った。
「ああ、実はもう終わってるの。でもちょっと寝かせたくて……。クッキーも粗熱を取った方がちゃんと味がわかるでしょ?」
イリニの視線の先には、書斎があった。クッキーを作り始める直前まで、籠もりきりだった部屋。机の上は資料が雑多に置かれているが、中心は整理されている。いつもはばらばらになっている紙の束が整っている。新作が出来たのだ。――作家でもあるイリニ・オデンスにとっては、比較的珍しい光景だった。
「なんだ、てっきりまだかと思ってたわ。暇だし、読んできてもいい? こき下ろしてあげる!」
勝気な笑顔を向けながら、ゲルダが手のひらから浮かびはじめる。質問の体を取っているが、止められたとしても読みに行くつもりなのだろう。
「ダメよ。ゲルダにはちゃんとしたのを読んで欲しいもの〜」
「いいじゃない。ちょっと置いたところで内容が変わるわけじゃないし」
「ええと、私が直してからって意味なんだけど……う〜ん、まぁいっか」
苦い顔を見せていたイリニは一転、穏やかに微笑んだ。
「どうぞ、感想をちょうだい。せっかくだから、校正もお願いね」
「あのねぇ、この偉大な私に校正って貴女……」
文句を言いながら、ゲルダが書斎に飛んでいく。ああ言いながらもなんだかんだでやってくれるのがゲルダで、イリニはゲルダのそんなところを好ましく思っていた。
(さて、じゃあ私はその間に――)
焼き加減を見守りながら、イリニはポットを手に取った。
校正作業をしてくれる偉大な魔女へ、献上品を捧げるために。
◇
キッチンのあるリビングに比べて、書斎の空気は冷えている。
広く取られた窓から冷気が浸み出して、床の上を滑っているのだ。床よりは暖かな空中を陣取って、ゲルダは出来たばかりらしい原稿を読んでいた。魔法で浮かせた原稿は動くたびに空気をかき混ぜて、すこし肌寒かった。
原稿の内容は、そう難しくない。イリニは基本的に教科書地区にふさわしい作風で、暖かで優しく、希望に溢れる作風をもっている。今回の物語も、終わりはハッピーエンド。かわいそうな彼らは最後には救われて、いつまでも幸せに暮らしました。
イリニが焼き終えたばかりのクッキーを魔法でつまみ食いながら、最後の文章を読み切る。ふと視線を移すと、イリニが部屋に入ってくるのが見えた。
「どうかしら」
「……甘ったるくて胃もたれしそうだわ」
クッキーを咀嚼しながら、ゲルダは呟いた。甘さが足りないと言ったクッキーは色のついた砂糖でコーティングされていて、甘すぎるくらいになっていた。
「紅茶も淹れたの。よかったら一緒に飲んで」
イリニの手には、ゲルダのサイズにあわせたコーヒーカップがあった。ゲルダはそれを浮かせて、自分の元に引き寄せる。手に取って、まだ熱いそれにゆっくり口をつけた。
「……今日は苦い方か。はぁ、なんでこう極端なのかしら……」
イリニの入れる紅茶はまずい。正確に言うと、とても甘いかとても苦いしかない。彼女の作風と同じ。今日の紅茶は苦い方。この世の絶望を煮詰めたみたいな味だった。
「……ま、クッキーと一緒に食べるのでちょうどいいわ。及第点よ」
そうイリニに言うと、彼女は優しく微笑んだ。甘ったるい笑顔だ。クッキーみたいに。あるいは彼女の新作みたいに。
「偉大な魔女にそう言っていただけるなんて嬉しいわ〜。これはお墨付きと思っていいかしら?」
「あら、勘違いしないでよね。あたしが評価したのは、あんたの作ったクッキーと紅茶について。作品については、いろいろ言いたいことがあるから、覚悟して聞きなさい! いい? まずは――」
魔法にペラペラと捲らせて、付箋がわりにつけた色のページを探す。色は魔法でつけているから、簡単に消すことができる。カラフルに色づいたページを指差しながら、ゲルダは矢継ぎ早に話していった。面白かったところ、悲しい気持ちになったところ、楽しい気持ちになったところ。誤字らしき場所に、脱字らしき場所。文句と、ささやかな賞賛。
古書とインクの匂いだけだった書斎には、いつのまにかクッキーの匂いと、苦い紅茶の香りとが混じっていた。開けっ放しだったドアからは暖かな空気が流れ込み、寒かったここもすっかり暖かくなっている。変わりだてしない冬の晩は、二人の笑い声を乗せながら、今日もゆっくりと更けていった。

1 note
·
View note
Photo
花火の音と、砂利を踏む音、騒がしい周りの声と――自分の心臓の音。
思ったよりも軽すぎる身体は、思ったよりも柔らかくて、正直、花火どころではない!
必死に何も考えないようにして地面とにらめっこをしていれば、彼女の靴擦れが目に入る。慣れない下駄で、ずいぶん歩かせてしまった。こんなとき、救護の知識でもあれば適切な処置を行えたのだろうが、今の自分には到底無理だった。――だからせめて、帰るまでは。
「ねぇ、司くん」
耳に近い場所から発せられる声。重力にしたがって落ちる身体を、少し勢いづけて持ちなおすことでそれに返事をすると、彼女は言葉を続けた。
「……その、ありがとう」
いつもの元気が減ってしまった声色。彼女がそんなだから――
「ど、どういたしまして……だけど、別に、これくらい、いい、し」
彼もなんとなくいつもの調子が出なくて、しどろもどろに、そう言葉を発するのが精一杯だった。
カラフルな光が辺りを照らす。赤、黄、青、白、光のあとから音がやってきて、音がやってくるときには、また別の光がやってくる。彼らはそれらに包まれながら、ゆっくりと歩みを進めていっていた。
けだま大先生とすん大先生と勝手にコラボ

けだまとかってにコラボ
2 notes
·
View notes
Photo

今日は休日で、天気は快晴。
すこしだけ眩しい太陽と、さわやかな風が心地いい。彼女は揺れた髪の毛にそっと手をあて、遠くをみつめる。――いったい、なにを見ているのだろうか。彼女の邪魔をしないよう、ゆっくりと隣に立つと、風の音が草木を揺らしながらだんだんとこちらへ近づいてきた。
耳をかすめる風切り音。葉と葉が擦れる音の向こうに、鳥の羽音が聞こえる。あっという間に通り過ぎていった風の、そのうしろ姿までを見届けると、彼女はどこか満足気にこちらへと振りかえった。
はためくリボンと、穏やかな彼女の笑み。
休日はまだ始まったばかりだ。カメラを携えて、いろんなところへ出かけよう。
0 notes
Text
Reinwardtia
――いつ来ても、この地区にはどきどきさせられる。
ざわつく雑踏の中で、どこか楽しそうに歩を進めるその人物。古書独特の匂いを一身に浴びながら、その長い髪を揺らして、彼女は天井いっぱいまで広がる本棚を見上げる。
ここは歴史書地区。
本棚に詰められている本は歴史書であり、その範囲はまさに古今東西――ありとあらゆる場所の、ありとあらゆる時代の歴史――のものとなるらしい。自ずとそのジャンルから、一冊単位で完結する物は殆どなく、20〜30冊、果ては本棚一ブロック以上(とてもじゃないが数えきれないのだ)もの同じフォーマットの背表紙が並んでいる。
それが、この地区全体を形作り、所狭しと並べられていることを考えれば、
(さながら、ここは人類の歴史の行き着く最終点、といったところか)
本であれば節操なく何でも収蔵してしまうこの国の特性を考えると、格式高い人類の歩みから、何てことない個人の日記のようなものまで、一緒くたに置いてあるのだろう。いづれにしてもそれは、誰かの目を通した人類(困ったな、人類でない種族の歴史もあるじゃないか)の歴史なのだ。
彼女は、そうした雑多ながらも、その雑多さが歴史そのものを表しているようなこの地区が、決して嫌いではなかった。
蛍火ように淡い光を放つ灯りを目印に、目的地を見つける。奥まった場所にあるスライド式の本棚の前には、少しわかりにくいが確かに表札がかけてあり、更にその上から在中であるか不在であるかを示す札が乱雑にかけてある。――幸い、いまは在中であるようだ。
一応、訪ねる人物は健全な青少年だ。ノックくらいはしてあげようじゃないか。
「〜〜、はい、どーぞー」
少しけだるげな声が、ドア越しに寄越される。身を屈めてドアノブを取ると、カランカランと真鍮の鐘の音を立てながら、それが開いた。
「おじゃまするよ、少年」
聞こえる程度に声を発しながら、ドアをくぐる。中は思ったよりも広く、本棚の裏にある作業場だとは思えない程の空間。更に奥に彼が生活している部屋がある、昔何の気無しに聞いた時、そのようなことを言っていた気がする。
「――トールさん、わざわざこちらまでいらっしゃるなんて、どうしたんですか?」
「キミとワタシの仲じゃないか、たまにはワタシだって意味もなく出向く事くらいあるさ――と言いたいところだが……そうもいかない事情があってね」
そう言いながら彼女――トールは手に持っていた大判の本を彼に渡した。何かを察したらしく、彼は受け取ろうとしたあとすぐそれを躊躇って、机の上にあったらしい手袋をはめ、改めてそれを手にした。
「あー、なるほど、こりゃまた古いの持ってきましたね」
丁寧にページを捲りながら、彼が独り言のように呟く。先ほどまでトールに向けられていた顔は、すっかり反対側、机の上にある本へ。彼の闇を切り出したかのような髪の毛が揺れるのが見えた。月の光のような銀色の髪を持つ彼女にとっては、些か新鮮な色だ。
「そうなんだ。ワタシの書庫を漁っていたら、ひょこり出て来てね。せっかくだから読みたいんだが、一応修繕してもらってからの方が良いかと思ったんだよ」
それこそが、今回の訪問の目的――古書の、修繕だった。目の前の彼、千景氏は、この歴史諸地区に作業場と自宅を構える修繕員なのだ。自ずとその関わりは浅くなく、折に触れて来てもらったり、このように稀にだが訪れたりすることがあった。
「ええ、そうですね、もっとちゃんと色々調べてからじゃないとなんとも言えないですけど、ちょっと普通に読める状態じゃあないです」
虫眼鏡を取り出して、じっくりと本のどこかを眺める彼。紙という有機物である限り、その劣化は、やはり避けられないらしい。いづれ読めなくなってしまうというのは、あまりに悲しい。少しでもその劣化を食い止めるために、彼らは居るのだ。
千景は、こうした修繕員の一人であるが、かなりの若手だ。この仕事は始めて随分経つようだが、はじめにあった時はもっと小さく、少年と言っても差し支えないような外見だったのを覚えている。時が経つのは早い物だ。物を読んで、現実の時の流れを忘れていると、なおさら。
そんな年端もいかない少年に、大切な大切な古書の修繕なんて任せられない。そう考える人間も少なくはなく、トール自身はじめに千景を見たときはその技術を疑ったものなのだが、その疑念はすぐに払われることになった。修繕員として申し分ない技術を発揮してくれたし、仕事も速い。将来性もある。
だが、その程度の修繕員であれば、この国には沢山いる。
いつのまにか歴史書地区という古書修繕のメッカのような場所に居住を構えるようになっているところからすると、恐らく周りの評価もそれなりに受けているのだろう。周りが彼にどのような評価を下しているかは知らないが、正直なところ、それはトールにはあまり関係ない。
彼女にとって大切で、彼女が評価する彼の美点。つい修繕を彼に依頼してしまう理由、それは――。
「――ところで少年、キミは最近やけに楽しそうだという話を風の噂で聞いたのだが、いい人でも見つかったのかい?」
「ぶぇッ!? ななな、ななんですかいきなり!? そんなっ、あのっ??!?」
これだ。
これこそが、つい、修繕を頼んでしまう理由。
「いやっ、えとっ、そんなッ、ことないですしっ……っていうか大体彼女は全然俺の事とか一般ピーポーとしか思って! ない、しべべ、べべつに俺だってッ、な、何とも、思ってないし、」
耳まで真っ赤にして、何を言っているんだこの少年は。
そんな反応をされると、ついついからかってしまうじゃないか。
「えーと、なんだっけね、詩歌地区の――」
「あーっ! あーっ! なんすかそこまで知ってるんじゃないすかアンタ!! 何すかその情報網!!」
椅子の上でわたわたとトールへ手を伸ばす千景。彼女はひょいとそれを避けて、悪戯げな笑みを浮かべた。
「とにかく、その本のこと、よろしく頼んだよ。うちの大切な子だからね。……それと、君の近況を、逐一ワタシに直接話にくるように。人の口に戸は建てられないとは言うが、戸を定期的に直しにくれば問題ないからね」
これ以上やると、拗ねられる危険性がある。不服そうな顔を浮かべて睨んでも、残念ながら全く怖くはない。どうせ、彼はその本を届けに来なければならないのだ。
「〜〜ッ、あーーっ、もーっ、俺で遊ぶのもいい加減にしてくれないかな!??! クッソーッ!! わかりましたよ!!!」
結局その黒い髪の毛を手で抑えながらも了承の意を示した千景を横目に、トールは入って来たドアノブを引いた。まだぎゃあぎゃあと騒いでいるようだが、思ってみれば高名な魔術師である彼女に、あのような言葉をかける人間はそう居ない。
彼女はにこやかな笑みを浮かべながら、ドアを閉めた。そうだ、ちょっとしたおまじないをかけておいてあげようじゃないか。
(ま、これはワタシからの餞別だよ)
翡翠色の眼を細めて軽く杖を振るトール。そんなに大仰なもの術式ではない。もっと根源的で、素朴で、牧歌的な、ただのおまじないだ。
「さて、ささやかながら楽しみが増えたな。……ふふっ、これは、からかい甲斐がありそうじゃないか」
そう遠くない彼の訪問――久しぶりに読むことのできる古書と、彼自身の近況報告を楽しみに、トールはたった今振った杖を持ち直す。少しの月光の粒を散らしながら、今度はそれを自分自身に。
その粒が、彼女に触れようとするその瞬間――。
既に彼女の姿はなく、その場に残された薄く瞬く光の粒だけが、ただゆっくりと、花びらのように舞い落ちていった。
1 note
·
View note
Photo

このマンガの形態、試しにやってみたんだけど、
予想をはるかに超えて作りやすかったので、
多分またしょうこりもなくこういうふうになにか書くかもしれない。
0 notes
Photo
「はい、アキちゃんこっち向けー」
「えっ、ちょっ、なに」
「ほらほら、俺だってシャッターくらいは押せるぞ」
「だからなんーー」
「ハイ、チーズ」
「(ニコッ)」


1 note
·
View note
Text
キューッ!(訳:餌)
少し寒くて乾燥した部屋。古紙とインクの混じった匂い。
手元だけが明るくなる様に調節された照明と、木製の使い古した机。
「キューーっ」
そうだ、奴も居た。どこからか飛んで来た鯨――と言うには大分小さな生物。知らない内に居着いて、気に入ったらしくここから離れない鯨。
机の上には、仕事のために並べた資料と、それとは別の古びた本。糊、刷毛、繊維状にまで薄くした絹。古い紙の破片。大きめの机だというのに、それらは所狭しと陣を取っている。――まだ作業途中なのだ。糊までが出しっぱなしになっている。乾いてしまわない内に、作業を終わらせるか続きをしなくてはならないだろう。
彼は欠伸をしながら、机と同じ材質で出来た椅子に腰掛けた。鯨は相も変わらず彼の周りを飛び回り、きゅうきゅうと鳴き声らしき声をあげていた。
「……気が散る、ちょっと黙って」
彼が小さくそう呟くと、鯨は一回転してから鳴くのをやめた。どうやら言葉は通じているらしい。それを確認した彼は、作業の続きを始めた。
(まずは、ここを補修しなきゃ劣化のスピードが速まってしまう。燻蒸はもう終わってるから、あとは落ち着いて補修するだけだ)
資料とにらめっこをしながら、彼はずり落ちてくる眼鏡を上げた。机の上に放置していたピンセットを掴み、紙の破片のひとかけらをつかみあげる彼。これを糊に浸してから、穴の開いた紙に乗せていく。
その古びた本には、穴があいているのだ。
本のタイトルは、もう読む事が出来ない程に劣化している。中も穴だらけ――虫食いだ。紙という有機物である以上致し方ないのだが、どうしても虫食いは発生してしまう。もう失われてしまった、文字のあった筈の小さな穴を眺めながら、彼は破片をそこへと乗せた。
「キュウッ」
鯨が一鳴きしながら飛んでいる。机の上を飛行するルート径路に含める辺り、自己主張をしているのかもしれない。自己主張――つまり、餌を寄越せということだ。
「駄目に決まってんだろ、あとで他のやるから待ってろよ」
徹夜続きの睨みを効かせれば、鯨は悲しげに鳴いて下がっていった。これを餌にするわけにはいかない。
というのも、どうやらこの鯨の主食は文字であるらしいからにして、そして彼のやっている作業は古書の修繕、これは依頼によって修繕している本であるから――つまり、間違ってもこれを食べさせる訳にはいかないのだ。
「おまえさー、文字ならなんでもいいんだろ? こんな高そうな本のよりもっと安くて希少性のない奴食えよなー」
「キュウ……」
悲しげな顔。そんな顔してもこの本はやらんからな!
「……」
尻尾を下げて旋回していく鯨。それが彼の後ろまで下がっていくので、彼はつい身体を捻って後ろを向く――と。
「わっ」
「わっ!!!」
さわやかな深緑色の髪の毛に眼鏡、片手に鳥かごを持つ――少女の姿があった。
「ふふっ、こんにちわ」
眼鏡の奥で、彼女がふわりと微笑む。鯨が丁度彼女の前に表れたので、びっくりしたが、すぐに平静を取り戻して挨拶――といった所だろうか。全くあいつは客人の前でもああなんだから――って、
「うわぇっ!? ちょっと、い、いま、いや今日って何日、でしたっけ!?」
「今日はー、ええっと、13日ですよ」
その言葉を聞きながら彼は机の上の時計を見る。
正確には、時計だったもの。四つに並んでいるはずの数字が、綺麗さっぱりなくなっている――これは、まぎれもなく、文字を食う鯨の仕業で。
「お〜〜〜〜ま〜〜〜〜〜え〜〜〜〜〜!!!」
彼が立ち上がり、鯨を捕まえようと両手を構える。じりじりと詰め寄り、壁に追いつめ、退路を断ってから、鯨肉にしてやる!
「キュウ〜、キュッ」
彼が両手で捕まえようとした瞬間、鯨が上部へと飛び立つ。彼の頭を一度バウンドし、そのまま飛んでいき、それは、少女の元へと向かった。
「わわっ、ふふ、鯨さんも、千景さんも、お元気そうでなによりです」
鯨は最終的に少女の懐へと入っていった。少女は開いた片手で鯨の頭を撫でる。すかった両手をわなわなとさせながら、彼――千景はのほほん顔の鯨のしっぽを、思いっきり力を入れて鷲掴んだ。
「す、すみません、一さん、こいつが時計の文字盤食っちゃったみたいで、すっかり時間忘れてました……」
そう、千景は目の前の詩歌地区の少女、一と会う約束をしていたのだった。
「いいんです、私もそんな急ぎではなかったですし、作業のお邪魔になるのだったら、私はどこか別の場所で待っています」
「いやっ、もうちょっとで終わるんで、そこのソファにでも待っ……」
そう千景が指差すソファには――本の山。
「てないですね、ちょ、いま片しますっ」
バタバタと本の山を崩そうとすると、一から静止の声が入った。
「大丈夫です、もうちょっとで終わるんですよね? 千景さんのお邪魔にならないのであれば、部屋の隅でのんびりしていますし、何か手伝える事があれば、何なりとお申し付けくださいっ」
(天使か……?)
そもそも千景が彼女を読んだのは、修繕――この場合穴が空き判別出来なくなった文字を入れる手伝いをしてもらうこと――のためだった。全ての穴を塞げていない今文字を入れる事は出来ないが、開いた穴だけでも先に入れて、その後は穴を塞ぎながらそれを行うことも、一応出来る。
「〜〜っ、お願いしていいですか」
「はいっ!」
地味な作業だが、こうすることによって、もう読む事すらかなわなくなってしまった本がまた読めるように、後世に受け継ぐことが出来る様になる。
彼女が判別出来なくなった文字を入れる事が出来るのは、彼女が「一度読んだ本の内容は忘れない」という記憶力の持ち主だであるから――そしてこの本を、昔彼女が読んだ事があったということのために、今ここに来てもらっていたのだ。
「”さしも彼にあたっては――”あ、ここ」
その内容を一字一句違わず記憶しているということは、古書修繕員にとっては最上級にありがたい存在であり――
「……?」
「ここ、引用です、”さしも彼にあたっては、須く先んじ御身を還さんと……”確か大十二史略伝説の中の一説じゃないでしょうか」
そう言いながら身を乗り出す彼女から、ふわりといい香りが漂ってくるとか――
「え、ああっ、そうなんですかっ!!」
とにかく、彼は、こうした時間が決して嫌いではなく。
「……キュー」
意図せず作業を長引かせた鯨に、彼は少しだけ、ほんの少しだけ感謝することにした。
0 notes
Text
貴方は圭ニコで『君の最期に』をお題にして140文字SSを書いてください。 http://shindanmaker.com/375517
「お前まであたしを、置いてくンじゃ、ねえよ」
冷たい雨の中、彼女は呟いた。光から遠い、路地裏で。ひっそりと。雨のように冷たくなった、彼の前で。
「…ばかやろ、最期くらい、」
今なら全部、雨が流してくれる。だから――
【バッドエンド】
「…最期くらい、一緒にいさせろってンだよ、圭」
らしくない言葉も、全部、流されて、消えてしまえばいいんだ。
【グッドエンド】
「……はは、ニコが泣いてるの、はじめて、みた」
「〜ッ!うるせぇ!こっこれは雨が目に入ったンだよ!」
続けようとした言葉も、もっと熱くなった目尻も、全部全部、流されてしまえばいいんだ!
1 note
·
View note
Photo

ついに始まる白軍の大攻勢!
だが反撃に転ずるべく体制を整えようとしていた七緒に下されたのは、黒軍本部からの「反撃するべからず」という命令だった!
このままでは制圧も時間の問題―—。窮地に陥った七緒は、単身ブライアーの元へと接近する。
向けた銃口、迫りくる、鋭い切っ先。そう長くない戦闘の果てに、ついに決着は付いたかに見えた。
先に口を開いたのは―—一体どちらだったのか。
互いが互いの命を握るその一瞬、二人の口元には、笑顔が浮かべられていた―—。
次回!学生戦争THE ANIMATION!「逃走の果て」お楽しみに!
って所まで想像したよね…
想定としては「七緒はブライアーに助けてもらいたかった」「ブライアーはそうだろうと思って殺さない程度に手加減してる」、だろうなあ。
そうすると、「七緒が助けてもらわなければならない」状況に追い込まれなきゃならんわけだ
という思考の元上記のような設定になりましたとさ。
あとですね、私の頭の中じゃ学校司令部と軍部司令部は別になっていてですね、
軍部は軍部で争ってるんだけど、その下位組織として学校があるわけですよ。先生とかは軍部の人だったりそうじゃなかったり。
だからガッツリ軍人ぽい先生の元ガッツリ軍事教練してる学校もあるし、普通の先生の元普通の教育に軍事教練も入ってるかな程度の所もあったりするわけです。軍部と繋がりが深いかそうでないかっていう違いがある、という設定。
その辺の細かい所学校のカラーによって変わるっていうようにすれば良いと思うんですけど、とりあえず私の頭の中での学生戦争の子たちは「ガッツリ軍部の司令を受ける学校」に所属している、考えています。
そのため学校司令部の面々は、「学校側からの司令」と「軍部からの司令」を擦り合わせて成果を出していかないといけないのです。
軍部は軍部、学校は学校っていう建前の元、七緒とかブライアーみたいな将来軍人になろうとしている子達は将来のために成果を立てようとしていたりするわけですね。
でも例えば圭さんとかだったりは、軍人にはなるだろうけど偉くなりたいとは思ってないため割りとフラフラしていたりする、とこんな感じ。
その中で、七緒に「軍部から出撃停止命令がきているため動くに動けない」っていうのを課せば、またブライアーに「軍部からの不自然な黒制圧命令」っていうのを課せば、こんな状況に追い込めるかななんて思ったわけです。
要するに七緒が素直に助けを求めてれば(またはブライアーが手を差し伸べてやってれば)終わる問題だったのに…というのにしたかったのだ…如何でしょう…?
いか考えられる展開/細かい心情とか事情はちゃんと作るときに考える
七「ね、ブライアーさん、次の作戦、取りやめてもらえませんか?」
ブ「言うに困ってそれか、貴様今の状況がわかってるのか?」
「その言葉、そのままそっくりお返し致しますよ」
「面白い事を言うな、私が手加減していなかったとでも?」
「でも、いま僕が引き金を引けば、あなたの首は飛ぶんです。貴方こそ、自らの状況を正確に判断出来ていないのではないですか?」
「……ふっ、良く回る口だ。素直に助けを求めればいいものを」
「……僕の目的をわかっていながら応戦し続けた貴方も、僕と同じ穴の狢だと思うんですけど」
「……ヒトナナゼロゼロ」
「はい?」
「ヒトナナゼロゼロ、2時、6時、9時の方向。我々は君たちの学校に、三方向から攻める手筈となっている」
「……」
「精々、生き延びるが良い」
「…この借りは、必ず」
「おや?君は私を追いつめ、情報を吐き出させたのではないのかな?」
「…そういえばそうでしたね」
「そうだとも」
「…では」
っていう会話をもっとねっとりやって、帰る途中お互いに
(奴が上官(部下)だったら、どんだけやりやすいことか…)
って思ってくれれば最高
0 notes
Text
@gakusen_TL 「あなたの方がよっぽど、……」を七緒からブライアーへの言葉で言い換えて下さい。 http://t.co/aDAEBRWwqs
「司令! 白前衛部隊がS-14地点を突破しました! このままでは本拠地へ攻め入られる危険性があります!!」
慌ただしい伝令役の声が響く司令室。その視線の再奥に座る銀髪の少年は、降りかかる声を払いのけるように一度手をやってから、静かに口を開いた。
「いま本拠地に迫るメリットはあんまりないです。――敵の目的は、こちらの戦力を削ることですので」
いま現在の情勢を知っていれば、比較的簡単に類推出来ることだった。”大人たち”の戦局が、大きく変わった訳ではない、ということが関わってくる。
ここで司令室に座る彼――向坂七緒の所属する黒陣営は、対する白と、今現在まで拮抗状態にある。どちらの陣営も、たかが学校同士のいざこざであったとしても、それが”大きなこと”であれば、介入してくる程度の余剰兵力があるのだ。
今白が無理矢理黒の本拠地を奪えば、黒軍部をそれを”些事”とは受け取らないだろう。いまや”たかが学校”と言う訳にもいかない。学校のカリキュラムには、それぞれの所属する軍教育が本格的に入れこまれ、軍師官を多数輩出する場所にもなっているのだ。
(いまここを取っても、すぐに黒軍部が奪取しにくることは目に見えてる。軍部の手を煩わせない程度に戦争をすることが、”僕たち”の役割だから――)
それは、司令部を務める七緒に取っても行動指針の一つでもあり、そして、相手――白司令官、スティーブン・ブライアーにとっても、同じことが言える筈だった。
「……向こうは本陣を叩くより、一部隊の各個撃破を優先するでしょう」
七緒は眼鏡越しに地図を見つめる。相手部隊の居るポイント、自部隊の居るポイント、その動き。それぞれのコマを俯瞰すれば――やがて動きが見えてくる。
「S-14地点の敵よりも、K-08地点の部隊が危険です。撤退しているようにも見えますが、このまま挟撃に持ち込まれる可能性も捨てられません」
二つの敵の部隊の、その真ん中には黒の第三部隊があった。第三部隊は先ほど敵部隊と接触し、敗走――その位置を相手に知られていてもなんらおかしくはない。
「至急、通信を飛ばして下さい。第��部隊をポイントK-09へ。背面から急襲、作戦は手筈通りに!」
「ハッ!」
ブライアーなら、どうするだろうか。
――いや、向こうの作戦はブライアーが取り行なっているのだから、ブライアーの作戦をブライアーがどう対処するかを考えても意味のないことだと、頭ではわかっているつもりなのだが――
(どうも、追い詰められてるみたいですね)
目の前の地図には、部隊の配置を表すコマが幾つも置かれている。状況は中の下。いかにしてこの場を逃げ切るかを考えなければならないだろう。
「背中から攻撃……ズルいけど、死ぬよかマシです」
伝令役が部屋を出て行ったの確認してから、七緒はゆっくりと目を閉じた。
(相手はきっと、正面突破を望んでいる。けど、いまの黒の体力じゃ、正面突破には耐えられない。体面なんかに構ってられないんだ――)
戦いにおける矜恃――誇りなど、生き死にの前では何の意味もなさない。生き残るためには、生き残させるためには、どんなこともやらなければならないのだ。
ポケットの中に入る懐中時計の感触を確かめれば、それはいつも通りの冷んやりとした手触りを彼に与えた。
(黒の掲げる日本の”誇り”だって、ほんとはどうでもいいのに――)
目を開ければ猫と目があったので、七緒はポケットから出した手を猫の頭へと移動させていく。
結果的に目に入る地図からは、敵部隊の動きとその目的がみて取れた。
――わかりやすいのだ。
いつだって正攻法で攻め入る白軍勢、その司令官であるブライアー。
その命令は自信に満ち、その自信故の強さ――例え搦め手であろうと、その策が妥当なばっかりに、”正攻法”になってしまうような作戦。
予測出来ることと対処出来ることは別だ。それに対して、こちらは頭を捻って藁であろうと、掴めるものすべてを掴みながら相対さなければならない。
「はは、ブライアーさん。これじゃあなたの方がよっぽど――」
途中で途切れた言葉に、頭を摺り寄せる猫が、小さく「ニャア」と返事を返した。
「ふふ、きみもそう思いますか」
自分たち以外誰も居ない司令室に、七緒の呟いた声が吸い込まれていく。
「……さあて、反撃の手立てを考えませんとね。首洗って待ってて下さい――”誇り高い”白司令サマ」
それをいいことに、彼は次の言葉を紡ぎ出す。
口だけではない一太刀を浴びせなければならないのだ。状況は中の下でも、宣言した以上、綺麗な首に刃を掠めさせるくらいのことはやらなければならない。
幸いまだ予備兵力はある。
手で猫を地図上から追いやって、七緒は次の掴むべき”藁”を紡いでいった。
0 notes